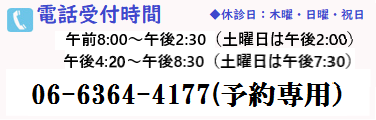医療ニュース
2017年7月31日 月曜日
2017年7月31日 体重は「現時点と20歳時の差」が重要
私が研修医の頃、循環器内科のT先生は、初診の患者さん全員に「20歳時の体重」を尋ねていました。T先生によれば、現在の体重そのものよりも、20歳時の体重との「差」の方が生活習慣病のリスクとして重要だそうです。
一般的には、生活習慣病のリスクを考慮するときは「現在の体重(もしくはBMI)」を基準とします。しかし、T先生に指導を受けていた私は、T先生の基準の方がずっと参考になることを何人もの患者さんを診察して”実感”し、私自身も「20歳時の体重」を尋ねるようになりました。
ただ、そうはいってもそれを実証した(エビデンスレベルの高い)研究はあまり目にしたことがありませんでした。しかし最近ついに見つけました。医学誌『JAMA』2017年7月18日号に掲載された論文(注)です。
米国ハーバード大学公衆衛生学教室のYan Zheng氏らの研究で、研究の対象としたのは(このサイトでも何度か紹介している)「看護師健康調査(Nurses’ Health Study:NHS)」と「医療従事者追跡調査(Health Professionals Follow-Up Study:HPFS)」。対象者数は女性92,837例(37年間の平均体重増加は12.6kg)と、男性25,303例(34年間の平均体重増加は9.7kg)。女性は18歳時、男性は21歳時の体重が基準とされています。
基準の時点から55歳までで体重が2.5~10.0kg増加した人は、増加しなかった人に比べて、糖尿病、高血圧、心血管障害などの発症リスクが有意に高く、慢性疾患や認知機能、身体障害などを持たずに過ごせる割合が低下することが判りました。具体的な発症率は次のような結果です。(数字は人口10万人・年あたりです)
女性体重不変 女性体重増加 男性体重不変 男性体重増加
糖尿病 110 207 147 258
高血圧 2,754 3,415 2,366 2,861
心血管疾患 248 309 340 383
肥満関連のがん 415 452 165 208
体重増加が大きければ大きいほど発症リスクは増大することが判っています。
************
ここで疑問になるのが、「では20歳時のときに肥満であった場合やせなくてもいいのか?」というものです。これを検証した研究は私の知る限りないのですが、私には臨床を通しての”実感”があります。これを一言で言うのはむつかしいのですが、例えば、柔道やアメリカンフットボールをしていて体重が標準より多い場合、つまり筋肉量が多いことが予想できる場合、中年になって、たとえその筋肉が脂肪に置き換わっていたとしても、体重が増加していなければあまり生活習慣病にはなりません。
20歳時に不健康に太っている、つまり脂肪が多く筋肉が少ない場合、中年期にさらに体重が増えていれば多くの疾患のリスクは上昇しますが、それほど体重が増えていない場合は、意外にも血圧や血糖は正常であることが多いのです。
ということは20歳時の時点で、肥満がある場合、それが筋肉質であったとしても脂肪過多であったとしても、その時点で血圧や血糖、その他血液検査に異常がなければ、生活習慣病のリスクは上がらないということになります。現時点でここまで言い切ってしまうのは”危険”ですが、私の実感としては「現在の体重」よりも「現在と20歳時の体重の差」が重要なのです。
注:この論文のタイトルは「Associations of Weight Gain From Early to Middle Adulthood With Major Health Outcomes Later in Life」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2643761
投稿者 | 記事URL
2017年7月31日 月曜日
2017年7月30日 プロバイオティクスは乳幼児の感染予防に効果なし
昨今の腸内細菌ブームは凄まじいものがあります。腸内フローラ、糞便移植、発酵食品、食物繊維などがキーワードとなっており、おなかのなかのいい菌を増やして、その菌にあやかって健康になろうとするムーブメントは単なる「流行」を超えているような気がします。マスコミからの取材依頼も、このテーマで寄せられることが増えてきました。
今回紹介したいのはそういう意味では「残念な」結果です。実際、この研究を取り上げた『Health Day』というオンラインの健康情報サイト(注1)では、露骨に「残念な結果(disappointing results)」と書いています。
その研究が報告されているのは医学誌『Pediatrics』2017年7月3日号(オンライン版)。対象者は8~14か月のデンマークの健康な乳幼児290人です。144人には6か月間プロバイオティクス(ビフィズス菌(Bifidobacterium)と乳酸菌(Lactobacillus))を摂取してもらい、146人には摂取してもらいませんでした(正確に言えばプラセボが投与されました)。
結果、保育園を休んだ日数に差はなく、また、風邪症状、下痢、発熱、嘔吐などの発生頻度にも有意差はありませんでした。一方、プロバイオティクスの副作用もありませんでした。
************
プロバイオティクスに有効性が認められなかった理由として、研究者らは「今回の研究の対象者の多くが母乳栄養で育てられていた」ことを挙げています。さらに上述の『Health Day』の記事は、「母乳がベスト」というカリフォルニア大学サンフランシスコ校の小児科医カバナ(Cabana)の言葉を引用しています。
カバナ医師は、それぞれの母親の母乳中に独自のヒト乳オリゴ糖(human milk oligosaccharides)が含まれていることを指摘し、母乳がプロバイオティクスより優れていると主張しています。オリゴ糖は、赤ちゃんの消化管内の特定の細菌の増殖を促します。このような物質を最近は「プレバイオティクス」と呼びます。
プロバイオティクスが乳幼児が抗菌薬を内服したときに起こる下痢に有効とした論文は過去にありますが、これは当たり前と言えば当たり前で、成人でもよくあることです。結局のところ、プロバイオティクスが免疫能を上げ感染症予防になることを高いエビデンスレベルで示した研究は今のところ「ない」と考えるべきでしょう。
現時点では乳児にとって「母乳」に勝る食品はないということです。ですが、世の中には母乳の出ないお母さんもたくさんいますし、母親がいない乳幼児もいます。そういった子供たちのためにもプロバイオティクス/プレバイオティクスのさらなる研究は期待されているのです。
注1:下記URLを参照ください。
注2:この論文のタイトルは「Probiotics and Child Care Absence Due to Infections: A Randomized Controlled Trial」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/06/29/peds.2017-0735
下記なら全文を読むことができます。
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2017/06/29/peds.2017-0735.full.pdf
投稿者 | 記事URL
2017年7月28日 金曜日
2017年7月28日 膀胱炎にニューキノロンを容易に使ってはいけない
このサイトでも何度か紹介したことのあるchoosing wisely。私の希望とは裏腹に、あまり日本では浸透していませんが、非常に大切な概念であり、我々医師も行政も、そしてもちろん患者さんにとっても「有益」なものです。choosing wiselyの概念を一言で言えば「ムダな医療」をなくすということ。具体的な「ムダな医療」の”あぶり出し”をおこなうために、米国の各学会が5つの例を挙げています。
2017年5月13日、米国泌尿器学会(American Urological Association)は、「ムダな医療」をなくすための5つの提言をおこないました(注1)。その5つのうちのひとつが「合併症のない女性の膀胱炎に容易にニューキノロン系抗菌薬を使ってはいけない」です。
ここでいう合併症は、例えば重症の糖尿病とか、HIV、悪性腫瘍といった特に免疫系に異常がおこりやすい疾患のことです。健康な女性の場合は、膀胱炎にニューキノロンでなく、他のより適切なものを使いなさい、ということです。
ニューキノロン系抗菌薬というのは一言でいえばとても”強力”な抗菌薬で、イメージで言えば「最終兵器」に近いものです。そんなものを単なる膀胱炎に使用すれば使用量が増え、いざというときに利かなくなる、つま「耐性菌」が出現することになります。商品名(先発品)で言えば、クラビット、タリビット、シプロキサン、オゼックス、グレースビット、スオード、アベロックス、ジェニナックなどです。米国泌尿器学会はこれらニューキノロン系抗菌薬の副作用を懸念するよう警告しています。
では、どのような抗菌薬を使えばいいのかというと、同学会はニトロフラントイン(nitrofurantoin)やST合剤(スルファメトキサゾール・トリメトプリム,sulfa-trimethoprim)を推奨しています。
************
日本は他国に比べ、ニューキノロン系抗菌薬が簡単に使われすぎていることがよく指摘されます。私は、別のところで「毎回風邪にクラビット」を処方する医師を批判したことがありますが、患者さん側も「風邪にはクラビット」と信じている人もいて驚かされます。風邪(上気道炎)に抗菌薬が必要なのは重症の細菌性のものだけであり、太融寺町谷口医院の例でいえば、せいぜい1~2割程度ですし、そのなかでクラビットを含むニューキノロン系抗菌薬が必要な例は年間数例に過ぎません。
膀胱炎の場合、重症化している場合には確かにニューキノロン系を用いるべきこともありますが、たいていはペニシリン系か第一世代セフェム系で事が足ります。ただ、米国泌尿器学会が提唱しているニトロフラントインやST合剤を日本で用いるのは現実的ではありません。そもそもニトロフラントインは日本では販売されていませんし、ST合剤を使いにくいと感じている医師は少なくなく、実は私もその一人です。
ST合剤はたしかに米国では膀胱炎などに頻繁に使われるのですが、それなりに強力な抗菌薬であり、エイズの合併症として有名なカリニ肺炎にもよく効きます。私はタイのエイズ施設で、ST合剤を頻繁に処方していましたが、かなりの確率(私の印象では3~4割)に薬疹が出ます。HIV陽性者に薬疹が出やすいのは事実ですが、ST合剤はHIVに関わりなく薬疹を含む副作用が起こることは少なくありません。日本の添付文書には「【警告】血液障害、ショック等の重篤な副作用が起こることがあるので、他剤が無効又は使用できない場合にのみ投与を考慮すること」と目立つように赤字で書かれています。わざわざこのように「警告」されている薬は容易に使えないのです。
風邪(上気道炎)の場合も、膀胱炎の場合も、重症度の判定、およびどのような細菌が原因になっているかについてはグラム染色という方法を用いて炎症細胞や細菌の像を観察します。グラム染色は簡単にできて数分で結果がでて、おまけに安い検査です。(培養検査やPCR法は高額になります)
つまり、膀胱炎の症状があるから抗菌薬、ではなく、まず尿沈渣のグラム染色をおこない、その結果に基づいて抗菌薬の有無を判定し、必要な場合は炎症の程度と菌の種類(グラム陽性菌か陰性菌か、桿菌か球菌か)を考えて抗菌薬を選択すれば、ニューキノロン系抗菌薬の出番はそう多くないのです。
注1:米国泌尿器学会のプレスリリースは下記を参照ください。
http://auanet.mediaroom.com/2017-05-13-As-Part-Of-Choosing-Wisely-R-Campaign-American-Urological-Association-Identifies-Third-List-Of-Commonly-Used-Tests-And-Treatments-To-Question
また、choosing wiselyのウェブサイトの該当ページは下記です。
http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/american-urological-association-fluoroquinolones-for-uncomplicated-cystitis-in-women/
5つの提言の他の4つも簡単に紹介しておきます。
①低リスクの限局性前立腺がんの治療を容易におこなうべきでない
②オピオイド系鎮痛薬を漠然と使わない
③血尿があるからといってルーチン検査として尿細胞診や尿中マーカー検査をすべきでない
④腎結石疑いの小児患者に容易にCT撮影をすべきでない
投稿者 | 記事URL
2017年7月9日 日曜日
2017年7月9日 鎮痛剤は心筋梗塞のリスク
鎮痛剤(痛み止め)は安易に飲むべきでない、ということはこのサイトでも繰り返し訴えていますし、日々の診察室でも毎日伝えています。世の中には、痛み止めを安易に使いすぎる人が少なくなく、初診時にはすでに「薬物乱用頭痛」を起こしている人もいます(注1)。
なぜ鎮痛剤を飲みすぎてはいけないのか。たくさんの理由があります。まずは「依存性」があることを自覚すべきです。重症化するとベンゾジアゼピン系睡眠薬と同じかそれ以上にやめることに苦労することもあります。次に臓器への障害があります。特に腎臓の障害を起こすことは珍しくなく、短期間であっても急性腎不全になり入院が必要になることもあります。長期的には心血管系病変のリスクがあります。
今回紹介したい研究は「鎮痛剤の使用で心筋梗塞のリスクが顕著に増加する」というもので、特筆すべきなのは「最初の1ヵ月が最もリスクが高い」ということです。以前から長期使用での心血管系疾患のリスクは指摘されていましたが、短期間でも危険性があることになります。
医学誌『British Medical Journal』2017年5月9日号(オンライン版)に件の論文が掲載されています。研究は過去に発表された論文を総合的に分析する方法がとられています。研究の対象者は合計446,763例で、このうち61,460例が急性心筋梗塞を発症しています。
今回検討されているのは「イブ」や「ロキソニン」などのNSAIDs(非ステロイド性消炎鎮痛薬)と呼ばれる鎮痛剤です。驚くべきことに調査対象となったすべてのNSAIDsで心筋梗塞のリスクが増加しています。使用量は多いほど高リスクとなっています。内服開始1週間でリスク上昇が認められ、1カ月でリスクがピークとなります。各NSAIDsのリスクは次の通りです。
・イブプロフェン(イブ、ナロンエース、バファリンルナなど) 1.48倍
・ジクロフェナク(ボルタレン) 1.50倍
・ナプロキセン(ナイキサン) 1.53倍
・セレコキシブ(セレコックス) 1.24倍
************
各NSAIDsの特徴を簡単に記しておきます。きちんとしたデータは見たことがありませんが、おそらく日本で最も使用されているNSAIDsはイブプロフェンだと思われます。理由は薬局で簡単に買えるからです。商品名で言えば、「イブ」の各シリーズ、バファリンプレミアム、バファリンルナ、ノーシンピュア、ナロンエース、フェリア、リングルアイビーなど多数あります。「ブルフェン」という名称の処方薬もありますが、医療機関ではあまり処方されず他のNSAIDsが好まれる傾向にあります。
医療機関で処方量の多いNSAIDsとしてロキソプロフェン(先発の商品名は「ロキソニン」)が挙げられます。これはなぜか日本で特に処方例が多く、海外ではさほど用いられていません。ですから、今回紹介したものも含めて海外の論文にはあまり登場しません。ロキソプロフェンはイブプロフェンと性質が似ていますが、胃腸への副作用がイブプロフェンよりも少ないという特徴があります。ですが、まったくないわけではなく、ロキソプロフェンで胃に穴があいた、という症例も珍しくはありません。(ロキソプロフェンについては下記メディカルエッセイ(注3)も参照ください)
ここ数年、使用量が増えているのがセレコキシブです。これは他のNSAIDsに比べて胃腸障害が少ないのが特徴で、そのため慢性の疼痛のために長期間鎮痛薬が必要な人に好まれます。ですが、今回の研究で明らかになったのは、胃腸障害が軽減されたとしても心筋梗塞のリスクはあるということです。
どのNSAIDsも内服開始後1週間から1か月くらいの間に心筋梗塞のリスクが上がることは覚えておいた方がいいでしょう。また、NSAIDsは血圧をあげるという副作用も忘れてはいけません。
注1;薬物乱用頭痛については下記コラムを参照ください。
はやりの病気第96回(2011年8月)「放っておいてはいけない頭痛」
注2:この論文のタイトルは「Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data」で、下記URLで全文が読めます。
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1909
注3:下記を参照ください。
メディカルエッセイ第97回(2011年2月)「鎮痛剤を上手に使う方法」
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる
- 2025年11月30日 運転時のカフェイン多量摂取は危険
- 2025年11月27日 「コーラ1本で寿命が12分縮まる」は本当か
- 2025年10月17日 カリフォルニアでは「超加工食品」が学校給食禁止に
- 2025年10月16日 その後のNDM-1とグラム染色の必要性
- 2025年9月21日 カンジドザイマ(カンジダ)・アウリスの恐怖
- 2025年9月15日 猛暑は「老化」「早産」「暴力」「犯罪」「成績低下」などの原因
- 2025年8月31日 インフルエンザワクチンで認知症を予防する
- 2025年8月28日 悪玉コレステロール(LDL)を上昇させる真犯人
- 2025年7月31日 砂糖入りだけでなく「人工甘味料入りドリンク」もアルツハイマー病のリスク
月別アーカイブ
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (2)
- 2025年10月 (2)
- 2025年9月 (2)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (4)
- 2021年3月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (3)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (1)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (4)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (5)
- 2016年10月 (3)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (4)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (4)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (4)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (172)
- 2013年7月 (408)
- 2013年6月 (84)