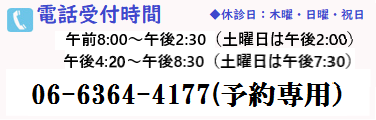ブログ
2013年6月17日 月曜日
34 語学はこんなにおもしろい! 第2回(全2回) 2006/2/28
私は一度、タイ語の先生に、「C」の二つの音(無気音と有気音)を続けて発音してもらったところ、違いがまったく分からなかったために、「一緒やん」という言葉が思わず出てしまったことがあるのですが、彼女はすかさず「イッチョじゃないよ!」と言ったので、おかしくなって笑ってしまいました。2つの「C」を、無気音と有気音として、厳密に区別しているタイ人が、タイ語より格段に音の少ない日本語の「し(SHI)」を発音できないのです。
英語を母国語とする外国人はどうでしょうか。私は、ある西洋人に、このタイ人の先生とのエピソードを話した上で、「英語を母国語とする人にとって、むつかしく感じる日本語の音があるか」という質問をしたことがあります。彼女の答えは「まったくない」というものでした。
けれども、よくよく思い出してみると、アメリカ人であろうがオーストラリア人であろうが、日本語の文章をきれいに発音している西洋人を私は見たことがありません。どれだけ日本に長く暮らしている人であっても、声だけを聞いて、「この人、日本人かな」と感じたことは一度もありません。
それに対して、日本語のよくできるタイ人は、「SHI」や「Z」などがあまり出てこない文章であれば、ほとんど日本人と同じように発音します。例えば「お元気ですか」という文を、英語を母国語とする人に発音してもらうと、イントネーションや発音の微妙な違いから、すぐに日本人でないことが分かりますが、これをタイ人が発音すると、場合によっては「この人、日本人かな」と思うほどきれいです。
どうやら、スピーキングという語学の領域は、単に母音や子音を正しく聞き取れて発音できるかどうか、という問題だけではなさそうです。
もうひとつアジアの例を挙げましょう。
中国という国は、多民族から成立している国家ですが、統一支配をする上で、語学の問題にもっとも難渋した(している)そうです。北京語が一応の共通語ということになっていますが、北京語は数多い中国語のなかでも音の数の多い、少なくともリスニングとスピーキングにおいてはもっとも難易度の高い言語です。
そんな言語を共通語にしようとしたものですから当然無理がでてきます。いくら言葉を強制されても、もともと発音できない音が多数含まれているのですから、地方の民族の人には正しく使えるはずがありません。例えば、台湾の言語は北京語よりも音が少なく、そのため台湾人には上手く発音できない音が北京語には多数あり、北京語を話す中国人が台湾人の中国語を聞けば、洗練されていない、どこか野暮ったい言葉に聞こえることがあるそうです。
日本人が外国語を学ぶときに、発音のハンディキャップを背負っているのは確かに事実ですが、西洋人が日本語を流暢に話すかと言えば、必ずしもそうではありませんし、タイ人は母国語に多くの音を持っていながら、正しく発音できない日本語がありますし、中国にいたっては、同じひとつの国でありながら、地方によっては標準語が正しく発音できないのです。
こう考えれば、日本人だからといって一方的に悲観的になる必要はありません。また、考え方を変えて、日本語と同様に音の少ない言語を勉強するというのもひとつの方法かもしれません。(センター試験で英語以外の科目を選択するというのはかなりリスキーかもしれませんが・・・)
ちなみに、日本人が発音に比較的コンプレックスを持つことなく勉強できるメジャーな外国語は、韓国語とスペイン語だと言われています。私の知る範囲でも、韓国語はある程度までマスターする人が多いような印象があります。スペイン語については、発音には抵抗なく入れたけれど、単語の語尾変化の多さに疲れてしまって挫折するというケースが多いようです。
ところで、語学が苦手という人は男性に圧倒的に多いような印象があります。これは昔からよく言われていることですし、脳生理学的な説明が試みられることもあります(例えば右脳と左脳の使い方の差異や脳梁(のうりょう)の太さの違いなど)。また、私自身の経験から言っても、英語をきれいに話す韓国人は圧倒的に女性に多いという印象がありますし、タイ人にいたっては、例えばタイ国内の銀行に入ると、女性はほとんどがある程度きれいな英語を話しますが、男性職員はかなりのベテランと思わしき人でも、さっぱりしゃべれないということがよくあります。
実際、「語学は女の方が有利なんだから試験にハンディをつけてほしい」、とまで言う男性もいます。語学にコンプレックスを持っている男性のなかには、「女性はもともと語学のセンスがあるのに加えて、日本人の女であれば、容姿にかかわらず(?)、たいていどこの外国人からもモテるから、恋人をつくることによって語学が飛躍的に上達する。それに対して日本人の男は、特に西洋の女性からはまったく相手にされないからハンディを背負っているんだ」、と言う人までいます。
う~ん、たしかに一理あるような気もします。例えば、オーストラリアには、de facto partner visaと呼ばれるものがあります。これは通称「恋人ビザ」と言われているもので、オーストラリアでは、結婚していなくても、ある程度長期間の付き合いがあれば、恋人とみなされて居住権を獲得できるという制度です。この制度を利用したことのある日本人女性(要するにオーストラリアの男性ときちんと付き合っている(いた)女性)の話は、たまに聞くことがありますが、男性でこのビザを取得したことがあるという話は私の知る限りありません。
けれども、男性も決して悲観することはありません。私の知る限りでは、リスニングとスピーキングで女性に劣ることが多いとしても、リーディングやライティングではそれほどひけをとっていないのではないかと思われます。
実際、英文がほとんど書けずに初歩的な文法のミスをしている日本人女性が、ビックリするくらいきれいな英語を話すことがよくあるのと同様、ほとんど英会話ができない男性が、難解な英文をスラスラ読んでいる光景も珍しくありません。
私は現在、月に2~3度、タイ語を習っていますが、その先生によると、「(私のような)男性は文字や文法をすぐに覚えるけれど発音はもうひとつ」、だそうです。それに対して、「女性は文字や文法をイヤがるけれど発音はきれい」、だそうです。男の私からすれば、文字や文法をイヤがる、というこの女性心理が理解できません。タイ文字はとても「かわいい」ですし、そもそも文字を覚えなければ辞書すら使えないのです。辞書も使えない状態で、語学力を向上させるなんてことは私には不可能です。しかし、女性たちは、辞書なしで会話力をどんどんアップさせていくのです。興味深いと思いませんか。
特に語彙力に関しては、男性も自信を持っていいのではないか、と私は思っています。もちろん、語彙力アップには絶え間ない努力が必要ですが、トータルでみれば、語学で女性に劣っているというわけでは決してないと思うのです。リスニングが採用されたといっても、まだまだ大学入試の英語は筆記試験が中心ですし、また、ビジネスの現場でも、いくら流暢に英語を話そうが、英字新聞をろくに読めないような日本人は信用されません。
それに、語彙力を増やし、正しい文法を見につけることによって、リスニング力も上達するのです。これは、多数の単語や文章に慣れることによって、その単語の発音が正確にできなくても、文脈から意味をとれるようになるからです。特に長い単語というのは少々発音に自信がなくても、馴染みがあれば簡単に理解できるものです。
「Y」の発音に苦手意識があり、「year」が正確に聴き取れず発音できなくても、例えば、同じ「Y」から始まる、「yellow-dog-contract」(労働組合に加入しないことを条件とする雇用契約のこと)という単語が会話のなかで出てきたときに、この単語を知っていればすぐに理解できるでしょう。そして、この単語を知っていれば、西洋人から(おそらく)一目おかれるでしょう。
受験生の方には時間的な余裕がないかもしれませんが、実際に英語を母国語とする外国人と話す機会をつくれば、単に自宅で英語を聞くよりもはるかに効果があります。これは、先に述べたように、よく使うフレーズを何度も聞くことによって文脈から単語を類推する能力がアップするからですが、他にも理由はあります。
英語教育番組にはないすぐれたところは、その外国人がどういうところでつまるか、あるいはどのような「間」を置くかが、セリフを話すだけの教育番組よりも手に取るように分かるからです。そして、こういうことが分かるようになると、英語独特のリズムのようなものが身につくようになります。また、もう一度聞き返すことによって、例えば、今の発音は「that」なのか「the」なのかといったことを確認することもできます。
それに、会話の内容を興味深いテーマにすることによって、楽しんで英語と接することができます。お互いの国の文化の違いや、考え方の相違点を知るのは本当に楽しいものですし、書物からは分からないことも多々あって、語学がますます好きになります。
私は昨年の秋から月に2~3度、英語のプライベートレッスンを受けていますが(と言うよりは、ほとんど雑談ですが)、次回のテーマは、「母国ではさっぱりモテない西洋の男が日本に来ればアイドル並みの扱いを受けている実情、なかには寄ってくる日本人女性をひどく扱っている男もいるという現実」、というものです。こういう話は、実際に被害(?)にあった日本人女性から聞くことはありますが、このテーマで、西洋人とディスカッションするということがおもしろいわけです。
こんな会話をしながら実力がアップするなんて・・・。語学っておもしろいと思いませんか。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
33 語学はこんなにおもしろい! 第1回(全2回) 2006/2/15
受験シーズンになって、私にメールをくださる受験生の割合が増えてきました。内容は、「二次試験対策をがんばって合格目指します!」というものもあれば、「センター試験に失敗したので来年に照準を合わせます」というものまで様々です。
最近目立つ質問に、「医学部二次試験の理科が3科目のところは不利ですか」、というものと、「英語のリスニングの効果的な勉強法ってありますか」、というものがあります。
「理科3科目」については、近日出版予定の『偏差値40からの医学部再受験テクニック編(仮)』にも書きましたので、ここでは詳しく触れませんが、私としては、不利になることはなく、むしろ有利になるものと思っています。
今日は、英語のリスニングについてお話したいと思います。
英語のリスニングに苦手意識を持っている人は非常に多いように思います。実は私も、リスニングは決して得意ではなく、英語の4つの分野、すなわち、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングのなかでは、リスニングがもっとも、そしてダントツで苦手です。
日本人の多くが英語のリスニングが苦手なのに対して、英語を母国語とする人たちは日本語を勉強するときに、リスニングがもっとも簡単だ、と言います。そしてこれは、英語を母国語とする人だけでなく、他の言語を母国語とする人にとっても同じようです。外国人が受験する日本語検定というのは4級から1級までありますが、日本に数ヶ月もいれば、たとえ日本語検定1級の試験でも、リスニングに関してはそれほどむつかしくないという外国人も珍しくありません。
この最大の原因は、日本語は母音も子音もその数が多言語に比べて圧倒的に少ないということです。母音を考えてみると、日本語の母音は「あ・い・う・え・お」の5つしかありません。一方、多言語では、英語で12、ベトナム語で15、タイ語で32、中国語は36もあると言われています。(尚、母音の数については、本によって書いてあることが違うので、これらの数字はあくまでも参考程度です。)
子音については、日本語は、「K、S(SH)、T(TH)、N、H、M、Y、R(L)、W、G、Z、D、B、P(PH)、J」の15個しかありませんが、英語では20個、タイ語では22個、中国語は30以上もあるといわれています。さらに、これらだけではありません。中国語とベトナム語には4つの声調が、タイ語には5つの声調があります。
文法や作文については、努力すればかなり実力を伸ばすことが可能ですが、リスニングについてはそう簡単には上達しません。よく、「音感のある人は上達が早い」と言われますが、(私も含めて)音感がそれほどなくてもやらなければならない人も大勢いるわけですから、「自分は音感がないから・・・」と言って逃げるわけにはいきません。
では、どうすればいいかと言うと、繰り返し繰り返し聞く練習をするのです。「なんだ、当たり前のことじゃないか・・・」と思われるかもしれませんが、これは、単に「何度も繰り返し聞けば聞き取れるようになる」という意味ではありません。むしろ、「正確に聞き取れなくても意味が理解できるようになる」ということが重要なのです。そして、そのためには、文法をしっかりとしたものにして、語彙力を増やすことが必要です。
例を挙げましょう。
英語を母国語とする人は、「ear」と「year」を正確に区別しますが、日本人でこれらを正確に聴きわけて、そして区別して発音している人はどれくらいいるでしょうか。少なくとも私にはほとんど絶望的です。先ほど日本語の子音に「Y」を含めましたが、実は日本人の多くはこの「Y」が正確に発音できません。「や・ゆ・よ」はそれぞれ「YA,YU,YO」と発音しているのですが、「YI」「YE」については、「I」「E」になってしまう人がほとんどです。五十音の表にも「や・い・ゆ・え・よ」と書かれていることからも、それは明らかでしょう。
外国人が日本に来て驚くことのひとつに、「日本人は自国の通貨の発音もできないのか・・・」というものがあります。つまり、日本の通貨は「YEN」(円)なのに、これを「EN」と発音するからです。「Y」の発音は、「I」と「J」の中間のような音ですが、これを日本人が正確に発音するのは至難の業です。(しかし、よく考えてみると、なぜ「円」の英語は「EN」ではなく「YEN」なのでしょうか・・・)
私は、「Y」の発音は難しくないのか、ということをオーストラリア人に質問したことがあります。彼女の答えは、「日本人が難しく感じるのは分からないでもないが、英語を母国語とする人からみればまったく難しくない」というものでした。
同様の質問をタイ人にしたこともありますが、彼女の答えも「簡単です」の一言でした。ちなみに、タイ語では日本のことを「???????」(これを無理やりアルファベットで表記するとyiipunもしくはyiibpunとなると思います)と言いますが、これを正しく発音できる日本人はほとんどいないそうです。彼女によれば、日本人は「YA」や「YU」は発音できるのに、「YI」ができないことが大変不思議で興味深いそうです。
では、日本人は、母国語のハンディキャップから、リスニング習得を諦めなくてはならないのでしょうか。もちろん、そんなことはありません。受験にも英語のリスニングは必須化されるようになってきているわけですから、かなりのハンディがあろうとも克服しなければなりません。
私は、先ほど「繰り返し繰り返し聞く」ことが大切だと述べましたが、これは「その単語の発音に慣れる」という意味ではなく、「その単語を含めた文章に慣れる」ということです。
「ear」と「year」は確かに単独で発音されれば聴き取るのは至難の業ですが、文脈と合わせて考えるとそれほどむつかしくはありません。実際、私はこれら2つの単語が聴き取れずに苦労した経験はありません。そのスピーカーが「耳」のことを言っているのか、「年」のことを言っているのかで迷うなんてことは、普通はありえないからです。
これは「L」と「R」でも同じことです。「glass」と「grass」、「collect」と「correct」などは、それだけで聞くと判別しにくいことがありますが、文脈から察すればそれほどむつかしくはありません。(ただし、TOEICのリスニングの問題でこれらの区別を問うている問題はあります。)
ただ、「L」と「R」については、発音するときには充分に注意しなければなりません。これを曖昧にして発音すると、文章の意味が伝わらないことがよくあります。私はそんな経験をこれまでに何百回としてきています。
英語を母国語としない外国人のこともみておきましょう。
「L」と「R」の区別は、韓国人も苦手なようです。そのため韓国では幼少児に舌の手術をおこなうこともあるそうです。舌を手術して「L」と「R」の発音が正しくできるのかどうか、私には甚だ疑問なのですが、世界一の受験大国と呼ばれている韓国の教育の狂信的な力の入れように驚きます。ちなみに、韓国人の多くは日本語の「ず」が正しく発音できないようです。私は一度「ミジュをください」と言われて、それが「水」だと分かるまでに随分長い時間がかかったという経験があります。
タイ語では「L」と「R」は区別されているのですが、欧米人に言わせると、タイ人の「R」は、はっきりと「R」と発音するときと、「L」に極めて近い音を出すときがあるそうです。
また、タイ語には、日本語はもちろん、英語よりも多数の母音と子音、さらに5つの声調がありますが、発音できない日本語があって興味深いと言えます。タイ人のほとんどは、日本語の「し(SHI)」が発音できません。だから「新幹線」は「チンカンセン」と発音しますし、「ショッピング」は「チョッピング」と言います。また、「Z」の音もタイ語にはなく、そのため「象さん」は「ソウさん」になります。
その一方で、日本人にはかなりのむつかしさを感じさせる発音がタイ語には多数あります。先に述べた「Y」もそうですし、「C」「P」「T」「K」はそれぞれ2種類(無気音と有気音)あって、これらを厳格に区別しなければなりません。例えば、日本人には(少なくとも私には)、同じように聞こえる「C」を発音するときに、息を出すか出さないかで、まったく別の音として扱うのです。欧米人も、この点についてはタイ語を難しいと感じているようです。
これらを発音するときに区別しようとすると、例えば「C」については、有気音の「C」は日本語の「ち(CHI)」と同じ音で、無気音の「C」は「じ(JI)」と同じ音で発音すると、問題なく通じることも多いのですが、逆にタイ語を聞くと、どう聞いても「C」の無気音は「じ(JI)」とは聞こえなくて不思議です。これは、タイ語には英語や日本語の「J」の音がないことが原因なのですが、語学のおもしろさはこういうところにもあります。
つづく・・・・
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第32回(2006年2月) 医者は「勝ち組」か「負け組」か
2006年1月23日、ライブドアの堀江社長が証券取引法違反で逮捕されたという事件は、翌日の各新聞のトップを飾り大きな議論を呼んでいます。この事件を報道しているのは日本のマスコミだけでなく、ReuterやBBCといった海外の一流メディアまでもが大きく取り上げました。
そして、海外のメディアも堀江容疑者の人物像について、不正行為の容疑についてばかりでなく放送局やプロ野球チームを買収しようとしたことや、衆院選に立候補したことなどにも触れています。
数年前から「勝ち組・負け組」という言葉が流行していますが、堀江氏は典型的な「勝ち組の象徴」として語られることが多かったように思います。
人間を単純に二極化してしまうようなこの「勝ち組・負け組」という言葉に私は当初から抵抗があったのですが、あまりにもこの言葉が世間に浸透してしまったために、様々な弊害が生じているように思えてなりません。
例えば、私にメールを送ってくる医学部受験を考えているという人のなかにも「医師になって勝ち組になりたい」というような表現を使う人がいます。
この「勝ち組・負け組」という言葉が広がることに危惧を感じるのは、世の中の価値を単に「お金」を尺度としてみなされてしまうからです。文脈にもよるでしょうが、結局のところ「お金」のある人間は「勝ち組」で、「お金」のない人を「負け組」と捉えることが多いように思われます。実際、堀江氏の発言のなかで「人の心はお金で買える」とか「お金があればオンナをものにできる」というものもあったそうです。
「人間の幸せはお金で決まるものではない」と言ってしまえば、中身のない綺麗事に聞こえますが、世の中にはお金を優先事項にしていない人も大勢います。今回は私の知るそういう人たちを紹介したいと思いますが、その前に世間で言われているような「負け組」とは何なのかを考えてみましょう。
森永卓郎氏の『年収300万円時代を生き抜く経済学』という本が大ベストセラーになったこともあり、年収300万円程度の人を「負け組」と呼ぶような風潮があります。ところが、あるデータによると、年収300万円程度の人の9割以上がインターネットの使える環境のパソコンを所有しており、また、半数以上の人が車を所有しているそうです。また、現在の日本ではよほどのことがない限り衣・食・住に困ることはありません。
はたして、自宅で悠長にインターネットをしている人を「負け組」と呼んでいいのでしょうか。たしかに、年収何億もある人と単純に収入だけで比較すれば「負け組」ということになるのかもしれません。けれども、それを言うならパソコンどころかその日に食べるものがない環境にいる人が世界にどれだけいるかを少し想像してみればどうでしょうか。
見方を変えれば、日本国籍を有していること自体がすでに「勝ち組」なわけです。
しかし、こういう見方は「屁理屈、あるいは単なる綺麗事だ」と言う人もいるかもしれません。そういう人に私が問いたいのは「それでは、衣・食・住に困らずに車やパソコンを有していてそれ以上に必要なものは何なのですか」ということです。
実際に年収300万円くらいの男性にこの質問をすると、よく返ってくる言葉が「それでは恋愛や結婚ができない」というものです。
けれども、本当にそうなのでしょうか。たしかに、恋愛や結婚に関するデータをみてみると、女性が男性に求めるひとつに「高収入」というのがあるようです。しかしながら、アンケートで「お金があるのとないのではどちらがいいですか」と聞かれれば、よほどの変人でもない限り「お金はある方がいい」と答えるでしょう。
統計学的な根拠があるわけではありませんが、私には世間の女性が「年収300万円程度の男とは恋愛ができない」と考えているようには到底思えないのです。私の周りの女性に話を聞くと、「お金はそれほど重要じゃない」と言いますし、年収300万円くらいの男性と付き合っている女性は何も珍しくありません。
誤解を恐れずに言うならば、パートナーのいない男性は、その理由を年収のせいにして恋愛のできない本当の理由を見ようとしていないだけではないでしょうか。また、パートナーのいない女性は「周りには年収の低い男しかいないからひとりでいるんだ」という言い訳を用意して、恋愛できない本当の理由を見ないようにしているだけではないでしょうか。
恋愛や結婚のことはさておき、衣・食・住は満たされているけれども「心の平安」がないという人に私がおすすめしたいのは「感動」を探すということです。そもそも、衣・食・住、さらに車やパソコンの次に必要なものが「お金」だ、という考えばかりが注目されるから、人間の価値を「お金」だけで評価するような「勝ち組」という概念ができあがってしまっているわけで、「お金」以外の「感動」を求めてもかまわないわけです。
もちろん、世の中にはお金が好きで好きでたまらないという人がいますし、私はそれはそれでかまわないと思います。実際、そういう人もいなければ資本主義がうまく回転しないのかもしれません。
けれども、「お金」以外の選択枝を見つめなおすのは悪いことではないでしょう。
例をあげましょう。
私が、タイのエイズホスピスにいたときにヨーロッパから来ているボランティアが何人かいました。彼(女)らは医師であったり、看護師や介護師であったり、普通の主婦であったりするわけですが、お金持ちはひとりもいませんでした。年収は300万円もありません。ヨーロッパでは一部の貴族的な身分の人を除けば、大半は年収300万円以下の人たちです。物価が安いかというとそうではなく、日本の方がよほど物が安く買えるように思います。
そんな状況のなかで、彼(女)らは短くても数ヶ月、長ければ数年という単位でボランティアに来ていました。義務感でボランティアをしているわけではありません。楽しくて「感動」があるからこそはるばるとやって来ているのです。これはやってみないと分からないかもしれませんが、患者さんと触れ合って得ることのできる「感動」というのは、お金では買えない、いわば「priceless」なものです。
もうひとつ例をあげましょう。
タイでは貧富の差が激しいという話を別のところでもしましたが、例えば、地方からバンコクに出稼ぎにきてホテルのルームメイキングをしているような女性の月収は1万円程度です。私が彼女らと話して感動するのは、表情に悲壮感がまったくなく、その仕事を楽しんでいるということです。お金はないけれども、外国人と話すのはおもしろいし、仕事が暇なときは同僚とおしゃべりするのが楽しいと言います。なかにはもう20年も同じ仕事をしている女性もいます。彼女らは月収1万円で楽しく生活しているのです。
日本に目を向けてみましょう。
『医学部六年間の真実』でも述べましたが、日本の医師というのは儲けようと思えばかなり儲けることができます。2005年12月に発覚したニセ医者の年収が2000万円というのがいい例でしょう。しかし一方では、年収数百万円程度で自分の好きな臨床や研究に没頭している医師も少なくありません。
私はこの春にクリニックの新規開業を考えていますが、私の試算ではこれまでに比べて年収が半分以下になります。それでも開業にこだわるのは、総合診療ができて(これまでは皮膚科の外来をしているときは風邪すら診ることができず、内科の外来をしているときは湿疹すら診れませんでした。なぜならそれらの診察をすれば他科に対する「越権行為」になるからです)、継続して患者さんを診ることができるからです。つまり、患者さんとの距離がぐっと近くなるわけで、それだけ「感動」も増えると考えているのです。
お金のみに価値を置いていれば、いつも強盗や詐欺師から身を守ることを考えなければなりませんし、近づいてくる人間はお金目当てかもしれない、と要らぬ疑いを持つことになるかもしれません。お金で買えない「priceless」な「感動」というものを考えてみるのは決して悪くないことです。
私個人としては「勝ち組・負け組」という言葉は好きではありませんが、あえて使うならば、「お金」ではなく、どれだけ自分の人生で「感動」を体験できたかによって「勝ち組・負け組」が決まる、とは言えないでしょうか。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第31回(2006年1月) 正しい医師への謝礼の仕方、教えます!
先日、ある患者さんと話していたときのことです。
「先生、あたし3年前に手術受けたときに10万円も医者に渡してんで~。ほんま腹立つわ~。」
医師への金銭の授与・・・。誰が考えてもおかしいのは明らかですが、いまだにこの悪しき慣習は根強いようです。
「そんなに腹立つんやったらあげへんかったらよかったのに・・・」
私がそう言うと、その患者さんは続けました。
「そやかて、そこの病院では手術を受けるときにはお金を渡すのが暗黙のルールやって聞いてんもん・・・」
そんなルール、本当にあるのでしょうか。
この患者さんのように10万円という大金は極端だとしても、今でも実際に、我々医師にお金を渡そうとする患者さんは少なくありません。特に手術の後に渡そうとする患者さんが多いような印象があります。
もちろん、こんなことは誰が考えてもおかしいわけで、医師もできるならば受け取りたくありません。お金を失うことになるわけですから患者さんの負担にもなりますし、受け取る医師としても気持ちのいいものではありませんから、合理的に考えれば、このようなおかしな慣習は直ちに撤廃してしまえばいいのですが、現実はそう簡単ではないようです。
私自身も含めて医師側からみれば、お金を渡そうとしてくる患者さんと接するのは、かなりしんどくて疲れます。もちろんできることなら受け取りたくないわけですから、最初はなんとかして断ろうとします。しかしそのうちに、患者さんが「先生が受け取るまで帰りません!」などと言って一歩も譲らなくなると、その場の空気から逃げ出したいがために受けとってしまうこともあります。
しかし、その気まずい空気からは抜け出したとしても、その後に「患者さんから受け取ってしまった・・・」という罪悪感に苦しめられることになります。
また、私の「受け取りません」という言葉にいったんは納得した患者さんでも、後で(どうやって住所を調べたのか)自宅に送ってくる人もいます。
私は、できるだけ早いうちに、いただいたお金をそのまま(商品券の場合は換金してから)、各団体に寄付するようにしていますが、寄付したからといって罪悪感が完全に消えるとは限りません。
私の尊敬するある医療従事者は、「患者さんからお金や物を受け取らない」ことを徹底しています。その人は、患者さんから非常に人気があるということもあり、お金や物を渡したいという患者さんが後を絶ちません。院内では何があっても絶対に受け取らないことが分かると、一部の患者さんはその人の自宅にお金を送ります。お金が送り返されてくると、今度は米や酒、果物といった物を送るようになります。しかし、その人の態度は徹底していますから、きちんと手紙が添えられて送り返されてくるというわけです。
医師への金銭の授与、この悪しき慣習は、なぜなくならないのでしょうか。
その最大の理由は、「お金を渡さないと治療で手を抜かれるんじゃないのか・・・」と患者さんが考えるからではないでしょうか。
けれども、そんなことは絶対にありえません。いくら大金を渡そうが、その逆にわがままばかり言って医療従事者をてこずらせようが、医療従事者が手を抜くということは絶対にありません。これは決して綺麗事や単なる理想論ではなく、医師が患者さんによって治療に差をつけるということはありえないのです。
その理由は、少し考えるとすぐに分かります。例えば手術を例にあげて考えてみましょう。医師というのは、できるだけ手術の成績をあげたいと考えています。つまり、自分のおこなった手術で患者さんがよくならなければ、自信を失うことになりますし、その医師や病院の評判が落ちてしまうことにもなりかねません。医師はどんな患者さんに対しても全力で手術をおこなっているのです。そして、これは他の治療でも同じです。治る病気が治らなければ、その医師や病院の評判が下がってしまいますから、治療で手抜きなどをおこなうと、結果としてその医師や病院が困ることになるのです。
ですから、「お金を渡さないと治療で手を抜かれるんじゃないのか・・・」という心配は理論上でもまったく不要なのです。
「純粋な感謝の気持ちからお金を渡したい・・・」、そのように考えられる患者さんもおられるかもしれません。自分にとっていいことをしてもらえば、何かのかたちで感謝の気持ちを現したい、と思うのは人間にとって自然なことかもしれません。
けれども、その患者さんに対しておこなった治療行為というのは、我々医療従事者は「仕事」としておこなっているのです。もちろんその「仕事」に対する報酬は病院からきちんと支払われています。与えられた「仕事」をして、その分の報酬を得ているわけですから、それ以上の収入を得ることはおかしいのです。それに、そもそも病院から支払われている報酬は、元をただせば国民の税金と保険料から捻出されているのです。
「でも、本当にあの先生にはよくしてもらったし、なにかのかたちでどうしても感謝の意を示したい・・・」、そのように考えられる方もおられるでしょう。
では、その問題にお答えしましょう。
お金を渡すからいろいろと問題が生じるわけですから、どうしても感謝の意を示したいなら、お金以外のものを渡せばいいのです。「お金以外のもの」といっても、商品券の類のものは金銭と同じですからダメです。また明らかにお金がかかっていると思われるモノもダメです。
患者さんによっては、お菓子や花を持ってこられることがあります。小さな箱に入ったチョコレートを退院した後で持って来られた方がいました。退院の日に一輪の花を「みなさんのおかげで元気になれました」という言葉とともに渡してくれた患者さんもいました。お金や商品券ならイヤな気持ちになりますが、こういうときは私は純粋に嬉しく感じます。
しかしながら、小額であっても、やはりお金のかかるプレゼントを患者さんが医療従事者に渡すという行為は、問題がないわけではありません。
ならば手作りのものならいいのか、そう考えられる方もいるでしょう。確かに手作りのアクセサリーなどをいただくと大変嬉しく思います。私も患者さんにもらった手作りのブローチや、子供が書いてくれた絵などは宝物にしています。
しかしながら、感謝の意を示すには、もっと簡単でもっと適したものがあります。
それは、「手紙」です。
患者さんからの手紙ほど嬉しいものはありません。医療従事者にとって、患者さんからの手紙というのはお金に代えることのできない価値のあるものです。私も患者さんからいただいた手紙は宝物にしています。小さな子供が覚えたての文字を使って色鉛筆で一生懸命に書いてくれた手紙など、何度読み直してもすがすがしい気分にさせてくれます。最近は、インターネットで私の名前を検索してメールをくれる方も増えてくるようになりました。
患者さんの手紙からは学べることもあります。例えば、「先生は最初は怖い人かと思っていましたが・・・」とか「あの検査があれほどしんどいとは思いませんでした」などと書かれていると、「ああ、もっと第一印象を大切にして丁寧に患者さんに接するようにしよう」とか「検査の苦痛についても勉強する必要があるな」とか、そういうフィードバックができるわけです。
それに、手紙というのは出した方も気持ちのいいものではないでしょうか。手紙なら、冒頭で紹介した患者さんのように後からグチを言いたくなることもなくなるはずです。
私は私生活で、人に親切にしてもらったり、助けてもらったりすると、できるだけ手紙や電子メールで感謝の意を伝えるようにしています。手紙や電子メールは、直接会って話したり電話で話したりするのとは違った表現ができるために、特に感謝の意を示したいときには最適ではないかと私は考えています。
手紙(や電子メール)がきっかけで、人間どうしの絆が太くなったり、お互いに理解し合えたりすることはよくあります。これはあらゆる人間関係で言えることだと思います。
そして、それは患者さんと医師の関係でも同じなのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
30 ニセ医者とシャブ中東大医大生 2005/12/31
2005年12月6日の新聞記事は我々医療従事者を大変驚かせました。
33歳の男性が、なんと医師免許を持っていないのにもかかわらず8年半もの間、医師として勤務していたことが発覚したというのです。偽造医師免許証のコピーを提出し、医師になりすまし、複数の病院で勤務し、年収はなんと2千万円もあったというのですから、我々医療従事者だけでなく、一般の方も大変驚かれたと思います。
この事件はいくつかの問題点がマスコミなどで指摘されていますので、それらをみていきましょう。
ひとつめに、なぜ偽造医師免許証がバレなかったのか、という点です。私も現在複数の医療機関で仕事をしていますが、雇用契約を結ぶ前には、医師免許証の原本と保険医登録票(こちらはコピーでいいことが多い)を提出します。おそらく被告の男性(以下、「ニセ医者」とします)の勤務先の病院では医師免許証の原本は求めていなかったのでしょう。
けれども、このニセ医者が偽造に関する高度な技術を持っていて、原本を偽造していたらいったいどうなっていたのでしょうか・・・。
ふたつめの問題点は、なぜ2千万円もの年収があったのかということです。2004年度の人事院調査のデータによりますと、全国の勤務医の平均給与は28~32歳で月収約73万7000円だそうです。この数字とニセ医者が取得していた年収2千万円には大きな格差があります。
私が、『医学部六年間の真実』で述べたように、医師の当直アルバイトというのは破格で、なかには一晩で20万円ももらえるところもあるようです。けれども、そのような高額アルバイトは重症の患者さんがひっきりなしに入ってくるような救急医療の現場であって、ニセ医者に務まるとは到底思えません。だとしたら、ごく軽症の患者さんしか来られない病院で働いていたことが予想されるわけで、当然そういう病院は給与はそれほど高くないですから(ただし一般の仕事に比べればそれでも破格です)、どう計算しても2000万円という数字は不可解なのです。
12月18日に政府が発表した、「診療報酬マイナス3・16%の改正」というのは大きな議論を呼び、医師会を初めとする医療団体は一斉に反対の表明をしています。「これでは医師に充分な報酬が支払われず医療の質が低下する」というのがその理由だそうです。
しかしながら、ニセ医者が2千万円も稼いでいるんだから、やっぱり医師はもらい過ぎているんじゃないのか、と言われても仕方がないのではないでしょうか。
もうひとつ指摘されている問題点は、(これはマスコミからというよりは我々医師の間で議論になることですが)、なぜ8年半もの間ニセ医者であることを隠し通せたか、ということです。それもニセ医者であることが発覚したのは、医療行為が不十分であったとか、患者さんからクレームが来て、とかではなく免許証の原本の提示を求められて発覚したわけです。ということは原本の提示が求められなければいつまでも続けていた可能性があるわけです。しかもこの二セ医者は、患者さんから評判がよかったというから驚きです。
医学部での六年間は、医学部受験とは比較にならないほどの勉強をおこなわなければなりません。後半の二年間は臨床実習で実際に患者さんを診察することによっても勉強をおこないます。卒業後は二年間の研修医期間が義務付けられています。しかし、これでもまだまだ不十分で、それからもしばらくは実質研修期間のようなものです。私の場合も、二年間の研修ではまだまだ未熟であることを自覚し、その後の二年間さらに研修医のような生活を続けました。
ところがこのニセ医者は、定時制の高校を中退した後、都立の病院で一年間見習いをおこなっていたそうですが、そんなことだけで医療行為がおこなえるようになるとは到底思えないのです。(この「見習い」というのもよく分かりません。いったい誰を対象とした何のための「見習い」なのでしょう・・・)
もしかすると、我々が(私が)思っているほど、現在の医療レベルというのは高いものではなく、たしかに六年間の勉強とその後の研修は大変ではあるけれど、そこからアウトプットされるものは、素人が短期間で勉強して得るものとそんなに変わらないのかもしれません。いや、そんなはずはない!と思いたいのですが、そんなことで意地を張るよりも、今まで通り日々の勉強を頑張る方が私にとってはきっといいことでしょう。
ところで、今回発覚したようなニセ医者は氷山の一角ではないか、という話があります。私には到底そのようには思えないのですが、インターネットで複数の掲示板を探してみると次のような書込みが見つかりました。
>コンタクト屋でアルバイトをしたことがあるんだけど
>医師不在時に、コンタクト屋の店員が医師のふりをして
>診察や投薬をしているのは日常茶飯事のことですよ…
>以前にせ医者が精神科病院に勤務していて、よく日医雑誌に投稿していた。頻繁に投稿していたので、緑陰随筆まで書いていたことがあったっけ。
やはり、ニセ医者は他にも大勢いるのでしょうか。
ところで、このニセ医者発覚が報道された同じ日に、この事件とは対照的な記事が報道されました。
それは、東大医学部の学生が覚醒剤中毒で逮捕されたという記事です。報道によりますと、覚醒剤取締法で逮捕されたこの27歳の東大医学部四年生は、超有名進学校の灘高を卒業している超エリートで、高校時代も成績は上位だったそうです。ところが医学部に入学してから覚醒剤にハマりだし4年連続留年していたとのことです。
私が『今そこにあるタイのエイズ日本のエイズ』などで指摘したように、シャブ中医師は何も珍しくありません。日頃から覚醒剤中毒者と接し(夜間の救急外来にはよく来ます)、覚醒剤の恐ろしさをよく知っているはずの医師がなぜ自らもシャブ中になるのかについては、『今そこに・・・』に書きましたからここでは述べませんが、危険性を充分に知っているはずの医師でさえ手をだしてしまう覚醒剤の恐ろしさは何度繰り返し強調してもしすぎることはありません。
医師でさえハマるわけですから、まだ知識が充分でない医学生が覚醒剤に溺れるのは理解できることです。いくら灘高で上位の成績であろうが日本で最難関とされる東大医学部の学生であろうが、そんなことは関係ないわけです。ちなみに東大では2004年の9月に、教養学部の学生が大麻取締法で逮捕されています。
さて、何も珍しくないシャブ中ドクター(医大生)をここで取り上げたのは、覚醒剤の恐ろしさを再確認したかったからだけではありません。というのは、マスコミの報道に疑問を感じるのです。
例えば、夕刊フジが報道したこの記事の見出しは「東大理Ⅲ(医学部)エリート人生がシャブで霧散」となっており、本文のなかで「クスリにハマり、エリート医師への道を自ら閉ざした学生の堕落ぶりに・・・」と述べられています。
たしかにこの男が再び医師の道を目指すのは不可能でしょう。しかし「エリート人生がシャブで霧散」というのは言いすぎではないでしょうか。この男はまだ27歳です。おそらく初犯でしょうし販売をしていたわけではありませんから、実刑にはならず執行猶予がつくことになると思われます。
ならば、人生が終わったわけでは決してありません。灘高から東大医学部に進学するくらいの頭脳を持っているのです。賢い頭脳があるからといって覚醒剤を断ち切れるかどうかは分かりませんが、もし完全に断ち切ったとすれば、その体験を本にするとか講演するとかして、現在もシャブに依存している人を救うような活動はできるのではないでしょうか。なにも東大出身の医師だけが「エリート」ではないのです。
念のために断っておくと、私はこの男の罪を軽くせよと言っているわけではありません。むしろ、現在の覚醒剤取締法はユルすぎることが問題で、初犯であっても実刑にすべきという考えを持っています。しかしながら、それと同時に、依存症の人から覚醒剤を断ち切る支援や、また断ち切った人に社会に復活してもらう方法も考えていかなければならないとも思っています。
覚醒剤取締法違反というのは、殺人やレイプとは犯罪の質が違うのです。覚醒剤取締法で逮捕されたとしても、殺人やレイプのような被害者はいませんし、本人の努力次第では充分に社会復帰することが可能なのです。
だから、私はこのシャブ中(元)医大生を応援したいと考えています。まずは覚醒剤を断ち切ることに専念してもらいたいと思っています。そして、その後は社会のために貢献してほしいのです。
これからの努力によっては、もしかすると医師になるよりも多くの人に貢献できるかもしれないのです。決して「エリート人生がシャブで霧散」と決まったわけではないのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第29回(2005年12月) なぜ日本人の自殺率は高いのか③(最終回)
「死生学」と呼ばれる学問のジャンルがあります。これは欧米では一般的なのですが、日本では以前に比べると随分マシになったかもしれませんが、まだまだ普及しているとは言えません。例えば、「死生学」を学ぶために大学を目指すという受験生は聞いたことがありませんし、「死生学」で修士論文や博士論文を書いている学生はほとんどいないのではないでしょうか。それどころか、ある大学で「死生学」をテーマとした市民講座を開くという話が持ち上がったとき、地域の住民から反対意見が相次いだそうです。
医療の現場では「死」に頻繁に遭遇しますが、現代医学というのはいかに「死」を逃れるか、あるいは引き伸ばすかという点からの考察ばかりで、例えば、「残りの生を幸せに生きる」という観点からはほとんど語られることがありません。
末期癌の患者さんやその家族を対象とした雑誌を見てみても、抗癌剤やリハビリの記事ばかりで、「いかによりよく死んでいくか」という観点からの記事はほとんどありません。「死」を頻繁に経験する医療現場でさえも「死」はタブー視されているのです。
日本社会は昔から「死」をタブー視してきています。タイの社会なら当たり前の「死体を見る」ということさえタブーとなっています。
けれども、このことが「死」を適切に捉えることを妨げて、結果として「自殺」につながっているのではないか、私はそのように考えています。「死」は誰にでも起こる避けられない運命であるのは自明です。ところが、その当たり前の「死」をきちんと見つめないことによって、安易と言わざるを得ないような「自殺」を選んでしまっている人が少なくないように思われるのです。
「自殺の自由」という考えを主張する人がいます。これはこれで正当化されなければならないのかもしれませんし、実際に自殺という道を選んだ人には図りしれない想像を絶するような苦痛があったものと察します。しかしながら、国際比較で異常ともいえるような高い自殺率を記録している日本では、やはり安易に死を選んでいる人が少なくないのではないかと感じずにはいられません。
ところで、なぜ日本では死体を報道することがタブーとされているのでしょうか。私は当初、死体の報道は法律で禁じられているのではないかと思っていたのですが、私の調べた限りそのような法律はありませんでした(ご存知の方おられましたら教えてください)。
法的な制約がないとすれば、世論の圧力が問題となる可能性があるが故に死体の報道がなされないのでしょう。おそらく、夕方のニュースで死体がアップで報道されたらテレビ局に苦情が殺到するでしょう。その理由は、例えば「不謹慎である」とか「子供に悪影響を与える」、あるいは「プライバシーの侵害」といったものではないかと思われます。
しかしながら、「不謹慎である」というのは明確な科学的根拠が見当たりませんし、「子供に悪影響を与える」というのも科学的なデータがありません。漫画や映画、ゲームといったツールでしか死体と接することがないために、逆に「死」というものをきちんと把握できていないのではないかと私は考えています。
「プライバシーの侵害」というのは確かにあるかもしれませんが、一般に殺人事件が起こると、被害者の生前の写真は公開されています。また、社会的に重要な意味のある事件であれば、公益性がプライバシーを優先するという議論が起こってもいいはずです。
つまり、死体を報道すべきでない、という考え方は、なんとなく昔からみんなが感じていることに過ぎないわけで、死体を報道することによって社会的混乱が生じるという科学的根拠はなく、むしろ死体を報道することによって、日本人がきちんと死と直面するようになるのではないか、さらに安易に自殺する人が減少するのではないか、と私は思うのです。
前回、タイでは輪廻転生の考えが深く社会に浸透しているという話をしました。一方、日本では心底から輪廻転生を信じている人はそれほど多くないのではないでしょうか。自己啓発を目的とした雑誌や書籍に目を通すと、「一度きりの人生・・・」「悔いのない人生を・・・」などといった表現をよく目にします。たしかに、何かを決意するときや頑張らなければならないときにはこういった考え方は有効です。例えば、医学部受験を決意するときにはこのように思うことが非常に効果的です。
けれども、いつもいつもこのような考えでいると、避けられない運命に遭遇したときや、予期せぬ不幸に見舞われたときには絶望を加速することになりかねません。そんなときには、「一度きりの人生・・・」ではなく、「何度も生まれ変わる魂が経験するひとつの場面」くらいに思ってしまう方が強いストレスから脱出できるのではないか、と私は考えています。
実は、このような考え方をもつにいたるきっかけとなった経験があります。
それは私が研修医の頃の経験です。ある末期の状態の患者さんと話をしているときのことです。自分でもそれほど長くないことを悟っていたその患者さん(女性)は、ある日私にポツリと言いました。
「先生、あたしね、もういいんです。もう充分です。そろそろあの世に行くときが来ました。あの世に行けば久しぶりに主人と会えるんです。あの世で会おうって主人が亡くなるときに約束したんです。あの世でふたりで楽しく過ごして、また生まれ変わったら結婚しようねって・・・・」
輪廻転生なんてあるわけないという人がおられれば質問したいと思います。この患者さんに、例えば「何を言っているんですか。あの世とか生まれ変わるとかそんな非科学的なことを・・・。人生は一度きりです。人間は死んだら終わりなんです!」と言うことができるでしょうか。
この患者さんが輪廻転生のことをどれだけ真剣に信じていたかは分かりませんが、少なくともこの患者さんにとっては輪廻転生という考えを持つことによって、死の不安が和らぎ、落ち着いた精神状態を保つことができていたのです。
「一度きりの人生・・・」という考えに縛られすぎると、避けられない運命に遭遇したときに、強いストレスから自殺へとつながることになるかもしれません。配偶者の突然の死や予期せぬ難病だけでなく、突然のリストラや厳しい借金の取立てにあったとしても、長い長い寿命の魂が経験するほんの一場面だという認識に立てば、少しは自殺を思いとどまるのではないでしょうか。
そろそろまとめに入りましょう。
私が日本人の自殺率が高い理由として考えているものは3つあります。
ひとつは、日本は「階級社会」ではなく、身分というものを考えることなく生きていける社会でありながら、以前のように国民の多くが中流階級である思っていた時代がすでに過去のものになったことが原因です。よく言われるように「終身雇用」「年功序列」というものが完全に崩壊してしまい、「才能のある者だけがやりたいことをみつけて努力したときにしか幸せが来ない」、というような幻想が存在するように見受けられます。このため、何をやっていいか分からない者は、デュルケームの言うところの「アノミー」の状態に容易に陥り、その結果自殺を選んでしまうというわけです。
ふたつめは、「一度きりの人生・・・」という観念が強すぎるというものです。例に挙げた仏教だけではなく、キリスト教をはじめほとんどの宗教は輪廻転生というものを認めています。それに対して無宗教の日本人は、この考えを信じていないだけでなく、それが精神状態に寄与する効果についても考えようとしていません。そのため「人生に失敗した」と考えることが自殺につながっているのではないかと思われるのです。
3つめは、「死」というものをタブー視しすぎているということです。「死」をタブー視するあまり、現実的に適切に「死」を捉えることができず、安易に「死」を選んでしまうというパラドックスが存在するのではないかと思われるのです。
「自殺の自由」を主張するのは個人の「自由」でありますが、日本の自殺率が先進国のなかで第1位であるという現実にはしっかりと注目する必要があるでしょう。
そして、予期せぬ不幸に突然見舞われたときに、何ができるか、何を思うことができるか、ということについて日頃から考えておくべきではないか、私はそのように感じています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第28回(2005年12月) なぜ日本人の自殺率は高いのか②
タイに行って驚くことのひとつは、日本からは考えられないくらいの階級社会である、ということです。
例えば、年収何億円もの稼ぎがあり、豪邸に住み高級車を乗り回している富裕層がいるかと思えば、裸足の幼児を抱きかかえながら真夜中に小銭を乞うている中年女性もいます。街角では、そんな身分の違う人たちが、当たり前のようにすれ違っています。
タイでは一応は小学校までは義務教育ということになっていますが、本当に小学校に通っているのか疑いたくなるような子供は少なくありません。真夜中に小さなバラを外国人に強引に買わせようとしている子供や、信号待ちで停車している車の窓ガラスを勝手に拭いて小銭をねだる子供は観光名物と言っていいほど有名です。彼(女)らは例外なくボロボロの衣服を身にまとい靴は履いていません。
タイでは、福祉とか生活保護とかいった考え方がそれほど浸透しておらず、タイにしばらく滞在すれば、日本は本当は社会主義国なんじゃないかと思わずにはいられません。
最近の日本は、「格差社会」という言葉がよく使われているような印象があります(例えば『希望格差社会―「負け組」の絶望感が日本を引き裂く』山田 昌弘著 筑摩書房)。親の身分や年収で子供の人生がある程度規定されてしまう、というのが「格差社会」の一面です。例えば、東大に入学する学生の大半が高収入の家庭で育っているというデータもあるそうです。ここから、「地方で貧乏な家に生まれると高学歴・高収入は期待できない」という理屈につながっていくようです。
実際のデータで、親の年収と子供の学歴(あるいは年収)にある程度の相関関係があるのが事実だとしても、私には日本が「格差社会」あるいは「階級社会」だとは到底思えません。
私は地方出身で裕福でない家庭に育っていますが、公立大学の医学部を卒業しています。私立の高校や予備校には経済的な事情から行けませんでしたが、他の先進国と比べると信じられないくらいに安い授業料(例えば米国の医学部では公立でも年間300万円以上の授業料が必要)と複数の奨学金を借りることによって、特に苦労もせずに卒業することができました。
また、ほとんどの人が希望をすれば高校程度は卒業することができるでしょうし、高卒であっても、本人の才能と努力次第で高所得者になるのはまったくの夢というわけではないでしょう。
そんな日本に比べて、タイでは地方の貧困層として育てられれば、将来的に高額所得者になるのはほとんど絶望的であろうと思われます。
これといった産業がなく、農作物も育たないために蛋白源として昆虫を食べなければならないような家庭で育てられれば、一攫千金を夢見て、男ならムエタイ選手を目指したり、女性なら都心に春を鬻ぎに行かねばならないというのが現状です。
私がタイの様々な層の人たちと話をして不思議に思うのは、彼(女)らがそういう「階級社会」を言わば当然のことと見なしているということです。
日本的な感覚で言えば、同じ国のなかでそれだけ身分に差があるのは許容しがたいことです。政治的に左翼的というか、プロレタリアート層が一致団結した運動が起こってもおかしくないのでは、と思うのですがそういう話は聞いたことがありません。
それどころか、初めから一生貧困層でいることに対して「諦めている」というよりもむしろ「納得している」という印象を受けるのです。先にあげたムエタイ選手や売春の話にしても、極一部の人を除けば、正確に言えば「一攫千金を夢見て」ではなく、「単に生活するため」という感覚でいるように思われるのです。
生まれたときから自分がどういう人生を歩むのかが分かっている・・・。タイの社会とはそんな社会であるように私には思われます。
しかしながら、ある意味でこれはこれでいい面もあるのではないか・・・。最近私はそのように考えています。というのは、彼(女)らは近代社会がもたらした「自由」の苦痛から解き放たれているからです。
前回に引き続き社会学者の説を紹介します。エーリッヒ・フロムという著明な社会学者がいます。フロムによると、人間は前近代的な諸々の束縛から解放されて (消極的)自由を手にすると孤独や不安にさいなまれ、自由を耐え難い重荷であると認識するようになります。
フロムの学説に照らし合わせて考えると、タイの(特に貧困層の)人たちは、近代的な消極的自由を手にしておらず、その消極的自由がもたらす苦痛を感じずにいるのではないか。そしてその結果、極度の貧困であるのにもかかわらず自殺に至らないのではないか、私はそのように考えています。
これは、前回取り上げたデュルケームが主張している「アノミー」を体験せずにすんでいる、という言い方もできると思います。
そしてこのことが、タイの自殺率が低い原因のひとつではないかと考えているというわけです。
ところで、タイは仏教国です。仏教といっても日本のような集約力の高くない仏教ではなく、国民の大多数が信仰している国民的宗教としての仏教です。実際、タイの社会は、仏教、あるいは僧侶なしでは語ることができません。例えば、通常名前は僧侶がつけます。タイ人は通常ニックネームで呼び合います。このニックネームは親がつけます。そしてIDカードに記載されている本名は僧侶がつけるのが一般的です。
名前だけではありません。例えば車を買う日とか、海外に渡航する日なども僧侶に決めてもらうことが珍しくありません。もちろん結婚式も仏教的儀式でおこないます。「得を積む」という考えはタイにもありますが、基本的な「得を積む」方法は、寺に対してどれだけ貢献するかということです(これを「タンブン」と言います)。もちろん寺を訪問することを慣習としていますし、街角にある仏像に対しても素通りすることなく手を合わせます。タクシーの中からでも手を合わすのが普通です。これはいかにも信心深そうな人はもちろんですが、普段はやんちゃをしてそうな若い男女でもそうなのです。
そんな仏教(小乗仏教)の考え方のひとつに「輪廻転生」というものがあります。タイ人は私の知る限り、ほとんど例外なく「輪廻転生」を信じています。
そして、この「輪廻転生」が低い自殺率と関係があるのではないか、私はそのように考えています。つまり、人生とは自ら得たものではなく、与えられたものであって、運命に逆らって生きるのはよくない。そして自殺は運命に逆らう最たる行動である。今世がそれほど恵まれたものでなくてもきちんと得を積んでおけば、来世では富裕層として生まれてくるかもしれない・・・。そのような考えがあるのではないかと思うのです。
ちなみに、タイには相続税というものがありません。つまり、先祖が金持ちであればよほどのことがない限り、子孫も裕福な暮らしができるというわけです。そして、相続税を導入すべき、という声は私の知る限り聞いたことがありません。
「輪廻転生」への信仰、これが私の考えるタイで自殺率が低いふたつめの理由です。
もうひとつ、タイ人が自殺をしない理由を私は考えています。
それは、死体に対する考え方です。バンコクには有名な「死体博物館」というものがあり、多くの死体が展示されています。例えば、凶悪殺人犯が死刑にされた後の死体が輪切りにされて多くの人の目にさらされています。また、私がいろんなところで報告しているエイズホスピスのパバナプ寺では、エイズで亡くなった人の死体がミイラにされ展示されています。また、タイの新聞やテレビのニュースでは、ほとんど毎日といっていいくらい、事件や事故での死体の映像が報道されています。
タイ人が日本に来て驚くことのひとつに、日本の新聞やテレビでは死体が写されていない、というものがあるそうです。死体が写されていないとその事件や事故がよく分からないではないか、と感じるそうなのです。
凶悪殺人犯の死体を輪切りにすることの良し悪しは別にして、たしかに日頃から死体を目にする機会が頻繁にあれば、嫌でも「死」というものを考えるようになるはずです。
それに対して、日本では昔から「死」というものが、タブー視されてきているのではないでしょうか。
つづく
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第27回(2005年11月) なぜ日本人の自殺率は高いのか①
私が初めて学問的に「自殺」というテーマに興味を持ったのは社会学部の学生の頃です。社会学部を学んだ者なら誰でも知っているデュルケームという学者の代表著作が『自殺論』なのです。
「自殺」までも学問の対象にする社会学とはなんて魅力的なんだろう・・・。当時の私はそのように感じて、必死にデュルケームの『自殺論』を勉強しました。
デュルケームの理論は、発表してから100年以上たった現在でも尚正しいのではないか、私はそのように考えています。今回取り上げたいテーマは、「日本人の自殺率の高さ」で、このことを考える際にもデュルケームの理論は参考になるのでは、と思うので、少し触れておきたいと思います。
デュルケームは、冬季よりも夏季、カトリックの国よりもプロテスタントの国、女性よりも男性、既婚者よりも未婚者、農村よりも都市で自殺率は高くなると言います。
現在の日本の自殺の状況をみてみましょう。季節ごとのデータは私の調べた限りありませんでした。宗教別の考察はキリスト教がそれほど深く浸透していないために日本にあてはめて考えることはできません。
しかしそれら以外の要素、つまり、女性よりも男性、既婚者よりも未婚者、農村よりも都市に自殺者が多いというのは、現在の日本にも当てはまります。
デュルケームは「自殺」を4つに分類しています。
ひとつめは「利他的自殺」と呼ばれるもので、自殺せざるを得なくなるような集団の圧力によって起こる自殺のことです。具体的には、社会の秩序を乱したとか、ルールや掟を破ったときにのしかかる社会的圧力から死を選ぶような場合です。現在でも、例えば暴力団の組員が組織の掟を破って責任をとるために自殺、というようなことはあるかもしれませんが、現代日本においてはそれほど多くはないでしょう。
ふたつめは、「利己的自殺」と呼ばれるもので、 孤独感や焦燥感などエゴイスティックなものによって起こる自殺のことです。これは現代日本では若い世代を中心にあり得るものと思われます。ただ、最近の統計も含めて日本では、若い世代よりも中年から老年の自殺が多いのが特徴ですから(日本では55歳から64歳で最も自殺率が高い)、このタイプの自殺は日本では多くはありません。
三つめは、「アノミー的自殺」と呼ばれるもので、社会的規則・規制がない(もしくは少ない)状態において起こる自殺のことです。自由のもと、自分の欲望を抑えきれずに自殺するというイメージです。
この「アノミー」という言葉は、デュルケーム自らが提唱した概念で、社会秩序が乱れ、混乱した状態にあることを指します。社会の規制や規則が緩んだ状態においては、個人が必ずしも自由になるとは限らず、かえって不安定な状況に陥るとデュルケームは言います。デュルケームによると、規制や規則が緩むことが必ずしも社会にとってよいことではないのです。
私が社会学を勉強していた80年代後半、日本はバブル経済に突入し、このようなアノミーの状態にあるのではないかと言われていました。デュルケームはなにも不景気のときだけに自殺率が上昇するのではなく、景気の急上昇期、大繁栄の時代にも自殺者が急増するということを示しています。この指摘が当時に私には非常に衝撃的でした。
しかしながら、結果的にはバブル経済の頃の日本の自殺率はそれほど高いものではありませんでした。
一方、バブル経済が破綻し、不景気に突入しだした頃から自殺率は上昇しています。そして失業率が極めて上昇した1998年から現在まで毎年3万人前後の人が自ら命を絶っています。日本の自殺率の推移は失業率と明らかな相関関係があるのです。
失業率が急上昇したのは、不景気そのものもさることながら、以前から崩れつつあった終身雇用がドラスティックに崩壊したり、正社員の雇用が大幅に減少し、代わりに契約社員やフリーターが一般化したりしたこともその一因です。一方では、IT企業に代表されるような若者のミリオネラーが次々と誕生し、一部の者に大金が集中しています。
このような現在の日本の状態は、まさにデュルケームの言う「アノミー」ではないでしょうか。
デュルケームが唱えた4つめの自殺は「宿命的自殺」と呼ばれるもので、閉塞感など欲求への過度の抑圧から起こる自殺のことです。これは、アノミー的自殺の亜種と類型でき、社会的混乱から生じた閉塞感などが自殺につながることは容易に想像できます。現代日本の社会混乱(アノミー)に上手く対応できず閉塞感を感じている人は少なくないでしょう。
さて、デュルケームの考察はこれくらいにしておいて、今度は医学的な観点から日本人の自殺を考えて生きましょう。
日本で自殺者が多いのは、確かに失業者の増加や不景気と相関がありますが、実は日本の自殺の原因の第1位は「病気による苦悩」です。慢性の病気や不治の病に耐え切れず、さらにおそらく家族に負担のかかることを懸念した人たちが自ら命を絶っているというわけです。
どのような病気が自殺へとつながるかという点についてはデータがありませんが、最近デンマークの学者が発表した興味深い論文(Archives of Internal Medicine(2004; 164: 2450-2455))をご紹介したいと思います。
この論文によりますと、シリコン豊胸術後の女性の自殺率が有意に上昇しているそうなのです。豊胸術を受ける女性は以前から精神的な悩みを抱えており、それが自殺と関係があるのではないかと、この論文では述べられています。
これは日本のデータではありませんが、今後日本における自殺を考える際の参考になるかもしれません。
次に自殺率の国際比較をみてみましょう。
日本の自殺率は世界第10位です。しかし、1位から9位は旧ソ連や東欧の国ばかりで、いわゆる先進国のなかでは日本は第1位です。
世界全体に目を向けてみると、明らかに自殺率の低いのが南米です。以前どこかで「自殺をしたくなったらブラジルに行け!」という言葉を聞いたことがあります。ブラジルに行けば、自殺を考えていた自分があほらしくなるそうなのです。
また、すべての国でデータが揃っているわけではありませんが、中東諸国も低い国が多いようです。連日のように新聞で報道されているイスラム教徒の「殉死」はどのように解釈すればいいのでしょうか……。
アジア諸国はどうかというと、これはバラバラです。日本以外ではなぜかスリランカの自殺率が高いようです(11位)。また、韓国(24位)、中国(27位)、香港(31位)もまあまあ高いと言えます。台湾はデータがありません。中国では、農村部の女性の自殺率が高いのが特徴で、旧態依然の、女性を大切にしない風潮が原因なのかもしれません。
一方、タイ(71位)とフィリピン(83位)では、南米と同様に極めて自殺率が低いと言えます。タイは人口10万人あたりの自殺者数が4.0人で日本の6分の1以下です。
私はフィリピンには行ったことがありませんが、タイには何度も訪問しています。親密な付き合いをしているタイ人も何人かおり、ある程度タイの文化に触れていると言えるかもしれません。
世界第10位、先進国のなかでは第1位にランキングされ、一応は仏教徒である日本人に対して、同じアジア人であり、仏教徒であるタイ人は世界的にみて自殺率が極めて少ないのはなぜなのでしょうか。
私は、これに対して一応の仮説を持っています。次回はその仮説について述べてみたいと思います。
つづく
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第26回(2005年10月) 後医は名医?!
「後医は名医」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
これは、我々医師がよく使う「ことわざ」のような言葉で、「同じ患者さんを診るなら、後から診た方が名医になれる」というものです。
例えば、ある患者さんがA診療所を受診したとしましょう。その患者さんはその診療所で診察を受け、薬を処方されたのにもかかわらず、一向にその病気は治りそうにありません。
そこで、この患者さんは次にB診療所を受診したとします。患者さんは、A診療所に行って薬を処方してもらったことを話しました。すると、B診療所では別の薬が処方されました。その薬を飲みだすと、一気に症状が消失しました。
ここで、この患者さんはどのような印象を持つでしょうか。
「A診療所はヤブ医者で、B診療所が名医だ」と思われるのではないでしょうか。
しかし、これには”トリック”があります。
まず、ひとつめは、この患者さんの症状は、薬に関係なく、自然に治った可能性があります。つまり、A診療所の処方もB診療所の処方も特に効いたわけではなく、患者さんの自然治癒力で勝手に治っていたということです。
次に、B診療所では、すでにA診療所で処方された薬が無効であることが分かっているために、次の手をうちやすかった、ということが言えます。疾患にもよりますが、実は患者さんの想像以上に、現在の日本においては、各疾患(症状)に対する治療法が標準化されています。
つまり、この病気では、通常は最初にA診療所で処方された薬剤が標準的で、その薬剤で効果がなかったときに初めてB診療所で処方された薬剤を使用する、ということがある程度確立されているわけです。
さらに、この患者さんがB診療所を受診したときに、A診療所を受診したときには見られなかった症状が出現していた、という可能性もあります。つまり、最初、この患者さんがA診療所を受診したときには、熱だけしかなかったけれど、B診療所を受診したときには、熱プラス特有の皮疹が出現しており、そこから、B診療所では適切な診断がつけられた、ということがあるのです。
このように、後から診察する医師の方が、その疾患を適切に診断するのに有利になることはよくありますす。
患者さんのなかには、最初近くの診療所を受診したけれどなかなか治らないため大きな病院に行きそこでの治療を受けた結果よくなった、という経験をする人がいますが、こういう経験のある人に言わせると、「やっぱり診療所よりも大病院の方が信頼できる」、となるわけです。
例をあげて説明しましょう。
川崎病と呼ばれる小児の病気があります。この病気は現在でも原因不明なのですが、発症すると入院治療を余儀なくされ、完治するまでに時間がかかることもある、場合によっては難儀な病気です。
川崎病は、最初熱が出て、そのうちに全身のリンパ節が腫れだしたり、目が充血したり、舌が真っ赤に腫れあがったり、全身のいろんなところにいろんなタイプの皮疹が出現したり、と様々な症状が出現するのが特徴です。
最初に熱が出たときに、「この熱は川崎病によるものです」と断言できる医師など世界中にひとりもいません。なぜなら、川崎病という病気は、いろんな症状が出現してから初めて診断がつけられる病気だからです。
通常、子供が高熱を出せば、ウイルスや細菌による急性感染症を疑います。かなりの高熱が出現していれば、細菌感染を疑い抗菌薬を処方することになります。ところが、川崎病では抗菌薬がまったく効きません。
心配したこの子供のお母さんは、この診療所では治らないのではないか、と考えて大きな病院を受診することになります。
そして、その頃には熱が出てから数日たっていることもあり、皮疹や充血などが出現しているのです。この患者さんをみた大病院の医師は、川崎病を疑い、すぐに入院させて点滴治療をおこないます。
すると、お母さんとしては、「さすが大病院。すぐに病名を言ってくれたし、入院、点滴と適切な対応をしてくれた。それに比べて最初に行った診療所では、病名も分からないし、出した薬は効かないし、もう二度と行きたくない」、となるのです。
私が、ある病院の小児科にいた頃、こういうケースが多々ありました。
しかしながら、もちろんこのお母さんの感じていることは必ずしも正しいわけではありません。
最初にみた診療所の医師も、子供をみる以上は、常に川崎病のことも念頭に置いています。しかし、川崎病に比べて、高熱が主症状の風邪の方が圧倒的に頻度が高く、熱の患者さんすべてに、川崎病の話をするのは適切ではありません。かえって余計な不安を与えることにもなりかねません。
診療所の医師としては、「まずは普通の細菌感染と判断し抗菌薬を飲んでもらおう。それでも効かないときは薬を変更するとか、あるいは他の症状が出現したら、(川崎病も含めて)他の疾患を鑑別しよう」、と考えているのです。
ところで、我々医師のルールのひとつに「前医を批判しない」というものがあります。これは、医師はお互いに尊敬し学びあうべき、という倫理的な観点から生まれたルールでありますが、実際的には「後医は名医」となってしまうことが頻繁にあることを知っているからです。
そもそも、最初の現場にいない人間が、あとからとやかく言うのはアンフェアであるわけで、たとえ結果として、最初の診断が間違っていたとしても、そのときのその状況ではそう診断せざるを得なかった可能性もあるからです。
ですから、安易に前医を批判する医師を私は信用できません。
先日、あるテレビプログラム(民放)を見ていると、医師が登場して、ゲスト出演者の質問に答えていました。そのゲスト出演者は、ある症状である病院に行って治療を受けたけど治らなかった、ということを話しました。すると、その医師は、「その医師の診断が間違っているのです。病院選びは正しくおこないましょう。私なら誤診はしません」というようなことを言っていました。
これほど、傲慢な医師もいないでしょう。普通なら、そのときはそのように診断した根拠があったはずだ、と考えます。もちろん、最初の診断が間違ったために、とりかえしのつかないことになった、というような事態になれば問題ですが、通常、医師というのは、病態の重症化や急変の可能性のことも考えて、診察をおこないます。
おそらく、その診察医も、まずはこの治療をおこなって、それで効果がなければ次に進もう、と考えていたはずです。それをきちんと患者さん(このゲスト出演者)に伝えていなかったところに非はあるかもしれませんが、それにしても、「前医の診察が間違っている」と断定するのは問題です。
こういった発言をする医者のせいで、医療不信が加速されているのではないか、と私は考えています。このテレビを見ていた人の多くは、「そうか、医師の診断力はバラバラだから、いい病院を受診しなくてはならないんだな」というふうに感じるでしょう。
けれども、そうではなくて、この出演医師のような、「前医を安易に批判するような医師」の方がよほど問題があるわけです。
モノを売る人のセールストークがライバル会社の悪口中心であれば、イヤな気持ちにならないでしょうか。それと同じで、同僚を安易に批判することによって、自分の価値を高めようとする医師は決して名医ではないのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
25 日本の医師はこれだけ不足している!! 2005/10/15
2005年9月22日、財団法人社会経済生産性本部が、「国民の豊かさの国際比較」を発表しました。発表によりますと、日本は、経済協力開発機構(OECD)加盟30カ国中、総合で第10位にランクされたそうです。2004年には総合第14位だったために、4ランク上昇したと喜びの声がある一方で、詳細を見渡すと決して楽観はできないという慎重論があるようです。
この国際比較の項目のなかには、健康指標というものも含まれており、健康指標だけでは第8位です。ここでは健康指標に含まれる項目を少し詳しくみていきたいと思います。
まず、平均寿命の長さでは第1位、人口当たりの病院ベッド数は(多い順に)第2位、乳児死亡率(少ない順に)第3位、人口あたりの死亡者数(少ない順に)第9位、国民ひとりあたり健康支出(多い順に)第17位、国民ひとりあたり公的健康支出(多い順に)第14位です。そして、人口あたりの看護師数は(多い順に)第19位、人口あたりの医師数は(多い順に)、なんと30カ国中、27位です。
平均寿命やベッド数が世界のトップに位置していながら、医師数が下から4番目の低さであるというのは、つまるところ、ひとりの医師がたくさんの患者さんをみていて、なおかつ質の高い医療を供給しているということになります。今回の社会経済生産性本部の発表では、医師の平均勤務時間は発表されていませんが、もしもこういう統計がとられたなら、日本の医師の勤務時間の異常なほどの長さが浮き彫りになったに違いありません。(先日の国勢調査では、1週間の勤務時間を書く欄がありましたが、私は117時間でした。)
日本の医師数が少なすぎるというのは、こういった統計をみても明らかです。
しかしながら、日本の厚生労働省は1990年代後半あたりから、医師数を抑制すべきであるという主張をし続けてきました。具体的には、2020年を目途に医学部の定員を10%削減するという目標を掲げていました。実際、私が医学部在学中の頃から、○○大学医学部は何年後かになくなる、とか、△△大学医学部と××大学医学部は近いうちに統合される、などという噂がとびかっていました。
私は、自分の本のなかでも繰り返し主張していますが、医師数が多すぎるということは絶対にありません。こんなこと、自分の身の周りをみれば明らかです。患者サイドから考えてみても、大病院はもちろん、診療所を受診しても、長時間待たされたあげくに、数分間の診察というのは珍しくありませんし、医師サイドからみても勤務時間が長すぎるのは明らかです。
では、こういう現実がありながら、なぜ厚生労働省は医師を抑制すべきだという主張を続けてきたかというと、それは、少子化と高齢化社会、人口減少から、徴収できる税金と保険料は頭打ちになり、それでは、医師の給与の現状維持ができないからに他なりません。
厚生省と同様、医師数抑制を主張し続けてきた日本医師会によれば、「医師が過剰になれば、粗製乱造で医療の質の低下を招くとともに、医師の失業につながりかねない」、そうです(asahi.com 2005年3月12日)。
果たして本当にそうでしょうか。本当に医師が過剰、というか、他の先進国並みになれば、医療の質の低下を招くのでしょうか。
少なくとも、睡眠不足から判断力の低下をきたすことはなくなるでしょう。最近発表されたアメリカの論文によりますと、睡眠不足の医師はアルコールを飲んでいるのと同程度に判断力が鈍るというデータがあります。
また、医師が増えれば、医師ひとりあたりが診る患者さんの数が少なくなり、患者さんひとりひとりにじっくりと取り組めることになります。現状では、入院患者さんのところに行くのが1日に一度だけであったり、また外来では、積み上げられたカルテを横目で見ながら、目の前の患者さんを早く終了させることを考えなければならないということが日常茶飯事なのです。このような診察をして、病院の経営者は喜ぶかもしれませんが、我々医師にとっても、患者さんにとっても、お互いあるべき姿ではないのです。
もうひとつ日本医師会が主張している「医師の失業」という問題についても、いったん医師になれば失業はない、という現状の方がよほど問題があるわけで、医師免許をいったん取得すればそれで安泰などと考えている医師がいるとすれば、このことこそが、日本の医療のレベルを低下させることになるのではないでしょうか。
厚生労働省の「医師数を抑制する」という主張は、どこからどう考えても納得のいかないものです。
しかしながら、最近になって、ようやく厚生労働省も現実を見始めたようです。新研修医制度の導入とともに、大学の医局には新しい医師が二年間は入局できなくなり、このため多くの医局で人手不足が深刻化しました。特に痛手を被っているのが、産婦人科と小児科で、この2つの科は従来から相対的に人が足らなかったところに、新研修医制度が導入され、結果として関連病院から医局員を引き上げることになり、その結果、その関連病院では産婦人科や小児科をやめざるをえなくなったのです。
産婦人科については、この傾向が特に顕著で、昨今の医事紛争の増加も重なり、総合病院で産婦人科を標榜するところが全国的に激減してきています。例えば、関西のある中堅都市(人口約27万人)では、ついに出産のできる総合病院がなくなってしまいました。その市では産科を標榜している個人病院が3つだけになり、この市で出産しようと思えばその3つの個人病院に行くしかないのです。これではとうていベッドが足りませんし、例えば喘息や高血圧などを持っている、本来高度医療のおこなえる総合病院で出産すべき妊婦さんはその市では出産することができないのです。
小児科不足も深刻です。例えば、関西のある総合病院は夜間に小児科の救急外来をおこなっていますが、その地域には、他に夜間に子供をみる病院がないために、多い日では一晩に100人もの患者さんを診なければならないのです。ひとりの小児科医が一晩で100人です。もちろんその小児科医は翌日の朝から通常業務が待っています。この状態で、一晩に100人の患者さんを、的確な判断力をもって、まったくミスをすることなく診察し続けることができるでしょうか。
産婦人科、小児科以外に深刻なのが麻酔科です。麻酔科医が不足しているために、本来麻酔科医が麻酔をすべき症例に対し、外科医が執刀をしながら麻酔をかけるということが、日本の医療現場ではごく普通におこなわれています。
他の領域においても、地方に行けば医師不足は深刻です。医師が不足し、存続が危うい病院は少なくありませんし、どこの病院にいっても、数少ない医師が多くの患者さんを診なければならないわけですから、当然医療の質は低下します。
厚生省は最近になって、ようやく「医師数抑制」の方針を見直すようになりましたが、医学部の定員を増やすという議論にはなっていないようです。
私は自分の本で主張しているように、医師の数は現在の倍くらいにすべきだと考えています。そうすれば医師側にとっても患者側にとっても、今よりははるかに満足度の高い治療ができるに違いありません。
こういうことを言うと、では財源はどうするのか、という反論が必ずでてきますが、その答えは簡単なことです。
医師の数を倍にする代わりに、医師の給与を半分にすればいいのです。よく、「医師が儲けているというのは幻想であって、実際は一部の開業医を除けば、特に勤務医などは安い給与でこきつかわれている」などという人がいますが、これは間違いです。
先日も、あるテレビ番組で、医師(勤務医)が登場し、「私の給与は1000万円しかないんですよ」と言っていましたが、1000万円を少ないと思っていること自体が異常です。
ちなみに、民間企業に勤める人が2004年一年間に受けとった一人あたりの平均給与は439万円です(日本経済新聞2005年9月29日)。この医師は、世間の人々がどれくらいの給与を貰っているのか知っているのでしょうか。知っていれば、こんな無神経な発言はできるはずがありません。医師の給与は、その439万円の中から徴収される税金と保険料でまかなわれているのです。こういう発言をする医師がいる限り、医師は世間知らずと言われても仕方がないでしょう。医師は新聞すら読んでいないということなのですから。
もっとも、医師不足のために勤務時間が長くなりすぎ、新聞を読む時間すらない、ということなのかもしれませんが・・・・。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 2026年2月28日 樹木は心血管疾患を防ぎ、草や花はリスクを上げる
- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン
- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?
- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる
- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性
- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
月別アーカイブ
- 2026年2月 (5)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (5)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (9)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (4)
- 2024年2月 (5)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (4)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (4)
- 2023年9月 (4)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (5)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (4)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (4)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (4)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (4)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (4)
- 2020年12月 (5)
- 2020年11月 (5)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (4)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (4)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (4)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (4)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (5)
- 2018年5月 (7)
- 2018年4月 (6)
- 2018年3月 (7)
- 2018年2月 (8)
- 2018年1月 (6)
- 2017年12月 (5)
- 2017年11月 (5)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (7)
- 2017年8月 (7)
- 2017年7月 (7)
- 2017年6月 (7)
- 2017年5月 (7)
- 2017年4月 (7)
- 2017年3月 (7)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (8)
- 2016年12月 (7)
- 2016年11月 (8)
- 2016年10月 (6)
- 2016年9月 (8)
- 2016年8月 (6)
- 2016年7月 (7)
- 2016年6月 (7)
- 2016年5月 (7)
- 2016年4月 (7)
- 2016年3月 (8)
- 2016年2月 (6)
- 2016年1月 (8)
- 2015年12月 (7)
- 2015年11月 (7)
- 2015年10月 (7)
- 2015年9月 (7)
- 2015年8月 (7)
- 2015年7月 (7)
- 2015年6月 (7)
- 2015年5月 (7)
- 2015年4月 (7)
- 2015年3月 (7)
- 2015年2月 (7)
- 2015年1月 (7)
- 2014年12月 (8)
- 2014年11月 (7)
- 2014年10月 (7)
- 2014年9月 (8)
- 2014年8月 (7)
- 2014年7月 (7)
- 2014年6月 (7)
- 2014年5月 (7)
- 2014年4月 (7)
- 2014年3月 (7)
- 2014年2月 (7)
- 2014年1月 (7)
- 2013年12月 (7)
- 2013年11月 (7)
- 2013年10月 (7)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (175)
- 2013年7月 (411)
- 2013年6月 (431)