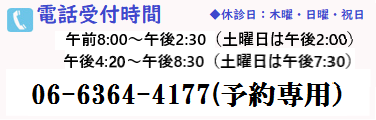はやりの病気
2016年7月22日 金曜日
第155回(2016年7月) 黄熱~世界一恐ろしい生物と予期せぬアウトブレイク~
今年(2016年)最も注目されている感染症のひとつがジカウイルス(ジカ熱)です。2015年後半からブラジルを中心に流行が始まり、妊婦さんが感染すると小頭症の赤ちゃんが生まれてくることや、生涯にわたり神経症状に苦しめられることもあるギランバレー症候群のリスクが知られるようになりました。さらにその後、性感染がけっこうな頻度で生じることがわかり、厚生労働省も、流行地域から帰国後、症状の有無にかかわらず最低8週間は性感染のリスクがあると発表しています。
オリンピックが間もなく開催されようとしているブラジルでジカウイルスが流行しているのはなんとも皮肉な話です。ジカウイルスは蚊に刺されることによって感染します。以前取り上げたように蚊とは「世界一恐ろしい生物」なのです(注1)。
世界一恐ろしい生物である蚊は「単独」でヒトを殺せるわけではありません。口から他の病原体をヒトに「注入」し、体内に侵入した別の病原体がヒトを殺すわけです。この病原体で最も多くのヒトを殺しているのがマラリアです。マラリアは世界三大感染症のひとつです。(他のふたつは結核とHIVです)
蚊が媒介するヒトを殺す感染症でマラリアの次に多いのはおそらく黄熱です。マラリアも含めて蚊が媒介する感染症というのは、アジア、アフリカ、南米などに多く、こういった地域の多くは公衆衛生学がそれほど発達しておらず、そのため正確な感染者数や死亡者数を知ることは困難です。それでもいくつかの発表をみてみると、死亡者最多はマラリアの50万人以上でこれはダントツの1位です。次いで多いのが黄熱で、WHOの発表では29,000~60,000人(注2)。日本脳炎(注3)とデング熱(注4)は共に2万数千人程度、チクングニア熱とウエストナイル熱が共に数百人程度、リフトバレー熱はほぼゼロ、小頭症やギランバレー症候群は恐怖ですがジカウイルスも死亡者についてはほぼゼロです。フィラリアという生涯に渡り苦しめられる感染症があり、これは蚊が媒介する感染症ではとてもやっかいなものですがフィラリア自体で死亡することはあまりありません。
つまり、マラリアを除けば、蚊で死ぬかもしれない感染症では「黄熱」が最も多いということになります。マラリア対策にはWHOを始め多くの団体が支援を打ち出していることが知られていますが、実は黄熱への対策も今世紀に入ってから積極的におこなわれています。
「黄熱イニシアチブ(Yellow Fever Initiative)」と命名されたWHOのプロジェクトが2006年に立ち上がりました。これは、黄熱が最も問題となっている西アフリカのいくつかの国で合計1億人以上にワクチン接種をおこなうという計画です。黄熱には治療薬がありません。また蚊(ネッタイシマカ)を全滅させることは事実上不可能です。であるならば、大きく感染者を減らすにはワクチンが最適ということになります。実際、このプロジェクトが功を奏し、WHOの発表によれば2015年の西アフリカでの黄熱のアウトブレイクは「ゼロ」となったのです。「黄熱イニシアチブ」は成功した。この調子なら黄熱は完全に撲滅することも不可能ではない・・。おそらく多くの人はそう思ったのではないでしょうか。
ところが、WHOがアウトブレイク「ゼロ」と発表した数か月後、事態は誰もが予期しなかった方向に向かいます。2015年12月頃からアフリカ南西部のアンゴラで黄熱感染者の報告が少しずつ増えだし、2016年3月までに335人が感染、うち159人が死亡したのです。これを受けて、WHOが正式に「アウトブレイク」を表明しました(注5)。アンゴラでの黄熱のアウトブレイクは1988年以来、28年ぶりです(注6)。1988年には感染者が37人、死亡者が14人でしたから、2016年の規模は10倍以上ということになります。
アンゴラのアウトブレイクはさらに広がることになります。中国人の感染者が相次いで報告されたのです。2016年3月には6人、4月には4人のアンゴラから帰国した中国人が黄熱を発症しました。
ここで黄熱とはどのような感染症なのかをまとめておきましょう。媒介する蚊はネッタイシマカで、アジア、アフリカ、中南米に多く生息しています。日本にも沖縄にはネッタイシマカがいますが、少なくとも記録が残っている太平洋戦争後では国内での黄熱発症者はいません。感染するのはアフリカと中南米だけで、アジアでは感染しないとされています。
感染すると3-6日の潜伏期間を経た後、発熱、筋肉痛、頭痛、嘔吐などの症状が出現します。しかし、多くの人はまったく症状がでず感染に気付かずに治癒します。症状は3-4日程度で消失しますが、なかには第二期に入る場合もあります。第二期に入れば再び高熱が生じ、肝臓や腎臓が障害を受けます。肝臓が急激にやられるために黄疸が出現し、このため身体は黄色くなります。これがこの病気の名前「黄熱」の由来です。尿は黒くなり、腹痛・嘔吐に苦しみます。出血が口、鼻、目、胃などから生じ、ここまでくれば半数の人は7-10日後に死に至ります(注7)。
いったん発症すると黄熱ウイルスに効く薬はありませんから、解熱鎮痛剤程度くらいしか使える薬はありません。しかし、黄熱には優れたワクチンがあり、WHOによればワクチン接種者の99%が30日以内に効果がでます(注8)。しかも比較的安全で安いワクチンですから、世界中でワクチンを一斉にうつことができれば黄熱はほぼ消失する可能性があります。
ただし、アフリカや中南米に渡航しない人には必要ありませんし、アフリカ・中南米のすべての国と地域が高リスクとはいえないですし、そもそも安価とはいえ、ワクチンには限りがあります。そこでWHOは「黄熱イニシアチブ」でアウトブレイクを繰り返している西アフリカをターゲットにしたのです。しかし、西アフリカでは成功したものの、アンゴラで28年ぶりの予期せぬアウトブレイクが起こってしまったというわけです。
黄熱ウイルスはヒト→ヒトへの感染はありませんが、ヒト→蚊→ヒトであれば感染します。ですから、黄熱が発生する国としては、黄熱ウイルスを持っているかもしれない外国人の入国を拒否したくなります。それで、いくつかの国では黄熱ワクチンを接種したことを証明するカード(これを「イエローカード」と呼びます)を持参することを義務づけています。
ここで注意しなければならないのは、出国した国によって求められる場合があるということです。例えば、日本からロンドンやシンガポールを経由して南アフリカ共和国に入国する場合はイエローカードを求められません。しかし、ブラジルに滞在した後で同国に入る場合は求められるのです。そして、このような国はたくさんあります。つまり、無条件でイエローカードを求められる国と、どこの国から入国するかによって求められる国があるということです。しかも、このルールは頻繁に変わるために、アフリカ・中南米に渡航する人は最新の情報に注意しなければなりません(注9)。
しかし、黄熱ワクチンは一度接種すれば生涯有効で、イエローカードは一度発行されれば生涯使えます。実は、つい最近まで、イエローカードの有効期間は10年間とされていたのですが、2016年7月11日から、これまでに発行されたものも含めて、生涯有効とされました。ですから、今は予定がなくても、将来中南米やアフリカに渡航することを考えている人はワクチン接種を検討するのがいいでしょう。(ただし、黄熱ワクチンを接種できる機関は限られています(注10))
日本で流行する可能性は極めて低いと思われますが、中国でもそのように言われていたわけですから、やはり流行国を渡航する場合には注意が必要でしょう。
************
注1:下記コラムを参照ください。
メディカルエッセイ第149回(2015年6月)「世界で最も恐ろしい生物とは?」
注2:WHOの該当ページ(下記URL)を参照ください。
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/
注3:厚生労働省検疫所の該当ページ(下記URL)を参照ください。
http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2014/03181434.html
注4:エーザイの該当ページ(下記URL)を参照ください。
http://atm.eisai.co.jp/ntd/dengue.html
注5:アンゴラでのアウトブレイクについてはWHOの報道(下記URL)を参照ください。
http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-angola/en/
注6:WHOの該当ページ(下記URL)を参照ください。
http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/mediacentre/qa/en/
注7:このあたりの記述はWHOの該当ページに基づいています。
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/
厚生労働省の黄熱のパージは下記URLを参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124615.html
注8:黄熱ワクチンを開発したのは、南アフリカ出身で米国の微生物学者マックス・タイラー(Max Theiler)で、1951年のノーベル医学生理学賞を受賞しています。ちなみに、野口英世はいち早く黄熱の対策に取り組んでいて、病原体を発見したと発表しましたが、後に誤りであることが分かりました。野口英世の時代には光学顕微鏡では観察できないウイルスの存在がまだはっきりとわかっていなかったのです。野口英世は黄熱で他界しています。
注9:いろんなサイトで、いろんな情報が公開されていますが、まず間違いなく確実にアップデイトされており最も正確なのはWHOの下記ページだと思われます。ただし、実際に渡航されるときにはその国の領事館に確認するのがいいでしょう。
http://www.who.int/ith/2015-ith-county-list.pdf?ua=1
注10:厚労省検疫所の下記ページを参照ください。
投稿者 | 記事URL
2016年6月20日 月曜日
第154回(2016年6月) 誰が薬剤耐性菌を生みだしたか
薬剤耐性菌という言葉、誰もが聞いたことがあり、言葉の意味も、なぜ薬剤耐性菌が生じるかについてもほとんどの人が知っています。我々医療現場にいる者からすると、この薬剤耐性菌というものに対する恐怖は並大抵のものではないのですが、マスコミも一般の人たちも、そして(腹立たしいことに)行政も今ひとつその危機感を持っていないように思えてなりません。
今回は、薬剤耐性菌の問題に対してきちんとした対策をとっていない人たち、主に行政を批判するコラムになります。批判の前に、現在の薬剤耐性菌についてまとめておきます。
抗菌薬を多用しすぎると、遺伝子に変異をおこしその抗菌薬で死なない細菌だけが生き残るようになり、これを「薬剤耐性菌」と呼びます。薬剤耐性菌が出現すると、今度はその耐性菌を退治できる抗菌薬の開発がおこなわれることになります。するとその新しい薬に対して耐性を獲得した菌が出現し、再び新しい薬剤が・・・、とイタチごっこのような「細菌vs人類」の対決が繰り広げられているわけです。
で、現在の”戦況”はどうかというと、人類に分が悪いというか、耐性菌の恐怖は次第に大きくなってきています。例えば、米国CDC(疾病管理局)は2014年に「CRITICAL – 2014 Year in Review」というタイトルの発表をおこない、そこで「新しい4つの感染症」を驚異として取り上げています(注1)。その4つのうち1つが薬剤耐性菌です。(あとの3つは、エボラ出血熱ウイルス、エンテロウイルスD68(注2)、MERSウイルスです)
実際にアメリカでは薬剤耐性菌の被害が深刻で、最近よく取り上げられるのが通称CREと呼ばれるカルバペネム耐性菌(正確には「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌」)です。カルバペネムという名の従来は「最後の切り札」として使われていた抗菌薬が効かない菌のことで、特定の菌種を指すのではなく、カルバペネムが効かない菌を総称して呼びます。
カルバペネム耐性菌に対して唯一有効なコリスチン(注3)という薬があるのですが、細菌vs人類の歴史は細菌側に有利な展開となります。2015年11月、コルヒチンが効かない細菌が中国の養豚場で見つかったのです。そして2016年5月、米国でコリスチンが効かないカルバペネム耐性菌に罹患した患者がみつかりました。この患者は49歳の女性で、尿路感染症がなかなか治らず、やむを得ずコリスチンが使われたものの効かなかったと報じられています。(その後この女性がどのようにして治療されたのか、現在も感染症が治癒せず続いているのかどうかについては報道がなく不明)
日本でもカルバペネム耐性菌は深刻な問題ですがそれ以外にもあります。ここ数年でよく取り上げられる薬剤耐性菌に「ESBL産生菌」と呼ばれる細菌(正確には「基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生菌」)があります。2016年6月16日の日経新聞によりますと、これまでに少なくとも66人の子供(うち9人は生後3日以内)がこの細菌による敗血症を発症し、うち2人が死亡しているそうです。ESBL産生菌は現在のところ先に述べたカルバペネム系が有効とされていますが、すべての患者に使えるわけではありません。
他には通称「KPC」と呼ばれる「カルバペネム耐性クレブシエラ」、ニューデリーで最初に発見されたことから命名されたNDM-1あたりが注目されています。NDM-1については過去のコラム(注4)で紹介したこともあります。
2016年5月26~27日に開催された伊勢志摩サミットで、薬剤耐性菌に対して世界各国で協調して取り組んでいくことが首脳宣言に盛り込まれました。評価されるべきなのは「畜産業で成長促進のために抗菌剤を使用することを段階的に廃止する」(注5)という合意が得られたことです。先に述べたコリスチン耐性の報告があった中国でも発見されたのは養豚場で、つまり家畜のエサに大量に抗菌薬が入れられていることが原因です。家畜に対する抗菌薬の使用については米国もおそらく中国とそう変わらないはずです。あまりマスコミは取り上げませんが、オバマ大統領が米国での畜産業から抗菌薬を廃止することに同意したのは画期的なことです。
伊勢志摩サミットで検討された薬剤耐性菌対策は、基本的には2015年の(ドイツの)エルマウサミットでの決定事項の流れを汲んだものです。ただエルマウサミットでは「抗生物質の適正使用を促進し」という表現にとどまっており具体性がありあません。そこで、日本政府は、伊勢志摩サミットの開催に先駆けて、2016年4月1日の閣議で「抗菌薬の使用量を2020年までに現状の3分の2に減らす」とする行動計画案を発表しました。マスコミの報道によれば、「医療機関向けに抗菌薬使用の指針などをつくる」としているそうです。
それから約2ヶ月が経過しましたが、医療機関向けの政府のこのような指針の発表はありません。私は新聞報道でこの政府の発表を聞いたとき、「医療機関への指針の前にすることがあるだろう」と感じました。
日本政府がまずすべきなのはアジア諸国に対する注意勧告です。タイやインドでは屋台で抗菌薬が売られている光景を目にすることがあります(本物かどうか疑わしいのもありますが・・・)。また、医師の処方箋がなくても薬局で抗菌薬が誰でも買える国は多数あります。例えばフィリピンの薬局では「ペニシリン1錠ください」と言えば、実際に1錠だけ買うこともできます。このような使用はもちろん「完全な誤り」であり、医師は抗菌薬を処方するときに量を適当に決めているわけではありません。ときには3日分、ときには7日分となるのは菌の種類と重症度、その患者さんの免疫能などを考えて総合的に判断しているからです。先に述べたNDM-1は、インドでは不適切な抗菌薬の使用が横行していることが原因で生まれたと言われています。日本政府がまずおこなうべきなのはアジア諸国への注意勧告に他なりません。
次に自国に目を向けてみましょう。私が日ごろ感じている日本での抗菌薬に関する最大の問題は「個人輸入」です。薬物の個人輸入は麻薬や覚せい剤でない限りは合法だそうですが、私は抗菌薬を禁止にすべきと考えています。いくつかある薬剤の個人輸入代行のホームページをみてみると、多くの抗菌薬がごく簡単に買えることが分かります。しかも、よほどの重症例でない限り処方しないような貴重な抗菌薬までもがクリック1つで購入できるのです。
例えば、ニューキノロン系の抗菌薬というのは重症例にしか処方すべきでないもので、そのニューキノロン系のなかでも極めて強力なグレースビットやアベロックスといった薬剤が必要な症例というのはごくわずかです。太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)の例でいえば、こういった強力なニューキノロンを処方するのは年に一度あるかないかです。それくらい重症例にしか使うべきでない抗菌薬がネット上で誰でも簡単に買えるのです。以前、谷口医院を初めて受診した患者さんから「ネットで買った抗菌薬が効かないんです」と言われたことがありました。このような言葉を聞くと絶望的な気持ちになります。私個人としては、「抗菌薬取締法」を制定し、抗菌薬は麻薬と同じように医師でないと処方できないようにするべきと考えています。
医療機関で抗菌薬を処方しすぎている、という声があります。この声は正しいのでしょうか。医師は、必要な症例に必要な日数分しか抗菌薬を処方していません。そして、なぜ抗菌薬が必要なのかを可能な限り説明しています。例えば風邪症状で受診した場合、喀痰や咽頭スワブ(喉を綿棒でぬぐったもの)を用いて、グラム染色をおこない、細菌感染の像が顕微鏡で観察されたから抗菌薬が必要といった説明をするわけです(注6)。グラム染色で細菌感染が疑えなければ抗菌薬は処方しませんし、ときには一切の薬を処方しないことも谷口医院ではよくあります。
ほとんどの医師は(グラム染色をおこなうかどうかは別にして)処方するときには患者さんに抗菌薬が必要な理由を話しているはずです。しかし、全員がかと問われるとそうでない可能性もあります。というのは、谷口医院を受診する人で、「前の病院では”とりあえず”抗生物質を飲むように言われた」と言う人がいるからです。抗菌薬は”とりあえず”飲むものではありません。喉が痛い、熱がある、といった理由だけで抗菌薬を飲んではいけません。飲むことによって余計に悪くなることだってあるのです(注7)。
こういうケースでは、実際には前の病院の医師も”とりあえず”などという言葉を使わずきちんと説明していることも多いと思うのですが、なかには、このケースは前の医療機関で説明不足かもしれない・・、と私自身が感じることがあるのも事実です。
しかしながら、抗菌薬の過剰使用の問題を世界全体でみたときに、日本の医師の過剰使用はあったとしてもごくわずかだと思います。まずはアジア諸国の無秩序で無法状態の抗菌薬の氾濫を食い止める政策をおこなうこと、次いで個人輸入での抗菌薬の購入を禁止することが重要です。最後に、個人レベルでおこなえる抗菌薬対策を挙げておきます。
・抗菌薬は必ず医師に処方してもらう(個人輸入はおこなわない!)
・処方された抗菌薬は大きな副作用が出ない限りは最後まで飲み切る。(ときどき、「自宅にあった抗菌薬を飲みました」、という人がいますが、抗菌薬が自宅にあること自体がおかしいのです)
・診察時に「抗菌薬が必要か」を尋ねるのはOK。「抗菌薬をください」はNG。(ときどき「お金を払うって言ってるでしょ!」と怒り出す人がいますが、抗菌薬の処方はそういう問題ではありません)
・抗菌薬を処方してもらうときは必要な理由を尋ねる。(抗菌薬を過剰に処方している医師が本当にいるなら、患者さんが毎回尋ねるようにすれば解決するでしょう)
注1:CDCのこの報告は下記URLを参照ください。
http://www.cdc.gov/media/dpk/2014/dpk-eoy.html
注2: エンテロウイルスD68の脅威については下記を参照ください。
はやりの病気第150回(2016年2月) エンテロウイルスの脅威
注3:カルバペネム耐性菌にも有効なコリスチンという抗菌薬は日本人が1950年代に開発しました。そんな優れた抗菌薬が、しかも日本人が開発したものがなぜこれまではそれほど使われていなかったかというと、副作用の頻度が高くまた重篤化することもあること、そして開発された当時はもっと安全で有効なものがあったことが理由です。尚、コリスチンの耐性菌は最近日本でも報告されました。
注4:はやりの病気第85回(2010年9月号)「NDM-1とアシネトバクター」
注5:外務省の下記ページを参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160313.pdf
注6:これについては、毎日新聞ウェブサイト版「医療プレミア」にコラムを書いたことがあります。
実践!感染症講義 -命を救う5分の知識-「その風邪、細菌性? それともウイルス性?」
注7:例えば、伝染性単核球症(キス病)に抗菌薬を使えば大変なことになります。詳しくは下記を参照ください。
投稿者 | 記事URL
2016年5月23日 月曜日
第153回(2016年5月) それほど単純でない高尿酸血症
太融寺町谷口医院(以下、谷口医院)の患者さんは働く世代の比較的若い患者さんが多いため、初診・再診にかかわらず「職場の健康診断で異状を指摘されたので来ました」と言って受診される人が大勢います。きちんと統計をとったわけではありませんが、よくある異状、すなわち、肝機能障害、高血圧、高脂血症(コレステロール、中性脂肪)、高血糖などのなかで、おそらく最も頻度が多いのが「尿酸値が高い」、すなわち高尿酸血症です。
高尿酸血症とは一般に血清尿酸値が7.0mg/dLを超えた状態を指します。7.0mg/dLを少し超える程度であれば、多くの人は無症状ですが、健診を実施する側(会社)としては、健診を受け異状がみつかった従業員に何もしないわけにはいきませんから、「かかりつけ医に相談してください。かかりつけ医がない場合はみつけてください」と助言することになるわけです。(大企業などで産業医が常在している場合は、産業医を受診することになります)
尿酸値が高いとなぜいけないのか。その理由はいくつもあるのですが、最も有名なのは「痛風」でしょう。文字通り、風が当たっても痛いとされる痛風発作は強烈であり、深夜に救急車を呼ぶ人も少なくない「のたうち回るほどの痛み」となります。痛み止めがなければ日常生活もままなりません。あんな痛い思いをするならしっかりと薬を飲みます、と一度でも経験のある人は言います。このケースは我々からすると”ラク”です。薬の重要性をそれほど伝えなくても、患者さんの方から薬を求めてくるからです。
では、痛風を起こしたことがなくて、健康診断で初めて高尿酸血症を指摘されたという場合はどうすればいいのでしょうか。谷口医院をかかりつけ医にしている患者さんは「できれば薬を飲みたくない」という人が多く、私自身が「薬は最後の手段です」と言って、簡単には処方しません。実際、「尿酸値が7を超えたので尿酸を下げる薬をください」と言う人はほとんどいません。
一度も痛風を起こしたことがない人の場合、尿酸値が7mg/dLを超えた程度であれば、私自身は原則として薬の処方はおこないません。では、8mg/dLを超えた場合は? 9mg/dLでは、10mg/dLを超えたらさすがに危ないのでは・・・、という疑問が出てきます。医師としては、「あのとき薬を出しておいてくれたらあんな痛い思いをしなくて済んだのに・・・」と患者さんから後から言われることは避けたいものです。
統計学的に血性尿酸値が7.0mg/dLを超えれば痛風を起こしやすくなっていることは分かっています。しかし、これくらいの人は非常に多く、日本人の成人の4人に1人が高尿酸血症と言われることもあります。「いつも7台だけど痛風なんて起こしたことがない」という人は実際に大勢います。ただし、数字が高ければ高いほど痛風を起こしやすいのは事実です。ですから、高尿酸血症を指摘された人、特に9mg/dLを超えた場合は、食生活や生活習慣の改善を早急におこない、再検査をおこなう必要があります。再検査でも目安として9mg/dLを超えるような場合は投薬を検討すべきでしょう。(ガイドライン上は8mg/dL以上で投薬検討とされています) しかし、それほど単純な話ではありません。
痛い、というのは大変分かりやすいですから、高尿酸血症=痛風というのは有名です。しかし高尿酸血症のもたらす弊害はそれだけではありません。高尿酸血症が持続すると、腎臓に障害をもたらし、高血圧や不整脈のリスクにもなりますし、心筋梗塞の危険性が上昇します。心筋梗塞のリスクとしては糖尿病や高脂血症、高血圧、喫煙、大量飲酒、肥満などの方が有名ですが、高尿酸血症もリスクのひとつです。高尿酸血症自体が高血圧のリスクにもなるわけですから、もしも尿酸値が少し高いだけだったとしても、高血圧がある場合は、初期の段階で積極的に薬を使う方がいい場合もあります。
そして、高尿酸血症のある人の多くが、軽度であったとしても、肥満、飲酒、運動不足、喫煙(喫煙は少しでも心筋梗塞の大きなリスクです)、高血圧、高脂血症などを合併しています。もしも、これらが一切なく、尿酸値がわずかに高いという程度であれば、プリン体を含む食品などの注意と水分摂取励行程度で生活指導は終わりで、再検査の説明をするだけです。しかし、多くの場合、他の生活習慣病、あるいはそのリスクがありますから、少々時間をとって現在の問題点を調べていく必要があります。時間をとって話を聞くと、塩分過多、運動不足、飲酒過多などが多くの人にあることが分かります。
つまり、「健診で尿酸値が高いと言われました」という多くのケースにおいて、尿酸値の数字だけをみて済ませるわけにはいかないのです。軽度であっても、他の虚血性心疾患のリスクについても確認して検討することになります。患者さんとしては、「数字がいくらになれば薬を開始すべきか」という質問をしたくなるのは分かりますが、数字だけでは簡単に決めることがないのです。ガイドラインには一応の基準というものがありますが、医師はそのガイドラインを杓子定規的に用いているわけではありません。
薬の選択も簡単ではありません。最近はインターネットなどで得た情報をもとに、「血圧の薬は〇〇〇で、尿酸は△△△を希望します」と”注文”する人もいて驚かされます。たいていは、使用した人の体験談などを読んだという程度で深く考えた上での”注文”ではありません。私の基本的な考えは、「患者さんに病気のことを勉強してもらい知識を増やしてほしい」というものです。ですから、インターネットを使って知識の吸収につとめるのは素晴らしいことだと思います。しかし現実には「体験談」による情報収集が中心の人が多く、偏った考えになってしまっていることが多々あります。
例えば、降圧薬として用いる利尿薬は尿酸値を高めることがあるために使用しにくいのですが、これを知っている人はそれほど多くありません。一方、それを知っていて、尿酸値が高くても使いやすい利尿薬があることまで知っている人がいて驚かされることがあります。しかし、その利尿薬に比較的高頻度で起こる重篤な副作用のことまで考慮してこの薬を「注文」する人となるとほぼ皆無です。「薬の選択はすべて任せてほしい」とまでは言いませんが、初めから「◇◇◇という薬を出してください。他の薬はイヤです」と言われると、治療が上手くいかないケースがあるのです。
話を尿酸に戻します。尿酸値を下げる薬も多数ありますが、歴史の浅い高価な薬を使わなければならないケースはごくわずかで、ほとんどは昔からある安い薬で充分です。1錠10円未満ですから3割負担で3円未満です。太融寺町谷口医院では高尿酸血症の患者さんの98%以上は、この1日3円未満の薬です。副作用は完全にゼロとは言いませんが、かなり安全な薬です。ちなみに、以前、尿酸値を下げる効果のあるサプリメントを飲んでいるという患者さんは1日70円以上と言っていました。しかもほとんど下がっておらず結局、この1錠3円未満の薬に変更しました。すぐに正常値まで下がりました。
ただし、最初の方で述べたようにやはり薬は最後の手段です。尿酸値を下げるには食事と飲酒の見直しが重要です。ネット上などでは反対意見もあるようですが、やはり「プリン体」の摂取を減らすことが不可欠です。ここでは詳しくは述べませんが、節酒は可能な範囲でおこなうべきで、お酒の選択も考えるべきです。プリン体フリーのビールは美味しくないという声は聞きますが、かといって「地ビール」ばかり飲むのは危険です(注1)。
尿酸値を下げたいときに食べ物の選択は簡単ではありません(注2)。一見身体によさそうなものもプリン体を多量に含むものがあるからです。例えば、「ほうれん草のおひたしに鰹節をかけたもの」は身体によさそうですが、高尿酸血症がある人には勧められません。ほうれん草の赤い部分と鰹節がプリン体を高濃度で含むからです。あとは、魚の干物や干し椎茸なども一見身体によさそうですがこれらも高濃度のプリン体を含みます。しかし、こういった和食は糖尿病や中性脂肪が高い人には良いものなのです。そして、先にも述べたように、ややこしいのは、尿酸値が高い人のいくらかは中性脂肪や血糖値も高いのです。じゃあ、いったい何を食べればいいんだ!と言いたくなります。そうなのです。どのようなものを食べるべきなのかというのは思いのほかむつかしいのです。医師や看護師、栄養士と相談して少しずつ食事を見直していかねばなりません。
高尿酸血症を含め生活習慣病を改善させる食事というのは地味な努力が不可欠であり、「これを食べればOK、これさえ食べなければOK」という単純なものではないというわけです。
***************
注1:公益財団法人「通風財団」のウェブサイトで公開されている「アルコール飲料中のプリン体含有量」を参照ください。地ビールがいかに高プリン体かがわかります。
http://www.tufu.or.jp/gout/gout4/73.html
注2:「通風財団」のウェブサイトで公開されている「食品中のプリン体含有量」を参照ください。
http://www.tufu.or.jp/pdf/purine_food.pdf
投稿者 | 記事URL
2016年4月18日 月曜日
第152回(2016年4月) 大腸がん予防の「6つの習慣」とアスピリン
国民の2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで死亡する時代と言われ久しくなります。がんを臓器別にみてみると、2013年のデータでは、男性は罹患者数が最も多いのが大腸がん、2位は胃がん、以下前立腺がん、肺がんと続きます。女性は最多が乳がん、2位は大腸がん、以下肺がん、胃がんです。男女合わせた全体では大腸がんが1位です。前年までは大腸がんは胃がんに次いで2位であり、2013年になって初めて、男性、男女合わせた全体で最多になりました。
胃がんはヘリコバクター・ピロリ菌を除菌することで大部分を予防することができます。乳がんは、定期検診の有効性が認められており、厚労省も40歳以上に勧めています。しかし乳がんの検診というのは早期発見して死亡を防ぐことが目的であり、発症自体を防ぐ予防法は確立していません。(アンジェリーナ・ジョリーのように遺伝的素因がある場合は「発症前の乳房切除」という選択肢もありますがこれは例外でしょう)
大腸がんの場合は、早期発見する方法としては定期的な大腸ファイバー(大腸カメラ)という方法がありますが検査自体が大変です。便潜血反応をみる検査は簡単にできますから40歳以上になればおこなうよう厚労省も推薦しています。しかし、完全に早期発見できるわけではありませんし、発症の「予防」になるわけではありません。
がんについては「早期発見」が重要ですが、できれば発症そのものを防ぎたいものです。AICR(米国がん研究協会、American Institute for Cancer Research)は、2016年3月1日、「6つの習慣を実践することにより大腸がんの半数を減らすことができる」というタイトルの発表をおこないました(注1)。その「6つの習慣」とは以下の通りです。
1. 健康体重を維持し、腹部の脂肪量をコントロールする
腹部の脂肪は、体重にかかわらず(たとえやせていたとしても)大腸がんのリスクになることが判っています。
2. 定期的に運動をおこなう
家の掃除でもランニングでも、日常でおこなえる運動にはさまざまなものがあります。重要なのは「定期的に」です。
3.食物繊維を積極的に摂る
1日あたり食物繊維10グラム(豆であれば1カップ弱)を摂れば、大腸がんのリスクが10%低下します。
4.赤肉の摂取量を減らし、加工肉を避ける
ホットドッグ、ベーコン、ソーセージなどの加工肉を避けます。加工肉による大腸がんのリスクは赤肉の2倍にもなると言われています(これについては後述します)。
5.アルコールを控えめにする
「男性なら1日グラス2杯、女性なら1杯が目安」と書かれていますが、アルコールが何を指しているのかがよく判りません。ただ、別のところに「ワインなら5オンス」と書かれており、これはワイングラス1杯程度です。つまり、男性ならワイングラス2杯(ビールならだいたい中瓶1本、日本酒なら1合程度です)、女性はこの半分くらいが適量ということになります。
6.ニンニクをたっぷり摂る
ニンニクの豊富な食事は大腸がんリスクを低下させます。シチュー、炒め物、焼き肉などにはニンニクを加えることが推薦されています。
がんを含む生活習慣に起因する疾患(=感染症以外のほとんどの疾患、というのが私の考えです)を防ぐには、「10の習慣」が有効であり、私は「3つのEnjoy、3つのStop、4つのデータに注意して」と覚えることを提唱しています。(詳しくはメディカルエッセイ第129回(2013年10月)「危険な「座りっぱなし」」を参照ください) 「10の習慣」は下記の通りです。
3つのEnjoy
①Exercise(運動は楽しくおこないましょう)
②Eating(食事は身体にいいものを楽しんで食べましょう)
③Early-morning waking up(毎朝早起きして1日を充実したものにし、夜はぐっすりと眠りましょう)
3つのStop
④Smoking(タバコはすぐにやめましょう)
⑤Stress(ストレスは上手にコントロールしましょう)
⑥Sitting too much(喫煙に匹敵するほど危険です)
4つのデータ
⑦血圧
⑧コレステロール
⑨体重(BMI)
⑩血糖
AICRが発表した「大腸癌を防ぐ6つの習慣」と比較すると、共通しているのは①と②だけですが、他の8つ(③~⑩)も大腸ガンのリスク低下になります。AICRの発表で注目に値するのは4番目の「赤肉・加工肉」と6番目の「ニンニク」です。
2015年10月29日、WHO(世界保健機関)は「加工肉が大腸癌のリスクとなる」という発表(注2)をおこない世界中で物議を醸しました。特にソーセージやハムが国の文化ともいえるドイツでは、WHO発表の直後から反対の声明が次々にあがりました。日本のマスコミも取り上げました。マスコミの取材に答えたほとんどの医師は、「現在の日本人の摂取量であれば問題ないであろう」という意見でした。しかし、可能であれば加工肉よりも新鮮な肉を摂取すべきなのもまた事実です。
ニンニクががんの予防になることは以前から指摘されていましたが、今回AICRがはっきりと言及したことは注目に値します。私の印象でいえば、あまりニンニクの有効性を主張している日本人の医師や公衆衛生学者は多くないように思えます。これは、日本料理がニンニクをほとんど使わないからではないかと私は思っています。
日本料理は以前は健康食の代表と言われていましたが、最近は地中海料理にその座を奪われています。地中海料理が健康にいいのは、新鮮な魚貝類(これは日本料理と共通しています)、新鮮な野菜、ピーナッツ類、オリーブオイル、そしてニンニクをたっぷりと使うからです。
ニンニクの欠点は翌日に残るあの「臭い」でしょう。臭いに敏感な日本人にはニンニク料理はなじまないかもしれません。しかし、大腸がんの予防になることがもっと注目されれば、ニンニク料理に社会が寛容になるのではないでしょうか。個人的にはそれに期待して、思いっきりニンニクが食べられる日を待ちたいと思っています。(ニンニクをオリーブオイルで炒めたときのあの香りは私を幸せな気持ちにさせますが、そのように感じるのは私だけではないでしょう)
ところで、今回のAICRの「6つの習慣」には入れられていませんが、大腸がんの予防にアスピリンが有効なのでは、ということがしばしば指摘されます。大腸がんを発症した人がアスピリンを毎日服用すると「再発の予防」になることが分かっているからです(注3)。では、発症したことのない人が毎日アスピリンを服用することで大腸がんを予防できるのかどうか、ということが気になります。
最近、これを検証した研究が報告されました。医学誌『JAMA oncology』2016年3月3日号(オンライン版)に掲載された論文(注4)によりますと、アスピリンを定期的に内服することにより大腸がんのリスクが19%低下するという結果が出ています。研究の対象者は合計135,965人(男性47,881人、女性88,084人)で、32年間の追跡期間中、男性7,571人、女性20,414人ががん(すべてのがん)を発症しています。乳がん、前立腺がん、肺がんなどではアスピリンの予防効果が認められませんでしたが、消化器系、特に大腸がんの予防効果が有意に認められています。
しかしながら、今のところ、私の知る限り、大腸がんに罹患したことのない人に対して、アスピリンを予防目的で積極的に勧めている医師はおらず、私自身も勧めるつもりはありません。アスピリンは解熱鎮痛効果のみならず、脳・心血管系疾患の再発予防がある(血を固まりにくくする)ことは以前から知られており、そのような目的で使用することには問題がありませんが、一方で鎮痛薬というのはアスピリンも含めて依存性がありますし、消化器系のがんを予防するのが事実だとしても、消化管の粘膜の出血のリスクがあるのもまた事実です。
私自身としては、大腸がんの予防には、AICRが唱える「6つの習慣」、さらに私自身が以前から提唱している「10の習慣」を実践し、さらに早期発見に努めるというのが最善であると考えています。
注1:この発表のタイトルは「6 Steps to Prevent Half of Colorectal Cancer Cases」で、下記のURLで全文を読むことができます。
注2:この発表は下記URLで読むことができます。タイトルは「Links between processed meat and colorectal cancer」です。
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/processed-meat-cancer/en/
注3:これは欧米では以前から指摘されていたことで、日本人にも当てはまるのかどうかはデータがありませんでした。しかし、日本人の患者約300人を対象とした研究が国立がん研究センターなどのチームでおこなわれ、日本人にもアスピリンによる大腸がんの再発予防効果があるという結果がでました。医学誌『Gut』2014年1月31日号(オンライン版)に掲載されています。タイトルは「The preventive effects of low-dose enteric-coated aspirin tablets on the development of colorectal tumours in Asian patients: a randomised trial 」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://gut.bmj.com/content/63/11/1755.abstract?sid=883f283e-f1ed-47f3-b10a-f5d3b9f89e0a
また、糖尿病治療薬のメトホルミンを大腸がんの外科手術後に服用すると再発予防効果があるとする横浜市立大学の研究が最近発表されました。医学誌『The Lancet oncology』2016年3月2日号(オンライン版)に掲載されています。論文のタイトルは「Metformin for chemoprevention of metachronous colorectal adenoma or polyps in post-polypectomy patients without diabetes: a multicentre double-blind, placebo-controlled, randomised phase 3 trial」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2900565-3/abstract
注4:この論文のタイトルは「Population-wide Impact of Long-term Use of Aspirin and the Risk for Cancer」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://oncology.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2497878&resultClick=3
投稿者 | 記事URL
2016年3月19日 土曜日
第151回(2016年3月) 認知症のリスクになると言われる3種の薬
この薬を飲めば認知症のリスクが上がるかもしれませんよ・・・
このように言われれば誰もが飲むのをためらうことでしょう。しかし実際には、医療機関で非常にたくさん処方されている薬や、一部は薬局で簡単に買える薬のなかにも、認知症の危険性が指摘されているものがあります。今回は渦中の3種の薬について述べたいと思います。
まず1つめです。以前から何度も認知症のリスクを上げるのではないかと言われてきたのが「ベンゾジアゼピン」です。「マイナートランキライザー」と呼ばれることもあります。ベンゾジアゼピンは、薬局で買うことはできず、睡眠薬、抗不安薬、抗けいれん薬などとして医療機関で処方されます。精神科医のみに処方されるわけではなく、実際はどの科の医師も処方しています。日本でよく使われるものを商品名(先発品)で挙げると、デパス、リーゼ、ワイパックス、ソラナックス、メイラックス、レンドルミン、エリミン、ベンザリン、サイレース、ロヒプノールなどです。
なぜ簡単に処方されるのかというと、ひとつには即効性があり、飲めばすぐに効果を実感できるのが最大の理由でしょう。費用も安く、「主観的にイヤな副作用」はあまりありません。つまり、嘔気とか下痢とか蕁麻疹(薬疹)とかいった、いかにも不快な副作用は起こりにくく、患者さんからすればとても便利な薬なのです。
しかし欠点もあります。最も問題となるのは「依存性」です。飲めばすぐに効くものの、効果が切れれば再び不安・イライラ、不眠などが生じるわけですから、すぐに追加で飲みたくなります。こうして「飲まないと落ち着かない」状態になってしまい薬を手放せなくなります。つまり「薬物依存症」となってしまうのです。(睡眠薬としてのベンゾジアゼピンがいかに危険であるかについては過去のコラムでも指摘しています(注1))
依存性以外の欠点(副作用)として、ベンゾジアゼピンは筋弛緩作用が強いためにふらつきや転倒のリスクがあることが挙げられます。このため高齢者には原則使ってはいけないことになっており、ガイドラインにもそう書かれています。しかし、実際には多用されているのが現実であり、日本の医師は高齢者にベンゾジアゼピンを使いすぎることがよく指摘されます。転倒で受診された患者さんを診察するとき、証明はできないものの、「その転倒はベンゾジアゼピンを飲んでなければ防げたのではないか」と感じることもあります。
高齢者の場合は、若年者に比べると薬が効きすぎるという問題もあります。ですから翌日も薬の効果が残っていて、ぼーっとして意味不明なことを言うことがあります。「最近調子がおかしい。認知症でしょうか・・」と言って受診される患者さんのベンゾジアゼピンを減らせば再び元気になった、ということはしばしばあります。つまり、認知症ではなくベンゾジアゼピンが効き過ぎていたために意味不明な言動が起こっていた、ということです。
医学誌『British Medical Journal』2016年2月2日号(オンライン版)に、「ベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げない」とする研究結果が発表されました(注2)。これまでは認知症のリスクになるとされていた見解を覆す研究ですから、これは注目すべきものです。研究の対象者は合計3,434人、平均追跡期間は7.3年ですから比較的大規模な研究で、信ぴょう性は高いと言えます。
そして、この研究が興味深いのは「ベンゾジアゼピンを少量使用した人の認知症のリスクは少し上昇し、たくさん使った人にはリスクは認められなかった」としていることです。結論として「ベンゾジアゼピンの使用は認知症のリスクを上げない」とされています。
なぜ、少量の使用で少しリスクが上がったのでしょうか。これはおそらく認知症の初期に出現する不安やイライラ、不眠といった症状にベンゾジアゼピンが使用されたからではないかと推測できます。また、認知症初期の不安定な時期には副作用のリスクを考慮して少量しか用いられていない可能性があります。そして、認知症初期には、まだ認知症の診断がついていないことが予想されます。つまり、少量のベンゾジアゼピンが認知症のリスクを上げたのではなく、認知症の初期段階ではまだ診断がついておらずこのときに少量のベンゾジアゼピンが使われている、ということです。
この研究によって、認知症のリスクという「汚名」を着せられていたベンゾジアゼピンの名誉が回復したといっていいかもしれません(注3)。しかし、先に述べたようにベンゾジアゼピンにはやっかいな依存性という問題があり、高齢者の場合はふらつき、転倒のリスク、さらに翌日にも薬の作用が残るという欠点もあります。ガイドラインどおり高齢者にはできるだけ使わないという方針は守るべきですし、依存性を考えれば若年者も決して簡単に使用してはいけません。
ベンゾジアゼピンについては疑いが晴れたわけですが、その逆に、突然認知症のリスクが指摘され、現在世界的に混乱を招いている薬があります。それは「プロトン・ポンプ・インヒビター(以下PPI)」と呼ばれる胃薬です。日本で名の通った製品名(先発品)は、オメプラゾン、タケプロン、パリエット、ネキシウム、タケキャブなどです。胃潰瘍や十二指腸潰瘍のみならず逆流性食道炎にもよく効く薬で、保険適用のルールが厳しい割には比較的よく処方されている薬です。またヘリコバクター・ピロリ菌の除菌にも用いられます。
医学誌『JAMA Neurology』2016年2月15日号(オンライン版)に掲載された論文(注4)によりますと、高齢者がPPIを使用すると、使用しなかった場合に比べて認知症のリスクが44%も上昇します。
にわかには信じがたいデータですが、これは対象者の多い大規模研究です。ドイツで2004年~2011年に治療を受けた75歳以上の合計218,493人が研究の対象です。ここから、PPIを定期的には使用していない症例や2004年の段階で死亡したり認知症を発症したりした症例などを除外し、最終的に73,679人が解析の対象となっています。このなかでPPI定期使用者が2,950人、非使用者は70,729人です。追跡期間中に認知症を発症したのが全体で29,510人です。分析すると、PPI定期使用者の認知症のリスクは使用していない人に比べて44%上昇していることが分かりました。
これはドイツの研究ですが、この結果を軽視できないと考えた「米国消化器学会(American Gastroenterological Association)」は、論文発表3日後の2016年2月18日、「How to Talk with Your Patients About PPIs and Dementia(PPIと認知症の関係について患者さんにどのように話すべきか)」というタイトルで、医師に対する注意勧告をおこないました(注5)。
これは高齢者が長期間PPIを服用したときの研究であり、短期間の使用や若年者の使用は考慮されていません。ですから、たとえばピロリ菌の除菌が必要な若年者がこの研究を受けて治療を中止するというようなことは避けるべきです。しかし、ドイツのみならず日本も含めて世界各国でPPIの不適切使用は少なくないのではないか、とも言われており、漠然と長期間内服している人は見直してみるべきかもしれません。
PPIのこの報告は世界中で話題になりましたが、実は以前からほぼ確実に認知症のリスクになるのではないかと言われている薬があります。それは「抗コリン薬」または「抗コリン作用の強い薬」です。
医学誌『JAMA Internal Medicine』2015年3月号(オンライン版)(注6)に掲載された論文によりますと、抗コリン作用を有する薬を高齢者が使えば使うほど認知症のリスクが上昇し、高用量使用者では非使用者に比べて54%もリスクが上昇するとされています。この研究の対象者は65歳以上の米国人合計3,434人です。
54%ものリスク上昇。しかも「抗コリン作用を有する薬」というのは、ベンゾジアゼピンやPPIのように医師が処方するものではなく、薬局で気軽に買えるものです。古いタイプの花粉症の薬やじんましんの薬、胃痛・腹痛で比較的よく使われる薬が代表です。睡眠改善薬として薬局で売られているものも該当します。
もちろん今回紹介した薬のいずれもが、必要なときは使うべきであり、自己判断で中止してはいけません(注7)。「薬の使用はいつも最少量」という原則を守っていればそう心配する必要はないのです。しかし、自己判断で漠然と長期で使うのは危険であることは肝に銘じるべきでしょう。
注1:下記を参照ください。
はやりの病気第148回(2015年12月)「不眠治療の歴史が変わるか」
はやりの病気第124回(2013年12月)「睡眠薬の恐怖」
注2:この論文のタイトルは「Benzodiazepine use and risk of incident dementia or cognitive decline: prospective population based study」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://www.bmj.com/content/352/bmj.i90
注3:ただし、ベンゾジアゼピンの認知症のリスクが完全に否定されたわけではありません。危険性を警告した最も有名な論文のひとつが医学誌『British Medical Journal』2014年9月9日号(オンライン版)に掲載されています。タイトルは「Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: case-control study」で、下記URLで全文を読むことができます。
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g5205
注4:この論文のタイトルは「Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2487379
注5:下記URLを参照ください。
http://partner.gastro.org/how-to-talk-with-your-patients-about-ppis-and-dementia
注6:この論文のタイトルは「Cumulative Use of Strong Anticholinergics and Incident Dementia」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2091745
注7:本文で紹介したもの以外に認知症のリスクを挙げるとされているものに、前立腺がんに対するアンドロゲン遮断療法があります。これについては下記コラムを参照ください。
メディカルエッセイ第158回(2016年3月)「「がん検診」の是非」
投稿者 | 記事URL
2016年2月14日 日曜日
第150回(2016年2月) エンテロウイルスの脅威
2016年2月現在、世界で最も関心の高い感染症はジカ熱をきたすジカウイルス感染症だと思います。WHOが「緊急事態宣言」をおこない、単に発熱をきたすだけでなく、感染するとギラン・バレー症候群や小頭症をきたす可能性が指摘されているわけですから、それは当然でしょう。
では、現在日本で最も注目されている感染症は何かというと、おそらくエンテロウイルスだと思われます。昨年(2015年)の秋頃から、急性弛緩性麻痺といって突然手足が動かなくなる病気が急増し、その原因が「エンテロウイルスD68」であることが指摘されているのです。今回は、このウイルスと麻痺について述べていきたいと思います。
「エンテロウイルス」は「属」「種」といった生物の分類の知識がないと混乱しやすいので、まずは言葉の整理から始めたいと思います。
ウイルスは遺伝子をDNAで持つかRNAで持つかによって2つに分類できます。RNA型ウイルスにピコルナウイルス科と呼ばれる「科」があり、これは6つの「属」に分かれます。エンテロウイルス属、ライノウイルス属(風邪のウイルスとして有名です)、ヘパトウイルス属(A型肝炎ウイルスはここに含まれます)、カルジオウイルス属、アフトウイルス属、パレコウイルス属です。
エンテロウイルス属には、ポリオウイルス、コクサッキーウイルス、エコーウイルス、エンテロウイルス、また動物に感染するタイプのものも多数あり、多くの種類があります。生物の分類は、このように「科」「属」「種」の順番に細かくなっていきます。新聞報道などで、エンテロウイルスとライノウイルスが似たようなものとされていることがあるのは、同じ「ピコルナウイルス科に所属」するからであり、エンテロウイルスとポリオウイルスが同じ仲間と言われるのは同じ「エンテロウイルス属に所属」するからです。図示すると次のようになります。
ピコルナウイルス科 —- ライノウイルス属 —- ライノウイルスなど
ヘパトウイルス属 —- A型肝炎ウイルスなど
カルジオウイルス属
アフトウイルス属
パレコウイルス属
エンテロウイルス属 —- ポリオウイルス(Ⅰ~Ⅲ型)
—- コクサッキーウイルス(A10,16など複数種)
—- エコーウイルス(1~34まで)
—- エンテロウイルス(D68、71など複数種)
—- 動物エンテロウイルス
—- ・
—- ・
英語が得意な人は「エンテロ(entero)」と聞くと「腸」を思いだすかもしれません。それは正しく、実際エンテロウイルス属のポリオウイルスは不衛生な水や食べ物から感染します。しかし「腸」にこだわるとエンテロウイルスの理解を複雑にしてしまうことがあります。
手足口病は過去数年間に何度か流行しています。文字通り、手と足と口に水疱ができる感染症で、感冒症状が伴うのが普通です。小児の感染症として有名ですが、近年は成人が発症することも珍しくありません。成人の手足口病は子供に比べて皮膚症状が重症化することがあり、なかには爪の変形が伴う場合もあります。爪がとれてしまうこともあります。
手足口病の原因ウイルスは複数種あり、コクサッキーウイルスA10、A16 やエンテロウイルス71などが有名です。上の図でいえばエンテロウイルス属に入るウイルスです。しかし、いつも「腸」から感染して手足口病を発症するわけではありません。経口感染が多いのは事実ですが、他人の咳やくしゃみから感染する、いわゆる「飛沫感染」もあります。発熱を伴うことがありますし、そもそも手足口病は「夏風邪」の代表のひとつです。(夏だけに生じるわけではありませんが)
原因が複数種あるなかでエンテロウイルス71の手足口病が最も重症化する傾向にあります。また、このウイルスは数年前から注目されており、特に2012年4月から7月にカンボジアで生じた流行では、78人の小児が感染し、なんとそのうちの54人が死亡しています(注1)。
2013年にはシドニーでもエンテロウイルス71がアウトブレイクし100人以上の小児が入院しました。やはり死亡例を認め、1年以上が経過した時点でも重篤な後遺症に苦しめられている小児もいました。最近、このときの流行で、死亡を含む神経症状を有した患者61人を1年間にわたり調査した論文(注2)が発表されました。61人のうち4人(7%)は病院に到着した点で心肺停止状態にあり数時間以内に死亡が確認されています。生存した57人には重篤な神経症状が出現し、12ヶ月後に51人は回復しましたが、残りの6人は依然神経症状に苦しめられていたそうです。
2014年には米国ミズーリ州とイリノイ州でエンテロウイルスD68(71ではない)がアウトブレイクし全米に広がりました。エンテロウイルスD68は1962年に米国カリフォルニア州で検出されたのが世界初とされていますが、その後世界的にもほとんど流行していません。ところが、2014年の夏頃より突如としてエンテロウイルスD68による重症呼吸器疾患の報告が相次ぎ、特に喘息を有する小児の間で広がりました。神経症状が生じた例も少なくなく、特に急性弛緩性脊髄炎(AFM)や急性弛緩性麻痺(AFP)と呼ばれる重篤な神経疾患が目立ち、長期間脱力などの神経症状が残存したケースもありました(注3)。最終的には2015年1月15日までに、呼吸器疾患を発症してエンテロウイルスD68が検出された患者は49州で1,153人となり、うち14人が死亡しています。
米国CDC(疾病管理センター)は2014年12月、「新たな感染症の脅威(New Infectious Disease Threats)」というタイトルで4つの感染症を挙げ、そのうちのひとつがこのエンテロウイルスD68です(注4)。ちなみに他の3つは、エボラウイルス、MERS(中東呼吸器症候群)、薬剤耐性菌です。
そして日本です。国立感染症研究所によりますと、2005~2014年9月までに日本国内で31都府県の272人からエンテロウイルスD68が検出されていて、夏から秋にかけて感染者が増加する傾向があります。2010年と2013年には感染者数が100人を超えていました。しかし、重症化するケースはまれであり、あまり大きな問題にはなっていませんでした。
ところが、2015年8月以降、エンテロウイルスD68の報告が突然急増しだし、同時に急性弛緩性麻痺の症例の報告が相次ぎ、一部の患者からエンテロウイルスD68が検出されたのです。エンテロウイルスD68による急性弛緩性麻痺が増加していることを強く示唆しています。そのため、厚生労働省は、2015年10月21日、「急性弛緩性麻痺(AFP)を認める症例の実態把握について(協力依頼)」という事務連絡を発令し、全国の小児科医療機関に依頼をおこないました。
現時点では、急性弛緩性麻痺を発症した全例からウイルスが検出されているわけではなく、未解明の点もあるのですが、米国の状況と合わせて考えると、エンテロウイルスの今後の動向には充分な注意を払うべきでしょう。
エンテロウイルスが注目されている理由はまだあります。感染すると1型糖尿病(生活習慣が原因でない小児にも起こる糖尿病)のリスクが上昇するという研究があるのです。医学誌『Diabetologia』2014年10月17日号(オンライン版)に掲載された論文(注5)によりますと、台湾の健康保険請求データに基づいた解析から、エンテロウイルス感染歴のある小児は、感染歴のない小児に比べ1型糖尿病発症リスクが48%高くなることが判りました。
死亡例や重篤な神経の後遺症を残すことがあり、さらに1型糖尿病のリスクも挙げるエンテロウイルス。従来は、単なる夏風邪の代表の手足口病の原因であったエンテロウイルス71がカンボジアやオーストラリアで猛威を振るい、1962年に発見されて以来特に問題のなかったエンテロウイルスD68が突如としてアメリカ、そして日本で脅威となっています。
なぜ、このような事が起こるのでしょうか。鍵のひとつは遺伝子の「かたち」です。エンテロウイルスは遺伝子をRNA型の1本鎖で持っています。ウイルスの遺伝子の「かたち」には、DNA2本鎖、RNA2本鎖、DNA1本鎖、RNA1本鎖の4種があります。そして、遺伝子は時と共に変異をします。一般にRNA型の遺伝子はDNA型の遺伝子より不安定であり、RNAの変異のスピードはDNAの100万倍以上と言われています。また、遺伝子というのはらせん状の長い分子になっていますから共にらせんを形成する2本鎖の方が1本鎖よりはるかに安定しています。つまり遺伝子をRNA1本鎖でもつ生物は、動物などのDNA2本鎖の生物よりも、何百万倍、何千万倍、あるいはそれ以上のスピードで変異を起こすのです。ちなみに、新型が次々と現れるインフルエンザの遺伝子もRNA1本鎖です。
つまり、インフルエンザウイルスが突然変異を起こし、かつて人類が経験したことのないような脅威となるのと同じように、エンテロウイルスもいきなり変異を起こし、ある日突然猛威をふるう可能性があったのです。手足口病が「子供に起こる軽症の夏風邪」だったのは変異が起こる前の話というわけです。
感染症で頼りになるのはワクチンです。エンテロウイルス属の代表であるポリオウイルスはかつての日本で驚異の感染症であり、ワクチンが導入される前は大勢の子供が感染し、生涯消えることのない「麻痺」を残し、成人となった今も苦しまれています。1960年には北海道を中心に5,000名以上の患者が発生し、日本政府はソ連から1961年に生ワクチンを緊急輸入しました。これにより日本のポリオ患者は激減し、1980年を最後にその後1例も発症していません。
エンテロウイルスのワクチンは世界中で開発がすすめられていますが、まだ実用化には至っていません。医学誌『Lancet』2013年1月24日号(オンライン版)に掲載された論文(注6)によりますと、中国でエンテロウイルス71のワクチン開発が進んでおり、効果と安全性が確認されているようです。しかし、その後実用化にいたったという話は聞きません。しかもこれは、すべてのエンテロウイルスに有効なわけではなく71のみを対象としたものです。米国が脅威の感染症と認定し、現在日本で流行し重篤な神経症状をきたすと考えられているエンテロウイルスD68のワクチンは目下のところ開発の目処がたっていません。
当分の間、この脅威のウイルスの動向から目が離せません。
注1:WHOの報告は下記にあります。
http://www.who.int/csr/don/2012_07_13/en/
注2:この論文は医学誌『JAMA Neurology』2016年1月19日(オンライン版)に掲載されており、タイトルは「Clinical Characteristics and Functional Motor Outcomes of Enterovirus 71 Neurological Disease in Children」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2482645
注3:この論文は医学誌『THE LANCET』2015年1月28日号(オンライン版)に掲載されており、タイトルは「A cluster of acute flaccid paralysis and cranial nerve dysfunction temporally associated with an outbreak of enterovirus D68 in children in Colorado, USA」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2962457-0/abstract
注4:CDCの報告は下記URLを参照ください。
http://www.cdc.gov/media/dpk/2014/dpk-eoy.html
注5:この論文のタイトルは「Enterovirus infection is associated with an increased risk of childhood type 1 diabetes in Taiwan: a nationwide population-based cohort study」で下記URLで全文を読むことができます。
http://www.diabetologia-journal.org/files/Lin.pdf
注6:この論文のタイトルは「Immunogenicity and safety of an enterovirus 71 vaccine in healthy Chinese children and infants: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 clinical trial」で、下記URLで概要が読めます。
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2961764-4/abstract
投稿者 | 記事URL
2016年1月22日 金曜日
第149回(2016年1月) 増加する手湿疹、ラテックスアレルギーは減少?
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)にはアレルギー疾患を持っている患者さんが少なくなく、また次第に増えているような印象があります。谷口医院をオープンする前、私が複数の医療機関で修行(研修)をしていた頃、皮膚疾患を診ている医療機関ではラテックスアレルギーの患者さんがよく来ていました。そして、今後も増加すると考えた私は、ウェブサイトのコラム『はやりの病気』第35回(2006年7月)でラテックスアレルギーを取り上げました。
谷口医院がオープンしたのは2007年1月(当時は「すてらめいとクリニック」という名称でした)。その頃には、コンスタントにラテックスアレルギーの患者さんが受診されていたのですが、その2~3年後から次第に減少していきました。
もちろん、ラテックスアレルギーの患者さんの大半は「ラテックスアレルギーです」と言って受診されるわけではなく、「手があれました」というのが最も多い訴えです。(ラテックスアレルギーは口元や性器にも発症します。これについては後述します) そして「手あれ」自体は減っていないどころか年々増えています。つまり、ラテックスアレルギー以外の「手あれ」が増えているということです。
ラテックスアレルギーが減少している最大の理由は「手袋の品質が上がった」からではないかと私はみています。ただし、このようなことを検証したデータを私は見たことがなく、他の医師がどう感じているかは分かりません。これは単なる私の日々の診療を通しての「印象」であることをお断りしておきます。
元々、ラテックスアレルギーの患者さんの半数以上は医療者でした。医師や看護師は日常的にラテックス製のグローブを使います。そのうちに身体がラテックスを異物とみなすようになり(これを「感作(sensitization)」と呼びます)、そうなれば、ラテックスに触れて数分後にアレルギー症状が出現します。
最初はラテックスが触れた部分のみが赤く腫れ、軽度の痒みが出る程度ですが、そのうちに痒みが痛みになり、さらに重症化すると全身の蕁麻疹、鼻水、呼吸苦なども出現し、悪化すればアナフィラキシーと呼ばれる生命にかかわる状態に移行することもあります。海外では死亡例もあります。つまり、ラテックスアレルギーというのは重症化すると「死に至る病」になるのです。
ラテックスアレルギーはいったん発症すると治すことはできません。つまり、一度ラテックスアレルギーの診断がつけば、生涯ラテックスに触れることはできないのです。そのため、医療者の場合、ラテックス以外の化学物質でつくられた手袋を使用することになります。
手袋の品質が上がったのは、おそらくラテックスの良質な部分のみを使用するようになったからです。一言で「ラテックス」といっても、分子レベルでみてみると、おそらく数百種のタンパク質が含まれているはずです。そしてそれらタンパク質のすべてがアレルゲン(アレルギーの原因)になるわけではありません。おそらく、分子レベルの研究が進んだことにより、アレルゲンになりうるタンパク質が同定され、そのタンパク質を取り除く技術が発達したのでしょう。
谷口医院の例でいえば、ラテックスアレルギーが減ったのは医療者だけではありません。以前は工場やパン工房で働く人にもラテックスアレルギーがけっこうあったのですが、最近は減ってきています。やはり、こういった施設でも品質改良されたラテックス製の手袋が使われるようになってきているのでしょう。
ラテックスアレルギーで忘れてはならないのがコンドームです。性交後に性器が痒くなったり痛くなったりするという人は、男性でも女性でも一度はラテックスアレルギーを疑うべきです。以前は、コンドームによるラテックスアレルギーは決して少なくなく、そのためにポリウレタン製のコンドームを勧めなくてはならなかったのですが、最近はこういった話をする機会も減ってきました。ということは、コンドームも品質改良がおこなわれ、アレルゲンとなりうるタンパク質が除去されているのかもしれません。
一方、さほど減っていないと思われるのが、ゴムサックと風船です。風船については、関西なら甲子園球場に行くと必ず口の周りが痒くなるという人はラテックスアレルギーを疑うべきです。ゴムサックと風船が減らないのは、おそらく手袋やコンドームと異なり、これらは今も従来のラテックスが使われているということなのかもしれません。
手袋やコンドームの改良によりラテックスアレルギーは今後も減少の一途をたどるのでしょうか。そうあってほしいと思いますが、ひとつ私が懸念していることがあります。それは「ラテックスフルーツ症候群」です。日本人の何パーセントがこの病気を持っているのかについてはデータを見たことがありませんが、決して少なくないのでは?と私は考えています。現在野菜や果物を食べると口が痒くなる人(これだけなら「口腔内アレルギー症候群」と呼びます)は、今後ラテックスアレルギーが出現する可能性があります(注1)。
さて、手あれ(手湿疹)に話を移します。ラテックスアレルギーは減っているのに、手湿疹が一向に減らないのは他に原因があるからです。
古い研究ですが、医学誌『Journal of the American Academy of Dermatology』1991年11月号(オンライン版)に掲載された論文(注2)によりますと、医療者のアレルギー性接触皮膚炎の8割以上は、何らかの促進剤(accelerator)(注3)が原因だそうです。ということは、そもそも手袋を使う以上はラテックスだけに注目していればいいわけではなかった、ということになります。
ならば、その促進剤を特定して原因物質を調べて、それが含まれていない手袋を使用すればいいではないか、ということになり、確かにその通りです。しかし、これは簡単な話ではありません。たしかに、原因の可能性のある物質を取り寄せて、パッチテストをおこなえば原因物質を特定できることがあります。しかし、現実には、原因となりうる「促進剤」は多数あり、それを入手するのが困難であり、それをいろんな濃度のものを作成し、背中に貼って丸二日シャワーを我慢し、頻繁に医療機関を受診して・・・、と何かと大変です。
では、どうすればいいのでしょうか。まず手袋が原因で手荒れやかぶれが起こった場合、重症化しうるラテックスが原因なのかそうでないのかに注目します。ポイントは、ラテックスは接触後数分で症状が出るのに対し、ラテックス以外の物質が原因である場合は、1~3日ほど経過してから現れるということです。これは実際には必ずしも簡単に見分けられる方法ではないのですが、このことは知っておくべきです。
ラテックスが原因でなさそうなら、別の手袋に替えて様子をみるのが現実的な方法です。しかし、症状が強いのなら医療機関を受診してそこで治療を受け、助言を受けるのがいいでしょう。
もうひとつは、促進剤のなかでも比較的高率にアレルギーを起こすことが分かっている「チウラム」と呼ばれる物質が含まれていない手袋、あるいは含まれていても少量の手袋を選ぶという方法は有効かもしれません(注4)。
手荒れというのは、もちろん他にも原因があります。手袋をまったく使用していなくてもアトピー性皮膚炎がある人は手が荒れやすいですし、掌蹠膿疱症、尋常性乾癬、汗疱といった皮膚疾患でも手荒れのような症状が起こります。梅毒では手のひらに痒くない発赤が起こることがありますし、手足口病でも発赤が出現します。石けんの使いすぎで手がボロボロになっている人がいますし、飲食店勤務の人は手袋をしていなくても手荒れを起こすことはよくあります。職業でいえば、美容師や理容師の人たちは、手袋も使い、頻繁に手を洗いますから手荒れには常に注意する必要があります。楽器が原因であったり、ガーデニングに問題があったり・・・、と手荒れの原因は様々です。
原因が何であれ、治らない手荒れ、繰り返す手荒れは一度かかりつけ医に相談すべきでしょう。
注1:下記コラムも参照ください。
はやりの病気第144回(2015年8月)「増加する野菜・果物アレルギー」
注2:この論文のタイトルは「Allergic and irritant reactions to rubber gloves in medical health services」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://www.jaad.org/article/S0190-9622%2808%2980977-2/abstract
注3:この部分は非常に訳しにくく困りました。原文をそのまま抜粋すると、「Accelerators, mainly of the thiuram group, antioxidants, vulcanizers, organic pigments」となります。
注4:現在医療機関で比較的よくおこなわれるセットになったパッチテストがあり、そのなかに「チウラム」も含まれます。ただし、これはセットですからチウラムのみを検査することはできません。このセットのパッチテストについては下記を参照ください。
投稿者 | 記事URL
2015年12月21日 月曜日
第148回(2015年12月) 不眠治療の歴史が変わるか
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)の患者さんは睡眠の悩みを訴える人が多く、毎日のようにその苦痛を聞いています。谷口医院の患者さんは働く若い世代が多いですから、「睡眠」の悩みとして一番多いのは狭い意味での不眠ではなく、「眠る時間の確保ができない」、つまり「労働時間が長すぎて困っている」、というものです。
過去に述べたように、睡眠不足は作業効率を落とし(飲酒運転と同じ!)、いろんな病気のリスクになります(注1)。また日本人を対象とした研究で「睡眠不足は死亡率を高くする」とするものもあります(注2)。
睡眠に関するもうひとつの問題が「睡眠時間を確保しても眠れない」、つまり「不眠」です。不眠があるからといって、それだけで睡眠薬を処方するわけにはいきません。まずは規則正しい生活ができているかどうかの見直し、そして原因になっているものがないかどうかの検討をしなければなりません。実際、不眠の原因が内分泌疾患(最多が甲状腺機能亢進症)であったり、薬剤性であったり、ということはしばしばありますし、うつ病など精神疾患であることも珍しくありません。その場合、まずは原疾患の治療が必要になります。
不眠の原因が特に見当たらず、生活習慣の見直しをおこなったけれどもそれでも不眠が続くという場合には「睡眠薬」の検討を開始することになります。
「睡眠薬」という表現以外に「入眠剤」「睡眠補助薬」「睡眠改善薬」などいろんな言葉があり混乱を招いています。ここはきちんと分類しておかないと話がややこしくなりますから、この時点で整理したいと思います。現在使われている「睡眠の薬」を分類すると次のようになります。
①ベンゾジアゼピン系:現在日本で使用されている大多数
②非ベンゾジアゼピン系:ゾルピデム(マイスリー)、ゾピクロン(アモバン)、エスゾピクロン(ルネスタ)
③メラトニン受容体作動系(ロゼレム)
④オレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ)
⑤バルビツール酸系
⑥非バルビツール酸系:ブロバリンなど
①ベンゾジアゼピン系が最も使用されているもので、商品名でいえば、ハルシオン、レンドルミン、リスミー、ベンザリン、ユーロジン、エリミン、サイレース、ロヒプノールなどが相当します。ごく短時間しか作用しないものから長時間作用するものまで、また比較的弱いものから強力なものまでそろっており、多くの場合すぐに効果がでますから、「確実に眠りたいときには便利な薬」という言い方ができるかもしれません。
しかし危険性は小さくありません。まずベンゾジアゼピン系には「依存性」という大変やっかいな問題があります。これは文字通り睡眠薬に「依存」してしまう、つまりある程度使い続けるともはやベンゾジアゼピンなしでは眠れない身体になってしまう、いわば一種の「薬物依存」です。睡眠薬に限らず薬というのは減らしていくことを考えなければなりませんが、ベンゾジアゼピン系というのは依存を断ち切ることが最も困難な薬のひとつなのです。
ベンゾジアゼピン系には「反跳性不眠」という問題もあります。これは、ベンゾジアゼピン系をある程度使い続けると、中止したときに、薬を始める前よりも不眠の重症度が強くなる、つまり、睡眠薬を使ったことにより、使う前よりも不眠症がひどくなってしまうことを言います。「依存性」と「反跳性不眠」の2つがベンゾジアゼピン系の代表的な問題点です。
ベンゾジアゼピン系にはまだ問題があります。「筋弛緩作用」がありこれは転倒のリスクになります。また日中の倦怠感や眠気が起こることもあります。特に高齢者ではこういったリスクが増大し、実際海外では多くの国で65歳以上の高齢者には使用してはいけないことになっています。一方、日本ではベンゾジアゼピン系の使用が諸外国に比べ極めて多いことがしばしば指摘されます。さらに、充分なコンセンサスが得られているとまでは言えませんが、一部にはベンゾジアゼピン系が認知症のリスクになるとする報告もあります。
ベンゾジアゼピン系にそんな問題があるなら②非ベンゾジアゼピン系に期待したいところですが、非ベンゾジアゼピン系も、化学構造がベンゾジアゼピン系とは異なるというだけで、実際の効果や副作用はベンゾジアゼピン系と変わりません。実際、過去に紹介した悲惨な事件の原因(注3)となったのは非ベンゾジアゼピン系の代表ともいえる「ゾルピデム(マイスリー)」です。
③は副作用が少なく、依存性もない大変使いやすい薬で、登場したときには期待が大きかったのですが、残念ながら効果に乏しくこれでは眠れないという人が少なくありません。この薬は国によっては薬としては認められておらず「サプリメント」の扱いです。
⑤と⑥はかなり強い薬で副作用が多く重症例にしか使われないものです。重症例に限り精神科専門医により処方される薬と考えればいいでしょう。
今、もっとも注目されているのが④オレキシン受容体拮抗薬(ベルソムラ)です。この薬は日本人の学者により開発され2014年12月から処方開始となりました。オレキシンというのは脳でつくられる覚醒を維持するホルモンと考えればいいと思います。オレキシンがオレキシン受容体と結合することにより人は覚醒していられる、というわけです。ベルソムラはそのオレキシン受容体をブロックすることにより、オレキシンの作用を抑制するという仕組みです。
このような理屈よりも重要なのが実際の効果と副作用です。まず副作用からみていきましょう。ベルソムラの最大の特徴は、(非)ベンゾジアゼピン系の欠点である「依存性」と「反跳性不眠」がないということです。これは大変大きいことです。副作用がまったくないわけではなく(たとえば眠気が昼間に持ち越されるといった副作用はありえます)、また歴史の新しい薬ですから長期使用での安全性については未知の部分もありますが、ベルソムラは従来の睡眠薬に比べて随分と使いやすい画期的な薬といえます。
③のロゼレムが登場したときも同じようなことが言われましたが、残念ながら、先にも述べたようにロゼレムでは効果が不十分であることが多かったのです。ベルソムラはロゼレムに比べて、睡眠効果も高く今後ますます使用されていくことになると思われます。
ただし、谷口医院の患者さんをみていると、ベルソムラは、キレの良さというか、効果の強さでいえばやはり従来の睡眠薬、つまり(非)ベンゾジアゼピン系よりは弱いといえます。それに、これまで(非)ベンゾジアゼピン系を使っていた患者さんに、直ちにベルソムラに切り替えてもらってもたいていは上手くいきません。
そこで、谷口医院では、現在(非)ベンゾジアゼピン系を使っている患者さんに対しては、いきなりベルソムラに変更するのではなく、まずはこれまで通り(非)ベンゾジアゼピン系を使用してもらいベルソムラを併用します。しばらくしてから、(非)ベンゾジアゼピン系の量を少なくします。たとえば1/2の量、もっと慎重に進める場合は3/4程度にします。そして少しずつ(非)ベンゾジアゼピン系を減らしていき、最終的にはベルソムラのみにするのです。ロゼレムで上手くいかなかったケースでもベルソムラでは成功することが多いといえます。
先にも述べたように新しい薬というのは長期で使用して初めて判る副作用もありますから、ベルソムラの場合も手放しに歓迎というわけにはいきません。しかし、今後(非)ベンゾジアゼピン系の使用を大幅に減らすことは期待できそうです。
注1:詳しくは下記「はやりの病気第139回」を参照ください。
注2:下記に簡単な紹介がされています。
http://jeaweb.jp/journal/abstract/vol014_04.html
注3:詳しくは下記「はやりの病気第124回」を参照ください。
参考;はやりの病気
第138回(2015年2月)「不眠症の克服~睡眠時間が短い国民と長い国民~ 」
第139回(2015年3月)「不眠症の克服~「早起き早寝」と眠れない職業トップ3~」
第86回(2010年10月)「新しい睡眠薬の登場」
第124回(2013年2月)「睡眠薬の恐怖」
投稿者 | 記事URL
2015年11月20日 金曜日
第147回(2015年11月) 毛染めトラブルの4つの誤解~アレルギー性接触皮膚炎~
2015年10月23日、消費者安全調査委員会は「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 毛染めによる皮膚障害」というタイトルの報告書を公表しました(注1)。毛染めによる皮膚のトラブルが相次いでいて、消費者に注意を促すのが目的です。
しかし、トラブルが相次いでいるといっても最近になって突然増え始めたわけではありません。コムギアレルギーを誘発した「茶のしずく石けん」や、白斑症を起こしたカネボウなどのロドデノールを含む化粧品、最近の事件ではダイソーが扱っていたホルムアルデヒドが含有されていたマニキュアなどの事件とは性質が異なります。
つまり毛染め(ヘアダイ)のトラブルは昔からあり、実際、消費者安全調査委員会が公表しているデータをみても被害が急増しているとはいえません。では、なぜ今になって同委員会がこのような報告書を発表したのか。それは、避けられるはずの被害が一向に減らないから、そして毛染めに対する「誤解」が蔓延している事態を打開すべきと同委員会が判断したからではないかと私はみています。
毛染めのかぶれに対する「誤解」は大きく4つあると私は考えています。順にみていきましょう。
頭皮や顔面の皮膚のトラブルを訴えて受診される患者さんに対して、「これはおそらく毛染めが原因ですよ」と言うとそれを否定する人がときどきいます。そういう人がいうセリフは「前から同じものを使っているから原因は毛染めではありません」というものです。
ここを誤解している人は非常に多いようです。毛染めのかぶれは、主に「アレルギー性接触皮膚炎」です。これはその毛染めを使い続けているうちに、身体が毛染めの成分を”外敵”とみなし、アレルギー反応が起こるようになるのです。つまり、「長い間使っていたからこそアレルギーが生じた」と考えなければなりません。
ここは多くの人が誤解しているのでもう少し続けたいと思います。薬疹を疑ったときも「この薬はもう半年も飲んでいるから原因ではありません」という人がいますが、これも「半年間飲んだからこそアレルギーになった」と考えるべきです。抗菌薬などは飲んで2回目以降にでます。もう少し例をあげると、スギ花粉症になる人は、生まれたときからスギ花粉症なのではなく、長い年月をかけてスギ花粉を少しずつ吸い込んである一定量を超えたときにアレルギーを発症します。ペットショップのオーナーがいきなりイヌアレルギーになり廃業せざるを得なくなったとか、そば屋の主人がソバアレルギーになり店をたたまなくてはならなくなったというエピソードを思い出せば理解しやすいと思います。
毛染めのかぶれに対する2つめの誤解は「自分が毛染めでかぶれるのは知っているし、実際いつもかゆくなる。けど、これくらいなら我慢できる」というものです。これは気持ちは分かりますが危険です。アレルギー性接触皮膚炎というのは、繰り返せば繰り返すほど重症化していきます。最初は頭皮の軽度の発赤と痒みだけだったけれど、そのうち程度が強くなり、ひどい場合は全身が腫れ上がったり、使用をやめてからも長期間通院しなければならなくなったりということもあります。実際、消費者庁に2010年度からの5年間で寄せられた事例が約1,000件あり、そのうち約170件は治療に1ヶ月以上かかった重症だったそうです。
ちなみに、5年間で1,000件と聞くと、そんなに多くないのかなと錯覚しそうになりますが、これは届け出があった数ですから、実際にはその何百から何千倍もあるはずです。消費者安全調査委員会の報告によれば、自宅での毛染めで15.9%、美容院での毛染めで14.6%がかゆみなどの異常を感じた経験があると回答しています。
毛染めに興味がない、あるいは縁がない、という人には理解しにくいかもしれませんので補足しておきます。少しでもかゆみが出るならそんなもの使ってはいけないんじゃないの?と考える人もいるでしょう。なぜ彼(女)らは、かぶれると知っていても使おうとするのか。それはそのリスクを抱えてでもきれいに染めたいからで、他に代替できるものがないのです。
毛染めのかぶれの原因物質のほとんどはパラフェニレンジアミン(以下PPDとします)と呼ばれるものです。(他にはメタアミノフェノール、トルエン-2、5-ジアミンなどもあります) なぜ高頻度でかぶれることが分かっていながら市場で売られているのかというと、これほどきれいに染まる染料が他にないからです。毛染め(ヘアダイ)でのかぶれを起こしたことがある人に対して、私はヘアマニキュアを勧めるようにしています。しかし、ヘアマニキュアでは好みの色(特に明るい色)がでないことが多く、また、すぐに色が取れてしまうという問題もあります。
フランスでは、あまりにかぶれの被害が多いことから、過去にPPDの毛染めへの使用が禁止されたことがあったそうです。しかし、それではきれいな色が出ないことで消費者から使用を認めてほしいという声が大きく再び許可されたという話があります。PPDは「究極の染料」と呼ばれることもあるほどです。
3つめの誤解は「パッチテストをしたから安心していた」というものです。パッチテストというのは、毛染めをおこなう前に、あらかじめその製品を腕などに塗ってみて反応が起こらないかどうかをみるテストのことを言います。ただ、本来医療現場で言う「パッチテスト」とは、該当する物質を皮膚に塗布しその上からカバーをかぶせる(まさにpatchです)方法のことを言います。
毛染めで本来のパッチテストをおこなうのは危険です。先に述べたようにかなりの確率でかぶれるわけですから、そのようなものをパッチして密閉すればそのテストで重症の皮膚炎が起こることもあるからです。ですから覆ってはいけません。そしてこのように該当する物質を皮膚に塗布して覆わないテストのことを「オ-プンテスト」と呼びます。しかし、消費者安全調査委員会はなぜかこの名称は用いずに報告書のなかで「セルフテスト」という名称を用いています。(本コラムでも「セルフテスト」と呼ぶことにします)
問題はセルフテストの「判定時期」です。かぶれの正式名称は「接触皮膚炎」といい、接触皮膚炎には2種類あります。1つは「刺激性接触皮膚炎」でこれは該当物質に接触してすぐに(せいぜい15分程度で)症状がでます。もうひとつが「アレルギー性接触皮膚炎」でこれは1~3日程度たたないと判定できないのですが、ここをきちんと理解していない人が多いのです。セルフテストはその毛染めを皮膚にぬってそこを濡らさないようにして少なくとも丸2日は経過をみなければなりません(注2)。「パッチテストをした」と言っている患者さんの何割かは、せいぜい30分くらいしか経過をみていないのです。これでは意味がありません(注3)。
そして4つめの誤解は「このようなかぶれのトラブルが起こったのは毛染め製品の会社や美容院の責任だ」というものです。これは気持ちが分からないわけではありませんが、まず会社の責任は問えません。先にも述べたように、PPDは一定の割合の人がかぶれることが初めから分かっている物質であり、これを前提に製品としているのです。では、会社に責任がないなら、販売者はどうなんだ、美容院はどうなんだ、という疑問を感じる人もいるでしょう。
たしかに販売者にはいくらかの説明義務違反があるかもしれません。しかし薬局ならまだしも、たとえばスーパーの棚に並んでいる毛染めをカゴに入れてレジで精算をおこなうときに、レジ打ちの職員がかぶれの説明をおこなうことが現実的にできるでしょうか。
美容室でなら、毛染めを用いる前に充分な説明をおこない、場合によってはセルフテストを先におこなうべきです。しかし、「美容室で15分間のパッチテスト(セルフテスト)をおこなったから安心と言われたのにかぶれた」と言って受診する人が少なくないのです。これはつまり、その美容師が刺激性接触皮膚炎とアレルギー性接触皮膚炎の区別がついていない、ということを意味しています。同じようなことはエステティックサロンにもいえます。エステティシャンがそのサロンで用いている美容液やクリームなどについて「パッチテスト(セルフテスト)をしました」と言ったときもそのテストを15分程度で済ませていることが多いのです。
これは私の個人的な考えですが、アレルギー性接触皮膚炎やセルフテストのことについては美容師やエステティシャンに任せるべきではないと思います(注4)。知識のある美容師を探すよりも、自身で知識を身につけて、たとえば美容室でヘアダイを勧められたなら、そのサンプルをもらって自宅でセルフテストをおこなうといった対策をとる方がずっと現実的です。つまり「自分の身は自分で守る」べきなのです。
最後に「毛染めトラブルの4つの誤解」をまとめておきます。
1 毛染めのかぶれは主に「アレルギー性接触皮膚炎」。使い続けるとアレルギーになるものであり「これまで使えていたから大丈夫」というわけでは決してない。
2 「これくらいなら我慢できる」は危険。アレルギー症状は次第に悪化する。重症化すれば長期間通院が必要になることも。
3 セルフテスト(パッチテスト)は少なくとも2日以上たってから効果判定しなければならない。方法がわかりにくければかかりつけ医に相談を。
4 充分な知識のない美容師(やエステティシャン)が存在するのは事実。彼(女)らに知識の向上を期待するよりも「自分の身は自分で守るべき」と考える方が現実的。
注1:この報告書については下記URLを参照ください。
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/8_houkoku_gaiyou.pdf
注2:セルフテストを実施するときは原則として丸2日はシャワーもできません。これが患者さんがこのテストをいやがる最大の理由です。ただし、どうしてもシャワーをしたいいう場合は、サランラップなどを用いてその部位を濡れないような工夫をしてもらって短時間シャワーをするという方法もあります。
注3:医療機関でPPAのパッチテストをおこなうことは可能です。本文で「毛染めの(本来の)パッチテストは危険」と述べましたが、医療機関でおこなうPPAのパッチテストは濃度を調節していますので危険性はほとんどありません。下記ページも参照ください。
湿疹・かぶれ・じんましん Q&A Q4 パッチテストをしてほしいのですが・・・
注4:このようなコメントが正しい知識をもった美容師やエステティシャンに対し失礼になることは充分承知しています。しかし「30分のパッチテストをしたから美容師(エステティシャン)に大丈夫と言われた」といって受診する患者さんが当院でも一向に減らないのです。これは、「パッチテスト」の意味が分かっておらず、接触皮膚炎の刺激性とアレルギー性を混同している美容師(エステティシャン)が少なくないことを物語っているのではないかと私には思えます。
投稿者 | 記事URL
2015年10月20日 火曜日
第146回(2015年10月) 疥癬(かいせん)と大村先生のノーベル賞
今年(2015年)のノーベル医学・生理学賞に北里大学特別栄誉教授の大村智先生が選ばれました。大村智先生はこれまではあまりマスコミで報道されることはなかったかと思いますが、我々医師や生物学者の間では知らない者はいないといっていい偉大な先生です。
ノーベル賞を受賞されてから各マスコミが大きく取り上げましたからおよその活躍は一気に日本全国に知れ渡ったと思います。どのマスコミも書いている内容は同じようなもので、伊東市のゴルフ場から採取した土に生息していた細菌(放線菌)から寄生虫の特効薬を開発され、それがいくつかの寄生虫疾患に有効で、特にオンコセルカ症という失明につながる感染症を防いだことがノーベル賞に値する、これまでこの薬(イベルメクチン)で助かった人は10億人にも上る・・・、とこんな感じだと思います。
たしかに、世界に発信する記事であればこれでいいと思うのですが、日本人が日本人向けに書く記事であれば、「日本では、イベルメクチンのおかげで疥癬(かいせん)の治療が大きく進展した」という内容のものが必要です。私の知る限り、大村先生のノーベル賞受賞後の一連の報道で疥癬に触れたものはありません。というわけで、イベルメクチンが疥癬に対してどれだけ優れた薬かということを今回は紹介したいと思います。
以前「ダニ」をまとめたコラム(注1)で紹介しましたが、疥癬はヒゼンダニというダニが原因です。ダニが来す感染症としては、ライム病や日本紅斑熱、あるいはここ数年で報告が増えたSFTSなどが有名でこれらは「マダニ」が原因です。これらは「ダニが病原体を媒介する感染症」なのに対し、疥癬は「ダニそのものが感染症」です。
またイエダニやシラミダニであれば刺されて痒みがでますが「それで終わり」です。痒みはかなり強いですが、ステロイド外用薬を数日間使えば治ります。したがって、これらは感染症ではなく単なる「虫刺され」です。一方、ヒゼンダニの場合は、ダニそのものが人の皮膚の下に潜り、そこに卵を産み付けます。卵が孵化して成虫になるとまた新たに卵を産むことになり、人の皮膚の下で世代交代を繰り返すことになります。つまりヒゼンダニの場合は虫刺されではなく「感染症」になります。
もっとも、ダニが皮膚の下で動き出すと強烈な痒みがでますから、「世代交代」をさせる前に患者さんは医療機関を受診することになり、体内に生息するダニを完全に退治する、つまり治療をおこなうことになります。
では体内に侵入したダニを駆除しましよう、ということになるのですが、これがむつかしいのです。正確に言えば、「大村先生が開発したイベルメクチンが登場するまではむつかしかった」となります。
疥癬というのは老人ホームや老人が多い病院で集団発生します。見舞いに来た家族や医療者に感染することもあります。こういった人たち(見舞いの家族や医療者)が自宅に帰り、自宅で家族に感染させることもあります。疥癬はタオルの共用などでもうつる可能性がありますし、性感染症のひとつでもあります(注2)。
ここでどのような場合に疥癬を疑うべきか、について述べたいと思います。疥癬が湿疹と異なるのは、まず夜間に激烈な痒みが起こるということです。ほとんどの湿疹や痒みをきたす疾患では昼よりも夜に痒くなりますが、疥癬の場合はその傾向が一段と顕著なのです。これはヒゼンダニが夜に皮膚の下で動き回るからです。
痒くなる場所は「皮膚の柔らかいところ」です。特に多いのが指と指の間の皮膚の薄いところで、ここに痒みのあるブツブツがある場合はまっさきに疥癬を疑います。また、陰嚢(男性)や外陰部(女性)の場合も疑うことになります。この場合は全体が痒いのではなく、陰嚢(または外陰部)の一部にできた「しこり」のような部分が痒くなっていることが多いと言えます。
診断は、その部分をピンセットで採取し顕微鏡で確定します。成虫や卵が見つかれば診断確定です。ただし、初期の場合はなかなか見つからず、何度も検査をして始めて確定診断がつくということもあります。
従来、日本の医療機関でおこなわれていた治療は、クロタミトンという塗り薬で商品名は「オイラックス」というものです。この薬は一応「効く」とされていますが、我々からみると効いているという実感がそれほどありません。実際、外国のデータで、「痒みをとる効果はなかった」とされているものもあります。
他の治療としては、過去にはイオウの入浴剤を使うという方法がありました。「ありました」と過去形になるのは、現在この入浴剤は販売されていないからです。この入浴剤、商品名は「ムトーハップ」と言いますが、これが販売中止となった理由は、なんとも理解しがたいというか、この製品を一生懸命に作っていた人たちからするとやりきれない思いがあるに違いありません。(この理由は今回の趣旨と関係がないためにこれ以上の言及は避けます(注3))
イオウの入浴剤がどれだけ効いていたかというと、私の経験でいえば「痒みが改善する」という人はたしかにいましたが、劇的に治るわけではなく、また「まったく効果がない」という人もいました。
海外ではγBHCという「農薬」が使われることがあり、日本でも医療機関が輸入すれば使えないことはないのですが、やはり皮膚に農薬を塗布するということに抵抗のある人は少なくなく、また実際に接触皮膚炎(かぶれ)が起こることもあり、なかなか使いにくいものでした。
このように何をやっても治癒させることがむつかしいのが疥癬で、そのうちに他人にうつしてしまってまた広がって・・・、ということがあり、本当に難渋する感染症なのです。しかも重症型(「ノルウェー疥癬」と呼ばれます)もあり、こうなると腎機能が低下し命にかかわることもあります。
しかし、大村先生の開発したイベルメクチンの登場で疥癬の治療がドラスティックに変わりました。2002年、糞線虫(注4)の治療目的でイベルメクチンが保険適用となったのです。しかしこのときの保険適用は糞線虫にだけであり、疥癬に対して使用するには自費診療となり1錠800円近くもしました。ただ、内服量は体重にもよりますが3~4錠を一気に一度飲むだけですから、数千円の出費で済みます(注5)。
いま、「数千円の出費で済む」という表現をとりましたが、これに反発したくなる人もいるでしょう。たしかに「数千円」とだけ聞くと「高すぎる!」と私自身も言いたくなります。しかし、疥癬のあの辛い痒みを考えると、「数千円でかゆみから解放されるなら安いもの」と思えてくるのです。それくらい、疥癬がもたらす眠れないほどの痒みは辛いものなのです。
そして2006年8月、ついにイベルメクチンが保険診療で処方できるようになりました。これで、疥癬の治療が随分と簡単になり、かつてのように難渋することはほとんどなくなりました。以前のように、リスクを抱えてでもγBHCを使うべきだろうか・・・、と悩む必要もなくなったのです。
大村先生の業績はアフリカで最も大きいのは事実ですが、日本の大勢の患者さんも救われているということをここで強調しておきたいと思います。
***************
注1:下記を参照ください。
はやりの病気第118回(2013年6月)「ダニほど誤解だらけの生物はいない」
注2:私が長年かかわっているタイのエイズホスピス「Wat Phrabhatnamphu(パバナプ寺)」でも疥癬の患者さんは非常に多く痒みで悩まされる人は耐えません。しかし、この施設ではヒト疥癬ではなくイヌ疥癬がほとんどです。イヌ疥癬のダニはヒトを刺しますが、感染はしません。つまりステロイド外用だけで改善します。なぜイヌに接するの?と思われるかもしれませんが、この施設では病棟にいつもイヌがいます。感染予防上よくないのでは?と感じられますが、「郷に入っては郷に従え」なのです。
注3:この理由については下記を参照ください。
医療ニュース2008年12月1日(月)「老舗の入浴剤「ムトーハップ」が製造中止に」
注4:糞線虫は世界的には重要な感染症で熱帯・亜熱帯地方では珍しくありません。一方、日本では九州南部から奄美、沖縄にはありますが、感染者の多くは高齢者であり増加してはいません。糞線虫の治療ももちろん重要ですが、なぜ製薬会社は初めから疥癬に対しても保険適用できるようにしてくれなかったのでしょうか・・・。
注5:保険診療と自費診療を組み合わせることは「混合診療」と呼ばれ禁じられている診療です。入院している患者さんにイベルメクチンを投与したとき、イベルメクチンが自費なのだから入院代も自費になるのではないかという疑問を私は過去にもったことがあります。しかし、本来の入院している疾患とは別のものと考え、疥癬だけを自費診療でおこなうと考えれば混合診療に該当しないと判断されるようです。ただし、疥癬の治療だけを目的として医療機関の外来を受診すれば診察代も含めてすべて自費になるはずです。こういう問題もあり、イベルメクチンが2006年以降疥癬の治療にも保険適用となり我々もほっとしています。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症
- 第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善
- 第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実
- 第264回(2025年8月) 「ブイタマークリーム」は夢の若返りクリームかもしれない
- 第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い
- 第262回(2025年6月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(後編)
- 第261回(2025年5月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(前編)
月別アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (119)