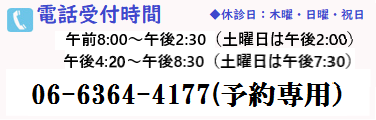はやりの病気
2013年6月15日 土曜日
第18回 風邪に抗生物質は必要か 2005/10/15
私は医師になるまでは、数年に一度程度しか風邪をひいていなかったのですが、医師になってからは、毎年必ず、それも年に数回は風邪をひくようになりました。季節の変わり目はほぼ必発で、今年はインフルエンザにも罹患しました。
なぜ、突然風邪をひきやすい身体になったかというと、過労という問題もありますが、年中風邪の患者さんと接していることが最大の原因です。特に、私は現在も週に一度、小児科の外来を担当していることもあって、子供から風邪をうつされることが少なくありません。子供の咽頭を診察するのは大変で、なかなか口を開けたがらない子供の喉の奥まで見せてもらおうとすると、どうしても唾液が私の顔にかかるのです。
さて、今回は「風邪の適切な治療」について考えてみたいと思います。というのも、最近、一般の(医療従事者でない)ある人から、「風邪に抗生物質を出す医者ってどうなんですかね~」というコメントを聞いたからです。
この人は、風邪で抗生物質を処方するのは過剰診療と考えているようです。こういう意見が出てくるのは、一部のマスコミが「風邪に抗生物質を処方するのはいい加減な医者」というような報道をしているからなのかもしれません。
では、本当に風邪に抗生物質は不要なのでしょうか。
「風邪」というのは、実は定義が曖昧で、こういう状態が風邪、とはっきり示すことはできませんが、ここで医学的に言葉を整理してみたいと思います。
まず、「風邪」とは広い意味では、「鼻から肺にいたるまでの気道に炎症をきたす病原体による急性感染症」となると思います。さらには、「感染性胃腸炎」など、気道よりもむしろ、腹痛や下痢、嘔吐などを主症状とする感染症も「おなかの風邪」などと言われることがあります。「おなかの風邪」まで議論を広げると、ややこしくなりますので、今回は、「気道に炎症をきたす病原体による急性感染症」だけを取り上げてみたいと思います。
さて、「気道に炎症をきたす病原体」には、どのようなものがあるのでしょうか。最も一般的で頻度の多いのがウイルスで、次に多いのが細菌、頻度はぐっと下がりますが真菌(カビの一種)や、さらに頻度は低いものの原虫などによるものもあります。
「風邪」をごく狭い意味で使うと「ウイルスによる気道感染症」ということになると思います。一般的に、このタイプの風邪は、それほど高熱が出ず、症状も軽く、仕事を休むまでもないことが多いと言えます。医学的にはこのタイプの風邪は「感冒」と呼ばれ、英語では「cold」となります。以前、アメリカ人に聞いたことがあるのですが、風邪で会社を休むときは「cold」だと言ってはいけないそうです。「cold」は軽い風邪であるという社会的な認識があり、そんなことで会社を休むのはけしからん、と思われるそうです。
このタイプのウイルスによる軽い風邪には、抗生物質は不要です。抗生物質は、細菌を死滅させることはできますが、ウイルスを殺すことはできませんから、投与しても意味がないのです。このタイプの風邪に抗生物質を処方するのは、たしかに過剰診療であるといえるでしょう。
さて、ウイルスによる風邪がすべて軽症かというとそうではありません。何事にも例外はあるのです。一般的に軽症の風邪をもたらすウイルスは、ライノウイルス、エコーウイルス、コロナウイルスなどですが、インフルエンザウイルスは誰もが知っているように簡単に重症化します。老人がインフルエンザに罹患すると、命にかかわることもあります。
また、一時マスコミを騒がせた「SARS」も、原因ウイルスはコロナウイルスの一種だという説が有力でありますし、小児に感染しやすいアデノウイルスも、ときに入院が必要なほどの重症化をきたすことがあります。このように、インフルエンザウイルス以外にも重篤な症状をきたすウイルスがあるのです。
次に細菌感染による風邪をみていきましょう。細菌感染による風邪は、通常「感冒」とは呼ばれず、炎症の強い部位に応じて、急性咽頭炎、急性扁桃炎、急性気管支炎、急性肺炎などという病名がつけられます。細菌感染は、感冒に比べて、高熱が出ることが多く、咳や咽頭痛などの症状も強くできます。病原体が細菌なわけですから、この場合は抗生物質が非常によく効きます。原因菌は、溶血連鎖球菌、黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌など様々です。(インフルエンザ菌というのは細菌であり、一般にインフルエンザと呼ばれているのはインフルエンザウイルスのことを指します。)
さて、我々医師が風邪症状を呈している患者さんを診察するときには、ウイルス感染なのか、インフルエンザウイルス感染なのか、細菌感染なのかを見極めなければなりません。どのようにして見極めるかというと、これは臨床症状と血液検査、レントゲンなどから総合的に判断するしかありません。このときにどのような病原体に感染しているかということを迅速に判定できればいいのですが、今のところ、迅速に判定できるのは、溶血連鎖球菌、インフルエンザウイルス、アデノウイルスの3つだけです。これら以外は医師の経験に頼るしかないのです。そして、細菌感染と判断すれば、抗生物質を投与し、インフルエンザと診断すれば抗インフルエンザ薬を処方し、通常のウイルス感染と判断すれば、抗生物質は処方しません。
患者さんのなかには、「あなたは一般のウイルスによる感冒だから抗生物質は不要だと思います」と言っても、どうしても抗生物質を処方してほしいという人が少なくありません。先ほど述べたように、ウイルス感染か細菌感染かの判定は、最終的には医師の力量に委ねられ、100%の確信はもてませんから、「これから重症化するかもしれないからどうしても抗生物質を処方してください」と言われれば、現実的には処方することもあります。この点が、抗生物質の過剰投与につながっており、実際、全世界の抗生物質消費量のおよそ4分の1が日本で消費されているというデータもあります。
医師が自分の力量に頼りすぎたために、結果的には患者さんを不幸にさせたかもしれないという症例があります。
以前、3ヶ月の乳児が、風邪症状を訴え、ある病院を受診しました。その乳児の血液検査ではC反応性蛋白(CRP)の値が3.18と軽度であったために、診察医は抗生物質を処方しませんでした。ところが、その後症状が急激に悪化し、10時間後には死亡してしまったのです。病理解剖の結果、その乳児はWaterhouse-Friderichsen症候群という、急激に副腎の機能が低下し、死にいたる病態に移行したのです。
この症例は訴訟になり、医師側が敗訴しました。抗生物質を投与していれば死亡はまぬがれたかもしれないというのが判決理由です。ただ、Waterhouse-Friderichsen症候群は極めて稀な疾患であることと、重症化するのがあまりにも急激なために、たとえ抗生物質を投与していても助かったかどうかは分からないという弁護側の言い分も一部は認められたようです。
一見ただの風邪にみえる症状が実は極めて危険な状態であるということは、それほど多くはありませんが、充分にありえることは知っておいた方がいいでしょう。
1歳1ヶ月の小児が、喘息性気管支炎(小児に多い風邪の一種)と診断され、帰宅したとたんに呼吸困難になり死亡したという事例があります。
子供だけではありません。風邪症状を訴えた35歳男性が、喉頭蓋炎(気管の入り口が腫れあがるため窒息してしまう)をきたし、入院直後に死亡したという例(この患者さんは抗生物質を数日前より投与されていました)もあります。
また、一般開業医を受診した45歳男性は、急性気管支炎、急性扁桃炎と診断され、解熱鎮痛薬を処方され(抗生物質は処方されず)帰宅しました。しかし、その後呼吸困難が出現し、その診療所を再診しました。医師は重症と診断し、すぐに救急病院に行くように指示し、自らは自分の車でその救急病院に向かったそうです。ところが、この男性も急性喉頭蓋炎の状態になり窒息死しました。
このように一言で「風邪」といっても様々であり、薬剤が一切必要ない状態から、直ちに入院して高度な医療を受けなければならないような場合まで様々なのです。
「風邪に抗生物質は必要か」、この問いには、イエスともノーとも言えません。ケースバイケースであり、気になるようなら自分で重症度を判断せずに、医療機関を受診することが必要なのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第17回(2005年9月) 掌蹠膿疱症とビオチン療法
「掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)」という病気が、ここ数ヶ月で一躍有名になったように感じます。その理由は、女優の奈美悦子さんがこの病で苦しみ、その体験を記者会見で発表し、さらに本を出版されたことが大きいように思われます。
私は現在、週に一度、ある病院で皮膚科の外来をしていることもあり、掌蹠膿疱症の患者さんも数人診ています。
典型的な症状は、手のひらと足の裏に水ぶくれのようなものができ、つぶすと白から薄い黄色の膿(うみ)のようなものがでてきます(これを「膿疱」と言います)。強い痒みが生じることもあれば、ほとんど痒くないという人もいます。
奈美さんが体験されたように、掌蹠膿疱症は骨関節炎を伴うこともあり、場合によっては耐え難い激痛が走ります。着替えるのに数十分かかるということも珍しくありません。
しかしながら、掌蹠膿疱症は、適切な治療をおこなうことによって痛みを取り除くこともできますし、薬剤を使用することによって皮膚の症状を治すこともできます。
最近、奈美さんが実施された掌蹠膿疱症の「ビオチン療法」について、患者さんから質問される機会がありましたので、私も奈美さんの書かれた『死んでたまるか!』を読んでみました。
タイトルからも分かるように、掌蹠膿疱症に骨関節炎が伴った場合、耐え難い激痛が走り、このまま死んでしまうのではないか、あるいは、死んだ方がまし、と思われる方もいると聞きます。奈美さんは女優をされていることもあり、激痛以外にも手のひらの症状を隠すのにかなりの苦労をされたことと察します。また、女性であれば(掌蹠膿疱症は女性に多い)女優でなくても見た目の問題にはナーバスになるでしょう。
ビオチン療法の話に入る前に、奈美さんが体験された苦悩について別の角度からみていきたいと思います。
奈美さんは、掌蹠膿疱症という診断がつき治療を開始するまでに随分と多くの病院や診療所をドクターショッピングされています。そして、著書のなかでこのように述べられています。
「内科、皮膚科、整形外科等々、ほとんどの医師は、私の病気「掌蹠膿疱症」という病名があることすら知らなかったのです」
しかし、実際にはこんなことがあるはずがありません。掌蹠膿疱症は「ありふれた」とは言いませんが、皮膚科医であれば誰でも患者さんを診ていますし、皮膚科以外の医師でも知らないなどということはありえません。医師国家試験にも出題される「医師にとっての当たり前の疾患」です。掌蹠膿疱症を知らなければ医師国家試験に合格することはないでしょう。ですから、家庭医(プライマリケア医)はもちろん、たとえ皮膚科や整形外科以外の専門医であろうとも、病気の名前を知らないということはあり得ないのです。
では、なぜ奈美さんはこのような発言をされるのでしょうか。奈美さんが虚偽を言っているとは思えませんし、実際に複数の医療機関を受診されたのも事実でしょうし、かといってこの病気を知らない医者がいるとも思えませんし、謎は深まるばかりです。
さて、話を本題に戻して、この病気を疑ったときにはどうすればいいかを考えていきましょう。
まず、手のひらに皮疹ができる病気というのは多数あります。かぶれ(接触皮膚炎)、水虫、汗疱、掌蹠角化症、梅毒、掌蹠膿疱症などが比較的頻度が高いといえますが、手足口病(子供に多いが大人にもできる)や川崎病(こちらは子供がほとんど)といったものもあります。激しい痒みを伴うものから、ほとんど自覚症状のないものまで、症状は様々です。
治療にうつるまえに、まずは診断をつけなければなりません。問診と皮疹の状態、それに顕微鏡の検査を組み合わせれば、簡単に診断がつく場合がほとんどですから(梅毒が疑われた場合は採血も必要になります)、まずは医療機関を受診すればいいでしょう。「絶対やめてください」とまでは言いませんが、自分で水虫と思って市販の水虫の薬をつけたり、単なる湿疹と思って市販のステロイドを塗ったりするのは危険です。そういうことをすると診断がつきにくくなったり、かえって治癒を遅くすることも多々あるからです。なかには治すために使った市販の軟膏にかぶれて皮疹がひどくなったという人もいます。ですから、初めから医療機関を受診する方が無難です。
皮膚科の診療所が近くにあれば受診すればいいでしょうし、皮膚科がなくても、家庭医の立場にある医師であれば、少なくとも初期の診察はおこなうことができます。
掌蹠膿疱症の診察については、疑った場合、関節の痛みがないかについても確認します。もっとも多いのが胸鎖関節と呼ばれる、鎖骨と胸骨の間の部分です。通常は医師が患者さんのその部位を押さえて痛くないかどうかを確認します。奈美さんは胸鎖関節以外にも様々な部位の痛みを訴えられており、何枚ものレントゲンを撮影することになったようですが、掌蹠膿疱症で骨関節炎を合併するのはそれほど多いわけでなく、押さえても痛みがない場合はレントゲン撮影は通常は不要です。
掌蹠膿疱症が手のひらと足底の皮疹だけであれば血液検査はおこないませんが、関節や骨の痛みがあれば血液検査で炎症の度合いをチェックすることもあります。
治療は、軽症であればステロイドやビタミンDの外用薬だけで様子をみます。症状がでたときのみに使用してもらうこともあります。
外用薬でよくならない場合、次のステップにすすみます。日本では扁桃を摘出したり、歯の治療に使っている金属を外したりといったことをおこなうこともありますが、これらの治療には必ずしも科学的な根拠(evidence)がなく、私は全員には勧めていません。
最近注目されているのは、ある種の免疫抑制剤です。実は、掌蹠膿疱症はT細胞系(白血球のなかにリンパ球と呼ばれるものがあり、さらにリンパ球を分類するとT細胞と呼ばれる細胞があります)の異常であることが分かっており、同じくT細胞系の異常であると言われている、関節リウマチや尋常性乾癬に使用する薬剤と同じものが有効なのです。
最も一般的なのは、メトトレキサート(商品名はリウマトレックス)であり、これを内服することにより症状が劇的に改善したという患者さんは少なくありません。ただし、メトトレキサートは、肝障害や間質性肺炎などの副作用が出現することがあり、使用中は血液検査やレントゲン撮影を定期的におこなう必要があります。(これを怠ると取り返しのつかないことになりかねません。検査を怠ったり、使用法を間違えたために命を落とした患者さんもいますから、医師の指示をしっかり聞く必要があります)
副作用以外に、もうひとつ問題があります。それは、メトトレキサートに保険適応がないということです。欧米では、一般的な治療であり、ガイドラインにも載っているのに、日本では現在のところ、なぜか保険でこの薬を使えないのです(注1)。
シクロスポリンという免疫抑制剤があり、これもかなり有効です。ただし、この薬も保険が使えない上、高血圧や腎障害が出現することもあり、やはり医師の指示をしっかりと聞くことが重要です(注2)。
また、これら以外にも最近注目されている薬剤が次々と誕生しています。先に述べたように、掌蹠膿疱症が関節リウマチや尋常性乾癬の親戚であるらしいということが分かってきて、関節リウマチの薬を掌蹠膿疱症にも使用するような動きになってきているのです。
これら以外には、私は試したことがありませんが、漢方薬や、奈美さんが実施されたビタミン(ビオチン)療法というものがあります。ただし、これらも保険適応がありませんし、これらには科学的な根拠(evidence)がなく、欧米ではまったく使われていません。もちろんガイドラインにも載っていません。ただ、漢方薬やビオチンは、メトトレキサートやシクロスポリンに比べて、副作用が少ないという利点はあるかもしれません。
奈美さんの場合、2004年の8月からビオチンを試されて、2005年の1月に症状が改善してきたそうですが、ビオチンを使用したのはその医師がビオチンだけを薦めたからのようです。(正確には、ビオチン療法だけをしている医師を奈美さんが受診されたようです)
奈美さんは、わらにもすがる思いで、秋田までこのビオチン療法を実施している医師を訪ねられたようですが、最初に、少なくとも欧米では標準的な治療である、メトトレキサートやシクロスポリンを試されてもよかったのじゃないかなと思わずにはいられません。
なぜなら、そういった治療をされている患者さんは短時間で苦しみから解放されているからです。
************
注1+注2(2019年12月25日追記):このコラムを書いたのは2005年の9月です。その後、文中で紹介しているメトトレキサートもシクロスポリンも現在では保険が適応されます。さらに効果のある薬剤も登場しています。ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤 「トレムフィア」という生物学的製剤が保険で使用できるようになったのです。ただし1回325,040円もします。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第16回 子供の肘がはずれた!? -肘内障- 2005/09/15
通常時間の外来であっても、土日や深夜の救急外来でも、「子供の肘がはずれた」とか「肘の脱臼をした」とか言って、病院に駆け込んでくる子供とそのお母さんは珍しくありません。なにしろ、突然子供が泣き出し、腕が上がらなくなるわけですから、お母さんとしては、ただごとではない、と考えて、それが深夜であっても慌てて病院に駆け込むのは当然のことだと思います。
実は、この状態は「肘内障(ちゅうないしょう)」という疾患で、特に珍しいものではありません。いわゆる「脱臼」でもなくて、医学的には「肘関節の亜脱臼」と言います。
「肘内障」がどんなときに起こるかというと、これはだいたい決まっています。しゃがんでいる子供を起こそうと、お母さんが子供の手を持って上に引き上げたときに起こります。引き上げたと同時に、突然子供が泣き出し、腕を上げなくなります。
なぜ、こんなことが起こるかというと、輪状靱帯頚部付着部と呼ばれる、肘の近くの靭帯の一部が子供では希薄だからです。ですから、成長するにつれて、肘内障は起こりにくくなります。
私は、一度小学2年生の子供をみたことがありますが、それは例外的で、何度も繰り返していた子供でも、小学校に入学する頃には起こさなくなるのが普通です。逆に、生まれたばかりの赤ちゃんにもあまり起こりません。1歳の誕生日を迎える頃から、起こりやすくなると言えると思います。これは、ちょうど1歳の頃に、歩き出すようになり、そのため、お母さんが子供の手を引っ張る機会が増えるからです。
「肘内障」は、珍しくないだけではなく、治療も簡単です。解剖学を理解した上で、正しい整復方法を実践する必要がありますが、器具はまったく使わずに、医師の手だけで治すことが可能です。通常は、レントゲンも撮りませんし、再診してもらうこともあまりありません。もちろん、薬も不要です。整復するのに必要な時間は、わずか10秒程度です。
わずか10秒で、腕が上がるようになり、急に泣き止みますから、その光景を初めて見た人は、「おぉぉっ・・・」と声を出す人もいます。実際、医師が尊敬の眼差しでみられる一光景であると言えるかもしれません。
ただし、いくら簡単であると言っても、それは正しい解剖を理解した上で、トレーニングをつんだ医師がおこなうという前提ですから、医師以外の人は試みるべきではありません。肘内障を疑えば、それが夜中でも直ちに病院を受診するべきだと私は考えています。
さて、患者さんであるお子さんは、肘が元に戻れば、それまで苦しめられていた痛みから解放され、突然機嫌がよくなります。お子さんに対してはこれで終了なのですが、我々はお母さんに話をしなければなりません。
お母さんは、「自分のせいで子供に痛い思いをさせた」、という気持ちがあるからです。けれども、このようなことはあまり気にする必要はない、と私は思います。
なぜなら、肘内障は決して珍しい疾患ではなく、多くのお子さんが経験することですし、年齢を経るにつれて、自然に起こさなくなるからです。一度起こすと、何度も繰り返す子供もいますが、それでも後になって何か障害が残るというようなことは普通はありません。
だから、お母さんも必要以上に自分を責める必要はないのです。もちろん、子供の手を強引に上に引っ張ったときに起こりやすいわけですから、これからはそのようなことをしないように注意する必要はありますが、他には特に必要な注意はありません。
私の経験から言えば、肘内障はなぜか同じ日に患者さんが集中するような印象があります。1日に4~5人もの患者さんを診ることもあります。これは、例えば夏祭りなどで、お母さんやお父さんがしゃがんでいる子供の手をひっぱる機会が多いときにもあり、これは理解できるのですが、なぜか、なんでもない普通の日に、夜中に何人も、しかも連続で来られるときがあって、これは不思議です。
「子供が脱臼して・・・」と言って来られるお母さんもおられますが、通常、子供には「脱臼」はありません。肘が動かなくなったときは、肘内障でなければ、「骨折」を考える必要があります。
その骨折とは「上腕骨」の骨折、つまり肘から肩にかけての長い骨の骨折です。そして、子供が肘を動かさなくなったときの上腕骨骨折の代表が2つあり、ひとつは、「上腕骨顆上骨折」、もうひとつは「上腕骨外顆骨折」と呼ばれる骨折です。
「上腕骨顆上骨折」は、子供の肘周囲の骨折で最も多いもので、肘を伸ばした状態で転んだり、転落したりしたときによく起こります。この骨折を起こすと、肘がおかしな方向に曲がってしまい、通常は肘の周囲が腫れあがります。これに対し、肘内障では腫れあがることはほとんどありません。
上腕骨顆上骨折にかかわらず、骨折の場合は、というか、骨折を疑ったときは、必ずレントゲンを撮る必要があります。レントゲンを撮って、どのような骨折なのか、そして上腕骨顆上骨折であった場合には、どの程度のものなのかを見極める必要があります。
この見極めには、整形外科専門医の診察が必要であり、(例えば私のような)家庭医が診察すべき範疇にはありません。だから、転倒や転落をきっかけに肘が大きく腫れたときは、家庭医でなく、初めから整形外科専門医を受診する方がいいかもしれません。(ただし、骨折かどうか分からないような場合や、近くに整形外科専門医がいない場合は、とりあえず家庭医を受診し、骨折であれば、整形外科医を紹介状を持参して受診してもかまいません)
肘が大きくおかしな方向に曲がっている上腕骨顆上骨折では、手術が必要になる場合もあります。骨折が軽度であれば、手術をしなくてもいいこともありますが、この場合でも通常3週間程度はギプス固定が必要です。(ちなみに、私は医学部の三年時まで、「ギプス」のことを「ギブス」だと思っていました)
「上腕骨外顆骨折」は、上腕骨顆上骨折に次いで多い肘周囲の骨折です。この骨折も、軽度であれば、ギプス固定だけで済むこともありますが、肘がおかしな方向に曲がっているような場合には、手術が必要になります。そして、この骨折の場合、最初、肘が曲がっていなくても、ギプス固定をしている間に少しずつ曲がってしまうこともあるので、ギプスを巻いた状態で、週に一度程度はレントゲン撮影をして、曲がっていないかどうか確認する必要があります。
先ほど、「子供の脱臼はない」と言いましたが、上腕骨外顆骨折では、例外的に、肘の脱臼を伴うことがあります。この場合は、手術と同時に脱臼を整復する必要があります。
上腕骨外顆骨折で最も注意すべきことは、そのときは何もなくても、後になって、つまり、成長するにつれて、肘が外側に曲がってしまうことがあるということです。(これを「外反肘変形」と呼びます。)
また、そのときは何もなくても、後になって、手の小指側の神経が麻痺してしまうことがあります。(これを「遅発性尺骨神経麻痺」と呼びます。)
この、後になって出てくる障害は、手術をしたときよりも、手術をせずにギプス固定だけの治療をしたときに多くみられると言われています。だから、この骨折の軽度なものに遭遇したときには、手術が本当に必要でないのかを充分に見極めなければなりません。これには、ある程度の経験が必要で、整形外科専門医が診なければならないというわけです。
ときどき、骨折してもそのまま放っておいたり、整骨院の治療で済ませようとする人がいますが、場合によっては危険なこともあります。子供の肘の骨折ではそんなことはないと思いますが、他の部位で、受傷時には整骨院の治療だけをしており、後になり、骨折していたことが分かり、しかも骨がずれていた、ということが時々あります。
骨折の可能性が少しでもあれば、まずはレントゲンを撮影することが大切なのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第15回(2005年8月) 日焼け -日光皮膚炎-
夏に受診する患者さんの訴えに「日焼け」があります。「日焼け」は炎天下に肌を露出していればほとんど誰にでも起こりえますから、「病気」ではなく単なる「生理現象」と考えている人もいます。
もちろん、軽症であれば単なる「生理現象」と考え、冷やす、安静にする、などの対症療法で、別段医療機関を受診する必要もありません。しかし、度を越して痛みが強いようなら「疾患」と考えるべきです。
そして、疾患としての日焼けは「日光皮膚炎」と呼ばれます。さらに、日光皮膚炎が重症化すると皮膚症状だけにとどまりません。むくみ(浮腫)に始まり、頭痛・発熱・悪寒・食欲不振・吐き気・嘔吐・睡眠障害などが起こることもあります。さらに、重症化すると、一気に血圧が下がり(ショック)、生命の危険が脅かされることもあります。
強い紫外線にさらされた皮膚は、軽症であれば赤くなる(紅斑)だけですが、ひどくなると水ぶくれ(水疱)ができたり、ぶつぶつ(丘疹)とか、ざらざらで厚ぼったい状態(苔癬化)になったりする場合もあります。
季節的には、当然夏が最も多いのですが、海外旅行で強い紫外線にあたって起こすような場合もあり、年中遭遇することがあります。
体感的に最も暑く感じるのは、日本では7月から8月あたりになると思いますが、実は紫外線の量は、5月から6月が最も多いとされています。また、4月の紫外線の量でも、日光皮膚炎を起こすには十分であり、4月頃から紫外線対策をおこなう必要があります。5月から6月の紫外線の量は、12月の2倍半程度だと言われています。しかし、少ない紫外線の量でも肌には様々なトラブルを起こす可能性もあり、シミやシワなどを気にする女性であれば、たとえ12月であっても何らかの紫外線対策が必要になります。
もちろん、緯度によっても紫外線の量は大きく異なり、九州の紫外線量は北海道の2倍ほどであると言われています。
さらに、標高でも変わってきます。だいたいの目安としては、1000メートル高くなるごとに、2割程度、紫外線量が増加すると言われています。
真冬にスキー場で日焼けするのはなぜでしょうか。これは雪面が紫外線を反射するからですが、反射した紫外線は通常の約2倍となります。また、乾いた砂面や水面ではだいたい2割増しとなります。
次に、紫外線を物理的に分類してみましょう。よく化粧品や日用品に「UV」と書かれているのを目にしますが、これは「UltraViolet」の略で、要するに「紫外線」のことです。
紫外線(UV)は3つに分けることができます。UVA,UVB,そしてUVCです。このうち、UVCは地球上に到達しません。これに対し、UVAとUVBは地上まで到達し人体に影響を与えます。一般的には、日光皮膚炎の原因はUVBが原因であるとされていますが、UVAもある程度は関与しています。
UVBはガラスを通過しませんが、UVAは通過します。また、UVAの方が波長が長いため、皮膚の深部にまで到達すると言われています。このため、UVAは日焼けやシミよりも、むしろシワに関与していることが指摘されています。
よく、日焼け止めやファンデーションに「SPF」とか「PA」と書かれていますが、これは、UVBとUVAをどれだけ防げるかということを示しています。
SPFはUVBをどれだけカットできるかの指標です。日本国内の紫外線量であれば、SPF1で、およそ20分間UVBを防げることになっていますが、もちろんこの20分というのはあくまでも目安であり、南の島や標高の高いところに行けばそんなにもたないでしょうし、汗で落ちてしまうこともありますから、適宜考えなければなりません。
よく、単純にSPFの数字が高ければ高いほどいい、と考えている人がいますが、SPFが50を超えるようなものは(なかには100を超えるものもあります)、その効果が疑わしいように思われます。なぜならSPF50の場合、20分x50=約17時間となり、これなら朝に塗布すれば一日中効果が持続することになりますが、炎天下に1日中いれば、日焼けしてしまうこともあるからです。
ですから、うまく日焼け止めを使うコツは、単にSPFの高いものを選ぶのではなく、何度も繰り返し日焼け止めを塗りなおす習慣をつけることです。
PAは、UVAを防ぐ効果を示します。表示はSPFのように数字で示すのではなく、+、++、+++の3段階で示されています。通常、海や山で過ごす場合にも++であれば十分だと思いますが、状況によっては繰り返し塗りなおす必要があります。
もうひとつ、言葉の整理をしておきましょう。日焼けを示す英語に、サンバーン(sunburn)とサンタン(suntan)があります。サンバーンは、真っ赤に腫れあがった皮膚、すなわち、日光皮膚炎の状態を指します。これに対し、サンタンは、炎症がおさまってからの皮膚が黒くなった状態(色素沈着)を現します。日本語では、同じ「日焼け」ですが、英語では、皮膚が赤い状態と黒い状態を別々の単語で区別しているというわけです。
日光皮膚炎の対策としては、もちろん予防が最も大切です。すなわち、紫外線にさらされるときには、あらかじめ適切な日焼け止めを繰り返し塗ることが重要です。
日焼け止めの選択には、2つの点に注意することが必要です。まずは、SPFとPAの値をチェックして、環境にあったものを選ばなければなりません。
もうひとつは、日焼け止めの成分が、紫外線吸収剤か、紫外線散乱剤かということです。紫外線吸収剤には、一般的にパラアミノ安息香酸と呼ばれる物質が使われており、これにはかぶれる人がいます。このかぶれが起こると、日光皮膚炎なのか、この物質による接触皮膚炎なのか、区別がつきにくくなることもあります。ですから、化粧品などでかぶれたことのある人は、あらかじめ紫外線散乱剤を使用するのが無難と言えるでしょう。
日焼け止めによる予防を怠ったり、忘れたりして、日光皮膚炎になってしまった場合はどうすればいいでしょう。軽症であれば、市販の抗炎症剤を使ってもいいかもしれませんが、重症化すれば医療機関を受診しなければなりません。
日光皮膚炎の患者さんを診たときに、軽症であれば、非ステロイド性の抗炎症剤を処方するだけで様子をみますが、それでは炎症がおさまらないような場合には、ステロイドの外用剤を短期間使用してもらうこともあります。また、吐き気や頭痛、発熱などの強い全身症状が出ているようなケースには、ステロイドの内服薬を処方することもあります。さらに、症状が強いような場合、例えば血圧が下がっているときや意識がもうろうとしているときは、緊急入院となります。
日光皮膚炎は、しばらくすると、症状が痛みから「痒み」に変わります。そして、この痒みは、例えば虫刺されや水虫のときのようなかわいらしい痒みではなく、耐え難い劇的なものになります。患者さんは、「こんなに痒いなら痛い方がずっとマシ!」と言います。この場合も、ステロイドの外用を処方します。痒みに対し、ステロイドの内服薬を処方することは滅多にありませんが、抗ヒスタミン薬を内服してもらって痒みを抑えることもあります。
日光皮膚炎は、紫外線以外の要因が原因となっていることもあります。その要因とは「薬剤」です。特定の薬剤を内服したり外用したりすることによって、日光に対する過敏性が強くなり、わずかな紫外線の量でも容易に日光皮膚炎を起こしてしまうことがあるのです。(これを「薬剤性日光皮膚炎」と呼びます。)
具体的な薬剤は、ある種の高血圧の薬や、抗生物質、鎮痛薬、リウマチの薬、抗癌剤、精神科の薬、抗てんかん薬、などです。また、外用薬では痛み止めの湿布や塗り薬で起こることもあります。
治療法は、紫外線のみによる日光皮膚炎のときと同じですが、まずは原因となっている薬剤の内服、外用を中止することが先決です。
もうひとつ、日光皮膚炎をおこしやすくするものがあります。それは「食べ物」です。その食べ物とは、パセリ、セリ、イチジク、ライム、レモンなどです。これらには、日光過敏の原因となるソラレンという物質が含まれていることが原因です。ですから、これらを大量に摂取したり、あるいは美容目的でパックをしている場合にも注意が必要です。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第14回 熱中症 2005/08/13
夏に特有の疾患の代表のひとつが、「熱中症」です。今年の夏も、私自身たくさんの患者さんを診ています。「熱中症」は、猛暑となった年には死亡例が報告されることもあり、「危険な」病気のひとつであります。ただ、一言で「熱中症」と言っても、自宅で安静にして様子をみれるような状態から、ただちに救急救命センターに搬送されなければならないような重症例まで様々です。また、「熱中症」と似た言葉に、「日射病」や「熱射病」というものもあり、言葉が混乱しているような印象を受けます。
今回は、この「熱中症」についてまとめてみたいと思います。
まずは、言葉を整理しましょう。「熱中症」は大きくふたつに分けることができます。簡単に言えば、「重症の熱中症」と「軽症の熱中症」です。何が重症で何が軽症か、最も大きな違いは、「体温が上昇するかどうか」です。体温が上昇しなければ「軽症」、上昇すれば「重症」、ということになります。
さらに細かくみていきましょう。
体温の上昇しない「軽症の熱中症」には、「日射病」と呼ばれるものと、「熱痙攣」と呼ばれるものがあります。
「日射病」は、炎天下で長時間立っていたり、運動中に、特に頭に直射日光を浴びた場合に起こりやすいと言えます。通常、皮膚が高温にさらされると、その部位の血管は拡張し、運動をおこなえば筋肉にたくさんの血流が流れます。そして、多量の汗が出ます。この状態が長時間続くと、血管内の血液量が足らなくなり、いわゆる「循環障害」、つまり「脱水」になります。これが「日射病」のメカニズムです。日射病では、通常、汗が多量に出ており、皮膚は冷たくなっていることが多く、体温は正常か、むしろ低くなっています。
「熱痙攣」は、多量の発汗で、塩分が失われることによって起こります。炎天下で大量に汗をかき、脱水を防ごうと、一生懸命水分を取ったがためにこの状態になることがあります。つまり、血液が薄くなりすぎている状態です。症状としては、痙攣が起こるのが特徴です。筋肉に痛みが伴うことも珍しくありません。また、内蔵の筋肉が痙攣を起こすこともあり、この場合は、腹痛や嘔吐が起こることもあります。
これを防ぐには、水分と一緒に塩分を摂ることが必要です。最もすぐれた飲料水のひとつが、いわゆるスポーツ飲料水です。スポーツ飲料水は、適度に塩分などの電解質が含まれており、汗をかいた身体には最適です。
昔の人は、真夏に麦茶に塩を入れて飲んでいたそうですが、これは「熱痙攣」を予防するのに極めて合理的な対処法です。豊富な種類のスポーツ飲料水は、科学的な考察のもとにつくられていますが、そのような知識のなかった昔の人たちは、経験的に適切な対処法を理解していたのでしょう。
次に、「重症の熱中症」をみていきましょう。重症の熱中症には、「熱疲労」と「熱射病」があります。これらでは、体温が上昇するのが特徴です。なぜ、体温が上昇するかというと、それまで身体が一生懸命体温を下げようと努力していましたが、ついにその努力が追いつかなくなり、体温調節機能が破綻してしまうからです。
「熱疲労」では、多量の発汗、頭痛、めまい、嘔気、嘔吐、筋力低下、視力障害、皮膚紅潮などの症状が出現し、ひどい場合は、動悸、頻脈、頻呼吸、血圧低下などもみられます。しかし、意識を失うことはありません。
「熱射病」では、体温が40.5度以上となり、意識障害が出現します。さらに、発汗が停止していれば、まず間違いなく「熱射病」であります。熱射病の致死率はきわめて高く、10%を超えると言われています。
「熱疲労」を放っておくと、「熱射病」に移行し、最悪の場合、致死的な状態になることもありますから、熱中症の可能性があり、体温が上昇してくるような場合は、迷わずに救急車を呼ぶべきです。
では、どのようにして、熱中症を防げばいいかをみていきましょう。
まずは、「脱水」の対策です。炎天下で運動や作業をすれば多量に汗をかき、脱水に陥ります。通常、高温環境での運動は、1時間に2.5リットル以上の汗をかくといわれています。そして、体重の3%を超える脱水になれば、体温が上昇しやすいことが分かっています。例えば、体重60kgの人であれば、60kg x 3% = 1.8リットルの汗をかけば、体温が上昇するような、すなわち「熱疲労」や「熱射病」といった「重症の熱中症」になる可能性があるわけです。1時間に2.5リットルの汗をかくわけですから、45分程度でこの状態になることもありうるわけです。
これが体重40kgの人であれば、体重の3%は、40kg x 3% = 1.2リットルですから、30分たらずで、危険な状態になってしまいます。
私が子供の頃は、「運動中に水分をとればバテるから水分はとってはいけない」と言われていました。これはひとつには、スポーツ飲料水がまだ普及していなかったということもあり、塩分をとらずに水分だけを摂れば、先に述べた「熱痙攣」の状態になることがあり、部分的には理にかなっている、とも言えるのですが、やはり危険なことです。
現在では、運動中もむしろスポーツ飲料水を積極的に摂取することが奨励されており、テレビでサッカーやバレーボールなどのプロスポーツをみていても、選手が試合中にも積極的にスポーツ飲料水を飲んでいる光景がうつされます。(これはいい宣伝効果になっていますね。)
さて、「脱水」を起こすのは何も高温環境下のみではありません。室温がそれほど高くなくても、湿度の高い状態であれば脱水になることもあります。なかには、室温が25度前後なのに、多湿が原因で脱水になったという症例もあります。お年寄りの方で、クーラーは身体に悪いと信じ込み、真夏でもほとんどエアコンを入れない人がいますが、これも危険です。昔の日本の家屋のように風通しのよい部屋にいるならまだしも、マンションなど現代型の住居にお住まいの方は、積極的にエアコンを活用すべきでしょう。
外にいても「多湿」の状態になり、脱水に陥ることもあります。これは、通気性の悪い衣服を着ている場合ですが、木綿製の作業服でも起こりえます。それは作業服が油まみれになっている場合です。つい先日も、ある病院で外来をしているとき、油で真っ黒になった作業服を着ている作業員の方が、熱中症で救急搬送されてきました。
次に気をつけていただきたいのが、「薬を飲んでいる人」です。薬のなかには、発汗を抑制し、「脱水」に、さらに「熱中症」を引き起こす可能性のあるものがあります。
具体的には、心臓や高血圧のときに使う「βブロッカー」や、前立腺肥大症の治療などに使う「αブロッカー」、また一部の精神症状に用いる「メジャートランキライザー」と呼ばれる薬の一部も相当します。排尿を促進したり、(本来の使い方ではありませんが)一部の人がやせるために使っている「利尿薬」も脱水を引き起こしますし、もちろん違法ですが「コカイン」や「覚醒剤」でも脱水が起こります。
また、薬ではありませんが、アルコール摂取も脱水を引き起こすので注意が必要です。「脱水を防ぐためにビールをたくさん飲んでいる」、という人をときおり見かけますが、これは大きな間違いです。アルコールは摂取すればするほど、体内でアルコールを分解するために大量の水が消費されるからです。
それから、肥満の人も注意が必要です。肥満の人は皮膚がたるんで重なりあっていることが多く、充分に汗が出ないのです。また、極端に痩せている人も注意が必要です。これは体重が少ないと、わずかな発汗でも体重あたりの発汗量が増えることが理由のひとつです。
熱中症は、予防することによってかなりの部分で回避できますし、もしも熱中症を疑ったときも、体温が上昇しているかどうかなどで、重症度が判定でき、救急車を呼ぶきっかけになります。もちろん、体温上昇がなくても、しんどさが普通でないときには救急車を呼びましょう。短時間に体温が上昇し、危険な状態になる可能性もありますし、熱中症以外の重要な病気である可能性もあるからです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第13回 エイズと差別 ② 2005/08/02
神戸で開催されたICAAP(アジア太平洋国際エイズ会議)で、私は多くのことを学びましたが、開会式も非常に印象的なものでありました。
壇上に30人以上のHIV陽性の方が上がられ、インドネシアの女性が代表で挨拶をされました。彼女の言葉は、我々参加者の胸に深く響き渡りました。
予定では、挨拶をするのは彼女ではなく、別の男性だったそうです。ところが、その男性が直前に交通事故に会い、来日ができなくなったそうなのです。彼女は、その男性の交通事故について話しました。
その男性は、事故の直後にある病院に運ばれました。ところが、その男性がHIV陽性であることがわかると、治療を拒否されたというのです。インドネシアでも、HIV陽性というだけで、医療機関から差別を受け、治療を拒否されることが少なくないそうなのです。
彼女は続けました。
「私が、こうしてHIV陽性であることを公の場で発表したことを、私の国のマスコミに報道されて、私の顔が医療機関に知られると、もう私は母国で医療を受けられなくなるかもしれません・・・。」
病気を治すことが使命であるはずの病院が、病気を引き起こす可能性のあるHIV陽性者を差別する・・・こんなことが許されていいのでしょうか。
しかしながら、残念なことに、こういうことは日本にもあります。
現在、医療従事者の間である議論が起こっています。それは、「入院時、あるいは手術の前に、患者さんがHIV陽性でないことを確認せよ」というものです。
なぜ、このような議論が起こるのかを理解していただくために少し説明を加えた方がいいでしょう。
現在、日本のほとんどの病院では、入院や手術の前に、「特定の感染症」の検査をおこなっています。「特定の感染症」とは、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、そして梅毒です。
これらに感染していることが分かると、患者さんは「特別扱い」されることになります。「特別扱い」とは、例えば手術室は他の患者さん用の部屋とは別であったり、同じ手術室を使うとしても、手術の順番が最後にされたり、あるいは点滴や採血の際に、「要注意」というレッテルを貼られます。カルテの表紙には、感染しているという旨を赤色で記載されることも珍しくありません。
少し考えると分かりますが、これはまったくおかしな話です。というのも、感染症は他にもたくさんありますし、また、未知のウイルスもあるからです。前回お話した、日本で120万人のキャリアがいると言われているHTLVも、「特定の感染症」に入れられていません。この3つの病原体だけが、特別視されるのははなはだおかしいわけです。
こういうことをおこなう慣習があるために、日本では、これらの感染症に対して差別がなされるわけです。(HIVほどではないですが、日本の医療機関では実はこれらの病原体を持っている患者さんにもある種の差別があります。)
さて、話を戻しましょう。現在、医療従事者の間で起こっている「入院や手術の前にHIVの検査をせよ」という議論は、「これら3つの感染症にHIVを加えよ」、というものです。
「特定の感染症」が、入院や手術の前に「勝手に」されているのに対して、HIVについては、患者さんの許可を取らなければ検査ができないということになっています。これは、法律で決められているわけではありませんが、おそらくほとんどの医療機関で同意書が必要になっているものと思われます。
これは、当然のことだと思いますが、皮肉なことに、HIVだけが同意書が必要であるために、HIVだけが強い差別の対象になっているように思われます。
おそらく、HIVの検査に患者さんの同意書が必要なのは、患者さんの「プライバシーの権利」と「知りたくない権利」を尊重すべきという理論からだと思います。
しかしながら、そうであるならば、なぜB型肝炎ウイルスなどの検査ではこれらの権利が守られずに、患者さんの同意なしに勝手にされるのでしょうか。一部の医療機関では、HIV以外の感染症に対しても、同意を取るようになってきていますが、全体からみればまだまだ少数派です。
話がややこしくなってきましたが、ここまでをまとめると次のようになります。
現在、入院や手術の前には、B型肝炎ウイルスや梅毒などの検査が患者さんの許可なしで「勝手 に」おこなわれている。これらの病原体に罹患していることが分かると、医療従事者から「特別視」さ れる。
HIV陽性者が増えていることから、入院や手術の前に全員にHIVの検査をおこなうべきだという議 論が起こっている。
しかし、HIVの検査には通常、同意書が必要であることなどから、「勝手に」検査をすることができ ず、現状では全例検査はおこなわれていない。
では、入院や手術の前に、全例HIVの検査をするべきなのでしょうか。
希望する人もおられるかもしれませんが、私は「すべきでない」と考えています。
その最大の理由は、現状では、HIV陽性者に対する医療従事者の差別があるのは明らかであり、感染が分かると、患者さんは入院や手術を拒否される可能性があるということです。
また、全例に検査をおこなうと、医療費が莫大なものになってしまうという問題もあります。
ちなみに、他の先進国では、このような「特定の感染症」の検査はおこなわないのが普通です。
「ユニバーサル・プレコーション」と言って、すべての患者さんは病原体を持っている可能性があるわけですから、いちいちそんな検査をせずに、針刺し事故などにはいつも注意をすべき、という考え方が根付いているのです。
日本も他の先進国にならって、HIVはもちろん、他の感染症についても入院や手術の前の検査はやめるべきだと私は考えています、
さて、医療機関で差別の対象になっているのは、HIV陽性者だけではありません。以前別のところでも指摘しましたが、セックスワーカーの方は医療機関から差別的な発言をされることが多い、という現実がありますし、ゲイやMSM(men who have sex with menの略、要するに男性同性愛者のこと)の方も、医療機関で嫌な思いを体験されています。
例をあげてみましょう。これらは、実際にゲイ/MSMの方々から聞いた実話です。
ある患者さんは、勇気を出して、医師に自分がゲイであることを告げました。すると、その医師は病院の他の複数のスタッフに、「この患者はゲイである」というようなことを大声で伝えたそうです。これでは、プライバシーがまったく守られていません。
また、ある患者さんは、自分がゲイであることを告げてから、以降その病院では、本名ではなく、イニシャルで呼ばれるようになったと言います。待合室でもイニシャルで呼ばれるので、他の患者さんから不審がられています。
自分がゲイであることを話してから、スタッフが急に冷たくなったという話は、いくらでもあります。
最後にもう一度問題提起したいのですが、 「病気を治すことを求めて病院を受診された患者さんを、その病気で差別したり、あるいは職業やアイデンティティで差別したりする」というようなことがあっていいのでしょうか。
次の一文はヒポクラテスの誓いとして掲げられています。
「人種、宗教、国籍、社会的地位の如何によって、患者を差別しない。」
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第12回 エイズと差別 ① 2005/07/16
私は、いわゆる「エイズ専門医」ではありませんし、これからも「エイズ専門医」になる予定はありません。その理由はいくつかありますが、最大の理由は、「エイズの専門治療に専念するのではなく、HIV陽性の方のかかりつけ医となって、風邪や頭痛から、ケガ、あるいは不安・不眠症状やうつ状態などまで、あらゆる症状を幅広くみたいから。そしてエイズ発症者に対しては、エイズ専門医と協力しながら、どんなことでも患者さんと一緒に考えることのできる医師を目指すから」というものです。
先日(2005年7月1日から5日まで)、神戸でICAAP(アジア・太平洋国際エイズ会議)が開催されました。この会議の参加者は、約2,800人で、アジアを中心とした世界中から多くの人が集まりました。通常の学会や国際会議と異なり、参加者は医師中心ではなく、むしろ、HIV陽性の方や、ドラッグユーザー(及びその擁護者)、セックスワーカー(及びその擁護者)、ボランティア、学生、NPO法人・・・、などたくさんの職種の方が集まりました。
通常の学会と異なり、展示場では、複数のグループが、音楽やダンスを披露したり、また夜には、いろんなグループが、神戸のいくつかの店を借り切って様々なイベントを開催していました。
学術的な発表以外にも、多くのワークショップが開かれ、世界中の人と意見を交換することができました。
ただ、ひとつ残念だったのは、日本人の参加者が少なかったということです。発表によると、日本人は800人しか参加していなかったそうです。そして、さらに残念なのは、日本の厚生労働大臣をはじめ、官僚がほとんど参加していなかったということです。WHOや国連のトップの方々はそろって参加されていた、のにです。
これには、世界中の方々が驚いていたようで、「日本のエイズに対する関心が低いことがよく分かった。それが分かっただけでも日本で開催した意味があったのではないか。」と発言されている人もおられました。
これはもちろん皮肉でありますが、日本のマスコミの方の参加が少なかったことも踏まえて考えると、日本ではエイズとは過去の忘れ去られた病気とでも思われているのでしょうか。
さて、エイズについてはお話すべきことが山ほどあるのですが、まずは日本の現状を確認しておきましょう。
厚生労働省の最新の発表では、日本のHIV陽性者とエイズ発症者の累計は、約1万人です。UNAIDSという国連の下部組織の統計では、約1万2千人となっています。よく、「先進国で感染者が増えているのは日本だけ」という言われ方をしますが、これは正確には誤りで、お隣の韓国も感染者が増えており、その上昇の仕方は、日本よりも深刻です。
次に、言葉の定義にうつりましょう。HIVとエイズの違いを言えるでしょうか。実は、正確にこれらの違いを言える人はそう多くはありません。医療従事者のなかにもよく分かっていない人がいます。
HIVとは「human immunodeficiency virus」の頭文字をとったものであり、日本語では「ヒト免疫不全ウイルス」といいます。つまり、HIVとはウイルスの名称です。
次にAIDSですが、これは「acquired immunodeficiency syndrome」の略で、日本語では、「後天性免疫不全症候群」といいます。つまりエイズとは病気の名前です。
そして、ここからがあまり知られていないのですが、エイズとは「単にHIV感染者の免疫力が低下した状態ではない」、ということです。エイズと診断するには、①HIV陽性であること、②特定23疾患のいずれかを発症している、の2つを満たしてなければなりません。
23疾患のそれぞれをここでは述べませんが、有名なカリニ肺炎やカポジ肉腫なども含まれています。ただ、この23疾患にもそれぞれに規定があって、例えば23疾患のひとつである、「ヘルペス感染症」は、「一ヶ月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの」という取り決めがあります。つまり、HIV陽性の人が、性器ヘルペスを発症しても、薬を塗って2週間程度で治ってしまえば、これはエイズではありません。
さて、言葉の定義よりも重要な問題があります。これは誤解している人がいまだに大勢いるのですが、「HIVに感染しても必ずエイズを発症するわけではない」ということです。
現在は、抗HIV薬で優れたものがたくさん開発されており、適切な時期に、専門医の指導のもとで、適切に薬を服用すれば、エイズの発症を防ぐことができます。寿命が縮まるわけではなく、エイズとは「死に至る病」ではないのです。このあたりの情報が適切に社会に浸透していないことが、「いわれのない差別」が発生する原因のひとつではないかと思われます。
また、HIVに感染しても、必ずしも全員が、無治療であってもエイズを発症するわけではない、という事実もあります。これは、現在多くの研究機関によって調査されていますが、どうやら特定の遺伝子を持つ人にこの傾向がみられるようです。
それから、「HIVに感染すると二度と性行為ができない」と思っている人がいるのも残念なことです。実際はまったくそんなことはありません。もちろん、コンドームは必要ですが、HIV陽性者の人も、陰性者と同様、性行為を楽しんでいます。
さらに、母子感染もかなりの確率で防げるということは知っていただきたいと思います。たしかに、少し前までは、HIVの母子感染が問題になっていました。現在でも、例えばタイ国などでは、地域にもよりますが、母子感染が後を絶ちません。
しかしながら、最新の医学をもってすれば、かなりの確率で母子感染を防げるのです。父親だけが陽性者であれば、精子からウイルスを取り除く技術がかなり実用化されていますし、母親が陽性者であっても、専門医が帝王切開することにより、ほとんど感染を防ぐことができるのです。
もちろん、HIVは容易に感染するようなウイルスではなく、HIV陽性者とキスをした、とか、HIV陽性者と鍋をつついた、とか、一緒に風呂に入った、というようなことでは感染しません。
このように考えると、HIV陽性者の方が、社会から差別を受ける理由はまったく見当たりません。性感染は確かに起こりえますが、コンドームを使用することによって完全に防ぐことができます(ただし、オーラルセックスの際にもコンドームを使用しなければなりません)。
血液感染も起こりえますが、こんな病気は山ほどあるわけで、HIVだけが差別されるのはおかしいわけです。
ひとつ例をあげましょう。HTLVというウイルスがいます。これは日本に感染者が多く、日本国内で120万人のキャリア(ウイルスを保有していて病気を発症していない状態の人のこと)がいると言われています。このウイルスは「成人性T細胞白血病」という白血病をおこします。白血病のなかには、化学療法で劇的に治癒するタイプのものもありますが、この白血病は有効な治療法がありません。
また、HTLVに感染すると、「成人性T細胞白血病」を起こさなかったとしても、「HAM」と呼ばれる、神経の病気が起こることがあります。これを発症すると、全身が動かなくなり車椅子の生活を強いられることも珍しくありません。そして、「HAM」の場合も有効な治療法がありません。
そして、HTLVは、HIVと同様、血液と精液に含まれており(ただし腟分泌液には含まれていません)、注射針の使いまわしや性行為で感染します(ただし女性から男性には感染しません)。
HIVに感染しても薬を飲むことでエイズが発症しないのに対して、HTLVは有効な治療法がないのです。ということは、HIVが差別の対象になるのなら、HTLVはもっと差別されなければ論理的な整合性がとれません。
もちろん、私は、日本に120万人いるHTLVのキャリアを差別せよ、と言っているわけではありません。
HIV陽性者やエイズ発症者が、社会的差別を受けるのは、はなはだおかしい、と言いたいわけです。
つづく
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第11回 キズの治療 ② 2005/07/06
「消毒をしない」「ガーゼを使わない」などの、キズの新しい治療法が普及しだしたのは、ここ2~3年のことです。私がこういう治療法を取り入れたのも1年ほど前からです。
それまでは、消毒→軟膏→ガーゼという治療を頑なに守っていただけに、最初はこういう治療をすることにすごく抵抗がありました。
「本当にこれでいいのだろうか」「消毒せずにもしも化膿したらどうしよう・・・」こういう思いが最初の頃にあったのは事実です。
ところが、数例の症例に対してこの新しい治療を施すと、こういう心配はまったく不要で、すごくきれいに治ることを実感するようになりました。
軽度の擦り傷であれば、1日でほぼ完治するのです。
従来ですと、擦り傷には充分な消毒をして(このとき患者さんはものすごく痛がります)、ガーゼをつけます。
そして、「絶対に濡らしてはいけません、お風呂も禁止です。」と言います。その翌日キズをみせてもらいます。
このときガーゼを剥がすわけですが、患者さんはものすごく痛がります。子供なら必ず泣きます。再び同じ作業(消毒→ガーゼ)をおこなって、しばらくは毎日病院に通ってもらうのです。
それが、傷口を消毒せずガーゼも当てず、傷口を水道水で洗浄した後、特殊な材質でできた被覆剤をあてるだけで、そして、毎日消毒するのではなく、そのまま数日間放っておくだけで、きれいに治っているのです。実際には、念のため翌日に来てもらって、痛みの様子と傷口の様子を観察させていただくことも多いのですが、私の経験では何か問題があったことは一度もなく、そのままにしておきます。
「どちみちかすり傷なんて放っておいても治るんだから、従来の消毒とガーゼの治療でも、水道水の洗浄と特殊な材質の被覆剤の治療でも、そんなに変わらないんじゃないの?」、そう思う人もおられるでしょう。
では、従来何をやっても治らなかったキズについてはどうでしょう。
例えば、長年糖尿病を患っている患者さんが、足に潰瘍(”ただれ”のひどい状態)ができると、これはなかなか治りません。糖尿病は「血管の病気」ですから、キズを治すのに必要な物質が、血管障害のためになかなかキズ口に届かないことや、糖尿病ではばい菌に対する抵抗力が落ちているために、キズがきれいになりにくいことが原因です。
私が診察したある患者さんは、いくつもの病院でいろんな治療をおこなってきましたが、足にできたキズが一年近くも治らないという状態でした。私は、その患者さんに、キズの新しい治療法の話をして、水道水で洗浄した後、特殊な材質の被覆剤を貼って、一週間後に再診するように言いました。それまで、どこの病院に行っても、「毎日消毒に来るように」と指示されていたその患者さんは、少々驚いたような表情をされました。私がおこなった治療は、消毒をしない上に、一週間ほったらかしにしていてください、というものですから、患者さんが驚くのも無理はなかったのでしょう。
一週間後、患者さんはやって来ました。キズがよくなっているかどうか、少々緊張しながら、そしてその緊張をできるだけ隠して、私は被覆剤を剥がしました。尚、ガーゼと異なり、被覆剤を剥がすときにはほとんど痛みがありません。
私は驚きました。一年間どんな消毒や軟膏処置をしても治らなかったそのキズが、わずか一週間で、そして一切の消毒液や軟膏を使用せずに、完治していたのです。一週間前にはたしかに潰瘍の状態だったそのキズが、新しいピンク色のきれいな表皮に置き換わっていたのです。これには患者さんも驚いていたようです。信じられない、という言葉を何度も繰り返していました。
もうひとつ、例をあげましょう。今度も糖尿病の患者さんです。靴擦れから足に潰瘍をつくり、近くのクリニックで消毒処置を受けていたけれどもいっこうに改善しないということで、そのクリニックから私の勤務する病院に紹介された患者さんです。
その患者さんの潰瘍は、あきらかに化膿しており、ガーゼを剥がすとひどい悪臭が漂いました。化膿しているというのは、そのキズに細菌が繁殖しているということで、この細菌をやっつけないことにはキズは治りません。「細菌がいるなら、それを殺せばいいわけだから消毒処置をおこなう」、従来の治療法ではそのように考えます。
しかしながら、最近では、「化膿したキズは消毒では細菌が死滅しない」ということが言われています。私は患者さんに説明して同意を得た上で、キズを消毒せずに、水道水の洗浄だけをおこない、抗生物質を処方しました。そして、被覆剤を貼付して1週間後に再診するように言いました。
1週間後、おそるおそる被覆剤を剥がすと、キズの大きさ自体はほとんど変わっていませんでしたが、深かったキズがやや浅くなり、赤みを帯びていました。そして悪臭はなくなっていました。ただ、ジュクジュクした状態は、目で見た感じは一週間前よりもひどくなっていたため、患者さんからすると、なんだ、全然よくなっていないじゃないか、というような状態でした。
しかし、私はこの状態を改善していると判断しました。患者さんに、この治療法をもう少し続けてみるよう話をし、一週間前と同じ処置、すなわち、水道水での洗浄と被覆剤の貼付をおこないました。そして一週間後の再診を言いました。
そして翌週、大きな改善はないものの、またキズが浅くなっていました。再び同様の処置をおこない、そしてまた翌週・・・。
初めてキズをみた日からちょうど四週間後、ついにキズはふさがり、まだまだ薄っぺらいもののきれいなピンク色の新しい皮膚ができていました。これで治療は終了です。私は、初診のときから、糖尿病の治療のために、食事指導や運動指導などの生活指導をしており、糖尿病の経過観察の目的で当分の間、この患者さんには通っていただくことになりましたが、キズの治療はこれで完全に終了です。
やっかいなキズのひとつに、出血の続いているキズがあります。縫いやすい部位であれば止血目的で縫合することもあるのですが、縫合処置をするには麻酔が必要ですし、子供の場合であれば縫合している間じっとしているのがむつかしいこともよくあります。そのため数人で押さえつけなければならないこともあります。また、顔面をうって鼻血が続いているようなときもやっかいです。この場合はお年寄りで血を固まりにくくする薬を飲んでいるような場合に顕著です。
そういうときに、大変有用な被覆剤があります。これは被覆剤というよりも不織布のような形状をしており、出血している部分にちぎってあてます。すると、この材質の強力な吸水力により、ひどかった出血が止まるのです。
これを使うことによって、子供のキズも痛みなしで治療をこなうことができます。従来の治療だと、消毒と麻酔でかなりの痛みが伴いましたし、連日おこなう消毒処置で消毒の痛みとガーゼを剥がす痛みがあったわけです。
また、老人の鼻血などでも、従来では血管を収縮させる薬剤をしみ込ませたガーゼを鼻のなかに入れて、しばらく圧迫目的で押さえてなければなりませんでしたが、この被覆剤、というか、ちぎった不織布をつめるだけで簡単に止血できてしまうのです。
ここまで書くと、どんなキズでもこの新しい治療法をおこなうと、医師でなくても簡単に治せそうな感じがしますが、次に、必ず医師の(ある意味では高度な)処置が必要なキズの処置をご紹介しましょう。
それは、土やアスファルトがキズの中に入ってしまっているような場合です。この場合は、洗浄と被覆剤の処置のみであれば、キズあとが目立ってしまいます。例えば土のなかに鉄分が混じっていれば赤いキズあとが、アスファルトなら青いキズあとが生涯残ることになります。そして、このようなキズあとを「外傷性刺青」と呼びます。
「外傷性刺青」をつくらないようにするためには、初期治療がすべてです。例えば、若い女性が顔面をアスファルトでこすったようなキズであれば、最初に診察する医師の腕次第で、その女性の人生が大きく変わってしまうと言っても過言ではありません。
こういうケースでは、キズ口の中の異物を取り除く治療が重要です。異物を完全に取り除いてしまえば「外傷性刺青」をつくることがなくなるからです。そのため、麻酔をしてブラシでキズをこすります。患者さんの痛がる表情を見ると、手加減したくなりますが、決して手加減せずに、麻酔を追加し充分にブラッシングをおこないます。この場合は、じっとしていられない子供であっても、おさえつけてブラッシングをおこないます。どれだけ嫌がられようが、憎まれようが、最初にしっかりと異物の除去をしておかないと、その子の人生を不幸なものにしてしまう可能性があるからです。
また、土の中にはやっかいなばい菌がいることが多く、破傷風のワクチンや抗生物質を投与して、キズ口から入ったばい菌が増殖するのを防ぐ治療も必要です。
「病気やケガ・・・」という言い方がよくされますが、実は医学教育のカリキュラムでは「ケガ」のことはほとんど勉強しません。各自が医師になってから自分で症例を通して経験していくというのが現実だと思います。
私の場合は、形成外科で半年間研修をおこなったこともあり、キズというのは好きな疾患のひとつです。その理由のひとつが、キズがきれいに治っていくところを目の当たりにするのがとても気持ちがいいからです。患者さんも嬉しいでしょうが、これは医師も同じ気持ちなのです。
どれだけ医学が発展しようが、キズ自体がなくなることはないでしょう。私はプライマリ・ケア医として、これからもどんどんキズを治していきたいと考えています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第10回 キズの治療 ① 2005/06/16
「生まれてからこのかた一度も病気になったことがない」という人をときおり見かけます。
しかしながら、「生まれてから一度もケガをしたことがない」という人は、おそらくそうはいないのではないでしょうか。
生命保険などのCMで、「病気やケガにそなえて・・・」というのをよく見かけます。病院というと、病気を診てもらいにいくところ、というイメージが先行しがちですが、ケガも病気とならんで医療の対象であります。
今回お話しようと思うのは、ケガのなかでも、いわゆる「キズ(傷)」と呼ばれるものです。キズといってもいろいろで、擦り傷、切り傷、噛み傷、出血の止まらない傷、鋭い傷、鈍い傷・・・、とまさに千差万別であります。
みなさんは、キズを負ったときにどのようにしているでしょうか。もちろん出血が止まらなかったり、骨折を伴っていたりしている場合は直ちに病院に行くことでしょう。これに対し、それほど重症でない、「カスリキズ」のようなものであれば、自分で手当てをされるかもしれません。
ここで、問題を出したいと思います。次の質問に○か×で答えてみてください。
1 キズは消毒するべきである。
2 キズは消毒しないと化膿する(膿む)。
3 キズが化膿すれば消毒すべきである。
4 キズにはガーゼをあてるべきである。
5 キズはぬらしてはいけない。風呂に入ってはいけない。
どうでしょうか。むつかしい質問はあったでしょうか。答えに自信はありますでしょうか。
それでは答えを発表いたします。正解は・・・・、すべて×です。
どうですか。全問正解できたでしょうか。不正解のあった方は、きっとこの正解に疑問を持たれるでしょう。
なぜなら、ケガをして病院を受診されたことのある方なら経験があるでしょうが、通常ケガをして病院を受診すれば、まず消毒をされ、ガーゼを当てられるからです。場合によっては軟膏を塗られることもあります。
今、私が言っているのは、ケガをしたときに、「消毒してはいけない」「ガーゼを当ててはいけない」「キズは乾かしてはいけない」ということなのです。
実は、ここ2~3年で、キズに関する考え方がドラスティックに変化してきています。従来は、「キズは化膿を防ぐために必ず消毒しなければならない」「ガーゼを当てて傷を保護し、決して濡らしてはいけないし、風呂に入ってもいけない」というように考えられていました。
ところが、この考え方に疑問を抱き、問題提起する医師が増えてきました。そういった医師たちは、今までの治療とはまったく異なる、「キズは消毒しない」、「ガーゼは一切使わない」という治療方針をとっています。そして、そういう医師のもとで治療を受けた患者さんは、従来の治療では考えられないほど短期間に、そしてなんと痛みもなくキズが治癒していくのを目のあたりにするようになったのです。
なぜ、「キズは消毒しない方がいいのか」、「ガーゼをあてて乾かせることがよくないのか」についての説明は、少々専門的な解説が必要になるのですが、ここでは簡単にそのメカニズムを説明したいと思います。
まず、「消毒」ですが、実は消毒液は、たしかにバイキンを殺す作用はあるのですが、同時に、正常な人間の組織にまで障害を与えることになります。そして、このために治癒するのが遅くなってしまうのです。
次に、「乾燥」についてですが、一見乾いた傷は治癒に向かいつつあるように見えます。そしてジュクジュクしているキズはバイキンが繁殖していて化膿しているような印象を与えます。ところが、これが間違いで、実は、ジュクジュクの正体は、「生体が出しているキズを治すために必要な化学物質を含んだ液体」なのです。要するに、キズを乾燥させるというのは、キズを治すために必要な物質を取り除く行為なのです。
そして、もうひとつ忘れてはならないのが、キズの治療に伴う「痛み」というのは、「消毒するときの痛み」と「ガーゼをはがすときの痛み」ということなのです。ですから、消毒とガーゼをあてることをやめれば、痛みはなくなってしまうのです!
実際、この治療を取り入れている病院の救急外来や外科病棟のなかには、消毒液やガーゼを一切置いていないところもあるくらいです。
もうひとつ怖い話をしましょう。消毒液のなかには、いわゆる「オキシドール」と呼ばれるものがあります。オキシドールは薬局で普通に買うことのできる消毒液のひとつです。実際にオキシドールを使われた方はお分かりになるでしょうが、キズにオキシドールをつけると、ブクブクと泡が発生することがあります。これはある種のガスが発生するからです。そして、怖いのはこのガスが血管の中に入ることがあるからです。ガスが血管の中に入って肺にまで行ってしまうと、肺の血管が詰まってしまい、急激に呼吸困難になることがあります。これは「肺梗塞」という病態で、そのメカニズムは、足の血管内にできた血の固まりが肺の血管にまでいってしまい呼吸困難に陥る、いわゆる「エコノミークラス症候群」とよく似ています。
もうひとつ、「ヒビテン(グルコン酸クロルヘキシジン)」と呼ばれる、病院ではよく使われる消毒液があります。これが問題なのは、ときおりこの薬剤にアレルギーのある人がいるからです。アレルギーのある人にこの消毒液を使うと、急激に血圧が下がり、呼吸困難に陥り、ひどい場合は命にかかわる事態にまで陥ります。
ちなみに、昔よく使われたいた「赤チン」と呼ばれるものは、キズを乾かすことを主な目的としており、キズの治りを遅らせていただけでした。
要するに、「消毒」というのは、キズの治療に必要どころか、痛みをもたらし、治癒を遅らせ、場合によっては生命の危険を脅かすような状態にまでさせることもあるわけです。
では、キズを負ったときにはどのようにすればいいのでしょうか。まず、大事なのは、病院に行くべきか自分で治療をしてもいいかを見極めるということです。私がよく患者さんに説明するのは、①出血が止まっていて、②土やアスファルトの欠片など異物が傷口に入っていなくて、③犬や猫にかまれた傷ではなくて、④キズがそれほど深くなく、⑤関節を痛めていたり骨折していたりする可能性がなければ、自分で手当てができることも多いというものです。
①の出血については、これは専門的な治療が必要ですし、②の異物については、異物が入ったまま傷の治療をおこなえば、傷跡はかなり汚くなりますし、長期間痛みがとれなくなることもあります。また、「外傷性タトゥー」といって、生涯にわたり刺青を入れたような皮膚になってしまうこともあります。こういう傷跡を残さないようにするためには、やはり専門的な治療が必要です。③の噛み傷については、重篤な感染症を起こすことがありますから、やはり専門治療が必要です。ときどき、けんかなどで人間に噛まれたといって受診される患者さんがいますが、人間の口のなかにはやっかいなバイキンもいて、そういうバイキンが傷口に侵入すると重症化することもあります。④については、例えば腱が切れているような場合は、専門的治療をおこなわないと後になって筋肉が動かなくなることがあります。⑤についても同様で、初期治療が重要になってくる場合が多いといえます。
もしもキズが病院に行くほど重症ではない場合は、自分で治療することも充分に可能です。まず、「消毒」ではなく、しっかりと「洗浄」をしましょう。病院では、生理食塩水で洗浄することもありますが、普通の「水道水」で充分です。日本の水道水は適切な処理がなされており、危険なバイキンが混じっていることはまずありません。
次に、キズを乾かさない環境にしましょう。具体的にどうすればいいかというと、ワセリンを使えばいいのです。ワセリンを傷口にたっぷりと塗ってその上に、ガーゼではなく、台所にあるサランラップをまけばいいのです。これで、キズが乾くことはありません。次にどうするかというと、そのまま放っておくのです。キズの深さや大きさにもよりますが、小さいものなら数日間できれいに治っているはずです。ただ、毎日キズがよくなっていくのを見るのはすごく楽しいことですし、お風呂にも入りたいでしょうから、お風呂に入る前にサランラップを取り除き、シャワーでワセリンを洗い流し、風呂上りに再びワセリンを塗ってサランラップをまけばいいのです。傷口はジュクジュクしていますから、化膿しているのではないかと疑われることもあるでしょうが、痛みがなければまず大丈夫です。(ただ、そうは言っても自信がなければ必ず医療機関を受診するようにしてください。)
バンドエイドというものがあります。キズにバンドエイドを使うのは正しい治療行為でしょうか。従来のバンドエイドは、キズにあてる部分に小さなガーゼが付いています。だから剥がすときに非常に痛いのです。この点からもバンドエイドはおすすめできないのですが、穴が開いていて、空気が通るようになっているタイプのものはキズを乾かすことになりますから、さらにおすすめできません。
最近、まったく新しいタイプのバンドエイドが発売されて話題を呼んでいます。それはJohnson & Johnsonから発売された「キズパワーパッド」という名前のバンドエイドです。これはガーゼの代わりに、ハイドロコロイドと呼ばれる素材を用いています。傷口からキズを治すために出される液体をこのハイドロコロイドで覆って、ジュクジュクした環境を維持させようとするものです。これは、消毒液やガーゼを一切使わない医師がおこなうキズの治療とほぼ同じ理屈です。
「キズパワーパッド」のホームページによると、「3倍早くキズを治す」「キズの痛みをやわらげる」「わずらわしい貼りかえがいらず、最大5日間まで貼ったままでOK」とその特徴が述べられています。
次回は、実際に病院でどのようにキズのこの新しい治療をおこなっているかをご紹介したいと思います。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
第9回 動悸 2005/06/01
日頃、私が外来で遭遇する患者さんの訴えで、もっとも多い症状のひとつが「動悸」です。
もちろん、一言で「動悸」といっても、いろんな種類があり、緊急性を要するものから、まったく治療の必要のないものまでいろいろです。そして、私の経験から言えば、まったく治療の必要のないものもまあまあ多いという印象があります。
睡眠不足が続いていたり、ストレスがたまっていたりしても、動悸を感じることがあるのですが、非常に多いと感じるのが、「健康診断で不整脈を指摘されてから動悸を自覚するようになった」というものです。
こういう患者さんに、「いつ、どんなときに動悸を感じますか?」と質問をすると、「夜、寝ようと思ってベッドに入ると、いつのまにか動悸が始まって眠れない。」と答えることが多いといえます。そして、「動悸が終わるときは自覚できますか。」と聞くと、たいていは、「いつのまにか気にならなくなって眠っている。」と答えます。
この動悸は異常なものでしょうか。そして治療が必要でしょうか。
答えは、否、です。
これは異常なものではなく、結論から言えば、自分の鼓動を感じているだけのことがほとんどです。私は、それを確認するために、診察室の机を指でタップして質問します。指で机を一分間に120回程度のペースでタップして、患者さんに聞きます。「あなたの動悸はこれくらいのペースですか。」すると、ほとんどの患者さんは、「そんなに早くない。」と言います。もし、この時点で患者さんが、「それくらいのペースです。」と答えると、異常な不整脈の可能性があり、精密検査をすることになります。
「そんなに早くない。」と答えた患者さんには、今度は一分間に80回程度のペースでタップして、「ではこれくらいですか。」と聞きます。すると、大部分の患者さんは、「はい、それくらいです。」あるいは「いえ、もうちょっと遅いです。」と言います。
患者さんがこのように答えた場合は、異常な動悸である可能性はほとんどありません。単に自分の心拍を感じているだけだからです。
では、なぜ今まで感じなかった自分の鼓動(心拍)を突然感じるようになったのでしょうか。それは、生まれて初めて健康診断で不整脈を指摘されて、自分の心拍が気になるようになったからです。
私はこのような患者さんを診るようになってから、自分でも確認してみました。夜、静かな環境で横になって自分の鼓動を意識するのです。最初のうちはなかなか上手くいきませんでしたが、そのうちに自分の鼓動がはっきりと自覚できるようになりました。つまり、少し訓練すれば誰でも自分の鼓動を自覚することができるのです。もちろん、そんなことできても何の得にもなりませんし、あえてする必要はありませんが・・・。
動悸を訴えて来院された患者さんには、私は一応、全例に心電図の検査を受けてもらうようにしています。心電図が正常で、自覚する心拍数が1分間に100回以下で、規則的な心拍であれば、異常であることはまずありませんから、私はそれを患者さんに話して、それ以上の検査や治療が必要でないことを説明して納得してもらうようにしています。
心電図に異常がある場合はどうでしょうか。動悸で受診される患者さんは、「健康診断で不整脈を指摘されて・・・」というパターンが多いわけですから、外来で検査した心電図にも不整脈があることがあります。しかしながら、治療が必要な不整脈というのは全体からみれば、ごくわずかです。たいがいは、「期外収縮」といって、規則的な心拍にときどき不規則な波形が混ざっているものです。これを自覚することもあるのですが、ほとんどは治療の対象になりません。実は、「期外収縮」は健康な人の多くにもみられる不整脈で、ほとんどの人が24時間連続で計測できる心電図をとると、一度や二度は出現します。
ところで、心臓は一日に何回拍動するかご存知でしょうか。計算すればすぐに分かりますが、仮に1分間に65回の心拍数とすると、65x65x24=約10万回となります。10万回も拍動し、それが人間の活動や精神状態によって早くなったり、遅くなったりするわけですから、たまには「誤作動」も起こるというわけです。そして、この誤作動は治療する必要がないのです。
心電図に明らかな異常がなくても、完全には「治療が必要な不整脈がない」とは言えません。なぜなら、心電図の検査をしているときには正常でも、家に帰ってから危険な不整脈が出現している可能性があるからです。私は、このような疑いのある患者さんには、24時間連続で心電図の検査をすることをすすめています。24時間連続の検査といっても、入院する必要はなく、小さな器具(電極)を身体に装着してもらって帰ってもらいます。その日は風呂に入ることはできませんが、普通に日常生活を過ごしてもらってかまいません。そして後日、身体に装着したその器械を持ってきてもらえば、その24時間の心臓の動きが分かります。
「あるとき突然動悸が始まって、突然終わる。しかし、毎日起こるわけではなく、数日に一度程度でしか起こらない。」という患者さんがいます。このように訴えるケースは、治療が必要であったり、あるいは注意深い経過観察が必要であったりする場合があります。このタイプの動悸には、24時間連続の心電図検査が無駄になることもありますから、胸に器械を装着してもらったまま数日間過ごしてもらい、「動悸があったときにこれを押してください」と言って、ボタンを渡しておきます。患者さんは、動悸を感じるとそのボタンを押し、そのときの心電図が医療機関にFAXされてくるという仕組みになっています。(21世紀の医療はこんなに発達しているのです!)
来院時に動悸が続いていることもあります。これは昼間の外来よりも、夜間の救急外来を受診する患者さんに多いと言えます。この場合、直ちに心電図をとり、不整脈を確かめ、治療が必要であれば、抗不整脈薬を投薬することになります。飲み薬を飲んでもらって、しばらくベッドで休んでもらうという方法もありますが、入院できる環境であれば、静脈内に直接薬剤を投薬することもよくあります。
心電図のモニターを見ながら、ゆっくりと薬を注射していきます。しばらくすると、乱れていた心電図の波形がきれいに正常の形に戻り、心拍数も正常になります。医師の自己満足と言われるかもしれませんが、この瞬間は「感動!」です。もちろん患者さんもその瞬間に、「先生、ラクになりました!」と言ってくれます。(ただ、抗不整脈薬の注射は簡単なものではなく、投与量や速度を間違えると取り返しのつかないことにもなりかねないので、ある程度の経験をつんでいないとできません。)
注射でもその不整脈がよくならない場合、患者さんの同意を得て、電気ショックをかけることもあります。この場合は、麻酔も必要になり、それなりのリスクはありますが、もっとも確実な方法のひとつとも言えます。
夜間に動悸を訴える患者さんの心電図をとって、緊張感が走ることのひとつが、その心電図が「心筋梗塞」を示しているときです。通常、心筋梗塞では「動悸」ではなく「胸痛」を訴えることが多いのですが、なかには「動悸」と表現して受診する人もいます。(その逆に、心拍数の早い不整脈を「動悸」ではなく「胸痛」と表現する人もいます。)
病気のなかには「少しなら待てるもの」と「一刻を争うもの」があり、心筋梗塞は後者です。この場合は、すぐに採血し、点滴をとって必要な薬剤の投与を開始し、胸部のレントゲンを撮影し、同時に専門医を呼びます。その病院に「循環器内科」の専門医がいなければ、専門医のいる病院を探して救急車で搬送します。
ひどい「貧血」があれば「動悸」がおこることがあります。よく遭遇するのが、不規則な食生活を続けている若い女性が真っ白な顔をして受診するケースです。昔から「血を増やすには鉄が必要」と言いますが、これはその通りで、体格は普通でも鉄分が不足している女性(男性は少ない)が、「鉄欠乏性貧血」を起こし「動悸」を訴え受診することは珍しくありません。
また、なかには、「動悸」で受診し、ひどい貧血が分かり、その原因が「白血病」であったというケースもあります。
詳しい血液検査をして「甲状腺機能亢進症」が見つかったというケースも珍しくありません。
「神経症」や「うつ状態」があって、その結果、ときどき動悸が出現するということもあります。
「動悸」を訴えて受診される患者さんは、精密検査も治療も必要のないことも多いのですが、直ちに治療が必要な、重篤な心臓の病気であったり、また心臓以外の病気が原因になっていることも少なくありません。
「たしかに動悸は気になるけど、たいしたことないって言われそうだから病院に行かない方がいいのかな・・・」そんなふうに考える人もいるかもしれませんが、「たいしたことがないことを確認する」のも医師の務めなのです。気になる方は遠慮せずに受診するようにしましょう。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症
- 第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善
- 第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実
- 第264回(2025年8月) 「ブイタマークリーム」は夢の若返りクリームかもしれない
- 第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い
- 第262回(2025年6月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(後編)
- 第261回(2025年5月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(前編)
- 第260回(2025年4月) 人工甘味料はなぜ太るのか
月別アーカイブ
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (119)