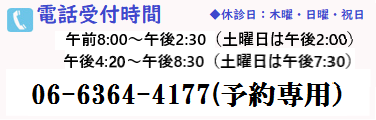マンスリーレポート
2013年6月15日 土曜日
2013年 6月号 やはり医師とは聖職なのか
社会保障制度改革国民会議というものが2012年11月から開催されています。この会議は、社会保障制度改革推進法に基き改革を行うための審議で、詳しくは首相官邸のホームページで知ることができます。
2013年4月に開催された第9回の会議では、日本医師会会長の横倉義武氏が出席し、現状の医療や制度改革に関する意見を表明しています。報道によりますと、この会議のなかで今後の日本医師会の役割についての質問があり、その質問に対して横倉会長は次のように述べたそうです。
「医師たるもの、医師になった時から、自分の人生は、国民のために身をささげるという決意」(注1)
私はこの報道記事を読んだとき、眠たかった頭を何かに殴られたような衝撃を受けました。もちろん医師は、つねに医学の知識と技術の習得に努めなければならず、教養を深めるだけではなく、人格を高める努力を続け、社会に貢献しなければなりません。そして営利目的の医業をおこなってはなりません。
このあたりは、日本医師会が作成している「医の倫理綱領」(注2)に記載されています。私は、太融寺町谷口医院(開院当時は「すてらめいとクリニック」)を開院してからは、自分のミッション・ステイトメント、クリニックのミッション・ステイトメントの次にこの「医の倫理綱領」をよく読むようにしています。そして、そこに書かれていることを遵守するよう努めているつもりです。
しかし、改めて医師会の会長から「自分の人生は国民のために身を捧げる決意」と言われると、私には本当にそこまでの「決意」があるのか、と自問しないわけにはいきません。国民のために身を捧げる・・・、とはどういうことなのでしょうか。文字通り棺桶に足を入れるその瞬間まで国民のために身を捧げる努力をしなければならない、ということなのでしょうか。
医師だけが参加しているメーリングリストや掲示板をみていると、ときどきこのことに思いを巡らせている医師の投稿があります。例えば最近私が興味深く読んだのは、もうすぐ還暦を迎えるというある医師(開業医)の投稿です。
その医師は最近高校の同窓会にでかけたそうです。同窓生には公務員も民間企業のサラリーマンもいて、同級生ですから全員が定年間近の年齢ですが、すでに早期退職をして悠々自適の生活をしている級友もいたそうです。
すでに退職している同級生も、もうすぐ退職する同級生も、今のところ仕事を続けたいと言っている人はおらず、早期退職した同級生のひとりは、好きな読書の傍ら天気のいい日は庭の野菜を栽培するという文字通りの晴耕雨読の生活をしているそうです。これから定年退職を迎える同級生たちも、定年後はゴルフ三昧の生活や、日曜大工を「日曜だけでない大工」として趣味に生きたい、と話しているとか。
その医師によれば、ここ数年は同級生が集まれば今後どのような生き方をしていくべきかといった話ばかりになるそうです。同級生のほとんどが好きなことをする、趣味に生きる、と言っているのに対し、その医師は、医師は聖職であり今後も地域医療のために開業医を続け患者のために一生を捧げるつもり、とその投稿を結んでいました。
もうひとつ、最近私が驚いた出来事を紹介したいと思います。私が大学病院の皮膚科で研修を受けていた頃、最も感銘を受けたのが石井正光教授でした。石井先生は、私が学生の頃から大変印象深い先生で、講義でも「ステロイド一錠減らすは寿命を十年延ばす」という話をされ、従来の治療と同様に、あるいはそれ以上に、生活習慣の改善が皮膚疾患を改善させるということを強調しておられました。
研修医の頃は石井先生の外来も見学させてもらったことがありますが、常に患者さんの立場にたった治療を実践されていることがよく分かりました。たしか2年くらい前だったと思いますが、ある皮膚科関連の学会のある会場で石井先生を数年ぶりに見かけました。そのときその会場では「患者の片足を切断せざるを得なかった症例」の報告がなされていたのですが、その発表を聞いた石井先生はさっと挙手され、「本当に切断が必要だったのか。他に治療方法はなかったのか」ということを繰り返し尋ねておられました。患者さんの側からみたときの最善の治療をとことん追求されている姿が大変印象的でした。
その石井先生が今年3月に大学病院を定年で退官されました。しばらくして石井先生からいただいた葉書を見て私は驚きました。これからの人生はゆっくりと過ごされるのかなと思いきや、なんと早速5月からクリニックを開業なさったというではないですか。これまで多くの患者さんに感謝され、多くの医師に影響を与えてこられた先生ですが、まだやり残していることがあるとお考えなのかもしれません。そして、聖職としての医師の使命をまっとうされたいという気持ちもお持ちなのでしょう。
現在40~50代の世代では定年後も働きたいと考えている人が少なくないという話をときどき聞きますが、多くは年金の不安などから、食べていくために働かなければならない、という意見だと思います。
一方、石井先生や、その前に述べた開業医の先生も、さらに冒頭で述べた医師会会長も「お金のためにこれからも働く」と考えているわけではありません。医師の所得や資産は世間の人が考えているほど多くありませんが、それでも定年まで働いたなら贅沢をしなければその後は年金だけでやっていけるでしょう。にもかかわらずこれからも仕事を通して社会貢献されるというのですから、やはり医師は聖職と呼ばれて然るべきなのかもしれません。
けれどもよく考えてみると、定年後も社会貢献に身を捧げる人は医師だけではありません。2011年12月、享年88歳で他界された谷口巳三郎先生は、定年退職後単身でタイに渡り、一時は破産寸前にまで追い込まれながらもタイ北部のパヤオ県で農業指導を文字通り死ぬまでおこなわれました(注3)。
JICAにはシニア海外ボランティアという制度があり、69歳までならJICAのスタッフとして海外でボランティア活動をおこなうことができます。定年退職後に参加しアジア・アフリカ諸国に日本の技術を伝えにいく人が少なくないと聞きます。もちろん国内でも退職後にボランティア活動に従事している人は大勢います。
たしかに、定年退職後も、あるいは生涯にわたり社会貢献に身を捧げるのは医師だけではありません。また医師のなかにも退職後悠々自適の生活をしている人もいるでしょう。私は過去に何度かタイの外国人が集まるカフェやバーで「医師を引退してからタイでのんびりしている」というヨーロッパ人の元医師と話したことがあります。退職後にのんびりと生活している元医師を責めることはできません。
しかしながら、医師という職業は、社会から強制されることはないにしても、生涯に渡り社会貢献することを期待されている、つまり社会から「聖職」と見なされているのは事実でしょう。
これから医師を目指す人にはそのあたりのことも考えてもらいたいと思います。そして私自身も今後どのようなかたちで社会貢献すべきなのかについて考えていきたいと思います。
注1:記事の原文では、「国民のために身のためにささげるという決意」とされていますが、これは正しくは「国民のために身をささげるという決意」だと思いますので訂正したものを記載しました。原文は、医療系サイトm3.comの「医療ニュース・医療維新」の2013年4月22日号で、タイトルは「かかりつけ医、定額報酬も可 日医横倉会長、第9回社会保障制度改革国民会議」です。
注2 日本医師会が作成している「医の倫理綱領」は下記のURLで読むことができます。
http://www.med.or.jp/doctor/member/000967.html
注3:谷口巳三郎先生については、NPO法人GINA(ジーナ)のサイトで何度も取り上げています。興味のある方は下記「谷口巳三郎先生が残したもの」を参照ください。
参考:GINAと共に
第67回(2012年1月)「谷口巳三郎先生が残したもの」
第33回(2009年3月)「私に余生はない・・・」
第14回(2007年8月)「リタイア後の楽しみ」
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
2013年5月号 薬局との賢い付き合い方(後編)
前回のコラムで取り上げた2つの薬剤師の例は、いずれも大変問題であり、そのような薬剤師しかいない薬局は利用しない方がいいでしょう。
では、なぜ2つの例にみた薬剤師は、ほとんど何の説明もなくロキソニンSを初めての客(患者さん)に販売したのでしょうか。おそらく薬剤師も、ロキソニンSの危険性については知っているはずです。(そうでなければ国家試験に合格しません) にもかかわらず説明もなく販売したのは、あまりにも客が多くて説明する時間がなかった、ということでしょうか。しかし、1つめの例にあげたAさんによれば、特に薬局は混んでいなかったそうですし、2つめの例の日経新聞の記事からもそのような様子は伺えません。それに、いくら混んでいても必要最低限の説明はしなければなりません。これらのケースでは、売れるものは売ってしまえ、という営利的な考えをその薬局や薬剤師が持っていると考えざるをえません。
過去に私は個人的に薬剤師に対してネガティブな感情を持ったことがあります。数年前、見ず知らずの薬局から突然メールが届きました。何やら重要な話があり会ってほしい、とのことで私は会うことにしました。
その薬局の代表者ともうひとりの薬剤師がやって来て私に言ったのは、「すべてお金を出すからクリニックを開業してくれないか」というものでした。「繁華街にひとつビルを持っていてその1階で薬局をしている。開業に必要な資金はすべて出すからそのビルで開業してほしい」、というのです。一見、医師からみてもこの提案は条件のよい魅力的なものにうつるかもしれません。
しかし私はこの提案を断りました。話をしていくなかで、この人たちは信用できないのではないか、と感じたからです。何を話しても、どのようにして利益を上げるか、という方向に話が向かうのです。
我々医師は、「どのような薬を患者さんに売る(処方する)べきか」、と考えているわけではありません。その逆に、まずは「薬を使わないでいいようにできないか」と考えるのです。つまり、医師の仕事とは、いかに薬を減らすことができるか、と言っても過言ではないのです。高血圧や糖尿病の患者さんに「安易に薬に頼るのではなくまずは生活習慣の改善をしましょう」というのも、抗生物質を出してほしい、と言われて、それが必要でない理由を説明するのも、我々医師は、いかに薬を減らせるか、ということに重きを置いているからです。点滴を希望する患者さんに、まずは水分摂取を心がけてください、と言って不満を言われながらも点滴を断るのもそのためです。
ちなみに「検査」も同様です。先日、じんましんの患者さんに、「原因が知りたいから血液検査をしてください」と言われ、「あなたのじんましんは血液検査をしても異常がみつからないタイプのものです」と言うと、「お金払うのはあたしですよ」と不満を言われましたが「無駄な検査」はすべきでないのです。頭痛を訴える患者さんにCTを撮影してほしいと言われ、「現時点では放射線を被曝してまで撮影する必要はありません」と答えてもなかなか納得してもらえないことがありますが、これは医師がさぼりたいからではないのです。検査や薬をいかに減らすか、これが我々医師の使命とも言えるわけです。
私に開業をもちかけた薬局の話に戻すと、「薬をできるだけ減らすようにする医師(私)と、営利主義の薬局が上手くやっていけるわけがない」、と判断して断ったというわけです。
では、多くの薬剤師が営利のことばかりを考えているのか、といえば決してそういうわけではありません。私が勤務医のときにお世話になっていた薬剤師の方々は、いつも患者さんの立場から薬のことを考えてくれていました。私も含めて医師は、なぜその薬が必要かを理屈だけで判断して処方します。飲みやすさや患者さんがその薬をどのように感じているか、などといったことについてまではなかなか思いを巡らせることができないのです。そもそも医師は薬そのものを見る機会が少なく、患者さんから「あの緑色の少し大きい楕円形の薬・・・」などと言われても、それがどの薬であるかが分からないことが多いのです。
その点、薬剤師であれば、日頃から服薬指導をおこなっていますから、それぞれの薬の形、色などはもちろん、患者さんとのコミュニケーションを通しての経験から、どれくらい苦いかとか後味はどうかとか、そういったことにも熟知していますし、薬の相互作用(飲み合わせ)の知識など医師よりも豊富であることも少なくありません。ですから、薬剤師からの報告というのは医師にとって大変ありがたいものなのです。
それに、私が勤務医の頃お世話になっていた薬剤師の方々は、決して薬を増やすような助言はしませんでした。むしろ、いかにして減らしていけるか、といった観点から私に助言をしてくれていました。ですから、前回例に出した二人の薬剤師や、先に紹介した私に開業をもちかけた薬剤師が特殊な例であり、大半の薬剤師は営利ではなく患者さんの立場から薬について考えているはずだと私は信じています。
しかし、ここでひとつの疑問がでてきます。(大きな)病院で勤務する薬剤師はいいとして、薬局を開業したり薬局で働いたりしている薬剤師は営利目的ではないのか、という疑問です。
薬局と異なり、医療機関の場合は利益がでるのは薬の処方ではなく診察代に対してです。医療機関では、もちろん薬にもよりますが、例えば前回とりあげたロキソニンで言えば、薬局で買えるロキソニンSは1錠あたり56.6円(12錠入り680円)ですが、太融寺町谷口医院(以下、谷口医院)で処方しているロキソニンの後発品は1錠わずか5.4円(3割負担で1.62円)です。利益でいえば1錠あたり0.5円にも満たないのです。
このように医療機関では薬による利益はほとんどなく、また検査でもそれほど利益がでるわけではありません。血液検査は外注しますし(検査会社は儲かると思います)、レントゲンなどはある程度数をこなさないと利益が出ないどころか赤字になります。レントゲンは少量とはいえ被曝することになりますから、ある程度重症でない限り初診で撮影することはありません。このため谷口医院ではレントゲンについてはリース代と維持費のコストの方が高いために毎月赤字を計上しています。
入院や手術をすればそれなりに利益になりますが(ただし諸外国と比べるとこれらも随分安く設定されていることがよく指摘されます)、これらをおこなわないクリニックでは何が利益になるかというと、ほとんどが診察代です。診察代は人件費以外のコストはかかりませんから利益率は大変高いといえます。しかも○分以上かけなければならない、という決まりもありません。つまり30秒で診察を終えても30分かけても診察代は同じなのです。
ですから、入院施設のないクリニックで利益をだそうと思えばどんどん患者数を増やして診察していけばいいということになります。しかし、きちんと診察するにはそれなりの時間が必要で、谷口医院ではだいたい日々60~70人の患者さんを診察していますが、これくらいが限界であり、これでも待ち時間はかなり長くなります。70人を超えると2時間以上待つ人がでてきて、連休明けなどで80人を超えると3時間以上の待ち時間がでることもあります。ときどき1日100人以上、もっとすごいところでは200人以上もひとりの医師で診察しているクリニックもあるそうですが、私にはとうてい不可能です。
話を薬局に戻します。診察代を徴収できない薬局では、薬をたくさん売ることが目的になってしまうのは仕方がないことなのでしょうか。私はそうでないと信じたいと思います。以下は2013年3月27日の薬局新聞に掲載されたコラムです。
「薬局と言うのは郵便局などと同じで公共の側面を持った施設だと思っている。しかし現状の薬局を見渡すと、その役割を十分に果しているとは言い難い」。先日開催されたJAPANドラッグストアショーの中で、クスリのアオキの青木保外志社長は薬局の役割の大きさと責任感について、薬局側が再考する必要があると訴えた。(中略)同氏のいう薬局の「局」は、調剤を実施することはもちろん地域住民の健康に対して責任を果たすことであると続け、「仮に薬局が地域から無くなってしまったら生活が困る。そういうレベルまで高める必要性がある」と語る。
薬剤師の方々がこの考えを忘れない限り薬局に対する社会からの信頼を失うことはないでしょう。つまり、薬局は医療機関と同様「公共の側面を持った施設」であり営利団体ではないのです。日本医師会が制定している「医の倫理綱領」の第6条には「医師は医業にあたって営利を目的としない」とはっきりと明記されています。薬剤師の世界にこれと同様のものがあるのかどうか分かりませんが、きっと薬剤師の根源的な精神は医師と同じものだと思います。
営利を目的とせず患者さんの立場に立った医療をおこなう。これが医師の「矜持」です(注1)。薬剤師には薬剤師の矜持があるはずで、その矜持を忘れていない薬剤師に相談する。これが薬局と賢く付き合う秘訣に他なりません。
注1;今回は医師の悪口を書いていませんが、医師にとんでもない輩がいるのも事実です。2009年に逮捕された奈良県大和郡山市のY病院のY医師は我々医師に衝撃を与えました。マスコミの論調のなかには「このような事件は氷山の一角」としているものもありますが、私自身はこのような例は極めて特殊なものであると信じています。この事件については下記のコラムでも取り上げていますので興味のある方は参照してみてください。
参考:メディカルエッセイ
第79回(2009年8月) 「”掟”に背いた医師」
第86回(2010年3月) 「動機善なりや、私心なかりしか」
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
2013年4月号 薬局との賢い付き合い方(前編)
私は以前から、セルフメディケーションをもっと促進すべき、という考えであり、このサイトのコラムでも何度か意見を述べています。この理由として、我々医療者からみたときには「医師不足の対策になる」というものがありますが、もちろん医療者の勝手な都合からセルフメディケーションをすすめたいわけではありません。
セルフメディケーションは、患者さんからみても多くの利点があります。まず、医療機関を受診し待合室で長時間待たされる、という苦痛から解放されます。次に、自分の健康や医学に興味を持つことにより日頃から体調管理に気をつけるようになります。上手くいけば、それが禁煙につながり、バランスのとれた食事、適度な運動などを促すことになるでしょう。そして、他人に頼らず自立した状態で長生きできるようになります。盲目的に医師の言うことに従っている状態では本当の健康を維持できない、と私は思っています。
そもそも現在のような医師不足の社会では、医師は患者さんと充分なコミュニケーションをとる時間が確保できません。どうしても説明や助言は必要最低限のものとなってしまいます。看護師や栄養士の指導や助言は有用ですが、やはり時間が無限にあるわけではありませんし、そもそも医療者と話をするためには医療機関まで足を運ばなければなりません。
セルフメディケーションを効率よく実践するには「薬局の利用」が有用なはず、です。有用な「はず」としたのには理由があります。私が提案したいのは、自分にあった薬局と薬剤師をみつけてセルフメディケーションを促進しましょう、ということですが、その前に、これを読んだ薬剤師の方々に非難されることを承知した上で、現在の薬局の悪口を言いたいと思います。
先日、ある患者さん(Aさんとします)から驚く話を聞きました。Aさんは頭痛があり太融寺町谷口医院にかかっているのですが、あるとき関東地方のある県に出張に行く時に、私が処方した常備薬のロキソニン(正確に言えばその後発品)を忘れたそうです。ロキソニンは薬局で買えるもの(ロキソニンS)もあることを知っていたAさんは、駅前の薬局に入り「ロキソニンSをください」と言ったそうです。すると、その薬局の店員(薬剤師だと思います)は、「飲んだことはありますか」と聞き、Aさんが「はい」と答えると、それ以上何も聞かれずに買えてしまったそうなのです。
あまりにもすぐに買えたことにAさんは驚いたそうですが、私も驚きました。ロキソニンが危険な薬、とまでは言いませんが、副作用が少ないとは言えません。ロキソニンの副作用では胃痛が有名ですが、これだけではありません。稀ではありますが、重症化する薬疹を起こすこともありますし、長期使用で心臓や腎臓に影響を及ぼすこともあります。私が日々の診療で最も注意しているのはロキソニンによる「薬物乱用頭痛」です。別名「ロキソニン中毒」とも呼ばれるもので、ロキソニンを大量に使用したために、ロキソニンがなければほんの少しの痛みにも耐えられなくなり、ますますロキソニンに依存するようになっていく頭痛のことをいいます。
通常医療機関では、ロキソニンを含めて鎮痛剤の処方には慎重になります。薬局でも初めての患者さんにロキソニンSを販売するときは、「現在他に飲んでいる薬はないか」「ロキソニンはどのような症状に対して必要なのか」「今その症状はどの程度のものなのか」「どれくらいの頻度で飲んでいるのか」などは尋ねなければならないはずです。
こういったことはどこかで問題提起しなければいけない、と感じていたところ、偶然にも2013年4月4日の日経新聞の一面に「薬ネット販売、抵抗は誰のため」というタイトルで、この問題が取り上げられていました。
この記事を書いた記者は、実際にロキソニンSを買おうとして東京都千代田の神保町駅付近のドラッグストアを訪ねて薬剤師に話したそうです。以下、記事を引用します。
薬剤師「初めてですか」
記者「そうですが、代わりに買いに来ました」
薬剤師「では、この注意書きをお渡しください」
記者「これでいいの」。あっけなさに拍子抜けした。
本人でなくてもこんなに簡単に買えてしまったというのです。注意書きを渡すだけなら薬剤師は要りません。その注意書きをロキソニンSの箱に書いておけば事足りるからです。
2009年、厚生労働省は、薬局で販売されている薬の第1類とそれに準じた第2類をインターネットで販売することを禁じました。この禁止令は違法であるとしてドラッグストアなどが訴訟を起こし、2013年1月、最高裁で、厚労省の禁止令は違法との判決がでました。これを受けてドラッグストアは販売を再開しているようです。
厚労省のなかでは、インターネットでの販売に反対する声が依然根強く残っているそうですが、上に紹介した2つの例のように薬局でこれほど簡単に買えてしまうなら、そもそも薬剤師など必要ありませんし、インターネットでの購入と差はありません。インターネットでの販売に反対する関係者らは、薬局では薬剤師が丁寧に説明していると信じているのでしょう。
ここで私の意見を述べておくと、「ロキソニンは薬局で売るのも禁止、インターネットでも禁止すべき」、というものではありません。忙しくて医療機関を受診できない人もいれば、身体にハンディキャップがあり薬局にさえも一人では行けない、という人もいるわけです。そういった人たちには、薬局での購入やインターネットの利用は大変ありがたいものになります。
しかしながら、あまりにも気軽にこのような薬が買えるということには問題があります。今の状態が放置されるとすると、「ロキソニン中毒」となる人が後を絶たなくなるかもしれません。また、過去に一度も飲んだことのない人が、自分の判断でロキソニンを内服するのは危険です。やはり一度は医師の診察を受けるべきです。
ではどうすればいいか。まず、ロキソニンを一度も飲んだことのない人が薬局やインターネットで購入するのは避けるべきです。ロキソニンを処方されたことのある患者さんは、かかりつけ医に、今後薬局でロキソニンSを購入することが可能かどうか確認し、医師が許可すればそれ以降は薬局での購入が可能、とすればいいのです。薬局で、過去に医療機関で処方されたことがあるかを証明すべき、というのであれば、医療機関で発行している「薬剤情報提供書」や「処方せん」のコピーを薬局で提示すれば解決します。そして、その薬局を「かかりつけ薬局」とするのです。
インターネットについては、その「かかりつけ薬局」のホームページからのみ購入できる、とすればいいと思います。こうすれば、複数のインターネットショップからロキソニンを大量に購入することが防げます。もちろん、この程度の対策であれば、例えば、他の薬局は利用していない、と嘘を言って、複数の「かかりつけ薬局」をつくれば、ある程度多量のロキソニンを手に入れることはできます。しかし、完全に自由にインターネットで購入できる状態とは大きく異なります。
というわけで、私は今後「かかりつけ薬局」という概念が普及していくべきだと考えているのですが、先に2つの例でみたような薬剤師しかいないのであれば、この考えを取り下げなければなりません。
実際のところはどうなのでしょう。2つの例のように患者さんを大切にしているとはとても思えないような薬局や薬剤師ばかりなのでしょうか。あるいは、この2つの例が例外であり、大半の薬局には患者さんが頼りにできる薬剤師がいるのでしょうか。
次回はそのあたりを考えてみたいと思います。
参考:
はやりの病気第96回(2011年8月)「放っておいてはいけない頭痛」
メディカルエッセイ第97回(2011年2月)「鎮痛剤を上手に使う方法」
マンスリーレポート2012年4月号「セルフ・メディケーションのすすめ~花粉症編~」
マンスリーレポート2012年5月号「セルフ・メディケーションのすすめ~薬を減らす~」
メディカルエッセイ第120回(2013年1月)「セルフ・メディケーションのすすめ~抗ヒスタミン薬~」
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
2013年3月号 医療者に向いてそうで向いてない人
いつも患者さんのことを第一に考えて行動する医療者・・・、と聞けば、「理想の医療者だ」と感じる人もいるでしょう。しかし、これが行き過ぎると、患者さんにとって、そしてその医療者にとっても、転帰が不幸なものになってしまうことがあります。
もちろん医療者は患者さんのために存在すべきであって、自分本位であることは許されません。しかし、それは自分の「自己」というものが確立していることが前提であり、どれだけ患者さんの立場に立ったとしても、一定の”距離”が必要です。
例を挙げたいと思います。
数年前、NPO法人GINA(ジーナ)の関連でタイにいたとき、私は日本人のある看護学生に出会いました。その学生とはほんの20分程度話しただけなのですが、彼女は大変興味深い話をしてくれました。
その学生は休みの度にアジアの医療施設の見学やボランティアに行っていると話していました。その学生が、アジアのある地域にある外国人の医療者がボランティアで医療をおこなっている施設に行ったとき、その地域の住民があまりにも貧困なことに驚いたそうです。
彼女がその施設に着いて初めて見た患者さんは10歳前後の女の子だったそうです。下痢と発熱でその施設にやってきて、その症状はそれほどひどくなかったのですが、彼女が衝撃を受けたのはその女の子が文字の読み書きができないことだったそうです。読み書きができないのは学校に行く余裕がないからですが、それ以前にノートや鉛筆がその女の子の家族にとってはとても高級なもので簡単に手に入れることができないのです。
そこで彼女は、「ならばあたしがこの子に必要なノートと鉛筆を買ってあげる!」とその施設のスタッフに言ったそうです。すると、そのスタッフに大笑いされ、「そんなことをしたら今日の夕方にはあなたに物をねだる子供が行列をつくるわよ。”優しい”日本人がやってきた、という噂が村中に広がり、すぐにあなたは無一文になるわ」、と言われたそうです。
この学生は大変優秀であり、このスタッフの助言の意味を理解しました。患者さんの力になりたい、という思いが”暴走”すると、ときに自らの身を滅ぼすことにつながりかねないのです。もしも彼女が、このスタッフに相談することなく自分の判断でノートと鉛筆を女の子にプレゼントしていたら、大変なことになっていたでしょう。
私はその看護学生と、それから一度も連絡をとっていないのですが、きっと立派な看護師になられていると思います。アジアのその施設にも、今もなんらかの形で支援されているのではないかと思います。
次の例は、自らを不幸にしてしまった研修医の話です。(私はこの研修医(男性)と直接会ったことがあるわけでなく、ある病院で指導する立場にある医師から聞いた話です)
その研修医(以下、A医師とします)はそのとき内科系のある病棟で研修を受けていました。あるとき摂食障害で食事が摂れなくなった20歳の女性(Bさんとします)が入院することとなり、A医師が受け持つこととなりました。A医師は大変熱心な研修医で、どれだけ忙しくても毎日最低一度はBさんのところに行き、話を聞くようにしていました。A医師の熱意が通じたのか、Bさんは少しずつ食事が摂れるようになり、2週間後には退院できることになりました。Bさんが退院するときに、A医師に「先生のおかげで元気になれました。退院してもちゃんとご飯を食べるから心配しないでくださいね」と話したそうです。
しかし、事はそううまくはいかないものです。他の多くの摂食障害をもつ若い女性と同様、Bさんは退院後再び食事を摂らなくなり、姉に連れられてその病院の外来にやってきました。今度は入院するほどでもないと判断され、数種類の薬を処方され帰宅しました。
その日の夕方、外来でBさんを診察した医師から話を聞いたA医師は、いてもたってもいられなくなりました。カルテから電話番号を調べ「自分の判断で」Bさんに直接電話をしたのです。電話に出たBさんの声には元気がありません。電話では話が噛み合わなかったと感じたA医師は、翌日の土曜日の午後に、なんとBさんの自宅を訪問したのです。電話では不機嫌だったBさんも直接A医師が家まで来てくれたことには感激したようです。しっかり治療を受けることを約束し、そのときはA医師も「来てよかった」と思ったそうです。
しかしその後もBさんの嘔吐は止まりません。精神状態も不安定になり、毎日のようにA医師に電話をするようになりました。A医師はBさんの自宅を訪ねたときに「何かあったら遠慮なく電話してほしい」と言って自分の携帯電話の番号を伝えていたのです。Bさんの電話はエスカレートしていきました。深夜でもおかまいなく電話がかかってきて、ついに「今からすぐ来てくれないと手首切っちゃう!」と言われたそうです。
A医師は心を病み、1ヶ月後には病院を去っていったそうです・・・。
さらに不幸な例を紹介したいと思います。この例はマスコミで報道されましたし、その後週刊誌などがかなり詳しいことまで取り上げましたから覚えている人も多いかと思います。
2002年12月、東京都板橋区にある当時46歳のO医師(実名が報道されましたがここでは伏せておきます)の自宅で当時28歳の婚約者Nさん(同様に実名は伏せます)がO医師に首を絞められ死亡しました。O医師は東京の精神科クリニックの院長であり、Nさんは元患者で、殺害された当時はO医師のクリニックで事務員として働いていたそうです。
この事件が世間の注目を集めたのは、普通では有り得ない医師と患者の恋愛に加え、Nさんに虚言癖があったからです。報道によれば、Nさんは、祖父が有名画家の藤田嗣治(ふじたつぐはる)で、母親は宝塚の元女優、自身の元婚約者は有名なDJでNさんはその男性の子供を身篭ったが、そのDJはエイズで死亡。自分自身も芸術のセンスがあり、坂本龍一と一緒に「戦場のメリークリスマス」を作曲した、と言っていたそうです。
当時のインターネットの書き込みなどでは、Nさんに翻弄されたO医師に同情しているものもありましたが、私はO医師がNさんに騙されていたわけではないと思っています。NさんはO医師の患者であるときに抗うつ薬を処方されていたそうですが、報道されたNさんの言動から推測すると(私がNさんを診察したわけではないので無責任な推測ではありますが)Nさんは「境界性人格障害」に該当すると思われます。
境界性人格障害に虚言癖が伴うのはよくあることで、精神科医のO医師がNさんの言葉を信じていたはずがないのです。そもそも「戦場のメリークリスマス」が流行った1983年はNさんはまだ小学校低学年なのです。
私の分析は、O医師が惚れたNさんに翻弄されたのではなく、O医師のNさんに対する同情心が行き過ぎて悲劇を招いた、というものです。つまり先に紹介したA医師と同じような構図だとみています。ただ、O医師がA医師と異なるのは、いつのまにかNさんに対する同情心が一線を超えてしまった、つまり、医師としての同情心が個人的な同情心に替わり、さらにそれが恋愛感情にまで進展するというタブーを犯してしまった、ということです。
報道によれば、O医師はフランスの哲学者ジャック・ラカンの研究者として一流であったものの(実際にラカンを研究した著作もあるそうです)、どこの医局にも属さずに他の精神科医と距離をとっていたようです。O医師はNさんを殺害した後、自らの命を絶とうとしたそうですが死にきれずに意識不明で救急搬送されました。その後意識を回復し懲役9年の実刑判決が下されています。
今は3月で受験のシーズンです。毎年春になると「医学部を目指しているのですが・・・」というメールをもらいます。医師(や看護師)を目指す人は、「患者さんのために・・・」という気持ちは大切ではあるものの、それが行き過ぎると患者さんを不幸にし、そして自らの身を滅ぼすこともあるということを知っておくべきでしょう。
投稿者 | 記事URL
2013年6月15日 土曜日
2013年2月号 幕末時代の勉強法から学ぶこと
近くにあっていつでも行けるからそのうち時間ができれば・・・と思っていて一度も訪れたことのない場所、というのは誰にでもあると思います。私にとってそのような場所のひとつが「適塾」でした。
適塾は、幕末の蘭学者・医者であり教育者でもあった緒方洪庵(おがたこうあん)が、1845年からおよそ20年間住みこんで開いていた蘭学の私塾です。
私が緒方洪庵に初めて興味を持ったのは、1995年、医学部の受験勉強をしていた頃でした。それまで緒方洪庵という人物についてはあまり詳しく知らなかったのですが、「倫理・政経」のセンター試験対策をしているときに参考書に登場していたことから関心が深まりました。
幼少時に天然痘にかかったというエピソードもあり、その後医学を極め天然痘治療に貢献し日本の近代医学の祖ともいわれた緒方洪庵は、医学部受験を志す者なら知らないわけにはいきません。緒方洪庵は医師としてだけでなく、教育者としても歴史に残る人物で、適塾では日本全国の若者に蘭学を教えていました。
適塾の塾生で最も有名なのが福沢諭吉でしょう。福沢諭吉は優秀な塾生たちのなかでも特に際立っていたようで、入塾するお金がなかったものの教科書を翻訳するなどの条件で住み込みの塾生になり、最年少の22歳で適塾の塾頭にまでなったそうです。しかし、血を見るのがダメだったようで、解剖は苦手で医学よりも蘭学を学んだ、とされています。
話を適塾に戻しましょう。私が医学部の受験勉強をしているとき、その適塾は修復工事が完了しており今でも見学に行くことができる、と聞きました。そこで私は、医学部に合格することができたなら必ず訪問してみよう、と誓ったのです。
しかしながら、訪れることを誓ったものの、いざ医学部に入学すれば勉強に忙しく、医師になってから訪れよう・・・、となり、医師になってからは、そのうち時間ができたら・・・、となってしまいました。このままでは、医師を引退してから・・・、と言い出しかねない、と思い、先日、木曜日の休診日、事務仕事が予定より早く終わったこともあって、念願の適塾訪問が実現することになりました。
適塾は大阪のオフィス街のど真ん中に位置しています。駅で言えば淀屋橋と北浜の中間くらいにあり、どちらからでも歩いて行ける距離にあります。私は太融寺町谷口医院から歩いて行きましたが30分もかからないくらいでした。このあたりは近代ビルが立ち並んだ都心のオフィス街ですから、こんなところに今でも適塾が本当にあるのかな・・・、と思いながら歩いていると、突然貫禄のある木造家屋が目の前に現れました。まるで、幕末にタイムスリップしたような感覚にとらわれます。
大阪という街は、都心のオフィス街であっても、明治時代くらいからそのまま残っているのではないか、と思わせるような古い家屋をときどき目にします。しかし、適塾はそのような古い建物のなかでも群を抜いて貫禄があります。品のいい白壁の町家風木造建築物、という感じです。
訪問時にもらった資料によれば、この建物は1845年に緒方洪庵が購入したそうです。1964年には国の重要文化財に指定され、1980年に解体修復工事が完了し一般公開が開始されたそうです。250円の入場料を払えば、建物の中を見学することもできます。二階建てになっていて、一階は客座敷、教室、土間などと表示されていました。興味深いのは二階にあるふたつの部屋です。ひとつは「ヅーフ部屋」、もうひとつは「塾生大部屋」です。
ヅーフ部屋とは、オランダ語の辞書「ヅーフ・ハルマ」の置いてあった部屋で、その辞書(ヅーフ辞書)も展示されています。説明文によると、ヅーフ辞書は適塾に1冊しかなく、塾生たちはこの辞書を奪い合うようにして勉強していたそうです。我々現代人の感覚でいうと、展示されていたその辞書はけっして分かりやすいわけではなく、単にオランダ語の横に日本語訳が書かれているだけで、色分けもなく、手書きであり、勉強するのがイヤになりそうです。
しかし、当時蘭学を学ぶ者にとって、それがほとんど唯一オランダ語を知る手がかりだったわけですから、学生たちにとっては大変貴重なものだったに違いありません。いい参考書がみつからない・・・、などという悩みがどれだけ贅沢なものかということを実感させられます。
もうひとつの部屋、塾生大部屋は、おそらく適塾を訪れる人にとって最も印象に残る部屋でしょう。塾生たちが自習をし、雑魚寝をしていた部屋なのですが、部屋に入った瞬間、視界に飛び込んでくるのは中央にある1本の柱です。この柱には無数の傷が付けられており、説明文によると、塾生たちが刀でつけた傷であり、血気盛んな若者たちが日夜激論を交わし、刃傷沙汰も日常茶飯事だった、とも言われているそうです。実際に刃傷沙汰があったのかどうかは分かりませんが、今でもその柱からは当時の”熱気”のようなものが伝わってきます。
塾生たちに割り当てられたのは畳1畳もないくらいのスペースで、そこで着替えや机になるものを置いて勉強していたそうです。成績順にいい場所をとれたようで、成績が悪いと陽のあたらない暗いスペースしかもらえずに明かりを確保するのにも苦労したであろうことが想像できます。エアコンのきいた静かな部屋で「なんだか今日は勉強気分じゃないなぁ」などと言ってゲームに夢中になる現代の受験生とどれだけ違うかを考えさせられます。
適塾には多くの資料が展示されていますが、私が最も惹かれたのは、ドイツの医学者であるフーフェランドが著し、緒方洪庵が訳したとされる『扶氏医戒之略』です。フーフェランドという人物は、過去のセンター試験に出題されたことはないかもしれませんが、高校生レベルの倫理学の資料集でも少し詳しいものであれば名前くらいは登場します。
フーフェランドは医学者なのになぜ倫理学の教科書に出てくるのか、そして緒方洪庵も、日本史に登場するのは理解できるとして、なぜ倫理学でも取り上げられるのか、その理由が『扶氏医戒之略』にあります。
『扶氏医戒之略』には、医師が守るべき戒めが12箇条にまとめられているのですが、これら12箇条のひとつひとつが、医療を実践する者にとって「医療倫理の真髄」とも呼べる程の優れたものなのです。医師のみならず、これから医学を学ぼうとする者にとっても、読めば魂が震えるくらいの感動があります。
適塾で見た『扶氏医戒之略』は、文語調で書かれていますから読みやすくはないのですが、それでも充分に「医療倫理の真髄」が伝わってきます。例えば第1条には「医の世に生活するは人の為のみ、おのれがためにあらずということを其業の本旨とす」と書かれています。つまり、医師は人(患者さん)のために存在しているのであって、自分のために生活するべきでない、ということです。その次には、名声や利益を顧みることなく、ただ自分を捨てて人を救うべきである、と書かれています。
第2条以降を簡単に紹介しておくと、「常に謙虚に診察すべき」、「医療費はできるだけ少なくすべき」、「他の医師を批判してはならない」、「詭弁や珍奇な説で世間に名を売るような行為は医師として最も恥ずかしいこと」など、まるで現在の医師を戒めるような内容です。また、「患者個人の秘密や最も恥ずかしいことすら聞かねばならないこともあり、医師は篤実温厚で多言せずに沈黙を守らなければならない」、と守秘義務についてこれだけはっきりと記されていることにも驚かされます。
適塾を後にした私は、早速インターネット上でこの『扶氏医戒之略』を探しました(注1)。読めば読むほど身が引きしまる想いがします。これから私は仕事のスランプを感じる度にこの12箇条を読み返すことになるでしょう。
そして、勉強のスランプに陥ったときは、改めて適塾を訪れて、あの「柱」の前に立ちたいと思います・・・。
************
注1:『扶氏医戒之略』の谷口恭による”超訳”を下記に記します。原文はネット上でもあまり見つからず長崎の「羅針塾」という学習塾のウェブサイトにありました。そこからコピーしたものを下に貼り付けておきます(著作権上問題があるかもしれませんがこの原文がネット上から消えてしまうことを防ぐためにあえてコピーさせていただきます)。
1.自分のためではなく、他人のために生きるのが医業の本来の姿である。医師であるならば、ラクな暮らしを望まず、己の利益や名声を顧みることなく、ただ自分を捨てて人を救うことのみを求めるべきである。医師の使命とは、人の生命を守り、疾病を回復させ、苦痛を和らげることにあるのだ。
2.患者を診るときはただ患者を診るのであって、決して身分や金持ちか貧乏かどうかで診察の内容を変えてはいけない。高価な金品と貧困にあえぐ患者の涙を比較できるはずがない。
3.治療を行うにあたっては、患者を治療することが目的であり、治療が自分の目的や手段であってはならない。自己の考えにこだわってはいけない。根拠のない治療をやってはいけない。また、常に謙虚な態度で、細心の注意をもって治療をおこなわねばならない。
4.医学を追求する以外にも、自分の言動に注意し、患者からの信頼を得なければならない。その時代の流行に流されたり、詭弁や自己流の珍奇な説を唱えたり、出世欲や名誉欲に駆られたりすような医師は極めて恥ずかしいと自覚すべきだ。
5.雑な診察で多くの患者を診るのではなく、一人の患者を細密に丁寧に診るべきだ。偉そうな態度をとったり、患者の診察を拒否するようなことがあってはならない。
6.不治の病気であったとしても、病苦を和らげて生を保つようにすることは医師の務めである。放置して患者を顧みないようなことは人道に反する。たとえ救うことができなくても、患者に安らぎを与えることは仁術である。片時たりともその生命を延ばすことに務め、死を告げてはならない。自分の言葉や行動から患者に死を悟らせないように気遣うべきである。
7.患者の金銭的負担は最小限にすべきである。たとえ命を救えても生活費に困るようでは、患者にとって有益でない。特に貧しい人を診察する際には、この点に留意しなければならない。
8.世間から好意をもたれるように心がけるべきだ。たとえ高い学問を修め、厳格な言動をしていても、市民の信用を得なければ医療はできない。また、社会や個人の事情にも配慮せねばならない。医師は患者から心身を託され、他人には言わないような事情や秘密を知ることもある。したがって、医師は誠実で優しくなければならない。守秘義務を遵守し、沈黙を守らねばならない。ギャンブル、飲酒、好色、金儲けなどは論外である。
9.前医の治療は褒めるべきだ。自分の考えと異なる治療であったとしても自分の主張は抑えるべきであり、前医を非難してはいけない。他の医師の短所をあげつらうような行為は賢人がすべきことではなく、他人の過ちを指摘することは人徳のない者がすることであり、他人の過失を責めるのは自分自身の人格を貶めることにつながる。医師にはそれぞれの考えや方法があるのだから、みだりにこれらを批判すべきでない。経験の多い医師からは学ばねばならない。後輩の医師には愛情をもって賞賛すべきだ。前医の治療について尋ねられたときには良かった点について説明するよう努めるべきだ。しかしながら、前医の治療を続けるかどうかについては、その時点で症状がなければ辞めるべきだ。
10.毎日、夜には昼間に診察した症例について考察し、詳細に記録することを日課とすべきだ。これらをまとめて一つの本を作れば、自分のためだけでなく、患者にとっても有益である。
11. 治療について会議を開くときはメンバーが多すぎてはいけない。多くても3人までにすべきだ。ひたすら患者の安全をまず考え、患者に関係のないことは考慮せず、そして言い争いをすべきではない。
12.患者が前医を捨てて受診を求めてきたときには、まずその前医に相談し、了解を受けなければ診察すべきではない。しかしながら、前医の治療が誤っていることがわかれば、それを放置することは医師の道に反する行為である。とくに、重症化しているような場合は躊躇すべきではない。
************
「扶氏医戒之略」緒方洪庵抄訳
一、 人の為に生活して己のため生活せざるを医業の本髄とす。安逸を思はず名利を顧みず唯己をすてて人を救はん事を希ふべし。人の生命を保全し人の疾病を複治し人の患苦を寛解するの外、他事あるものに非ず。
二、 病者に対しては唯病者を見るべし、貴賎貧富を顧りみること勿れ。一握の黄金を以貧士双眼の感涙に比するに何ものぞ、深く之を思うべし。
三、 其術を行うに当っては病者を以って正鵠とすべし。決して弓矢となすこと勿れ、固執に僻せず、漫験を好まず、謹慎して眇看細密ならんことを思うべし。
四、 学術を研精するの外、言行に意を用いて病者に信任せられん事を求むべし。然れども時様の服飾を用い詭誕の奇説を唱へて、聞達を求むるは大いに恥じるところなり。
五、 病者を訪ふは粗漏の数診に足を労せんよりは、寧ろ一診に心を労して細密ならんことを要す。然れども自から尊大にして屡々診察するを欲せざるは甚悪むべきなり。
六、 不治の病者も仍て其患苦を寛解し、其生命を保全せんことを求むるは医の職務なり。棄て顧りみざるは人道に反す。たとひ救う事能ざるも、之を慰するは仁術なり。片時も其命を延んことを思うべし。決して其死を告るべからず。言語容姿皆意を用いて之を悟らしむること勿れ。
七、 病者の費用少なからんことを思ふべし。命を与ふるも命を繋ぐ資を奪はば亦何の益かあらん。貧民に於ては茲に甚酌なくんばあらず。
八、 世間に対しては衆人の好意を得んことを要すべし。学術卓絶すとも、言行厳格なりとも、斉民の信を得ざれば之を施すところなし。又周く俗情に通ぜざるべからず。殊に医は人の身命を委托し赤裸を露呈)し最蜜の禁秘をもひも啓き、最辱の懺悔をも告げざることは能ざる所なり。常に篤実温厚を旨として多言ならず、沈黙ならんことを主とすべし。博徒、酒客、好色、貧利の名からんことは素より論をまたず。
九、 同業の人に対しては之を敬し之を賞すべし。たとひ然ること能ざるも勉めて忍ばんことを要すべし。決して他医を議するなかれ。人の短をいふは聖賢の明戒なり。彼が過ちを拳るは小人の凶徳なり。人は唯一朝の過ちを議せられて己れ生涯の徳を損す。其損失如何ぞや。各医自家の流有て、又自得の法あり。慢りに之を論すべからず。老医は尊重すべし。少輩は愛賞すべし。人若し前医の得失を問ふことあらば勉めて之を得に帰すべし。其冶法の当否は現症を認めざるは辞すべし。
十、 毎日夜間に方って更に昼間の接病を再考し、詳らかに筆記するを課定とすべし。積んで一書を成せば、自己の為にも病者のためにも広大の脾益あり。
十一、治療の商議は会同少なからんことを要す。多きも三人に過ぐべからず。殊によく其人を選ぶべし。只管病者の安全を意として、他事を顧かえりみず、決して争議の及ぶ事勿れ。
十二、病者曽て依託せる医を舎て窃に他医に商ることありとも、漫りに従うべからず。先づ其医に告げて其その説を聞くにあらざれば従事すること勿れ。然りといへども、實に其誤冶なることを知て、之を外視するは亦医の任にあらず。殊に老険の病にあっては遅疑することある勿れ。
************
改訂:本ページは繰り返し改訂しています。最終改訂日は2025年7月31日です。
投稿者 | 記事URL
2013年6月14日 金曜日
2013年1月号 「違和感」を大切にし「常識を疑う」ということ
昨年(2012年)に読んだ本で一番良かったのは?、と尋ねられれば、私は迷わずジョン・キム氏の『媚びない人生』を挙げます。
この本は、キム氏が慶応大学でおこなっているゼミの卒業生に対する「贈る言葉」を原点にまとめたもので、これから社会に旅立つ若者へのメッセージという趣の本です。しかし、内容は若者に限定したものではなく、私のような40代の者が読んでも共感する部分が多く、私個人としてはすべての人に読んでもらいたい、と感じている一冊です(注1)。
キム氏は、韓国生まれで、家庭は決して裕福ではなく、小学生の頃からひとりで暮らさなければならなかったそうです。19歳のとき、日本の中央大学に国費留学し、アメリカ、ヨーロッパを含む3大陸5ヵ国で学ばれたそうです。
『媚びない人生』に書かれているすべての言葉に対し、私は無条件に同意するわけではありませんし、初めて聞くような内容でもないのですが、「すべての時間を学びの時間にする」、「従順な羊ではなく野良猫になれ」、「失敗しない人は絶対に成功しない」、「過去から見た今の自分が常に成熟した自分であるべきだ」、「人間の生きた価値はどれほど長く人生を生きたかではなくどれほど濃度の濃い人生を生きたかによって決まる」、などストレートな表現が胸にビシビシと突き刺さります。
私は今年の年始の数日感、国内のある地方都市で休暇をとったのですが、最もやりたかったことのひとつが、この『媚びない人生』を熟読しなおす、ということで、実際に繰り返し読み耽りました。
この本のなかで私が最も噛み締めた言葉は、「常識や前提は極めて社会的なものであり、物事を鵜呑みにする行為は自分を放棄する行為である」、という言葉です。別のところでは「違和感を大切にしなければならない」とも書かれています。
私は今年45歳になりますから、そろそろ人生真ん中あたり、なのですが、これまでの人生を振り返ると、節目節目で自分のとった行動の多くは「違和感」を覚えて「常識を疑った」ことから始まりました。
高3の12月で偏差値40しかなく、受験代が無駄になるだけだ、と教師に言われたけれども希望する関西学院大学を受験したのは、<教師に受験校を決められるのはおかしいではないか!>という「違和感」が捨てられず、<常識を覆してやる!>という気持ちがあったからです。
しかし、そこまでして行きたかった関西学院大学理学部での勉強に興味が持てず、代わりに社会学を勉強したくなった私は学内の社会学部に編入学ができるかどうかを尋ねに行きました。そこで言われたのが「一応、制度上はできることになってはいるが前例がないので無理でしょう」という言葉でした。<前例がないなら自分でつくればいいではないか!>と考えた私は、(その熱意が通じたのか)結果的には合格通知を手にすることができました。
関西学院大学社会学部を卒業後、私は大阪のある企業に就職しました。英語がまったくできないのにもかかわらず海外事業部に配属されたため、最初の一年間は足手まといになっただけで会社に何の貢献もできず辛い体験がほとんどでしたが、2年目からは少しは仕事を覚えることができました。自分の書いた手紙でそれまでその会社とは取引のなかった中東のある国の企業と契約が取れたときの嬉しさは今でも覚えています。翌年には輸入品を国内市場に販売促進する仕事を与えられたのですが、このときもキャンペーンの企画やチラシの作成など自分で仕事をつくる喜びを感じることができました。何よりも当時の私は仕事を楽しんでいました。
しかし、あるとき私の心にふと「違和感」がよぎりました。<このままでいいのだろうか・・・>という「違和感」です。せっかく安定した企業に就職できてやりがいのある仕事をさせてもらっているんだからそれで充分じゃないか・・・、私の心にもそのような気持ちがあったのは事実ですが、その一方で、<果たしてこのままで・・・>という気持ちが拭えきれず、結局私は学問の道に戻ることを決意しました。大学を卒業するときには大学院進学も考えていましたし、入社したときから、いずれ学問をまたやりたい、とは考えていたのですが、最終的にそれを決めたのは、私の心にあるとき芽生えて払拭することができなかった「違和感」だったのです。
心に芽生えた「違和感」が人生を変えるエピソードはまだ続きます。母校の関西学院大学社会学部の大学院進学を志した私は、時間をみつけてある先生のところに通いだしました。本を紹介してもらい小論文の添削などもおこなってもらいました。当時の私が社会学を通して研究したかったのは、人間の感情、思考、行動などについて、だったのですが、しかし、こういったことを探求すればするほど、脳生理学、免疫学、分子生物学などの生命科学へと興味の対象が移っていったのです。そして私は医学部受験を決意しました。
次に「違和感」が私の行動に影響を与えたのは、医学部の学生時代に(医学部以外の)友人・知人から言われたいくつかの言葉です。それらの言葉とは現在の医療や医師に対する問題点・疑問点であり、<ならばそういった問題を克服した医療を自分がやればいいではないか>と思うようになっていったのです。ちょうどその頃、自分に研究は向いていないということが分かりかけていたこともあり、研究から臨床への方向転換を決意したのです。
研修医の頃、そのときは大学病院の皮膚科で研修を受けていたのですが、ある先生に言われた一言が私の心に「違和感」を芽生えさせました。皮膚腫瘍で入院していたある患者さんの尿の色が濃いことに気づいた私は、先輩医師にそれを報告し、尿の比重を測りたい、と言いました。すると、「皮膚科は皮膚だけみてればそれでええんや。君が尿がおかしいと思うんやったら内科か泌尿器科にでも紹介すればええやないか」、という言葉が返ってきたのです(注2)。単に「尿の色が濃い」だけでこちらが何もせずに紹介するのはおかしいと感じましたし、このときに私は既存の縦割りの専門医療というものに疑問を持ちました。そして<ならばどのような症状の患者さんも診られるようになるべきではないか>と考えたのです。
私がタイのエイズホスピスを初めて訪れたとき、そこで目にした光景は、家族からも地域社会からも病院からも追い出され、行き場をなくした末期のエイズ患者さんたちでした。その施設で働いていた医師たちは欧米から来ていたボランティアの医師でエイズ専門医ではなくプライマリケア医でした。抗HIV薬が普及しだしてからはエイズ専門医も診療に関わりだしますが、エイズ専門医の仕事は主に適切な薬の選択にあり、実際に患者さんの声を聞き症状に対処するのはプライマリケア医です。私はタイのエイズ施設で欧米のプライマリケア医たちの診療を目にし、指導を受けました。
先に述べた研修医時代の皮膚科での経験もあり、私は何らかの専門医ではなくプライマリケア医を目指すことを決意し、帰国後母校(大阪市立大学医学部)の総合診療部の門を叩きました。ちょうどその頃、全国的にプライマリケア(総合診療、家庭医療)が注目されだしていたのは予期せぬ偶然でした。しかし大学での研修だけでは不充分です。
そこで私は、月曜日は病院の婦人科で研修、火曜日は整形外科クリニックでの外来見学、水曜日は皮膚科で・・・、というように日替わりで複数の医療機関に研修(修行)に出ることにしました。これらの多くは無給であり、そのような「前例のない」私の行動に対して同僚の医師たちからは不思議がられましたが、それが最も効率がよい研修方法であることを確信していた私は気に留めませんでした。
このように、これまでの半生を振り返ると、進路の決定や変更には私の心に生じた「違和感」がきっかけとなっていて、とった行動は常識や前提に縛られないもの、もっと言えば常識や前提に刃向かうようなものです。こんな私は「従順な羊」ではないでしょう。ひとりで生きていく「野良猫」ほどかっこよくはないでしょうし、「過去から見た今の自分が常に成熟した自分」と言えるかどうかも疑問です。しかし、少なくともこれまでの人生に後悔はありません。
キム氏は、『媚びない人生』のなかで「いつまでたっても学ぶだけの人は、それだけの存在で終わってしまう」とも述べています。私自身も学ぶだけでなく、「違和感」を大切にし「常識や前提を疑う」ことの大切さを他人に伝えていきたいと思います。
注1:この本が出版された直後にキム氏の学歴詐称が明らかとなり、自身もウェブサイト(下記URL)でこの点を謝罪されています。なかには、学歴詐称する者の言論など聞くに値しない、という声もあるようですが、私自身はそのようなことがあったとしても一読に値する良書だと感じています。
http://johnkim.jp/message.html
注2:このように書くと私はこの先生を嫌っているように思われるかもしれませんが、嫌っているわけではなくその反対で、この先生は今も私にとって皮膚科領域での尊敬する先生のひとりです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月14日 金曜日
2012年12月号 謎に包まれたままの女性医師の死亡
医師が選ぶ今年(2012年)の最大のニュースは、何と言っても山中先生のノーベル賞受賞だと思います。暗いニュースが多いなか、山中先生のノーベル賞受賞は、医師、研究者のみならず将来を担う多くの若者に夢を与えてくれました。
私は毎年12月になるとその年を振り返るようにしています。10月に山中先生の受賞を聞いたとき、今年一番の出来事はこの嬉しいニュースに違いない、と感じていました。
しかし、12月になった今、私が最も驚いているのは、11月半ばに伝わってきた「矢島祥子医師死亡事件の時効成立」という報道です。最初は「時効」という文字を見たときに「何かの間違いではないのか」と感じました。なぜなら、殺人事件の時効は2010年に廃止されたはずですし、矢島医師が死亡したのは2009年ですから、時効が有効だったとしても殺人なら時効成立までに25年間あるはずだと考えていたからです。
それがなぜ3年で時効成立になるのか・・・。そして、矢島医師とはどのような医師だったのか・・・。まずはこの事件を振り返っておきたいと思います。
2009年11月16日午前1時20分頃、大阪市西成区の木津川の千本松渡船場で矢島祥子医師(当時34歳)の遺体が釣り人により発見されました。遺書もなく、状況から少なくとも自殺ではないように思われますが、管轄の西成警察署は当初「自殺による溺死」と断定しました。
西成署がどのような理由で自殺と断定したのか、報道からは伝わってきませんが、遺族は自殺という説明に納得がいかず、警察に捜査の申し入れをされたそうです。私が直接確認したわけではなくあくまでも「一部の報道」ですが、遺体にはアザや頭部のコブが複数みつかっており、これが事実だとすると、生きているときに暴行されたことを示唆しています。また、首に圧迫痕があった(つまり首を絞められた)、とする報道もあります。
つまり、これは自殺などではなく殺人ではないか、と遺族は(というより多くの関係者は)考えているわけです。それに、死体が発見されるまでの数日間の行動も自殺を示唆するようなものはなく、遺族や知人らが、警察が自殺と断定したことに、しかも比較的短時間で断定したことに不審感をもったのも当然です。
報道されている情報によれば、事件数日前の矢島医師の行動にも不自然な点はなく、2日前には勤務先の診療所で深夜まで残業し、午前4時15分に診療所を退出しています。2日後に自殺をする人間がそんなに頑張って仕事をするでしょうか。
この事件を聞いた医師のおそらくほとんど全員が「これは自殺ではない」と感じたと思います。なぜなら、医師であれば自殺をするにしてももう少しスマートな方法を選ぶだろう、と我々は直感するからです。例えば、ラクに死ねる薬と注射器を持ち出す、とか、局所麻酔をして痛みをとってから動脈を切るとか、そういうことを考えるはずです。なかには屋上から飛び降りて自殺した医師もいますが、川に身を投げて溺死という(中途半端な)方法を取るとは考えにくいのです。薬物を摂取して川にとびこんだのかもしれませんが、体内で薬物が検出されたという報道はありません。
あまり知られていないことかもしれませんが、医師という職業は、自殺者が多い職業のトップに入ります。私と同じ医学部の同級生にも若くして自殺した医師がひとりいますし、どこの大学でもだいたい学年2~3年にひとりは若い命を自らの手で終焉させています。●●大学医学部の○年卒の△△医師が自殺した、という情報がときどき医師仲間から伝わってきます。どこの学部でも学年にひとりくらいは自殺があるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、医学部の定員というのは一学年がせいぜい80人程度であることを考慮すると少なくないことがわかると思います。
自殺の話があがると、どのようにして死んだのかということも同時に伝わってきます。そういうこともあって、我々医師は、医師が自殺をするならどのような方法をとるか、ということについてだいたい推測できるのです。方法だけではありません。なぜ自殺をしたのか、ということについても同志としての医師だから理解できる、ということもあります。
しかし矢島医師の事件の場合、動機がまったく理解できませんし、死体の発見のされ方も自殺にしては極めて不自然です。自殺と断定できる確実な証拠がないのであれば、他殺、つまり殺人の可能性を考えて捜査がおこなわれるべきではないでしょうか。あるいは警察はこの死を事故とでも考えているのでしょうか。34歳の女性医師が誤って川に転落し溺死するなんてことがあるでしょうか。
なぜこの事件が3年で時効を迎えるといったことが報道されたのか。それは、刑法で定められている死体遺棄罪の時効が3年だから、ということでしょう。しかし殺人罪の時効は2010年以降廃止されていますし、矢島医師の死亡した2009年には時効廃止が適応されないとしても、この事件が殺人なら時効成立まであと20年以上あるはずです。ということは、警察が殺人の可能性を否定しない限りは捜査を続けることは可能なはずだと思うのですが、警察は今もこの事件を積極的に捜査してくれているのでしょうか・・・。
ここで矢島医師とはどのような医師だったかについて紹介しておきます。いくつかの報道によりますと、1975年群馬県高崎市生まれ、群馬大学医学部を卒業し、在学中にキリスト教の洗礼を受けられています。医学部卒業後は沖縄県立中部病院(昔から厳しい研修で有名な研修医に人気のある病院です)で研修を受けた後、大阪の病院で6年間勤務され、その後は西成区のあいりん地区にある診療所で勤務されていました。
一部では「平成のマザーテレサ」とも呼ばれており、あいりん地区を中心に路上生活者の医療支援などに献身されていたそうです。事件が起こる前から、西成の路上生活者のみならず医療者の間でも有名で、真摯に路上生活者を支援する姿はマスコミに報道されたこともあるそうです。私が矢島医師の名前を初めて聞いたのは、NPO法人GINA(ジーナ)を立ち上げてしばらくした頃で、私などよりも困窮している人々のために遥かに尽力している話を聞いて、敬服する気持ちを持ったことを覚えています。いつかお会いして話を聞いてみたいと思っていました。
なぜ矢島医師は殺されなければならなかったのでしょうか。お世辞にも治安がいい町とは言えないところですから、例えばひったくりやノックアウト強盗に合ったという可能性もあるでしょう。矢島医師が抵抗したために殴られてアザやコブができて、それでも抵抗をやめなかったために頸部が圧迫され窒息死し川に捨てられた、というストーリーです。しかしこのようないきあたりばったり的な殺人であれば、何らかの証拠が残されていたり、犯人に前科があったりして、比較的簡単に事件が解決するのではないでしょうか。
気になるのは裏社会との関係です。例えば、矢島医師が診察している患者のなかで覚醒剤の常習者がいたとしましょう。おそらく矢島医師であれば、この患者が覚醒剤をやめる意思があれば警察に通報したりはしないでしょう。しかし、この患者が大量の覚醒剤を保持しておりそれを販売していることを知ってしまったとしたらどうでしょう。正義感の強い矢島医師はおそらく警察に通報することを考えるでしょう。
あるいは(これはネット上で噂されているようですが)生活保護の不正受給の情報を矢島医師がつかんだ、という可能性はどうでしょう。その不正受給には闇社会の人間が関わっており、さらに(こうなるとフィクションの世界のようですが・・・)警察の上層部も関与しており、矢島医師がつかんでいる情報をにぎりつぶさないことには生活保護受給者だけでなく一部の闇社会の人間や警察にとって非常にマズイことになる、だからプロに殺害された・・・、というものです。
犯人が逮捕されたところで矢島医師は戻ってきません。しかし、逮捕されないことには遺族の方のみならず、矢島医師にあたたかい言葉をかけられて病気を治してもらっていた多くの路上生活者の方々の無念が晴れることはありません・・・。
私にできることはありませんが、警察の方々にこれからも捜査を続けていただくよう心よりお願いしたいと思います。
投稿者 | 記事URL
2013年6月14日 金曜日
2012年11月号 就活に成功する人しない人
このコラムの7月号で、厳しい就職活動(以下「就活」とします)について取り上げました。就活の失敗が続き自殺を考える人が増えていることについても述べました。
太融寺町谷口医院(以下、谷口医院)の患者さんのなかにも、20代から40代、ときには50代の人で、就活で苦労しているという人がいます。また、就職は比較的簡単に決まるのだけれど長続きしない、という人も少なからずいます。
一方、谷口医院では看護師や受付事務員などスタッフが10人近くいますから、私自身が人を雇用する立場に、つまり面接試験をする側の立場にいます。谷口医院は開院してからもうすぐ丸6年となり、それなりにたくさんの人(おそらく100人近くになると思います)を面接しています。
今回は、どのような人が就活に成功しやすくて、どのような人が失敗をしやすいか、について私の経験から考えてみたいと思います。
まず結論を言うと、「就活は<運>と<縁>で多くが決まる」、となります。7月号のコラムで、私は「結局のところ自分自身ががんばるしかない」と述べましたから、矛盾するようなことを言っているようにみえますが、これらは両方とも真実です。
やりたい仕事があり、働きたい企業があるなら、それに向けて頑張ることはもちろん必要です。しかし、<運>と<縁>に左右されることがあるのも歴然とした事実です。ですから、もしも希望する企業に合格しなかったとしても、まず「落ち込まないこと」が大切です。「今回は運と縁がなかったんだ・・・」と考えるべきなのです。
人材紹介会社のある社員から以前、次のようなことを聞いたことがあります。「A社は給料も高く従業員に優しい優良企業でなかなか<空き>がでない。だから(中途での)就職は難しい。しかし、たまにふと<空き>がでて求人がでることがある。そんなとき、たまたま就活をしている人がいればラッキーですよ。難関と思われているA社も、面接で聞かれることは普通ですから・・・。常識的な人であれば採用されますよ」、とその社員は話していました。
私はこの意見がすとんと腑に落ちました。私もまったく同じような印象を持っているからです。谷口医院でも求人を出したとき大量の応募が来ますが、だいたい1週間から長くても10日程度で募集を締め切ります。そして、いつも、締め切った直後に連絡してくる人がいるのです。こういう人は、のんびりしすぎているというわけではなく、たまたま就活を始めた時期と谷口医院が募集を締め切る時期が一致していた、というだけの話です。谷口医院の募集は原則メールでの応募としており、私自身もほとんどのメールに目を通していますが、締め切った直後に応募してきた人に限って「会ってみたい」と思わせるプロフィールや志望動機が書かれているのです。もしもこの人があと1週間就活を始めるのが早ければ今頃は谷口医院のスタッフだったかもしれない、というわけです。こういうとき、私は「この人とは<縁>がなかったんだ」と考えるようにしています。
就活は大変でしょうが、面接試験の選考をおこなう雇う側にも苦労はあります。雇う側としては、優秀な人が応募してくれるのはもちろん嬉しいのですが、もっと欲を言えば、優秀な人がひとりだけ応募しれくれれば尚ありがたいのです。しかし、実際は複数の優秀な人が応募してくれるために悩まされることになります。優秀な人たちには申し訳ないのですが、最終的な合格の理由となるのは、「(前職をすでに退職しているので)すぐに働ける」「家が近い」、など本人の実力とは何ら関係のないことが多いですし、「最終選考者のなかで一番早く応募してくれたこと」が採用の理由のひとつになることもあります。
人材派遣(紹介)会社の人や企業の人事部の人、あるいは私と同じような立場の開業医と話をすると「雇ってみて働いてもらわないことには分からないことがたくさんある」という話題になります。言い換えると「面接でその人の本性や実力を見抜くことはできない」となります。ですから、雇う側としては、「面接時に常識とやる気を感じ取ることができればそれで合格」なわけです。巷には、就活成功マニュアルのような本が出ていて、受け答えの仕方から服装にいたるまで事細かく指南されているようですが、私の個人的な意見を述べれば、そのようなものは必要ありません。
このように言うと、「それじゃあ、何度か面接を受ければ誰でもどこかには就職できるということですよね。でも実際は何社受けても受からない人もいますよ」という反論がくるでしょう。たしかに、いくら受けても合格しない人がいるのも事実です。ここからはこれについて述べていきます。
就活に成功しないよくある例が「志望動機が分からない人」です。よく、履歴書をたくさんの企業に送っても面接までたどりつけない、という人がいますが、もしもあなたがそのように感じているなら履歴書に書いている志望動機を見直すべきかもしれません。「この履歴書の志望動機は何度も使いまわししているのだろう」、人事担当者にこのように思われれば面接にたどり着く可能性は極めて低くなります(注1、注2)。
例えば、医療機関を受けるのであれば、雇う側としては「なぜ(他院でなく)当院を志望しているのか」を知りたいわけです。先にも述べたように、その理由が「家が近いから」とか「勤務時間が自分の都合に合うから」とかはOKです。一方、「医療に興味があるから」とか「人と接する仕事がしたいから」では説得力が感じられないのです。「この人は履歴書を使いまわししているのだろう」と思われます。雇う側としては、「働いてみると最初に思っていたのと違った・・・」と思われて、早期退職されることを避けたいわけです。
志望動機がはっきりしており「どうしてもここで働きたい」という気持ちがあれば、自然に熱意がでてきます。雇う側からみてその<熱意>は大変重要なポイントとなります。逆に熱意のない人にはこちらも興味がでてきません。例えば、面接に遅刻をしてくるとか、セーターなど普段着で来るとかは論外ですし(これらは実際にあった例です)、面接で質問をしても「どうせまた落とされるんでしょ・・・」と言わんばかりの受け答えに覇気がない人もいます。面接の際、必ずしも弁が立つ必要はありませんし、話し上手でなくてもまったくOKです。また、専門用語を知っている必要もなければ、むつかしい理論について解説する必要もありません。しかし、声が小さくあまりにも自信のなさそうな人に魅力は感じられないのです。
ノーベル賞を受賞された山中先生は、大阪市立大学大学院の面接時に「ぼくは薬理のことは何もわかりません。でも、研究したいんです!通してください!」と声を張ったというエピソードを自伝(注3)で書かれています。同書によれば、後になって面接官の先生から「あのとき叫ばへんかったら落としてたよ」と言われたそうです。山中先生はとても謙虚な先生ですから、このエピソードは幾分差し引いて考える必要がありそうですが、就活をしている人にとっては示唆に富んだものだと思います。
謙虚さがない人は面接では不利になります。過去の実績をアピールすることは大切ですが、「私の実力だと合格して当然です」という態度はいい印象を与えません。逆に、上に述べた山中先生のエピソードにもあるように、「これから一生懸命やります」という姿勢の方が重要なわけです。実際、「過去にこれだけの実績がありますからできますよ」という態度の人は、働いてみるとまるでダメということがしばしばあります。医療機関で言えば、ベテランの看護師が仕事ができるとは限りません。むしろ古い考え方に固執していて新しい考えについていけないということがよくあります。事務員なら、過去に大きな病院で働いていたとしても、それが小さなクリニックで通用するわけではありません。
なんだか説教じみた話になってきましたが、まとめてみると、「常識的な態度で望めば就活を恐れる必要はない」のです。まず、なぜ(他ではなく)その企業(や医療機関)で働きたいのかをはっきりさせ、熱意と謙虚さをもって面接に望めば、あとは<運>と<縁>の問題、というわけです。
注1 例えば当院(太融寺町谷口医院)であれば、少しウェブサイトをみれば、待ち時間対策に苦労している、ということが分かるはずです。にもかかわらず志望動機に「ひとりひとりの患者さんにじっくりと向き合い心のこもった受付をしたい」などと書いてあれば、「この人は面接に望もうとしているクリニックのウェブサイトすらも見てないんだな・・」と思われます。そして書類選考で落ちることになります。もちろん<心のこもった受付>は大切なことですが、同時に<てきぱきと業務をおこない待ち時間対策に貢献したい>といった一文があればまったく印象が変わる、というわけです。
注2 最近、医療機関事務職応募の志望動機によく記載されているのが「以前自分が(もしくは家族が)医療機関を受診して受付の人に大変よくしてもらって・・・」というものです。このエピソードが書かれている履歴書が非常に目立ちます。何かの指南書に「医療機関を受けるならこのようなことを述べなさい」と書かれているのではないかと疑りたくなるほどです。本当にこのような体験を経て医療機関を目指している方には気の毒ですが、この文言は書かない方がいいかもしれません。しかし、自分の体験から希望する仕事に興味を持つようになった、というのは立派な志望動機ではあります。個人的な体験はできるだけ具体的に述べ(自分にしか書けないような文章にして)、なおかつ、なぜその医療機関で(他院ではなく)働きたいのかを訴えることができれば説得力がでてくると思います。
注3 『山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた』(講談社)より
投稿者 | 記事URL
2013年6月14日 金曜日
2012年10月号 山中先生から学んだこととこれからも学びたいこと
ビジョンを持って楽しく研究しましょう。そして薬理学教室の美味しいコーヒーを一緒に飲みましょう。
一字一句同じではないでしょうが、これは1999年の(たぶん)3月、大阪市立大学医学部の大教室の教壇で山中伸弥先生が我々学生に対して話された言葉です。
2012年10月8日、ノーベル医学・生理学賞を受賞された京都大学の山中教授は、神戸大学医学部を卒業された後、大阪市立大学医学部整形外科に入局され、その後同大学薬理学教室に入られ、1996年から1999年11月まで薬理学教室の助手として、研究に教育にと活躍されていました。
私が大阪市立大学医学部に入学したのは1996年、薬理学を学んだのは3回生のときですから、1998年4月から1999年3月までの一年間、薬理学の授業のうち何コマかは山中先生に教えてもらっていました。山中先生の講義は非常にむつかしく、配布されるプリントはほとんどが英語であり、私の苦手な分野だったこともあり、テスト勉強に苦しんだことを覚えています。ちなみに、当時、山中先生が大学医学部で講義されていたのは、(当然ですが)iPS細胞についてではなく、循環薬理学だったと記憶しています。
当時の大阪市立大学医学部では、4回生の前半は講義や実習はなく、基礎医学系の研究室に入って特定のテーマについての研究をすることになっていました。2~4名くらいのグループに分かれ、それぞれのグループはどこかの基礎医学系の教室に所属し、指導教官の元で研究をおこなうことになります。
例えば、第一解剖学教室では3つの研究班があり、3つの班の指導教官はA先生、B先生、C先生の3人で、各班の定員は2~4名、などと決められており、学生は希望する班を選ぶ、というわけです。基礎医学系の教室ですから、解剖学以外に、生理学、生化学、薬理学、細菌学、などがあります。山中先生は薬理学教室の3つの班の1つの指導教官だったと記憶しています。
各学生がどの班を選択するかにあたり、オリエンテーションのようなものが開かれ、この場で各教室の指導教官の先生方が学生を前に、どのような研究ができるかを話します。せいぜい3~4ヶ月の研究ですが、学生からすれば初めての本格的な研究ができるわけですし、指導する教員の立場からしてもできるだけ優秀な学生に来てもらいたい(やる気のない学生には来てもらいたくない)わけですから、このオリエンテーションは双方にとって大切な場となります。
冒頭で紹介した山中先生の言葉は、このオリエンテーションで話された最後の締めの言葉です。なぜ、私が山中先生の言葉を今でも覚えているのか、これは私にとっても不思議です。なにしろ、他の先生の言葉は一切記憶にないのですから。
当時の私は、研究が自分に向いていないことをひしひしと感じており、医学部を続ける自信を喪失していました。入学当時は、臨床家を目指すのではなく基礎医学の研究をやりたいと考えていた私は、入学直後から必死に勉強していたつもりでしたが、どうも研究をおこなうにはセンスも能力もないのではないかということに気づき始め、それを確証するようになっていきました。
この頃の私は、授業にはかろうじて出席していましたが、生活の中心はアルバイトになっていました。複数のアルバイトに精を出し、土日におこなっていたワゴンセールの販売では西日本全域の出張もこなしていました。複数のアルバイトをおこなうようになると、自然と知人が増えていきます。そのなかで、私はいろんな病気で悩んでいる人と知り合うこととなり、また、医療機関でイヤな思いをした、という人たちの話を聞くこととなり、こういった経験があって、研究ではなく臨床家として将来は患者さんと接していく道を選択することを決意しました。
そんな当時の私にとって、基礎医学系の研究というのは「過去のもの」という感じがして取り組む気力が起こりませんでした。山中先生のエネルギッシュな話も、印象的だったとはいえ、当時の私には「無理だろう」という気持ちが先行したのです。しかし、何らかの基礎医学の研究班に入ってレポートを書かねば進級ができません。私が選択したのは公衆衛生学教室のある班で、研究内容は「老人ホームで入居者から話を聞いて統計処理をおこなう」というものでした。社会学部出身の私にとってこれは得意分野です。社会学のフィールドワークの感覚でできると感じ、実際に研究は特に苦労もなくできました。
冒頭で紹介した山中先生の言葉はなぜかその後も心に残っていたのですが、その後先生を見かけることがないな、と感じていたら、その年の終わりには大学を辞められたと聞いて驚いたことを記憶しています。
その後私は医学部を卒業し、研修医となり、研修後タイに渡り、帰国後は大学に戻り総合診療センターに所属することになり、臨床の道を進んでいきました。基礎医学の研究に対する未練がまったくなくなったわけではありませんが、自分に向いているのは基礎医学ではなく臨床であることをこの頃にはすでに確信していました。
久しぶりに山中先生の名前を聞いたのは2006年でした。著明な医学誌『Cell』に「マウスのiPS細胞を確立した」ことを発表されたのです。iPS細胞については、いろんなところで解説されていますからここでは述べませんが、このときに私が感じたことは2つあります。まず先生の所属が京都大学になっていたことです。詳しい経緯は分からないけれど、おそらく京都大学の方から引っ張られて移られたのだろう、と感じました。もうひとつは、iPSというネーミングが、おそらくiPodをもじったのでしょうけれど、ユニークな山中先生らしいというか、山中先生が名づけたに違いない、と感じました。
その後、山中先生は国内外の著名な賞を次々と受賞され、医学関連の雑誌やサイトだけでなく、全国紙の一面にも登場されるようになります。研究内容だけでなく、山中先生のパーソナリティや過去のエピソードなどにも触れている記事が増えてきました。そのような記事を目にするようになり、私にとって大変意外に感じられる一面もでてきました。
それまでの私の山中先生に対するイメージは、エネルギッシュでユーモアのセンスに富んだアメリカ帰りの超エリート、というものでした。しかし、先生についてのエピソードを読んでみると、医学部卒業後は整形外科の臨床医を目指したが、手術に時間がかかり指導医から才能がないと言われ基礎医学(薬理学)に転向した。アメリカで研究をおこなったまではいいが、帰国後アメリカのように自由に研究できないことから「うつ」状態となり、研究を諦め臨床に戻ることをほぼ決意していた。そんななか、奈良先端科学技術大学院大学の公募に(引っ張られたのではなく)自ら応募して助教授に就任された、などと書かれています。
つい最近知ったのですが、山中先生は若い世代に講演をされるときに「人間万事塞翁が馬」という故事を引き合いに出されることがあるそうです。私の山中先生に対する過去のイメージからはこの故事はマッチしないのですが、臨床家として苦労したこと、研究を半ば諦めかけたときに奈良先端科学技術大学大学院で道が開けたことなどを考えるとこの故事はすっと腑に落ちます。
山中先生自身が話されているように、iPS細胞が人類に役立つようになるにはまだ時間がかかります。これからは今まで以上の苦労をなさるかもしれません。山中先生は今もスポーツマンでフルマラソンにも参加されているそうです。きっとこれからの研究も、マラソンのように、少々ライバルに抜かれても、調子が上がらずにしんどくなっても、「人間万事塞翁が馬」を思い出し、ビジョンを目標に進まれることでしょう。
そんな山中先生から、これからも学ぶことがたくさんありそうです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月14日 金曜日
2012年9月号 トイレの使い方、間違ってませんか?
このコラムで取り上げているのは基本的には「医療」のことで、それ以外では私が受験に関する書籍を上梓している関係から「勉強」のこと、さらに「自己啓発」のことなどです。社会支援やボランティアに関する話題は取り上げたことがありますが、医療に関係のない時事問題や社会問題などについてはほとんど触れたことがありません。
そしてこの方針はこれからも続けていくつもりです。しかし今回は、どうしても言っておきたいことがあるのでそれについて述べたいと思います。実は私はこのことを、いずれ大勢の方に関心を持ってもらわなければならない、と、もう10年以上前から感じていました。
これまで私がこのことをここに書かなかったのは、私がこのようなことを言う立場にはないだろうと感じていたことと、いずれこのことを話すのに適切な位置にいる人が訴える日がくるのではないかと期待していたからです。
しかし、私が大勢の人に知ってもらう必要性を感じてから10年以上経過した今でも、このことを取り上げる人は(私の知る限り)いません。
ではもったいぶらずに述べていきましょう。私が大勢の人に伝えたいこととは、「海外でのトイレの正しい使い方を本当に知っていますか」、ということです。もう少し具体的に言いましょう。私は世界中のトイレを知っているわけではありませんので、私が言いたいのはアジアのトイレについてです。結論を言えば次のようになります。
日本以外のアジアでは、ほとんどの場所でトイレットペーパーを流してはいけない。
日本人であれば、トイレットペーパーを流すのが常識ですが、これは日本以外のアジアでは「非常識」なのです。そのため、海外のホテルやレストランで日本人がトイレでトイレットペーパーを水と一緒に流して詰まらせて大変なことになった、という話がよくあります。私が改めてこのようなことを主張しなくても、アジアに旅行したことのあるほとんどの人にとってはすでに「常識」になっているでしょうが、残念ながらこの「常識」が守れていない人が少なくないようなのです。
以前台湾のあるホテルで用を足そうとロビーにあるトイレに入ったときに驚いたことがあります。「紙を流さないで!」と日本語で書かれた張り紙がいくつもトイレの壁に貼られていたのです。これはすなわち、紙を流してトラブルを起こす日本人が後を絶たないことを示しています。ちなみに、このトイレには英語の張り紙もありましたが日本語ほど派手には書かれていませんでした。おそらく紙をトイレに流すなどといった「非常識」なことをするのは欧米人ではなく圧倒的に日本人に多いということでしょう。
では、台湾では使用したトイレットペーパーをどうするのかというと、隅の方に置いてあるゴミ箱に入れます。ですから、その箱を覗くと、前の人が使用したトイレットペーパーが捨てられていて、紙には臭そうな便がびっしり付着……、ということもあります。もし、「そんな不潔なトイレで用を足せない……」と感じる人がいるなら、その人は海外(アジア)には行かない方がいいでしょう(注1)。
このようにお尻を拭いた紙を箱に捨てなければならないのはもちろん台湾だけではなく、日本以外のアジアではどこも同じです。韓国では空港や高級ホテルでは紙を流してもかまわない、という話も聞いたことがありますが(注2)、少なくともソウルの普通のレストランでは流せませんし、ファストフード店でもご法度です。しかし、このルールを知らずに(あるいは知っていても無視して)紙を詰まらせてトラブルとなるケースが少なくないそうです。
タイやマレーシア、フィリピンなどでは、少し高級なところでは便器の横に小さなシャワーのようなものがついています。用を足した後、そのミニシャワーでお尻を洗浄するのです。そして備え付けの紙でお尻を拭いて、その紙をゴミ箱に入れるようにします。
こういった地域では紙がない場合もあります。紙がなければ手でお尻を拭かなければなりません。手でお尻を拭くことには抵抗のある人もいるでしょうが、しっかりとシャワーをして便を洗い流しておけば案外簡単にできるものです。(それでも手でお尻を拭くことができない、という人は、アジア旅行はかなり制約されたものになることを覚悟しなければなりません)
このミニシャワーはいつも常備されているとは限りません。というより、ホテルや空港、高級レストランなど、限られた施設にしかこの便利なミニシャワーはありません。タイやフィリピンでの一般的な方法は、トイレの中に水を貯めている水がめのようなものがあり、そこにおかれている小さな洗面器のような容器を右手で持ち水がめから水をすくい、容器に取った水を左手で少しずつお尻にかけていきます。そしてそのまま左手でお尻をふきます。
おそらく、この方式で初めから何の戸惑いもなく用を足せる日本人はそれほど多くないでしょう。しかし、これが現地での「標準式」トイレのルールなのです。紙を持参すればいいではないか、と考える人もいるでしょうが、このようなトイレにはゴミ箱が置いてありませんから、自分のものとは言え便が付着した使用済みのトイレットペーパーを持ち歩くのはかえって大変だと思います。
私が初めてこのトイレの体験をしたのは、タイのある地方都市のデパート内でした。デパートですから、トイレにミニシャワーくらい付いているだろうと考えていたのですが、そのトイレは「標準式」トイレでした。この県で最も人が集まりそうなバスターミナル付近にあるデパートでこのトイレですから、おそらくこの地域にはミニシャワーがついているトイレは皆無でしょう。私は用を足した後、右手で容器を持ち水がめから水をすくい、恐る恐る左手でぴちゃぴちゃとお尻に水をかけてみました。しかし水は上手く肛門に命中しません。そのうちに床が水浸しになってしまい、それ以上水をかけるのをあきらめてそのまま左手でお尻を拭きました。すると、左手指の先端に伝わってきたのはぬるっとした感触で……。苦労したのに水は肛門に届いていなかったのです……。
今では私はこの「標準式」タイ式トイレに何の抵抗もなくなっています。ミニシャワーがついていればそれを使いますが、なくても苦痛にならなくなりました。しかし私はこんなことを自慢したいのではありません。問題は、「現地のトイレのルールを知らずに紙を詰まらせてしまう日本人が後を絶たない」という現実です。
先月(2012年8月)も私はタイに渡航したのですが、チェンマイのホテルの従業員と話しをしているとこの話題になりました。やはりトイレの紙でトラブルを起こすのは日本人だそうです。
けれども、紙を詰まらせた日本人の立場からすれば「そんなこと知らなかったし、今まで誰も教えてくれなかった!」となるわけです。この問題を解決するには、海外(アジア)のトイレのマナーを誰かが教えることが必要です。そう思って、いくつかの旅行会社や旅行関連の書籍を発行している出版社のウェブサイトを見てみたのですが、残念ながらトイレのルールについて解説したものはみつかりませんでした。
ならば学校で教えればどうでしょう。小学校の社会の授業で「世界のトイレのルール」というタイトルで講義をおこなうのです。実習も入れるべきでしょう。ミニシャワーまで取り付けた簡易トイレを用意するのは簡単でないかもしれませんが、きっと生徒たちは興味をもち、さらに世界に関心が持てるのではないかと思うのですが……。
それから、どなたか「世界トイレ辞典」のようなものを作ってもらえないでしょうか。例えば、中国の地方に行くと、今でも壁のないトイレが普通にありますし、ネパールの奥地では、トイレで大便をするとどこからともなくブタがやってきてすぐに便を食べてしまうそうです。このようなことも含めた「世界トイレ辞典」、出版されれば直ちにベストセラー……、とはいかないでしょうか。
************
注1 日本ではなぜ紙を流せるのか、というと下水道が発達しているからです。また汲み取り式なら紙は便と一緒に捨てることができるでしょう。しかし、日本でも場所によっては紙を流してはいけません。私は以前北アルプスに建てられたある山小屋でトイレを借りたことがあるのですが、その洒落た山小屋ではトイレもたいへんきれいに掃除されていました。そしてその壁に貼られていた張り紙には「紙は流さないでください」とあり、アジアのトイレでみるのと同じようなゴミ箱が置かれていました。
注2 他にもアジアでも高級な施設では紙を流してもかまわないところがあるかもしれません。私自身はアジアではどこでも紙を流しませんが、何度か「大便をしたときに紙を流してもいいですか」とホテルの従業員などに尋ねたことがあります。しかし、これを英語で表現するのが思いのほか困難でした。流すは「flush」でいいと思うのですが、私の発音が悪いこともあってなかなか通じません。そこで「wash out」「drain」「run off」「throw away into the basin」などと言ってみるのですが、最終的にはジェスチャーが一番通じました……。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 2025年12月 「振動裁判」は谷口医院の全面敗訴
- 2025年11月 私が安楽死に反対するようになった理由(後編)
- 2025年10月 私が安楽死に反対するようになった理由(前編)
- 2025年9月 人間に「自殺する自由」はあるか
- 2025年8月 「相手の面子を保つ(save face)」ということ
- 2025年7月 「人は必ず死ぬ」以外の真実はあるか
- 2025年6月 故・ムカヒ元大統領の名言から考える「人は何のために生きるのか」
- 2025年5月 「筋を通す」ができないリーダーは退場あるのみ
- 2025年4月 階上キックボクシングジム振動裁判は谷口医院の全面敗訴
- 2025年3月 医師になるつもりもなかったのに医学部に入学した理由(後編)
月別アーカイブ
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (103)