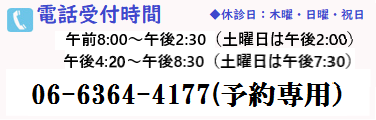マンスリーレポート
2026年2月1日 日曜日
2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
数年前の、あれはたしか総合診療関連の学会だったと思うのですが、ある緩和ケア医が自身の経験について講演していました。その内容は「不要な医療をやめて人間らしい最期を看取るには」というような感じのもので、話の趣旨としてはまあまあ納得できるものだったのですが、その話のなかででてきた「最期の晩餐」の話にすごく違和感、というか、もっといえば不快感のようなものを覚えました。
その医者は担当する末期の患者全員に「最期の晩餐は何がいいか」と尋ねると言うのです。そこから話を広げてその人の人生観を共有するんだ、みたいなことを言っていました。話が巧みなその医者は会場にいた聴講者のひとり(おそらく医者)に、「あなたは何を選びますか」と問い、いきなり質問されたその(おそらく)医者は、たしか「家族旅行のときにみんなで食べたフランス料理が……」という感じのことを答えていました。するとその演者の医者は「やっぱり家族と過ごすのが幸せで……」というおきまりの幸せの方程式のような話に持ち込みました。
次のその医者は意外な展開に話を運ぼうとしたのか「かつてこのテーマで市民講演をしているときにある男性の聴講者に同じ質問をすると『吉野屋の牛丼』という答えが返ってきて驚いたことがあります」という話を始めました。聴衆も意外に感じたのか、会場の空気が「次に演者は何を言うか」に注目している雰囲気になりました。演者は「その男性は『若い頃に苦労していた頃の味がなつかしい』と言うのです」と、これまた感動のヒューマンドラマをなぞるような展開へと持っていきました。
私がこの医師のこの話を聞いてまず不思議に感じたのは、「実際の終末期にはそんなもの食べられるはずがないのにそんなこと聞いてどうするんだ?」というもので、受け入れられず不快感を覚えたのは、私自身がこれまで看取ってきた大勢の患者さんたちを思い出したからです。
私がこれまで大勢の患者さんを看取ってきた時期は2つあります。1つは研修医2年目から3年目にかけて複数の病院で当直のアルバイトをしていた頃です。医師のアルバイトはとにかく破格で一晩で5~10万円も稼げたので(この価格設定がおかしいわけです。まあもらっておいてから「おかしい」という私もおかしいわけですが……)、週に3~4回くらいはそういうアルバイトをしていました(昼間は複数の病院やクリニックで研修を受けていましたから、あの頃はほとんど寝ていなかったのですがその話はやめておきます)。
忙しい病院では救急車をどんどん受け入れながら、病棟では旅立っていく人たちの看取りもします。たいていは点滴や酸素のチューブ、それに尿道の管(カテーテル)がつながれていて意識はすでにありません。モニタが示す心電図の波形や心拍数がおかしくなっていけば看護師が家族を呼び出して「そのとき」を待ちます。そのうち心電図の波形がフラットになり死の兆候を確認し、儀式のような「死亡宣告」をします。「最期の晩餐」を楽しんでいる患者さんなど見たことがありません。
もう1つ、私が大勢の患者さんを看取ったのはタイのエイズホスピスでボランティア医師として働いていた2004年から2005年にかけてです。当時のタイではHIVの薬が使われ始めたばかりで、その待望の薬も副作用で使えないことが多々あり、まだHIVは「死に至る病」だったのです。そのため、大勢の患者さんを看取ることになりました。
そのタイのホスピスでは日本とは異なる大きな点がありました。「末期では点滴や尿道カテーテルを使わない」のです。「タイでは」というよりも「欧米方式では」の方が正確かもしれません。私やタイ人の看護師が相談して点滴を始めようとしても、欧米の医師やボランティアが反対するのです。「点滴は自然な姿ではなく、最期は自然なコースをたどるべきだ」と言うのです。私が接したのは欧米人数人だけですべての欧米人が同じ考えなのかどうかは分かりませんが、彼(女)らは口をそろえてこれが我々の国では常識だと言うのです。
そのホスピスにいた欧米人たちの終末期に対する考えは日本とは大きく異なっていました。あるとき日本人のボランティアが末期に近づいた患者さんにスプーンを使って食事介助をし始めました。すると、米国人の医師は「そんなヘルプはすべきでない」と言ってやめさせたのです。たしかにその患者さんはあと何日も生きられないほど衰弱していて死を待っているのはあきらかでした。日本人女性は「食べれば少しでも元気になるかも」と考えて一生懸命食事介助をしていて、それは日本で見慣れた光景でしたから、私はその若い日本人女性を応援していたのですが、米国人医師は非情にも「終末期に食事を食べさせるのは虐待ともいえる」とまで言うのです。
日本では、最期には食事どころか水分補給も自己でできずに点滴に頼ります。一方、欧米では食事がひとりで摂れなくなればそれは死への自然な道のりだと考えます。どちらがいいかという問題はひとまず置いておくこととしますが、最期まで点滴を続け死にゆく人はたいてい身体中がむくんでいます。他方、私がタイで診てきた点滴をしなかった患者さんたちは全身がエイズに蝕まれていても人間らしく旅立っていくように見えました。
日本でも欧米でも死の直前に食事がとれなくなるのは事実です。ならば冒頭で取り上げた緩和ケア医がいうような「最後の晩餐」を患者さんに語らせることに何の意味があるというのでしょう。
たしかに、食事というのは幸せを感じる瞬間ではあります。愛するパートナーや気の置けない友人との食事は人生を豊かにします。これは間違いありません。また、ひとりで摂る食事であっても、美味しいものを食べる瞬間には幸せを覚えます。食べ物だけでなく、たった一杯の紅茶を飲んだだけでリラックスできて安らぎを感じることもあります。それに、美味しい食べ物のことを考えただけでワクワクすることもあります。よって、食が人に幸せを与えるのは事実です。
ですが、それは本当の意味での幸せでしょうか。あるいは人生において最も大切な幸せでしょうか。もしもあなたが今「最期の晩餐に何を食べたいですか」と問われたとして、食べたいものを想像してワクワクできるでしょうか。「死ぬ間際に〇〇が食べられれば幸せな一生で締めくくれる」と考えられる人は本当にいるのでしょうか。
私にはそんな人がいるとは思えません。「幸せとは?」という問いに対する「答え」を私はずっと考えています。本サイトでも幸せについては度々取り上げています。たいていいつも「幸せについて私は今もよく分かっていません」というような結末になってしまっていますが、それでも最近は少しずつ見えてきたような気がします。その見えてきたひとつが「最期の晩餐で幸せになれるわけではない」です。
人間が本当の意味で幸せになれるのは「他者との関係」に他なりません。これは考え抜いて分かった答えではなく、谷口医院の患者さんたちが教えてくれたことです。例えば、ある50代男性の患者さんは「妻ははように出ていったし、残された娘には父親らしいことなんにもできひんかったけど、そんな娘から『お父さん、ありがとう』と言われたとき、自分はなんて幸せなんやろと思ったんです」と話していました。60代女性のある患者さんは「わたしの人生は辛いことばかりで死んでしまいたいと何度思ったか。けど今の店長がわたしを拾ってくれてコンビニで働きだして、それで初めて他人から感謝されて。店長はわたしの命の恩人です。残業代が出なくても働いているのは幸せだからなんです」とゆっくりと言葉を紡いでいました。
死の直前にすべきことは「最期の晩餐」ではないはずです。では旅立つ直前には何をすべきか。そして本当の意味で幸せとはどのようなものなのか。それは「自分の人生を豊かにしてくれた人たちに感謝の気持ちを述べること」ではないでしょうか。上述の50代の男性なら死ぬ直前に娘に枕元に来てもらうことが最高の幸せでしょう。50代の女性の場合は、死ぬ直前にその「店長」を枕元に呼ぶことはできないかもしれませんが、まだ元気なうちに感謝の気持ちを述べておいて、そして旅立つ直前には心の中で改めてお礼を言うことがこの女性の「最期の幸せ」ではないでしょうか。そして、心の中でお礼を言うのなら、どのような宗教観を持っていたとしても、あるいは無宗教だったとしても、合わせた両手を胸の上に置きたくならないでしょうか。点滴のチューブに邪魔されずに。
人生の最期に「最期の晩餐」を考えるという発想が私には理解できません。そして、点滴での水分補給についてもその必要性を考え直すべきではないでしょうか。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性
- 2025年12月 「振動裁判」は谷口医院の全面敗訴
- 2025年11月 私が安楽死に反対するようになった理由(後編)
- 2025年10月 私が安楽死に反対するようになった理由(前編)
- 2025年9月 人間に「自殺する自由」はあるか
- 2025年8月 「相手の面子を保つ(save face)」ということ
- 2025年7月 「人は必ず死ぬ」以外の真実はあるか
- 2025年6月 故・ムカヒ元大統領の名言から考える「人は何のために生きるのか」
- 2025年5月 「筋を通す」ができないリーダーは退場あるのみ
月別アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (103)