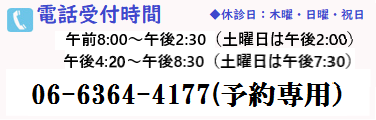はやりの病気
2023年9月10日 日曜日
2023年9月 『福田村事件』から見えてくる人間の愚かな性(さが)
2020年初頭から始まった新型コロナウイルス(以下、単に「コロナ」)に関する騒動はほぼ終わったと言っていいと思いますが、「ワクチン論争」はいまだに続いています。
私自身は「ワクチン肯定派」でも「反ワクチン派」でもなく、「ワクチンは『理解してから接種する』ものであり、接種すべきか否かは個々によって異なる。コロナワクチンの場合は安全性が担保されているとは言い難く、うつのはリスク、しかしうたないのもまた(一部の人には)リスクだ」と言い続けています。
ちなみに、この考えをコロナワクチンが登場したばかりの頃に公表した毎日新聞「医療プレミア」のコラムは大炎上しました。内容は、「コロナワクチンは製薬会社から発表されている有効性は高いが、新しいワクチンだから接種するのはリスクとなる。しかし感染すれば(当時はまだ薬がそろっていなかったこともあり)重症化して命を奪われるかもしれないから接種しないのもリスクである」という内容で、編集部に提出した私が考えたタイトルは「コロナワクチン、うってもうたなくても『大きなリスク』」でした。
それを公開するときに編集者が「新型コロナワクチン 打つも打たぬもリスク大きい」としました。ところがこれが大炎上し、その結果「新型コロナ ワクチン接種はよく考えて」というつまらない(と私は思います)タイトルに変更されてしまいました。
最初のタイトル、そして内容は反ワクチン派、ワクチン肯定派双方の”怒り”を買いました。私がコロナワクチンに関するコラムを書くと、たいてはワクチン肯定派・否定派の双方から攻撃されるのですが、このときには、どちらかというと「肯定派」の人たちからの怒りが強く、私の人格を否定するような内容のものも少なくありませんでした。彼(女)らから、私は「反ワク」のレッテルを貼られたのです。しかし、興味深いことに、同じコラムを読んだ反ワクチン派の人たちは、私が肯定派だ、と言って怒りを表すのです。
こんな論争、というかつまらない言いがかりは無視するしかありません。それに、私はこういう誹謗中傷に慣れている、というわけではありませんが、何を書かれてもほとんど負の感情を抱きません。なかには(特に医師には)SNSで罵られたり悪口を書かれたりすると、それで落ち込んで、極端な場合はそれを根に持って訴訟を起こすこともあるそうですが、私自身は「無視すれば済む話なのに……」と思ってしまいます。
もっとも、SNSの誹謗中傷が原因で自殺した若い女性の話や、そのせいでタレントとしての仕事を失った人の話も聞いていますから、何を書きこんでもいいわけではないということは理解しているつもりです。しかし、私自身は「書きたければ書けば?」と思ってしまいます。きっと、私は(いい意味で)鈍感なのでしょう。ちなみに、私は面と向かって罵詈雑言を吐かれたとしてもあまり苦痛ではありません。まあ、実際にはそんな経験はほとんどないわけですが。
話をコロナワクチンに戻しましょう。ワクチンは個々の状況を考えて決めるべきです。つまり、ワクチンが必要な人もいれば、うたない方がいい人もいるわけです。質問や相談があれば個別に考えて助言するのが医師の仕事であり、谷口医院の患者さんにはそうし続けています。一律に「ワクチン賛成」とか「反対」といった意見を述べることがおかしいのです。
しかも、奇妙なことに、反ワクチンの人(医師も含めて)たちは、決まって「反マスク」と「イベルメクチン信奉」をセットにします。一人くらいは「ワクチンをうたない代わりにマスクで予防しよう」とか「ワクチンをうって、なおかつ感染すればイベルメクチンで対処しよう」と言う医師がいてもおかしくないと思うのですが、そういう医師は(一般市民も)みたことがありません。
なお、マスクについては近くにハイリスク者がいなければ不要ですが、必要な時と場合もあります。それは常識的にもそうだと思うのですが、「反マスク」を強く主張する医師はそうではないという主張を譲りません。ちなみに、最近「英国王立学会」が、マスクが有効であることを示す報告をしています。
なぜ、「反ワクチン+反マスク+イベルメクチン信奉」がセットになるのでしょう。その答えはきっと「人間とは集団闘争が好きな生き物だから」ではないかと私は考えています。つまり、自分の考え(「イデオロギー」と呼んでいいでしょう)に共感する仲間を求め、そして反対する連中を攻撃したいと考える生き物だと思うのです。実は、似たようなことを過去のコラムにも書いています。このコラムでは「リベラル」と「保守」はステレオタイプ化してしまっていて、リベラルなら「自衛隊海外派遣反対」と「福祉充実」がセットになってしまう、などの事例について述べました。
最近、森達也監督の『福田村事件』を観て、やはりそうだろうと確信するようになりました。
『福田村事件』は実際にあった事件を元につくられた映画です。1923年、香川県三豊郡の被差別部落出身の薬売りの集団が、千葉県福田村で朝鮮人と間違われて集団虐殺された事件です。
何年か前にこの事件について初めて聞いたときにまず私が感じたのは「(日本人を殺すのはダメで)朝鮮人なら殺してもいいのか」です。
森監督は私の期待に応え、その部分を浮き彫りにしてくれていました。永山瑛太扮する薬売りのリーダーが……、と書きかけたところで気付きました。このように映画のストーリーを話すことを「ネタバレ」と言うことに。ただ、この映画はミステリーやサスペンスではなく実話に基づいた社会的な映画なので許されるでしょう(許せない人はこれ以上読まないでください)。
話を戻すと、薬売りたちが「朝鮮人ではないか」という疑いをかけられ福田村の村民に囲まれ襲われそうになった状況のなか、一部の良識ある村民のおかげで「(朝鮮人ではなく)日本人ではないか」という空気が流れ始めました。つまり誤解が解けて助かるかもしれない雰囲気になったのです。しかしその直後、薬売りのリーダーは「朝鮮人なら殺してもいいのか!」と大声で何度も訴え村民の周りを歩き始めます。ここで、意外な女性にいきなり殺され、ここから見境のない残酷な殺戮シーンが始まります。
この映画では「差別」が幾層にも絡んでいます。三豊郡(現・三豊市でしょうか)が被差別部落という設定(実話ですから実際もそうだったのでしょう)で、作品中には何度も「エタ」という言葉が飛び交い、彼(女)らが一斉に水平社宣言を暗唱するシーンもあります。
また、別のシーンでは東京在住の社会運動家が警察官に斬首され、朝鮮人の女性が(おそらく)自警団に新聞記者の目の前で殺される場面もあります。さらに、韓国(当時の朝鮮)の京畿道で日本人が29人の朝鮮人を殺戮した提岩里教会事件に関与した元教師が(たぶん)主人公です。
日本人vs朝鮮人、資本主義者vs社会主義者、一般市民vs被差別部落民、といった差別の構図を抉り出し、人間とは敵と味方をつくらずにはいられない愚かな存在だ、ということを森監督は訴えたかったのではないでしょうか。
反ワクチン主義者(あるいはワクチン絶対主義者)がこの映画を観れば私が言いたいことに気付いてくれるでしょうか。
投稿者 | 記事URL
2023年8月20日 日曜日
第240回(2023年8月) 「自然光」と「公園」が”抗うつ薬”になる
旧・谷口医院(太融寺町谷口医院)では2021年1月より、何の予告も挨拶もなく突然入居した階上キックボクシングジムの振動に苦しめられてきました。突然の振動に小さな悲鳴を上げ、身体を震わせる患者さんを前にし、我々医療者はいつ針刺し事故を起こしてもおかしくない環境を強いられ、私自身が精神的に次第に病んでいきました。裁判自体は「振動」の測定データのある谷口医院が有利でしたが、「もうこれ以上事故を起こすリスクを背負えない」と判断し、また、さんざん探した移転先が見つからなかったためにやむを得ず「閉院」を決めそれを公表しました。
ところが予想をはるかに超えた「閉院は困る」という声が届き、最終的には谷口医院に長年通院されている不動産会社の社長から現在の物件を紹介してもらい移転できることになった、という話は随所でしました。
2年7か月ぶりに「振動のない部屋」で仕事をするのは思いのほか快適です。旧・谷口医院ではたとえしばらく静かだったとしても突然ハンマーを落とされたような激しい振動を起こされ、壁や天井が揺れるなかで恐怖に耐えねばならなかったわけですからやはりあの環境は異常でした。その異常な環境に2年7ヶ月も苦しめられ、そしてようやく解放されたのですから快適なのは当然です。
それに、苦しくて恐怖感が消えなかったのは振動だけが原因ではありません。ジムの社長は一度会っただけでは顔を覚えられないような地味な風貌をしているのですが、話がまるで噛み合わず、対面時にはTシャツ、短パン、ビーチサンダルという恰好でやって来て「何か文句あんのか?」という態度。何を言ってもヘラヘラしているだけで、コミュニケーションが一切とれないのです。家主が何か対策をとってくれるのかと思いきや、振動で診察が続けられないことを伝えると「家賃を倍にする」と言われ、そんな無茶苦茶な欲求が認められないことを裁判で告げられると、今度は「谷口医院がビルを不法占拠している」と言いだして谷口医院を訴えてきたのです。
このようなキックボクシングジムと家主から患者さんとスタッフを守らねばならないわけで、今から振り返れば「よく神経がもったな」と思わざるを得ません。おそらくあのまま続けていればいずれ私の精神が破綻したでしょう。この2年7ヶ月は間違いなく私のこれまでの人生の最悪期でした。その地獄のような生活から解放されたのですから、現在は天国にいるようなものです。
しかし、8月14日から診察を開始し数日がたったとき、はたしてこんなにも気持ちがいいのはそれだけなのかと、ふと疑問が湧いてきました。なぜなら、「振動」から解放されたことで快適なのであれば、それはどこにいても同じように快適であるはずだからです。
しかし、実際に快適で気分が安定するのは新しい谷口医院に出勤したとき、なのです。自宅よりも職場にいるときに快適なのは、私が「仕事人間」の証ということなのでしょうか。初めはそうかな、と考えていたのですが、そのうちに妙なことに気付きました。出勤の際、遠回りしたくなるのです。帰り道に寄り道をする人は大勢いるでしょう。ですが、朝の慌ただしい時間にわざわざ遠回りして出勤する人がいるでしょうか。
もっとも、私の場合、朝の7時前後に出勤していますからかなり時間の余裕はあります。しかし、それにしても旧・谷口医院に用事もないのに遠回りして出勤したことなどただの一度もありません。
では、なぜ私は新・谷口医院にはわざわざ遠回りして出勤するのか。おそらく公園の横を歩きたい、あるいは公園を横切りたいからです。ただし、私が遠回りしたくなるのは晴れた日だけです。ということは朝の光が心地いいということなのでしょう。
新・谷口医院に到着し診察室に入ると、まず私は窓から外の景色を眺めます。特に特徴のある景色があるわけではなく、クリニックに面した道路の向こう側はマンションですから、他人の部屋の窓が見えるだけできれいな景色ではありません。しかし、窓は南側にありますから、季節にもよるのでしょうが、窓から差し込む光がなんとも言えない平和的な気分にさせてくれるのです。
こうなると「理屈」が欲しくなるのが私のクセです。もともと私は冬に抑うつ感が生じて春に解消されます。自分は「冬季うつ病」ではないかと疑ったこともあり勤務医時代の2005年にコラムを書きました。そこで、自然光が人を幸せにすることを示した研究がないかどうかを調べてみました。最初に見つかったのが「毎日の太陽光はあなたを幸せにするか? 幸福と天気の主観的な尺度(Does Daily Sunshine Make You Happy? Subjective Measures of Well-Being and the Weather)」で、研究規模が比較的大きいですし、タイトルから期待できそうだと考えたのですが、結局「自然光と幸福感の関係ははっきりしない」が結論でした。
もう少し調べると、一流誌「The LANCET」の2002年12月7日号に「脳内セロトニン代謝に対する太陽光と季節の影響(Effect of sunlight and season on serotonin turnover in the brain)」という論文が見つかりました。脳内でセロトニンが生成される速度は、日光にあたる時間に関係していて、明るさが増すと速度が急速に上がるそうです。「セロトニン=幸せホルモン」と単純化することに私は反対の立場ですが、とは言え私が晴れた日の朝に得ている幸せ感は朝の光で脳内に生成されたセロトニンのおかげかもしれません。
もうひとつ興味深い論文が見つかりました。医学誌「Building and Environment」2022年9月号に掲載された「家屋内での露光による幸福: 居住空間における幸福の認知と悲しみに対する自然光の影響(Enlightening wellbeing in the home: The impact of natural light design on perceived happiness and sadness in residential spaces)」です。
この研究が面白いのでちょっと詳しく紹介しましょう。研究に参加したのは750人。様々な部屋のシュミレーション画像を見てもらい幸せ感または寂寥感を評価してもらっています(シュミレーション画像の写真は論文に掲載されていますので是非見てみてください)。その結果、室内に差し込む自然光の量が多いほど、参加者はより強い幸福を感じることが分かったのです。そして、冬よりも夏の方がより強い幸福を感じるようです。窓の大きさも幸福感の因子になっているようで、壁に対する窓の割合が40%のときに最も幸せ感が強いそうです。参加者の年齢・性別も関与するようで、30歳未満の若者と女性はより強い影響を受けます。
偶然にも、私がいつも仕事をしている診察室の窓は壁のだいたい40%を占めています。窓は南向きのため早朝から夕方まで光が入ってきます。ということは、計らずも私は最適の環境を手に入れたということになるのかもしれません。
ところで私が寄り道をして通っている公園には晴れの日以外は行かないとはいえ「緑」という健康によさそうなものがあります。公園の横にあるマンションは家賃が高いと聞いたことがありますが、公園が健康に良いとする科学的なエビデンスはあるのでしょうか。
ありました。医学誌「International Journal of Environmental Research and Public Health」2014年3月号に掲載された論文「近くの緑地訪問と精神的健康: ウィスコンシン州の健康調査からのエビデンス(Exposure to Neighborhood Green Space and Mental Health: Evidence from the Survey of the Health of Wisconsin)」です。この研究によれば、近隣の緑地のレベルが高いほど、うつ病、不安、ストレス症状のレベルが有意に低いことがわかりました。
さらに興味深い研究が見つかりました。医学誌「People and Nature」2019年8月19日号に掲載された論文「都市の緑地を訪れた人は、Twitter上での感情が高まり、否定的な言葉が少なくなる(Visitors to urban greenspace have higher sentiment and lower negativity on Twitter)」です。人々が公園に訪問前、訪問中、訪問後にどのようなツイートをするかが調べられました。結果、公園訪問中のツイートは感情が(いい意味で)高ぶり、その後数時間はその感情が持続したことが分かったのです。
どうやら現在の私が快適な日々を過ごすことができるのは、キックボクシングジムが巻き散らす振動から解放されたことだけでなく、公園が近くにあって自然光が差し込む部屋で仕事ができるという非常に恵まれた環境のおかげのようです。上述したように、我々にこの物件を紹介し「閉院」の危機から救ってくれたのは不動産会社を経営している谷口医院の患者さんです。本当にありがたい話です。
投稿者 | 記事URL
2023年7月19日 水曜日
第239回(2023年7月) 「GLP-1ダイエット」は早くも第3世代に突入?!
相変わらず質問・相談の絶えない「GLP-1ダイエット」(正確には「GLP-1受容体作動薬によるダイエット」となると思いますが、ここでは簡略化された「GLP-1ダイエット」で通します)。少し前までは、初の内服である「リベルサス」に関する質問が多かったのですが、最近はその先を行く”第2世代”、さらには”第3世代”とも呼べる新しい製品に関心が集まってきています。
といっても第2世代の「マンジャロ」は、日本ではつい最近、(抗肥満薬ではなく)糖尿病の薬として発売されたばかりですし、第3世代の「Retatrutide」は、本稿執筆時点の2023年7月の時点で発売されている国は世界中のどこにもありません。我々医療者でも入手したばかりの情報を一般の人が仕入れて、さらに的確な質問をされることに驚かされます。今回はこれらの特徴をまとめて、今後日本で普及するかどうか、さらに問題点もまとめてみたいと思います。
まずはGLP-1ダイエットの歴史を振り替えてみましょう。
2010年6月 注射薬(1日1回注射)のリラグルチド(商品名「ビクトーザ」)が糖尿病に対して保険処方開始。その頃より、美容系クリニックがダイエット目的にリラグルチド(商品名「サクセンダ」)を輸入し販売開始。徐々に売上を伸ばす
2020年6月 注射薬(週に1回注射)のセマグルチド(商品名「オゼンピック」)が糖尿病に対して保険処方開始。ほぼ同時に、美容系クリニックがダイエット目的として販売開始。1日1回注射のサクセンダに代わりシェアを伸ばす
2021年2月 セマグルチドの内服薬「リベルサス」が糖尿病に対して保険処方開始。ほぼ同時に、美容系クリニックがダイエット目的として販売開始。注射型のオゼンピックに代わりシェアを伸ばす
2023年3月 セマグルチドが「ウゴービ」という名称でダイエット目的で保険薬として承認される。しかし2023年7月20日時点で「薬価収載」されておらず、処方できない状態が続いている
2023年4月 第2世代のGLP-1ダイエット薬(週に1回注射)とも呼べるチルゼパチド(商品名「マンジャロ」)が糖尿病に対して保険診療開始。
2023年6月 米国イーライリリー社が第3世代のGLP-1ダイエット薬とも呼べる「Retatrutide」について、米国サンディエゴで開催された米国糖尿病協会(ADA)で報告した
ここで、なぜGLP-1ダイエット薬を第2世代、第3世代と区別すべきかについて説明しておきます。実は、第2世代、第3世代という表現は正式なものではなく、私が勝手に命名しているにすぎません。しかし、患者さん(閉院・移転の関係で7月以降はメール対応のみ)に説明する上で、このような言い方をすると伝えやすいのです。
第1世代のGLP-1ダイエット薬は、有効成分が「GLP-1受容体作動薬のみ」です。ビクトーザもサクセンダもオゼンピックもリベルサスもこれに該当します。
第2世代は「GLP-1受容体作動薬+GIP受容体作動薬」です。「GIP」(Gastric inhibitory polypeptide)という言葉には聞き馴染みがないかもしれませんが、GLP-1受容体作動薬と同じように、血糖値を下げて肥満を解消する効果があると考えて差支えありません。
第3世代は「GLP-1受容体作動薬+GIP受容体作動薬+グルカゴン受容体作動薬」です。上述したようにGIPという用語はほとんどの人にとって馴染みがない言葉だと思いますが、グルカゴンは高校の生物に出てきますから聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。生物を選択していた人なら「インスリンの反対の作用」と覚えていると思います。
となると、疑問が出てきます。インスリンは血糖値を下げる働きがあるから、それが分泌されなくなったり効きが悪くなったりすれば治療としてインスリンを注射します。そしてこれが従来からおこなわれてきた糖尿病の治療法です。ならばインスリンと反対の方向のグルカゴンを作用させれば血糖値が上がってしまい、糖尿病を悪化させ、さらには肥満を増強しそうな感じがします。私自身も少し前まではそう思っていました。
ですが、実態はどうもそうではなく、グルカゴンはかなり複雑な働きをするようなのです。細かいメカニズムは解明しきれていないようなのですが、臨床試験の結果として、グルカゴン受容体を作用させれば、糖尿病の治療、さらにはダイエットにもつながることが分かってきたのです。ただし、この薬は現時点では学会で有効性が報告された段階であり、商品として市場に登場、さらに日本市場に現れるのはまだまだ先の話です。処方が開始されるにしても先に糖尿病薬としてであり、ダイエット目的の処方は見通しすらついていません。
ところで、谷口医院ではこれまでGLP-1ダイエットを希望する人に対して一切の処方をしていません。しかし「どうしても痩せたい」という人を止めることはできず、美容クリニックで(あるいは一般の内科系クリニックで)処方を受けている(というより購入している)人もいます。驚くべきことに、まったく肥満がないような若い女性にまで、しかも美容クリニックのみならず、一般の内科系クリニックやさらには糖尿病専門医までもがGL-1ダイエット薬を処方しているのが現状です。
では、GLP-1ダイエットに危険性はないのかと言えば「おおいにある」が答えです。まず、肥満がない人はこのような薬を使うべきではありません(と言ってもダイエットに取りつかれた人は何としてでも入手するのですが)。
次にある程度の肥満があった場合も副作用についてきちんと理解しておく必要があります。そもそもGLP-1ダイエットでやせるのは当たり前です。なぜなら食欲が激減するからです。実際、「食べる楽しみを失ったから(GLP-1ダイエットを)やめました」という人は後を絶ちません。
「GLP-1ダイエットのせいで食欲がなくなったから注射を(内服を)中止します」、にはそれほど大きな問題はありません。ですが、「GLP-1ダイエットのせいで命を失(いそうにな)った」は絶対に避けなければなりません。そして、実際、そのような報告が増えています。
EMA(European Medicines Agency、欧州医薬品庁)の安全委員会は、現在GLP-1受容体作動薬が原因の自殺念慮と自傷行為について検討しています。アイスランドではこれまでにGLP-1受容体作動薬が原因と思われる自殺念慮や自傷行為が約150件寄せられています。現時点では欧州の他国の状況や、EMAが今後どのような決定をするかについての情報はありませんが、注意深く経過をみていく必要があります。
翻って現在の日本。過去にも述べたように(下記コラム参照)、日本医師会の今村副会長が「(肥満に対しGLP-1ダイエット薬を処方するのは)医の倫理に反する」とまで記者会見で述べたのにもかかわらず、全国の美容外科医、一部の内科医、さらには一部の糖尿病専門医は肥満者のみならず、肥満がない人(特に若い女性)に処方しています。谷口医院が知る限り、「処方医から自殺念慮や自傷行為のリスクがあると聞いた」と答えた人はゼロです。
誤解のないように言っておくと、谷口医院はGLP-1ダイエットに反対しているわけではありません。むしろ、「ウゴービが保険適用になれば開始しましょうね」と話している患者さんも次第に増えてきています。
ですが、肥満のない人に対する処方は(つまり保険適用外の処方は)谷口医院ではおこなう予定はありません。そのような人たちに対してはこれまで通りオーソドックスなダイエット方法を伝えていきます。これで、けっこうな人たちが理想体重にもっていって健康を維持できているのです。
参考:
はやりの病気第223回(2022年3月)「GLP-1ダイエットが危険な理由」
はやりの病気第228回(2022年8月)「GLP-1ダイエットが危険な理由~その2~」
投稿者 | 記事URL
2023年6月22日 木曜日
第238回(2023年6月) コロナ後遺症予防にパキロビッドかゾコーバを
新型コロナウイルス(以下、単に「コロナ」)がすっかり軽症化し、重症化リスクのある人を除けば取るに足らない感染症に成り下がりました。国民のほとんどがあれほど渇望していたワクチンも、今や希望者は激減し、2021年の「ワクチンをうてる場所がなくて……」という悲痛な叫びがもはや幻のように感じられます。
ではコロナはすでにインフルエンザと同じ程度の、あるいはインフルエンザよりも軽い風邪と考えていいのでしょうか。残念ながらそういうわけではありません。「後遺症」があるからです。
ここでよくある誤解について述べておきます。風邪症状が生じてその後後遺症が残るのはコロナ特有の現象と考えている人がいますが決してそうではありません。生活ができなくなるほどの後遺症が生じる感染症にQ熱、ライム病などがあります。たしかにこれらは稀な感染症ではありますが、インフルエンザやマイコプラズマといったよくある感染症でも後遺症が残ることはしばしばあります。これらに感染した後に咳が1ヵ月続いた、というケースはいくらでもありますし、「倦怠感(だるさ)が取れない」「頭痛をよく起こすようになった」という訴えもまあまああります。
ただし、「半年以上に渡り味覚障害が続いている」といったケースは、私はコロナ以外では知りません。PEM(運動後倦怠感)という現象も、感染症ではなく慢性疲労症候群(ME/CFS)でならよくありますが、感染症後のPEMは、ほとんど私は経験したことがありません。なお、PEM/慢性疲労症候群については過去のコラム「誤解だらけの慢性疲労症候群(ME/CFS)」を参照ください。
他にも、脱毛、性機能障害(コロナ感染後性欲がなくなる、あるいはED(勃起障害)が起こる)、突然動悸が始まるようになった、という後遺症はコロナ以外ではほとんど聞きません。ということは、他の感染症後の後遺症とは異なる、コロナ特有の後遺症があるということになります。
すでに本サイトで公表しているように、当院では2023年5月末からコロナ後遺症の点数化を試みています。12の項目の合計点が12点以上あれば、「コロナ急性期後の後遺症(postacute sequelae of SARS-CoV-2 infection」、通称「PASC」の診断がつけられます。そして、PASCの診断がついた事例だけを正式な「コロナ後遺症」とすべきだ、とする意見が世界では増えてきています。
診断基準を点数化するという試みは、我々医療者にとってはありがたいものです。診断が簡単になるからです。特にコロナ後遺症の場合は、診断書や傷病手当を書くべきか否か、という社会的問題が伴いますから、こういった書類を作成するときにはありがたいツールとなります。
ですが、患者さん側からみたときは、症状が点数化されてもそれが治療につながるわけではなく、また自身では重症だと思っていたのに点数が11点しかなくて、そのせいで給付金がもらえなかった、という事態が生じるかもしれません。よって、診断基準の点数化は患者さんにとっては利点があるとは限りません。それに、これら12の診断基準はどれもが「(検査などで)確かめようがないもの」ですから、簡単に”嘘”を言うことができます。ですから、あらかじめこの基準を知っていれば医師の前で嘘をつくことによっていくらでも点数を上げることができるのです。
このように診断基準の点数化は問題が多数あり、また患者側からみればそんな点数はどうでもよくて、最重要事項は「治してほしい」です。ところが、コロナ後遺症の治療は本当に難しいのです。もちろん、当院で治った人も多数いるのですが、そのなかの何割かは薬が効いたのか自然に治ったのかの区別がつきません。漢方薬もよく使いますが、他の疾患に比べて漢方薬のキレがよくないというか、やはり効果があるのか自然に治ったのかがよく分からないのです。
「ワクチン」が治療になることはあります。実際、苦しい後遺症に苛まれていたけれど、ワクチンをうったとたんに(本当に”とたんに”)よくなる人もいるのです。しかし、その一方で、ワクチン接種で余計に悪くなる人もいるので、安易には勧められない方法です。英国のデータによると、ワクチン接種で後遺症が改善した人は56.7%に上りますが、18.7%の人たちは逆に悪化しています。
日本の論文もあります。後遺症を抱える患者の20.3%はワクチン接種2週間から6か月後に症状の改善を認めたものの、54.4%はワクチン接種後も症状の変化がありませんでした。この結果から著者らは「ワクチンは症状の変化に関係がない」と結論づけています。
どうやら「後遺症を発症すればコロナワクチンで治す」という方法には期待しない方がよさそうです。ただし、コロナワクチンは「後遺症のリスクを下げる」効果はありそうです。この日本の論文では、ワクチンを2回接種すると、未接種者に比べて後遺症発症リスクを36%、1回接種者に比べて40%下げることが分かりました。仏人を対象とした研究でもワクチン接種が後遺症のリスクを下げるという結果が出ています。医学誌「BMJ」2023年3月1日号の論文「コロナワクチン接種により重症及び後遺症が軽減されると研究で判明(Covid-19: Vaccination reduces severity and duration of long covid, study finds)」によると、ワクチン接種者は未接種者に比べて後遺症がすべて消失した人は2倍にもなります。
こうしてみると「後遺症を防ぎたければワクチン接種」となります。ですが、感染後の後遺症ではなく、ワクチンの後遺症に悩まされている人が少なくないのもまた事実です。そして、冒頭で述べたように、現在コロナワクチンをうたないという選択をする人がどんどん増えてきています。
しかし、後遺症にはいまや効果的な「予防薬」があります。パキロビッド、ゾコーバ、ラゲブリオといった抗コロナ薬です。本来、抗コロナ薬は感染が判った直後に内服することによって「重症化リスクを下げ」、「有症状期間を短くする」効果が期待できます。それらに加えて、後遺症のリスクを下げる効果も期待できるのです。
私の実感としては、パキロビッドは確実に後遺症のリスクを下げてくれます。論文では26%下げるとされていて、この数字は小さいように思えますが、谷口医院の経験でいえば「パキロビッドを服用して後遺症の生じた事例はゼロ」です。
ラゲブリオは重症化リスクを下げるかどうかは疑わしく、欧州では「ラゲブリオを使用すべきでない」と勧告されています。しかし、後遺症のリスクを軽減させるのは確実らしく、ある論文によると、ラゲブリオは感染後180日日後の絶対リスクを2.97%低下させます。2.97%という数字が小さすぎる気がしますが……。また、塩野義製薬によると、ゾコーバは後遺症のリスクを45%も低下させるそうです。ただし査読済の論文が発表されていませんからエビデンスがあるとは言えませんが。
では、なぜ抗コロナ薬が後遺症にも有効なのでしょうか。一部の患者は「長期間ウイルスが体内に残っているから」という説が最近注目されています。発症してから230日後に、脳全体を含む複数の部位でウイルスのRNAが検出されたという報告があります。また、海外メディアによると、英国では患者の体内からウイルスが発症505日目に検出されたという報告もあります。
通常、身体の隅々までウイルスの有無を検査することはできませんから(生きている状態で脳にウイルスがいるかどうかを調べることはできない)充分に調べられていないだけで、実際には後遺症で苦しんでいる人のいくらかはウイルスが残っているのかもしれません。現在のルールでは抗コロナ薬を使用するのは発症直後に限られていますが、後遺症で苦しんでいるケース(例えば前述の診断基準で12点以上のケース)では使用を認めるべきなのかもしれません。
現時点で後遺症発症予防に対してできることはワクチンと発症直後の抗コロナ薬です。後遺症のリスクが高い人(谷口医院では「精神状態が脆弱な中年女性」が後遺症の最たるリスク)は積極的に考えた方がいいかもしれません。
投稿者 | 記事URL
2023年5月22日 月曜日
第237回(2023年5月) 麻疹(はしか)とこれからの発熱外来
麻疹(はしか)が流行しつつあります。麻疹そのものについての情報提供はこれまで、このサイトおよび他のサイトに私が書いたものもありますので(下記の毎日新聞「医療プレミア」の麻疹に関するコラムはすべて無料で読めます)、興味のある方にはそちらをご覧いただくとして、ここでは今後「麻疹かもしれない」と思ったときにどのように医療機関を受診すべきかについて述べていきたいと思います。
まず、「麻疹の再感染及びワクチン接種後の感染」について話をしておきましょう。
先日(2023年5月17日)、テレビ朝日の「ABEMA Prime」の出演依頼を受けて麻疹に対する話をしました。生放送ということで、どのような質問をされるのか不安があって、さらに、リハーサルなし、それどころか私自身が出演者と面識がないどころか、失礼ながら私がテレビを見ないこともあって、キャスターやパネリストがどのようなキャラクターの方々なのかもまるで分からない状態で番組がスタートしました。
しかも、私の出演はオンラインですからスタジオの”空気”が読めません。生放送で場違いなことや、空気が読めない発言をすれば大変なことになります。番組の「台本」のようなものを開始直前に受け取ったのですが、それをすべて読み終わらないうちに番組が始まってしまいました(下記URLで1週間はオンデマンドで診られるそうです)。
興味深いことに、そして非常に幸いなことに、キャスターの益若つばささんが冒頭で私にとってとてもありがたいコメントをしてくれました。益若さんは最近帯状疱疹に罹患されたそうです。そのときに「子供の頃に水痘(みずぼうそう)にかかったことがリスクと言われた。麻疹もそうなのかどうかが心配です」といったことを発言してくれたのです。しかも番組の途中で、再度その疑問を取り上げてくれました。
これは多くの人が知りたいことであり、医師の立場からみれば「極めて良い質問」です。そして、この答えは「麻疹の再感染はない」です。益若さんが苦しまれた帯状疱疹はたしかに過去の水痘ウイルスの感染が原因です。ですが、麻疹の場合は感染して治癒すれば強力な「抗体」ができて二度と感染することはありません。
その番組で私は「個人的な意見だが麻疹のパンデミックは起こらない」と述べました。その理由は2つあります。1つは2006年に麻疹ワクチンは2回接種が定期化されたために現在の18歳未満のひとたちはしっかりとした抗体があるから。そしてもう1つは現在55歳(あるいは60歳)以上の人たちの大半は感染しているために自然の抗体ができているからです。
通常、パンデミックが起こって多数の犠牲者が起こる感染症は免疫能が不十分な小児と高齢者を襲います。ところが麻疹の場合は、この2つのグループが強固の免疫で守られていますからパンデミックの心配はないのです。
では、ワクチンを2回接種した場合はどうでしょう。この場合はなかなか100%感染しないとは言えません。ワクチンを2回接種したのにも関わらず感染してしまう可能性はあります。ただし、ワクチンを2回接種していれば重症化することは(ほぼ)ありません。高熱が出ず、皮疹もごくわずかの軽症で済むのです。これを「修飾麻疹」と呼びます。
本稿執筆時点で2023年4月から5月にかけて麻疹を発症した事例が4例報告されています。1例目はインドで感染した茨城県の30代男性、2例目と3例目は1例目の男性と同じ新幹線の車両に乗車していた30代女性と40代男性。そして4例目が神戸の事例で、1例目の男性が神戸に移動していたことからこの男性から感染したものとみられています。これら4例のうち神戸の事例については公表されていないので詳細が分かりませんが、他の3例についてはいずれもワクチン未接種(または接種歴不詳)とされています。
茨城と東京の3例はいずれも入院しているようでおそらく軽症ではないのでしょう(4例目の神戸の事例は詳細不詳)。ということは、やはり麻疹対策での最重要事項はワクチンということになります。つまり、高齢者は既感染で、18歳未満は2回のワクチン接種で免疫を得ているわけですから「20~50代のワクチン追加接種」がパンデミックを回避するための最大のポイントになります。
もしもあなたがワクチン未接種または1回接種のみだったとして、麻疹かもしれない発熱が出たときはどうすればいいでしょうか。麻疹は「皮疹」が有名ですが、これは後半に出ます。もう少し正確に言うと、麻疹の発熱は「二相性」といっていったんは解熱します。そのときに口の中に白い斑点(これを「コプリック斑」と呼びます)ができ、その直後に2回目の発熱が起こり、このときに全身に皮疹が出現します。
1回目の発熱時ですでにかなりの倦怠感が伴います。この時点では麻疹よりは新型コロナ、またはインフルエンザが疑われることもあるでしょう。つまり、皮疹があろうがなかろうが、高熱と倦怠感があれば、医療機関の発熱外来を受診するしかないわけです。過去3年で私は何十回と繰り返して訴えてきたように「発熱外来」のあるかかりつけ医を見つけておくのがものすごく大切です。
では、軽症の場合はどうでしょうか。これも何度もお伝えしているように「新型コロナであろうがインフルエンザであろうが、重症化リスクのない人の場合は医療機関受診はそもそも不要」です。何もしなくてもそのうち治るからです。もっともこれは受診してはいけないという意味ではありません。場合によってはオンライン診療も含めて受診を検討すべきでしょう。
では軽症の麻疹を疑ったときにはどうすればいいのでしょうか。例えば、微熱と(特にかゆくない)皮疹が出た場合、我々はほぼ全例で麻疹を鑑別に加えます。そして、麻疹の疑いがあればどうするか。答えは「隔離」です。場合によっては軽症でも保健所と相談して入院先を探すこともありますし、入院できない場合は他人と接することのないよう自己隔離してもらいます。
なぜ、麻疹に感染すると隔離されなければならないのか。もちろん他人への感染リスクを下げるためですが、それならばインフルエンザや新型コロナと同じと思われるかもしれません。ですが、違うのです。新型コロナやインフルエンザよりも麻疹の方が他人への感染リスクを下げることがずっと重要なのです。
2016年にインドネシアで麻疹に感染した30代の日本人男性は現地で重症化し、意識をなくし人工呼吸器の装着を余儀なくされました。帰国後はリハビリを開始しましたが、後遺症が残ったと報告されています。風疹と異なり、麻疹は妊娠中の女性が感染しても母子感染はありませんが、赤ちゃんのみならず母体の命が危険に晒されます。つまり、ワクチン未接種(または1回接種のみ)の人たちがそれなりに多い現状に鑑みると、他人への感染は可能な限り避けなければならないのです。
麻疹の潜伏期間は10~12日程度あります。この間にも他人に感染させる可能性があります。発症後も、軽症であれば行動を控えない人もいるでしょう。一般的に麻疹に感染すると発症から完全治癒まで2~3週間はかかります。こんなにも自己隔離することはできない、と考える人もいるでしょう。ですが、成人が麻疹に感染したときのリスクを甘くみてはいけません。実際、4月から5月に感染した人たちは入院しているわけです。
日本には「はしかにでもかかったようなもの」という慣用句があり、これは一過性の発熱のみ、つまり「軽症」であることを示しているわけですが、成人に感染した場合のことを考えるとこの慣用句は必ずしも適切ではないのです。
参考:
マンスリーレポート
2016年9月 麻疹騒動から考える、かかりつけ医を持たないリスク
医療ニュース
2017年5月29日 ワクチン1回では不十分~後遺症も残る麻疹脳炎~
2016年8月31日 麻疹とマスギャザリング
「医療プレミア」
2022年12月19日 麻疹 「世界の全地域で差し迫った脅威」とWHOが訴えるわけ
2019年9月22日 人ごとでないフィリピン「ワクチン不信」と麻疹急増
2017年6月4日 本当に「大丈夫」?渡航前ワクチンの選び方
2016年4月3日 SSPE 恐ろしい「はしかのような」病から学ぶこと
2016年3月27日 麻疹感染者を増加させた「捏造論文」の罪
投稿者 | 記事URL
2023年4月22日 土曜日
第236回(2023年4月) これからの性感染症対策~mpox, DoxyPEP, HIV~
2023年3月下旬、肛門周囲にびらん(ただれたような状態)のある患者さんが受診し、診断はmpoxでした。この新しい(性)感染症は、感染性が桁違いに強く、この患者さんの場合は自らが疑ってくれていたので事なきを得ましたが、もしもそうでなかった場合は、(新型コロナウイルスの初期のように)谷口医院が「数週間の閉鎖」をしなければならなかったかもしれません。
2021年より問い合わせが増えだした「DoxyPEP」。最近ますます希望者が増えています。しかし、この予防法は気軽におこなうべきではありません。
依然感染者が減らないHIV。しかし、毎日飲む抗HIV薬は副作用がほとんどなくなり、しかも1日1錠が標準的な治療となってきています。さらに、2ヶ月に一度実施する注射薬も登場しました(当院ではまだ扱っていませんが)。しかし、治療が簡単になってきたとはいえ、生涯にわたり続けなければなりませんから感染はなんとしても防ぎたいものです。そして、それが可能なのが(PrEPと)PEPです。
今回の「はやりの病気」は、最近の性感染症の注目すべき点を復習し、今後、感染を防ぐためにはどのようなことに気を付ければいいのか、感染したかもしれないときにはどうすればいいのかを述べていきたいと思います。
まずはmpoxをみていきましょう。ややこしい名前について先にまとめておきましょう。この疾患は当初はmonkey pox(日本語はサル痘)でした。しかし、「サルに失礼」という声が世界中から寄せられたために、WHOはmpox(Mpoxではなくmpox)に変更しました。このとき、日本では「M痘」になると報道されたのですが、結局厚労省は「エムポックス」としたようです。ややこしいのでここではmpoxで通します。
mpoxには現時点で特効薬がありません。治験中の薬はありますが、一般の医療機関で処方できるようになるのはまだ当分先の話です。となると、ワクチンに期待したいところですが、このワクチンが非常に複雑です。結論からいえばあまり有用ではありません。解説しましょう。
mpoxのワクチンは生ワクチンと不活化ワクチンがあります。生ワクチンはmpoxではなく天然痘のワクチンです。これがmpoxにも効くのではないかと考えられているのです。しかし、仮に効いたとしても「禁忌(接種できないケース)」が多くて使い物になりません。そもそもmpoxの最大のリスク因子は「HIV陽性」です。しかし、生ワクチンはそのHIV陽性者に接種できないのです。これは抗HIV薬を服用していてウイルスが血中から検出されない場合でも、です。
次に、生ワクチンはアトピー性皮膚炎を含む慢性湿疹を患っているか、または過去に患っていた場合も禁忌となります。しかし、(mpoxのように)皮膚から皮膚に感染する感染症は、アトピーなどの炎症があればうつりやすいのです。皮膚のバリア機能が損なわれ感染症に対して脆弱になるからです。
ということは、生ワクチンは最大のリスク因子であるHIV陽性者に使えず、また、皮膚感染を起こしやすい湿疹のある(あった)人にも接種できないわけです。ハイリスク者に使えないワクチンではどうしようもありません。
不活化ワクチンは有効で、実際、米国はハイリスク者に集中してワクチンを(無料で)接種したことで短期間でmpox対策に成功しました。このワクチン、本来は1瓶が1回用なのですが、なんと米国政府は1瓶を5分割して5人に接種したのです。従来の筋肉注射ではなく皮内注射で接種しました。このような接種方法は標準的でないことから、ワクチンの製造会社(デンマークのBavarian Nordic社)からは、一時は「米国との取引をやめる」と言われたものの米国は強引に押し通しました。このやり方には賛否両論があるでしょうが、結果として米国がmpox撲滅にほぼ成功したのは事実です。
一方、日本は不活化ワクチンどころか、(あまり役立ちそうにない)生ワクチンでさえ供給不足です。例えば、すでに感染者の診察をして、今後も診察することになるであろう私でさえ、現在の規定ではワクチン接種を受けることができないのです。
ワクチンが使えないなら他の予防が重要になります。そして、mpoxは感染力がものすごく強いのは間違いありません。感染者の報告では、ゲイの男性が性行為を通して、というケースが多いのは事実ですが、例えばパーティで皮膚と皮膚が触れただけで感染したストレートの男性や女性の報告もあります。米国では家庭内での小児への感染も報告されています。国立国際医療研究センターによると、複数の男性と性行為をもった30代女性や、初対面の女性と性行為をもった40代の男性らの感染も報告されています。つまり「ゲイに多いのは事実でもゲイの感染症ではない」のです。要するにHIVと同じです。
ではどのように予防すればいいのでしょう。ECDC(欧州疾病予防管理センター)によると、ベッドリネンなどに付着したウイルスは、数カ月からなんと数年間にもわたって感染性を維持することがあります。ということはmpox陽性者に触れたものに触れば感染の可能性が出てくる、ということになります。
皮膚にウイルスが触れただけではそう簡単には感染しないでしょうが、そこに傷や炎症があればリスクが出てきます。ということは、傷や炎症がある部分は露出しないようにして、かつ手洗いをマメにすればOKです。mpoxはアルコールで死滅しますが、アルコールを使い過ぎないようにして流水下での手洗いをメインにするようにしましょう。アルコール使用で手荒れが起こればそちらの方がリスクとなるからです。
そして、言うまでもなく「初対面の人との性行為」はリスクとなります。ロマンスは突然生まれることも多いわけですが、mpox感染のリスクが背負えるかどうかは充分に考えなければなりません。
次いでDoxyPEPの話をしましょう。この”治療法”の問合せをしてくるのは、ほとんどはゲイの西洋人なのですが、最近少しずつ日本人(やはりゲイ)からも増えてきています。ということは、日本人のストレートの男女からの問合せもそろそろ始まる頃だと思います。DoxyPEPとは、抗菌薬ドキシサイクリン(DOXY)200mg(100mg2錠)を性交後72時間以内に一度だけ内服する方法で、クラミジア、梅毒、淋菌を、それぞれ90%、80%、50%防ぐことができるとされています。ただ、医療ニュース「DoxyPEPを過信するべからず」で述べたように、耐性菌を生み出すリスクもありますから、この方法に頼ってリスクのある性行為を持つべきではありません。
HIVについては谷口医院を開院した2007年に比べると治療のやりやすさには雲泥の差があります。当時から抗HIV薬はありましたが、副作用がつらくて、できるだけ内服開始を遅らせるのが目標でした。ところが、最近は1日1錠のみの内服で済み、内服を続けられないような副作用はほとんどありません。最近は(谷口医院では実施していませんが)2ヶ月に一度だけ注射すればOKの注射薬も登場しています。
そして後発品を用いたPEPができるようになったことがかなり大きいと言えます。以前は先発品でしかできませんでしたからPEPを実施しようと思えば30万円近く必要でした。それが現在は後発品が使えますからその6分の1以下の費用でできるようになったのです。それでも依然安くはありませんが、「安心が買える」わけですから非常に有用な治療法です。
性感染症の予防で最も大切なことは「誠実な相手と交際する」ですが、長い人生の間にちょっとリスクのある行為に及ぶこともあるかもしれません。以前なら、そういう状況を想定して、1)B型肝炎ワクチンの接種と抗体形成の確認、2)コンドームの使用、3)ワクチンでもコンドームでも防げない感染症の検査、の3つが重要でした。
ところが現在はmpoxという厄介な感染症が加わりましたから、しばらくの間(少なくともmpoxがおさまるまでの間)、リスクをとることを避け、誠実なパートナーを見つけるのが最も優れた対策と言えるでしょう。
投稿者 | 記事URL
2023年3月19日 日曜日
第235回(2023年3月) 温泉好きの長引く咳はレジオネラ
2023年2月24日、筑紫野市の「二日市温泉 大丸別荘」を訪れた人が体調不良を訴え医療機関を受診、レジオネラ症と診断されていたことが発表されました。原因はその旅館の浴槽から検出されたレジオネラ菌であることが判明しました。
レジオネラというのは肺炎で有名なのですが、通常の肺炎と異なる点がいくつかあり、感染しても放っておいてもいいことがある一方で、「死に至る病」となることもあります。筑紫野市の温泉事件でいろんなことが報道されましたが、必ずしも正確に伝わっていないようなので、ここでまとめておきたいと思います。
このような出来事はあってはならないことではありますが、そうは言ってもそんなに珍しいケースではなくひとつの典型的な発症パターンです。よって、自分自身や家族の感染を防ぐためにもこの事件を振り返っておきましょう。
・保健所による旅館の検査が2022年8月と11月に実施されて.いた。この旅館の浴槽からは基準値の3,700倍に相当する量のレジオネラ菌が検出されていた
・福岡県の条例では週に一度以上の湯の入れ替えが義務付けられているが、この旅館では少なくとも2019年以降、年に2回しか入れ替えをしていなかった
・旅館は「常に源泉からお湯を入れながら循環させる仕組みなので大丈夫だと思っていた」と釈明した
なぜ保健所の検査でレジオネラ菌が検出されていたのにもかかわらず、旅館は処理をしなかったのでしょうか。旅館が保健所の指導を無視したか、保健所がしっかりとした指導をしていなかったかのどちらかでしょう。
常識的には「この旅館からはレジオネラ菌が検出されました。この病原体はときに死に至る病を引き起こします。条例どおりの対処法で充分ですからきちんとしてください」と言われれば旅館はそれを守るのではないでしょうか。保健所の指導を無視するとは考えにくく、だから保健所がきちんと対処方法を伝えてなかった、つまり保健所の怠慢なのかな、と思われますが、実際のところは分かりませんからこれ以上の詮索はやめておきます。
重要なのはそういった「不潔な温泉の見分け方」です。保健所がきちんと検査をしているか、とか、旅館は保健所の指示を守っているか、といったことは宿泊客には分かりません。ですが、「レジオネラ菌がいるかもしれない温泉や浴場」は推測することができます。
床やタイルに「ぬめり」があれば要注意、と考えるのです。「ぬめり」の正体は微生物が作り出すぬめっとした(slimyな)膜のようなものです。キッチンのシンクの「ぬめり」が代表です。この「ぬめり」をバイオフィルムと呼びます。
キッチンのシンクにできるバイオフィルムを作り出しているのは細菌なのですが、温泉や浴槽でバイオフィルムが存在していれば、細菌だけでなく「粘菌」と呼ばれる微生物が原因のことがあります。粘菌よりも「アメーバ」という言葉の方が有名かもしれません。そして、レジオネラ菌はこの粘菌(≒アメーバ)の体内に棲息します。
レジオネラという細菌は「蒸し暑い環境」が大好きです。50度でも数時間生存することができ、20度以下では増殖できません。35度くらいが至適温度と言われています。よって、温泉や浴場はレジオネラ菌にとってうってつけの場所なのです。
温泉や浴場というのは蒸気(エアロゾル)が蔓延しています。当然その蒸気のなかにはレジオネラを含む粘菌も浮遊しているわけです。これをヒトが吸い込んで、肺胞まで到達すると感染が成立します。そしてヒトの肺胞で増殖したレジオネラ菌は全身を巡ります。結果、下痢、嘔気・嘔吐、腹痛などの消化器症状、さらに頭痛や痙攣、重症化すれば意識症状などの神経症状も起こり得ます。このため、レジオネラ肺炎という言い方の方が人口に膾炙しているかもしれませんが、「レジオネラ病」と呼ぶ方が正確です。
もちろん、レジオネラ菌を含む蒸気を吸い込んだとしても誰に対しても感染が成立するわけではなく、また感染が起こったとしても全員が発症するわけではありません。当然、無症状で治癒することもあるでしょうし、また軽症で終わることもよくあります。
この「レジオネラ菌に感染して風邪症状が出たけれどすぐに治った」というケースを「ポンティアック病(Pontiac fever)」と呼びます。こちらは軽症ですから、そもそも発症しても全員が医療機関を受診するわけではありません。仮に受診したとしても治療は不要です。これはレジオネラ菌が検出されても、です。
しかし、ポンティアック病の診断確定(=レジオネラ菌検出)には重要な意味があります。それは、その地域でこれから(あるいはすでに)レジオネラ病が発症する(している)可能性があるからです。つまり、ポンティアック病の診断がついてその人が旅館に宿泊していたとすれば、その旅館の宿泊客の健康調査をすることでレジオネラ病の早期発見ができる可能性があるのです。尚、レジオネラ菌の検査は尿検査でおこないます。精度は高く、喀痰のPCRよりも遥かに実用的です。
ポンティアック病の名前の由来はミシガン州のポンティアックという地名(デトロイトの近く)で発見されたことによります。1968年のことでした。ちなみに、本稿を執筆するにあたり、ポンティアックの場所を確認するためにGoogle Mapに「Pontiac」と入力すると、米国だけでも10カ所くらい表示されました。ポンティアック病の発症の地はデトロイトの近くです。
レジオネラ病で知っておきたい特徴はまだあります。通常、感染症の肺炎というのはヒトからヒトにうつりますが、レジオネラの場合、感染源は蒸気(エアロゾル)の吸入ですから、ヒトからヒトに感染することはありません。ですから、ときに死に至る病となる重要な感染症ではありますが、隔離は必要ありません。
一般の人からみてレジオネラを予防するには「温泉や旅館に行くときはぬめり(slim)がないかに注意する」となりますが、では、温泉や旅館の側からみればどのような対策を立てればいいのでしょうか。
温泉や浴槽でレジオネラが発症する、つまりバイオフィルムができるのは、通常の家庭用の浴槽と異なり、「循環式浴槽」だからです。この循環式浴槽が清潔にされていなければ、粘菌が増殖し、その粘菌の体内でレジオネラ菌が増殖するというわけです。そこに熱が加わり、その粘菌がエアロゾルとなって空気中を浮遊すると、それを吸い込んだ人がレジオネラ症を発症するのです。
件の筑紫野の旅館は「循環式だからレジオネラ菌も流される。だから清潔」と考えていたようですが、バイオフィルムのせいで長時間浴槽に粘菌と一緒にこびりついているのです。ですから、循環式浴槽だからこそ清潔にすべきだ、と考えなければなりません。その対策については、厚労省がわかりやすいマニュアルを公開してくれています。その名もズバリ「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」です。このマニュアルには「連日使用型循環式浴槽では、1週間に1回以上定期的に完全換水し、浴槽を消毒・清掃すること」と書かれています。
最後に医療者からの視点で大切なことを書いておきましょう。レジオネラは通常の肺炎でよく使われるペニシリン系やセフェム系の抗菌薬が一切効きません。ということは、「診断をつける」ことがものすごく大切になります。尿検査で簡単に分かると述べましたが、肺炎の症状がある患者さん全員にレジオネラを調べるのは現実的ではありません。医師は肺炎症状を呈している患者さんを診て、真っ先にレジオネラを疑うわけではないのです。ですから、心当たりのある人は「温泉に行きました」と医師に伝えてください。
投稿者 | 記事URL
2023年2月20日 月曜日
第234回(2023年2月) アルコール飲料は「百害あって一利なし」か
「アルコールは大量に飲みすぎると身体を害するけれど、少量ならむしろ健康増進に役立つ」と昔から言われてきました。実際、それを示した研究もいくつかあります。
しかし、ここ数年、「どうもそれは違うのではないか。飲酒は百薬の長どころか、百害あって一利なしではないか」という意見が増えてきています。そこで今回は比較的新しくて信ぴょう性が高いと思われるいくつかの研究を紹介し、いったい飲酒は身体に良いのか悪いのかを改めて考えてみたいと思います。
まず、日本人を対象に「飲酒が身体によい」と結論付けられた代表的な研究を紹介しましょう。2004年に医学誌「British Journal of Cancer」に発表された「総がんリスクに対する飲酒の影響:日本における大規模集団研究(Impact of alcohol drinking on total cancer risk: data from a large-scale population-based cohort study in Japan)」です。
この研究の結論は「男性では機会飲酒者(occasional drinkers)のがんの発生率が最も低い」とされています。論文をきちんと読むと、機会飲酒者のがんの発生リスクを1.00とすればまったく飲まない人のリスクは1.10。つまり、「まったく飲まない人はときどき飲む人に比べて発がんリスクが1割高い」となります。これだけを言われればちょっとくらいは飲んだ方が身体に良さそうです。ビール酒造組合のウェブサイトにもこの論文が紹介されています。
では、もう少し詳しくこの論文をみてみましょう。機会飲酒者に対して定期的飲酒者(regular drinkers)のデータを紹介します。機会飲酒者のリスクをゼロとすると定期的飲酒者の週あたりのアルコールの量とがん発生率は次のようになっています。
発がんリスク 缶ビール350mL換算
アルコール1~149g/週 1.18 10本/週
アルコール150~299g/週 1.17 10~21本/週
アルコール300~449g/週 1.43 21~32本/週
アルコール450g以上/週 1.61 32本以上
これをみれば、ビールのロング缶(500mL)を1日1本程度飲めば、機会飲酒者に比べて18%発がんリスクが上昇することが分かります。ところで、ロング缶(または中瓶)1本と聞けば、なんとなく「少量」という気がしないでしょうか。ところが、この量でもリスクがこれだけ上昇しているのです。ということは「酒は百薬の長」が事実だったとしても、その「量」は「350mLの缶ビール1日1本以下」となるわけです。
このように論文を読むと、上述したビール酒造組合のウェブサイトに書かれていることがひっかかります。このサイトは、「一日にビールに換算して、350mL缶で2、3本程度のお酒を飲む人が、最も心臓血管疾患のリスクが低い」と書いて、その次にこの日本人を対象としたがんのリスクの研究の論文を紹介しているのです。
素直に読めば、ビール1日350mL缶2、3本が日本人のがんのリスクを下げるかのような印象をもってしまいます。余程注意深く読まなければ「缶ビール毎日3本くらいがちょうどいい」と錯覚してしまいます。同組合がわざと誤解させるようにウェブサイトを構成している、と感じるのは私だけではないでしょう。
尚、日本人を対象としたこの研究では女性のデータはありません。また、「ビール(及び他のアルコール飲料)にどの程度のアルコール(g)が含まれているか」は厚労省のサイトが参考になります。
冒頭で述べたように、最近アルコールは少量でも有害であるとする研究が増えています。2023年1月18日のNew York Timesは最近(2023年1月)に新たに発表されたカナダのガイドラインを取り上げています。
このガイドラインの5ページは少々衝撃的です。イラストをみれば一目瞭然で「お酒はまったく飲まないのが一番いい」のです。缶ビール1本でも健康上有害だというのです。
ではカナダ政府が気を衒ったことを言い始めただけで世界の潮流は依然「少量なら健康に良い」なのでしょうか。”残念ながら”そうではありません。2023年1月4日、WHO(世界保健機関)は「我々の健康にとって安全なレベルのアルコール消費はない(No level of alcohol consumption is safe for our health)」という声明を発表しました。上述のカナダのガイドラインもWHOのこの発表の影響を受けてのものだと推測されます。WHOの主張をまとめてみます。
・アルコールは少なくとも7種類のがんの原因となる。
注:WHOのこのサイトには7つの詳細を書いていませんが、これは口腔咽頭がん、喉頭がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、直腸がん、乳がんの7つで、2016年に医学誌「Addiction」に掲載された論文が示しています。
・欧州地域におけるすべてのアルコールに起因するがんの半分は「軽度」および「中等度」のアルコール消費が原因。具体的には、ワインなら週に750mLのボトル2本未満、缶ビールなら500mLを1日1本。
・そもそもアルコールは「グループ1」の発がん物質。グループ1にカテゴライズされている他の代表的な物質は、アスベスト、放射線、タバコ。
なんとも衝撃的な発表です。他の論文もみてみましょう。医学誌「Nature Communications」2022年3月4日号に掲載された論文「英国人におけるアルコール消費量と灰白質および白質量との関連(Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank)」によると、「1日平均1~2単位のアルコールでも脳が委縮」します。これは英国のバイオバンクと呼ばれるデータベースに登録されている36,678人の健康な中高年を対象とした調査で、英国のアルコール1単位は(米国やカナダと異なり)8gですからまさにワイン1杯、もしくはビールコップ1杯程度です。
アルコールが引き起こすのはがん、心疾患、脳委縮などだけではありません。科学誌「Science News」2022年11月4日の記事「米国のアルコールによる死亡率は、パンデミックの最初の年に急激に上昇した(The U.S.’s alcohol-induced death rate rose sharply in the pandemic’s first year)」に、分かりやすいグラフが掲載されています。米国では過去20年にわたりアルコールによる死亡者が増加しており、2019年から2020年にかけては人口100,000人あたり10.4人から13.1人へと26%も上昇しています。増加した最大の原因は新型コロナウイルスですが、問題はウイルスそのものではなくストレス下で飲酒に走る人があまりにも多いことです。
アルコールが自殺者を増やすというデータもあります。医学誌「Journal of Addictive Diseases」2020年3月14日号に掲載された論文「アルコール使用と自殺のリスク:系統的レビューとメタ分析(Alcohol use and risk of suicide: a systematic review and Meta-analysis)」によると、アルコール摂取により自殺のリスクが全体で65%(男性56%、女性40%)上昇します。
死亡だけではありません。日本人を対象とした研究ではアルコール消費が白内障のリスクを上昇させます。
こうして新しい研究をたどってみると、どうやらアルコールは「百害あって一利なし」と考えるべきなのかもしれません。ただし、アルコールが健康に良いとする研究もないわけではありません。医学誌「Pain」2022年2月号に掲載された論文「片頭痛とアルコール、コーヒー、および喫煙の関係(Alcohol, coffee consumption, and smoking in relation to migraine: a bidirectional Mendelian randomization study)」によると、アルコール摂取で片頭痛のリスクが46%下がります。ただし、当院の経験でいえば、片頭痛の患者さんの何割かは飲酒で悪化しています。
もうひとつアルコールが健康にいいとする研究を紹介しましょう。日本人を対象とした研究で医学誌「BMC Geriatrics」2022年2月28日号に掲載された論文「飲酒で高齢者の認知機能が上昇する(Alcohol drinking patterns have a positive association with cognitive function among older people: a cross-sectional study)」です。この研究によれば、「ワインの機会飲酒をしている75歳以上の日本人は認知機能が向上」します。驚くべき結果です。
飲酒が健康に良いとするこのような研究もあるものの、WHOの発表やカナダのガイドラインなどを見る限り、アルコール摂取は従来考えられていたような「百薬の長」とはもはや呼べなさそうです。これからのアルコールとの付き合い方、見直した方がいいかもしれません。
投稿者 | 記事URL
2023年1月20日 金曜日
第233回(2023年1月) 「湿度」を調節すれば風邪が防げる
随所でお知らせしているように、太融寺町谷口医院は2023年6月30日をもって閉院せざるを得なくなりました。この「はやりの病気」は閉院後も継続する予定ですが、私の身の振り方によってはそれができなくなるかもしれません。よって、閉院までの間、大勢の方が関心を持つような内容にしたいと思います。
このコラムの第1回のタイトルは「インフルエンザ」で、公開したのは谷口医院がオープンする2年前の2005年2月3日です。この頃の私は、大学病院の総合診療科の外来を担当しながら、他の診療所や病院にも研修(修行)に出て、夜間は当時の自宅の1階を改造してつくった「日本一小さな診療所」を運営していました。
改めてその第1回の自分の文章を読んでいると、まあおおまかには現在と変わっていないのですが、現在の見解は下記のように変更しなければなりません。
・(2005年には)タミフルを絶賛している → タミフルは、健常者に対しては有症状期間を少し短くするだけであり、小児・高齢者などハイリスク者以外は使う必要がないことが分かっています
・(2005年には)リレンザ・イナビル・ゾフルーザの話がでてこない → 抗インフルエンザ薬のラインナップが増えています。また、現在は感染者に接してからの予防投与(これをPEPと呼びます)も推奨される場合があります
・(2005年には)手洗い・うがいを推奨している → これらは現在も変わりませんが、私としては現在は「谷口式鼻うがい」を推奨しています
・(2005年には)「換気」について触れられていない → 当時は換気についてさほど注目されていませんでしたが、現在は重要であることが分かっています
・(2005年には)「麻黄湯」(や葛根湯)の有用性について触れられていない → 当時の私はまだ有効性をそこまで確認できていませんでした。今は確信しています。
新型コロナウイルス(以下、単に「コロナ」)が猖獗を極めていたのは2020年の年明けから2021年の終わり頃までといっていいでしょう。当時はハイリスク者のみならず、40代、あるいは30代の健常者にも「死」のリスクがありました。現在は「死に至る病」とは言えなくなり、基礎疾患のない若者であれば特に恐れる必要がありません。
コロナのおかげ(という表現は変ですが)で、「風邪の予防」に対する世間の感心が高まりました。コロナが始まった2020年の前半はやたら「接触感染」という言葉が飛び交いました。このため、オフィス内や飲食店内では手洗いだけでなく手指消毒、さらに机、テーブル、ドアノブなどが繰り替えし消毒されるようになりました。そして一部の企業や飲食店では今も続けられています。
一方、接触感染を軽視する声もあります。「コロナの重要な感染ルートは飛沫感染と空気感染であり、触れる物には過敏になる必要がない」という意見です。しかし、これは極端な意見です。私の経験からいっても接触感染はコロナだけでなくインフルエンザでも少なくはありません。これは2005年の第1回のコラムには書きませんでした。当時の私はまだこのことに気付いていなかったからです。
ですが、今は確信しています。コロナ、インフルエンザを含むほとんどの風邪の病原体は接触感染します。とはいえ、一部の企業や店舗のように執拗に消毒処置をする必要はありませんし、手荒れするほどアルコール消毒をするのはナンセンスです。手洗いは「水道水」が基本であり、アルコールは「水道が近くにない場合」のみ、つまり補助的な使用に留めるべきです。
では過剰な消毒やアルコールの手指消毒をしないならどうやって接触感染を防げばいいのでしょう。それは「鼻を触らない」です。ただし、コロナが流行しだした頃にさかんに言われたように、「ちょっとでも顔を触るのはNG」はやり過ぎです。谷口医院の患者さんから話を聞いて分かるようになったのは「鼻をほじる」「鼻毛を抜く」などの行動をとる人がよく風邪を引くことです。よってこういった行動を慎めばそれだけで風邪をひくリスクは下げられるのです。
今回は新たな風邪の予防法についての話をしましょう。それは「湿度の調節」です。
昔からよくある疑問に「なぜ冬になると風邪をひくのか」というものがあります。「寒いから」と答える人が多いわけですが、ではなぜ寒さが発症因子になるのでしょうか。実はこれについては医学の教科書にきちんと書かれていません。そこで、私が「なぜ冬に風邪をひきやすいか」についてその理由を並べてみます。
#1 冬には日光を浴びる量が少なくなりビタミンDの生成が減少し、免疫能が低下する(可能性がある)
#2 冬は寒いために屋内にいる時間が長くなり、窓を閉め切るために換気が効率的におこなわれず、そのため他者からの飛沫感染、あるいは空気感染のリスクが上がる(これは間違いありません)
#3 空気が乾燥する(湿度が低下する)
#3の湿度について。最近の研究で、病原体増殖の至適湿度というものがあることが分かってきました。メリーランド大学の公衆衛生学者Donald Milton氏によると、風邪のウイルスとして有名なライノウイルスは高い湿度を好むそうで、そのため米国では初秋に流行するようです。一方、インフルエンザウイルスやコロナウイルスは冬に流行しやすく、湿度が40%を下回った環境を好むようです。これらは科学系メディア「ScienceNews」に掲載されています。
では、インフルエンザやコロナはなぜ乾燥した環境で感染しやすくなるのでしょうか。通常、ウイルスが人の呼気から放出されるとき、裸の状態で飛び出すわけではなく、唾液や鼻水などに包まれて体外に出ていきます。これら体液には、粘液や蛋白質などの成分が含まれていて、ウイルスを殺菌する効果もあります。湿度が高い状態であれば、体液が乾きにくく、時間をかけてウイルスを殺すことができます。体液は身体を離れてもウイルスをやっつけてくれているというわけです。その逆に、湿度が低ければウイルスを包んでいる体液がすぐに蒸発してしまい、殺菌効果が期待できずウイルスの感染力が維持されてしまうのです。この研究は査読前論文を集めたbioRxivという医学誌に掲載されています。
上述のScience Newsの記事には興味深い顕微鏡の写真が掲載されています。湿度が低ければ(40%)、体液が乾燥しウイルスがむき出しとなっています。インフルエンザやコロナはこの状態のときに感染しやすいと考えられます。湿度が中等度(65%)であればウイルスが体液に包まれておりウイルスを不活化させると予想されます。しかし、興味深いことに湿度が高すぎれば(85%)、ウイルスは死滅しにくいようです。
乾燥は「次に感染する人」の防御力にも影響を与えます。「乾燥した空気は気道の表面に存在する細胞死を引き起こす」ことを示した動物実験があります。気道粘膜の表面を守っている細胞が死んでしまえば、当然病原体は奥に侵入しやすくなりますから、「乾燥→気道粘膜の表面の細胞死滅→病原体が侵入し感染成立」となるのです。
以上をまとめると、環境を病原体が感染しにくい湿度にすべきであり、それは乾きすぎても湿気が多すぎてもダメで、50~65%程度が望ましいということになります。自宅、特に寝室は空気清浄器(できればHEPAフィルター付き)と共に加湿器や除湿器を置いて対処するのがいいでしょう。もちろんその前に用意しなければならないのは湿度計です。
では、自分の意図で調節できない職場やビルの中、あるいは地下街ではどうすればいいのでしょうか。マスクがお勧めです。マスクが感染予防に有効なことは明らかで、いくつもの信頼度の高い論文があります。マスクをしていても病原体が口腔内や鼻腔に入ってくるのは事実ですが、感染者が病原体を排出しにくくなります。コロナではなんと100%カットしてくれるという研究もあります。これだけでも(少なくともコロナには)マスクは「感染させない」という意味でかなり有用なわけですが、「感染しない」という意味でも非常にすぐれたツールです。気道の乾燥を防ぐことにより気道粘膜の表面のバリア機能を正常に保ってくれるからです。
最後にもう一度まとめてみましょう。インフルエンザ、コロナを含めて有効な風邪の予防対策は、「鼻うがい」「手洗い」「鼻を触らない」「換気」「湿度の調節」「マスク」「麻黄湯」です。ちなみに、私が最後に風邪をひいたのは2012年の12月。それから鼻うがいを始め、その後一度も風邪をひいていません。インフルエンザにもコロナにも無縁です。
投稿者 | 記事URL
2022年12月18日 日曜日
第232回(2022年12月) まもなく登場する市販のダイエット薬は効くのか
2022年11月28日、たまたまネットニュースに目が留まり、その内容に驚きました。日本では未承認の肥満薬「オリルスタット」が処方薬でなく、市販薬として認可されたというのです。オルリスタットは、膵臓や消化管から分泌されるリパーゼを阻害して脂質の吸収を抑制し、体重を減少させる薬です。
報道によると、販売を手掛けるのは大正製薬で、商品名は「アライ」。添付文書上の「効能・効果等」は「腹部が太めな方の内臓脂肪および腹囲の減少(生活習慣改善の取り組みを行っている場合に限る)」。「腹部が太めな方」の基準は、腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上、とのことです。
さて、このニュースを見て大勢の医療者が驚いたはずです。なぜならこのオリルスタットという抗肥満薬は、”歴史”のあるいわくつきの薬剤だからです。
オリルスタットは大正製薬が開発した薬ではありません。開発を手掛けたのはスイスの製薬会社ロシュです。1990年代には少なくとも米国FDAからは承認を得て、医薬品(処方箋の必要な薬)として「ゼニカル(Xenical)」という名前で米国の医師により処方されていました。
日本で導入の動きがあったのは2000年代前半で、製薬会社は中外製薬です。ロシュと協力関係にあった同社が日本での発売を目指して治験に取り組んだのです。ところが、2005年4月、中外製薬は開発のハードルの高さなどを理由に開発を中止することを発表しました。
ところでオリルスタットを語るときにはもうひとつの薬の話もせねばなりません。その薬とは「セチリスタット」。名前が似ていることからも分かるようにオリルスタットと似たような薬です。リパーゼを阻害して脂質の吸収を抑制し、体重を減少させるメカニズムです。
セチリスタットの開発を手掛けたのは英国のAlizyme Therapeutics社。2003年、武田薬品が日本における開発・販売の権利を取得しました。その後、2009年にオランダのノルジーン社がAlizyme Therapeutics社から製造・販売などすべての権利を獲得しました。
つまり、2003年の時点では中外製薬と武田薬品が類似した抗肥満薬の国内導入にしのぎを削っていたわけです。そして、2005年に中外製薬は撤退することを決定し、武田薬品だけが国内販売を目指して動いていたのです。
武田薬品の”努力”が実りました。2013年9月、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会により、武田薬品のセチリスタットは「オブリーン錠120mg」という名称でついに承認されたのです。
あとは「薬価収載」だけです。処方薬が実際に処方されるには、承認後の「薬価収載」を待たねばなりません。通常、承認から薬価収載までは「原則として60日以内、遅くとも90日以内」というルールがあります。よって、遅くとも2013年の年末には医療機関での処方が開始される予定でした。
ところが、セチリスタットはなかなか薬価収載されません。実は食品衛生審議会で承認された後、薬価収載について協議する中央社会保険医療協議会(通称「中医協」)からセチリスタットの販売を疑問視する声が上がったのです。
そして2018年7月13日、武田薬品はセチリスタットの販売を断念し、日本での開発・製造・販売権を導入元企業のノルジーン社に返却することを発表しました。武田薬品はそれまでにかなりの大金を費やしていたはずですが、薬価収載の見込みが立たないのならそれ以上引っ張ればさらにムダ金を使うことになります。また、興味深いことに、オリルスタットが世界の多くの国で処方・販売されているのに対し、セチリスタットに関してはそのような話をほとんど聞きません。もしかすると、現在もどこの国でも処方・販売されていないのかもしれません。
ここで時計の針を2000年代前半に戻します。中外製薬がオリルスタット120mgの国内導入を断念する前年の2004年、国外では新たな動きがありました。英国の製薬会社グラクソスミスクライン(の子会社)が、ロシュからオリルスタット120mgを半分の60mgとした製品の販売権を取得しました。そして、2007年、米国FDAは「ゼニカル(Xenical)」の半量のオリルスタット60mgを薬局で販売することを認可したのです。その商品名が「アライ(Alli)」です。
オリルスタットが再び日本で話題となりました。2009年1月、今度は(中外製薬ではなく)大正製薬が、グラクソスミスクライン(の子会社のグラクソグループリミテッド)と日本での開発・販売の契約を交わしたことを発表したのです。
随分ややこしくなってきましたので、ここでこれまでの流れをまとめておきましょう。
〇オリルスタット120mg: ロシュが開発。米国では「ゼニカル(Xenical)」という名前ですでに90年代から処方されていた。日本では中外製薬が販売を試みたが、ハードルの高さから2005年に断念した。
〇セチリスタット: 英国の製薬会社が開発し、その後オランダのノルジーン社が製造・販売権を獲得したが、海外での処方・販売実績はほとんどない(と思われる)。日本では武田薬品が治験をおこない厚労省からは承認されたものの、最終段階の「薬価収載」がおこなわれず、結局、販売権をノルジーン社に返却した。
〇オリルスタット60mg: グラクソスミスクライン(の子会社)が、ロシュから半量の60mgの製品の販売権を取得。2007年より米国で「アライ(Alli)」の名前で、薬局で販売され始めた。日本では大正製薬が2009年1月にグラクソスミスクライン(の子会社)と日本での開発・販売の契約を交わした。そして、市販薬として日本の薬局に近日登場予定。
このような複雑な”歴史”があり、大正製薬はグラクソ(の子会社)との契約から14年近く経過した2022年12月、ついにオリルスタット60mg(=「アライ」)の厚労省からの認可を得たのです。
さて、今後アライはどの程度普及するでしょうか。報道によれば、薬局での購入までの道のりが少々険しそうです。まず、ネット上で購入することはできず、必ず薬剤師との対面が必要となります。さらに、服薬開始の1か月前から腹囲と体重を記録する必要があるそうです。
これを面倒くさいと考える人はきっと少なくないでしょう。まあ、実際には適当に数字を書く人も大勢いるでしょうし、薬剤師もいちいちひとつひとつの数字をチェックしないでしょう。個人輸入や美容外科クリニックでやせ薬を買うことを考えればはるかに簡単に購入できます。
文献上の報告や、個人輸入で入手したことがあるという患者さんからの情報によれば、それなりの頻度で下痢をするそうです。それは脂肪の吸収が妨げられることを意味しますから、人によっては体重減少が期待できるかもしれません。
ですが、ダイエットの話で私が必ず言うように「その薬を一生続けるのですか」という問題が残ります。ダイエット薬は効果があったとしても、中止すればほとんどの人がリバウンドを起こします。また、極端な糖質制限や短期集中の運動も効果は出ますが、元の生活に戻せば元の木阿弥になるどころか、ダイエット終了後にはより太りやすい身体になります。
本サイトで繰り返し述べているように、ダイエットをしたいのなら、どのような方法であっても「生涯続けられること」をすべきなのです。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
- 第267回(2025年11月) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症
- 第266回(2025年10月) 難治性のSIBO、胃薬の見直しと運動で大部分が改善
- 第265回(2025年9月) 「砂糖依存症」の恐怖と真実
- 第264回(2025年8月) 「ブイタマークリーム」は夢の若返りクリームかもしれない
- 第263回(2025年7月) 甲状腺のがんは手術が不要な場合が多い
- 第262回(2025年6月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(後編)
- 第261回(2025年5月) アルツハイマー病への理解は完全に間違っていたのかもしれない(前編)
月別アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (119)