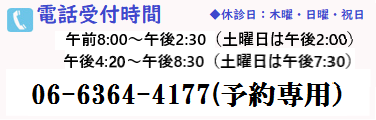メディカルエッセイ
2013年6月21日 金曜日
55 「ダイエットに報奨金」の意味するもの 2007/8/22
先日、イタリア北部のバラッロ・セシアという町で、ダイエットに成功した住民に報奨金が贈られる、という制度が導入されました。
この制度では、1ヶ月で、男性なら4キロ、女性であれば3キロの減量に成功すれば、50ユーロ(約8千円)の賞金がもらえます。さらに、5ヶ月後にその体重を維持していれば、100ユーロ(約1万6千円)の賞金が交付されます。
人口約7,400人のこの町では肥満が深刻化しており、町長自らがこの制度を提案したそうです。当初の予算は1万ユーロ(約160万円)です。
この地域では、すでに多くの住民が医師や薬局で「肥満証明書」を発行してもらい、「肥満」の登録をおこなっているようです。
イタリアでは人口のおよそ1割に相当する500万人が肥満と言われており、トゥルコ保健相は、この制度を「革新的で前向きな自治体の施策」とたたえ、「結果次第で国として導入できるかもしれない」とコメントしているそうです。
この制度が大変有益なのは、住民と行政の双方にメリットがあるからです。住民側からすれば、健康で美しい身体を手に入れることができる上にボーナスまでもらえます。ボーナスを励みにダイエットをおこなえば成功しやすいかもしれません。
一方、行政側からみれば、住民の肥満を減らせばそれだけ病気が減り、医療費の削減が期待できます。
「肥満は万病の元」と呼ばれるように、肥満はほとんどの生活習慣病の原因です。メタボリック・シンドロームの診断基準に肥満が含まれていますし、高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症などは、初期の段階で肥満の改善を図れば薬に頼らなくてもすみます。
こういった病気が進行すると、いずれ心筋梗塞や脳梗塞がおこることになります。突然心筋梗塞が起こった場合は急死することもありますし、命が助かったとしてもその後の人生はたくさんの薬を飲み続けることになり、また定期的な検査も必要になりますから、医療にかなりの時間とお金をとられます。
ときどき「好きなものを食べまくって心筋梗塞でそのまま逝ってしまえば苦痛も少なくて幸せ」と言う人がいますが、肥満の結果が心筋梗塞になるとは限りません。動脈硬化が進行し、脳梗塞を患った場合、若くして「寝たきり」となることもあります。こうなれば、その後の何十年の人生を「寝たきり」で過ごすことになります。
肥満を放置し糖尿病になった場合、その後の人生は大きく変わります。目が障害され視力を奪われ、足が腐り切断を余儀なくされ、腎臓が破壊され人工透析を強いられます。週に何度も透析を受けるために通院しなければなりませんから、病院が生活の中心になります。
このような「肥満の成れの果て」は、患者当事者からみれば、できるだけ、というよりなんとしても避けたいものですが、行政側からみても同じです。例に示した、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病からの人工透析などは、ひとりあたりの年間の医療費が数百万円になります。入院を繰り返せば1千万円を軽く越えるでしょう。
さて、報奨金目当てにダイエットをおこなう人で実際に成功するのはどれくらいの割合でしょうか。もちろん、誰もが成功するような課題であればこのような制度は誕生しませんから、「肥満」の登録をおこなった住民が全員報奨金を手にするということはないでしょう。ダイエットとはそんなに容易なものではないからです。
つまり、行政が報奨金を出してさえも成功しない人は少なくない・・・、これがダイエットの真実なのです。
すてらめいとクリニックに通院されている患者さんのなかにもダイエットに取り組んでいる人は少なくありません。なかには、1ヶ月で7キロの減量に成功した人もいれば、数ヶ月たってもまったく進展のない人もいます。
すてらめいとクリニックでは、効果的な減量ができるような薬剤(主に漢方薬)を患者さんの特性をみながら処方していますが、これは食事療法と運動療法の双方をしっかりとおこなってもらうのが前提です。食事と運動の重要性をないがしろにして「ヤセル薬」に頼ろうとしても結果は目に見えています。ダイエットに「王道」はない、というわけです。
薬剤に詳しい人なら、マジンドールやシブトラミンがあるじゃないか、と思われるかもしれません。これらはいずれも食欲抑制剤で肥満の治療に使われることのある薬剤です。マジンドールは日本でも極めて高度な肥満症の場合には保険適用があります。しかし、使用は長くても3ヶ月までと決められていますし、副作用の少ない薬剤ではありません。シブトラミンは日本では取り扱われていませんが、インターネットで海外から比較的簡単に入手できます。
こういった薬剤の危険性はこのウェブサイトでも何度か指摘してきましたが、実際、個人輸入の結果、死亡にいたったというケースは少なくありません。おおざっぱに言ってしまえば、食欲抑制剤というのは覚醒剤に近いようなものです。覚醒剤をキメれば食欲がなくなりますから若い女性が覚醒剤にハマる理由のひとつがダイエットです。(日本では以前は覚醒剤(ヒロポン)が合法でしたが、その効果・効能に「痩身」と書かれていたことを思い出しましょう)
先日、知人から興味深い体験談を聞きました。その知人の知人(主婦)がアルバイトをしたそうなのですが、その内容は「3ヶ月で10キロ太れば10万円」というものです。しかもアルバイト先の会社に行くのは初めの日と3ヵ月後の2回だけで、あとは家でテレビをみながら好きなものを食べるだけだそうです。
このいかがわしいアルバイトのカラクリは次のようなものです。太りだす前の写真と太ってからの写真を撮影します。そしてそれら2枚の写真は週刊誌のダイエット製品の広告に載せられます。
もちろん、ダイエット製品使用前が3ヵ月後の10キロ太った写真、使用後が太りだす前のやせているときの写真です。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
54 ある薬物中毒者との約束 2007/7/23
以前、私がある病院の救急外来をしていた頃の話です。
深夜に50代の男性が救急車で運ばれてきました。救急隊の話によれば、その男性は二階にある自分のアパートの窓から飛び降りて足を骨折している疑いがあるとのことでした。それを見た通りがかりの人が救急車を要請したそうです。
救急隊は「患者さんとコミュニケーションがとれなくて困っている」と言っていましたが、私はその患者さんの姿をみたときに、覚醒剤中毒者であることがすぐに分かりました。
両手が震えており、こちらの質問には一切答えず、なにやら呪文のようなものをぶつぶつと呟いています。目の診察をすると瞳孔が開いています。
覚醒剤が怖い理由のひとつは、キマったときに必ずしも”いい状態”になるわけではない、ということです。
女子高生らがおこなうことのある「スピード・パーティ」(覚醒剤は以前はシャブと呼ばれていましたが、最近は”スピード”、あるいはその頭文字をとって”エス”と呼ばれることが多いようです)では、みんながホンネで話せるようになりますし、試験前に徹夜をしたり、深夜のドライバーが眠気覚ましに使ったり、あるいはヤセル目的で使うときには、当事者にしてみれば”いい状態”になります。(もちろん、本質的には”いい”ことでは絶対にありません)
しかし、いつも”いい状態”になるわけではなく、”悪い状態(バッド・トリップ)”にはまってしまうこともあります。これは、本人の精神状態があまり良くない状態で覚醒剤がキマったときにおこりがちです。
こうなると、恐怖感や被害妄想が増幅され、ときには自傷行為にいたることもあります。救急車で運ばれてきたこの男性も、「FBIに追跡されているので逃げようとして窓から飛び降りた」と小さな声で話していました。
(医学の教科書には、「統合失調症になると、FBIに追跡されている、と言うことが多い」、と書かれています。たしかに、統合失調症の場合も患者さんはそのように言うことがあるのですが、私の経験で言えば、統合失調症の場合に比べて、覚醒剤中毒者の発言の方が話に整合性があるように思えます)
覚醒剤がキマっていることを確信して尿検査を実施したところ、案の定、メタンフェタミンに陽性反応がでました。レントゲンで骨折はありませんでしたが、この状態で家に帰すわけにはいきません。入院の手続きをおこない、点滴を開始しました。
翌日のことです。その患者さんに覚醒剤の話をしたところ、その患者さんは「お願いだから警察には言わないでほしい」、と私に嘆願してきました。
詳しく話を聞いてみると、その患者さんは、「以前は覚醒剤にどっぷりとつかっていたけれども、ここ数年は手を出していなかった。最近、会社をクビになって自暴自棄になってついつい手をだしてしまった。もう二度と手を出さないから警察には言わないでほしい」と言います。
医師をしていると、覚醒剤中毒者に会う機会は少なくありません。深夜に眠れないと言って救急病院に飛び込んでくる患者さんのなかで覚醒剤中毒者は珍しくありませんし、独特の振る舞いを観察すれば比較的簡単に診断がつきます。
そして、覚醒剤中毒者が”嘘つき”なのは世間の常識です。覚醒剤を買うために家族や知人から金を借りるときにはありとあらゆる嘘をつきますし、いったん依存症になった人が「もう覚醒剤はやめた」という発言は、結果としてそのほとんどが嘘です。
ですから、この患者さんがいくら真剣な顔をして一生懸命に訴えたとしても”二度と手を出さない”という言葉は簡単には信用できません。
しかしながら、この患者さんが覚醒剤を使用していたことを警察には通報すべきなのでしょうか・・・。
医師には守秘義務があります。これは個人情報保護などのレベルの話ではなく、医師には刑法上の守秘義務があるのです。「診療上知りえた情報は決して他言してはいけない」という厳しいルールです。もしも違反をすれば、個人情報保護法ではなく、刑法で裁かれることになります。
しかし、その一方で、公益性を優先するという考えがあってもいいと思われます。この患者さんの覚醒剤使用を警察に通報することにより、治安が維持でき不利益を被る人を未然に防ぐ、という考え方です。実際、もしも、この患者さんが覚醒剤の個人使用だけでなく販売もおこなっていたとすれば、私は躊躇せずに警察に通報したでしょう。
しかし、この患者さんは密造や密売をしているようには思えませんでしたし、”もうやらない”という言葉は結果的には嘘になるとしても、「数年ぶりに手をだした」というのは本当かもしれません。
悩んだ私は、ある法医学の先生を訪ねることにしました。その先生のコメントは次のようなものです。
「例えば、その患者さんが数年前に覚醒剤に手をだしていたけれど現在は完全に断ち切っているような場合は守秘義務を守るべきだろう。しかし、今現在も使用している場合は通報しても守秘義務違反を問われるようなことにはならない。たしかに法学者の間でも意見の分かれる問題ではあるが・・・」
結局、私はその患者さんの「もうやらない」という言葉を信じることにしました。結果として「もうやらない」という言葉が嘘になる、つまり約束を破ることになる可能性が強いのですが、そのときはその言葉を信じることにしたのです。
これは、今になってふりかえってみても「守秘義務を守るべきだと思った」というようなものではなく、なんとかその患者さんに立ち直ってほしかったという気持ちが強かったからだと思います。
その患者さんは、覚醒剤のために、仕事をなくし、家族をなくし、新しい仕事もなくしています。友人にも見放され、信用してくれる人は皆無です。
入院中、娘に会いたいとの希望を話されたために、私は娘さんに連絡をとり一度だけ病院に来てもらったのですが、その娘さんには父親との仲を修復する意思はありませんでした。
「あの人は父親ではありませんからもう二度と連絡をしないでください・・・」
その娘さんは私にそう言って帰っていきました。娘さんが帰った後、その患者さんが私に言いました。
「(覚醒剤は)もうやらない・・・」
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
53 「気付いたモン負け」というルール 2007/6/25
私が医学部に入学したのは27歳のときですが、それまでは在阪の商社で四年間サラリーマンをしていました。この会社は、大企業とは呼びがたく、また世間での知名度はそれほど高くないのですが、今思い出してみても本当にいい会社だったと思います。
実際、私はサラリーマン時代を通して、実に様々なことを学びました。私が多少なりとも習得できたことは、ビジネス英語、貿易事務、翻訳・通訳業務、ビジネスレターの書き方、英文タイプ(おかげで私はパソコンは苦手ですがブラインドタッチはできます)、会議資料の作り方、プレゼンテーションの仕方、様々なマーケティング手法、・・・、などが挙げられます。
しかしながら、私がこの会社で四年の月日を過ごし最も収穫となったのは、同僚や先輩から学んだことがらです。大勢の魅力的な人たちと一緒に仕事ができたことは自分の財産であり、今の自分があるのはあの頃の経験があったからだと自負しています。現在の私の最大の楽しみのひとつは、ときおり開かれる(元)社員の飲み会です。
さて、今日は、私がサラリーマン時代に学んだことのなかでもとりわけその後の自分自身に影響を与えてきたひとつのルールをご紹介したいと思います。
そのルールを、「気付いたモン(者)負け」のルールと呼びます。
今の世の中では、社員どうしで飲みに行って仕事の話をする、というのはあまり格好のいいことではないのかもしれませんし、社員どうしで飲みに行くこと自体が流行らないのかもしれませんが、私がその会社にいた頃は、よく社員どうしで飲み会を開き、仕事の話で盛り上がりました。
もちろん、初めから終わりまで仕事の話をするわけではありませんが、みんなが仕事にやりがいを感じ、楽しんで仕事をしていましたから、自然に話題は仕事に向かうのです。よく、社員どうしで飲みに行くと上司や会社の悪口に始終する、という人がいますが、当時の私たちの話題の大半は、「今すすめているプロジェクトをもっと拡大すべきだ」、とか、「今の○○部の問題点はここにあるからこう改善すべきだ」といった夢のある(と言えばおおげさでしょうか・・・)話になります。
その会社の飲み会が大変おもしろかった理由のひとつは、いろんな部署の人たちが集まってきていたことです。昼間の勤務時間には、他部署の人とはなかなかホンネで話せませんから、飲み会の場で初めて、「ああ、△△部の人たちは、あの問題にはそのような考えを持っていたのか・・・」、などということが分かるのです。
例えば、ある人が「現在の◇◇という商品は大変すぐれたモノでかつ価格も安い。関東では売れているのに関西では売り上げが芳しくない。だからやりようによってはもっともっと売れるはずだ」、というようなことを言ったとします。それに対して、その場にいる人たちが賛同したとします。
「それではその企画について実現していこう」というコンセンサスが得られたとき、「じゃあ、誰がリーダーとなるんだ」という話題へと移ります。このときリーダーとなるのは、必ず「その問題を提起した人」です。そして、これを「気付いたモン(者)負けのルール」と呼びます。
たとえその問題を提起した人が新入社員であってもルールは守られます。新入社員であろうが課長であろうが、言い出した本人がリーダーとなるのです。もちろん、リーダーだけが仕事をするのではなく、その場にいてその案に賛同した人たちはフォローワーとなります。
というわけで、私が働いていたその会社では、非公式のプロジェクトチームが次々と誕生していました。こういったプロジェクトは売り上げに直接寄与するものだけではありません。例えば、業務システムの改善とか、新しいファイリングシステムの構築、といったプロジェクトも数多くありました。
「気付いたモン負け」の”負け”というのは、もしかすると関西特有の表現なのかもしれません(少なくとも英語に直訳すれば意味不明になります・・・)。
給料がアップするわけでもないのに、自分が言い出したがために仕事の量が増えます。当初は考えてもみなかった困難が次々に現れ予想外の苦労を強いられることもよくあります。それに、プロジェクトはいつも成功するとは限りません。狭い意味での「損得」という概念で考えると、気付いたモンが「損=負け」となることもあります。
もちろん、プロジェクトが成功すれば純粋に嬉しいですし、その後の飲み会はさらに楽しくなります。では、成功したときの喜びだけを考えて我々がそのプロジェクトに取り組んでいたのかと言えばそういうわけでもありません。
「気付いたモン負け」という言葉の本質は、「損得でなく問題を見つけたならば取り組まなければならない。それが社会でスジを通すということだ」ということなのです。
何をするにも自分にとって損か得か、と考える人もいるようですが、世の中とはそういうものではないのです。「なぜ(得にもならない)そんなことをするのか」と尋ねられれば、「問題に気付いたからする!」で、この答えでじゅうぶんなのです。
これを身をもって学んだことが、私がサラリーマン生活を通して得た収穫のひとつです。
さて、その後の私の人生は、特に転機となる場面では、この「気付いたモン負け」というルールをよく適用しています。
医学部の大学院に進学し研究の道に進むと決めたこと(結局、臨床医となりましたが・・・)、患者さんは必ずしも医療機関を信頼しているわけではないことを知りそんな患者さんの力になることを決意したこと、エイズで困窮している人たちと知り合いNPO法人GINAを立ち上げたこと、都心で苦しんでいる人たちが気軽にアクセスできるクリニックがないことを知りならば自分がつくろうと決心したこと、・・・、これらのモチベーションは、すべて私が問題点に”気付いた”ことによるものです。
不器用な生き方かもしれませんし、要領が悪いかもしれません。損得勘定だけで行動をとっている人からは理解されないでしょう。
それでも私は、今後もこの「気付いたモン負け」のルールを守っていくことになるでしょう。
それは、このルールが社会の真実であることに”気付いた”からです・・・。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
52 目標は患者数ゼロ?! 2007/5/22
以前、尊敬するある医師から質問されました。
「医師の究極の目標は何か分かるか?」
何と答えていいか分からず黙った私にその先輩医師は言いました。
「それは、患者数をゼロにすることや」
患者数ゼロ・・・、これでは病院の経営が成り立たなくなりますし、医師は失業してしまいます。
その先輩医師は患者数ゼロが目標であるその理由を話してくれました。先輩医師の話をまとめると次のようになります。
現在、日本の病院には、本当は病院に来なくてもいいと思われる患者さんが少なくない。過剰に心配しすぎて些細なことで何度も医師にかかろうとする人もいれば、まるで待合室をサロンのように考えて近所の人たちとの話を目的に通院しているような人すらいる。このような人たちに通院は不要であることを分かってもらうことも医師の仕事のひとつである。
たしかに、この先輩医師の言うことは正論です。実際、ごく軽度の頭痛でMRIを撮ってほしいと言って病院を受診する患者さんや、「胸のレントゲンを撮りましょうか」と言うと、「レントゲンではなくCTを撮ってください」と言う人もいます。「もう注射や点滴は必要ないですよ」と言っても、「点滴をうたないと元気がでないんです」と言って毎日のように点滴を希望する人もいます。
もちろんすべての事例にあてはまるわけではありませんが、医師からみて「それは過剰な検査や投薬だろう・・・」と思うことでも、ときに患者さんは求めてきます。
そんなとき、ほとんどの医師は、なぜ今その検査や投薬が必要でないかを患者さんに理解してもらおうと努めます。つまり、医師というのは、できるだけ過剰な検査や投薬を避けようと考えているのです。
しかしながら、このことは世間一般ではあまり理解されていないようです。
例えば、ある大手新聞の5月11日の夕刊に掲載された医療関係の記事には次のような表現があります。
「医療機関は検査や投薬をすればするほど収入は増えるため、必要のない診療行為をする例も目立つ」
果たしてこのようなことを考えている医師は本当に存在するのでしょうか。言うまでもなく、医師は患者さんのために存在するのであって、常に患者さんにとって最善の方法を考えながら治療をおこなっています。検査や投薬は患者さんの利益になるからこそおこなうのであって、それは医療機関のためのものではありません。
しかし、先に述べた大手新聞の記事にみてとれるように、この点はあまり理解されていないのかもしれません。
昨今、病院を株式会社にしようとする議論が浮上していますが、私を含めてほとんどの医師が反対する理由はここにあります。医療機関は患者さんのためのものであって、株主のものとなるようなことは絶対に避けなければなりません。アメリカでは医療機関にも市場原理を取り入れて株式会社化している病院が増えているようですが、株式化して治療成績や患者満足度が低下している施設が少なくないと聞きます。
もしも病院が株主のものであれば、不必要な事例に対してまで高額な検査や投薬がおこなわれることになりかねません。そんなことは絶対にあってはならないのです。
さて、冒頭で紹介した先輩医師は、患者ゼロを目標にすべき理由としてもうひとつの例を話してくれました。まとめると次のようになります。
予防をしていないことが原因で病院に来ざるを得ないような患者さんも少なくない。糖尿病や高脂血症といった生活習慣病がその典型で、日頃から食事や運動に取り組んでいれば病気になることを防げたと思われる人があまりにも多く、そのような人たちに対しては健康なときから予防の大切さを理解してもらうのも医師の仕事である。
これもまさに正論であり異論はありません。私は常日頃から患者さんに、「最低でも年に一度は健康診断を受けるようにしてください」と言っています。特に生活習慣病は早期発見が大切だからです。
生活習慣病の他にも早期発見・早期治療が大切な病気はいくらでもあります。
もう少し早く来てくれたらごく軽い薬だけで済んだのに結果として強い薬を使わざるを得なくなった事例や、点滴に通ってもらわなければならなくなってしまったケースもあります。
心の病でも同じです。早めに来てくれれば対処方法があったかもしれないのに、症状が進行し、仕事を辞めてから初めて受診する人や、なかには自殺未遂の後にようやく受診された人もいます。
一方では些細なことを過剰に心配する人がいて、その一方ではなかなか医療機関にかからずに症状が進行するまで放っておく人もいるのが現実なのです。
都心に住む人たちのなかには(地方でも同じかもしれませんが)、健康診断を何年も受けていない、という人が少なくありません。大きな企業に勤めていなければ健康診断の機会がないのかもしれませんが、健康診断くらいならたいていのクリニックで実施できます。
また、健康診断の機会を待たなくとも、気になる症状があれば気軽にクリニックで相談すればいいのです。過剰に心配して不必要な通院を繰り返す前に、その症状に対する適切な検査と(必要なら)治療をおこなえば、無駄な時間と無駄なお金を費やさずにすみます。
「患者数ゼロ」という究極の理想には届かなくても、私自身は当面の目標を「患者さんの通院を最小限に」としています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
51 ある同級生に感謝していること 2007/4/25
以前別のところにも書きましたが、私が医師になってまだ2ヶ月しかたっていない2002年の7月、大学病院の近くの路上で交通事故に会いました。
結局、その後27日間の入院生活を強いられることになったのですが、この入院生活は今思い出してもかなりの苦悩が伴うものでした。
激痛ではないものの鈍い痛みが首と右腕を常に支配し、どのように表現していいか分からない不快な頭重感、それに右腕のしびれや脱力感と共存しなければなりませんでした。右手にはほとんど力が入らずに、ペンや箸はなんとか持てるものの、少し重いドアを開けることすらままならない状態でした。
しかし、私を最も苦しめたのはそういった身体的な苦痛よりもむしろ精神的な閉塞感でした。なにしろ、医師になってまだ2ヶ月しかたっていない時の入院生活です。早く仕事を覚えなければならない時期なのにもかかわらず安静を強いられるのです。
医師の仕事を続けることはもうできないかもしれない・・・、そんな考えさえいつしか頭を支配するようになりました。特に辛いのが夜です。ほとんどの患者さんがそうであるように、私の痛みも日中よりも夜間に増強されます。少しでも痛みが軽減される姿勢を探すのに一晩中かかって、結局ほとんど眠れないという日もありました。強力な睡眠薬を使っても、不安感が薬の効能を打ち消します。
入院生活を通して何人かの友人・知人が見舞いに来てくれたことは心の支えになりましたが、単に挨拶に来ただけ、と明らかな社交辞令風の人もいて、そういうときはかえって精神状態が悪くなります。
一方で、私の立場に立って話を聞いてくれるような人たちもいて入院生活の励みになりました。今回は、そんな心優しい人たちのなかでも私が最も印象に残っているひとりの女性について思い出してみたいと思います。
その女性は私の医学部の同級生です。私が医学部に入学したのは4年間のサラリーマン生活を終えた後の27歳のときですが、その女性は現役で入学していますから私とは9歳年が離れていることになります。
当時は医学部を卒業した後は卒業生の大半が大学病院で研修を受けていました。私もその同級生も大学を卒業し、そのまま大学病院で研修医生活を送っていました。
入院してちょうど1週間が過ぎようとしていたある夜にその同級生は私のベッドサイドにやってきました。それまでも他の同級生たちが何人かは見舞いに来てくれていましたが、仕事が忙しいこともあって、たいていは挨拶程度の話しかせずに数分で去っていきました。同じフロアで働く同級生さえも、それほど長い時間滞在せずに仕事に戻っていました。
1年目の研修医は寝る時間もないほどに忙しいものですから、短時間でもベッドサイドに来てくれることに感謝しなければならないのは分かるのですが、やはりひとりの患者としてみると少し寂しい気もします。
そんななか、その同級生はある晩突然やって来て、1時間以上も私のそばにいてくれたのです。私はその女性とは学生の頃から仲がよかったとは思いますが、例えばふたりで食事にいくような関係ではありません。おそらくふたりでじっくり話をしたことなどそれまではなかったと思います。
けれども、そのときその同級生は、どこからか椅子をもってきてベッドに横たわっている私の横に座り、ゆっくりと私の話を聞いてくれたのです。
私はどちらかと言うと、自分が話すよりも相手の話を聞くことの方が多いのですが、そのときは、彼女の話を聞くのではなく、一方的に私が話しをしていることに会話の途中で気づいたのを今でも覚えています。
しかも、私の話していたことは他愛もないことばかりで、彼女にとって興味深い話はほとんどなかったと思います。それでも彼女は、ときには相槌を打ち、ときには笑顔を浮かべ、ときには私の気持ちが分かると言い、私の話に付き合ってくれたのです。
気がつくと1時間以上も経過していました。私は、彼女が仕事を途中で中断して見舞いに来てくれていることを思い出しました。おそらく、彼女はこれからカルテの整理やレポートの作成などで少なくとも数時間は病院に残らなければならないはずです。私は、大変申し訳ない気持ちに駆られましたが、あえて謝りの言葉は述べず、代わりにお礼を言って彼女の背中を見送りました。
彼女が去ってからも、心の重荷がすーっとおりて身体が軽くなったような感じが続いていました。前日まで強力な睡眠薬を倍量飲んでも寝られなかったのが、その日は担当の看護師が睡眠薬を持ってくる前に深い眠りに落ちていました。
薬よりも手術よりも優れた治療法・・・、とまでは言えないでしょうが、「患者のそばでじっくりと患者の話を聞く」というのは、患者さんの精神状態を安定させるだけでなく、身体的苦痛を取り除くことさえあるということが、ひとりの同級生のおかげで分かりました。
実際の臨床の現場では、ひとりの患者さんに時間を取り過ぎることが許されないケースが多々あります。他の患者さんを待たせることになりますし、病院やクリニックの経営的な観点からは非効率だからです。
しかしながら、ときに医師が患者に共感すること(これを「ラポール」と言います)が既存のどんな治療法よりも優れていることがあるということは、医療者はもっと注目すべきではないかと私は考えています。
これを書いている今、あのとき見舞いに来てくれたあの同級生とはもう5年近くも会っていないことに気付きました。彼女がいま、どこの病院で働いているのかを私は知りませんが、きっと患者さんから大きな信頼を寄せられる医師になっているに違いありません。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
50 「医療クライシス」を打開する方法 2007/3/20
2月24日の毎日新聞に、「医療クライシス」というタイトルで、医療関係者の声が特集されています。少し紹介しますと、
「(医師の仕事は)どれだけ過酷な勤務か知っていますか。(中略)医者を選んだのは人生の失敗でした」(40代開業医)
「結果責任を問われ、心身をすり減らして治療しても、感謝されるどころか疑いの眼を向けられることも多くなっている」(30代勤務医)
「医療に携わるなら、ある程度はボランティアのような覚悟で望まなければならないのは分かっていたが、過労死認定基準を大幅に超えていることには驚いた」(医学部を目指す女子高生)
・・・・・・
このような意見が多数集められているのですが、これらをまとめると、「医師の勤務時間は極めて長い割には報酬もそれほど多くなく、責任が非常に重く、一生懸命やってもそれほど感謝をされない」、ということになります。
もちろん、すべての医師がそのように感じているわけではありませんが、最近はこのように否定的な思いを持つ医療従事者が増えてきているのは事実です。
しかし、これらは突然そうなったわけではなく、以前から事情はそれほど大きく変わるわけではありません。細かいことを言えば、新研修医制度の導入で大学に残る若い医師が減少し、そのため大学傘下の病院から医師を引き上げざるを得ず医師の数が減る病院がある、とか、最近の医療訴訟の増加で医師をやめていく者が増えてきている、とかいったことはありますが、勤務時間が長い、報酬は多いわけではない(ただし少なくはありません)、責任が重い、感謝されないことも多い、などというのは今に始まったわけではありません。
「今に始まったわけではない」と言っても、私自身も医師として、こういった現状に満足しているわけではありません。満足しているわけではありませんから、自分の意見を本にも書いたわけです。
その意見をここで改めてご紹介すると、
医師の数を倍にせよ!
というものです。医師の数を倍にすれば、単純計算すればひとりあたりの患者さんの数が半減しますから、勤務時間が長い、という問題は解消されるでしょう。
しかし、医師の数が倍になれば、医療費が増額されない限りは、報酬は半減します。医療費を増額せよ、という意見もあります。OECD(経済協力開発機構)の2003年のデータによりますと、GDPに対する医療費の占める割合は、OECD平均が8.6%なのに対し、日本は7.9%です。G7だけでみると10%を超えていますから「先進国」のなかでみれば日本は医療にお金をかけていない国ということになります。(ちなみに、30ヶ国中1位は米国の15.0%、最下位は韓国の5.6%です)
したがって、この各国のGDPに占める医療費の割合の国際比較を持ち出して、医療費を上げるべきだ、という主張をときどき聞くことがあります。これはまったく正しい主張だと私は思いますが、残念ながら、日本政府は「はいそうですね。じゃあ来年から予算を上げますね」とは言ってくれません。
ということは、言い続けることは重要だとしても、当面の間は医療費の増額というのは期待できないわけです。もしも、医師の数が倍になり医療費が増額されないとすると報酬は半分になります。報酬が半減と聞くと、たしかにぞっとしますが、勤務時間も大幅に減少しての報酬半減です。
医師の仕事を一生懸命すればするほどプライベートな時間は犠牲となります。家族と過ごす時間が充分であると考えている医師などまず皆無ですし、時間がとれないことが時に家族関係を悪化させることもあります。
例えば、私の知り合いのある男性医師は、夜中に頻繁に病院から呼び出されるのですが、急変した患者さんがいれば駆けつけるのが当然という考えを持っています。しかし、この男性医師の奥さんはこの行動が理解できません。奥さんの言い分はこうです。
「本来の勤務時間以外の時間に出勤するなら時間外手当をもらうべき。そもそも医師という仕事は残業代がないのもおかしい。休みは月に一度あればいい方だし、これはあきらかな労働基準法違反だ」
この奥さんの言っていることも理解できます。「残業代」とか「休日出勤手当て」などというのは医師の世界ではほぼ皆無ですし、土日には学会・研究会などで出張費や宿泊費も自己負担で全国にでかけますから、医師の世界を特殊な世界と感じるのも無理はないでしょう。
もしも、医師の数が倍増して、夜間にも複数の医師が待機できるような状況を整えればこの奥さんの悩みは解決するかもしれません。たとえ収入が半減したとしても家族の時間は確保できるというわけです。
医師数が足らないのは勤務医だけではありません。開業医だって同じです。例えば、私は1月から一応開業医ということになりましたが、これまで勤務していた複数の病院では引き継いでくれる医師がいないため今も勤務を続けています。夜間の当直勤務も月に3~4回はおこなっています。夜間は勉強や学会発表のための準備などに時間をとられ睡眠時間を削らざるをえませんから、プライベートな時間などほぼ皆無です。
もうひとつ例をあげましょう。開業医には70歳を超えても仕事を続けている人が少なくありません。なかには80歳を超えても現役でがんばっている医師もいます。こういう医師たちはお金のために働いているのではもちろんありません。むしろ、これまでに蓄えたお金と年金で老後をのんびりと過ごしたいと考えている人たちも少なくないと思います。にもかかわらず、仕事を続けなければならないのは、仕事をやめると患者さんの行き場がなくなるからです。「私は今月かぎりで医師をやめますから、次からは別の病院に行ってください」とはなかなか言えるものではないのです。診療所を引き継いでくれる医師を探しているが見つからなくて困っている、と言っている年輩の開業医も少なくありません。
「医療費を増額せよ」に比べると、「医師の数を増やせ」という議論はそれほど活発にはおこなわれていないように感じますが、現場で働く多くの医師は、「収入が減っても勤務時間を減らしたい」と考えているのです。(少なくとも私はそう感じています)
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
49 全人医療への道のり 2007/2/19
最近出席したプライマリケア関連の研究会で、ある大学の教授が、その大学での医学部生の教育について講演されていました。
その大学では非常にすぐれた教育システムをとっているようで、その講演を拝聴してまず感じたのは”羨望”でしたが、私の心のなかでもうひとつの気持ちが湧き上がってきました。その気持ちとは”なつかしさ”です。
その大学の教育システムでは、1年生のうちに「アーリー・イクスポージャー(
early exposure)」と呼ばれる、いわゆる「早期研修」があります。私の出身の大阪市立大学にもこの研修制度があり、私は講演を聞きながら、もう10年以上も前の自分がその研修を受けたことをなつかしく思い出したのです。
医学生といっても1年生のうちは医学の知識などほぼ皆無で、医療に対する感覚としては一般の患者さんとなんら違いはありません。早期研修では、医学生が何の知識も技術もない、いわばまだ”白紙”の状態であるうちに病院実習をおこないます。
この実習では、医学部1年生は医師の仕事を見学するのではなく、看護師について実際の看護業務を手伝います。手伝うといっても、シーツ交換すらろくにできない医学生は、実際には足手まといになっているだけなのですが・・・。
私は医学部入学当初は医師(臨床医)を目指していたわけではなく、将来は医学の研究をおこないたいと考えていました。そのため、この早期実習には初めから乗り気でなく、実習が必修だったため仕方なく参加したというのが正直なところです。しかし、2日間の実習を通して次第に臨床の現場に興味をもつようになりました。(もっとも、この実習を終えた後も自分は研究者になるんだという決意は変わらず、臨床医を目指しだすのは医学部の3年生の頃です)
私が早期研修を受けた大阪市内のその病院では、すべてのスタッフの患者さんへの対応が本当に素晴らしいものでした。医学部に入学した頃の私は、臨床に興味があったわけではありませんし、臨床に対してなんとなくイメージしていたのは、マスコミの報道などによる医療ミスとか脱税とか、そういった否定的なものでしたから、予想と現実の大きなギャップに驚いたのです。(マスコミの医師や病院に対する報道は否定的なものが圧倒的に多いのです・・・)
患者さんの立場にたって業務をおこなっているスタッフというのは医師や看護師だけではありません。事務や受付の人々まで、まさにスタッフが一丸となって患者さんのケアに取り組んでいるといった感じでした。
2日間私につきっきりで指導してくれた看護師が私に話してくれた言葉は今でも覚えています。その病棟は整形外科病棟で様々な年齢層の患者さんが入院されていました。その看護師は患者さんに応じて、ときには厳しく、ときには患者さんの手をとり、10代の男性に対しては姉のように、70代の女性に対してはまるで孫のように接していました。そして私に言いました。
「あたしたちは患者さんの病気や怪我をみてるだけじゃないの・・・。患者さんが安心して入院生活を送れるようにいろんな手助けをしているのよ・・・」
この言葉が単なる美辞麗句ではなく、行動の伴ったものであることはすぐに理解できましたが、私には、なぜスタッフ全員が患者さんの立場に立ったケアが徹底しておこなえているのかが不思議でした。その頃の私はそれなりにいくつかの社会を経験していましたから、人間が善人だけでないということも知っていたからです。
2日間の研修の最後におこなわれた反省会でその謎が解けました。
反省会はその病院の会議室でおこなわれ、研修をおこなったわれわれ医学部1年生や医学部の教師のほか、その病院の看護師長も参加されました。その会議室の壁にかけられていた額には「全人医療」という言葉がありました。そして、われわれは、その看護師長から「全人医療」についての話を聞きました。
「全人医療」とは、患者さんの臓器、例えば肝臓の悪い人なら肝臓だけを、目の悪い人なら目だけをみるのではなく、その人の心理的あるいは社会的苦悩にも配慮し、患者さんの人格を尊重した医療である、というようなことをその師長は話されていました。
先にも述べたように私はこの時点では臨床医を目指していたわけではなく、そのときは、スタッフの患者さんへの態度に感銘を受けたのは事実ですが、将来的には自分にはそれほど関係のないことだろうと感じました。しかし、その言葉が心のどこかにずっと残っていたのは間違いありません。(現にこうして今でも覚えているのですから・・・)
私はこれまでに、研修やアルバイトも含めれば20以上の病院や診療所で診療をおこなってきましたが、看護師を含めたスタッフの対応というのは病院によって様々です。なかには、これで患者さんの立場に立った医療がおこなえているのか・・・、と思わずにはいられないような、自分が患者なら受診したくない病院というのもあります。
しかし、その一方で、どうしてこんなにも素晴らしいスタッフばかりがそろっているんだ・・・、と感じるような病院もあります。先にのべた私が早期研修を受けた病院もそうですし、私が研修医の頃にお世話になった病院もそうでした。その病院で主任をされていたある看護師はこのように話していました。
「この病院では全職員は採用になったときから、いえ、看護師の場合は、(その病院附属の)看護学校に入学したときから、徹底して”患者さんの立場にたった医療”の教育を受けるの。だから、多くの患者さんや、そして先生たちも、この病院に来て驚くのよ。だけど、あたしたちにとっては当たり前のことなの・・・」
「全人医療」という言葉にこだわる必要はありませんが、いつの頃からか私は患者さんの臓器だけをみるのではなく、その患者さんの社会背景や心理状態にも配慮できるような医師になりたいと思うようになっていました。最終的には、大学の「総合診療科」に所属し、今も総合診療(=家庭医療=プライマリケア)を実践しているのは、そういう思いもあるからです。
しかし、私自身が実際に「全人医療」ができているかと問われれば、自信をもってできているとは到底言えません。たしかに、すてらめいとクリニックでも患者さんのなかには複数の訴えを話される人がいますが、それは単に臓器の数を足しただけであって、「全人医療」からは程遠いもののように思えます。
「個人の単なる集合」と「組織」は異なるように、あるいは「部分の総和」が「全体」ではないように、単に複数の訴えを聞いて治療をおこなったからといって、それが「全人医療」になるわけではありません。
私の「全人医療への道のり」はまだまだ続きそうです・・・
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
48 あなたはAEDが使えますか 2007/1/20
それは私が医師1年目、ある病院の救急部で研修を受けていた頃の話・・・。
深夜1時ごろ、救急隊から連絡が入りました。「20歳の女性が突然心肺停止となり、現在救急車内で人工呼吸と心臓マッサージをおこなっている。5分以内に到着するから救命してほしい」、との要請です。
救急部に緊張が走りました。心肺停止での救急搬送は珍しくありませんが、20歳となると話は別です。末期の病気でいつ心臓が止まるかも分からないと医師に言われている高齢者の心肺停止であれば、本人も家族もある程度は”死”というものを受け入れていることが多いのですが、20歳の場合はなんとしても助けなければなりません。
しかし、30分以上に及ぶ救命処置の効果もなく、その女性は享年20歳で生命を終えることになりました。
後にいくつかのことが分かりました。ひとつは、この亡くなった女性は以前心電図の異常を指摘されたことがあるということ、さらにこの女性は看護学生で寮に入っており、通報したのは同じ寮に住む看護学生であるということも分かりました。
そして、もうひとつ分かったことがあります。通報した看護学生は、亡くなった女性が突然意識を無くした現場にいたのにもかかわらず、その場で何もできず、通報したのは女性が倒れてからおよそ10分が経過していたということです。
意識をなくして倒れた同僚に何もできず、通報するのも遅れたということからこの看護学生は大変なショックを受け、救急隊に対してまともに話をすることができなかったそうです。
************
突然の心肺停止が目の前で起こったとき、あなたは何ができますか。もちろん、すぐに救急車を呼ぶことが最も大切です。しかし、それ以外にもできることはあります。一般の人にもできる、あるいはおこなう義務のある救命処置です。
この一般の人にもできる(しなければならない)救命処置のことをBLS(一次救命処置)と呼びます。医療従事者はもちろんトレーニングを受けていますが、現在では、医療者以外にも、客室乗務員やスポーツジムのインストラクター、コンサートホールや競技場の警備員といった人たちも訓練を受けています。また、最近では自動車の教習所でも学ぶようになってきています。
なぜ、BLSは一般の人もできるようになっておかなければならないのか・・・。それは、心肺停止が起こったときの措置は一刻を争うからです。呼吸が止まった状態が4分間続けば、脳に回復しないダメージを与えることが分かっています。心肺停止の人を発見してから救急車が到着するまでに4分以上はかかるでしょうから、その間はそばにいる人が人工呼吸をしなければ、その人は命が助かったとしても植物状態になってしまいます。
心停止の場合、少し遅れても電気ショックを与えたり止まっている心臓を動かす薬剤を使ったりすれば再び心拍が再開することもありますが、脳に長時間血流がなくなるとやはり植物状態になりますし、時間がたてば心拍が再開する可能性も格段に低くなります。したがって、そばにいる人が心臓マッサージをおこなわなくてはならないのです。
当たり前の話かもしれませんが、心肺停止ほど時間が勝負の状態はありません。そこで、以前から一般の人もできるだけ医療行為に参加できるようにしようという試みがありました。
**************
スポーツジムや空港に設置されているランドセルくらいの大きさのオレンジ色の箱を見たことがありますでしょうか。
これは、AED(自動体外式除細動器)と呼ばれる心臓に電気ショックを与える器械です。心停止には心臓マッサージをおこないますが、あるタイプの心停止の場合は、マッサージよりも電気ショックが有効な場合があります。AEDは、電気ショックが有効な心停止かどうかを瞬時に判断することのできる器械です。
心停止を確認すれば、AEDをその人に装着します(2つのパットを胸に貼ります)。すぐにAEDは電気ショックを与えるべきかどうかを判断し、与えるべきときは「電気ショックが必要ですのでボタンを押してください」としゃべります。その声を聞いて、その場にいる人がボタンを押すと電気ショックがパットを伝わって流れます。もしも、電気ショックが無効であると判断した場合は、「そのまま心臓マッサージを続けてください」としゃべります。
アメリカでは、AEDが普及しだしてから突然の心肺停止の救命率が劇的に上昇しています。例えば、シカゴの空港ではAEDを設置してから心肺停止を起こした人の61%が助かったという報告があります。ラスベガスのカジノでも、53%が救命されたというデータがあります。AEDを設置する前のデータははっきりしないのですが、おそらくほとんどが助からなかったものと思われます。
日本でもAEDを普及させようとの動きが数年前から活発になりました。現在は一般の人がおこなえる救命処置(BLS)の項目にAEDの使用が入れられています。AEDだけでなく、人工呼吸も心臓マッサージも理屈を覚えただけではできるようにはなりません。実技指導を受けて模擬演習をしなければ実際にできるようにはならないのです。
ちょうど私が研修医の頃、BLSを一般市民に広めてACLS(二次救命処置)を医療者に普及させようというムーブメントが起こりました。私は、冒頭で述べた20歳の看護学生の死を経験したこともあり、その直後にACLSを覚え、BLS及びACLSのインストラクターをおこなうようになりました。ACLSだけでなく(ACLSは医療者向けの救命処置で薬剤の使用や気管内挿管もおこないます)、BLSにも取り組んだのは、一般の方にもできるだけ救命活動に参加してほしいと思ったからです。
ただ、私がインストラクターをしていた頃は、AEDの使用は医師や救命士に限られており、客室乗務員も日本上空を離れてからでないと使用が許されていませんでした。2004年の7月にようやく一般市民にも認められるようになり、次第に普及するようになってきました。
1月16日の毎日新聞によりますと、広島県では県の医師会が中心となって一般市民にAEDの使用を含むBLSの講習をおこない始めたそうです。
これが全国的に広がり、多くの国民がBLSをできるようになり、さらにAEDがどこにでもある社会になれば、心肺停止の救命率が飛躍的に上昇するでしょう。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
47 美しい身体をつくるには 2006/12/21
メタボリック・シンドロームという言葉が定着してきたからなのか、健康診断を受ける人が増えてきたからなのか、最近では30代で生活習慣病に罹患している人、もしくは放っておけば罹患するであろう、いわゆる”予備軍”の人を診察する機会が増えてきています。
生活習慣病には、糖尿病、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、・・・・、といろいろありますが、こういった疾患に罹っている、もしくはその予備軍の人たちに共通している点は「肥満」です。メタボリック・シンドロームの診断基準にあるように、特にウエストラインの太さが目立つ人が多い印象があります。
「肥満」になれば、生活習慣病のリスクが高まるだけでなく(「肥満」そのものが生活習慣病だとする考え方もあります)、自身のボディイメージが損なわれますから、肥満に悩む多くの人たちは「ヤセル」ことを目標としているようですが、なかなかこの「ヤセル」ということは簡単ではないようです。
世間では、様々なダイエット方法が氾濫し、痩身効果をうたった器具が次々と開発されていますが、なかなか劇的な効果の得られるものは多くないようです。こういったものは有効性が怪しいどころか、危険性の伴うものも少なくなく、医師などの専門家の指導のもとでおこなわなければ大変危ないと思われるのですが、それでも世間の関心はとどまることがありません。
しかしながら、あらためて言うまでもなく、ヤセルのに最も効果的なのは「食事」と「運動」です。このふたつをないがしろにしていれば、どれだけ痩身効果をうたった高価な器具を使ったところでそれほど効果は得られません。
「食事」について言えば、あきらかに現代日本の食生活は「過食」です。その人の生活環境にもよりますが、事務職に従事している人であれば、一日に必要なエネルギー量は男性であれば2,000キロカロリー前後、女性なら1,600から1,800キロカロリー程度で充分でしょう。
しかし、例えば食堂やレストランで、ランチセットなどとして組まれているもののなかには、一食で1,000キロカロリーを超えているものが少なくありません。昼食がメインであればまだいいかもしれませんが、夕食にも同じようなもの、あるいはそれ以上のものを食べ、さらにおやつまで食べていれば一日の摂取カロリーは軽く3,000キロカロリーを超えてしまいます。これでは肥満になるのは時間の問題です。
それに、日本人の体質は高脂肪食を日常的に摂取するようにはできていません。もともと高蛋白・低脂肪の食生活に適した遺伝子を日本人は持っているはずですから、欧米型の食事を導入すれば、一気に肥満となり生活習慣病を発症するのは時間の問題です。
そして、これは日本に限ったことではなく、例えばフィリピンの一部では、西洋の食文化が入ったために以前は肥満などなかったのに、現在では住民の過半数が肥満に悩んでいるという地域もあります。最近、タイでも食生活の変化から肥満児が増えており、行政が伝統的なタイ料理を食べるように呼びかけています。
とは言え、カロリーの高いものは美味しいものが多いですから、ついつい食べ過ぎてしまう人の気持ちが分からないわけではありません。医師という仕事をしていれば、とにかく時間がなくて食事の時間を捻出するのに苦労を強いられますから、私の場合、できるだけカロリーの高いものを食べられるときに食べるようにしていますが、これは世間からみると例外的なことでしょう。もしも、私も昼食時と夕食時にある程度の時間が確保できるなら、過食によって肥満となるかもしれません。
「運動」はその重要性をほとんどの人が認識しているでしょうが、時間を決めてエクササイズに通ったり、ジョギングを規則的におこなったりしている人はそれほど多くないのかもしれません。おそらく現代の日本人のライフスタイルでは、よほど大きな決心をして運動の時間を確保しない限り、規則的な運動というのは相当むつかしいのでしょう。
しかしながら、「食事」と「運動」を適切におこなうことによって、「肥満」のない身体、そして美しい身体をつくることは、本当は誰にでもできることなのです。「あたしは太る体質だから仕方がないの・・・」という人がいて、確かに太りやすい太りにくいというのは体質(遺伝子)によってある程度は規定されていることが分かっていますが、それがすべてではありません。日本人もフィリピン人もタイ人も少し前までは、肥満に悩む人などほとんどいなかったのですから。
私はこのことを以前、タイのイサーン(東北)地方で実感したことがあります。タイという国は、地域によって文化が大きく異なり、イサーン地方の奥地ではバンコクなどとは食生活がまったく異なり、西洋食が存在しません。コンビニもほとんどなく、日本人が日頃食べているようなお菓子も入手できません。
私はその地域に5日間ほど滞在しましたが、年齢・性別を問わず、太っている人をひとりも見かけませんでした。太っているどころか、男女とも非常に美しいプロポーションをしているのです。
男性であれば、肩幅が広く、腹筋が割れており、重いものを平気で片手で持ち上げます。私は、家をつくっている現場で仕事を手伝わせてもらったことがあるのですが、彼らはいとも簡単に50キロのセメントを片手で運んでいました。あまりにも簡単そうに運んでいるので私も手伝わせてもらったのですが、私の体力では片手では不可能で、結局私だけが両手で運ぶことになりました。彼らには無駄な脂肪がついていないどころか、無駄な筋肉もついていません。
女性の場合も、ウエストに余分なぜい肉が付いている人などひとりもおらず、全員が美しい手足をしています。しかし、無理なダイエットでやせた身体ではなくて、筋肉はしっかりとついており、少々の力仕事ならなんなくこなしています。彼女たちは家をつくるといった肉体労働はあまりおこないませんが、日頃から魚や(食用の)カエルを捕ったり、農作業に従事したりしているためにバランスよく運動ができているのでしょう。
イサーン地方では食事にも驚かされます。主食はもち米で、魚を醗酵させてつくった味噌のようなものにつけて食べます。あとはキノコや野菜、アリの卵や昆虫がメインです。肉や魚はないわけではありませんが、それほど食卓には乗らず、肉についてはホルモン(内蔵)がほとんどで、日本人が好んで食べるような部分の肉はほとんど口にしません。
さらに驚くのは”おやつ”です。彼(女)らがおやつに食べるのは、昆虫か果物のどちらかなのです。その地域のある女性はこう話していました。
「あたしは以前バンコクに住んでいたことがあるけど、コンビニにはほとんど行ったことがないわ。バンコクでも屋台で昆虫や果物は買えるんだもの。昆虫や果物の方が安くて美味しいんだから、あたしたちにはコンビニは不要なのよ」
この食生活は栄養学的にみて抜群です。主食は米で、野菜やキノコと少量の肉や魚がおかずとなっており、醗酵した魚でアミノ酸や乳酸菌を摂取し、昆虫と果物でビタミンとミネラルがバランスよく効果的に取れています。
つまり、イサーン人がほとんど例外なく美しい身体を保持しているのは、彼(女)らの特有の遺伝子がそうさせているのではなくて、合理的な食生活と運動(仕事)をしているからなのです。
日本人もイサーン人と同じような食生活と運動を・・・、というのは非現実的ですが、彼(女)らの美しい身体とイサーンの文化をときどき想像するようにすれば、あるいは昔の日本の文化を思い出せば、今自身が何をすべきかについてのヒントが得られるのではないでしょうか。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第46回(2006年11月) 臓器売買の医師の責任(後半)
医師と患者さんとの関係は信頼の上に成り立っているわけで、患者さんとその親族がグルになって医師を欺こうと思えば簡単にできてしまう、という話を前回しました。
今回の事件は、臓器売買をめぐってこのような問題が生じたわけですが、患者さんと親族がいくら「お願いします」と言っても、倫理上の観点からできない問題もあります。
例えば「自殺幇助」が該当します。高齢で生きる希望をなくしている患者さんがいたとしましょう。生きる希望をなくしているからといって末期癌など治療法のない病を患っているわけではありません。患者さんは死ぬことを希望しており、仮に家族もその考えを尊重したいと考えているとしましょう。このとき、「分かりました。致死量の劇薬を注射しましょう」などと言う日本の医者は(おそらく)ひとりもいません。「自殺幇助」が罪になるだけでなく倫理上許されないことを医師は分かっているからです。ヨーロッパの一部の国ではこのようなケースでも罪に該当しない法律をつくっていますが、それは例外と考えるべきでしょう。
「自殺幇助」などに比べると「臓器売買」については、倫理上あるいは歴史上、抵抗はそれほど大きくないと言えます。実際に、海外で臓器を買っている日本人が少なくないのは周知の事実です。日本人が生体腎移植を受けている国で最も多いのがフィリピンと中国だと言われています。少し詳しくみてみましょう。
2006年10月6日の共同通信がフィリピンの生体腎移植の実情を報道しています。フィリピンでは貧困地域に住む住人に対して、いわゆる臓器ブローカーが腎臓売買の斡旋をもちかけます。対象となるのは18歳から25歳の健康な男性で、腎臓を提供すると13万~16万ペソ(約30~38万円)が支払われます。腎臓を買うのはほとんどが日本人で、支払う金額はこれの10倍程度だそうです。
実際に腎臓を提供したある男性のコメントがこの記事に載せられています。その男性は、「(腎臓を受け取った日本人は)ありがとうと言ってくれたし、元気になっていたし、良かったと思う」、と述べています。
また、フィリピンでは死刑囚が臓器を有償で提供しています。つまり腎臓を売っているのです。これは、合法であるばかりか、「臓器を提供することに賛同した受刑者は刑を軽減する」という法案が提出されたこともあります。
フィリピン大学の哲学科のある教授は、「臓器提供は、受刑者が社会に何かを還元できる機会だ」、とコメントしています。
詳細は覚えていませんが、数年前に、肝硬変を患った日本の有名プロレスラーが、フィリピンで生体肝移植を受け、肝臓の一部を提供したフィリピンの若い男性が術後に亡くなったという報道もありました。
共同通信の同記事では、インド、中国、ブラジルの臓器売買の実情も報道されています。
インドでは、以前は、臓器売買は合法でしたが現在では違法となっています。しかし、現在でも水面下で売買がおこなわれているのが実情です。そして、違法とされているのは移植に伴う臓器売買だけです。研究用の臓器の売買は合法であるばかりか、増加傾向にあるそうです。ちなみに、インドでは移植に伴う臓器売買が違法になる前は、南部のタミルナド州が臓器ビジネスの拠点でしたが、現在では北部ウッタルプラデシュ州やパンジャブ州が中心となっているそうです。
中国では年間の移植件数が1万2000件を超え、米国に次ぎ世界第二位の「移植大国」となっています。腎移植だけで年間5000件以上が施行されています。中国の場合はドナーの大半が死刑囚であり、これが倫理上の観点から問題視されていますが、中国側にとっては貴重な外貨獲得源になっていることもあり、地方政府は実質臓器売買に荷担していると言えます。
ブラジルでは臓器売買は違法とされていますが、実際には水面下でおこなわれています。2003年に摘発されたブローカー組織は、およそ1万ドル(約118万円)で腎臓の提供者を募集していました。この組織では少なくとも38人の貧しい人々を南アフリカへ連れて行き、そこで移植手術がおこなわれたようです。
では、先進国ではどうでしょうか。偶然にも米国エール大学の移植医が「British Medical Journal」という医学誌に移植に関する論文を2006年10月5日に発表し、翌日に共同通信が報道しています。
この移植医は、「生体移植の腎臓提供者に金銭が支払われるような仕組みを立法化すべきだ」、と述べています。
同医師によりますと、「米国では2005年に6,500回余りの生体腎移植が行われたが、その10倍の約6万5千人が腎臓移植を待っており、平均待ち時間は2~4年」と、臓器不足が深刻化しています。
米国では、血液や精子、卵子の売買は合法です。同医師は、「政府の管理下で提供者への報酬も統一して移植を実施すれば違法な売買はなくなり、公平さが増し、安全性も向上する」、とコメントしています。
このように歴史的、地理的にみても臓器売買は必ずしも絶対的な「悪」とは言えません。考え方によっては、腎臓を受け取る人は健康を取り戻し、病院と医師には報酬が支払われるのに、腎臓の提供者だけが不利益を被るのは不公平であるという見方ができるかもしれません。もちろん、臓器売買は日本の臓器移植法で禁止されている行為ですから、国内でおこなえば罪に問われることになります。
しかし、内容を吟味せずに、ただ単に「法律に抵触することはすべて絶対に許してはならない」、などと言ってしまえば事の本質を見誤ることになりかねません。以前、このコーナーで述べましたが、「法律による罪の重さと本当の意味での罪の重さは相関しない」と私は考えています。
今回の愛媛の病院で腎移植を執刀した医師は、臓器売買をおこなった当事者ではなく、当事者たちの嘘の証言により騙されて手術をおこなったのです。その嘘が見破れなかったということが、大手マスコミの主張する「病院と医師の倫理意識の低さは驚くしかない」というコメントに果たして相当するのでしょうか。
金に羽振りをきかせて、後進国の若者の腎臓を買いまくっている多くの日本人が存在しているということ、世界で最も移植医療の進んでいるアメリカの専門医が臓器売買の合法化を提唱しているということ、アメリカを含め先進国のなかには血液や精子、卵子の売買が許されている国があるということ、今回の売買事件では提供者が「いいことをしたかった」とコメントしていること、そして、執刀医は腎臓提供者と受け取った患者さんの双方から「身内の関係ですのでよろしくお願いします」と頭を下げられていたこと、などを考慮したときに、この執刀医は、驚かれるほどの低い倫理意識しか持っていなかったのでしょうか・・・。
地域でもっとも腕の立つ移植医と言われていたこの医師が、この事件のせいで今後移植手術がおこなえなくなるとすると、最も不利益を被るのは誰でしょうか・・・。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第186回(2018年7月) 裏口入学と患者連続殺人の共通点
- 第185回(2018年6月) ウイルス感染への抗菌薬処方をやめさせる方法
- 第184回(2018年5月) 英語ができなければ本当にマズイことに
- 第183回(2018年4月) 「誤解」が招いた海外留学時の悲劇
- 第182回(2018年3月) 時代に逆行する診療報酬制度
- 第181回(2018年2月) 英語勉強法・続編~有益医療情報の無料入手法~
- 第180回(2018年1月) 私の英語勉強法(2018年版)
- 第179回(2017年12月) これから普及する次世代検査
- 第178回(2017年11月) 論文を持参すると医師に嫌われるのはなぜか
- 第177回(2017年10月) 日本人が障がい者に冷たいのはなぜか
月別アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (125)