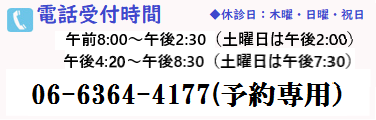メディカルエッセイ
2013年6月21日 金曜日
85 製薬会社の使命と医師の使命 2010/2/20
2010年1月初旬、欧州議会議員会議(PACE, Parliamentary Assembly of the Council of Europe)が、WHO(世界保健機関)が2009年に宣言したインフルエンザのパンデミック(世界流行)宣言は、「偽りのパンデミック(fake pandemics)」の可能性が強い、と主張し調査をおこないました。
私は、このニュースを読んで大変驚きました。新型インフルエンザは、昨年4月頃からメキシコをかわきりに、米国、カナダ、日本、英国、オーストラリアなどで流行し、当初からメキシコでは高い死亡率が報告され、各国で従来の季節型インフルエンザよりも重症化することが多く死亡率も高いという調査が相次いでいるのです。
最近になって罹患者は減少しつつありますが、それでも終息したわけではなく、依然猛威をふるっています。WHOが迅速に「パンデミック宣言」をおこない、予防の重要性を訴え、ワクチン接種の勧奨をおこなったことは評価に値するのではないでしょうか。
なぜ、欧州議会議員会議(以下PACE)がWHOのパンデミック宣言を”偽り”としているかというと、PACEはワクチン製造企業とWHOの間に癒着のような関係があると考えているようです。
PACEは1月25~29日に開催された冬季会議のメインテーマを「Faked pandemics, a threat to health(偽りのパンデミック、健康への脅威)」と決定し,本部(仏ストラスブール)で緊急討議を行い、さらにWHOとワクチン製造企業の関係者に対する公聴会も実施しています。
WHO、ワクチン製造企業の関係者を招集して公聴会を開くというのですから、PACEはWHOのパンデミック宣言に対して相当嫌悪感を抱いているような印象を受けます。
これはなぜなのでしょうか。考えられる理由のひとつに、議員も世論も日頃から製薬会社に対してネガティブなイメージを抱いている、というものがあるのかもしれません。要するに、製薬会社は儲けすぎている、もっと言えば、「病気にかかるかもしれないという人の弱みにつけこんで利益を得ようとしている」といったイメージがあるのかもしれません。
映画『ミッション・インポシブル2(M:I-2)』では、殺人ウイルス「キメラ」と解毒剤「ベレロフォン」を奪還するのが、トム・クルーズ演じるイーサン・ハントの”ミッション”になっていましたが、この殺人ウイルスを開発したのは巨大製薬会社「バイサイト」という設定になっています。
また、新型インフルエンザが登場したとき、誰かが人為的にウイルスを製造したのではないか、という噂、(例えば、製薬会社がウイルスを作成し、ワクチンと特効薬を同時に売り出そうとしたのではないか、という噂)が一部でありました。
実際には自らの金儲けのために人為的にウイルスを製造するといったことはないでしょうが、病気の不安を煽って儲けようとする製薬会社があるのではないかと考える人はいるようです。
例えば、高血圧の診断基準は、以前は収縮期血圧(上の血圧)が160mmHg以上とされていました。これは1978年のWHO(世界保健機関)が定めた基準です。それが、1999年の新しい基準では、140mmHg以上と診断基準が厳しくなっています。さらに、2009年のJSH(日本高血圧学会)では、140mmHg以下であっても肥満やメタボリックシンドロームなどがあれば治療を検討すべき、ということになっています。
つまり、次第に高血圧という診断がつきやすくなり薬開始へのハードルが下がっているわけで、ここから、製薬会社が病気の人を増やして薬を売りたいからではないか、という噂がでてくるのです。(もちろん、高血圧の診断基準は公正な大規模調査により裏付けられていますから、製薬会社の思惑で基準が変更になったわけではありません)
さて、では製薬会社は儲けようとしていないかと言われれば、「不当に儲けようとはしていない」とは思いますが、製薬会社自体はほとんどが株式会社の形態をとっていますから利益を出さないと存続できないのは事実ですし、利益を出さなければ株主から厳しい追求をされることになります。それに、ある程度の利益を捻出し、それを新薬の開発費に投資しなければ、薬学の進歩は望めないことになります。製薬会社に勤める人も、ある程度の収入がなければ困るでしょう。
つまり、利益を出さなければ組織が存続できず、薬学の発展も望めないという側面があるものの、利益至上主義になってしまうことが許されないのが製薬会社の立場というわけです。
これは一般の製造業者とは似ているようで似ていません。例えば、自動車でも家電製品でもコンピュータでもいいのですが、一般の製造業者は、今の生活よりも便利になるものを開発することが使命です。つまり需要を掘り起こすことで企業の存続意義がでてきます。一方、製薬会社の場合は、今ある病気に対する薬を製造することがミッションなわけで、新たに病気を生み出したり病気に対する不安を煽ったりしてはならないのです。これを別の言葉で言えば、一般の製造会社はゼロからプラスを創造することが、製薬会社はマイナスをゼロに近づけるのがミッションであるということになります。
マイナスをゼロに近づける、という言い方をすると我々医師も同じなのですが、製薬会社のミッションと医師のミッションは、少し異なります。
私は、以前、ある後発品中心の製薬会社に「支援をするから開業しないか」という話を持ちかけられたことがあります。物件はすでに確保してあり家賃や内装費まですべて会社が負担するからクリニックの院長として診療をしてもらえないか、という提案です。
これは、普通の(医療以外の)会社や店舗ならありがたい話だと思います。何しろ開業資金がゼロとなり、その後もコンビニなどのフランチャイズとは異なり、毎月の売上から何パーセントを払わなければならないという制約もないのです。上手くいかなかったときのリスクがほぼゼロで、かつ利益をそのまま受け取ることができるのです。
しかし、私はこの申し入れを断りました。その理由は、以下のようなものです。
製薬会社のミッションは、薬を販売し利益を上げることである。一方、医師のミッションは、いかに薬を処方しないか、である。薬をできるだけ使わずに、また使ったとしても最小限に努めるのが医師の使命なのである。このようにミッションの方向が異なっているのだから、製薬会社と医師のタイアップは上手くいくはずがない。
製薬会社にはライバル会社が多く、利益追求をしなければ会社が存続できません。しかし、医療機関は利益追求を考えてはならず薬の処方は最小限にしなければなりません。このあたりの微妙な違いを日々感じながら、我々医師は薬の処方をおこなっているのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第84回(2010年1月) 本能としての正義感
先日、高校のミニ同窓会でのこと・・・。
高校卒業後、警察官になったK君と席が隣り合わせになった私は、興味本位で警察の内部のことを尋ねてみました。というのも、週刊誌やテレビドラマで警察内部の実情が紹介されるとき、警察の不祥事や暴力団との癒着などが浮き彫りにされることがあるからです。私は、正義を貫くことをミッションとしている警察官が、そのミッションとは逆に反社会的な行動をするようなことがあるのかどうか、本当のところを知りたかったのです。同級生のK君なら本当のことを話してくれるに違いありません。
K君によると、「すべてを知っているわけではないが、そんなこと(不祥事など)はありえない。警察官は常に自身の正義感に基づいて任務を遂行している」と言います。「正義感をなくせば人間はおしまいだ」と強く訴えるK君に私は共感を覚えました。
なぜ共感したかというと、私は年を追うごとに「正義」というものを意識するようになってきているからです。私のいう「正義」とは、警察官が日々考えているような「悪を社会から失くす正義」といった大きなものではなく、日常生活の中で、ちょっとした不公平が許せなかったり、ずるいことをする人間を非難したくなったりするような正義です。
飲み会の席で「正義」について熱く語ったのは私にとっては初めてで、K君との会話は大いに盛り上がりました。
そして、あることに気づきました。
K君と私は高校生のとき、一度クラスが一緒になったことがあるのですが、お互いテストになると憂鬱な気分になり、よく愚痴をこぼしていました。テストのときは名簿順に座りますから、K君と私はいつも席が隣で、「なんとかカンニングをする方法がないか」ということを半ば冗談半ば本気でよく話し合っていたのです。
そんなK君と私が、それから20年以上の月日を経て「正義」について熱く語り合っているのです! このことに気づいたK君と私は高校生時代を思い出して笑ってしまいました。
さて、K君が言うように「正義感をなくせば人間はおしまいだ」ということに賛同する人はどれくらいいるでしょうか。
私自身のことを言えば、おそらく20代半ばくらいまでは、「ふん! 何が正義だ。正義なんて言葉を口にする人間は偽善者に決まっている!」と考えていました。ところが、その後次第に正義を当然のことと感じるようになったというか、正義でないこと、例えば不公平や不正に対して強い嫌悪感を抱くようになってきたのです。これは、私が医師という職業を選んだことと無関係ではないでしょうが、それだけではないように思います。
たしかに私は医学部に入学し、知人から医療現場での不満を聞くにつれて、医療現場ではどのような患者さんであれ平等に医療を受けられなければならない、と考えるようになりましたし、タイのエイズの実情を目の当たりにし、エイズという病が原因で、社会から家族から、そして医療機関からも差別を受けている人を救わなければならないと考えました。そして、それらが太融寺町谷口医院やNPO法人GINA(ジーナ)のミッション・ステイトメントの原点になっています。
しかし、私が「正義」にこだわるのは、このような個人的体験だけでなく、もっと本質的なものがあるように感じていました。というのも、正義を貫くことには、何か”感動”のようなものがあるからです。例えば、身近なところに何らかの不公平があり、それを自分自身で指摘し改善するような行動をとったときに”感動”のような感覚がありますが、これは自己満足と言われるかもしれません。けれども、例えば、映画やテレビドラマで、主人公が様々な嫌がらせや脅迫を乗り越えて正義感を貫く姿にはほとんどの人が感動するのではないでしょうか。
つまるところ、「正義」とは本来は誰もが持っている言わば”本能”のようなものではないか、と感じることが私にはあったのです。そして、最近この私の感覚を裏付けるような研究が発表されました。
玉川大学脳科学研究所の春野雅彦研究員が、脳の中に不公平を嫌がるときに盛んに活動する部位があることを突き止めたのです。これは科学誌『Nature Neuroscience』のオンライン版2009年12月20日号で発表されています。(注)
この研究では、まず男女64人に報酬金の分け方について好みを調べています。自分と相手がもらう金額の差が小さくなるのを好む25人と、そうでない14人を選抜しています。そしてこの39人に自分と相手の報酬金の差を36パターン示し、その際の脳の活動をfMRI(
機能的磁気共鳴画像装置)で観察しています。
その結果、自分と相手がもらう金額の差が小さくなるのを好む人は、金額の差が大きいほど扁桃体と呼ばれる情動に関連する脳の部分が活発に活動することが分かりました。また扁桃体の活動の様子に応じて、不公平をどの程度嫌がるかも予測できたそうです。
扁桃体は、脳の大脳辺縁系と呼ばれる部分の一部にあたります。一般的には、「原始的な脳」と言われ、基本的な怒りや恐怖など、生物にとって原始的な情動に関連していると言われています。「原始的な脳」に対して、ヒトに発達している理性などをつかさどる「高次な脳」は大脳皮質に存在します。大脳皮質が高度な思考や理性を司っているというわけです。
一見すると、「正義」「公正」「平等」などは、高次な理性によって処理されている、すなわち大脳皮質に関係していると思われがちです。ところが、この研究では、こういったものは扁桃体に関係している、要するに原始的な情動のひとつである可能性を指摘しているわけです。
何らかの不正を発見したとき、ずるいことをしている輩をみたときに、我々は瞬時に「許せない」という感覚を覚えます。これは自分自身が得をするか損をするかといったものとは別の次元での感覚です。そして、自分自身の損得とは関係なく、平等、公平、正義などが感じられるときに我々は安堵感を覚えるのではないでしょうか。
私は、こういった平等、公平、正義などを絶対正しいと思う感覚は、人間の本能であると感じています。こういった感覚が本能であり、上に述べた研究が示すように原始的な脳が司っているとすれば、人間以外の動物にも認められることになりますが、最近の動物行動学の研究でも動物の様々な「利他的な行動」が報告されています。
よく「良心の呵責に耐えられなくて・・・」と言って罪を告白したり懺悔を考えたりする人がいますが、これも本能に逆らえないからではないでしょうか。
よく「本能」というと、食欲、性欲、自己顕示欲などが取り上げられますが、正義、公平、平等などを求める欲求も本能のひとつと捉えるべきではないか、と私は考えています。そして、こういった欲求に逆らうような、要するに正義、公平、平等などに反するような行動をとれば、本能に逆らうこととなりいずれ精神の破綻をきたすのではないかとも感じています。
そう考えると、私のように年をとってから正義を強く意識するようになった人間というのは、これまでの人生でさんざん正義に反する行動をとっていたために、それを埋め合わせたいという欲求が強いということなのかもしれません。
注:上記論文のタイトルは「Activity in the amygdala elicited by unfair divisions predicts social value orientation」です。
(http://www.nature.com/neuro/journal/v13/n2/full/nn.2468.html)
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
83 投薬ミスはいかにして防ぐべきか 2009/12/21
医療事故のなかで最も多いミスのひとつが「投薬ミス」です。似たような名前の薬を誤って処方・投薬することにより、患者さんに害のある薬を与えることとなり、結果として患者さんに不利益となることがあり、最悪の場合は死につながることもあります。
喘息が悪化したときなどによく使うステロイドの点滴に「サクシゾン」というものがあります。これと似た名前の薬剤に「サクシン」というものがあり、こちらは強力な筋弛緩剤で、全身の筋肉に作用するため呼吸筋も動かなくなり呼吸停止となります。
2000年11月、北陸地方のある病院で事故は起きました。40代の男性患者にサクシゾンを投与すべきところを誤ってサクシンが投与されその患者は死亡しました。これを受けたサクシンの製造会社は、製品ラベルを分かりやすいものに変更するなどで再発防止に努めましたが、悲劇は再び起こりました。
不幸な事故から8年後の2008年11月、今度は四国のある病院で、70代の男性患者に解熱目的で医師がサクシゾンを指示しようとしたところ、実際に投薬されたのはサクシンで、そのおよそ2時間後、この患者は呼吸停止による死亡が確認されました。
この事故は夜間に起こっています。宿直していた医師がなかなか解熱しない患者さんに対して、コンピュータを用いて投薬の指示をおこないました。端末に「さくし」と打ち込んで自動的に表示された「サクシン」を選択したのです。
この事故の後、製造会社は、「薬の名前を変更する以外に再発を防ぐ方法はない」、と考え、「スキサメトニウム」という名称に変更しました。サクシンは15年ほど前から使われている筋弛緩剤で、「サクシン」という名称に慣れ親しんでいる医療者の間で混乱を招くのではないかという声も一部にはあったようですが、二度の死亡事故を踏まえて名称変更に踏み切ったのです。
薬の名前なんてきちんと確認していれば間違うはずがないんじゃないの?、と思われる方も多いと思いますが、時間が勝負の臨床の現場では似たような名前には神経がすり減らされる思いがする、というのが我々医療者のホンネであります。
似たような名前の薬剤は他にも多数あり、例えば、「ノイロビタン」と「ノイロトロピン」、「アレロック」と「アロテック」、「ノルバスク」と「ノルバデックスD」などが有名です。
さて、今回は私自身がしてしまった投薬ミスについてお話したいと思います。
週末の混雑している夕方の外来に受診されたある患者さんに対し、ある薬を処方したのですが、その薬は少し胃に負担がかかることがあるために、患者さんが胃がそれほど強くないと話されたこともあり、私は胃薬を同時に処方しました。しかしこの胃薬の投薬が結果的に投薬ミスとなってしまったのです。
その胃薬は、ムコスタという胃粘膜保護剤の後発品(ジェネリック薬品)で、名前を「レバミピド」と言います。私は、電子カルテに「れ」と打ち込んで表示されたレバミピドを選択したつもりでした。
ところが、その日の診察終了後、カルテをチェックしていると、実際に処方したのは「レバミピド」ではなく「レボフロキサシン」という抗生物質であることが判りました。
それに気づいた私はその場で患者さんに電話をしました。幸い、その患者さんはまだ薬を飲んでおらずなんとか事なきを得ました。謝罪をおこない、状況を説明し誤って処方した「レボフロキサシン」は内服しないように伝えました。
今回は、その日のカルテチェックで気づきましたが、同じミスを二度と起こさないという自信はありません。以前から「レバミピド」と「レボフロキサシン」は名前が似ているから注意が必要ですね、という声は院内から上がっていましたが、私は「レ」が同じだけで間違えるなんてことはないだろう、と考えていたのです。
そう考えていたのにもかかわらずミスをしてしまったわけですから、同じことを再度してしまわない保障はありません。私は翌日の朝のミーティングでこの問題を取り上げ、取り扱う薬の変更を提案しました。
「レボフロキサシン」は「クラビット」という抗生物質の後発品です。「クラビット」は非常に優れた抗生物質ですが、値段が高いという短所があります。1錠あたり173.7円もするのです。例えば、この薬を1回1錠1日3回で5日間処方すると、3割負担でも800円近くかかることになります。これを後発品の「レボフロキサシン」にすると、患者負担額が500円ちょっとにまで下がります(それでもまだ高いように思えますが・・・)。
抗生物質のクラビットに比べると、胃粘膜保護剤「レバミピド」の先発品であるムコスタは1錠あたり22.1円とそれほど高くありません。後発品のレバミピドが15.5円で、ムコスタとの1錠あたりの差は(3割負担の)患者負担で1.98円です。院内で検討した結果、この程度の差なら、値段の高い先発品を使っても似たような名前から生じる投薬ミスのリスクを考えれば許容されるのではないかという結論に達しました。(胃薬は抗生物質に比べると長期の処方になることが多いという違いはありますが・・・)
それにしても、今回の投薬ミスは、自分の能力の限界というか、注意力のなさというか、ともかく自分自身の無能さを自覚することになり大いに反省しました。
「人間だから誰でもミスをする」とか「ミスは完全に防げない」とか言われることがあり、私は「そうかもしれないが医療者はあってはならない」と考えていました。しかし、今回のこの自分のミスで少し考えが変わりました。
「医療者は絶対にミスをしてはいけない」ではなく、「ミスを最小限にするために最大限の努力をしなければならない」と考えるべきではないかと今は思います。
今回の私の投薬ミスによって、直ちに取り扱う薬を変更するという決定をしました。しかし、今後太融寺町谷口医院で投薬ミスが二度と起こらないという保障はありません。現在もおこなっている薬のダブルチェック(実際に薬を患者さんに渡す前に最低2人のスタッフがチェックすること)を丁寧におこなうこと、どれだけ忙しくても患者さんが飲み方をきちんと理解してくれているかどうかを薬を渡すスタッフが確認すること、そして、今回のように似たような名前の薬が他にないかをいつも考えること、などを徹底したいと考えています。
そして、私にしかできないカルテのチェックにも念を入れたいと思います。たとえ長時間に及ぼうとも、その日の診察のカルテは何度も読み直すという習慣を大切にしたいと考えています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
82 肥満患者が医師に丁寧に扱われていないというのは本当か 2009/11/20
医師はすべての患者に平等に接する、というのは我々医師にとっては、言わば当たり前のことであるはずで、わざわざ言葉にする必要もないようなことです。しかしながら、この当たり前のことも守られなくなる可能性がないわけではなく、そのため、様々な医師の倫理要綱には、例えば、「貧富の差に関わりなく医師は患者を平等に診察しなければならない」といった内容のものが記載されています。
では、実際はどうなのでしょうか。実は、私が臨床医を目指そうと思った理由のひとつが、この「患者間の不平等をなくしたい」というものでした。そもそも私は医学部入学当初は臨床医をする気持ちはありませんでした。元々社会学部の大学院を目指していた私は、いったん医学部で医学を学んだ後に医学的なアプローチで社会学を研究したいという希望を持っていたのです。
ところが、医学部に入学してみると、患者さん、というか知人や、あるいは知人の知人が、まだ医師になっていない医学部生の私に対して、医療機関に対する不満を話すことが多かったのです。
「医者はちゃんと話を聞いてくれない・・・」「長時間待たされて診察時間は1分で終わった・・・」、こういう不満が多いのですが、この手のクレームは想像できることです。患者さんが結果として不満をもつのはもちろん良くないことですが、少ない医師が多くの患者さんを診察しなければならない日本の医療の現状を考えるとある程度は止むを得ないという側面もあります。
しかしながら、次のような不満は学生の私でさえも多いに問題があると感じました。
「外国人だからという理由できちんと診てもらえなかった」(30代の南米出身の男性。日本語はほぼ完璧なのにです)
「信用していたから自分の過去も話した。すると医者の態度が突然かわり、診察に行くとイヤな顔をされるようになった」(過去に違法薬物の経験があるという20代男性)
「言う必要があると思ったから本当は隠しておきたかった同性愛者であることを告げた。すると看護婦や他のスタッフも含めてジロジロ見られるようになって明らかに他の患者とは対応が違うようになった」(30代の男性同性愛者)
「言いたくなかったけど過去に自分がウリ(売春)をしていたことを医者に話した。過去のことなのに医者と看護婦に説教をされた」(20代女性)
外国人であろうが、違法薬物を使用していようが、売買春をしていようが、患者は患者です。このような理由で、医療機関で不快な思いをし、その結果病院を受診しなくなれば、病気が悪化することだってあるはずです。
私は、普段は他人に言えないようなことでも包み隠さず話すことができる、そしてそのことを自身の個人的価値感ではなく病気を治すという観点から話を聞くのが患者と医師の関係だと考えています。
医療の現場で、国籍や職業、犯罪歴などで差別されることがあってはならないのではないか・・・。私はそのように強く感じ、ならば自分自身がこういった患者さんも平等に診る医者になろうと考えました。研究者志向から臨床医を目指そうと思ったのは他にも理由がありますが、こういった人たちとの会話が私を臨床医に駆り立てたのは事実です。
また、タイのエイズ施設でボランティアをしていた頃、HIV陽性という理由で病院からさえも差別的な扱いを受けた患者さんを何人も診ることになり、これがNPO法人GINA(ジーナ)を設立するきっかけとなりました。
太融寺町谷口医院のミッション・ステイトメントに「患者さんの年齢、性別(sex, gender)、国籍、宗教、職業などに関わらず、全ての患者さんに平等に接する」とあるのは、私の個人的なこういった経験があるからです。
さて、今回お話したいのは、「肥満患者は医師に丁寧に扱われていない」という大変ショッキングな研究結果が発表されたということです。
この研究は米国ジョンズ・ホプキンス大学によっておこなわれ、医学誌『Journal of General Internal Medicine』2009年11月号に掲載されています(注1)。研究者らは医師40人に、肥満患者に対する態度について質問表を用いて質問した結果、238人の患者についてBMI(注2)が10増加するごとに、医師の患者に対する敬意が14%減少することが判明したといいます。
研究者らは「このような医師の態度が、医師と患者の関係にどのような影響をもたらすかは不明」としていますが、「患者が再診を受けることを拒絶したり、否定的態度で扱われたと感じたりすることが示されている」と述べています。さらに、「(丁寧に扱わないことによる)情報伝達の減少は患者の健康転帰に有害性をもたらす可能性がある」と指摘しています。
BMIが10増加するごとに、医師の患者に対する敬意が14%減少する、というのはにわかには信じがたいことです。
米国の現状はよく分かりませんが、日本の医療の現場でもこのようなことがありうるのでしょうか。肥満があるからといって、コミュニケーションが取りにくいということはありませんし、医師に対して反抗的というわけでもありません。私には、この研究結果が事実を反映しているとは到底思えないのですが、実際はどうなのでしょうか。
この研究では、医師の同様な態度は、アルコール中毒、麻薬使用者、HIV感染者などに対しても当てはまることが指摘されています。肥満というだけで丁寧に扱われないのなら、社会的に問題のあるアルコール中毒者や麻薬使用者などがもっとぞんざいにされていることは想像に難くありません。また、HIV陽性者が丁寧に扱われないのは、残念ながら現在の日本でもあり得ることです。
私自身はクリニックのミッション・ステイトメントにも掲げているように「全ての患者さんに平等に接する」ということを医師としてのミッションと考えています。しかしながら、今回この論文を読んで感じたことは、「たとえ私が平等に接しているつもりでいても、患者さんの側からみたときには丁寧に扱われていないと感じているかもしれない」ということです。
特に、患者数が多くひとりあたりに時間をあまりかけることができないときに、説明が早口になったりあまり大事でない部分は省略したりすることがあります。すると、結果的に患者さんは「ぞんざいに扱われた」と感じ、その結果再診に来なくなるかもしれません。すると場合によってはその病気がさらに悪化する可能性もあります。
「全ての患者さんに平等に・・・」というミッションは、常に心の片隅に置いておかねばならない・・・。この論文を読んでそれを再認識するようになりました。
注1:論文のタイトルは「Physician Respect for Patients with Obesity」です。
要約はhttp://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11606-009-1104-8で読むことができます。
注2:BMIとはボディ・マス・インデックスの略で、体重(キログラム)を身長(メートル)の2乗で割った数字です。体重88キログラム、身長2メートルの人なら、88÷2の2乗=88÷4=22となります。一般的には22~25くらいが標準とされています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第81回(2009年10月) 医学部受験はなぜ再受験生に有利か
拙書『偏差値40からの医学部再受験』などでも述べましたが、医学部受験は現役生よりも再受験生の方が有利なのではないか、と私は思っています。
これには反論も多いと思います。例えば、いくつかの大学医学部では現役生の割合がやたらと高く、これには現役生は点数に「ゲタをはかせてもらっている」、あるいは再受験生には「ハンディが課せられている」などの噂もあります。また、2005年には群馬大学医学部で合格者の平均点(最低点ではない!)を上回る得点をとった55歳の女性が、実際に年齢が理由で不合格とされました。
このような噂や事実があるのにもかかわらず、私が医学部受験は再受験生に有利と考える最大の理由は、「勉強を楽しむことができる」というものです。
もちろん、勉強、特にテストが伴う勉強というのは楽しいだけではありません。かなりの苦痛も伴いますし、焦燥感、不安感、抑うつ感、ときには絶望感にさえ襲われることがあります。
しかし、会社を辞め収入源を断たれても再受験生として受験勉強をしたいと考えるのは、学問に対する強い思い入れがあるからに他なりません。拙書でも述べたように、受験勉強に伴う苦痛など社会人として体験する様々な苦労に比べれば微々たるものです。
少し考えてみればすぐに分かることですが、入試というのは、あらかじめ与えられた履修範囲(高校で習うこと)から問題が出題され、すべての受験生が同じ時間を与えられて採点は客観的におこなわれ点数が高ければ合格となるのです。
一方、社会で体験する多くの苦労は実に理不尽なものです。例えば、客観的にはライバル社の製品の方が優れていると感じていても自社製品を売らなければならないとか、どう考えても期日までにできそうにない仕事をプライベートを犠牲にしてまで仕上げたとたん会社の方針が変更され努力が無駄になった、などといったことは日常茶飯事です。
そんな理不尽で筋の通らない社会人の苦労に比べれば、勉強のスランプなど実に些細なことです。
このことに気づいているだけで再受験生の方が受験には有利なわけですが、それ以上に、「再受験生は勉強の楽しさをすでに知っている」ということを強調したいと思います。
私が医学部受験を本格的に開始したのは1995年の1月で26歳のときでした。この頃の勉強は苦労もありましたが、振り返ってみれば大変楽しく勉強に専念できたと思います。苦手の数学では解けない問題もありましたが、それを考えながら眠ると夢のなかで解けていた、といった経験を何度かしましたし、生まれて初めて取り組んだ古文は最初はさっぱり分かりませんでしたが、そのうち好きになり、半年後には源氏物語や徒然草の原書を読むようになりました。友達や家族とも連絡をほとんどとらなくなり、私は文字通り「寝食を惜しんで」勉強に没頭していたのです。
ところで、先日皮膚科関連のある学会で、ある有名な医師が講演しており、そのなかでハッとする内容がありました。
26から33歳の頃がもっとも研究に専念できる・・・
その有名な医師は講演のなかでそのような意見を述べたのです。そして、この26から33歳が研究にふさわしいという考えは、その医師だけでなく「多くの医師や研究者が感じていることである」ということを主張していました。
私が、なぜハッとしたかというと、これが自分にもあてはまったからです。私は26歳のときに本格的に医学部受験の勉強を開始し、1年後には医学部に入学し、その後の6年間は多少のスランプはあったものの、総じて言えば勉強に専念することができたのです。
講演していた有名な医師がおこなった立派な研究と比べれば、私がしたことは単なる勉強ですから比較するのは大変失礼なのですが、私は「そうだったのか・・・。自分が勉強に専念できたのは”勉強適齢期”だったからなのか・・・」というふうに感じ、この26から33歳という説に納得させられました。
さて、この「26から33歳説」に共感した私は、さっそくこのコラムで取り上げようと考え、頭の中で整理することにしました。
ところが、です。頭の中でこの説を反芻すればするほど、26から33歳という年齢を重視するのはちょっと違うかもしれない・・・、と思えてきたのです。
私が勉強に没頭したいと考えるようになったのは、社会人を経験してからです。以前に通っていた大学生活や社会人の生活を通して、次第に勉強の魅力に惹かれるようになっていったのです。
そして、もしかするとこの著明な医師も同じような転機をたどったのではないか・・・。そのような考えが頭をよぎりました。この医師は、おそらく中学高校と一生懸命に勉強をし、医学部入学後も過酷な勉強を強いられ医師国家試験に合格し、2年間の研修医を経て、大学院に入学し研究に専念するようになったそうです。ということは、大学と病院で様々な経験を通して勉強や研究の魅力を感じるようになったのではないでしょうか。
私はこのように考えています。既存の教育システムでは、小中高及び医学部などの大学では勉強は能動的にではなく、テストを中心に与えられたカリキュラムをマスターするように強いられます。しかし、本来勉強の面白さは、与えられたことを覚えるのではなく、自ら問題を発見することにあります。私の場合も、医学部受験を決意したのは、人間の身体や精神の神秘性に興味を持ったからです。そして、学問や勉強そのものに真剣に取り組みたいと思うのは、試験に合格しなければならないから、ではなく、もっと純粋な目的ができたときではないかと思うのです。そして、もちろん個人差はありますが、その純粋な目的意識を自覚できるようになるのは、様々な人生経験を経てからではないだろうか、と感じているのです。
であるならば、何も勉強や研究に真剣に取り組みたくなるのは26から33歳に限ったことではありません。いくつになっても勉強を開始することはできるのです。少し例をあげると、伊能忠敬が測量に興味を持ったのは50歳を超えてからですし、少しジャンルが異なるかもしれませんが画家の丸木スマさんが初めて美術に取り組んだのは74歳のときです。
結局のところ、学問の面白さに気づいた人間が研究や勉強に有利になるのです。勉強が好きで好きでたまらない、寝食を惜しんで勉強するのが楽しくて当然・・・、そのように感じる者が成果を上げることができるのです。
医学部受験も例外ではありません。いくつになっても、勉強の面白さに気づきさえすれば医学部合格も時間の問題ではないか・・・。私はそのように考えています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
80 それって愛ではないけれど 2009/9/20
今月のある日曜日の夜、たまたま時間ができた私は、映画『ディア・ドクター』を近くの映画館に見に行きました。
『ディア・ドクター』は西川美和監督の作品で、笑福亭鶴瓶が演じるニセ医者の動揺する心境を描いたものです。(ここで「ニセ医者」と言ってしまうと、いわゆる”ネタバレ”になってしまうかもしれませんが、他の多くのサイトですでにニセ医者であることが書かれていることと、公開してすでに3ヶ月近くがたっているということを考慮して許されるのではないかと考えました)
作品の良し悪しは別にして(いくつかの映画評論サイトを見てみましたが、のきなみ高得点がつけられています)、私がこの映画で最も印象に残った場面を紹介したいと思います。
僻地で働いていた主人公のニセ医者は、ある理由から突然失踪します。警察の調べでニセ医者であることが分かり、刑事が関係者から証言を集めるのですが、香川照之が演じる薬会社の営業マンに対して、刑事が、「なぜ(失踪したニセ医者は)医者をやろうと思ったのか」と、この営業マンに尋ねます。この営業マンは日頃からニセ医者の診療所に出入りしていて仲良くやっていました。
黙っている営業マンに対して、刑事は「(ニセ医者が僻地で医療をやろうと思ったのは)”愛”なのか」とイヤミっぽく質問します。つまり、金儲け以外に免許がないのに医師をしていた理由は、病人に対する愛情なのか、と皮肉をこめて聞いているのです。
ここで、この営業マンは<ある行動>に出ます。(<ある行動>は映画を見ていない人のために伏せておきます) この営業マンが言いたかったのは、無医村の僻地で医者をやろうと免許のないニセ医者が志したのは”愛”と呼べるようなものではなくて、もっと別のものだ、ということです。
このシーンを見たときに、私は、「そうそう!」と心の中で叫びました。
私も医師ですから「どうして医師になろうと思ったのですか」と聞かれることがしばしばあります。特に私は、文科系の大学を卒業し、いったん商社に就職し、その後医学部受検を試み、医学部に合格したのは27歳のときですから、どうしても経歴を言うとこの質問を受けることが多いのです。
実は私は、医学部入学当時は、まだ医師になることを考えていませんでした。医学部入学前は母校の関西学院大学社会学部の大学院に進学することを考えていて、医学部に進路変更したのは、医学の観点から社会学で取り上げるようなテーマを考えてみたいという思いがあったからです。要するに、私の医学部受験の動機は、「医師ではなく医学者を目指したいから」というものでした。
それが、医学部在籍中にいろいろな出来事があり(すべては書けませんが、病気に関することで医療機関を受診してイヤな思いをした、という話を何人もの人から訴えられた経験が大きいと言えます)、それで、こういう医師を目指したい、という”想い”が芽生えたのです。
その”想い”は”愛”か、と問われれば、そんな崇高なものではありません。そんな立派なものではなく、「このような医療を実践する医者がいないのだとすれば、そしてそういう問題に自分自身が気づいたのだとすれば、それは自分自身がやるしかないではないか・・・」、そういう類の”想い”なのです。
登山家であるジョージ・マロリーは、マスコミからのインタビューで「なぜエベレストに登るのか」という質問に、「そこに山があるから」(原文では”Because it is there.”)と答えたというエピソードがありますが、医師が医師を目指す理由もこれに近いものがあるのかもしれません。
医師を目指すこととエベレストに登ることを一緒にしてしまうのは、登山家の方に失礼かもしれませんが、もっと身近なところでも、この「そこに山があるから」と同じ動機で行動するケースはいくらでもあります。私は以前このコラムで「気づいたモン負けのルール」というものを紹介しましたが(下記コラム参照)、おそらく多くの人は、無意識的にこのルールに従って行動しているのではないかと私は考えています。人間は損得勘定のみで行動するわけではないのです。
話を『ディア・ドクター』に戻したいと思います。
主人公のニセ医者は、地域の人に慕われているというよりもむしろ神や仏のような扱いを受けています。困っている人から連絡が入ると、スクーターに乗りどこにでもかけつけます。また、毎晩医学書を見ながらひとりで遅くまで勉強をしています。このような姿を目の当たりにした研修医は、「一通りの研修を終えた後、再びこの村にやってきて(このニセ医者と)一緒に働きたい」、と言いだします。
しかし、その地域で、たったひとりで医療をおこなうには、”愛”ではない医師を志す”想い”があったとしても、それだけでは務まりません。ときには交通事故の重症の被害者や妊婦や乳幼児も診なければならないわけです。ありとあらゆる患者さんに対して、最終的には隣町の高次医療機関に搬送するとしても、初期診察というのはひとりでおこなわなければなりません。
映画の中では、破水がおこった妊婦を救急車の中で診察しながら、医学書をめくっているシーンがあったり、緊張性気胸といって早急に胸に針を刺さなければ命を失いかねない状態の患者を診たりするシーンがあります。緊張性気胸の場面では、ベテランの看護師の助言に従いながら処置をおこない、なんとか事なきを得るわけですが、これは見ている方もヒヤヒヤします。おそらく、重症患者を目の前にして何もできないニセ医者をみていた看護師は、このニセ医者がニセモノであることに気づいていたのではないかと思われます。
映画では、”愛”ではない別の”想い”でニセ医者が活躍している姿を描きながら、同時に、そんな”想い”だけでは医療はできない、という現実も訴えられているのです。
私は映画館を出るとき、この映画はもしかすると現役の医師に対するメッセージがこめられているのではないかと感じました。
つまり、「あなたたち(本物の)医師とこの映画のニセ医師の違いは、医師免許を持っているかどうか以外に何があるのでしょう。たしかに(本物の)医師であるあなたには、このニセ医師が持っていない知識や技術をいくつも持っているでしょう。しかし、そんな(本物の)あなたは、すべての病人や怪我人に対して何の迷いもなく最も適切な治療ができるのですか。それができないから、あなたは毎日のように勉強を続けているのではないですか。それではそんな勉強熱心なあなたと、このニセ医師の本質的な違いは何なのですか・・・」、このような問いかけをされているように感じたのです。
もしも、このニセ医師が金儲けや興味本位から僻地で医療をしていたなら、このようには感じなかったに違いありません。
”愛”ではない医師を志す”想い”が見事に描かれているが故に、それが我々医師に対する辛辣なメッセージとなっているように私は感じたのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第79回(2009年8月) ”掟”に背いた医師
奈良県大和郡山市の病院が生活保護受給者の診療報酬を不正受給していた事件は我々医療従事者に大きな衝撃を与えました。
報道によりますと、この病院は2005年から2008年に生活保護を受けていた複数の患者に対し、心臓カテーテル手術をしたように書類(カルテなど)を捏造し、合計約860万円もの大金を詐取したとされています。
これら以外にも、実際には必要のない患者に心臓カテーテル手術を施した、との報道もあります。一部には、この病院の医師らが患者に対し、「手術しないと死ぬよ」と話していたとも伝えられています。
マスコミの報道は、どうしても病院や医師を悪者として取り扱う傾向にあります。それは、マスコミの使命として仕方がないのかもしれませんが、実際にはそのあたりの偏った見方を取り除いて事の本質を見極めなければなりません。
私はこの事件を初めて聞いたとき、「解釈の仕方によっては、診療報酬請求が不正ととられかねない」程度であろうと思っていました。
例えば、一部のマスコミの報道にあった「手術をしないと死ぬよ」と医師が患者に話していたという点については、おそらく次のような会話があったのではないかと考えました。
患者「先生、やっぱり手術が必要になるんですかね」
医師「そうですね、今手術をしておかないと、この前みたいに突然胸が痛くなって意識を失う可能性がありますよ。この前はたまたま近くにいた人が救急車を呼んでくれたから奇跡的に助かったけど、今度同じようなことがあれば命にかかわるかもしれませんよ・・・」
心臓の手術の説明をおこなうとき、このような会話がおこなわれることはよくあります。これを患者側が過剰な解釈をすれば、医師に「手術をしないと死ぬよ」と言われた、となる可能性があります。
ですから、私は当初は悪意をもったマスコミが、権力(この場合は病院)を叩くために、大げさな報道をしているのではないかと思っていたのです。
ところが、その後、実際には手術をしていないのに手術をしたかのようにみせかけた偽りのカルテが発覚し、それを職員が認め、最終的には院長や理事長も認めた、との報道がおこなわれました。
実情がここまで明らかになると、私の解釈が誤りであり、マスコミの報道が正しいことを認めざるを得ません。こんな病院があり、こんな医師が存在しているということが同じ医師としてにわかには信じがたいのですが、いったいなぜこんなことが起こってしまったのでしょう。
「不正請求」という言葉は、しばしばマスコミに登場しますから、一般の方からみれば、他の医療機関でもこのような悪いことがおこなわれているのではないかと感じられるかもしれません。
しかし、「不正請求」の大半は、悪意がない、というか、保険請求のシステムの関係で「不正」とされているだけです。例をあげましょう。
最近喉が渇いて夜中にトイレに行く回数が増えたという45歳の男性が初診で受診されたとしましょう。この人がメタボリックシンドロームを示唆するような体型をしていれば我々医師はこの症状から糖尿病を疑います。糖尿病を疑っているわけですから、病名を「糖尿病の疑い」として、血糖値を測定します。検査をするにはそれに応じた「病名」を付けなければならない決まりになっているのです。
さて、ここまではいいのですが、「HbA1C」という糖尿病の状態をより正確に示す項目も検査すべきだと考えることがあります。しかし、「HbA1C」は「糖尿病の疑い」という病名では認められず、「糖尿病」という病名が必要になります。このとき医師はどうするか。まだこの時点では糖尿病という診断が確定していないわけですから「糖尿病」という病名を付けることには抵抗がありますし、これ自体が不正な記載になると感じられます。そこで「糖尿病の疑い」という病名のままでHbA1Cを測定することになるのですが、こうすると「不正請求」とみなされて診療報酬が支払われなくなることがあるのです。(実際、太融寺町谷口医院でもこの理由で「不正請求」と見なされ支払いを拒否されたことがあります)
このような例は他にもいくらでもあります。そして、「不正請求」の大半が、このように、少なくとも悪意はなく患者さんのためになる(と医師が考える)ものであり、病院の利益を目的としたような不正請求というのは、ほとんどの医師からすれば考えられないことなのです。ですから、今回の大和郡山市の病院の行為は、我々医師からみても許せるものではないのですが、それ以上に、信じられない・・・、というのが正直な感想なのです。
なぜなら、病院がこのようなことをすれば、医療という社会システムそのものが崩壊の危機にさらされることになるからです。
少し古い話になりますが、2005年に千葉県の1級建築士が、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していた、いわゆる「耐震偽装問題」が報道されました。この事件は、一般市民を不安にさせただけではなく、ほとんどの建築関係者を落胆させたに違いありません。1級建築士も人間ですから、生涯を通して品行方正に暮らしているわけではないでしょうが、構造計算書を偽造、というのは何があっても、(端的に言えば命を差し出しても)してはいけないことではなかったでしょうか。つまり、この1級建築士は職業人としての”掟”に背いているわけです。
大和郡山市の病院も同じことです。何があっても絶対にしてはいけないこと(「タブー」と言ってもいいかもしれません)をこの医師は犯しているのです。これは法律で裁かれる以上に、”掟”に背いた責任をとるべきであると私は考えています。
個人的な話になりますが、私自身としては法律というものをあまり重要視していません。法律よりも大切なものが”掟”であり、それぞれの職業には職業人としての”掟”があると考えています。
以前、ジャーナリストが取材源を露呈してしまうのは(それが故意でなかったとしても)”掟”に反する行為である、ということを述べました(下記コラム参照)。他にも、例えば、学校の先生が未成年の生徒に性的関係を強要したり、警察官が闇組織に情報を流したり、政治家が脱税していたり・・・、といった事件は、職業人としての”掟”に背くことになります。
おそらく大和郡山市の病院の医師も、医師になりたての頃は、このようなことは思いもつかなかったでしょう。何かがきっかけとなり医師としての矜持を捨ててしまったのでしょうか。それとも、この医師の人格がもともと破綻していたのでしょうか。
いずれにせよ、”掟”に背いた職業人が社会から許されることはないでしょう・・・。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
78 臓器移植法改正で闇の臓器売買は減少するか 2009/7/21
2009年7月13日、 「脳死=人の死」とすることを前提に、臓器提供の年齢制限を撤廃する改正臓器移植法(A案)が参院本会議で賛成多数で可決され成立しました。
改正法は公布から1年後に施行されることになりますから、直ちに多くの「脳死=人の死」からの臓器が提供されるわけではありませんが、これで日本も国内での臓器移植が増えることが予想されます。
今回の法改正の最大のポイントは「脳死=人の死」としていることと言えるでしょう。
現行の臓器移植法では、<臓器を提供する場合に限って>脳死を人の死としています。それに対して、改正法では、脳死と判定されれば、それは少なくとも法律の上では「人の死」となるわけです。
もちろん、残された遺族に対して、「あなたの息子さんは脳死と判定されましたので、すでに死亡しています。死亡されたんだから臓器をわけてくれてもいいじゃないですか」、などと医者が言うわけではありません。
「脳死=人の死」というのは単に法律上の解釈にすぎないわけで、本質的な意味では脳死が人の死かどうかなどといった問題は誰にも分かりません。(その逆に、生命はいつ誕生するのか、つまり、生命誕生は受精時なのか、着床時なのか、死産届けが必要な妊娠12週以降なのか、あるいは母体から取り出されたときなのか、といった問題も誰も本質的な意味では答えられません)
臓器移植に関して言えば、いくら法律上で「脳死=人の死」と言われても、自分の脳死後、あるいは自分の子供が脳死となったときに、臓器を提供しなければならないという義務はありません。生前に臓器提供を拒否していれば臓器が移植に使われることはありませんし、意思表示がはっきりしていない場合でも、遺族が臓器提供に同意しなければ移植されることはないのです。
一方で、是非とも自分の臓器を使ってほしいという人もいるでしょうし、自分の子供が脳死になれば、子供が反対しなければ、あるいは子供に判断能力がなければ、自分の子供の臓器を必要な人に提供したいと考える親もいるでしょう。
そのような臓器提供に積極的な考えをもつ人がいて、なおかつその臓器を必要としている人がいるなら、法律が妨げになるべきではない、と言えます。日本の法律が臓器移植を事実上妨げているから、海外に臓器を求める人がいるのは事実です。
現行の法律では国内での移植手術が大変困難であるのが現実で、このような状況に目をつけて登場してきたのが臓器売買ビジネスです。臓器ブローカーが移植を必要としている患者さん、もしくは患者さんの家族を探し、同時に、海外(特にフィリピンと中国が多いと言われています)で臓器を提供したがっている遺族(臓器提供の見返りに報酬を受け取ることができると言われています)、そして、移植手術を貴重な収入源にしている病院をみつけ、それらをつなぎあわせるというわけです。
こういった臓器移植は実際のところはどれほどの数になるのかははっきりと分かりません。合法なのか非合法なのかさえも曖昧なルートもあるようです。それに、臓器の提供者が本当に脳死だったのかどうか、つまり、本当は脳死の基準を満たしていないのに臓器を必要としている人のために(あるいは自分らの金儲けのために)脳死にされた人がいるのではないか、そのような噂は後を絶ちません。
映画『闇の子供たち』では、日本人の心臓疾患のある子供(レシピエント)に心臓を提供した(させられた)のは、生きたタイ人の少女でした。もちろん、これはフィクションですし、実際にこのようなことはあり得ませんが、例えば、交通事故で意識不明、植物状態は免れないが脳死の基準を満たしていない・・・、このようなケースで脳死と判定されてしまうことは本当にないと言いきれるでしょうか。(これは私の憶測ではありますが)フィリピンや中国といった交通事故の多い国で、臓器をほしがる日本人、金儲けをしたいブローカーと悪徳病院、植物状態で寝たきりになる事故の被害者の家族、とそろったときに、脳死の判定基準は緩やかになってしまわないのか・・・、と思えてなりません。
さて、日本の臓器移植法が改定されれば、日本人は日本人に臓器供給を、という流れになるのは間違いないでしょう。すでに世界各国から、日本人は(高い円で)外国人の臓器を買っている、と非難されてきました。これまでは、「法律が障壁となって自国で臓器が手に入らないから・・・」という言い訳ができましたが、法改正後は、この言い訳が通用しませんから、たとえ日本国内で臓器を提供してくれるドナーが見つかりにくかったとしても、これまでのように海外にドナーを求めて、というわけにはいかなくなるでしょう。
ここでひとつ疑問を呈したいと思います。
法改正で「脳死=人の死」となり、臓器提供のハードルが下がったときに、脳死の判定が、『闇の子供たち』のような極端な事態にはならないとしても、日本でも緩くなってしまわないか、という疑問です。
もちろん脳死の判定には、いくつもの具体的な条件があり、複数の医師が判定に加わることになっています。悪い噂の耐えない国とは異なり、日本ではきっちりと判定がおこなわれるにきまっているじゃないか・・・、そう思う人がほとんどでしょうし、私自身もそのように思いたいのですが、私がどうしてもこの疑問をぬぐえない原因となっている事件が少なくとも2つあります。
1つは「和田心臓移植事件」です。1968年8月8日、和田寿郎医師を主宰とする札幌医科大学胸部外科チームは、日本初となる世界で30例目の心臓移植手術を成功させました。しかし、後に”事件”と呼ばれるようになったことからも分かるように、この移植手術にはいくつもの疑問が残されています。詳細は割愛しますが、私が最も問題と感じている疑問は、脳死の判定基準が本当に守られたのか、という点です。実際、脳死判定にはかかせないはずの脳波が測定されていなかったことが後に判明しています。
もうひとつは、最近奈良で発覚した「山本病院診療報酬不正受給事件」です。奈良県郡山市の山本病院が、生活保護受給者の診療報酬を不正受給していたことが2009年6月に発覚しました。この病院では、手術をする必要のない患者さん(主に生活保護受給者)に心臓カテーテル手術を施行し(手術を受ける必要のない生活保護受給者に「手術をしないと死ぬよ」と医師が話していた、という報道もあります)、さらに、実際には手術をしていないのに、手術をしたように虚偽のカルテを作成していたことが関係者の証言で明らかにされました。(この事件は我々医療従事者にとっても大変ショッキングなものでした。いずれこの事件については詳しく取り上げたいと思います)
たしかに、心臓カテーテル手術と移植手術はまったく異なるものですし、移植手術の場合は、レシピエントだけでなくドナーが必要となります。しかし、ドナーについては、山本病院のように生活保護受給者にターゲットを絞ったとしたら・・・、そもそも生活保護受給者は身寄りのない人が多いわけで、そのような人が脳死には至らないものの植物状態になったとしたら・・・、そして臓器が必要な人がいたとして(実際いくらでもいます)、さらにそれらをつなぐブローカーが現れたとしたら・・・。
現在のシステムでは、臓器移植を希望する人は日本臓器移植ネットワークに登録することになっています。そして脳死の判定は厳格にされていますし、臓器移植手術をおこなうことができる病院は厳しい基準で選別されています。ですから、日本国内で闇の臓器売買などは起こるはずがないのですが・・・。
私の危惧が杞憂であることを祈ります・・・。
参考:
NPO法人GINAウェブサイト「GINAと共に」第27回(2008年9月)「幼児売春と臓器移植」
メディカルエッセィ第45回(2006年10月)「臓器売買の医師の責任(前半)」
メディカルエッセィ第46回(2006年11月)「臓器売買の医師の責任(後半)」
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
77 大学病院の総合診療科の危機 その2 2009/6/20
さて、マスコミの報道によりますと、大学病院の総合診療科が廃止に追い込まれている理由として次のようなものが挙げられています。
①利用度が上がらなかった。
②専門の診療科の方が患者に人気がある。
③総合診療を担当する医師が少ない。
④総合診療は時間がかかる割には、手術や高額な検査を行わず、経営側から見れば不採算部門。
⑤臓器別の専門診療科よりも地位が低く見られがちなことも、医師側に不人気。
これらを順にみていきましょう。
まず、①の「利用度が上がらなかった」ですが、大学病院はそもそも他の医療機関からの紹介状がなければ受診できない病院です。したがって、大学病院の総合診療科を受診する患者さんというのは、診療所/クリニックや地域の病院で診断がつかず、どこの専門科を受診すべきかが分からない(もしくはその時点では専門科を受診すべきでない)と医師が診断した症例に限られます。このような症例はそれほど数が多いわけではなく患者総数が多くないのは当然のことです。
また、大学病院にもときどき紹介状を持たずに受診する人がいますが、たいていは”門前払い”をされます。これは、見方によっては「医師の応召義務違反」となるかもしれませんが大学病院の役割を考えればある程度は止むを得ないことです。しかし、紹介状がないからといって強い症状のある患者さんに帰ってもらうわけにはいきませんから、紹介状がなかったとしても急いで診察・治療をする必要のある場合はこの限りではありません。したがって、こういうケースでは総合診療科が診察することがあります。ただしこの場合も症例数としてはそれほど多いわけではありません。
ですから、大学病院の総合診療科を受診する人というのは、初めから限られているのです。
次に②の「専門の診療科の方が患者に人気がある」ですが、これも①で述べた理由と同じで、大学病院には他の医療機関からの紹介状を持参した患者さんが受診するのが原則であり、その紹介状の宛名は、「総合診療科」ではなく「脳神経外科」「消化器内科」など専門科になっていることがほとんどであることを考えると当然のことです。患者さんは紹介状に書かれた「科」を受診するわけですから、「人気のあるない」というのは少し論点がずれているような気がします。
③の「総合診療を担当する医師が少ない」というのも当然のことです。①、②で述べたように大学病院を受診する患者さんは、他の医療機関からの紹介状を持っているというのが原則です。一方、総合診療をおこなおうとする医師の多くは、紹介状持参の患者さんではなく、初期診療(一番最初の診察)をすることに重きを置いています。患者さんが健康上のトラブルを抱えたときにまず受診するのは大学病院ではなく地域の診療所やクリニックですから、大学病院で総合診療を学ぼうと思っても限界があります。ですから、総合診療を担当する医師は小さな医療機関であればあるほど多く、大学病院では少ないのが理にかなっているのです。
④の「総合診療は時間がかかる割には経営的に不採算」というのは、医療を市場社会で考えるならその通りであって、医療機関を「利益を追求する組織」と考えるのであれば廃止になっても仕方がないのかもしれません。
前回のコラムで例にあげたように、複数の訴えをもった患者さんが総合診療科には(太融寺町谷口医院にも)よく受診されます。このような患者さんを診察するとき、まず話を聴くだけでかなりの時間を費やします。患者さんが検査を望んでいたとしても、現時点では不必要と考えられるケースも多く、その場合、「なぜ今その検査が必要でないのか」を患者さんに納得してもらうまで説明しなければなりません。そのため診察に30分以上もかかって検査や薬は一切なし、なんてこともよくあります。これでは経営的に成り立たないのです。
しかしながら、医療というのは本来市場社会には馴染まないものです。医療機関と言えどもある程度の利益を出して税金を払うことができなくなれば倒産してしまうのは事実ですが、医療従事者たる者が利益を追求するようになってしまえば、もうそれは医療とは呼べないのではないでしょうか。現実と理想のバランスをとるのはむつかしいことかもしれませんが、「経営的に不採算だから総合診療科を廃止する」というのは寂しく感じます。
⑤の「臓器別の専門科より総合診療科の地位が低くみられる」というのは私にはよく分かりません。「科」によって序列があると考える人がいるということなのだと思いますが、おそらくそのような”地位”を気にする人は、「職業に貴賎はない」という言葉をキレイごとと捉え、医師と他の職業の間にも”序列”を考えているのではないでしょうか。
さて、大学病院における総合診療科が廃止に追い込まれているのは事実だとしても、その一方で、民間病院の総合診療科に人気があるのもまた事実です。実際、総合診療に力を入れている病院には、研修医の就職希望が集中しています。(こういった病院の多くは、給与は決して高くありません。給料ではなくやりたいことを求めて多くの研修医が希望をしているのです)
また、総合診療関連の学会や研究会も大変盛り上がっており、今月開催される予定だった総合診療関連の大きな学会は、定員の定められているワークショーップのほとんどで申し込みが殺到し随分早くに締め切られていました。(この学会は新型インフルエンザの影響で8月に延期されることになりました)
では、総合診療科は民間病院にのみ意味があって大学病院には存在価値がないのかというと、決してそんなことはありません。やはり大学病院というところは、いろんな情報がいち早く入ってきますし、いろんな人材が豊富ですから、総合診療を学ぶという点においては大変有益な場です。
私が大学の総合診療科で学んでいた頃は、週に1~2回、大学病院の総合診療科外来で研修を積み、それ以外は地域の診療所やクリニックに勉強に行っていました。大学病院でのカンファレンスや症例検討会というのは大変充実しており、一般病院でのカンファレンスにはない良さがあります。その症例が治癒に至ったとしても、その過程において学術的な観点からとことん討論を重ねるような形式はやはり大学病院特有のものだと思われます。また、大学にいれば各専門科の医師にすぐに質問しにいけるというメリットもあります。
大学病院の総合診療科が廃止になるのは大変残念なことです。大学病院の利点をいかしながら、地域の病院や診療所/クリニックと連携をして、営利を追求するのではなく、幅広い知識と技術を学べるような総合診療の教育・研修システムが構築されることを願います。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
76 大学病院の総合診療科の危機 その1 2009/5/20
このウェブサイトでは何度も紹介していますが、「総合診療科」というのは、患者さんの臓器のみをみるのではなく、患者さんを総合的にみることを重要視しています。従来、医療機関というのは臓器別に細かく専門化されすぎていましたから、それを反省する意味もあり日本でも今から10年ほど前に注目を集めだしました。
実際、2000年前後までに、総合診療科(「総合診療部」または「総合診療センター」と呼ばれることもありますがここでは「総合診療科」で統一します)は、およそ50の大学病院に設置されました。
ところが、ここに来て大学の総合診療科が次々と廃止に追い込まれています。
2005年9月に北海道大学が総合診療科を廃止し、2007年4月には杏林大学が廃止を決めました。2009年度からは京都大学が廃止、群馬大学は救急部と統合することになりました。また、2002年には島根大学が総合診療科設立の翌年に廃止を決めています。(報道は2009年4月20日の読売新聞)
大学での総合診療科が次々と廃止されている理由を考える前に、まずはなぜ総合診療科が必要と考えられるようになったかについてまとめておきましょう。
臓器別に診療をおこなうのが従来の日本の医療です。例えば、肝臓と心臓と皮膚に疾患のある人に対しては、肝臓、心臓、皮膚の診察を得意とする3人の医師がそれぞれ診察にあたるというわけです。
このような診察方法のメリットとしては、それぞれの臓器のスペシャリストが担当するわけですから、例えば、その患者さんが非常に稀な病気にかかっていたとしてもその疾患を見逃される可能性は少なく、初めから最新で最適の治療が受けられることが期待できます。これは、患者さんからみてもありがたいことです。町の開業医のみを受診しているだけでは発見できなかった病気が見つかるかもしれないのですから。
ではデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。医師側からみたときには、いつも他の医師がどのような検査をおこないどのような薬を処方したかに注意を払わなければなりません。検査内容が重なってしまえば医療費の無駄遣いになりますし、患者さんにとっても二度手間になります。薬についても同じ系統の薬を処方することにならないか、また薬の相互作用についてもいつも考えていなければなりません。したがって、複数の医師を受診している患者さんに対しては、毎回「他の医師の受診で薬の変更や追加はないですか」と聞かなければなりません。
患者さんからみたときのデメリットとしては、まずは3人の医師を受診しなければなりませんからお金と時間がかかります。お金の問題はさておき、時間は大変なものです。これだけ医師不足が深刻化している日本では、ひとりの医師に診察してもらうまでの待ち時間はかなりのものになります。3人の医師を受診するのに1日では不可能な場合もあるでしょう。また、同じ話を何度もしなければならないでしょうし、場合によっては採血を何度もしなければなりません。患者さんの気持ちとしては、「3人の医者が話し合って必要な項目を決めてくれれば1回の採血で済んだんじゃないの」、となるかもしれません。
問題はまだあります。この例で言えば、肝臓、心臓、皮膚のそれぞれの疾患が独立したものであればいいかもしれませんが、例えば、肝臓と皮膚の疾患は同じことが原因で発症していた、というようなことがあった場合、それぞれのスペシャリストを受診していたときには発見が遅くなるかもしれません。なぜなら、患者さんとしては肝臓の医師には肝臓に関することだけを話し、皮膚の医師に対しては皮膚のみについての症状を話すことになり、その関連性が問診から読み取れなくなることがあるからです。
仮に人間の身体はA,B,Cの3つの臓器から成り立つとしましょう。この場合、「A+B+C=人間」となるわけではありません。必ず「A+B+C<人間」となります。少し形而上学的に言えば、「部分の総和と全体は同じでない」ということです。なぜなら、AとB、BとC、CとAの相互性・連関性にも意味があり、さらにA,B,Cの3つがそろったときに初めて現れる事象や意味が存在するからです。
抽象的なうんちくはこれくらいにして話を元に戻しましょう。
例えば、次のような患者さんがいたとします。
32歳女性。営業職。2~3ヶ月前から食欲がなくなり、ときどき吐き気がする。1ヶ月くらい前からめまいも自覚するようになり、先週は2回ほど動悸があった。最近、肌のつやがなくなってきたような気がするし、先月には円形脱毛もできた。夜に眠れないことがあるし、最近イライラすることが増えた。これまでなかった生理不順が目立つようになってきた。花粉症が今年から始まったのか目のかゆみと鼻づまりが気になる。
さて、もしもすべての医療機関が臓器別にしか診察しないとすると、この患者さんはいったいいくつの科を受診しなければならないでしょうか。食欲不振+吐き気→消化器内科、めまい→脳内科もしくは脳外科、動悸→循環器内科、肌+脱毛→皮膚科、不眠+イライラ→精神科、生理不順→婦人科、目のかゆみ→眼科、鼻づまり→耳鼻科、といったところでしょうか。
営業職で忙しいこの女性がこれだけたくさんの科を受診することは現実的でしょうか。この女性のように複数の悩みがある人は実際にはいくらでもいます。では、このような人たちはどこの医療機関に行けばいいのでしょうか。
こういった悩みをもつ人に対して最初に対応すべきなのが総合診療科なのです。(総合診療と同じように使われる言葉に「家庭医療」「プライマリケア」というものがあり、定義の仕方によっては意味がそれぞれ少しずつ異なる場合もあるのですが、ここでは同じ意味とします。以下も「総合診療」で統一します)
大学病院や大病院の診療科が臓器別になっていることからも分かるように、医学教育も臓器別におこなわれています。ただし、臓器別の教育には有効な面も非常に多く、学生や研修医の立場からしても医学を理解する上で臓器ごとに学ぶことは絶対に必要です。
しかし、それだけでは実際の患者さんには対応できないのです。そのことに気づいていた私は、2年間の基礎研修を終えた後に大学の総合診療科の門を叩くことになりました。(実は、私が総合診療科の医局に入ろうと考えたのは、タイのエイズ施設でボランティアをしていたときに欧米の総合診療科医たちが臓器にとらわれずにどのような症状にも対応していたのを見て感銘を受けた、というのもひとつの理由なのですが、ここでは詳しくは述べないでおきます)
大学の総合診療科に入った私は、早速大学病院を受診される患者さんの診察(上級医の診察の見学や補助)をおこなうようになりましたが、自分が思うような成果が得られないことに気づきました。大学病院を受診される患者さんには一定の特徴があり、大学病院の患者さんを診るだけでは本当の意味での総合診療ができないと感じたのです。
私が感じたこのようなことと、今回のテーマである「大学病院で総合診療科が廃止」には関係があるように思えます。次回はそのあたりについてお話したいと思います。
つづく
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第186回(2018年7月) 裏口入学と患者連続殺人の共通点
- 第185回(2018年6月) ウイルス感染への抗菌薬処方をやめさせる方法
- 第184回(2018年5月) 英語ができなければ本当にマズイことに
- 第183回(2018年4月) 「誤解」が招いた海外留学時の悲劇
- 第182回(2018年3月) 時代に逆行する診療報酬制度
- 第181回(2018年2月) 英語勉強法・続編~有益医療情報の無料入手法~
- 第180回(2018年1月) 私の英語勉強法(2018年版)
- 第179回(2017年12月) これから普及する次世代検査
- 第178回(2017年11月) 論文を持参すると医師に嫌われるのはなぜか
- 第177回(2017年10月) 日本人が障がい者に冷たいのはなぜか
月別アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (125)