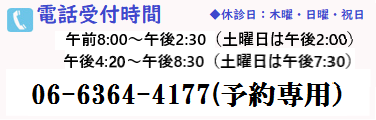メディカルエッセイ
2015年3月20日 金曜日
第146回(2015年3月) Choosing Wisely(不要な医療をやめる)(後編)
今回は症例の紹介から始めたいと思います。
20代の女性(Aさんとします)は、2週間前から毎晩全身にじんましんがでていました。放っておいても2~3時間で症状が消えるために、最初のうちはあまり気にならなかったのですが、毎日続き、痒みも増しているようなので、気になって太融寺町谷口医院(以下、谷口医院)を受診しました。
問診を終え、しばらくは毎日薬を飲むべき、という説明をすると、Aさんはなにやら不服そうな表情をしています。
私:「何か気になることがあるのですか」
Aさん:「なんで血液検査をしてくれないんですか」
私:「このじんましんは検査をしても異常所見がでないタイプで血液検査に意味がありません」
Aさん:「でも、何か見つかるかもしれないじゃないですか。お金を払うのはあたしですよ!」
私:「・・・・・」
じんましんが出れば血液検査が必要、と思っている人は非常に多く、なぜ必要ないかを説明するのに苦労することがしばしばあります。逆に、じんましんで初回の受診時に「血液検査が必要です」と言われたときには、それなりの理由があるのです。食物アレルギーを疑ったときもそうですが、一部の感染症や膠原病でもじんましんが生じることがあります。
血液検査が必要でないタイプのじんましんで受診し、「前の病院では検査をしてくれなかった」と不平不満を言う人も少なくありません。Aさんはその後当院を受診していませんから、彼女もまた血液検査をしてくれる医療機関を探し求めているのかもしれません。
もうひとつ例をあげましょう。
40代の女性(Bさんとします)は、数週間前から身体がだるく疲れやすいと言います。昨日から風邪症状が出現し夕べは近くの病院の救急外来を受診したそうです。Bさんは点滴をしてもらい抗生物質を処方してもらうつもりでいたそうなのですが、点滴は断られ処方された薬は市販のものと変わらない風邪薬のみだったと言います。
身体がだるく疲れやすいというのはよくある症状ですが、そこから大きな病気がみつかることがあります。ガン、HIV、結核、膠原病、甲状腺異常などが見つかるきっかけとなることもありますから、このような患者さんの訴えには充分注意すべきです。また、このような症状がうつ病などの精神疾患からきていることもよくあります。しかし、「身体がだるく疲れやすい」という症状の大半は、単純疲労、つまり休息が不充分なことから起こるものであり、こういったことは問診と簡単な診察からある程度わかります。
Bさんの場合も「単純疲労」の典型であり、私は点滴も薬も必要ないと判断し、まずは休養をとることが先決であることを話しました。しかしBさんは納得しません。
Bさん:「あのね、お金払うの、あたしですよ。お金払うから点滴して薬だして、って言ってるのよ」
私:「我々は患者さんにとって最善であることをしなければなりません。今のあなたにとって最善なのは薬も点滴も使用せずにしっかりと休養をとることです」
Bさん:「わかりました。こんなクリニック、二度ときません。今日は薬も点滴も何もないんだからお金も払いません!」
私:「・・・・・」
抗菌薬(抗生物質)は細菌を抑制するものであり、ウイルス感染と思われる軽度の風邪には使っても意味がない、というよりは副作用のリスクを抱えるだけですから有害と考えるべきです。また、「細菌感染には抗菌薬」という考えも正しくありません。特に下痢を伴っているような場合は、抗菌薬を内服することでさらに腸内の善玉菌まで殺してしまいますから、細菌感染を疑っても軽症であれば抗菌薬は用いるべきでありません。
点滴については過去にも述べたことがありますが(注1)、日本には「点滴神話」なるものがあり、点滴をあたかも「魔法の薬」のように思っている人がいます。そして、実際にプラセボ(プラシーボ)効果で元気になる人がいるのは事実ですし、ブドウ糖を入れれば血糖値が上昇するために一気に疲労回復することはあります。これは疲れたときに甘い物を口にすると元気になるのと同じ理屈であり、わざわざ点滴する必要はありません。
日本人の「点滴神話」は患者だけでなく医師の側にもあり、私はこれをタイのエイズホスピスで実感しました。エイズ末期で吐き気がおさえきれず食事を摂ることができない患者さんに対し、私は点滴を指示し、実際に患者さんには喜んでもらっていました。しかし、欧米の医師たちはこのような患者さんにも点滴はすべきでない、と主張するのです。自力で食事がとれなくなり回復の見込がないなら点滴は不要な延命治療、という考えなのです。おそらく欧米の医師が、日本に来て患者さんの希望に基づいて点滴をしている光景をみると驚くに違いありません。
ちなみに、Bさんが受診して数ヶ月後、谷口医院から歩いて5分くらいのところに「点滴専門クリニック」ができました。疲労回復や美容目的の点滴を希望する人のためにつくられた自費診療のクリニックだそうです。今度Bさんが受診したら教えてあげようと思っていたのですが、その後Bさんは一度も受診していません。そして、1年もしないうちにその点滴専門クリニックもなくなっていました。やはり、このような需要はそれほど多いわけではなく「点滴神話」が「神話」にすぎないことを理解している人の方が多いのでしょう。
ここで原点に話を戻したいと思います。Choosing Wisely(不要な医療をやめる)という考え方は我々医師のわがままではなく、患者さんからみても有益であるはずです。さらに医療費の抑制にもつながり行政にも有益であり、医療者・患者・行政の三者にとって望ましいものです。
では、患者さんにどのように理解してもらえばいいのでしょうか。AさんやBさんに正しく理解してもらうのにはどう説明すればよかったのでしょう。最も大切なのは、医師の技量を上げるということです。AさんとBさんについて私は彼女たちを批判的に描写していますが、AさんBさんにきちんと理解してもらえなかったのは私の方に責任があります。
Aさんが血液検査にこだわったこと、Bさんが抗菌薬と点滴にこだわったのには何らかの理由があったのかもしれません。例えば、Aさんの知人が重症のじんましんでアナフィラキシーショックを起こしたことがあるとか、Bさんの親御さんが抗菌薬の開始が遅れて肺炎が重症化し長期間の点滴を余儀なくされたことがあった、といったことです。
ですから、AさんとBさんが不快な思いをしたのは私の責任であります。しかしながら、入院患者さんならともかく、忙しい外来で多くの患者さんを待たせているなかで、患者さんの背景やどのような考えをもっているかということを分析することには限界があります。
そこで提案したいのが前々回紹介したABIM(American Board of Internal Medicine、アメリカ内科学委員会)が作成しているChoosing Wiselyのウェブサイトのようなものの日本語版をつくる、ということです。これがあれば、Aさんには「ここにも書いてあるようにこういったじんましんで血液検査はすべきでないんですよ」ということが言えます(注2)。前々回紹介した息子の頭部CT撮影にこだわったお父さんにも説明しやすくなります(注3)。Bさんには、なぜ抗菌薬が不適切かということを説明できます(注4)。しかし、さすがに点滴神話はアメリカには存在しない日本の特徴であり、ABIMのこのサイトには「安易に点滴をするな」とは書いてありません。アメリカにはそんなことをする医師がそもそもいないからでしょう。
今のところ、Choosing Wiselyの日本語版をつくろう、という声は聞いたことがありません。しかし、誰かがやらねばならない、と私は考えています。では、誰がやるのか。「気付いたモン負け」というルール(注5)が私のなかにあって、このルールに従うなら気付いた私がやらなければならない、ということになります。
ただし、単なる翻訳ならともかくABIMのサイトのようにきちんとしたものの日本版をつくるには、複数の専門家が集まって膨大な論文を検証するという気の遠くなる作業が必要であり、とてもひとりでできるものではありません。そこで、私はABIMのChoosing Wiselyを日本語に訳し、当院の症例なども合わせて分かりやすいものを少しずつ(本当に少しずつですが)このサイトで伝えていきたいと考えています。
注1:下記コラムを参照ください。
メディカルエッセイ第68回「「医療はサービス業」という誤解」
注2 下記ページの3に記載されています。
http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/american-academy-of-allergy-asthma-immunology/
注3 下記ページの1に記載されています。
http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/american-college-of-emergency-physicians/
注4 下記ページに記載されています。
http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/antibiotics/
注5:下記コラムで紹介しています。
メディカルエッセイ第53回(2007年6月)「”気付いたモン負け”というルール」
投稿者 | 記事URL
2015年2月20日 金曜日
第145回(2015年2月) Choosing Wisely(不要な医療をやめる)(中編)
Choosing Wiselyという言葉を日本のマスコミで見聞きしたことはまだありませんが、今後数年以内に取り上げられる機会が増えていくのではないかと私はみています。
というのは、「不要な医療をやめる」べきなのは誰が見ても明らかであり、これに異論のある人などいるはずがないからです。では、なぜ現代の医療がこれほどまで「不要な医療」が多いのでしょうか。
そのキーワードは<念のため>と<利益のため>です。
<念のため>からみていきましょう。前回紹介した頭をぶつけた男の子のお父さんは、「自分の息子が頭をぶつけ痛い痛いといって泣き止まない。もしかすると脳内に出血したかもしれない。そうでないことを祈りたいがきちんと検査をして調べる必要がある」と思い込んだわけです。つまり<念のために>検査をしておきたい、と考えたのです。
医師の側からみてみると、前回紹介した私の先輩医師は「CT撮影の必要はない」と医学的に判断しました。これは自分の診察に自信がないとできないことです。自信のない医師であれば「大丈夫だと思うけど、もしも微小な出血があったらどうしよう・・・。後から訴えられるかもしれないし・・・」という思考になり、「<念のために>CTを撮りましょう」となるのです。
次は行政サイドからみてみましょう。医療費削減のことを考えると、行政としては「少し頭をぶつけたくらいで貴重な保険を使ってCTを撮るのはやめてほしい」と考えます。しかし、例えば保険診療のルールに「重症の頭部外傷でなければ頭部CT撮影をおこなってはいけない」とすることまでは思い切れないのです。重症と軽症の線引きが明確にできるわけではなく、後で医師や患者から「保険のルールが厳しくなければあのときにCTを撮って迅速に診断がつけられたのに・・・。診断が遅れたのは行政の責任だ」と言われることを避けたいわけです。ですから医師が<念のために>CT撮影が判断したと言われるとそれに従うしかないのです。
医療の世界に<利益のため>などという思惑があるなど言語道断だ、と感じるのが普通の感覚でしょう。私もそう思います。しかし製薬会社は民間企業であり、公的機関ではありません。ほとんどの製薬会社は株式会社であり、市場から株を通して資本を集め、その資本で研究開発をおこない薬を製造します。会社は誰のものか、という議論には様々な意見がありますが、経済学的には株式会社は株主のものです。つまり製薬会社は株主から配当と株価上昇を期待されているのです。
しかし、薬というのは「使わないのが最善」です。我々医師がいかに薬を使わないようにするか、減らしていくかを考えているのと同様、本来は製薬会社につとめる人たちも同じように考えていなければなりません。実際、製薬会社の従業員も、自分自身が患者になったときは、薬の使用は最小限にしたいと考えるはずです。
以前にも述べたことがありますが(注1)、製薬会社というのは他の一般の企業とこの点が異なります。一般の企業、それは自動車でも家電製品でも通信でも不動産でも、食品、アパレル、貴金属でもなんでもいいのですが、これらは生活を豊かにするものです。高性能の自動車や高級な食材が売れるのはそれらを手に入れることにより生活が豊かになるからであり(それが「思い込み」や「幻想」という意見はあるにしても)、消費者も売り手も共に満足するものです。市場社会が発展するのはまさにこの点にあります。
一方、薬というのは、可能なら生活の中に入ってきてほしくないものですし、できることなら見たくもありません。薬なしの生活が最善なのです。高級車に乗って流行の衣装でドレストアップして美食に舌鼓をうつ、のが多くの人にとって憧れになるのとは正反対なわけです。車も衣装も欲しくなく質素な生活に幸せを感じるという人もいるでしょうが、そのような人たちも一流品でなくとも自分の気に入った服を買ったり、美味しいものを求めたりはするはずです。
まともな薬剤師であれば、自分たちのミッションが「薬をたくさん飲んでもらうことではなく最小限にすべきこと」を知っています。しかし、これが会社になるとどうでしょう。複数の不正行為が発覚し業務停止に追い込まれたノバルティス社は、「100Bプロジェクト」と命名された社内目標を掲げていたことが報道されました。100Bとは10億の100倍で1,000億を目指すプロジェクトのことだそうです。
繰り返しになりますが、本来、薬というのは最小限でなければならないはずです。1,000億円の売り上げを目標にするというのはその逆を目指しているということにならないでしょうか。
ちなみにノバルティス社は2015年2月に厚生労働省が業務停止処分にすることを決定したことが報道されています。私はこのニュースを日経新聞で最初に知ったのですが、日経の記事には業務停止処分の期間が記載されていませんでした。私は「これだけの問題を起こしたのだから当分は業務停止が解かれないだろう」と勝手に解釈したのですが、これが間違いだということを医師の掲示板で知りました。朝日新聞と毎日新聞では15日程度の処分という記載があるのです。たった15日の業務停止、同社の社員にとっては2週間の特別休暇になるだけじゃないか!という怒りの声がその掲示板には多数載せられていました。そして改めて日経の記事をみると、意図的に、つまり15日では短すぎるではないかという世論をかわすために、ノバルティス社に気を遣ってあえて期間を書かなかったのではないかと疑いたくなってきます。ちなみに産経新聞にも期間の記載はなく、読売新聞には業務停止の記事すら見当たりませんでした(これらの新聞はすべてオンライン版です)。
念のために付記しておくと、私は世の中の製薬会社が悪の中枢と言っているわけではありません。製薬会社のおかげで命が救われている人が大勢いるわけで我々は製薬会社に感謝しなければなりません。
谷口医院に自社製品の情報提供をしにきてくれるMR(製薬会社の営業のこと、以前はプロパーと呼ばれていました)は、私が考えていることを理解してくれています。過去に二度と顔を見たくないと感じたMRもいますが彼(女)らは、「どんな理由でもいいから薬買ってください」という対応をしてきます。もちろんこんな言葉は直接は使いませんがそこには「薬は患者さんのために」という視点が抜けています。一方、現在谷口医院に定期的に来られるMRの人たちは、私が必要とする情報、つまり患者さんにとって有益な情報を届けてくれます。また、薬局で勤務するまともな薬剤師は、薬を無理に売るようなことはしません。「町の健康相談員」のような存在となり地域で頼りにされている薬剤師も少なくないはずです。
私が最も懸念しているのは製薬会社でもなく薬局でもなく「ネット業者」です。ここに名前は出しませんが、そのサイトでは副作用の注意が充分に必要な薬がごく簡単に買えて翌日には自宅に届けられます。私には、こういったネット業者が購入者の健康のことを第一に考えているとは到底思えず<利益のため>だけにやっているのではないかと考えずにはいられないのです。
一方、医療機関は<利益のため>に診療をしているわけではありません。たしかに、例えば、必要のない手術をおこない患者さんを死亡させ2009年に院長が逮捕された奈良県大和郡山市のY病院などのような特殊な医療機関が存在したのは事実ですし、もしかすると現在でも同じような<利益のため>に患者さんに不要な検査をしたり薬を出したりしている悪徳病院があるかもしれません。
もちろん、ほとんどの医療機関は<利益のため>ではなく、いかに患者さんの負担を減らすかを考えています。しかし、この点が一部の患者さんからは誤解されており、ここから医師・患者間のコミュニケーションに齟齬が生まれます。私が患者さんから言われる言葉で最も疲れるのは、「お金を払うって言っているのに何で検査してくれないの!」というものです。なぜ患者さんからこのような言葉が出るかというと、この人は「検査をしたら医療機関の利益にもなるでしょ」と考えているからであり、こういう患者さんは医療機関も<利益のため>に診療をしていると考えているのです。
次回は、Choosing Wiselyの具体例を当院での実際の症例に基づいて紹介し、前回取り上げた子どものCTを執拗に迫る父親にはどのように理解してもらうか、といったことについて述べたいと思います。
注1:下記コラムを参照ください。
メディカル・エッセイ第135回(2014年4月)「製薬会社のミッションとは」
投稿者 | 記事URL
2015年1月21日 水曜日
第144回(2015年1月) Choosing Wisely(不要な医療をやめる)(前編)
今月(2015年1月)に公開した<院長あいさつ>のなかの「開業9年目に向けて」というコラムのなかで述べましたが、私はこれからの日本の医療には「Choosing Wisely」という考え方が不可欠だと考えています。「Choosing Wisely」とは、直訳すれば「賢く選択する」となりますが、わかりやすく言えば、「適切な医療を選ぶ」、言い換えれば「不要な医療をやめる」ということです。
ここで私が研修医時代に経験したChoosing Wiselyを考える上で興味深い症例を紹介したいと思います。
患者さんは3歳の男の子。自宅のベッドから落ちて頭をうちお父さんに連れられて深夜の救急外来にやってきました。幸運なことに、その日の救急外来の担当医は脳神経外科医でした。医師は充分な時間をかけてその男の子の診察をして、お父さんに「大丈夫だと思います。このまま何もせずに様子をみてください。もしも、意識がぼーっとしたり、吐いたりするようであればあらためて受診してください」と言って診察を終わらせようとしました。
すると、驚くべきことに、その子のお父さんが突然言葉を荒げて怒り出したのです。「思います、では困るんです! この子は頭をうってるんですよ! CTを撮るのがあんたらの仕事でしょ! もしもこの子に何かあったらあんた責任とれるんか! こっちは金払う言うてるんや、医者はサービス業ちゅうもんがわかっとらんのか!・・・」、とこんな感じで次第にけんか腰になってきました。
この症例のように「頭をぶつけたからCTを撮ってほしい」という要望は「以前は」少なくありませんでした。「以前は」と過去形なのは、最近ではその傾向が変わってきているからです。これは患者側が冷静にリスクを判断できるようになったから、というよりも、おそらく東日本大震災の影響でしょう。放射線の有害性がマスコミにより大きく取り上げられるようになり、CTどころか単純X線にすら過剰な恐怖心を持つような人もいます。
しかし、震災前までは「頭をぶつければCT」と考えている人は非常に多く、特にこの症例のように、子どもが頭をぶつけたときの親の間では顕著でした。これはおそらく1999年に起こった「杏林大病院割りばし死事件」が影響を与えていると思われます。これは4歳の男の子が転倒し救急搬送されたものの、割りばしが喉の奥に突き刺さっていたことが見逃され翌日に死亡したという事件です。折れた割りばしは小脳にまで到達しており、これを診察した医師が見抜けなかったのです。このときにCTを撮影していれば発見されたであろうことから、CTを撮影しなかった医師が業務上過失致死などで送検されました。
この事件は最終的に医師の無罪が確定しました。救急外来受診の状況から割りばしの存在を疑うのは困難であり、このような例は世界的にみても極めて稀なものであり、CTの撮影をおこなわなかったことを過失とは認められない、というのが大まかな判決の内容です。
しかし、このような判決を聞いても遺族の立場からすれば納得しづらいでしょうし、もしも我が子に同じことが起こったら・・・、と考えれば、「頭になにかある場合はCTが必要」と考えたくなる気持ちは理解できます。
しかし頭をうったり転倒したりした症例すべてにCT撮影というのは現実的ではありません。このようなことを言うと、「それは(全体の)医療費を抑制するためですか」と言う人がいますがそうではありません。このケースでは、一番の問題は被爆であり(CTの被曝量は単純X線の比ではありません)、次の問題は患者さんが負担する費用の問題です。もっとも、多くの自治体では小児の場合はどのような治療を受けても1回の受診料が500円程度になっていますから「それは問題でない」という人もいるでしょう。しかし成人であれば3割負担で数千円の費用がかかります。
件の症例の続きに戻ります。診察室で大声を張り上げて今にも診察医を殴りかかるくらいの勢いでこのお父さんは引き下がりませんでしたが、医師側からみれば、小さな子どもに無駄な被爆をさせるわけにはいきません。「すべきではない検査はできません」と冷静に説明を繰り返します。結局、これ以上何を言っても無理と判断したそのお父さんは捨てゼリフを吐いて診察室を去って行きました。
私は診察医の後ろでこのやりとりを聞いていたのですが、無駄な被爆と医療費を回避すべきと考えていたその医師の考えが強く伝わってきました。「CTは不要です」と断言するのも勇気がいることなのです。自分の診察に自信がなければ「もし何か見つかればどうしよう・・・」という不安が出てきますし、もっといえば、今回の転倒と関係のない異常所見が見つかることだって可能性としてはあるわけです。患者さんの立場からすれば、「もしもあのときCTを撮っていれば・・・。CTを拒否したあの医者を一生許さない!」となることもあり得るのです。
私はこのエピソードをこれまで何度か(医療者でない)知人に話したことがあるのですが、「これが医師のあるべき姿だ」というと首をかしげる人が少なくありません。彼(女)らは、「要望があるならCT撮ってあげたらいいんじゃないの。異常がなかったらそれでお父さんも満足しただろうし、病院だって儲かるんじゃないの?」、というのです。
医師は「聖職」などというつもりは毛頭ありませんが、医師は他の職業と異なる、としばしば感じるのがこの点です。つまり、市場社会におけるほとんどの仕事は営利を追求することが(それだけではないにしても)第一の目的であり、一方、医療というのは(利益がなければ組織の存続ができないのは事実ですが)営利を追求しない(してはいけない)仕事です。日本医師会の「医の倫理綱領」の第6条には、はっきりと「医師は医業にあたって営利を目的としない」と述べられています。
この点を理解していない人は非常に多いと言わざるを得ません。鋭い指摘をするジャーナリストや知識人でさえも誤解していることがあります。Choosing Wiselyの議論になったときも、「検査や治療を減らせば医療機関が儲からなくなるから日本では普及しないんじゃないの」という意見すらあり驚かされます。
しかし、アメリカの医師も日本の医師もミッションは同じです。アメリカの学会が一丸となってChoosing Wiselyのキャンペーンをできて、我々日本の医師にできないはずはありません。なかなか理解を得られないかもしれませんが、我々医師は利益のことを考えて診療をしているわけではありません。その逆にいかに不要な検査や治療を減らしていくかを考えているのです。これを説明するのに「医師の矜持」にかけて、という言い方ができるかもしれませんが、そんなたいそうな表現を用いなくても、普通に医学部で学び、医師になれば研修期間が終了する頃には「医師の常識」が身についているのです。
身体の具合が悪くて医療機関を受診するのはお金持ちだけではありません。というより裕福でない人の方が多いでしょう。そのような人たちは、治療にどれくらいお金がかかるだろう・・、と不安な気持ちで受診することも少なくありません。すでに具合が悪くて仕事を数日間休んでいたり、場合によってはその症状のせいですでに退職していたりすることもあるのです。そんな人たちに対して、少しでも検査を増やして濃厚な治療をしてお金を稼ごう、などと考えることのできる人間はいません。
それに、治療がうまくいくと、患者さんは心の底から感謝の言葉を話されます。そういう言葉を聞くと、もっとがんばろう、という気持ちになり心が奮い立たされます。そんなときに、どうすればお金が儲かるか、などとはまともな神経をしていれば考えることができないのです。
つまり、医師は高い人格を有しているから自分の利益よりも患者さんの負担を少なくすることを考えるのではなく、仕事を通して困っている人の力になりたいと”自然に”感じ、また感謝の言葉を聞くにつれて”自然に”利他的な考え方になっていくのです。
Choosing Wiselyという考え方が誕生したひとつの理由として、膨大する医療費を抑制しなければならないという国(アメリカ)の意向が反映されているのではないかという意見があります。しかし、Choosing WiselyのPRをしているのはABIM(American Board of Internal Medicine、アメリカ内科学委員会) という医師からなる非政府組織です。つまりChoosing Wiselyは行政主体ではなく医師主体なのです。
広く世論にChoosing Wiselyの本質を理解してもらうことができれば、患者さんの時間とお金の負担が減少し、医師としては思うような診療ができ、コミュニケーションのすれ違いや誤解が減ることが期待できます。おまけに全体の医療費も縮小できますから、患者、医師、行政の3者にとって望ましいことになるはずです。(検査会社、製薬会社、医療機器のメーカーなどは利益が減少することになるでしょうが・・・)
次回は、先に紹介した子どものCTを執拗に迫ったお父さんのような例にはどのような説明をすべきなのかについて検討し、医師・患者のコミュニケーションのすれ違いが生じる理由について言及し、そしてChoosing Wiselyの具体例(注1)を紹介していきたいと思います。
注1:ABIMが作成するChoosing Wiselyの具体例は下記URLですべて閲覧することができます。
http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/
投稿者 | 記事URL
2014年12月20日 土曜日
第143回(2014年12月) STAP細胞”誕生”の理由
私にとって2014年に最も印象深かった言葉は「STAP細胞」です。毎年12月1日に発表される「現代用語の基礎知識」がおこなっている「流行語大賞」に、私は「STAP細胞」が間違いなく選ばれると思っていたのですが、結果はトップ10にも入っていませんでした。
しかし、広告業界のポータルサイトの「AdverTimes(アドバタイムズ)」が選んだ「2014年のワースト謝罪会見」(注1)の第1位に、理化学研究所(以下「理研」)の小保方晴子氏がおこなった釈明会見が選ばれていました。(謝罪はしておらず「謝罪会見」のランキングに選ばれるのはおかしいような気がしますが・・・)
私自身は研究者とは呼べませんし、これからもこのような研究に関与することはありませんが、当初理研(というか小保方氏)が発表していたように、いったん分化した細胞が未分化細胞に戻るということが、酸にさらすといった単純な方法で起こりうるのなら、これは大変なことになると感じ「複雑な思い」を抱きました。
「複雑な思い」というのは、2014年1月にこの発表を聞いたとき、「そんなことが起こるはずがない」と感じたからです。しかし、これは「仮説」ではなく実験で証明されており科学誌『Nature』にすでに掲載されており、理研の優秀な研究者たちのおこなった研究なのです。後から手のひらを返したように小保方氏をバッシングしだした科学者たちも当初はこの業績を絶賛していました。医師のメーリングリストでも称賛を讃えるコメントのオンパレードだったのです。
理研は2014年11月末を期限にSTAP細胞の再現実験をおこない、その結果作製に成功しなかったことを12月19日に発表しました。「ない」ことを理論的に証明することは困難ですが、これで事実上STAP細胞は存在しないとみなされることになります。
STAP細胞については、実に様々な人たちが、それは一般のネットユーザーから科学者までが、いろんな議論をし尽くしていますから、もう話すべきことはないかもしれませんが、なぜSTAP細胞が生まれたのかについて私はひとつ主張しておきたいことがあります。
STAP細胞”誕生”の経緯を報道などから簡単にまとめておくと、まず幹細胞の研究者でもあるハーバード大学教授のチャールズ・バカンティ氏の研究室に小保方氏が留学し、STAP細胞の存在に興味をもち研究を開始しました。帰国後、小保方氏は理研の客員研究員として若山照彦氏の研究室で本格的な研究に取り組みます。その後、理研の研究ユニットリーダーに就任し、(後に自殺することになる)笹井芳樹氏をメンター(上司)として研究を重ねSTAP細胞の作製に”成功”するのです。
この経緯のどこに「問題」があったのでしょうか。STAP細胞などというものは、私も含めて科学や医学を少しでも勉強した者にとってみれば「突拍子もないありえない物」です。ですからこんなもの初めから研究すること自体がおかしい、という声もあるでしょう。しかし、私はこの点はむしろ小保方氏は”素敵”だと思います。誰も考えつかないような突拍子もないものを研究するこの態度と行動は個人的には応援したくなります。
では、実際にはないものを「ある」と狂信的に信じて研究を重ねたことはどうかというと、私はこの点についても小保方氏の行動を非難したくありません。実験というのは、手順をまず決めてそのとおりにしていると”たまたま”世紀の大発見ができたなどというのはほとんどが「嘘」です。ニュートンがリンゴが木から落ちるのをみて万有引力の法則を発見したというのはおそらく後からつくりあげた話です。よしんばそれが事実だったとしても、ニュートンは万有引力の法則があることを初めから確信していたはずです。
野口英世は梅毒の病原体の培養に”成功”したと発表しましたが、その後誰も成功していません。野口は狂犬病の病原体も発見したと発表しましたが、これは後に完全に誤りであることが分かりました。狂犬病の病原体はウイルスであり、野口が寝食を惜しんで覗いていた顕微鏡では見えないのです。野口は金と女性にだらしなく人間的に尊敬されるべき人物ではないかもしれません(注2)。しかし、そのような私生活があり、研究成果を残せなかったのは事実だとしても、それでも科学者として研究に取り組む態度は尊敬に値します。
存在するはずないと(普通の科学者なら)誰もが思うSTAP細胞の研究に小保方氏が寝食を惜しんで(見たわけではありませんが)取り組んだことについては、私は氏に尊敬の念すら感じます。
しかし、あるはずと信じていたSTAP細胞が作製できなかったとすればそのときはどうすべきだったのでしょうか。『Nature』に論文を発表した2014年1月、そして釈明会見をおこなった4月にも、小保方氏はSTAP細胞の存在を信じていたと私は思います。しかし同時に、STAP細胞が”まだ”きちんと証明できていないことも知っていたはずです。
一部の評論家や精神科医は、虚偽の研究成果を堂々と述べる小保方氏にはもともと人格障害があったなどと言っているようですが、私には他に理由があるように思えます。私は氏の精神異常やパーソナリティ障害の有無を論じる立場になく、そのようなことはできませんが(実際に診察したわけでもないのにマスコミの報道だけから推測で病名を公表する精神科医が私には理解できません)、たとえパーソナリティの問題が氏にあったとしても、それ以上に彼女の暴走の原因となった「問題」があります。
その「問題」は早稲田大学にあります。小保方氏は2002年に早稲田大学理工学部応用化学科に入学し、その後大学院に進み2011年には論文が評価され博士の学位を取得しています。しかしこの論文に不正がありました。
2014年7月17日に発表された早稲田大学の調査委員会の報告書によると、「(小保方氏の論文は)著作権侵害行為であり、かつ創作者誤認惹起行為といえる箇所が11カ所もある」とされています。つまり、他人の論文から勝手に拝借した箇所が多数あったことを大学が正式に認めたのです。11箇所と聞いてもどれだけのものかわかりにくいですが、発表によればなんと論文全体の2割にも相当するそうです。論文の2割が他人が書いたものを拝借していたとは・・・、私に言わせればこれは「学問に対する冒涜」以外の何物でもありません。
他の論文からわずかでも拝借するとそれだけで学問に対する冒涜になるのか、という反論があるかもしれません。私自身も、関西学院大学理学部に在籍していた頃、実験のレポートが書けなくて同じ班のメンバーにレポートを見せてもらっていました(注3)。しかし完全な丸写しはしていませんし(自慢になりませんが・・・)、実験のレポートと博士論文では重みが違いすぎます(これは説得力がないかもしれませんが・・・)。
学生時代に同じ班のメンバーにレポートを見せてもらっていた私には小保方氏を非難する資格はないかもしれません。しかし、そんな私も早稲田大学には強く抗議をしたいと思います。私の母校のひとつの関西学院大学はキリスト教に基づいた大学ということもあり、不正には厳しい処罰が下されていました。私がしたような他人にレポートを見せてもらうというくらいではあまり問題にならないでしょうが(それでも「丸写し」すれば即留年でしょう)、論文に一部でも他の文献からコピーしたところがあったり、テストでカンニングをおこなったりすれば、悪ければ退学、よくてもその年の単位すべて取り消し、さらにキャンパス内の教会で牧師さんの前に跪いて懺悔をしなければなりません。
一方、早稲田大学では、小保方氏の博士論文に対し大学側が正式に不正を認めているのにもかかわらず、「博士号の取り消しには当たらず猶予期間中に論文が再提出されれば学位を維持する」としたのです。まともに考えれば不正が発覚した時点で即博士号取り消しにすべきです。
早稲田大学グローバルエデュケーションセンターのウェブサイト(注4)をみてみると、「レポートにおける剽窃行為について」というタイトルで不正行為の処分についての記述があり、「不正行為が発覚した場合(中略)、その時点で履修しているすべての科目の無効、停学を含む厳しい処罰が下されます」とされています。なぜ小保方氏には再提出の猶予が認められるのでしょうか。
さらに私が不思議なのは、早稲田の卒業生や在学生がなぜ大学側のこの対応に黙っているのか、ということです。論文に不正がみつかっても再提出すればお咎めなし、でOKなら、不正が見つからなければやってもいいんだ、と考える学生が出てくるに違いありません。卒業生は周囲から「お前も不正で卒業したんじゃないのか」と思われるかもしれません。
このような杜撰な環境の大学で研究を続けていれば、「しょせん学問なんていい加減なもの、論文の作成なんてどうにでもなるんだ」、という意識が芽生えても不思議ではありません。「『Nature』に提出した論文が少々いい加減でも咎められることはないだろう。STAP細胞は確実に存在するんだから、そのうちに追随者がもっときちんとしたデータをつけてSTAP細胞の存在を確固としたものにしてくれるに違いない。みなさんがんばってね!」と小保方氏は考えていたのではないでしょうか。
STAP細胞が”生まれた”理由のひとつは早稲田大学の杜撰な教育体制。それが私の考えです。
注1:下記URLを参照ください。
http://www.advertimes.com/20141204/article176736/
注2:野口英世のこういったエピソードについては下記コラムで触れています。
マンスリーレポート2014年6月号「渡辺淳一氏の2つの名作」
注3:レポートと同じ班のメンバーに見せてもらっていたことは下記コラムで紹介したことがあります。
マンスリーレポート2013年10月号「安易に理系を選択することなかれ(前編)」
注4:下記URLを参照ください。
http://www.waseda.jp/gec/about/info/academic/info_report/
投稿者 | 記事URL
2014年11月21日 金曜日
第142回(2014年11月) 速く歩いてゆっくり食べる(後編)
前回は、忙しくて運動の時間がとれない人は日頃から速歩きを心がけましょう、ということを述べましたが、早速何人かの患者さんから「始めました」という声を聞きました。
なかには「活動量計を買いました」という人もいました。活動量計とは1日の活動量(消費キロカロリー)が計測できる小さな器械で、最近急速に市場に登場してきているようです。ある患者さんはキーホルダーに付けてズボンのベルト通しにかけていました。胸ポケットに入れている患者さんもいましたし、腕時計と一体化したものを持っている人もいれば、ブレスレット型のものを付けている人もいました。
また、ある患者さんからは「先生はMETs(メッツ)のことを言ってるんですよね」と指摘されました。METsというのは身体活動を評価するための指標で、スポーツ医学や循環器科の領域でよく使われるのですが、最近では随分と世間に浸透してきているようです。この患者さんの言うとおり、運動は単に時間だけで評価するのではなく強度も考慮しなければなりません。そしてこれが私が前回述べた「ゆっくりのウォーキングでは効率が悪い」ということでもあります。
さて今回は食事について述べていきたいと思います。メディカルエッセイ第129回(2013年10月)「危険な「座りっぱなし」」で提唱した、健康を増進させる「10個の習慣」のひとつにEating(食事)があります(注1)。これは、食べる内容と量に注意しましょう、というのが一番言いたいことですが、「食べる早さ」にも注目しましょう、というのが今回のテーマです。
このサイトで「フレンチ・パラドックス」について何度か取り上げたことがあります(注2)。フレンチ・パラドックスとは、フランス人はあぶらっこい肉料理を好んで食べて、おまけに喫煙率も高いのに、心筋梗塞など心血管系疾患の罹患率が低いことを表した言葉です。この原因として「赤ワイン」が注目されたことがありました。
現在では「フレンチ・パラドックス」は否定的な意見の方が多いのですが、この言葉はまだ生きているように思えます。疫学調査というのは統計の取り方によって随分変わりますし、研究者の恣意性が入る可能性は否定できません。また心筋梗塞で死亡した例が統計から漏れることはないでしょうが、軽度の狭心症レベルを心血管系疾患に加えるかどうかというのは議論が分かれるところでしょう。つまり、統計の取り方によって、フレンチ・パラドックスが正しくなることも正しくなくなることもありえるということです。
虚血性心疾患や脳血管障害を他国の基準と同様に把握することは困難ですが、身長と体重なら客観的に評価することが可能です。そこで世界の肥満者の割合を調べてみると興味深い結果がでてきます。ビジネス誌『Forbes』のウェブサイト(注3)に世界各国の肥満者の割合の表が掲載されています。このデータはBMI(体重(kg)÷身長(m)の2乗)が25以上の人の割合を示しています。例えばアメリカは世界第9位で国民の74.1%がBMI25以上であることを示しています。イギリスは第28位で63.8%、オーストラリアは21位で67.4%です。ちなみに日本は第163位で22.6%です。
さてフランスですが、この表では第128位で40.1%です。フレンチ・パラドックスを否定する人たちも、この数字を見せられるとフランスでは肥満者の割合が相対的に少ないことを認めないわけにはいきません。そしてフランス料理は高脂肪のあぶらっこい料理がメインであり、朝からクロワッサンとカフェオレという高脂肪・高炭水化物の食事を摂るのが日常なのです。
つまり、フレンチ・パラドックスが正しいかどうかは別にして、フランス人は脂っこいものを好んで食べるのにも関わらず肥満者が少ない、というのは客観的な事実なのです。
これはなぜなのでしょうか。結論を言えば「ゆっくる食べるから」が答えではないかと私は考えています。私がフランス人と一緒に食事をしたのは会社員時代の経験を入れても数える程しかありませんが、彼(女)らは話をしながらゆっくりと食べる、という印象があります。
これを映画のシーンで考えてみましょう。アメリカの映画ではオフィス内でハンバーガーを頬張ったり、紙の容器に入った中華料理らしきものをスプーンで食べたりしながら仕事をしている場面がしばしばありますし、立ちながらホットドッグを食べているシーンなどもよくあります。『オーシャンズ11』を見たことがある人はブラッド・ピットが食事をするシーンを思い出してください。この映画ではブラッド・ピットが何かを食べているシーンが繰り返し出てきますがいつも慌てて何かをかきこんでいる感じです。
一方、フランス映画ではどうでしょうか。家でゆっくりとディナーを楽しんだり、カフェで長時間くつろいだりするシーンはよくありますが、オフィスで慌てて何かを食べているシーンは思いつきません。オードリー・ヘップバーンの名作『シャレード』では、ニセ刑事がオードリー・ヘップバーンをオフィスに招いてサンドイッチを食べるシーンがありますが、これも緊迫した状況だというのにワインを飲みながら食事をしています。
映画のシーンで医学を論じるのはあまりにも非科学的ですから、ここからは最近の研究を紹介したいと思います。
1つめは医学誌『BMJ Open』2014年9月5日号(オンライン版)に掲載された論文で日本の研究です(注4)。2011年に日本国内の健康管理センターの健康診断を受け、心筋梗塞など冠動脈心疾患や脳卒中にかかったことがない56,865人(男性41,820人、女性15,045人)について、食べる速度とメタボリックシンドロームの関係について分析したところ、食べる速度が早いとメタボリックシンドロームになりやすいことが判ったそうです。
2つめも日本の研究で、医学誌『Obesity』2014年7月10日号(オンライン版)に掲載されています(注5)。この研究では岡山大学の学生が対象とされています。対象者は元々肥満がなかった(BMI25未満)学生1,314人で、入学から3年間の追跡調査がおこなわれています。その結果、元々肥満でなかった学生が早食いを続けるうちに肥満していくことが判ったそうです。「早食いだ」と答えた人は、そうでない人より4.4倍も肥満しやすいという結果となり、性別では男性は女性の2.8倍肥満しやすいことがわかったそうです。
幼少児期の家族との団らんが肥満を予防する、という研究もあります。医学誌『Pediatrics』2014年10月13日号(オンライン版)に論文が掲載されています(注6)。研究によりますと、暖かさ(warmth)、家族での団らん(group enjoyment)、親の積極的な関わり(parental positive reinforcement)などが小児肥満の予防になるそうです。
この研究では、合計120の家庭の食事風景をiPADで録画してもらい、食事に費やす時間、食事の内容、家族同士の交流などが分析されています。その結果、肥満児の家庭では、食卓に明るい雰囲気が少なく、秩序がない傾向だったそうです。また標準体重児の食事時間が平均18.2分なのに対し、肥満児では13.5分と短くなっていたようです。
なぜ早食いは肥満につながるのでしょうか。いろんな理由があるでしょうが、最も大きいのはいわゆる「満腹中枢」の作動開始時間でしょう。よく言われるように、食事を開始してしばらくすると、脳が「これくらいにしておきなさい」という指令を出しますがこの指令塔が満腹中枢というわけです。満腹中枢は、胃を支配している神経や血糖値からの情報を総合的に判断し、食事開始後およそ20~30分後に指令を出すと言われています。
つまり、満腹中枢が指令を出すまでの間は食欲はそのまま続いているわけで、20~30分の間に大量に食べることができてしまうのです。こう考えるとフランス料理というのは実に理にかなっています。ワインと会話を楽しみながら「前菜」をゆっくり食べると、食べ終わる頃には満腹中枢が働き始めるのです。メインディッシュの高脂肪の肉や魚は食べ過ぎることなく適量に抑えられ、食後のデザートを食べても肥満につながりにくい、というわけです。
とはいえ、何かと慌ただしい日本人の多くはフランスの家庭のようにゆっくりと前菜を楽しむ余裕はないでしょう。しかし、「ゆっくり食べる」ことが肥満を抑制し健康増進につながるということは覚えておくべきでしょう。
注1:このコラムは下記を参照ください
メディカルエッセイ第129回(2013年10月)「危険な「座りっぱなし」」
注2:例えば下記医療ニュースを参照ください。
医療ニュース2014年7月7日「「赤ワインが健康に良い」は、もはや幻想・・・」
注3:『Forbes』のこのサイトは下記を参照ください。
http://www.forbes.com/2007/02/07/worlds-fattest-countries-forbeslife-cx_ls_0208worldfat.html
注4:この論文のタイトルは「Self-reported eating rate and metabolic syndrome in Japanese people: cross-sectional study」で、下記URIで概要を読むことができます。
http://bmjopen.bmj.com/content/4/9/e005241.abstract?sid=f10f5de6-55c4-4fd1-b10c-a5408a3925da
注5:この論文のタイトルは「Relationships between eating quickly and weight gain in Japanese university students: A longitudinal study」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.20842/abstract;jsessionid=CA99332C6C7E60AFB6700A3CF19DC102.f03t04
注6:この論文のタイトルは「Childhood Obesity and Interpersonal Dynamics During Family Meals」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://pediatrics.aappublications.org/content/134/5/923.abstract?sid=652cabe4-27eb-4c4d-b1f4-1b617ef23df0
投稿者 | 記事URL
2014年10月21日 火曜日
第141回(2014年10月) 速く歩いてゆっくり食べる(前編)
歩くことが健康増進につながるのは間違いないのですが、日常の診療では、よく歩いているのにもかかわらず生活習慣病が改善しない、という人がいるのも事実です。また「1日1万歩」という言葉が一人歩きしていますが、例えば20代の健康な人が1日1万歩をゆっくりと歩いても健康増進にはほとんど意味がないでしょうし、その逆に80代の高齢者であれば早歩きで4千歩も歩けば充分健康に寄与します。
日頃の患者さんをみていても、「営業職で歩くことが多いから大丈夫です」とか「会社から帰宅するとき散歩をしてから電車に乗るようにしています」という人でも生活習慣病が改善せず悪化していくような人もいます。その逆に、「運動の時間はとれず内勤なのでほとんど歩いていません」という人でも日常の中のちょっとした工夫でダイエットに成功し、生活習慣病が改善する人もいます。
私は医師として生活習慣病を抱える患者さんを多くみてきましたが、運動をしていても(食事の量が増えているわけでもないのに)生活習慣病が改善しない人がいること、また、その逆にあまり時間がとれなくて最低限のことしかしていないという人でも改善することも多いことが数年前から気になっていました。
当初私は、(患者さんには失礼ですが)患者さんが本当のことを言っていないのではないかと考えていました。つまり、「営業職で歩く」といってもわずかな距離を大袈裟に言っているのではないかと考え、その逆の「さほど運動できていない」と言って効果がでている人は謙遜して控えめに話しているのではないか、と思っていたのです。
しかし、数多くの患者さんを診ているなかで、どうもそういうわけでもなさそうだ、ということに気付くようになりました。ここで私が太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)で診ている2人の患者さんを紹介したいと思います。(といっても患者さんの情報を公開するわけにはいきませんので、本人が特定できないようにアレンジを加えています)
ひとりめの患者さんは40代の男性(Aさん)で、仕事は通信機器の営業です。軽度の高血圧と高脂血症、さらに肥満があり、3~4ヶ月に一度私の元を受診しています。運動は得意でもないけれど苦手というわけでもないそうです。営業には電車を使い、歩く距離は少なくないと言います。また、仕事が早く終われば一駅分歩くようにしていて、さらに週末は自転車に乗ることを心がけているそうです。
できるだけ薬は使わないというのが生活習慣病の治療の基本ですし、またAさんもそのように考えているために、生活習慣の改善、具体的には食事の量と内容の見直し、そして運動をおこなうよう私は助言しています。診察を開始して2年近くがたちますが、残念ながら中性脂肪の値も血圧の数値も良くなるどころか少しずつ悪化してきています。このままでは薬を開始しなければならなくなります。
ふたりめの患者さんは50代の公務員の女性(Bさん)です。BさんもAさんと同じように軽度のメタボリック・シンドロームがあり、谷口医院受診のきっかけは、健診で異常を指摘されて、というものでした。BさんはAさんと異なり、運動は苦手とはっきりと言います。そして、主婦でもあるために運動時間をとることはできない、ウォーキングは定年退職後におこなうことを考えているけれども今は無理、ということでした。
そこで私は、今の状態でもできることをアドバイスしました。職場が3階だというので、まず職場では階段を使うこと、駅でも可能な限り階段を使うことをすすめました。電車では座らずにつり革を持って可能な範囲でつま先だちを繰り返す運動をおこなってもらうようにしました。(これを「カーフ・レイズ」と呼びます。本格的なカーフ・レイズはバーベルを持っておこないますが、自体重だけでも充分な運動になります) そして速歩きを心がけるように助言しました。結果は、これを3ヶ月おこなっただけで2kgの減量と、肝機能、中性脂肪の値が改善し、血圧も血糖値も下がったのです。(ちなみに、自宅でダンベルを用いた筋トレもすすめたのですが、これはやってもらえませんでした)
筋肉量を維持するには筋肉にある程度の負荷をかける必要がありますし、丈夫な骨を維持して骨粗鬆症を予防するのにもある程度の負荷が不可欠です。ならば筋トレをすればいいではないか、となるわけですが、先に紹介したBさんのように、理屈では分かっていても実際には・・・、という人は少なくありません。ジョギングは、特に下半身の筋肉量維持や股関節の骨折予防、また膝関節症の予防にもなるのですが、継続しておこなうのはそれなりに大変で、運動が苦手という人には相当ハードルが高いといえます(Bさんもそうでした)
ではどうすればいいのか、ですが、私はウォーキングをすすめています。ただしどのようなウォーキングでもいいというわけではありません。私は直接Aさんが歩いているところを見たことがありませんが、おそらくAさんの歩く速度では遅すぎるのです。つまり、一般的な歩行速度では、あまり意味がないということです。高齢者ならまだしも40代で普通の速度(おそらく時速はせいぜい5km/hr程度でしょう)であればあまり生活習慣病の改善にはつながらないのです。
Aさんは自転車にも乗っていると言っていましたが、市内で自転車に乗ってもあまり健康増進には寄与しません。ウォーキングにしてもサイクリングにしても少し心拍数が上昇するくらいにもっていく必要があります。しかし、心拍数が上がるほど自転車をこぐとスピードが出過ぎて危険です。ウォーキングであればこのような危険性はありませんし、少し心拍数が上昇するくらいの速度を意識するようにすれば大変有効な運動になります。
Bさんが実践しているように「階段を使う」というのも大変優れた方法です。谷口医院の何人かの患者さんは、駅では原則として階段を使うというのをルールにしています。実際にやってみると分かりますが、日頃運動をしていない人がエスカレーターを使わないというのはけっこうしんどいものです。しかし、慣れてくると階段の利用がそれほど苦痛でなくなってきます。
ウォーキングは速く歩いてこそ意味がある、というのは私ひとりが主張していることではなく科学的に実証した疫学データもあります。日本で最も有名なのは、東京都健康長寿医療センター研究所の青柳幸利医師がおこなった青柳研究(中之条研究とも呼ばれています)です。この研究は、群馬県中之条町の65歳以上の高齢者約5,000人を対象として13年間の追跡調査をおこない、1日の歩数や運動強度と健康の関係を調べたものです。その結果「1日8,000歩、20分の速歩き」が健康の鍵という結論が導かれています(注1)。
海外でも歩く速さと生活習慣病の関係の研究はときどき報告されており、例えば医学誌『Journal of the American Heart Association』2010年4月6日号に掲載された論文では、歩くのが速い女性は脳卒中を起こしにくい、ということが述べられています(注2)。
また、最近では「運動認知リスク症候群」(Motoric cognitive risk syndrome、MCRと略されます)という疾患の概念が確立されてきています。これは、遅い歩行速度と軽度の認知異常がある状態のことをいい、認知症の前段階と言われています。ここで重要なのは、「軽度の認知異常」は本人にも家族にも分かりにくいけれども、「遅い歩行速度」なら気付きやすい(気付かれやすい)ということです。早い段階で認知症のリスクが評価されると、適切なタイミングで薬を開始することが可能になります。
私は、メディカルエッセイ第129回(2013年10月)「危険な「座りっぱなし」」で健康を増進させる「10個の習慣」を提唱しました(注3)。「10個の習慣」の1つがExercise(運動)であり、今回はそのひとつのExerciseについて述べました。まとめると、次のようになります。
・本格的な運動のハードルが高い人にはウォーキングがおすすめ
・ウォーキングのためのまとまった時間がとれないという人は日頃から速歩きをこころがける
・エスカレーターやエレベーターは極力避けて階段を使う
・漠然とゆっくり歩いて歩数を稼いでも健康増進には寄与しない
・日常生活で筋トレもできる。電車の中でのカーフ・レイズはそのひとつ
・年齢に応じたトレーニングを考慮する
次回は「10個の習慣」のひとつであるEating(食事)について、最近の研究結果を踏まえて効果的な食事について述べていきたいと思います。
注1:この研究は下記URLで詳しく知ることができます。
http://www.yakult.co.jp/healthist/221/img/pdf/p20_23.pdf
また、青柳医師の著書『病気の9割は「運動」が原因』(あさ出版)でも詳しく知ることができます。このタイトルは一見すると運動を否定したもののようにとれますが、実際には適度な運動が推薦されています。おそらく出版社や編集者がインパクトのあるタイトルを求めたためにこのような誤解を招くものになったのだと思います。
注2:詳しくは、下記医療ニュースを参照ください。
2010年4月14日「歩くのが速い女性は脳卒中を起こしにくい」
注3:下記コラムを参照ください
メディカルエッセイ第129回(2013年10月)「危険な「座りっぱなし」」
投稿者 | 記事URL
2014年9月20日 土曜日
第140回(2014年9月) 頑張れマクドナルド!
私のようにクリニックを開業している医師は法的には公務員ではありませんし、クリニック自体も法的には公的機関ではありません。しかし、保険診療中心のクリニックであればクリニック自体は”公的な”機関と言えるでしょうし、医師というのは”公的な”存在、もっと言えば「全体の奉仕者」あるいは「公僕」とみなされるべきと私は考えています。
公僕として存在すべき医師は、日本医師会の「医の倫理要項」第6条にもあるように、営利を求めてはいけませんし、特定の団体に便宜を図るようなことをおこなってもいけません。特定の製薬会社の薬品を偏って処方してはいけませんし、特定のサプリメントや健康食品、化粧品などをすすめることもできません。マスコミからの問い合わせや取材依頼はしばしば来ますが、「特定の製品や治療法に肩入れするような取材は受けない」というのが太融寺町谷口医院のポリシーです。
かつて、このサイトの『マンスリーレポート』で「この夏の暑さと塩と味の素」(2013年8月号)というタイトルで「味の素」を絶賛したことがありますが、これは味の素が塩分を制限するのに有効であり、かつ競合品が日本でもアジアでも(私の知る限り)存在しないからです。
今回はこのように私が決めている「特定の製品を肩入れしない」というルールから逸脱するかもしれませんが、あえてマクドナルドについて取り上げたいと思います。
2014年8月31日の日経新聞に掲載された「マクドナルド負の連鎖」というタイトルの記事は同社の停滞ぶりを多角的に伝えています。中国の鶏肉の「期限切れ事件」や「豆腐しんじょナゲット」が8割以上の店舗で過剰請求されていた事件などに触れ、既存店売上高が急落し、業績の予想すらできない窮状に陥っていることを報じています。
この日経新聞の記事は法的、あるいは経済的・経営的な観点から論じられており、また日経以外のマスコミのマクドナルドの報道をみてみても、数年前まで「原田マジック」などと持ち上げられていた原田前社長の経営方法は実はフランチャイズの売却益が出ていただけではないのか、とか、現在のサラ・カサノバ社長兼CEOでは再建は無理ではないか、とか、そういった内容のものが目立ちます。
今回は、医学的な観点から(と呼べるほどのものではありませんが)、私は日頃接している患者さんにマクドナルドについてどのように話しているか、そしてマクドナルドがこれからどのように社会貢献できるのかについて意見を述べてみたいと思います。
その前に、私自身にとってマクドナルドとはどのような存在なのか、なぜ、他のバーガーショップではなくマクドナルドが気になるのか、について話したいと思います。
私がファストフード店でハンバーガーを初めて食べたのは小学校5年生のとき、1979年でした。大阪の近鉄上本町にあるマクドナルドで食べたメニューは、普通のハンバーガーとフライドポテトS、そしてマックシェイクのセットです。このときのことを私は今でもはっきりと覚えています。
そもそもハンバーグなどというものは、当時の私の家にとっては月に一度食卓に上がるかどうかの贅沢品でした。それをパンにはさんで手で食べるというのが私には衝撃的だったのです。最初の一口を食べたときのあの美味しさは筆舌に尽くしがたいとしか言いようがありません。私にとってはピクルスというものも初めての経験で世の中にこんなに美味しいキュウリがあるのかと驚きました。じゃがいもと言えば、てんぷらにするか味噌汁にいれるかくらいしか知らなかった私はマックフライポテトにも感動しました。マックシェイクにいたっては、じっくりと味わって食べなければならない貴重なアイスクリームをストローで飲んでしまっていいのか、こんな贅沢は許されるのか、と罪悪感を覚えたほどです。
物心がついたときからマクドナルドは身近にある、という人にはこういった感覚は分らないでしょうし、私のことを大袈裟と思うでしょう。しかし、当時の私たちにはマクドナルドというのは頭をハンマーで殴られるほどのカルチャーショックであり、私の友達などは「妹にも食べさせてあげたい」と言って、ハンバーガーをお土産に持って帰っていたほどです。大阪から当時の私たちの地元(三重県伊賀市)は2時間くらいはかかりますから、家に着く頃にはハンバーガーは冷たくなっています。それでも貴重なお土産になったのです。(ちなみに三重県伊賀市(当時は上野市)にマクドナルドができたのは私が高校を卒業してからです。ファストフード店がない田舎では、学校が終わってから友達とダラダラする場所は友達の家かゲームセンターくらいでした)
大学生になってからの私はマクドナルドに入り浸りでした。多いときは週に5回は利用していました。朝マックを食べて夕食もマクドナルドで、という日もありましたし、夜中の店舗のメンテナンスのアルバイトをしていた当時の友人から廃棄処分にするハンバーガーを分けてもらってもいました。(このようなことは今の時代に発覚すれば大変なことになるでしょうが1980年代当時はあまり問題視されていなかったと思います)
念のために言っておくと、私はマクドナルドを盲目的に崇拝しているわけではありませんし、他のバーガーショップよりマクドナルドが優れていると言っているわけでもありません。私が沖縄を訪れるときはマクドナルドよりもむしろ「A&W」をよく利用しますし、大阪にいるときも他のバーガーショップにもよく行きます。
それでも私にとってのマクドナルドというのは、初めて食べたときの衝撃が今でも脳裏に焼き付いていますし、学生の頃(関西学院大学時代)に最も頻繁に利用した食べ物屋ですから、いくらかの思い入れがあるのは事実です。新聞の見出しに「マクドナルド」という文字があれば必ず目を通しますし、これからも少なくとも月に一度くらいは食べに行くつもりです。
さて、私のマクドナルド回想記はこれくらいにして、少しは医学的な観点から述べてみたいと思います。同社には申し訳ないですが、私は患者さんに食事指導をするときに「マクドナルドは利用回数を減らしましょう」と話すことが増えてきています。ファストフードが健康によくないという研究が増えてきていますし(注1)、研究を待たなくても生活習慣病や肥満を気にしている人がマクドナルドのメニューが良くないのは自明です。
他のバーガーショップに比べてもマクドナルドが良くないのは「マックフライポテトM」の量が多すぎる、ということです。これにハンバーガーのパンを食べるわけですから、カロリー過剰摂取になるだけでなく炭水化物の過剰摂取も明らかです。特に糖質制限を考えている人などからすれば、マクドナルドのポテトを含んだセットメニューは絶対NGと考えるべきでしょう。ならばSサイズのポテトを選べばいいではないか、となりますが、ほとんどのハンバーガーのセットにつくポテトはだいたいMサイズになっています。ポテトの代わりにサラダも選べますが、サラダは1種類だけであり、ポテトMに比べると魅力に乏しい気が(私は)します。
余計なお世話だ、と思われるでしょうが、これからのマクドナルドに求められるのは「健康になるためのファストフード」と私は考えています。もっと言えば「健康のためにマクドナルドへ!」というキャッチコピーをつけるくらいになってほしいのです。現在は輸送技術が随分と発達しており、新鮮な野菜や果物を産地直送で届けるサービスなども普及してきています。もしもマクドナルドに行けば新鮮な野菜や果物がふんだんに食べることができて健康になれる、となればどうでしょう。ハンバーガーはカロリーと炭水化物の量を考慮したものとして、セットメニューのポテトを今のSサイズの半分くらいにし、新鮮な野菜や果物を加えられないでしょうか。
さらにウェブサイトではマクドナルドを利用して健康になる食事療法を紹介し、糖質制限や塩分制限をおこなっている人のためのメニューも紹介するのです。健康教室を開いてもおもしろいでしょう。はっきり言えば、現在のマクドナルドは「ジャンクフードの代表」というイメージがあります。これを根底から覆して「健康食の代表」にするのです・・・。
************
このコラムの下書きを書き終えた日、私はたまたま大阪駅近くのマクドナルドに行く機会がありました。よく訓練された従業員がてきぱきと顧客を案内し丁寧な対応をしてくれるおかげで私も含めてみんなが満足している様子でした。憧れの「ビッグマック」(学生の頃は手が出ない高級品でした)を食べた私はその美味しさに満足し店を後にしました。店内は満員でしたが、次から次へと新しいお客さんが押し寄せ長い行列をつくっていました。
どうやら私がマクドナルドの先行きを心配するのは「余計なお世話」だったようです。ですが、1人のマクドナルドファンとして、マクドナルドが「健康食の代表」と呼ばれる日がいつか来ることを願っています・・・。
注1:例えば、週2回のファストフード店の利用で、糖尿病発症リスク、心筋梗塞による死亡のリスクが、それぞれ27%、56%上昇するという研究があります。この論文のタイトルは「Western-Style Fast Food Intake and Cardiometabolic Risk in an Eastern Country」で、下記のURLで全文を読むことができます。
http://circ.ahajournals.org/content/126/2/182.full?sid=309d67ec-0597-48b8-8be8-686391b53d96
参考:
医療ニュース2013年6月7日「近所にファストフード店が多いと肥満リスク増大」
メディカルエッセイ第126回(2013年7月)「我々はベジタリアンの道を進むべきか」
メディカルエッセイ第114回(2012年7月)「糖質制限食の行方」
投稿者 | 記事URL
2014年8月21日 木曜日
139 難病を患うということ 8/21
すでにお知らせしているように、私は2014年8月1日から自分自身の変形性頚椎症の手術のために太融寺町谷口医院を長期間休診とさせていただきました。しばらくの間は静養とリハビリが必要であったために、術後すぐに退院というわけにはいきませんでした。
変形性頚椎症についての説明はマンスリーレポート2014年7月号及び8月号である程度おこないましたので、ここでは繰り返しませんが、私が最も困っていたのが左上肢に力が入らないということでした。
手術を受けると痛みからはすぐに開放されることはあっても筋力低下や筋萎縮はすぐには治らずに回復するまでに何ヶ月も何年もかかることもあるし、場合によっては回復しないこともある、ということは知っていましたし、手術を受ける前にも聞いていたのですが、それでも、「圧迫されている神経が開放されるのだからすぐに神経が機能を取り戻して元のように左腕に力を入れることができるのではないか」という、今思えば何の根拠もない夢を見ていたのは事実です。
実際のところは、私の甘い期待は裏切られ、手術後2週間以上経過した今も、手術を受ける前とほとんど症状は変わっていません。(2014年4月には茶碗も歯ブラシも聴診器も持てないほど悪化していましたが、6月頃からわずかではありますが回復しており、茶碗の保持や聴診器の使用も短時間ならおこなえるようになっていました。術前と術後で症状はほぼ変わりありません)
症状の劇的な回復を夢みていた私は現実を知らされました。「現実はそれほど甘くないか、それならば長期的な観点から考えていこう」、と冷静に考えなければいけないのは今から思えばわかるのですが、術後数日が経過した頃の私は、まともな思考回路が形成されておらず、なんと、「手術をしても腕に力が入らないのは原因が別にあるに違いない」と、まったく非合理的なことを考え出したのです。
しかも、私の悲観的なこの考えは負のスパイラルに堕ちていきました。まず気になりだしたのが私の症状についてです。典型的な変形性頚椎症の症状は痛みとしびれがまずあり、それが長期間持続すると筋力低下や筋萎縮がおこります。しかし、私の場合は痛みやしびれはそれほどたいしたことはなく、最も辛い症状は筋力低下です。筋力低下が全面的に出てくる疾患と言えば・・・。それは神経内科的ないくつかの病気、なかでもALS(筋萎縮性側索硬化症)ではないのか、と疑いだしたのです。
いったんそう考えると私の思考の「負のスパイラル」はますます深みにはまっていきました。そういえば、左上腕の筋肉がピクッ、ピクッと無意識的に震えることが過去数ヶ月に何度かあったことを思い出しました。これは「筋線維束攣縮」と呼ばれる現象で、ALSを含めた神経内科的疾患でしばしば観察され、逆に変形性頚椎症ではあまり見られないものです。
ALSは比較的早く進行し、最初は片側の上肢の筋力低下、その次は反対側の上肢の筋力低下、さらに下肢にも症状が生じ、飲み込んだり話したりするのが困難になってきます。しかしこれは典型例であり、ALSの非典型例では、ゆっくりと経過が進行し、しばらくの間は片側の上肢のみに症状が起こることもあります。実際、ALSなのにもかかわらず最初は私の疾患、つまり変形性頚椎症と誤診されることもあるという話を思い出しました。
それにまったく頚椎症を示唆する所見がないのにもかかわらず、頚椎X線や頚椎MRIを撮影してみると頚椎が変形していることはよくあります。変形性脊椎症というのは軽症のものも含めればかなりの人が罹患していると言えますから、ALSと変形性頚椎症が合併しているということも珍しくはないわけです。
こういったことまで考え出すと、私の「負のスパイラル」はますます加速され、いつのまにか「ALSに違いない。寿命はもってもせいぜい5年。その間に何をしておくべきか・・・」といったことまで考え出したのです。
これは冷静になって考えれば極端な思考であるのは自明なのですが、しかしだからといって理論的に私がALSでないということを100%証明することもできません。それに、筋力低下をきたす難治性の疾患はALSだけではありません。同じく難病である多発性硬化症という疾患も筋力低下が最初に現れることがありますし、パーキンソン病だってそうです。そのようなことを考えているときに、俳優のロビン・ウイリアムスがパーキンソン病に罹患したことからうつ病を発症し自殺した(注1)、というニュースを目にしました。私の「負のスパイラル」はさらに加速されていきました。
ここまでくると、私の精神状態はまともではなく「うつ状態」と言ってもおかしくはありません。食事は摂っていましたし、自らに課した朝と夕方のリハビリはおこなっていたのですが、心の中は厚くて黒い雲に覆われているようなイメージです。
いったい私はこれからどうすればいいのか、クリニックの患者さんにはどのように話すべきか、GINAが支援しているタイのエイズ孤児に対してはこれからどのようにすればいいのか・・・。そのようなことを四六時中考えるようになっていました。真っ暗な闇の中で光の方向が分からずにもがき苦しんでいる感覚です・・・。
そんなとき、入院中の私を叱咤激励してくれた人たちがいました。それは、私が過去に診た患者さんたちです。といっても、実際に患者さんが私を見舞いに来てくれたというわけではありません。ある日の昼下がり、病室のベッドで夢なのか回想なのかよく分からないようなまどろみのなか、過去の患者さんたちが私の頭の中に登場しだしたのです。
今も鮮明に記憶に残っているのは、私が研修医のときに担当させてもらっていた脊髄損傷の患者さんたちです。私が研修を受けていた病院は脊髄損傷の患者さんを積極的に受け入れており、当時形成外科で研修を受けていた私は褥瘡(床ずれ)の診察で、毎日のように病室を訪れ話を聞いていました。彼(女)らは脊髄が完全にやられていますから、全員が車椅子の生活を強いられており、それは奇跡的な治療法がいきなり登場しない限りは治癒することはありません。そんな彼(女)たちが、「自分たちのことを忘れないで!」と私に訴えるのです。
夢か回想かよくわからないそのまどろみのなかで、過去に私が診たALSの患者さんもでてきました。その患者さんは車椅子に移動するのも困難で会話もできずほとんど寝たきりです。さらに、私がタイで診てきたエイズの患者さんたちもやってきました。「あたしたちのこと忘れたの?」すでに他界している彼(女)らは私にそう訴えかけるのです。GINAが支援しているエイズ孤児たちも無言のまま私を見つめています。
太融寺町谷口医院の患者さんたちも次々に私の頭のなかに登場します。私がガンの告知やHIVの告知をおこなった人たちもいれば、命に関わる病気ではないものの長期間の罹病で相当辛い思いをしているような人もいます。
いったい私はどうすればいいのか・・・。まどろみが消え完全に意識が覚醒し、あらためて過去そして現在の患者さんたちに思いを巡らせていたときに突然ある人の言葉を思い出しました。
それはある日本人のクリスチャンの女性の言葉です。私が変形性頚椎症で簡単でない手術を受けることを伝えたとき、その女性は「あなたにはやり残していることがあるんだから手術は必ずうまくいきます」と言ったのです。なんでも、キリスト教的にはそのような考え方をするそうなのです。
私はキリスト教徒ではありませんが、それを聞いたときに「なるほど」と感じました。そしてこの度、手術後症状が回復せずにうつ状態となり、これまでに診た患者さんが私の心に「しっかりしろ」と訴えかけてきたときに、再びこの言葉が私の頭の中を駆け巡ったのです。
脊髄損傷もALSもパーキンソン病も、ガンもHIVも、あるいは寿命は縮まらなくても生活に不自由がでる疾患も、それらを患った人たちは日々を生きるということに頑張っているのです。そして私は医師でありNPO法人GINAの代表をとつめているのです。私に残された道は、自身の疾患については現実を受け止めてリハビリに励む、そして職業人として患者さんたちに誠心誠意をもって接する、これしかありません。
私が今回手術を受けたのは症状の回復を期待して、あるいはこれ以上症状を進行させないために、ということで、手術が成功したことは大変ありがたいわけですが、症状が思ったほどに改善せずに、それがきっかけで難病を患っている人たちに想いを巡らすことにつながったことも手術と入院生活のおかげではないだろうか・・・。今私はそのように考えています。
注1:米国の俳優ロビン・ウイリアムス(63歳)は2014年8月11日、カリフォルニア州の自宅にて首をつって自殺したと報道されました。パーキンソン病が原因でうつ病を発症したとの報道があります。
投稿者 | 記事URL
2014年7月22日 火曜日
第138回(2014年7月) 認知症の鉄道事故、なぜ議論が盛り上がらない? (追記:2016年3月)
2014年4月24日、名古屋高裁は、愛知県大府市の認知症の男性が徘徊してJR東海の電車にはねられて死亡した事故について、「見守りを怠った」という理由で91歳の妻に359万円の支払いを命じました。
自分の夫が電車にはねられ死亡して、さらにその鉄道会社から359万円も請求されるという判決に違和感を覚えるのは私だけではないでしょう。この判決は(おそらく)すべての全国紙で報じられましたから、大変な物議を醸すことになるだろう・・・、私はそのように予測していました。JR東海に非難が集中し、場合によっては不買運動ならぬ「JR東海不乗運動」まで起こるのではないかと私はみていたのですが、そのようなことはまったく起こっていないようです。
この事件は、認知症の患者さん、その家族、医療や介護関係者には他人事ではないはずで、同じような事故が日本全国で起こることが充分予想されます。はねられた認知症の患者さんの家族に責任を追及するのはおかしいですし(私はそう思います)、しかし、かといって鉄道会社が寛容になれば解決するものでもありません。問題の根は深いわけですが、まずはこの事件(事故)を振り返っておきたいと思います。
2007年12月7日、当時91歳の認知症の男性が徘徊し線路内に進入しJR東海の電車にはねられ死亡しました。この男性は「要介護4」の認定を受けており、当時85歳の妻と同居していました。その妻が目を離したすきに男性は外出し電車にはねられたというわけです。
JR東海は電車が遅れたことにより損害が発生したと主張し、損害賠償を求め訴訟を起こしました。2013年8月、地方裁判所はJR東海の請求通り720万円の支払いを命じました。さらに地裁はこの死亡した男性の長男にも注意義務違反を認定しました。しかし、長男は経済的に父親を支援していたとはいえ、20年以上別居しているそうです。電車事故で夫に先立たれた高齢の女性に高額の支払いを命じ、さらに20年以上別居している長男にも責任を追及するというのはあまりにも気の毒です。
当然弁護側は控訴をおこないました。そして2014年4月、名古屋高裁で先に述べた判決が出たという次第です。報道によりますと、弁護側は上告も検討しているそうですが、それは当然でしょう。
ここで私が問題として取り上げたいのは、ひどすぎる判決よりもむしろ、なぜマスコミがこのようなJR東海や司法判決に黙っているのかということ、そして一般の人たちはなぜJR東海の対応に怒りを示さないのか、ということです。
最近は些細なこと(当事者にしてみればそうではないのかもしれませんが)で企業やショップ、レストランなどに苦情(クレーム)を言う人が増えてきていると聞きます。店員に土下座をさせてそれを写真に撮りネット上で流した人もいるとか・・・。私個人の印象を言えば、最近は消費者が過剰に権利を主張しすぎるように感じますし、また店員の対応も丁寧すぎるというか、言葉遣いからお礼の仕方まで行き過ぎでは?と感じることがしばしばあります。例えば、タクシーに乗るときはわざわざドライバーが外からドアを開けるサービスは行き過ぎています。自動でドアが開くだけでも親切すぎるくらいで、私自身の希望を言えば、乗せる側が開けるのではなく乗る側が自分で開ける方がいいと思います。実際海外にいけばタクシーのドアは自分で開けるのが普通です。
話を戻しましょう。企業に完璧さを求める消費者たちはなぜJR東海の対応に怒りをぶつけないのでしょうか。他人のことには興味がないということなのでしょうか。しかし、徘徊の症状が出ている認知症を家族に持つ人なら他人事ではないはずです。また、今は親が認知症でなくても、80歳を超えると程度の差はあるものの半数が認知症を発症すると言われています。ですからほとんどの日本人にとって人ごとではないのです。
医療機関や介護施設からももっと大きな声が出てきていいはずです。もしも入院中や介護施設に滞在中に抜け出して線路に進入し電車にひかれたとすれば、誰が責任を追及されるでしょうか。おそらくこの場合は、鉄道会社からも家族からも医療(介護)施設に矛先が向けられることになるでしょう。ちなみに私は、研修医時代に担当の患者さんが病院を抜け出して(脱走して)問題になったことがあります。その患者さんは認知症を患っていたわけではありませんが、反社会的な側面を有していたために何か問題を起こさないかとヒヤヒヤしました。結局夕食の時間には戻ってきていましたが。
では、認知症の患者さんが電車にはねられた場合、鉄道会社は黙っているのがいいのか、というとそういうわけでもありません。鉄道会社は大企業ですから、それでもやっていけるでしょうが(昔は飛び込み自殺があったときは遺族感情に配慮して訴訟などは起こさないことが多かったはずです)、これが個人ならどうでしょう。例えば、徘徊したときに他人の家に火をつけた場合はどう考えるべきでしょう。あるいは、徘徊しているときに若い女性がひとりで歩いていれば、強姦される可能性もないわけではありません。実際、医療・介護の現場では女性職員が認知症の患者さんからセクハラを受けることは日常茶飯事ですし、なかにはレイプまがいの事件もあります。
つまり、徘徊した患者さんが何か事件を起こしたときに、家族や入居施設に損害賠償を請求すれば解決するものではもちろんないわけですが、その一方で(JR東海のような)”被害者”が黙っていればそれで解決するという問題でもないというわけです。ちなみに、2013年1年間で、認知症で行方不明になったと警察に届出をされたのが約10,300人で、そのうち390人が死体で発見されたそうです。(警察庁が2014年5月14日衆議院の厚生労働委員会で発表しています)
ではどうすればいいのでしょうか。もしも最高裁でも今回の事件の判決が覆らなければ、家族や医療・介護施設は認知症の患者さんを徘徊させないようにあらゆる手段を講じるでしょう。つまり、最終的にはベッドに縛り付けて身動きがとれないように拘束することが予想されます。
ところで、医療や介護の現場で「抑制」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。私は医師になりたての頃、随分とこの言葉に戸惑いました。医療者や介護者がいう「抑制」というのは、要するに認知症などでベッドから落ちる(あるいはベッドから抜け出して困った行動をとる)可能性のある患者さんの手足をベッドの柵にくくりつけて身動きがとれないようにする”医療行為”のことを言います。「抑制」などという表現であればなんとなくソフトなイメージが沸きますが、やっていることは「拘束」です。
私はここで、「抑制」などというマイルドな言葉を使って非人道的な処置をとる医療者・介護者を糾弾すべき、と言っているわけではありません。患者さんの手足を拘束しなければ転倒や他人に危害を加える事故を防ぐためにそのような処置はやむをえないと思います。
認知症で徘徊する患者さんが人や会社に迷惑をかければすべて介護者の責任にされるのなら、患者さんの自由を奪う行為、つまり事実上の身体拘束が激増するだろう、ということをここで指摘しておきたいと思います。
認知症の問題は社会全体で考えていかなければなりません。今回のJR東海の事故のようなことが起こったときにお金が保証される損害保険のようなものがあればいいという案も出ているようですが、保険に入るお金がないという人も必ずでてきます。町中に監視カメラをつけるとかGPS機能のついた腕時計を装着させるとか(あるいはGPSのカプセルを皮膚に埋め込むとか)いう案も出てくるかもしれません。しかし、このような案が出てくれば、人権侵害ではないか、という意見もでてくるでしょう。
ひとついえるのは、家族だけで認知症のケアはできない、ということです。また、医療機関や介護施設、介護サービスなどにも限界はあります。つまり社会全体でこれからの認知症対策を考えていく必要があるのです。北欧では高齢者の認知症対策が上手くいっており徘徊する者はいない、と言われることがあり、見習えるところはあるかもしれませんが、日本の方が高齢化は進んでいますし、社会保障のあり方も異なりますし、国民性も異なるでしょうから、そのまま北欧のケアの方法をまねるだけでは上手くいかないでしょう。
日本独自の認知症対策について国民全員が真剣に考えなければならない時代にすでに入っているのは間違いありません。
**********
追記(2016年3月7日)
2016年3月1日、最高裁判所は「妻と長男は監督義務者にあたらず賠償責任はない」と結論づけ、JR東海の敗訴が確定しました。
このコラムのタイトルにもしたように、2014年の名古屋高裁の判決の時点では遺族の責任が追及されているのにもかかわらず世間での議論はそれほど盛り上がりませんでした。しかし、今回の最高裁の判決はマスコミからも注目されたようです。
特に、長男の妻が世間の注目をあびました。長男夫妻は両親の元を離れて横浜に住んでいたそうです。しかし認知症の義父と高齢の義母の面倒をみるために、長男の妻は夫から離れて単身で愛知県に引っ越し、義父に対して熱心に介護をおこない献身的な日々を過ごされていたそうです。
2016年3月7日の日経新聞一面のコラム(春秋)では、小津安二郎監督の映画『東京物語』で長男の妻の役を演じていた三宅邦子さんを引き合いに出していました。偶然にも、私が今回の訴訟に関する一連の報道を見聞きして思い出したのも『東京物語』でした。しかし、私が思い浮かべたのは三宅邦子さんではなく、戦死した次男の妻を演じた原節子さんでした。原節子さんは『東京物語』のなかで、義父と義母に対し実の息子や娘以上に献身的な態度で接します。『東京物語』が公開されたのは1953年です。もしも現在高齢の方が初めてこの映画を見れば、「こんなによくできた義理の娘などこの時代にいるわけない」と感じるのではないでしょうか。
日経新聞のコラムでは、献身されたこの妻に対し「無私の5年余に頭を下げたい」という言葉で結んでいます。私もまったく同じ気持ちです。
投稿者 | 記事URL
2014年6月20日 金曜日
137 24時間働けますか 2014/6/20
私は臨床医以外に、産業医や労働衛生コンサルタントとしての顔もあるために、労働者と面談をしたり、その逆に事業主から意見を求められたりすることもしばしばあります。ここ1年くらいで最も多い相談が「過重労働」に関するものです。少し前までは、いわゆる「新型うつ病」が多かったのですが、最近はなぜか新型うつ病と思われる相談はすっかりと鳴りを潜め、もっぱら過重労働がメインになってきています。
現行の労働安全衛生法の規定では、労働者が、月100時間を超える過重労働が(ひと月でも)あるか、あるいは2~6ヶ月の平均で月80時間を超える過重労働があるかすれば、産業医の面談を受けなければならないことになっています。ここで言葉の定義を確認しておくと、「過重労働」というのは平日の残業時間と休日出勤を足した時間のことです。例えば、平日は毎日3時間残業して毎週土曜日に出勤して5時間ずつ働いたとすれば、3時間x5日x4週間+5時間x4日=80時間/月、となり、これが2ヶ月続けば産業医の面談を受けなければならないのです。
さて、実際に面談をしてみると興味深い事象がみえてきます。例えば、月に120時間を毎月超えているような若い労働者が「まだまだがんばれますよ。今度また大きなプロジェクトがあってしばらく会社に泊まり込みになりそうです。先輩たちは厳しいですけど楽しいことも多いんですよ」というようなことを言う場合があります。このような人は産業医(私)との面談も会社に言われたから”仕方なく”受けているのであって、できることなら早く仕事に戻りたい、このような面談も時間の無駄、と考えていることもあります。
一方で、その逆に、過重労働は60時間程度だけど(先に述べた法律の基準に達していなくても産業医との面談をおこなうことは可能です)、「会社に酷使されている。うちの会社はブラック企業だ・・・」という人もいます。
これら両極端な例をみればわかるように、労働者にとって仕事がどれだけ負担になっているかというのは単純に労働時間だけでは分からないものです。しかし、現在の日本では過重労働からくると思われる心身の疾病がたくさん発症しているのは事実です。厚労省や行政、あるいは会社としては何らかの基準をつくって、心身不調者を早期発見する義務があるわけで、そのスクリーニングとして簡単に数値化できる過重労働の時間を指標にすることは間違っていません。
では、長時間働いてもそれを苦痛と感じない人と、それほど長時間でなくても苦痛を感じさらに心身の不調を訴える人がいるのはなぜなのでしょう。労働時間以外に何がこれらを決める要因になるのでしょうか。
ワタミと言えば今やブラック企業の代名詞のような扱いを受けている企業ですが、なぜここまで注目されるようになったのかというと、従業員が過重労働から自殺をした、という事件があり、さらにマスコミの取材でワタミの社内冊子が白日の下にさらされることになったからです。『理念集』と名付けられたその冊子には、「365日24時間死ぬまで働け」、「出来ないと言わない」などと大変厳しい教訓が書かれているそうです。(『週間文春web』2013年6月5日)
365年24時間死ぬまで働け・・・、はいくら何でもまずいのでは?と、おそらくほとんどの人が感じるでしょう。若いときはがむしゃらに働け!と実際には思っている厳しい中高年の人たちも、このご時世にこの意見に同調するのは気が引けるでしょう。
しかし、です。日本マイクロソフトの元社長(現在HONZ代表)の成毛眞氏は、最近『週刊新潮』(2014年5月29日号)の連載コラムのなかで、とてもおもしろいことを述べられていました。氏は、マイクロソフト社の新入社員が入社前に出席する内定式の挨拶で次のようなことを話されていたそうです。
(前略)最初の3年間は24時間365日仕事だけをしろ、と。仕事以外で許されるのは、週に一度の入浴くらい。恋人がいる人は入社までに別れを告げ、いない人は、すぐにパートナーを作り、やはり入社前にふっておくべきだとけしかけた。
成毛眞氏という人について、私は『週刊新潮』のこの連載が始まるまでほとんど何も知らなかったのですが、この人の文章は内容も表現も大変魅力的で、よくこれだけ興味深い文章が毎週書けるものだと、私は発売日を楽しみにしています。
それにしても、24時間365日働け!、風呂は週に一度!、恋人とは入社までに別れておけ!、とは恐れ入ります。私はこの文章を読んだとき、おかしすぎて声が出てしまったほどです。(入社前にふられたパートナーの人には失礼ですが・・・)
さて、成毛眞氏はこのご時世になぜこのような発言をするのか、そしてこれを読んだ私(を含むほとんどの読者)は氏になぜ否定的な感情を抱かないのでしょうか。それは真意が別にあることが分かっているからです。
成毛眞氏はこのコラムの後半で次のように述べています。
1日8時間働くのと、1日24時間働くのとでは、経験値が3倍異なる。社会人になりたての時期の3倍の差は、どの会社でどんな業務をしているかの違いよりも、遙かに重要である。この頃に離された距離は、その後、どれだけ頑張っても埋められるものではない。だから死にものぐるいで頑張らなくてはならない・・・
もちろんマイクロソフトの若い社員たちは、実際には週に一度どころか毎日シャワーをあびていたでしょうし、恋愛もちゃっかりと楽しんでいたに違いありません(見たわけではありませんが・・)。しかし仕事は猛烈におこない何日も会社に泊まり込んだという人は少なくないでしょうし、帰宅してからも(仕事を持って帰っていなかったとしても)頭の中で四六時中仕事のことを考えていた時期があったはずです。
私は個人としては成毛眞氏の考え方に共鳴します。ただし、医師として、とりわけ産業医としては、全面的に同意します、とは言えません。やはり、ものには限度がありますし、こういった極端なコメントには、それを抑制する方向の意見も必要だからです。
私は、産業医としてはもちろんですが、個人としても、風呂は週に一度、とまでは言ったことがありません。しかし、会社員時代も医師になってからも後輩たちには次のように言っています。
今の仕事が勉強になるかどうか、将来の糧になるかどうかをよく考えるべきだ。今やっていることが少しでも自分のためになる可能性があるならやめるべきではない。君はずっとこの組織(会社・病院)にいるわけではない。どこへ行っても通用する知識と技術を今やっていることを通して学ぶんだ・・・・。
私はこれまでに会社員、十種以上のアルバイト、複数の病院での勤務医、太融寺町谷口医院(医師は私ひとりですが研修医が勉強に来ます)と、様々な勤務地で大勢の後輩をみてきましたが、相談をもちかけられるとこのように答えてきました。そして、これが通じやすいのは一般の会社員よりも医師に対してです。これは医師の方がいったん知識と技術を身につければ他人に貢献できる、つまり身につけた知識と技術が求められる場面が多いからでしょう。
しかし、医師以外の仕事であっても、その会社でしか通用しないことを延々とやらされる仕事と、少々困難ではあるけれど成し遂げれば自分の糧になり将来役立つ可能性のある仕事ではまったく異なってきます。
最近私は産業医として労働者と話すとき、このような点に気をつけています。すると労働時間だけでは決してわからないその人の考えや将来の展望、会社への帰属意識、事実上の疲労度などが見えてくるのです。
ただし私は、まだまだがんばれます!という労働者に対し、ではまだまだがんばってください!と言っているわけではありません。先ほど、医師は知識と技術を身につけるために少々辛いことでもがんばれる、と言いましたが、過労から心筋梗塞を発症した研修医や自殺においこまれた研修医がいるのもまた事実です。
過重労働を強いられている、あるいはブラック企業で働かされている、と感じている人は労働時間に関わりなく上司あるいは産業医に相談することを検討すべきでしょう(注1)。一方、労働時間が多いけれど全然苦痛じゃない、と考えている人も、ときには息抜きに産業医との面談を受けてみてはどうでしょうか。過重労働を苦痛と感じないような仕事のできる人なら、ときには日頃の仕事とまったく異なる分野の人間と話をすることで思わぬ発想がでてきて仕事にいかせることもある、ということを知っているでしょうから。
注1:大企業なら会社に常勤の産業医がいるでしょうし、中小企業でも50人以上の社員がいるところであれば嘱託産業医が月に一度会社に来るはずです。しかし50人未満の企業の大半は産業医と契約を結んでいません。ではどうすればいいかというと、各地域の産業保健総合支援センターや地域産業保健センターに問い合わせればいいのです。無料で産業医の面談が受けられるサービスもあります。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第186回(2018年7月) 裏口入学と患者連続殺人の共通点
- 第185回(2018年6月) ウイルス感染への抗菌薬処方をやめさせる方法
- 第184回(2018年5月) 英語ができなければ本当にマズイことに
- 第183回(2018年4月) 「誤解」が招いた海外留学時の悲劇
- 第182回(2018年3月) 時代に逆行する診療報酬制度
- 第181回(2018年2月) 英語勉強法・続編~有益医療情報の無料入手法~
- 第180回(2018年1月) 私の英語勉強法(2018年版)
- 第179回(2017年12月) これから普及する次世代検査
- 第178回(2017年11月) 論文を持参すると医師に嫌われるのはなぜか
- 第177回(2017年10月) 日本人が障がい者に冷たいのはなぜか
月別アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (125)