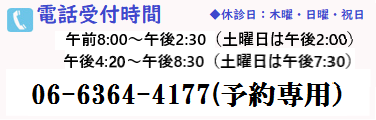メディカルエッセイ
2013年6月17日 月曜日
第26回(2005年10月) 後医は名医?!
「後医は名医」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
これは、我々医師がよく使う「ことわざ」のような言葉で、「同じ患者さんを診るなら、後から診た方が名医になれる」というものです。
例えば、ある患者さんがA診療所を受診したとしましょう。その患者さんはその診療所で診察を受け、薬を処方されたのにもかかわらず、一向にその病気は治りそうにありません。
そこで、この患者さんは次にB診療所を受診したとします。患者さんは、A診療所に行って薬を処方してもらったことを話しました。すると、B診療所では別の薬が処方されました。その薬を飲みだすと、一気に症状が消失しました。
ここで、この患者さんはどのような印象を持つでしょうか。
「A診療所はヤブ医者で、B診療所が名医だ」と思われるのではないでしょうか。
しかし、これには”トリック”があります。
まず、ひとつめは、この患者さんの症状は、薬に関係なく、自然に治った可能性があります。つまり、A診療所の処方もB診療所の処方も特に効いたわけではなく、患者さんの自然治癒力で勝手に治っていたということです。
次に、B診療所では、すでにA診療所で処方された薬が無効であることが分かっているために、次の手をうちやすかった、ということが言えます。疾患にもよりますが、実は患者さんの想像以上に、現在の日本においては、各疾患(症状)に対する治療法が標準化されています。
つまり、この病気では、通常は最初にA診療所で処方された薬剤が標準的で、その薬剤で効果がなかったときに初めてB診療所で処方された薬剤を使用する、ということがある程度確立されているわけです。
さらに、この患者さんがB診療所を受診したときに、A診療所を受診したときには見られなかった症状が出現していた、という可能性もあります。つまり、最初、この患者さんがA診療所を受診したときには、熱だけしかなかったけれど、B診療所を受診したときには、熱プラス特有の皮疹が出現しており、そこから、B診療所では適切な診断がつけられた、ということがあるのです。
このように、後から診察する医師の方が、その疾患を適切に診断するのに有利になることはよくありますす。
患者さんのなかには、最初近くの診療所を受診したけれどなかなか治らないため大きな病院に行きそこでの治療を受けた結果よくなった、という経験をする人がいますが、こういう経験のある人に言わせると、「やっぱり診療所よりも大病院の方が信頼できる」、となるわけです。
例をあげて説明しましょう。
川崎病と呼ばれる小児の病気があります。この病気は現在でも原因不明なのですが、発症すると入院治療を余儀なくされ、完治するまでに時間がかかることもある、場合によっては難儀な病気です。
川崎病は、最初熱が出て、そのうちに全身のリンパ節が腫れだしたり、目が充血したり、舌が真っ赤に腫れあがったり、全身のいろんなところにいろんなタイプの皮疹が出現したり、と様々な症状が出現するのが特徴です。
最初に熱が出たときに、「この熱は川崎病によるものです」と断言できる医師など世界中にひとりもいません。なぜなら、川崎病という病気は、いろんな症状が出現してから初めて診断がつけられる病気だからです。
通常、子供が高熱を出せば、ウイルスや細菌による急性感染症を疑います。かなりの高熱が出現していれば、細菌感染を疑い抗菌薬を処方することになります。ところが、川崎病では抗菌薬がまったく効きません。
心配したこの子供のお母さんは、この診療所では治らないのではないか、と考えて大きな病院を受診することになります。
そして、その頃には熱が出てから数日たっていることもあり、皮疹や充血などが出現しているのです。この患者さんをみた大病院の医師は、川崎病を疑い、すぐに入院させて点滴治療をおこないます。
すると、お母さんとしては、「さすが大病院。すぐに病名を言ってくれたし、入院、点滴と適切な対応をしてくれた。それに比べて最初に行った診療所では、病名も分からないし、出した薬は効かないし、もう二度と行きたくない」、となるのです。
私が、ある病院の小児科にいた頃、こういうケースが多々ありました。
しかしながら、もちろんこのお母さんの感じていることは必ずしも正しいわけではありません。
最初にみた診療所の医師も、子供をみる以上は、常に川崎病のことも念頭に置いています。しかし、川崎病に比べて、高熱が主症状の風邪の方が圧倒的に頻度が高く、熱の患者さんすべてに、川崎病の話をするのは適切ではありません。かえって余計な不安を与えることにもなりかねません。
診療所の医師としては、「まずは普通の細菌感染と判断し抗菌薬を飲んでもらおう。それでも効かないときは薬を変更するとか、あるいは他の症状が出現したら、(川崎病も含めて)他の疾患を鑑別しよう」、と考えているのです。
ところで、我々医師のルールのひとつに「前医を批判しない」というものがあります。これは、医師はお互いに尊敬し学びあうべき、という倫理的な観点から生まれたルールでありますが、実際的には「後医は名医」となってしまうことが頻繁にあることを知っているからです。
そもそも、最初の現場にいない人間が、あとからとやかく言うのはアンフェアであるわけで、たとえ結果として、最初の診断が間違っていたとしても、そのときのその状況ではそう診断せざるを得なかった可能性もあるからです。
ですから、安易に前医を批判する医師を私は信用できません。
先日、あるテレビプログラム(民放)を見ていると、医師が登場して、ゲスト出演者の質問に答えていました。そのゲスト出演者は、ある症状である病院に行って治療を受けたけど治らなかった、ということを話しました。すると、その医師は、「その医師の診断が間違っているのです。病院選びは正しくおこないましょう。私なら誤診はしません」というようなことを言っていました。
これほど、傲慢な医師もいないでしょう。普通なら、そのときはそのように診断した根拠があったはずだ、と考えます。もちろん、最初の診断が間違ったために、とりかえしのつかないことになった、というような事態になれば問題ですが、通常、医師というのは、病態の重症化や急変の可能性のことも考えて、診察をおこないます。
おそらく、その診察医も、まずはこの治療をおこなって、それで効果がなければ次に進もう、と考えていたはずです。それをきちんと患者さん(このゲスト出演者)に伝えていなかったところに非はあるかもしれませんが、それにしても、「前医の診察が間違っている」と断定するのは問題です。
こういった発言をする医者のせいで、医療不信が加速されているのではないか、と私は考えています。このテレビを見ていた人の多くは、「そうか、医師の診断力はバラバラだから、いい病院を受診しなくてはならないんだな」というふうに感じるでしょう。
けれども、そうではなくて、この出演医師のような、「前医を安易に批判するような医師」の方がよほど問題があるわけです。
モノを売る人のセールストークがライバル会社の悪口中心であれば、イヤな気持ちにならないでしょうか。それと同じで、同僚を安易に批判することによって、自分の価値を高めようとする医師は決して名医ではないのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
25 日本の医師はこれだけ不足している!! 2005/10/15
2005年9月22日、財団法人社会経済生産性本部が、「国民の豊かさの国際比較」を発表しました。発表によりますと、日本は、経済協力開発機構(OECD)加盟30カ国中、総合で第10位にランクされたそうです。2004年には総合第14位だったために、4ランク上昇したと喜びの声がある一方で、詳細を見渡すと決して楽観はできないという慎重論があるようです。
この国際比較の項目のなかには、健康指標というものも含まれており、健康指標だけでは第8位です。ここでは健康指標に含まれる項目を少し詳しくみていきたいと思います。
まず、平均寿命の長さでは第1位、人口当たりの病院ベッド数は(多い順に)第2位、乳児死亡率(少ない順に)第3位、人口あたりの死亡者数(少ない順に)第9位、国民ひとりあたり健康支出(多い順に)第17位、国民ひとりあたり公的健康支出(多い順に)第14位です。そして、人口あたりの看護師数は(多い順に)第19位、人口あたりの医師数は(多い順に)、なんと30カ国中、27位です。
平均寿命やベッド数が世界のトップに位置していながら、医師数が下から4番目の低さであるというのは、つまるところ、ひとりの医師がたくさんの患者さんをみていて、なおかつ質の高い医療を供給しているということになります。今回の社会経済生産性本部の発表では、医師の平均勤務時間は発表されていませんが、もしもこういう統計がとられたなら、日本の医師の勤務時間の異常なほどの長さが浮き彫りになったに違いありません。(先日の国勢調査では、1週間の勤務時間を書く欄がありましたが、私は117時間でした。)
日本の医師数が少なすぎるというのは、こういった統計をみても明らかです。
しかしながら、日本の厚生労働省は1990年代後半あたりから、医師数を抑制すべきであるという主張をし続けてきました。具体的には、2020年を目途に医学部の定員を10%削減するという目標を掲げていました。実際、私が医学部在学中の頃から、○○大学医学部は何年後かになくなる、とか、△△大学医学部と××大学医学部は近いうちに統合される、などという噂がとびかっていました。
私は、自分の本のなかでも繰り返し主張していますが、医師数が多すぎるということは絶対にありません。こんなこと、自分の身の周りをみれば明らかです。患者サイドから考えてみても、大病院はもちろん、診療所を受診しても、長時間待たされたあげくに、数分間の診察というのは珍しくありませんし、医師サイドからみても勤務時間が長すぎるのは明らかです。
では、こういう現実がありながら、なぜ厚生労働省は医師を抑制すべきだという主張を続けてきたかというと、それは、少子化と高齢化社会、人口減少から、徴収できる税金と保険料は頭打ちになり、それでは、医師の給与の現状維持ができないからに他なりません。
厚生省と同様、医師数抑制を主張し続けてきた日本医師会によれば、「医師が過剰になれば、粗製乱造で医療の質の低下を招くとともに、医師の失業につながりかねない」、そうです(asahi.com 2005年3月12日)。
果たして本当にそうでしょうか。本当に医師が過剰、というか、他の先進国並みになれば、医療の質の低下を招くのでしょうか。
少なくとも、睡眠不足から判断力の低下をきたすことはなくなるでしょう。最近発表されたアメリカの論文によりますと、睡眠不足の医師はアルコールを飲んでいるのと同程度に判断力が鈍るというデータがあります。
また、医師が増えれば、医師ひとりあたりが診る患者さんの数が少なくなり、患者さんひとりひとりにじっくりと取り組めることになります。現状では、入院患者さんのところに行くのが1日に一度だけであったり、また外来では、積み上げられたカルテを横目で見ながら、目の前の患者さんを早く終了させることを考えなければならないということが日常茶飯事なのです。このような診察をして、病院の経営者は喜ぶかもしれませんが、我々医師にとっても、患者さんにとっても、お互いあるべき姿ではないのです。
もうひとつ日本医師会が主張している「医師の失業」という問題についても、いったん医師になれば失業はない、という現状の方がよほど問題があるわけで、医師免許をいったん取得すればそれで安泰などと考えている医師がいるとすれば、このことこそが、日本の医療のレベルを低下させることになるのではないでしょうか。
厚生労働省の「医師数を抑制する」という主張は、どこからどう考えても納得のいかないものです。
しかしながら、最近になって、ようやく厚生労働省も現実を見始めたようです。新研修医制度の導入とともに、大学の医局には新しい医師が二年間は入局できなくなり、このため多くの医局で人手不足が深刻化しました。特に痛手を被っているのが、産婦人科と小児科で、この2つの科は従来から相対的に人が足らなかったところに、新研修医制度が導入され、結果として関連病院から医局員を引き上げることになり、その結果、その関連病院では産婦人科や小児科をやめざるをえなくなったのです。
産婦人科については、この傾向が特に顕著で、昨今の医事紛争の増加も重なり、総合病院で産婦人科を標榜するところが全国的に激減してきています。例えば、関西のある中堅都市(人口約27万人)では、ついに出産のできる総合病院がなくなってしまいました。その市では産科を標榜している個人病院が3つだけになり、この市で出産しようと思えばその3つの個人病院に行くしかないのです。これではとうていベッドが足りませんし、例えば喘息や高血圧などを持っている、本来高度医療のおこなえる総合病院で出産すべき妊婦さんはその市では出産することができないのです。
小児科不足も深刻です。例えば、関西のある総合病院は夜間に小児科の救急外来をおこなっていますが、その地域には、他に夜間に子供をみる病院がないために、多い日では一晩に100人もの患者さんを診なければならないのです。ひとりの小児科医が一晩で100人です。もちろんその小児科医は翌日の朝から通常業務が待っています。この状態で、一晩に100人の患者さんを、的確な判断力をもって、まったくミスをすることなく診察し続けることができるでしょうか。
産婦人科、小児科以外に深刻なのが麻酔科です。麻酔科医が不足しているために、本来麻酔科医が麻酔をすべき症例に対し、外科医が執刀をしながら麻酔をかけるということが、日本の医療現場ではごく普通におこなわれています。
他の領域においても、地方に行けば医師不足は深刻です。医師が不足し、存続が危うい病院は少なくありませんし、どこの病院にいっても、数少ない医師が多くの患者さんを診なければならないわけですから、当然医療の質は低下します。
厚生省は最近になって、ようやく「医師数抑制」の方針を見直すようになりましたが、医学部の定員を増やすという議論にはなっていないようです。
私は自分の本で主張しているように、医師の数は現在の倍くらいにすべきだと考えています。そうすれば医師側にとっても患者側にとっても、今よりははるかに満足度の高い治療ができるに違いありません。
こういうことを言うと、では財源はどうするのか、という反論が必ずでてきますが、その答えは簡単なことです。
医師の数を倍にする代わりに、医師の給与を半分にすればいいのです。よく、「医師が儲けているというのは幻想であって、実際は一部の開業医を除けば、特に勤務医などは安い給与でこきつかわれている」などという人がいますが、これは間違いです。
先日も、あるテレビ番組で、医師(勤務医)が登場し、「私の給与は1000万円しかないんですよ」と言っていましたが、1000万円を少ないと思っていること自体が異常です。
ちなみに、民間企業に勤める人が2004年一年間に受けとった一人あたりの平均給与は439万円です(日本経済新聞2005年9月29日)。この医師は、世間の人々がどれくらいの給与を貰っているのか知っているのでしょうか。知っていれば、こんな無神経な発言はできるはずがありません。医師の給与は、その439万円の中から徴収される税金と保険料でまかなわれているのです。こういう発言をする医師がいる限り、医師は世間知らずと言われても仕方がないでしょう。医師は新聞すら読んでいないということなのですから。
もっとも、医師不足のために勤務時間が長くなりすぎ、新聞を読む時間すらない、ということなのかもしれませんが・・・・。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第24回(2005年9月) 「クスリ」を上手く断ち切るには ④(最終回)
これまでに、私が述べてきたことをここで確認しておきましょう。
・違法薬物はやらないに越したことはないが、必要と感じている人もいる理由は理解しなければならない
・その理由とは、人間は「日常」だけでは生きられずに、「非日常」の時空間も必要であり、「クスリ」は簡単に「非日常」を体験できる、というものである
・「非日常」の時空間が特に必要になるときというのは、人生のどん底に沈んでいるとき、自暴自棄になっているとき、あるいは、「クスリ」のリバウンドで苦しんでいるとき、なども該当する
・ 「非日常」を適切に体験できればそれは素晴らしいことであるが、現代社会では必ずしも容易なことではない。そのため、医療機関を受診するのもひとつの方法である
しかしながら、「あたしって、非日常をうまく体験できないから、先生助けて~」と言って医療機関を受診するわけにはいきません。そんなこと言っても、私以外の医師は「???」となるに違いありません。
けれども、私の言う「日常/非日常」というのは、実は社会学では常識的な考えです。これまでも多くの学者が提唱してきています。「日常/非日常」という言い方は、場合によって、「ハレとケ」であったり、「労働(生産)/祝祭」であったり、「過剰/蕩尽」であったりします。
もう少し解説しましょう。人間は、生産活動をするようになってから、モノを過剰につくるようになりました。食べる分だけ生産すれば事足りるはずなのに、それ以上のものをつくります。そして、ある一時期に、それら過剰なものを一気に消費するのです。これは一見非合理なように見えます。なにも努力して余計なものをつくって一気に消費しなくても、初めから余分なものなどつくらなくてもよさそうに思われるからです。
けれども、例えば、お祭りのときには、普段口にしないような料理や酒を絶対に食べられないほど大量に用意してドンちゃん騒ぎをします。普段はご法度のケンカやナンパもお祭りのときは誰もとがめません。年に一度、それまで住民が一生懸命作り上げた建物をみんなで壊す習慣のある地域も世界にはあります。日本でも、岸和田のだんじり祭りや青森のねぶた祭りでは、勢いあまって建物が壊れたり怪我人が出たりすることも珍しくありませんが、非難する人はほとんどいません。
祝祭や儀式があるような文化では、住民が自然に「非日常」を体験できて「健康に」過ごせるというわけです。おそらく、こういう文化を心底楽しめるような人は「クスリ」が必要になることはないのではないかと私は考えています(もっとも、バリ島の伝統的な祝祭のように、儀式で「クスリ」を用いるということはあるでしょうが・・・)。
理由はともかく、人間は「日常」と「非日常」をうまく使い分けてきた、というのが社会学の考え方です。そして、現在でも周りを見渡せばこういう現象は見受けられます。
例えば、毎日早朝から深夜まで休みなく長期間働き、ようやく仕事が一段落すると、ハメを外して遊びたくなります。普段真面目でおとなしい人が、飲み会で人柄が変わるというのもよくあります。コツコツ貯金をしてやりたいことを我慢していると、あるとき一気に消費してしまうものです。
もうひとつ、強烈な「非日常」を紹介しましょう。それは「恋愛」です。恋愛といっても、例えば長年寄り添っているカップルや夫婦の恋愛は「非日常」でなく「日常」になってしまっています。そうではなく、例えば、恋愛の初期というのは、突然それまでの「日常」になかったドキドキするものが舞い込んでくるわけですから、これは強烈な「非日常」になるわけです。また、周囲から反対されている恋愛や、不倫や浮気のようなかたちの恋愛も「非日常」になるでしょう。駆け落ちを考えているカップルが世間の常識からはずれた行動を取るのは、まさに「非日常」の真っ只中にいるからです。
だから、長年連れ添った配偶者よりも、新しい浮気相手に夢中になるのはある意味では当然のことなのです。「日常」に退屈していたところに、突然魅力的な「非日常」が舞い込んできたわけですから・・・。念のために言っておきますが、私はこのような恋愛を奨励しているわけではありません。むしろ、恋愛の非日常性を理解していれば、長年連れ添ってからでも二人で何らかの「非日常」を見つけることによって、恋愛を長続きさせることができるのではないかと考えています。
一般的には、「のむ・うつ・かう」というのが、「非日常」の典型であるかもしれません。だから、「のむ・うつ・かう」というような行為をうまくおこなえる人というのは、社会学的には(私に言わせれば医学的にも)健全であるのです。
しかしながら、複雑な現代社会では、近代以前のような祝祭というのは地域にもよりますがそれほど期待できませんし、モノをつくって壊すという行動も簡単にできるものではありません。また、「のむ・うつ・かう」などという行動も、環境によってはむつかしいでしょうし、そうそう新しい恋愛や危険な恋愛をおこなうわけにもいきません。
では、どうすればいいのかというと、一般的には、スポーツ、旅行、音楽、買い物、などがいいのでしょうが、自分でいろんなことを試行錯誤してみて見つけていく他に方法はありません。
そして、うまく見つけられなかった場合には、人生のスランプがやってきます。ちょっとしたトラブルやストレスにも上手く対処できなくなってしまいます。そして気分は沈みがちになり、何をやっても上手くいかなくなります。
さて、そろそろ話しを戻しましょう。うまく「非日常」を体験できない場合、医療機関を受診するのもひとつの方法であると私は言いました。もちろん、医師にむかって「先生、非日常を体験させてください」というわけにはいきません。
では、どうすればいいかと言うと、気分がすぐれずに、人生のスランプであることをそのまま訴えればいいのです。あるいは、薬物をやめたいがリバウンドで苦しんでいるということを言えばいいわけです。
そして、医師は話を充分聞いた上で、必要であれば、薬剤を処方することになります。向精神薬と言えば、何か恐いものというイメージをもたれている人もおられますが、そんなことはありません。当たり前の話ですが、違法薬物なんかより遥かに安全です。
例えば、「プロザック」という薬剤があります。これは「SSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitorsの略、これを和訳すれば、選択的セロトニン再取り込み抑制剤、となる)」というクスリのひとつで、別名「ハッピードラッグ」と呼ばれています。抗うつ薬の一種ですが、従来の抗うつ薬に比べ副作用が少なく、医師の処方箋がなくても買える国もあるくらいです。アメリカには2000万人以上のプロザックユーザーがいると言われており、サラリーマンやOLが出勤前に飲んでいるそうです。日本でもインターネットを通して個人輸入して使用している人はかなりの数に上ると言われています。
「プロザック」は、日本ではなぜか販売されていませんが、同じ効果のある「SSRI」がたくさんあり、どこの医療機関でも処方してくれます。
「SSRI」だけではありません。抗不安薬やSSRI以外の抗うつ薬も作用の軽いものから、それなりに作用の大きいものまでたくさんの種類があり、必要に応じて医師は処方をおこないます。もちろん、安易に使用するものではなく、ある程度長期的に医師の管理のもとで服用する必要がありますが、充分に効果が期待できます。
実際に、私がみた患者さんで、長年覚醒剤を断ち切れずに自殺未遂までしたけれども、SSRIのみで(しかも少量で)完全に社会復帰を遂げ、元気に働くようになり新しい恋人までできたという例もあります。
抗不安薬を使用して、ストレスを感じなくなり、一度やめた仕事を復活させたという患者さんもおられます。
頭のかたい昔の人は、「何がストレスだ!何が不安だ!何が退屈だ!」などと言って、現代人が「クスリ」が必要な理由を分かろうとしません。違法薬物を使用するのは、社会からドロップアウトしたやつらだ、などと決め付け、普通の女子高生や、サラリーマンや主婦がドラッグに手を出している現実を見ようとしません。彼らには、複雑な現代社会の構図が読めていないのです。
私は、「現代社会に住む誰もが向精神薬を服用すべきだ」と言っているわけではありませんし、使用するには必ず医師の指導のもとでおこなう必要があると思っています。
けれども、「非日常」を求めて違法薬物に手を出す前に、あるいは違法薬物から断ち切るために、いくつかの向精神薬は有効である、ということを主張したいのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第23回(2005年9月) 「クスリ」を上手く断ち切るには③(全4回)
これまで、覚醒剤、麻薬、大麻、MDMAと、違法薬物をみてきました。残りを簡単に片付けておきましょう。
「マジックマッシュルーム」というキノコが一時大量に出回りました。このキノコは、幻覚が見られるというのが特徴で、例えばバリ島の伝統的な儀式などでは今でも使われています。大量に出回った最大の理由は、最近まで合法だったからです。合法だったといっても、それは取り締まる法律がなかったからであって、危険性は以前から指摘されていました。そして、2002年の6月に、麻薬取締法のなかの指定薬物に加えられたのです。
麻薬取締法について簡単にみておきましょう。この法律は、正確には「麻薬及び向精神薬取締法」といい、そこで指定されているのは、狭義の麻薬であるヘロインやモルヒネだけではなく、コカインやLSD、その他医薬品として扱われている向精神薬の一部が含まれます。そして、マジックマッシュルームもこのなかに入れられたというわけです。
しかし、マジックマッシュルームが違法になったとたんに急速に別の薬物が普及しだしました。それらは「合法ドラッグ」と呼ばれるもので、麻薬取締法やその他の薬物を取り締まる法律では規制できないものです。これらは、違法とされている物質を少し変化させるだけで、取り締まる法律がなくなり合法となりますから、堂々と販売されるのです。
これでは、いくら法律を増やしても「いたちごっこ」になります。そこで、2005年の4月から、麻薬取締法が改正され、これまで合法ドラッグとされていたものも「麻薬に類似するもの」となり規制の対象となりました。
これで、依存性や中毒性のあるすべての薬物が違法となったわけです。
もうひとつだけ、違法薬物について述べておきましょう。
それは、「シンナー」です。日本でよく問題になるのは「トルエン」で、純度の高いものは通称「純トロ」と呼ばれています。これは「毒物及び劇物取締法」で規制されています。シンナーは、他のどんな薬物よりも簡単に手に入りますから、ついつい手をだしてしまう機会が多いかもしれません。しかし、シンナーは、短期間に視神経、呼吸器、循環器に障害ももたらし、そのうち脳細胞も障害されることになります。
シンナー中毒で死亡する中学生の報告もそう珍しいことではありません。一方、中学生に常用者が多いのに対し、成人してからシンナー中毒になるという人はそれほど多くありません。比較的短期間で致死的な状態になる恐ろしい一面を持つ一方で、依存性が他の薬物に比べればそれほど高くないのがその原因だと思われます。
さて、これまで違法薬物をざっとみてきましたが、私がお話したいのは、それらの危険性だけではありません。
人間が「クスリ」を欲しがるのには理由があるわけで、やみくもに正論を振りかざし、「違法薬物はやめましょう」と言ってみても何も始まりません。どれだけ説得力があるかは分かりませんが、私なりの薬物対処法をお話したいと思います。
まず、避けられるのであれば避けるに越したことはありません。一度やって味を覚えてしまうと、そう簡単には抜けられません。麻薬はもちろん、覚醒剤やMDMAでも、一度やってしまったばかりに、断ち切るのにかなりの苦痛と苦労を強いられたという人は少なくありません。「依存しない人もいる」という意見は昔からあり、たしかに一度でも摂取した全員が依存症になるわけではありませんが、誰にでもその危険性があることは知っておくべきです。
タバコを吸う人なら、禁煙をすることがどれだけ大変かが分かるでしょう。麻薬は論外ですが、覚醒剤でもそのタバコの数十倍の苦痛が伴うと言われています。禁煙の数十倍の苦痛・・・。こう考えると、安易に覚醒剤に手を出しにくくなるのではないでしょうか。
次に、避けられない状況があったと仮定しましょう。若い世代の間では、「今日は、みんなホンネで話そうね」などと言って、覚醒剤パーティをおこなうことが少なくないと聞きます。たしかにみんなで覚醒剤を使うと、全員がハイテンションになり、普段言えないようなことも言えるようになるかもしれませんし、絆が深くなることもあるかもしれません。
そんなとき、自分だけ「あたしはやめておくね」などということが言えるでしょうか(このようなプレッシャーのことを「同調圧力」、または「peer pressure」と呼びます)。
では、このようなケースではどうすればいいのでしょうか。答えになっていないかもしれませんが、周囲の空気が変わろうとも、自分だけ仲間はずれにされようとも、「自分はやらない!」と言うことが必要です。
長期的にみれば、薬物をやらないという選択が絶対的に正しいわけです。たとえ、そのときのメンバー全員にシカトされようが、友達をなくそうが、世界の大部分の人は、自分の意思を貫いて薬物をやらなかったあなたの勇気に感動するはずです。長い人生のなかで、一度や二度、すべての友達を失ったとしても、自分の信念を通すことの方が大切なのです。それに、それを契機に疎遠になった友達がいたとしても、いずれ、あなたのあのときの勇気の意味が分かって、相手の方から近寄ってくるものです。つまり、「嫌われる勇気」を持つことが大切なのです。
だから、周囲のプレッシャーに負けない、自分の強い意志が求められるのです。
人生のどん底に沈んでいたり、何かが原因で自暴自棄になっていたりするときに、ふと目の前に違法薬物があった場合にはどうすればいいのでしょうか。周囲のプレッシャーに負けないような強い意志が普段は持てたとしても、自分の精神状態がまともでないときには、そんな理性は保てません。生きる望みを失っているようなときには、強い意志はどこかに消えてしまっているものです。
しかし、これには解決法があります。
それは、薬物に手を出す前に、医療機関を受診するということです。人生のどん底に沈んでいたり、自暴自棄になっているとき、というのは、人間なら誰でもあることだとは言え、正常な状態ではありません。これは、風邪は誰でもひくけれども、風邪をひいているときには正常ではない、というのと同じようなことです。精神状態がすぐれない、というのは、決して珍しい異常ではないのです。
だから、わざわざ敷居の高い専門の精神科を受診する必要はありません(もちろん受診してもかまいませんが)。自分のかかりつけ医でいいわけです。もちろん、症状が重症で、入院などのより専門的な治療が必要な場合もあるでしょうが、その場合でもかかりつけ医に紹介状を書いてもらえば、すみやかに最良の治療が受けられます。
何らかの理由で精神状態が正常でないとき以外にも、病院を受診するのが得策であるときがあります。それは、「一度やってしまった薬物を断ち切りたいとき」、です。この場合、例えば覚醒剤が切れたときに、リバウンドはかなりの苦痛を伴います。他人からみれば廃人にしかうつらないようなときもあります。そんな状態では、まともに物事が考えられませんし、手を伸ばせば届く範囲に薬物があれば、再び手を出すのも時間の問題でしょう。
そんなときこそ、医療機関を受診するべきなのです。
では、医療機関を受診すれば、人生のどん底から救ってくれたり、依存している薬物を断ち切ることができるのでしょうか。答えは「YES」です。もちろん、本人の努力も必要ですし、100%の確率で成功するとは限りません。けれども、少なくとも自分ひとりで悩んだり、カウンセリングだけに頼ったりするよりは、遥かに効果がある、と私は考えています。
また、以前も述べましたが、人間には「日常」だけではなく「非日常」の時空間が必要です。そして、この「日常」と「非日常」を上手く使い分けることこそが、人生を上手に生きるコツである、というのが私の理論で、この理論を用いると、受験勉強のスランプから抜け出せるということを、『偏差値40からの医学部再受験』で述べました。
人生のどん底に沈んでいたり、依存している薬物のリバウンドで苦しんでいるときなども、実は「非日常」の時空間が必要なときではないか、と私は考えています。
そして、いずれの場合でも、自分の努力で「非日常」を体験できず、人生の苦しみから抜け出せないときには医療機関を受診することが有効である、と私は考えているのです。
つづく
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
22 「クスリ」を上手く断ち切るには②(全4回) 2005/8/29
覚醒剤の次は、違法薬物の王様である「麻薬」をみていきましょう。
「麻薬」とは、狭義には、ケシの種子からとれる阿片から精製されたものを言い、モルヒネやヘロインの名で知られています。(ちなみに、ケシの栽培や阿片の所持はあへん法で、モルヒネやヘロインは麻薬取締法で裁かれます。)
麻薬の効果は、覚醒剤とはまったく異なり、ハイテンションにもしてくれませんし、活動性は低くなります。しかし、なんとも言えない恍惚感に包まれて至上の幸福感につつまれます。(といっても私は経験がありませんので。念のため・・・。)
アヘン戦争で、イギリスが中国人に阿片を浸透させたのは、誰もが戦意を消失することを狙ったからです。これに対し、もしも中国人が阿片ではなく、覚醒剤を使用していたら、眠らずにどこまでも戦ってくる無敵の軍隊になったかもしれません。
麻薬の最も恐ろしい点は、その依存性にあります。前回は、覚醒剤の依存性についてその恐ろしさをお話しましたが、実は麻薬はその比ではありません。いったん、その味を覚えてしまえば、かなりの確率で廃人になり、そしてそのうちに死亡します。
ただし、麻薬は協力な鎮痛効果があることから、医薬品としてはなくてはならないものです。痛みがあるうちは、麻薬はいくら使っても中毒症状になることはありません。(これを「ceiling effectがない」と言います。)
前々回、「シャブ中ドクター」は珍しくないという話をしましたが、「麻薬中毒ドクター」は聞いたことがありません。現在の日本の医療では覚醒剤に比べると、麻薬の方が使用量はずっと多いと言えます。もちろん、麻薬の取り扱いは厳重に規制されていて、もしも1錠でも紛失させると、それを届出しなければならず、場合によっては処罰の対象になります。けれども、臨床での消費量は、覚醒剤よりも麻薬の方がずっと多いわけです。最近では、末期癌患者の在宅医療にも麻薬を使いますから、麻薬が家族の管理になることもあるわけです。医師が不正に持ち出そうと思えば、それほどむつかしいことではないと思われます。
しかし、「麻薬中毒ドクター」というのは、ほとんどいないのです。これはなぜなのでしょうか。おそらく、医師もバカではないため、その危険性を承知しているからでしょう。医師であれば、麻薬と覚醒剤の効能の違いや危険性について充分に理解しています。「シャブ中ドクター」が後を絶たないのは、麻薬に比べて、覚醒剤が中毒性が低いことを甘くみているのと、眠気覚ましや集中力アップのために有用だという理解があり、さらに罪がそれほど重くないことが原因ではないかと、私は考えています。
麻薬は、強烈な依存性と耐性のできやすさから、覚醒剤に比べて、初めは吸入で満足していても、静脈注射に移行するのが早いと言われています。麻薬の静脈注射から立ち直った人もいるにはいますが、そのまま廃人になり命を落としていく人の方がずっと多いのは間違いありません。
したがって、法律は当然厳しいものになります。麻薬は保持しているだけで、まず実刑から逃れられることはありませんし、一部の国では、持っているだけで射殺というところもあります。知らないうちに誰かに自分のポケットにヘロインを入れられ、問答無用ですぐに射殺、ということもあるわけです。
静脈注射をすれば、麻薬であっても覚醒剤であっても、感染症の危険性はありますが、麻薬の場合はあまり問題にはならないのではないかと思われます。感染症の危険性よりも、中毒になり、そのうち死亡する可能性の方がずっと高いからです。
次に、大麻取締法で規定されている、「大麻」をみていきましょう。「大麻」は別名、「マリファナ」とか「ガンジャ」と言われることもありますし、単に「草」とも呼ばれます。また大麻の樹液を固めたものを「ハシッシュ」と呼び、大麻と同様の効果があります。
大麻は、覚醒剤や麻薬と異なり、依存性はないと言われています。また、オランダやインドの一部の州では合法ですし、カンボジアでは伝統料理にも使われます。ちなみにカンボジアではタバコの方が高級品であり、大麻を吸うのはタバコを買う金がない貧乏人だと言われていたことがあるそうです。
大麻を吸うと、全身の感覚が研ぎ澄まされます。ミュージシャンがよく使用するのは、音楽がシャープに聞こえるからではないかと思われます。例えば、ひとつの曲のベースの音だけを取り出して聞くことができるようになりますし、あるいは音感が敏感になることが作曲の際に有用なのかもしれません。聴覚だけではありません。視覚も鋭敏になります。白い壁が紫や緑に見えてきたり、雲の形が動物や人の顔に見えたりします(これを「パレイドリア」と呼びます)。
覚醒剤のようにハイテンションになることはなく、どちらかと言うと、麻薬のときのように動けなくなります。しかし、麻薬で得られるような恍惚感はありません。なぜか喉が渇き、食欲も亢進するため、大麻をやりすぎて太ってしまったという人もいます。
大麻愛好家の人たちは、依存性もないし注射をしたりすることもないわけだから、他の違法薬物はもちろん、タバコや酒よりもよっぽど健康的なものではないのか、と主張します。
たしかに、この考え方には一理あって、危険性がそれほど強くないことから、オランダなどでは合法となっているのでしょう。「大麻以外の薬物は一切やらない」、というポリシー(?)を持っている人もいて、たしかに健康上の被害はそれほど問題にならないかもしれません。「先生、オランダに行って大麻をやってもいいですか。」と聞かれたら、私は医師として何と言っていいか分かりません。草に火をつけて吸入するわけですから、身体にいいはずはありませんが、それ以上のことは言えないのです。
大麻が危険なのは、日本への持ち込みです。日本では当然違法であるわけで、そのため海外から日本に持ち込めば高値で売ることができます。もちろん、税関で厳しいチェックがありますから、簡単には持ち込むことができません。そのため、最近よく取られている方法は、少量の大麻をサランラップに包んで、それをコンドームに入れて、そのコンドームを飲み込むというものです。
しかし、この方法は非常に危険です。腸管でコンドームが破けて、大麻が吸収される、ということがありうるからです。日本の空港に着いたものの、大麻が全身にまわってしまい、立ち上がれなくなり、救急搬送され、病院で逮捕という事件がときどきおこっています。女性の場合、腟内に挿入する方法もあり、この場合は飲み込むよりも危険性は少ないでしょうが、見つかって逮捕されることはよくあります。
大麻取締法は、麻薬や覚醒剤に比べてたしかに罪は軽いのですが、コンドームで大量に持ち込んでいれば販売目的とみなされて、まず実刑から逃れられません。
ちなみに、このコンドームに入れて飲み込むという方法を、覚醒剤でおこなった場合、危険性は大麻の比ではありません。もしも腸管でコンドームが破ければ、日本に到着する前に、上空で突然死、という可能性もあります。
次に、最近日本で消費量が爆発的に増えている「MDMA」についてみていきましょう。「MDMA」とはメチレンジオキシメタンフェタミンの略で、通称「エクスタシー」と呼ばれています。「MDA」と呼ばれるものもあり、これはメチレンジオキシアンフェタミンの略で、こちらは通称「ラブドラッグ」と呼ばれることもあります。MDMAもMDAも、その名称から分かるように、メタンフェタミンやアンフェタミンの類似物質、要するに、覚醒剤の親戚です。しかし、規制する方法はなぜか、覚醒剤取締法ではなく、麻薬取締法です。
MDMAもMDAも効果は同じようなもので、強い興奮作用があります。覚醒剤とよく似ており、セックスの際に用いると強烈な快感に襲われます。(しつこいようですが、私は経験がありませんので・・・。)
覚醒剤と同様に、日本では都心部を中心に若い世代の間で出回っています。(日経新聞2005年8月4日夕刊の記事によりますと、2005年上半期での押収量は過去最多を記録しており、これで7年連続の増加となったそうです。)また、UKではクラブで簡単に入手できるそうです。UKは薬物に厳しい国で、例えば、日本では睡眠剤として医療機関で処方される「ハルシオン」は、使用法によっては幻覚をみたり、記憶をなくしたりして(間違った使い方をすると)非常に危険な薬物です。そのため、ハルシオンの製造元のアップジョン社は、本国のUKで販売を禁止しています。それほど薬物に厳しいUKでも、なぜかロンドンなどのクラブでは比較的簡単にMDMAが入手できるそうなのです。(ちなみに、ハルシオンは、かつてドラッグ天国と呼ばれたタイでも以前から販売禁止にされており、タイ人は主に日本人から入手していたそうです。)
日本のクラブでも、ロンドンと同様、MDMAは比較的簡単に入手できるようです。もちろん、覚醒剤と同様、非常に危険な薬物で、錯乱や不安に襲われることもありますし、死亡例も報告されています。通常は内服のみであるため、静脈注射に移行することはありませんが、MDMAのユーザーは覚醒剤にも手をだすことが多く、病院に救急搬送された患者さんの尿から覚醒剤とMDMAの両方が検出されるということも少なくありません。
つづく
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
21 「クスリ」を上手く断ち切るには①(全4回) 2005/8/13
前回は、「(違法な)クスリは絶対にやってはいけないが、手を出す気持ちも理解できないわけではない」、という話をしました。その最大の理由は、「クスリ」を使えば、容易に「日常」から抜け出して「非日常」の世界に飛び込むことができ、そこで得られる興奮や快感は、人生に感動を与えることもありうる、というものです。
けれども、私は医師として、そして個人としても、違法なクスリには断固反対します。反対するだけでは、単なる「正論の振りかざし」であり、説得力がないかもしれませんが、これは反対するしかありません。ただ、代替案も提案したいと考えています。
その前に、まずは違法薬物を分類して、その危険性を考えていきましょう。
現在の日本で流通している最大の違法薬物は「覚醒剤」です。一般的に覚醒剤とは、アンフェタミンとメタンフェタミンのことを指しますが、現在の日本で圧倒的に流通量が多いのはメタンフェタミンであり、輸入先は北朝鮮が多いと言われています。そして北朝鮮製のメタンフェタミンは非常に純度が高く、例えばタイなどで出回っているアンフェタミンなどよりも格段に「良品」だとされています。
覚醒剤は通称「シャブ」と呼ばれます。しかし、最近は、この「シャブ」という言い方がイメージが悪いからなのか、「スピード」とか、その頭文字をとって「エス」と呼ばれることが多いようです。
また1950年代まで日本の薬局で簡単に買えた「ヒロポン」も覚醒剤であります。おそらく、世界中で覚醒剤が合法だったのは日本だけだと思われます。
様々な違法薬物があるなかで、覚醒剤だけが日本の社会の隅々まで浸透しており、最もメジャーな薬物になっている原因は、日本人の気質に合うからではないか、と私は考えています。後で述べますが、「大麻」は覚醒剤に比べて、危険性が少ないですし、所持していても罪は軽いですから、大麻の方が流通していてもよさそうに思うのですが、現在の日本では圧倒的に覚醒剤の方が出回っているような印象があります。
覚醒剤を使用すると、ハイテンションになり、「眠れずに仕事や勉強ができる」とか「確実にダイエットできる」という効能がありますから、現代の日本人の需要に合っているのかもしれません。実際、合法だったヒロポンの効能書きには「痩身」と記載されていたそうです。
ヒロポンは、タクシーの運転手など、徹夜で仕事をしなければならない人たちの間で流行していましたが、現在も、徹夜で仕事をしなければならないサラリーマンや、一夜漬けをしなければならない学生などが覚醒剤をよく使用しているようです。また、ダイエット目的に使う女子高生や主婦も珍しくありません。
「エスは上手につきあえば怖くないよ」という人たちは、静脈注射ではなく、吸入(いわゆる「アブリ」)をしているようです。これは覚醒剤をアルミ箔に載せて気化させ、その気体を鼻から吸入するという方法です。たしかに、この方法だと緩徐に体内に吸収されますから静脈注射よりは安全であるかもしれません。しかし、最初はアブリで満足できていても、そのうちにそれでは足りなくなり、いずれ静脈注射に移行するという例は珍しくありません。
吸入、静脈注射以外によく用いられている方法が、「女性の腟壁に塗布する」という方法です。前回お話した「覚醒剤中毒の女医」も、そうやって使っていたという報道がありますが、この使用法が恐いのは、女性が気付かないうちに男性がコンドームに塗布して挿入し、女性はかつて経験したことのない快感に襲われ、その男性から離れられなくなることがある、ということです。なかには、その快感を「真実の愛に出会った」、ととらえる女性もいるかもしれません。そうなると、心理的にもその男性から離れられなくなってしまいます。
覚醒剤についてあまり知識のない人は、ここまで読めば「それほど悪いものでもないのかな・・・」と思われるかもしれません。しかし、ここからが覚醒剤の恐ろしいところです。
医薬品も含めて、多くの薬物には「耐性」というものがあります。最初は少ない量で満足できていたのに、そのうちに同じ量では効かなくなるということです。そのため、量を増やしたり、吸入から静脈注射に移行したりするようになってきます。量を増やしても、また効かなくなり、そのうちにどんどんと一度に使用する量が増えていきます。
覚醒剤はもちろん違法薬物ですから、裏ルートから購入しなければなりません。(といっても最近はごく簡単に入手できるようですが・・・。)そして、価格は決して安いものではありません。普通のサラリーマンやOLの給料ではとうてい追いつかなくなります。借金をできるところからは限界まで借りるようになります。前回紹介した女医のような立場であれば、病院から金になるものを持ち出すようなこともおこないます。
家族や友人からも借金するようになります。この時点になれば、本人も返済の目途がつかず、家族や友人を裏切ることになることは理解できるはずなのですが、一度覚醒剤に蝕まれた身体は正常な思考回路を妨げます。それまで信頼関係にあった家族や友人に対して、平気で嘘をつくようになります。そして、そのうちに家族や友人から見放されていきます。
覚醒剤は、キマっているときには、たしかにハッピーかもしれませんが、これが切れたときにいわゆるリバウンドが確実にやってきます。まるで廃人のように気力や活力がなくなり、脱力感に襲われます。こうなると、再び覚醒剤をキメるまで、まともな行動ができなくなります。もちろん仕事などできません。そして、そのうちに職を失うことになります。
職を失い、家族や友人に見放されても、身体は覚醒剤を欲しがります。この頃には全身の臓器がボロボロになっており、もはや生命の存続も危なくなります。夜道で倒れているところを補導されたり、救急搬送されたりすることになります。こうなると、逮捕までは時間の問題で、法的な制裁を受けることになるわけです。(病院の尿検査などで覚醒剤反応が陽性になることがあり、これを警察に通報すべきかどうかはむつかしいところです。覚醒剤取締法と医師の守秘義務の兼ね合いがあるからです。これについては改めて述べたいと思います。)覚醒剤中毒で、病院に搬送された人は、入院や懲役になればまだましな方で、実際に命を落とす人も珍しくありません。
ところで、覚醒剤は、初犯であれば、販売や製造などをしていない限り、実刑になることはあまりなく、執行猶予がつくと言われています。(これに対し、違法薬物の王様である麻薬は、個人で使用しているだけでも、まず間違いなく実刑となります。)
私は、覚醒剤取締法を直ちに改正して、個人の使用のみでももっと重い刑にすべきだと考えていますが、現在のところそのような動きはないようです。ちなみに、タイではタクシン政権が、違法薬物対策に力を入れ、覚醒剤を大量に所持している人間には容赦なく射殺するような方針を取るようになりました。これはいきすぎたきらいもあり(なんとこれまでに5000人以上もの人々が射殺されており、冤罪も少なくないと言われています)、反省の声も上がっているようですが、タイ国がドラッグ天国から、違法薬物を入手しにくいクリーンな国に変わったのは事実です。射殺まではいきすぎだと思いますが、日本も何らかのかたちで覚醒剤取締法を強化してほしいと私は考えています。
さて、決して忘れてはならない覚醒剤の恐ろしい点がもうひとつあります。それは「感染症」です。
実際に、覚醒剤を静脈注射する際に用いる注射針の使いまわしで、B型肝炎やC型肝炎に罹患した人は少なくありません。もちろん、HIVに感染することもあります。
「静脈注射するから感染するのであって、アブリなら心配ないじゃないか」、そのように言う人もいます。
しかし、先ほど述べたように、覚醒剤に耐性ができ、吸入では効果が得られなくなり、静脈注射に移行する人は決して少なくありません。そして、パーティなど複数で覚醒剤をキメるような場合、ひとりが注射を始めると、そのうちにひとりふたりと注射するようになり、自分だけが注射をしないわけにはいかなくなることもあります。(これをpeer pressureと言います。)
さらにもうひとつ問題提起をしておきましょう。最近、新型のHIVがニューヨークで発見されました。通常、HIVはヒトに感染してからおよそ10年間の潜伏期間を経てAIDSを発症しますが、抗HIV薬を適切なタイミングで内服することによりAIDSの発症を防ぐことができます。ところが、この新型HIVは、感染してから1年未満でAIDSを発症するのです。さらに、抗HIVが無効だというのです。
そして、ここからが問題なのですが、この新型HIVに罹患した人の全員が覚醒剤を使用していたというのです。しかも、注射ではなく、吸入で、です。
これはどういうことなのでしょうか。おそらく新型HIVに罹患した人たちは、注射針の使いまわしではなく、性行為など他のルートで感染したのでしょう。しかし、覚醒剤を高頻度で使用していたために、体内に何らかの変化が起こり、その変化がウイルスを新しいタイプにしたのではないか、私はそのような可能性を考えています。
つづく
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第20回(2005年8月) 覚醒剤中毒の女医
2005年3月25日、大阪の40歳の女医が、覚醒剤取締法で逮捕されました。
報道によりますと、兵庫県尼崎市内の病院で副院長をしていたこの女医は、2003年9月から04年10月にかけて病院に納入された向精神薬や注射器を売り覚醒剤の購入資金に充てていました。
私が『医学部6年間の真実』のなかで詳しく述べたように、覚醒剤中毒の医師というのは何も珍しくありません。覚醒剤をキメてから、手術をおこなっていた外科医と麻酔科医が逮捕された「兵庫医大覚醒剤事件」を皮切りに、数々の「シャブ中ドクター」が明るみになりました。今でも年に何度かは、新しく発覚したシャブ中ドクターが新聞に載ります。もっとも、珍しくなくなったせいか、最近では大きく取り上げられることはないようですが……。
さて、今回逮捕された大阪の女医は、単に覚醒剤をキメたかった、という以外に複雑な事情があったようです。そのあたりが、『裏モノJAPAN』という雑誌の2005年8月号で詳しく取材されていますので、ここで簡単にご紹介しておきたいと思います。
この女医は、関西で開業医をする父親の次女として生まれ、早い時期から父親の後継者として医学部進学を義務づけられていたそうです。
予定通り、ストレートで医師になった彼女は、27歳のときに同じ医師である男と結婚しました。
ところが、その旦那が他に女をつくり結婚生活は五年で破綻し離婚に至ったそうです。
その後、友人の紹介で知り合った実業家の男性と恋愛関係になりました。アメリカで事業をしたいというその男を追いかけ、彼女は勤務していた病院をやめてアメリカに渡ることになりました。
その男から、「運転資金に」とか「事業資金に」などと言われて彼女は900万円以上を貢いだそうです。
ところが、結局その男は、彼女に一方的に別れを告げて去っていったそうです。
彼女は2001年に日本に帰国しました。寂しさを紛らわすためにツーショットダイヤルにのめりこんだそうです。そして、そこで知り合って付き合いだすことになったのが、覚醒剤の密売人だったというわけです。
間もなく、二人は同棲を始めました。その男が覚醒剤を静脈注射していることはすぐに分かったそうですが、彼女はとがめるどころか、「自分にもちょうだい」と言ってすすんで自分の腕に注射をしたといいます。
それだけではありません。セックスの際、腟壁に覚醒剤を塗るようになったそうです。かつてない興奮と快感が身体をつらぬき、一度その味を覚えると、彼女自ら積極的にセックスを求めるようになったといいます。
この頃から、男の帰りを待ちきれず、ベランダに体を乗り出し、男に向かって手を振る姿がよく目撃されていたそうです。
彼女は当時、複数の病院でアルバイトをしていましたから、それなりの収入はあったのですが、覚醒剤にハマりだせば貯金などすぐに底をつきます。そこで、彼女は自分の勤務する病院から、大量の注射器や向精神薬を持ち出して資金にあてていたというわけです。
逮捕後、取調官から問われても彼女は同じ供述を繰り返すばかりだったといいます。
「あの人が好きだったのです。あの人との絆を強くしたかった・・・・」
2005年3月24日の大阪地裁の初公判で、彼女は起訴事実をすべて認めました。すべてを失った、という悲愴感は彼女にはなかったそうです。彼女のなかにはまだその男との「絆」が残っているのかもしれません。
「シャブ中ドクター」が新聞の隅に載ることは珍しくなく、2005年7月にも、福岡大病院に勤務する41歳の男性医師が、覚醒剤取締法で逮捕されました。この男は、当直時にも「眠気覚ましに使った」などと供述しているそうです。
覚醒剤の効果は、「テンションがあがる」「眠らなくても平気」「食事を摂らなくてもエネルギッシュに働ける」などがありますし、違法ではあるものの、現在の日本では割と簡単に入手することができますから、その怖さを知っているはずの医師でさえ、気軽に手をだしてしまうのかもしれません。
最近は、あまりにも覚醒剤を使用する人が増えたために、「気をつければ中毒にならない」とか「お酒と一緒で度を越さなければハッピーになれる」とかいう噂が出回り、以前に比べると、それほど危険視されなくなっているような印象を受けます。
また、覚醒剤は実は合法的に入手する方法もあります。「リタリン」という名前の向精神薬は、覚醒剤の類似物質で、大量に内服すると、シャブとして出回っているメタンフェタミンと同じような効果が得られます。医師であれば簡単に入手できますから、「シャブ中ドクター」は見つかっていないだけで、かなりの数に昇るのでは、と私は考えています。
しかしながら、「覚醒剤には絶対に手を出すべきではない」という事実は変わりありません。
たしかに、中毒にならないように上手く使いこなしている人もいるようですが、そういう人たちがいつ中毒にならないとも限りませんし、中毒になって、職を失った、家族を失ったという人は枚挙にいとまがありません。
さて、中毒症状になりやすいパターンのひとつが、今回逮捕された女医がしていたような、パートナーとの「セックスでの使用」です。もちろん私は経験がありませんが、覚醒剤を使用したセックスの体験者に話を聞くと(患者さんと仲良くなるとこういう話もしてくれます。当然、昔の話であり、現在は立ち直っているからこそ話せるのでしょう)、普通の(覚醒剤なしの)セックスができなくなると言います。快感が何十倍にもなり、何時間おこなっていても疲れが来ないと口を揃えて言うのです。そのため、三日三晩、ほとんど休憩せずに、セックス浸りになることもあるそうです。覚醒剤を使うことによって、強烈な快感が数時間も続き、射精にいたらなくなりますから、早漏で悩んでいる男性のなかには特にやめられないという人もいます。また、覚醒剤をコンドームに塗られて腟に挿入されれば、女性は知らないうちに依存症になることもあります。
それまでに経験したことのない興奮と快感に襲われるわけですから、パートナーとの精神的な結びつきが強くなることも想像に難くありません。
おそらく、この女医もそうだったのでしょう。離婚後に出会って、アメリカまで追いかけて大金を貢いだ男には一方的に別れを告げられ、ツーショットダイアルで知り合った男性にやさしくされた彼女は、寂しさと男の優しさに覚醒剤がもたらす興奮と感動が加わったために、その男から離れられなくなったのでしょう。
仕事や生活を「日常」とすると、一部の恋愛やクスリは「非日常」に相当します。「日常」では常識であることが、「非日常」の世界では必ずしも常識ではなくなり、ある意味では「つまらないもの」に見えることがあります。そして、つまらなくなった常識を捨てて、「非日常」の興奮に身を投げたくなることがあります。例えば、家庭や仕事を投げ出して、駆け落ちするカップルや、これ以上やると社会に復帰できないことを知りながらハマっていくクスリなどはその典型です。
そして、これらは善くないことであることは自明ではありますが、そうなっていく気持ちもまた理解できないわけではありません。
だから、私は、「密売人と付き合ってはいけません」とか「クスリをやってはいけません」などというようなことを、「常識人が振りかざす正論」として主張するつもりはありません。単なる正論の主張だけであれば、おそらくいずれ逮捕されることに気付きながらも、その男との覚醒剤を使ったセックスから逃れられなかったこの女医の気持ちも理解できるはずがないのです。
覚醒剤に手を出すべきでないのは自明でありますが、覚醒剤に手を出してしまう人がいる理由も理解しなければならないと私は考えています。そして、そういった人たちが、覚醒剤から解放されるような手助けをするのが医師のつとめである、と私は思います。
次回から、そのあたりを考えていきたいと思います。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
第19回(2005年7月) 「年齢が理由で医学部不合格」は妥当か
群馬大学医学部を受験した東京都目黒区の主婦(55歳)が、「合格者平均以上を得点しながら年齢を理由に”門前払い”されたのは不当」と入学許可を求めて前橋地裁に提訴した、という事件が報道されました。
簡単にこの事件を復習しておきましょう。
2005年の群馬大学医学部を受験したこの主婦(佐藤さん)は、5月下旬に同大学から送られてきた封筒を開けて驚いたそうです。
合格者の平均点は551.2点。佐藤さんの得点はそれを10.3点上回る561.5点だったそうです。「本当は合格だったのが、間違って不合格にされたのでは」、佐藤さんはそう考え、すぐに大学に電話を入れました。
応対した担当者は「合格者の平均点を超えているのに、なぜ不合格なのか」という問いに、「センター試験、個別試験、小論文、面接、調査書のいずれかに著しく不良のものがある場合は不合格もありうる」と入試要項の一文をそのまま読み上げたといいます。
「では私の場合、著しく不良だったのは面接だったのか」と佐藤さんが尋ねると、この担当者は「総合的に判断した」と言葉を濁したそうです。なかなか引き下がらない佐藤さんに、担当者は「個人的見解」と前置きした上でこう言ったそうです。
「国立大学には長い年月と多額の費用をかけて社会に貢献できる医師を育てる使命がある。しかしあなたの場合、卒業時の年齢を考えたとき社会に貢献できるかという点で問題がある」
このときに、佐藤さんは自分の年齢が不合格の理由だったことを悟りました。「時間を費やし、入れ込んで勉強しただけに、年齢が理由で不合格にされるのは、やり切れない。「総合的な判断」で年齢が考慮されるなら、最初から入試要項に明記しておいてほしかった。何のために三年も頑張ってきたのか…」
この思いは当然でしょう。ちなみに、2003年には熊本大学を卒業した六十六歳の男性が医師国家試験に合格しています。
さて、この事件をめぐって、医師専用の掲示板やメーリングリストでは、多数の意見が飛び交いました。新聞などマスコミの取材に答えた医師もいます。
例えば、2005年7月5日の東京新聞の記事によりますと、都内の外科医(41歳)は「多額の税金を使う国立大学医学部の場合、育てた医者の将来的な社会的貢献度を尺度にするのは間違っていない。この女性が一人前の医者になるのは60歳代半ばで、体力的に難しい。研究医ならまだしも、女性が希望する臨床医は難しいだろう」との見解を述べています。
医師が意見を述べている掲示板やメーリングリストでもこのコメントに同調するような意見が多数ありました。
「高齢者医学部入学反対者」の述べている理由をまとめてみると次にようになります。
#1 高齢者(何歳から高齢者かは分かりませんが)が医学部合格を果たして卒業したとしても、一人前の医師として働ける期間は長くない。これは税金の無駄遣いである
#2 医師は他の職業よりも体力と知力が要求される。体力が衰えて、記憶力の鈍った高齢者に適切な医療はできない
#3 高齢の研修医は、年下の指導医や看護師などのパラメディカルが指導をおこないにくく迷惑である
#4 高齢者が医学部に入学することによって、若い受験生がひとり不合格になる。この若い受験生が気の毒である
#1が最も多い意見ですが、#2や#3や#4の意見を述べる医師も少なくありません。
では、ひとつひとつを検証していきましょう。
まず、#1について。「医師として働く期間が短いのは税金の無駄遣い」というのであれば、医学部合格者は全員が医師となり、長期間働かなくてはならなくなります。けれども、実際は、医学部に合格したものの途中でドロップアウトする者もいますし、医師になったけれども結婚や出産を機に退職する女性医師は珍しくありません。数は多くありませんが、他の職業に転職する者もいます。
たしかに、自治医大や防衛医大のように、卒業までの費用全額を行政が負担しているような大学では、卒業してから一定期間は行政の人事命令どおりに働く必要があるでしょう。
しかしながら、群馬大学も含めて普通の大学ではそのような規制はないはずです。そもそも憲法では「学問の自由」が保障されています。年齢を理由に不合格とするのは明らかに憲法違反です。
私は27歳で医学部に入学しました。27歳であればほとんどどこの大学でも年齢を理由に不合格になることはないでしょうが、私が面接でも答えた医学部の志望動機は「臨床医になりたい」ではなく、「社会学的な観点から医学を学びたい」というものでした。結局、臨床医になったわけですが、当時の私は「卒業までに税金が投入されるのは分かっているが、それは他の学部でも同じで(金額は違うでしょうが)、学問を学びたいという理由があり合格点を取れば入学を拒む理由はどこにもない」という考えをもっており、それは今でも変わっていません。
佐藤さんの件に話を戻すと、彼女が言うとおり、年齢を理由に不合格にするならば、大学は初めからそれを示すべきで、願書を受けつけるべきではありません。そんなこと、誰が考えても分かることで、わざわざ司法の判断を待つこともないように思えます。おそらく、大学側としては、裁判では年齢以外の不合格の理由を立証しようとするのでしょう。
次に#2について。それを言うなら、障害者の医学部入学も制限すべきという理論にならないでしょうか。現在の医師法では、全盲者であっても全聾者であっても医師国家試験を受験することができます。医学部生の間に、あるいは医師になってから、病気や事故で体力のいる仕事ができなくなる医師だっているでしょう。#2の意見を述べる人は、そういう医師らに対してどのように思っているのでしょうか。
#3はおそらく社会というものが分かっていない人が発言しているに違いありません。たいていどこの職場でも上下関係というのは年齢ではなくキャリアで決まります。私が企業で働いていたときは、年齢がずっと上の後輩がいました。また、19歳時にアルバイトでウエイターをしていたときには17歳の先輩、30歳の後輩がいました。もちろん17歳の先輩には絶対的な敬語を使いますし、私が仕事でミスをすれば容赦なく手や足が出ました。そして、30歳の後輩には容赦なく厳しい指導をしました。これは社会の常識で当然のことです。
こんなこと、学生のアルバイトでも分かることですが、#3のような発言をする医師は社会に出たことがないばかりか、学生のときも家庭教師や塾講師など、他人から「先生、先生」と呼ばれる仕事しかしていないのでしょう。
#4は明らかに不当な年齢差別で、「高齢者は長生きしないから選挙権を与えない」と言っているのと同じようなものです。
私自身の臨床の経験で言えば、社会人を経験していて得したことは山ほどありますが、逆に損をしたことは一度もありません。社会人の経験があると言うだけで、いろんなプライベートな話をしてくれる患者さんは少なくありません。その逆に、「社会人の経験のあるような医師には診られたくない」という患者さんにはお目にかかったことがありません。
私はまだ30代ですし、(当たり前ですが)主婦の経験もなければ、身内を介護した経験もほとんどありません。そういう意味では、佐藤さんの視点は私とはまったく異なるわけで、佐藤さんだからこそ心を開く患者さんもきっと少なくないでしょう。
誤解を恐れずに言うならば、年齢ではなく「プライドを満たしたい」とか「裕福な暮らしがしたい」という理由で医学部を受験する輩を不合格にしてもらいたいものです。
参考:東京新聞2005年7月5日「向学心を阻む“年齢の壁” 高齢化時代にチャンスを」
メディカルエッセイ第148回(2015年5月)「高齢の研修医はなぜ嫌われるのか」
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
18 6月20日は何の日か知ってますか? 2005/7/6
「○○の日」というのをちょこちょこ目にします。例えば、6月4日は、ム(6)シ(4)だから「虫歯の日」、11月12日は、イイヒフだから「皮膚の日」、2月22日は、ニャンニャンニャンで「猫の日」なんていうものもあります。
では、6月20日な何の日がご存知でしょうか。この日は、日本で決められた日ではないため、「虫歯の日」や「皮膚の日」のように数字の語呂合わせからできてはいません。
正解は、「世界難民の日」です。「世界難民の日」は、2000年の12月に国連総会で制定され、2001年6月20日に第1回が実施、今年は第5回目ということになります。これを記念して、日本全国各地でも様々なイベントが開かれています。
ところで、この「世界難民の日」をご存知の方はどれくらいおられるでしょうか。今年の6月20日は月曜日で、私はその日の新聞やテレビに注目していたのですが、私の知る限り、このことを取り上げたマスコミはゼロでした。「猫の日」や「虫歯の日」であれば、関連したイベントがマスコミに取り上げられるのに、です。
「世界難民の日」がマスコミで報道されないのは、それだけ日本国民の難民に対する関心が低いからでしょう。誰も興味を示さないからマスコミも取り上げないということだと思います。私は、報道しないマスコミを批判しようとは思いません。けれども、年に一度でもいいから、日本では考えられないような劣悪な環境で生活せざるを得ない人々、特に子供たちがいることを、何らかのかたちで考える機会があってもいいのではないかと思います。
私は以前別の場所で、「寄付をするならユニセフやUNHCRなどしっかりとした団体に寄付をしましょう」という旨を主張しました。街頭で募金活動をしている団体のなかには、相当うさんくさいものもあり、寄付金が正当に使われているかどうか、はなはだ疑わしいと思うからです。
最近、残念なことに、私のこの考えを裏付けるような事件が報道されました。
大阪の34歳の男性と60歳の男性が、職業安定法違反(虚偽広告)容疑で逮捕されたという事件です。
新聞(産経新聞2005年5月31日)によりますと、容疑者は、NPOを名乗って大阪市内の繁華街でアルバイトを雇って街頭募金をする際、「ケーキ製造」などと虚偽の求人広告を出していたというものです。二人は昨年十月から十一月に発行された求人雑誌で計六回にわたって、大阪市内の喫茶店名義でアルバイトの求人広告を掲載し、実際は街頭募金のスタッフとして雇うつもりだったのに、ケーキの製造や試食、清掃業務など虚偽の名目で募集した疑いが持たれているとのことです。
容疑者らは、当日、集合場所に来た十代後半から二十歳代前半の若者らに、「ケーキ製造などのアルバイトはすでに募集が終了した。募金活動だけが残っている」と嘘をつき、募金箱やそろいのジャンパーなどを貸して、そのまま街頭募金をさせていたといいます。
募金場所は大阪のキタやミナミの繁華街で、一度に数十人を雇用し、「NPO緊急支援グループ」という団体名で難病の子供たちへの支援を呼びかけさせ、終了後、集まった募金と引き換えに時給千円のアルバイト代を支給していたとのことです。募金は多い日で一日に百万円近くあり、これまで数千万円以上を集めたそうです。
彼らは、実際に50万円を、あるNPO法人に寄付し、あたかも慈善活動をしているように見せかけるという巧妙な手口を使い、残りの金額は使途不明になっているそうです。
容疑者のひとりは、株式投資やソフトウエアの開発、昆虫育成などの事業失敗で多額の借金を抱えていたそうですが、日頃から贅沢な暮らしをしており、周囲からは不振がられていたという報道もあります。
これほど許しがたい事件もないと思いますし、この団体に寄付をされた人達は抑えがたい憤りを感じられていることだと思います。
さて、「よく分からない街頭募金に協力するのではなく、ユニセフやUNHCRなど世界規模のしっかりとした機関に寄付をすべき」、というのが私の考えですが、それで問題がまったくないかというと、残念ながらそういうわけでもありません。その理由を述べていきましょう。
まず、その寄付金が、災害などで実際に困っている末端の人々のところにまで届いているかどうか疑問が残ります。例えば、スマトラ沖津波の被害者が多いインドネシアでは、津波から半年が経った最近になってようやく被災者にいくぶんかのお金が支給されたそうです。しかもとうてい生活できないようなわずかな金額だそうです。
これを報道した「クローズアップ現代(2005年6月27日放送)」によると、ユニセフなどの機関が寄付したインドネシアの行政機関で、不正に横領された可能性が強いそうです。
また、タイのピピ島では、タイ政府が多額の資金を投じて島を再建しようとしているのですが、それは次回津波が起こったときに被害を少なくするようなインフラの整備に重点が置かれ、海岸線に沿って建築物の構築がすすめられているそうです。ところが、海岸線には大勢の住民の住居や商店が存在し、政府の計画がすすめられると、立ち退かざるを得ません。そういった住民たちは、津波で家や店をつぶされ、必死の思いで建て直したのにもかかわらず、政府の勝手な方針によって再度撤退を余儀なくされるというわけなのです。これでは、結果的には我々の寄付金が、結果的に被災者を苦しめるという皮肉なことになってしまいます。
大きな機関からの寄付金とはまったく正反対の観点からみてみましょう。
タイのプーケットは、津波で大きな打撃を受けたのにもかかわらず、現在急速なピッチで復興が実現しています。これはひとつには、タクシン政権がピピ島よりも、プーケットの観光事業再建に力を入れ、巨額の資金を投入していることもありますが、実際には、外国人が、店を建て直したり、ビーチをきれいにしたりと、ボランティアとして活動していることが大きな理由のようです。彼らはもちろんボランティアとして無償で復興を手伝っているのです。
何ヶ月もに渡り、プーケットに留まり、無償で復興を手伝っている彼ら彼女らのバイタリティはどこからくるのでしょうか。そういえば、私が昨年1ヶ月間、ボランティア医師として滞在した、タイのロッブリーのパバナプ寺でも、西洋人のボランティアは短くても半年、長ければ数年の単位でボランティアに来ていました。短ければ数日、長くても一ヶ月から二ヶ月間しか滞在しない日本人のボランティアとは大きな違いです。
私のある知人が言っていたのは、「西洋人は文化として寄付やボランティアの習慣がある」、ということです。
私は、これは日本人もそのまま見習うべきだと考えています。長期間ボランティアをしている西洋人は、必ずしも裕福な人たちばかりではありません。にもかかわらずボランティアに従事するのは、それが「文化としての習慣」になっているからでしょう。
最近、「子供が小さいうちから家族で海外旅行をしたい」、と考える家庭が増えているそうです。子供の頃から、日本よりも発展途上の国に行き、現地の人々の生活を見学したり、あるいは、そういった地域にボランティアに来ている外国人と交わり、仕事を手伝ったりすることは素晴らしい体験になるのではないでしょうか。
今から何年かがたったとき、6月20日は何の日かを知らない大人たちに、若い世代がそれを教えて、世代間で難民について考える、そんな時代がきてほしいものだと思います。
投稿者 | 記事URL
2013年6月17日 月曜日
17 なぜあの学生は退学にならないのか 2005/6/16
2005年5月に、大阪大学でとんでもない事件が発覚しました。
大阪大学医学部の学生が、「ネイチャー・メディシン」という医学誌に発表した論文のなかで、なんとデータの捏造があったと言うのです。
少し詳しくみてみると、その学生が発表した論文に使われている画像データが複数個所で同じものが使われていることを、研究室の研究員が発見したそうです。直ちにその学生を問いただしたところ、学生は、一部で意図的に画像を改変したことを認めたそうです。また、この学生が国内に発表した論文にもデータが未熟なところがあり、論文の取り下げの申請がおこなわれたそうです。
この学生は、「マウスの実験はきちんとやった」と言い、画像については「いいデータを早く出さなければと思った」と話したそうです。
しかし、「実験はきちんとやった」などというこの学生の言葉をいったい誰が信じることができるでしょうか。
この論文の内容は、肥満に関する遺伝子についての研究結果であり、将来的には肥満の予防あるいは治療に応用できると考えられていたものです。学生は、医学をばかにしているばかりか、他の研究者の信頼もなくしていると言わざるを得ません。
捏造したデータを平気で発表する研究室の信頼も落ちるでしょうし、これでは大阪大学医学部から発表されるすべての論文、さらには他学部の論文、もっと言えば、日本人のすべての論文の信憑性が疑われることになるかもしれません。
この学生のとった行動は、法的にどれくらい裁かれるべきなのか私には分かりませんが、断じて許せるものではありません。捏造したデータを使った論文を平気で発表できるこの学生は、いったい医学というものをどのように考えているのでしょうか。真実を解明することに情熱を燃やし、着実に研究を積み重ねている研究者に対し、この学生はどのように思っているのでしょうか。法的には無罪であったとしても、この行為は、科学に対する「冒とく」であり「侮辱」であり、二度と科学に携わることをさせてはいけない、と私は考えます。
たしかに、人間は誰でも「失敗」することがあります。昨今マスコミで報道されている「医療過誤」にしても、「失敗」から患者さんの生命をなくしたものもあります。それに対して、「人間は誰でも失敗するものだから過失のある医師を許してほしい」というつもりはありません。けれども、過失をした医師とて、患者さんのためになると思うことをしているのです。例えば、患者さんを救おうと思って手術をおこない、結果的にそれが「失敗」となり、法的に過失が認められたというわけです。
それに対し、データ捏造の学生は、明らかに「悪意」があります。この学生の行為で、命を亡くした人はいないでしょうが、「悪意」のある行為を断じて許してはいけない、と私は思います。
それにしても、なぜこの学生は退学にならないのでしょうか。退学にならないどころか、報道では名前さえ公表されていません。この学生は現在医学部の6回生だということですから、来年の今頃は医師免許を所得して、研修医として患者さんの治療をおこなうことになるのでしょう。しかし、こんな医者を誰が信用することができるでしょうか。
この医学生の起こした事件とほとんど同時期に、北海道のある医師が殺人容疑で書類送検されました。この医師は、入院中の患者さん(当時90歳)の人工呼吸器のスイッチを切り死亡させたというのです。この医師がスイッチを切る時点では、この患者さんはすでに意識不明であり、もしもスイッチを切らなかったとしても死亡した可能性が強いとのことです。
報道によりますと、この医師と患者さんの関係は非常に良好で、患者さんの長男の妻は、「まるで親子のように仲が良かった。近所でも評判のいい先生だった。」と発言しているそうです。そして、殺人容疑での書類送検に対して、「こんなことになるなんて…。先生はまだ若いので、先のことが心配です」とつぶやいたとのことです。また、呼吸器のスイッチを切ることについては家族の同意があったと報道されています。
現在の日本では、安楽死に関する法的整備がきちんとなされているとは言い難い状況であり、このようなケースに遭遇することは私にもしばしばあります。法的には、いったん作動させた人工呼吸器を止めることはむつかしいことが予想されますから、患者さんが高齢で、先が長くないと思われるときには、あらかじめ患者さんと家族に、呼吸状態が悪くなったときに人工呼吸器を使うかどうかを確認しておくことが多いと言えます、
おそらく、この医師もそのようなことを考えていたと思います。これは、私の推測ですが、この患者さんは、まだ先が短いという状態ではなく、呼吸器の説明をするタイミングになかったのではないかと思われます。ところが、何らかの理由で、突然呼吸困難に陥り、緊急的に気管内挿管をおこない、人工呼吸器を接続する事態になったのではないかと思われます。高齢者は、例えば、誤嚥などによって突然呼吸不全に陥ることもあり、それはこの医師も予想していたのでしょうが、患者さんと「親子のように仲がよかった」こともあり、急変したときの対応について、本人や家族にそういった話をするタイミングが結果的には遅くなったのではないでしょうか。
安楽死や尊厳死といった問題は、また改めて述べたいと思いますが、こういった問題は、単に法律を制定すれば解決するといった問題ではありません。「死」とは、法律で決められるものではなく、それぞれ個人が決めるべきものだと思うからです。
この医師が殺人容疑で書類送検されたのに対して、データを捏造した医学生は名前の公表がなされないばかりか、1年後には医師として患者さんと接することになります。このふたりのうち、どちらが患者さんの立場にたった医師と言えるでしょうか。答えは自明でしょう。私が患者ならこの書類送検された医師を信頼します。
法律というものは、本当の意味でものごとを正しく判断できない、というのが私の持論です。本当の意味での罪の重さと、法律で裁かれる罪の重さは必ずしも相関していないように感じることがよくあります。
例えば、「殺人」という罪を考えたときに、自分の低次元な欲求を満たすために少女を誘拐し殺害した未成年者は数年間の刑期を終了すれば社会に復帰します。これに対し、ヤクザが自分の親分の仇をとるために、抗争相手のヤクザを殺害すれば、ヤクザという理由だけで一般人よりも長い刑期を命じられるのが普通です。これら2つの例では、本当の意味でどちらが重い罪を受けるべきでしょうか。
もうひとつ例を挙げましょう。大阪市では、スーツの支給を始め様々な手当てを市役所の職員に供給していたことが発覚し、税金を不当に使用していることが明らかになりました。これは職業倫理上許されないことですが、誰も職を失っていません。
数年前に、中部地方のある警察官が、裏ビデオ所持で逮捕された犯人の所有していたビデオを自宅に持ち帰り懲戒免職になったという事件がありました。
市民の税金を不当に使っていた大阪市の職員と、ビデオを自宅に持ち帰った警察官のどちらが懲戒免職になるべきでしょうか。
私個人の考え方ですが、法律に従って生活することが正しく生きることではないと思います。私の基準は、「法律」ではなく、「良心」や「情熱」「人情」といったものです。アウトロー的な言い方をすれば、「法律」ではなく「掟」に従うべきということです。
「掟」に照らして考えれば、データ捏造は絶対に許せる行為ではありません。多くの医師や研究者、それに間接的には患者さんをも裏切る行為になるからです。これに対し、日頃から仲がよかった患者さんの人工呼吸器のスイッチを家族の同意を得た上で切る行為は「法律」には反しているとしても、「掟」の基準では許されるのです。
私は『偏差値40からの医学部再受験』で、医学生のカンニングを激しく非難していますが、これも「掟」を踏みにじる行動だからです。
どのような仕事についても、自分なりの「掟」をもっていれば道を踏み外すことがなくなるのではないでしょうか。仕事だけではありません。あらゆる行為、あらゆる人間関係に「掟」を適用すれば、変わらざる真理と価値観に従い、正しく生きていけるということを私は確信しています。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第186回(2018年7月) 裏口入学と患者連続殺人の共通点
- 第185回(2018年6月) ウイルス感染への抗菌薬処方をやめさせる方法
- 第184回(2018年5月) 英語ができなければ本当にマズイことに
- 第183回(2018年4月) 「誤解」が招いた海外留学時の悲劇
- 第182回(2018年3月) 時代に逆行する診療報酬制度
- 第181回(2018年2月) 英語勉強法・続編~有益医療情報の無料入手法~
- 第180回(2018年1月) 私の英語勉強法(2018年版)
- 第179回(2017年12月) これから普及する次世代検査
- 第178回(2017年11月) 論文を持参すると医師に嫌われるのはなぜか
- 第177回(2017年10月) 日本人が障がい者に冷たいのはなぜか
月別アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (125)