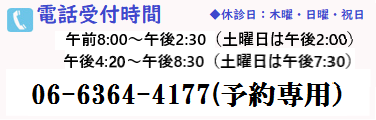2017年5月29日 月曜日
2017年5月29日 ワクチン1回では不十分~後遺症も残る麻疹脳炎~
感染研感染症疫学センターが毎月発行している「病原微生物検出情報」2017年5月号に興味深い麻疹(はしか)の症例が報告(注1)されました。この症例は、非常に示唆に富むもので、私がこの報告を読んだ最初の印象は「起こるべくして起こった」というものです。まずはこの症例を簡単にまとめてみましょう。
********
【症例】36歳男性。生来健康。
2016年8月中旬より出張でジャカルタ滞在。渡航前は会社から推奨のあったA型肝炎ウイルスワクチン(以下HAV)、 B型肝炎ウイルスワクチン(以下HBV)、日本脳炎ワクチン(以下JE)の3種を接種。9月上旬顔面腫脹、その2日後に高熱と全身の発疹、さらに意識が混濁し現地病院に緊急入院。気管内挿管がおこなわれ人工呼吸器管理となった。様態改善せず、入院4日目にシンガポールへ移送。移送後も痙攣発作を認め麻疹脳炎の診断確定。抗けいれん薬開始。症状改善傾向にあり人工呼吸を中止。発症26日後に帰国し日本の医療機関に入院。
入院時、意識清明であったが、舌が正常に動かない、飲みこむのが不自由など麻疹脳炎の後遺症を認めた。胃に管を入れ栄養を摂りリハビリテーションが開始された。発症から68日後に退院となり退院時には食事が可能となったが、現在も後遺症が残存。
********
さて、この症例、渡航前にワクチンを接種していなかったのはなぜでしょう。会社から推奨のあったのは、HAV、HBV、JEの3種のみ。ジャカルタのみなら狂犬病は必須ではなくこれはいいとして、なぜ麻疹と風疹が含まれていないのか、この点が大いに疑問です。そして、会社は医学の専門家ではないですから責任を問われないかもしれませんが(とはいえ、なぜ産業医がこの従業員に麻疹ワクチンの推奨をしなかったのかは追及されることになるかもしれません)、ワクチンを接種していた医師は何をしていたんだ、と感じる人もいるでしょう。
では医師は何をしていたのか。ここからは私の予想です。おそらくワクチンを実施した医師は、麻疹や風疹ワクチンの必要性についても説明したはずです。そして、おそらくこの会社員の男性は、「会社から推奨されていないので大丈夫です」というようなことを言ったのではないでしょうか。
なぜ私にこのような推測ができるかというと、太融寺町谷口医院にも同じようなケースが多数あるからです。この患者さんが言う「大丈夫です」というセリフ、最近頻繁に聞くのですが(もしかすると「流行語」なのでしょうか)、言葉以外から伝わってくるニュアンスとしては「余計なことを言わないで」というふうに感じられることもあり、そうなると現実的にはそれ以上のことが言えず、せいぜい「他の感染症のこともしっかり学んでおいてくださいね」と助言するくらいのことしかできません。
実際には、ほとんどのケースで「大丈夫」でなく、たいへん危険な状態で現地に渡航することになります。では、患者さんがすべて悪いのか、というとそうではなく、会社の辞令や命令で現地渡航するわけで、それに伴う費用は会社が出すべき、という考えは分からなくはありません。決して安くないワクチンを自分のポケットマネーで負担しなくてはならないのは腑に落ちないと考えるのでしょう。
ですが、海外では(本当は日本でも)「自分の身は自分で守る」が原則です。特に感染症は「正しい知識」があれば防げることが多いのです。もしもこの男性が会社に頼らずに、自分自身でジャカルタの医療状況について調べていたらきっとこのようなことにはならなかったに違いありません。
また、もしも会社の上司や人事部が、または産業医がもう少し現地の疾患のことを知っていたら違った対策をとることになったに違いありません。あるいは、ワクチンを接種した担当医が、聞くのを嫌がる男性を引き留めてでも麻疹の危険性を忠告していたら…。
この男性の後遺症が今後どうなるのかは公表された報告からは分かりません。今のところ、この症例は一般のメディアでは報じられていないようですが、関係者のみならず、海外旅行(それは観光も含めて)に行く機会のあるすべての人が知っておくべきだと私は思います。
注1:下記URLを参照ください。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/1047-disease-based/ma/measles/idsc/iasr-in/7279-447d02.html
投稿者 | 記事URL
2017年5月28日 日曜日
2017年5月28日 妊娠中のマクロライド系抗菌薬は流産のリスク
妊娠中は薬に頼らざるをえない事態を可能な限り避けなければなりません。規則正しい生活を心がけて感染症の予防をしっかりとおこなうことが重要です。
しかし、いくら気を付けていても妊娠中に風邪をひくことはあります。ほとんどの風邪はウイルス性ですから治療には何もせずに休養をとるのが一番です。そして、市販の風邪薬の多くは妊娠中には飲んではいけない成分を含んでいます。
では、ウイルス性ではなく細菌性の風邪をひいたとき、あるいは細菌性の膀胱炎や腸炎に罹患したときにはどうすればいいでしょうか。細菌性であったとしても日ごろ健康な人であれば、上気道炎でも膀胱炎でも腸炎でも水分摂取と安静で治ることもあります。ですが、高熱が続いたり倦怠感が強くなってきたりした場合は抗菌薬を使わざるを得ません。
では、妊娠中の抗菌薬はどれくらい危険なのでしょうか。抗菌薬と流産の関係を検証した研究が最近発表されました(注1)。
研究の対象者はカナダ・ケベック州在住で1998年から2009年の間に妊娠して自然流産した15~45歳の妊婦8,702人。対照者は妊娠週数及び妊娠した年を一致させた87,020人の妊婦です。
流産と抗菌薬使用の関係を検討した結果、流産した女性の16%が妊娠初期に抗菌薬を使用していたことが判りました。一方、対照者は13%未満でした。特筆すべきなのはマクロライド系抗菌薬のアジスロマイシン(先発品の商品名は「ジスロマック」)の流産のリスクは1.65倍、クラリスロマイシン(同じく「クラリス」「クラリシッド」)なら2.35倍にもなることが判ったことです。(尚、この研究では、メトロニダゾール、ニューキノロン系、テトラサイクリン系などの流産のリスクにも触れていますが、これらは日本では妊娠中には「禁忌」とされており使用されることはありませんからここでは言及しないでおきます)
************
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)にも妊娠中の患者さんが少なくありません。妊娠前から谷口医院をかかりつけ医にしている人のみならず、従来かかりつけ医を持っていなくて妊娠後に谷口医院を受診するようになったという人もいます。妊娠中は、出産に関することであれば産科の担当医を受診しなければなりませんが、妊娠中に風邪をひいたときなどは、産科医を受診すると他の妊婦さんにうつすリスクがありますから、産科医を受診しにくいのです。
妊婦さんが受診された場合、それがどのような疾患であったとしても薬の処方は最小限にします。(もっとも、谷口医院ではどのような患者さんにも「薬は最小限にすべき」と伝えていますから、実際には妊娠の有無でそれほど変わるわけではありません)
妊婦さんに抗菌薬を処方せねばならない場合、効果が期待できそうであればペニシリン系を選択します。なぜなら、この世界最古の抗菌薬(注2)は、歴史的に大勢の妊婦さんに使用されてきており相対的に安全であることが分かっているからです。
問題は、ペニシリンが役に立たないケースです。ペニシリンはグラム陽性菌とカテゴライズされる細菌には比較的よく効きます。グラム陰性菌に対しては過去にはよく効いていましたが、最近は耐性菌が多く効かないケースも目立ちます。また、細胞内寄生菌といって顕微鏡では観察できない菌のいくらかはペニシリンがまったく無効です。比較的よくあるのがマイコプラズマ、クラミドフィラ(クラミジア)(注3)など咳が主症状となる上気道感染です。この場合、通常は日本ではマクロライド系の抗菌薬を選択するのが一般的です。けれども、今回の研究が示しているように、これだけ流産との相関が高いなら、症状をみながら薬を使わずに自然治癒に期待する選択を積極的に考えるべきかもしれません。
細菌性のものも含めて風邪(上気道炎)を予防するには日ごろのうがい・手洗いが重要です。また、夫に風邪症状があるときには家に帰らないようにしてもらうこともあります。妊娠すれば、可能な限りの風邪をひかない対策を実行すべきなのです。
さて、谷口医院でもしばしば相談を受けるのが「性器クラミジア感染症」です。この疾患は大半が無症状であり、妊娠初期におこなわれる「妊婦検診」で発覚します。谷口医院をかかりつけ医にしている人は、「産科で薬を飲まないといけないと言われたけど大丈夫でしょうか」と言って受診します。また、何らかの事情(おりものの異常がある、無症状だが危険な性交渉があった)などで谷口医院を受診し、性器クラミジア感染症が見つかることもあります。そして妊娠していたという場合がときどきあります。
上気道炎(風邪)の場合とは異なり、性器クラミジア感染症(クラミジア子宮頚管炎)の場合は自然治癒の期待はできません。そして、無症状であったとしても治療しなければなりません。大切な胎児をつつんでいる子宮にそのような細菌が棲息していれば胎児に感染するリスクが出てくるからです。そして、クラミジアにはペニシリン系(およびセフェム系抗菌薬)は一切無効です。また、妊娠していなければクラミジアにも使用できるニューキノロン系やテトラサイクリン系抗菌薬は妊娠中の使用は「禁忌」とされています。結局、マクロライド系抗菌薬しか選択肢がないのです。
しかし、今回の研究が示しているようにマクロライド系は流産のリスクがあるわけです。結局のところ、妊娠する前にきちんと性感染症の検査をしておく、というのが最も大切ということになります。
注1:この論文のタイトルは「Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion」で、下記URLで概要を読むことができます。
http://www.cmaj.ca/content/189/17/E625.abstract?sid=48adccb6-9169-4c74-b40e-8a8f1f50dcd9
注2:世界最古の抗菌薬はペ二シリンではない、という意見もありますが、世界的にコンセンサスが得られているのはペニシリンです。詳しくは下記コラムの注2を参照ください。
毎日新聞「医療プレミア」「日本初の女性医師を生涯苦しめた病とは」
注3:クラミドフィラ(クラミジア)には「言葉の混乱」があります。①クラミジア肺炎、②クラミジア・シッタシ(オウム病)、③クラミジア・トラコマティス(性器クラミジア感染症)のうち、①と②はクラミドフィラという呼び方が正確なのですが今も「クラミジア」と呼ばれるのが一般的です。最近(2017年4月)、2人の妊婦が死亡したことが報じられたクラミジアは②です。詳しくは下記コラムを参照ください。
投稿者 | 記事URL
2017年5月23日 火曜日
第172回(2017年5月) 医師に尋ねるべき5つの質問
医師の世界が世間では理解されていない、と感じることがしばしばあります。もちろんある程度は仕方がありませんし、「こんなに頑張ってることを知ってください」と言うつもりもありません。どのような業界でも少しくらいは世間から誤解されていることがあるのはむしろ当然でしょう。
ですが、その「誤解」のために、医師が大きな不利益を被る、さらに結果として多くの患者さんにも損失を与えることがあったとしたらどうでしょう。そのような「誤解」を世間に与えかねない「うんざりさせられるニュース」をまずは紹介したいと思います。
医師の情報サイト『M3.com』に「「増収のために不要な検査」は事実か」という記事(注1)が2017年5月3日に掲載されました。この事件のあらましをまずはまとめてみましょう。
2015年12月10日、当時69歳の女性が国立病院機構横浜医療センターに入院しました。診察の結果、心臓カテーテル検査が必要と判断され実施され、結果、心臓に異常はありませんでした。しかし、女性は「増収のために不要な検査をされた」という理由で病院を訴えました。
この女性は総腸骨動脈瘤という疾患が疑われて入院しています。総腸骨動脈は下半身にある動脈ですから心臓とは関係ないと思われるかもしれません。ですが、総腸骨動脈瘤が疑われるということは動脈硬化が進行している可能性があり、それならば心臓の血管の状態を評価しておくという考えは何ら間違っていません。ですから医療行為自体には「過失」があるようには思えません。
ですが、私は横浜医療センターに問題がないと言っているわけではありません。心臓カテーテル検査は多少なりとも危険が伴う検査です。ですから、緊急性がある場合を除き、その必要性と危険性を充分に説明し、また患者さんが充分に理解した上で実施しなければなりません。医師側が充分に説明したつもりであったとしても、結果的に患者さんが「知らなかった」と言えば、医師の過失の可能性が出てきます。これは同意書にサインがあったとしても、です。
したがって、危険性を知らされていなかったなら「説明義務違反」という理由で、医師や病院を訴えることには筋が通っています。ですが「増収のため」などあるわけがないのです。
横浜医療センターは国立病院です。国立病院も利益がまったくなければ存続できませんが、医師が「利益」を考えて仕事をしているわけではありません。そもそも、心臓カテーテル検査を実施しようがしまいが、その医師の給料が変わるわけではありません。上司から「今月は売上が少ないからあと〇件心臓カテーテル検査のノルマを課す」と言われるわけではありません。医師が考えているのはchoosing wisely(注2)です。つまり、「ムダな検査や投薬を減らす」のが医師がいつも考えていることなのです。
病院では、ひとりの医師が独断でものごとを決めるわけではありませんし、カンファレンスでは症例ごとに検討がおこなわれます。入院し心臓カテーテル検査を実施するような症例であれば必ずカンファレンスで取り上げられます。もしも不要かもしれない検査がおこなわれていれば、他の医師から猛烈な攻撃を受けることになります。(逆に必要な検査をおこなっていなくても責められます)
最近、医師は労働者かどうかという議論がよくおこなわれます。医師は拘束される時間が長く、病院に泊まり込むことも日常茶飯事であり、また自宅に戻っても勉強しなければなりません。どこまでを「労働」とみなすかが曖昧であり、医師の仕事は「聖域」だから労働法は適用されるべきでないという考えがあります。実際、日本医師会の横倉義武会長は2017年3月29日の記者会見で、「医師が労働者なのかと言われると違和感がある。(中略)医師の雇用を労働基準法で規定するのが妥当なのかを抜本的に考えていきたい」と述べました。
医師はお金のために働いているわけではない、と言うときれいごとに聞こえるかもしれませんが、これは大筋で事実です。病院勤務の場合、どの科であろうが給料が変わるわけではありませんし、歩合制でもありませんし、ノルマもありません。ですから、循環器内科医が、今月は〇件の心臓カテーテル検査を実施しなければ…、などという発想にはならないのです。
開業医の場合も(以前も述べましたが)、医療法人であれば解散するときに内部留保はすべて国に没収されますし、choosing wiselyをいつも考えています。我々が苦労するのは「いかに増収」ではなく、「いかにムダな検査や投薬を減らすか」です。「金払うって言うてるやろ!」と患者さんに暴言を吐かれながらも、我々は必要なことのみをおこなっているのです。
なんでこんな簡単なことが”聡明な”弁護士に分からずに「増収のため」などと言いだすのか…、と嘆きたくなりますが、おそらく実際には弁護士はそんなことは百も承知しているはずです。弁護士が裁判で「増収のため」という理屈を持ってくるのは、そういう戦略をとった方が裁判を有利に進められるからでしょう。それは、「とにかく勝てばよい」という弁護士の理屈に則れば正しくて、原告の女性には喜ばれるのかもしれませんが、社会には迷惑です。
このような報道がおこなわれると、「医療機関は増収のために検査をやることがあるんだ」と世間に思われる可能性があります。すると、患者さんと医師との間の信頼関係が損なわれることになりかねません。もちろん、すでに(信頼できる)かかりつけ医を持っている人はそのようには思わないでしょうが、今から医師を探すという人は、その病院が増収のための検査をしないかどうかを見極めなくては、と思うかもしれません。
さて、このニュースを読んで、どうにも「後味」が悪いのは、弁護士のうんざりさせられる戦略だけではありません。患者さんのためにおこなった心臓カテーテル検査を「説明を聞いていたら受けなかった」とどうして言われなくてはならないのか、担当医の立場に立てばとてもやるせない気持ちになります。担当医は、検査で異常がなかったことを患者さんに伝えるときには「きっと喜んでもらえるだろう」と思ったに違いありません。それが、患者さんから「説明をきちんと聞いていれば検査を受けなかった」という言葉が返ってきたというのですから悲しくなります。
もちろん、先述したように、どれだけ医師が一生懸命に説明していても患者さんが理解できていなければ医師の説明義務違反という「過失」になります。それは分かるのですが、なんとも寂しいというか、このようなニュースが増えると医療者側も患者側もお互いが疑心暗鬼になってしまい、コミュニケーションがうまくいかず治る病気も治らなくなるのではないかと危惧します。
こういう話題になるとよく出てくるのが「きちんとコミュニケーションをとりましょう」という議論で、これは正しいのですが、具体的に患者さんが何をすればいいのか分かりません。そこで、すぐに使える医師への効果的な「5つの質問」を紹介したいと思います。といってもこれは私のオリジナルではなく、世界の多くのchoosing wiselyのウェブサイトに掲載されています。「choosing wisely five questions」でネット検索すればすぐに出てきます。その「5つの質問」を下記に記します。(この「5つの質問」は過去のコラムでも紹介したことがあります)
①その検査や治療は本当に必要なのでしょうか?
②その検査や治療にはどのようなリスクがありますか?
③もっとシンプルで安全なものはないのですか?
④もしもそれをおこなわなかったとすればどんなことが起こりますか?
⑤それはどれくらいの費用がかかりますか?
これを読んで「そんなこと、医師に聞くのは失礼では?」と感じる人もいるかもしれません。ですが、太融寺町谷口医院の患者さんは、日ごろからこういう質問をよくします。これにはおそらく「地域差」が関係しています。
以前、バンコクのホテルで勤務する知人(タイ人)に聞いた話があります。アメリカ人は何かあればすぐにフロントに文句を言ってくるのに対し、日本人は帰国してから「丁寧な苦情の手紙」を送ってくるそうです。おそらく大阪人はアメリカ人と”感性”が似ているのではないか、というのが私の意見です。
実はこの「5つの質問」、2017年2月に開催されたある学会で私の発表に取り入れました。その演題のタイトルは「大阪発のchoosing wisely」。この「5つの質問」を日本の医療現場で広めることができるのは大阪人をおいて他にはない、というのが私の言いたいことです。
************
注1:下記URLを参照ください。
投稿者 | 記事URL
2017年5月23日 火曜日
第165回(2017年5月) ステロイドの罠と誤解
当たり前の話ですが、薬の使用はいかなるときも最小限にしなければなりません。たしかに長期間使用することを前提にした薬剤も多数ありますが、「少しでも減らす」ことを念頭に置いて開始しなければならないものの方が圧倒的に多いと考えるべきです。
前回の「はやりの病気」で紹介したベンゾジアゼピンはその最たるもので、依存症に苦しみ、離脱を試みても禁断症状に辛い思いをしている人が少なくないことを述べました。ベンゾジアゼピン以外で特に使用に注意しなければならないのは、鎮痛剤と抗菌薬であることも述べました。
今回は「ステロイド」の話です。ステロイドこそ、使用にはいくら慎重になってもなりすぎることはなく、わずかな使用でも副作用について熟知しておかなければなりません。では、なぜ前回のコラムで指摘した「慎重に使用しなければならない3つの薬」にステロイドを入れなかったのか。それは他の3種に比べて、使い過ぎて副作用に苦しむ人はそれほど多くないからです。
ですが、まったくいないわけではありませんし、離脱に苦しんでいる人も「3種」に比べれば少ないというだけであり、その苦しさはときに社会生活を制限されるほどです。例を挙げましょう。
【症例1】40代女性
通年性のアレルギー性鼻炎で、寝る前にセレスタミン(一般名は「ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤」)を毎日2錠内服。それを6ヶ月継続しているとのこと。最近倦怠感が強く太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)受診。
この倦怠感とセレスタミンに関係があるかどうかは分かりません。しかし、セレスタミンを毎日2錠で6ヶ月は明らかに多すぎます。採血をおこなうとコルチゾールと呼ばれる体内で自然に合成されるステロイドの値が異常低値を示しています。ステロイドを飲んで血中濃度を上げれば自然につくられるステロイドホルモンが増えないのは当然です。「倦怠感とセレスミタンの関係は100%の確証をもって<ある>とは言えないが、セレスタミンをやめなくてはならない」と説明し、セレスタミンをゆっくりと減らしていきました。コルチゾールの値も少しずつ上昇し、半年後には正常値となり、倦怠感もすっかりなくなっていました。
実は似たような例は少なくありません。このセレスタミンという薬(後発品もたくさんでています)、漠然と長期投与されている例が目立ちます。症例1のように1日2錠ならまだ”まし”かもしれません。私がみた最も”ひどい”例は、1日6錠を1年間内服していた男性がいました。この男性は「前医からそんな強い薬とは聞いていなかった…」と嘆いていました。ちなみに、セレスタミンの添付文書には「用法」の説明として、「1回1~2錠を1日1~4回経口投与」と書かれています。1回2錠1日4回の内服を続ければ大変なことになります。
次はある意味でもっと”ひどい”例です。
【症例2】20代女性
アマチュアバンドのヴォーカリスト。東京在住。ステロイドを飲めば喉の炎症がとれていい声が出ると(本人が言うには)「知り合いの医師」に言われ、デキサメタゾンというステロイドを毎日内服。大切なステージの前には増量して内服しているとのこと。明日の大阪公演のため来阪したがデキサメタゾンが切れてしまっている。処方希望。
この女性、ステロイドの危険性をまるで理解していません。ただ、このケースは判断に迷います。この女性にとっての「明日のステージ」はステロイドの副作用よりも大切なものであることが理解できるからです。この女性はかかりつけ医をもっておらず、いろんな医療機関で同じステロイドを処方してもらっていることが判りました。そこで私は、危険性を充分に説明したうえで、「今回は処方するが東京に戻ってからかかりつけ医をもって相談すること」を条件に最小限の処方をおこないました。
たしかに風邪や大声を出したことで喉(喉頭)に炎症が生じた場合、ステロイドを内服すればその炎症が速やかに軽減します。ですから、谷口医院でも、例えば「あさってが自分自身の結婚式」とか「年に一度の合唱コンクールが明日」という場合は、危険性を説明した上で処方することもあります。けれども、これは例外中の例外であり、症例2の女性のように毎日内服などは絶対におこなうべきでありません。
ここでよくある「誤解」を紹介したいと思います。ステロイドを欲しがる人がよく言うのは、「世の中にはステロイドを毎日たくさん飲まなければならない病気もいっぱいあるでしょ」というものです。たしかに膠原病や炎症性腸疾患、一部の自己免疫疾患などで高用量のステロイド内服をせざるを得ないケースもあります。ですが、その場合、ほぼ確実に、骨がボロボロになり、おなかの周りにぜい肉がつき、肌はニキビに悩まされ、血糖値が上がります。精神状態が乱れることもあり、感染症にかかりやすくなり、そして寿命が短くなることは覚悟しなければなりません。こういった副作用を未然に防ぐために、いろんな薬を併用することになります。ですがすべての副作用を防げるわけではありません。
もうひとつよくある、これは本当によくある「誤解」を紹介します。それは「短期間なら安全でしょ」というものです。たしかに谷口医院でも、ごく短期間の処方をおこなうことがあります。適切なタイミングで適切な量のステロイドを使用しなければ、症状が悪化し入院が必要になることもあるからです。しかし、「短期間」が数日以上になれば問題です。
最近、ステロイド内服薬は短期間の使用でも、敗血症、静脈血栓塞栓症、骨折といったリスクが2~5倍に高まることが医学誌『British Medical Journal』2017年4月12日号(オンライン版)で紹介されました(注1)。この研究は米国でおこなわれ、1,548,945人分のデータベースが解析されています。ステロイド内服薬がわずか6日間使用されただけで、敗血症(感染症が重症化して全身に細菌が巡ること)のリスクが5倍にもなることが判ったのです。
この研究が興味深いのは、ステロイド内服がどのような目的で使われたかが調べられていることです。上位5つの疾患が、上気道感染症(いわゆる「風邪」のこと)、椎間板障害(頚部痛や腰痛など)、アレルギー、気管支炎、下気道疾患(肺炎のこと)です。これらはいずれもありふれた疾患ですが、ステロイド内服を使わなければならないケースはほとんどありません。谷口医院の例でいえば、これらの疾患にステロイド内服を処方するケースは年間数例で、処方期間はせいぜい2~3日です。
ただし、アレルギー疾患に対し、内服ではなく「吸入」「点鼻」「外用」などのステロイドを処方することはよくあります。過去にも述べたように(注2)、喘息は、上手にステロイド吸入を使うことによって症状が安定し、高い安全性を維持し、費用も安くつかせることができます。吸入ステロイドがなぜ安全かというと、作用するのは気道粘膜であり、血中には吸収されないからです。これは点鼻薬も同様です。「点眼」の場合は眼圧上昇に注意しなければなりませんから長期使用はNGです。外用は、皮膚の副作用を考慮しなければなりませんから最小限の使用にします。アトピー性皮膚炎の場合は、いかに早くステロイドを終わらせてタクロリムスにバトンタッチするかが基本です(注3)。
最後に、私の母校大阪市立大学医学部の石井正光元教授の言葉を紹介しておきます。
ステロイド一錠減らすは寿命を十年延ばす
************
注1:この論文のタイトルは「Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study」で、下記のURLで概要を読むことができます。
http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1415
投稿者 | 記事URL
2017年5月11日 木曜日
2017年5月 就職の相談
患者さんから就職の相談をされたときどうしていますか?
少し前、複数の医師と雑談をしていたときに私がふった話題です。そこにいた医師は全員が無言に…。どうやら私は場違いで無神経な発言をしてしまったようです。しばらくして一番ベテランの医師が言うには「そんな相談されない」とのこと。
一方、私は研修医の頃から就職についての相談をしばしば受けています。おそらくこの理由のひとつは、私が医学部再受験の本を上梓したからだと思います。私は今もFacebookやLINEなどのSNSを一切おこなっていませんが、クリニックやNPO法人GINAのサイトから相談メールがよく届きます。数年前までは、就職よりも医学部再受験についての相談が多く、就職については、看護師、作業療法士、臨床心理士といった医療系の仕事についてのものが多かったのですが、最近は医療系以外の相談、例えば大学生から新卒の就職について相談されることもあります。
質問や相談をする人のすべてが私の本を読んでいるわけではありません。おそらく日ごろから「困ったことがあれば何でも相談してください」と言っていることが原因のひとつでしょう。この「困ったことがあれば」というのは、一応は「医療のことで」という前提で話しているつもりなのですが…。恋愛相談を受けることもしばしばあります。以前は恋愛関係の相談はLGBTの人たちからのものがほとんどだったのですが、最近はストレートの人からも寄せられるようになってきました。もちろん私は万能カウンセラーではなく、それほど期待に応えられるわけではないのですが…。
ですが、困っている人を放っておくわけにはいきません。結果として役に立たないことの方が多いのですが、ほとんどの相談に対して返答しています。(一部、明らかにふざけたような質問は無視しています)
話を「就職」に戻しましょう。私がひとつめの大学(関西学院大学)を卒業した1991年はバブル経済真っ只中で「空前の売り手市場」と言われていました。今年(2017年)は、そのバブル時代以上に求人率が高いそうですが、91年当時の方が時代背景もあり企業側が”過剰な”対応をしていました。説明会は高級ホテルの立食パーティが当たり前、入社前に海外旅行を用意する企業や新車一台プレゼントしてくれる会社まであったほどです。ですからよほど「狭き門」の企業を目指さない限りは、就職試験で落ちるということがなかったのです。
また、医師はいつの時代も人手不足ですから、やはりよほどの「狭き門」の病院でない限り、就職できないということはありません。医学部の学生時代のアルバイトも、医学生自体が稀少な存在ですから、どこに行っても珍しがられてすぐに採用ということになりました。
つまり、私は「職を探す」ということについてこれまで一切の苦労をしたことがなく、試験や面接で落とされた経験が一度もないのです。常識的に考えれば、こんな私に就職の助言などできるはずがないのですが、ものすごく都合のいい解釈をすれば、私は「職探しで一度も失敗したことがない男」となるのかもしれません。また、今は人を採用する側にいますから、こんな人はNGでこういう人はOK、ということが多少は分かるつもりです。特に医療職についてはそれなりに助言ができると思います。
では、さっそく私が考える「職探しの極意」を紹介したいと思います。まず「就職」と「受験」は異なります。どちらも「運と縁」が関与しますが、受験に比べて就職はその傾向が桁違いに高くなります。そして、このことを初めから理解しておくべきです。もしも希望しているところに就職できなかったとしても、それはあなたに実力がなかったからではなく「運と縁」がなかったと考えるべきです。就職の場合、新卒時を除けば就職時期は「適宜」となるのが普通です。最近、私の友人が「超」がつくような優良企業に就職が決まりました。めったに中途採用をしない会社です。求人が出た時期と友人が職を探していた時期が”たまたま”重なり、さらに偶然にも他にめぼしい応募者がいなかったようです。
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院)」でも、募集して新しい採用が決まり求人活動が終了したそのわずか数時間後に、職歴も志望動機も申し分がなく「是非一緒に働きたい!」と感じる人からの履歴書が届いたということが過去に何度かありました。そして採用した人が、1ヶ月もしないうちに”本性”を現し、とうてい医療者には向いていないことが判り…、仕事のパフォーマンスは最悪で患者さんからのクレームが後を絶たず…、ということも。
一般に(とはいえ、これは特に私に強い傾向があることは認めます)、就職希望者が「未熟ですが一生懸命がんばりますのでお願いします!」と熱意を強く訴え、そして「なぜここで働きたいのか」その理由がまともなものであれば、たとえ、これまでの経歴が不十分であっても、試験の点数が低くても、その熱意が高ければ採用に至ります。逆に「私のこれまでの経験で充分にやっていけます」というような態度の人は、谷口医院では不採用になることが多いといえます。
しかし、この採用方法はときに”裏目”に出ます。一度、面接時に泣きながら「前の職場で辛かった。新たに当院でがんばりたい」と強く訴えた看護師を採用したことがあります。しかし、採用後、最初のうちは多少の”がんばり”を見せてくれたものの、数か月もたてば、言われたことしかしない、言われたことも文句をつけてやらない、という態度に変わっていきました・・・。
ですが、私はこれでいいと思っています。「裏切られても信じることから…」というのが私の考えです。こういう医療者と接した患者さんには申し訳ないですし、開き直るわけではありませんが、もしも当院の医療者が患者さんに不快な思いをさせることがあればそれは私の責任であり、精一杯のフォローをします。
仕事に流動性のあるこの時代、新卒の人も含めて「生涯働き続ける職場」を探す必要はないと思います。では、どのような基準で就職先を探せばいいのか。それは「自分の勉強になるかどうか」だと私は考えています。実際、私自身がそのような観点のみでこれまで仕事やアルバイトを探してきました。(かなり都合のいい解釈をすれば、私が面接や就職試験で一度も落とされたことがないのは、この考えを面接官や雇用者に汲み取ってもらったからかもしれません)
私はこれまでアルバイトも含めれば20以上の職場で働いていますが、面接のときに、「貴社(貴院)のためにがんばります」と言ったことは一度もありません。毎回私が主張するのは「貴社(貴院)で勉強させてください」ということです。もしかすると、こういうことを言う者は少なく「珍しいから」という理由で採用されるのかもしれませんが、これは私の本心です。その企業(や病院)のために働くなどと考えたことはただの一度もなく、私が考えることはただひとつ。「その仕事は自分の勉強になるか」というとても身勝手なものです。
私にとって仕事とは「お金を稼ぐ手段」ではなく「勉強」であり、どこの職場でも少しでも学ぶことを考えます。会社員時代は、英語、貿易事務、マーケティングなどを学ぶ”学校”でしたし、医師になってからはひとりひとりの患者さんが私にとっては「貴重な臨床症例」です。医学部の学生時代、何人かの先生から「患者さんから学ばせてもらえ」と言われ、当時はこの意味がよく分からなかったのですが、医師になってから日々実感しています。よりよい医療をおこなうには教科書だけでは不十分で臨床経験を重ねなければならないのです。
私は、医療者は(それは狭い意味の医療者だけでなく事務職や受付も含めて)、この「患者さんから学ぶ」そして「患者さんに貢献する」という姿勢が絶対に必要だと考えています。医療機関のために働く必要は一切ありません。患者さんから学びそして貢献するというこの精神(私はこれを「医療マインド」と呼んでいます)があれば、必ずやりがいをもって気持ちよく働くことができ、そして患者さんから「感謝」されます。
谷口医院のこれまでのスタッフを振り返ると、「医療マインド」を持っている者は、日ごろから私に患者さんの相談や質問をし、患者さんから感謝の言葉をかけられ、そして”卒業”するときにも患者さんの話をします。逆に、退職時に患者さんの話が一切でてこないスタッフもいます。そういうスタッフは例外なく「医療マインド」がなく、実際、それなりに長く働いたとしても患者さんから感謝の言葉がほとんど寄せられていません。
人のために貢献できる職業は医療者だけではありませんが、医療者は「貢献していること」を日々実感することのできる恵まれた職業だと私は考えています。「医療マインド」は絶対に必要ですが、これを身につけるのに特別な訓練は必要なく、「困っている患者さんの力になりたい」と思うことができればそれで「合格」です。(ですが、簡単そうにみえてこれができない人も世の中にはいるのです)
最後に阪急東宝グループの創始者小林一三氏の言葉を著書『私の行き方』から紹介したいと思います。これを書かれたのはおそらく戦前だと思われますが、今読んでも胸に響きます。
せち辛い世の中ではあるが、生きがいのある生活だとか、人格を認めてもらわなければ困るとか、そういう理屈、それは正しい主張であるとしても、それらの議論にこだわらず、己を捨てて人のために働くのが、かえって向上昇進の近道であると信じている。
投稿者 | 記事URL
2017年5月11日 木曜日
2017年5月11日 白ワインは女性の酒さのリスク
医療者からみると「よくある疾患」なのに、あまりメディアなどでは取り上げられず知名度の低い皮膚疾患のひとつが「酒さ」です。酒さは顔面にできる慢性の炎症性疾患で治療に難渋することがしばしばあります。
ほとんどの患者さんは「なんでこんな病気になったのですか?」と尋ねます。遺伝的な要因を除外すれば、私の印象でいえば、一番多いのがステロイドの不適切な使用、二番目が紫外線です。飲酒が原因や悪化因子になるのもほぼ間違いありません。どのようなお酒がいけないのかについてははっきりしたことは分かっていませんが「ワイン」という説が有力です。
女性のアルコール摂取は酒さの発症因子。なかでも白ワインのリスクが高い…。
医学誌『Journal of the American Academy of Dermatology』 2017年4月1日号(オンライン版)にこのような研究が報告されました(注1)。
この研究の対象者は「看護師健康調査II」(Nurses’ Health Study II)と呼ばれる調査に参加した82,737人の女性で、追跡期間は14年(1991~2005年)、4年ごとに飲酒に関する情報が収集されています。追跡期間中4,945人が新たに酒さを発症しました。
酒さの発症とアルコール摂取量には相関関係がありました。1日あたり1-4グラムのアルコール摂取で酒さの発症リスクが1.12倍に上昇、30グラムだと1.53倍にもなっていました。アルコールの種類で分類してみると、白ワインのリスクが最も高いことがわかりました。
************
アルコール30グラムというのは、ビールなら大瓶1本、日本酒なら1.5合、ワインならグラスに2杯強といったところです。
男性についても大酒飲みが酒さになるのはおそらく間違いありませんが、今回の研究は女性のみを対象としたものであり、この程度の飲酒が男性でもリスクになるのかどうかは分かりません。
また、しっかりとした確証はないものの、赤ワインは酒さの(発症ではなく)「悪化」のリスクという説があります。
注1:この論文のタイトルは「Alcohol intake and risk of rosacea in US women」で、下記URLで概要が読めます。
投稿者 | 記事URL
2017年5月11日 木曜日
2017年5月10日 スタチンで糖尿病患者の下肢切断リスクが低下
ここ数年「スタチン」と呼ばれるコレステロールの薬が話題になることが増えてきました。その理由はおもに2つあります。
1つは、2010年9月に日本脂質栄養学会が「コレステロールは下げる必要がない」といった内容の発表をおこなったことです。このときマスコミは「コレステロールは高いほど長生きする」といった報道をおこない随分と物議を醸しました。コレステロール値は下げるべきか下げなくていいのか、実はこの論争は今も続いており、日本脂質栄養学会は「下げるべきでない」という考えを今も変えていません。一方、日本動脈学会をはじめとするいくつかの大きな学会や日本医師会は従来どおりの基準を守るべき、つまり高ければ治療すべき、という考えです。(このあたりの詳細は過去のコラム(注1)を参照ください)
もうひとつ、スタチンが話題になるのは「スタチンを内服することにより糖尿病のリスクが上昇する」と言われだしたからです。フィンランドの大規模調査ではっきりと有意差をもってこれが実証され、使用に慎重さが求められるようになりました。ただし、スタチンの種類にもより、例えばプラバスタチンは逆に糖尿病のリスクが3割も下がるという調査もあります。(詳細は過去のコラム(注2)を参照ください)
問題なのは、自分自身の判断でこれまで処方されていたスタチンを勝手にやめてしまう患者さんがいることです。病気や薬というのは、それほど単純なものではなく週刊誌の報道をみて自分で中止したり開始したりすべきではありません。医師で意見が異なることがあるのは事実ですが、例えば「LDLコレステロールが〇〇mg/dL以上ならこのスタチンを開始すべき」と簡単に決められるわけではありません。その人の年齢、性別、体重、運動度、ライフスタイル、他の疾患の有無などを考慮して総合的に判断します。
私は過去のコラム(注2)で、スタチンはまず使うならプラバスタチンがいいということを述べましたが、盲目的にプラバスタチンを処方しているわけではありません。患者さんごとにどのスタチンが最も適しているかを判断する必要があるのです。
今回お伝えしたい情報は「スタチンの使用で糖尿病患者の下肢切断リスクが低下する」という研究です(注3)。糖尿病が進行すると下肢の血行が不良となり、切断せざるを得なくなります。このようなことはなんとしても避けなければなりませんから、血糖コントロールは非常に重要です。そして、糖尿病がある人の多くが高コレステロール血症ももっています。そのときに「糖尿病が怖いから」という理由でスタチンを自分の判断で中止するようなことがあってはいけません。今回の研究はむしろスタチンを内服することによって糖尿病の合併症を防げるとしています。
研究は台湾のものです。対象者は台湾在住で糖尿病と末梢動脈疾患を有する20歳以上の69,332人です。スタチン使用者が11,409人、スタチン以外の脂質低下薬使用者が4,430人、非使用者が53,493人です。
データベースを用いて解析した結果、スタチン使用者は非使用者に比べ、下肢を切断するリスクが25%、院内心血管死亡率が22%、全死因死亡率が27%低かったことが判りました。
************
糖尿病がある場合、LDLコレステロールの基準を低くするのが基本です。糖尿病も高血圧も肥満も喫煙も他のリスクもない場合、少々基準値を超えていてもスタチンの処方は必ずしも必要ありませんが、糖尿病があれば(もちろんその程度にもよりますが)LDLコレステロールの基準をかなり厳しくすることもあります。
結論としては、自分の判断で薬を中止するのではなく「スタチンを含めて現在の内服薬がなぜ必要か」について納得いくまで主治医と話をすることです。
注1:メディカルエッセイ第101回(2011年6月)「過熱するコレステロール論争」
注2:医療ニュース2015年4月6日「スタチンは糖尿病のリスク、使うならプラバスタチン」
注3:この論文のタイトルは「Statin therapy reduces future risk of lower limb amputation in patient with diabetes and peripheral artery disease」で、下記URLで概要を読むことができます。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン
- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?
- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる
- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性
- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる
月別アーカイブ
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (2)
- 2025年11月 (2)
- 2025年10月 (2)
- 2025年9月 (2)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (5)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (4)
- 2021年3月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (3)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (1)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (2)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (4)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (5)
- 2016年10月 (3)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (3)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (4)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (4)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (4)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (4)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (172)
- 2013年7月 (408)
- 2013年6月 (84)