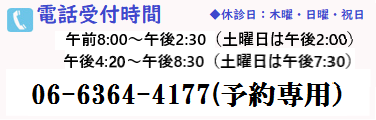マンスリーレポート
2013年3月号 医療者に向いてそうで向いてない人
いつも患者さんのことを第一に考えて行動する医療者・・・、と聞けば、「理想の医療者だ」と感じる人もいるでしょう。しかし、これが行き過ぎると、患者さんにとって、そしてその医療者にとっても、転帰が不幸なものになってしまうことがあります。
もちろん医療者は患者さんのために存在すべきであって、自分本位であることは許されません。しかし、それは自分の「自己」というものが確立していることが前提であり、どれだけ患者さんの立場に立ったとしても、一定の”距離”が必要です。
例を挙げたいと思います。
数年前、NPO法人GINA(ジーナ)の関連でタイにいたとき、私は日本人のある看護学生に出会いました。その学生とはほんの20分程度話しただけなのですが、彼女は大変興味深い話をしてくれました。
その学生は休みの度にアジアの医療施設の見学やボランティアに行っていると話していました。その学生が、アジアのある地域にある外国人の医療者がボランティアで医療をおこなっている施設に行ったとき、その地域の住民があまりにも貧困なことに驚いたそうです。
彼女がその施設に着いて初めて見た患者さんは10歳前後の女の子だったそうです。下痢と発熱でその施設にやってきて、その症状はそれほどひどくなかったのですが、彼女が衝撃を受けたのはその女の子が文字の読み書きができないことだったそうです。読み書きができないのは学校に行く余裕がないからですが、それ以前にノートや鉛筆がその女の子の家族にとってはとても高級なもので簡単に手に入れることができないのです。
そこで彼女は、「ならばあたしがこの子に必要なノートと鉛筆を買ってあげる!」とその施設のスタッフに言ったそうです。すると、そのスタッフに大笑いされ、「そんなことをしたら今日の夕方にはあなたに物をねだる子供が行列をつくるわよ。”優しい”日本人がやってきた、という噂が村中に広がり、すぐにあなたは無一文になるわ」、と言われたそうです。
この学生は大変優秀であり、このスタッフの助言の意味を理解しました。患者さんの力になりたい、という思いが”暴走”すると、ときに自らの身を滅ぼすことにつながりかねないのです。もしも彼女が、このスタッフに相談することなく自分の判断でノートと鉛筆を女の子にプレゼントしていたら、大変なことになっていたでしょう。
私はその看護学生と、それから一度も連絡をとっていないのですが、きっと立派な看護師になられていると思います。アジアのその施設にも、今もなんらかの形で支援されているのではないかと思います。
次の例は、自らを不幸にしてしまった研修医の話です。(私はこの研修医(男性)と直接会ったことがあるわけでなく、ある病院で指導する立場にある医師から聞いた話です)
その研修医(以下、A医師とします)はそのとき内科系のある病棟で研修を受けていました。あるとき摂食障害で食事が摂れなくなった20歳の女性(Bさんとします)が入院することとなり、A医師が受け持つこととなりました。A医師は大変熱心な研修医で、どれだけ忙しくても毎日最低一度はBさんのところに行き、話を聞くようにしていました。A医師の熱意が通じたのか、Bさんは少しずつ食事が摂れるようになり、2週間後には退院できることになりました。Bさんが退院するときに、A医師に「先生のおかげで元気になれました。退院してもちゃんとご飯を食べるから心配しないでくださいね」と話したそうです。
しかし、事はそううまくはいかないものです。他の多くの摂食障害をもつ若い女性と同様、Bさんは退院後再び食事を摂らなくなり、姉に連れられてその病院の外来にやってきました。今度は入院するほどでもないと判断され、数種類の薬を処方され帰宅しました。
その日の夕方、外来でBさんを診察した医師から話を聞いたA医師は、いてもたってもいられなくなりました。カルテから電話番号を調べ「自分の判断で」Bさんに直接電話をしたのです。電話に出たBさんの声には元気がありません。電話では話が噛み合わなかったと感じたA医師は、翌日の土曜日の午後に、なんとBさんの自宅を訪問したのです。電話では不機嫌だったBさんも直接A医師が家まで来てくれたことには感激したようです。しっかり治療を受けることを約束し、そのときはA医師も「来てよかった」と思ったそうです。
しかしその後もBさんの嘔吐は止まりません。精神状態も不安定になり、毎日のようにA医師に電話をするようになりました。A医師はBさんの自宅を訪ねたときに「何かあったら遠慮なく電話してほしい」と言って自分の携帯電話の番号を伝えていたのです。Bさんの電話はエスカレートしていきました。深夜でもおかまいなく電話がかかってきて、ついに「今からすぐ来てくれないと手首切っちゃう!」と言われたそうです。
A医師は心を病み、1ヶ月後には病院を去っていったそうです・・・。
さらに不幸な例を紹介したいと思います。この例はマスコミで報道されましたし、その後週刊誌などがかなり詳しいことまで取り上げましたから覚えている人も多いかと思います。
2002年12月、東京都板橋区にある当時46歳のO医師(実名が報道されましたがここでは伏せておきます)の自宅で当時28歳の婚約者Nさん(同様に実名は伏せます)がO医師に首を絞められ死亡しました。O医師は東京の精神科クリニックの院長であり、Nさんは元患者で、殺害された当時はO医師のクリニックで事務員として働いていたそうです。
この事件が世間の注目を集めたのは、普通では有り得ない医師と患者の恋愛に加え、Nさんに虚言癖があったからです。報道によれば、Nさんは、祖父が有名画家の藤田嗣治(ふじたつぐはる)で、母親は宝塚の元女優、自身の元婚約者は有名なDJでNさんはその男性の子供を身篭ったが、そのDJはエイズで死亡。自分自身も芸術のセンスがあり、坂本龍一と一緒に「戦場のメリークリスマス」を作曲した、と言っていたそうです。
当時のインターネットの書き込みなどでは、Nさんに翻弄されたO医師に同情しているものもありましたが、私はO医師がNさんに騙されていたわけではないと思っています。NさんはO医師の患者であるときに抗うつ薬を処方されていたそうですが、報道されたNさんの言動から推測すると(私がNさんを診察したわけではないので無責任な推測ではありますが)Nさんは「境界性人格障害」に該当すると思われます。
境界性人格障害に虚言癖が伴うのはよくあることで、精神科医のO医師がNさんの言葉を信じていたはずがないのです。そもそも「戦場のメリークリスマス」が流行った1983年はNさんはまだ小学校低学年なのです。
私の分析は、O医師が惚れたNさんに翻弄されたのではなく、O医師のNさんに対する同情心が行き過ぎて悲劇を招いた、というものです。つまり先に紹介したA医師と同じような構図だとみています。ただ、O医師がA医師と異なるのは、いつのまにかNさんに対する同情心が一線を超えてしまった、つまり、医師としての同情心が個人的な同情心に替わり、さらにそれが恋愛感情にまで進展するというタブーを犯してしまった、ということです。
報道によれば、O医師はフランスの哲学者ジャック・ラカンの研究者として一流であったものの(実際にラカンを研究した著作もあるそうです)、どこの医局にも属さずに他の精神科医と距離をとっていたようです。O医師はNさんを殺害した後、自らの命を絶とうとしたそうですが死にきれずに意識不明で救急搬送されました。その後意識を回復し懲役9年の実刑判決が下されています。
今は3月で受験のシーズンです。毎年春になると「医学部を目指しているのですが・・・」というメールをもらいます。医師(や看護師)を目指す人は、「患者さんのために・・・」という気持ちは大切ではあるものの、それが行き過ぎると患者さんを不幸にし、そして自らの身を滅ぼすこともあるということを知っておくべきでしょう。
最近のブログ記事
- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性
- 2025年12月 「振動裁判」は谷口医院の全面敗訴
- 2025年11月 私が安楽死に反対するようになった理由(後編)
- 2025年10月 私が安楽死に反対するようになった理由(前編)
- 2025年9月 人間に「自殺する自由」はあるか
- 2025年8月 「相手の面子を保つ(save face)」ということ
- 2025年7月 「人は必ず死ぬ」以外の真実はあるか
- 2025年6月 故・ムカヒ元大統領の名言から考える「人は何のために生きるのか」
- 2025年5月 「筋を通す」ができないリーダーは退場あるのみ
月別アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (103)