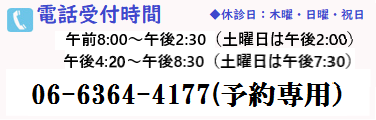メディカルエッセイ
80 それって愛ではないけれど 2009/9/20
今月のある日曜日の夜、たまたま時間ができた私は、映画『ディア・ドクター』を近くの映画館に見に行きました。
『ディア・ドクター』は西川美和監督の作品で、笑福亭鶴瓶が演じるニセ医者の動揺する心境を描いたものです。(ここで「ニセ医者」と言ってしまうと、いわゆる”ネタバレ”になってしまうかもしれませんが、他の多くのサイトですでにニセ医者であることが書かれていることと、公開してすでに3ヶ月近くがたっているということを考慮して許されるのではないかと考えました)
作品の良し悪しは別にして(いくつかの映画評論サイトを見てみましたが、のきなみ高得点がつけられています)、私がこの映画で最も印象に残った場面を紹介したいと思います。
僻地で働いていた主人公のニセ医者は、ある理由から突然失踪します。警察の調べでニセ医者であることが分かり、刑事が関係者から証言を集めるのですが、香川照之が演じる薬会社の営業マンに対して、刑事が、「なぜ(失踪したニセ医者は)医者をやろうと思ったのか」と、この営業マンに尋ねます。この営業マンは日頃からニセ医者の診療所に出入りしていて仲良くやっていました。
黙っている営業マンに対して、刑事は「(ニセ医者が僻地で医療をやろうと思ったのは)”愛”なのか」とイヤミっぽく質問します。つまり、金儲け以外に免許がないのに医師をしていた理由は、病人に対する愛情なのか、と皮肉をこめて聞いているのです。
ここで、この営業マンは<ある行動>に出ます。(<ある行動>は映画を見ていない人のために伏せておきます) この営業マンが言いたかったのは、無医村の僻地で医者をやろうと免許のないニセ医者が志したのは”愛”と呼べるようなものではなくて、もっと別のものだ、ということです。
このシーンを見たときに、私は、「そうそう!」と心の中で叫びました。
私も医師ですから「どうして医師になろうと思ったのですか」と聞かれることがしばしばあります。特に私は、文科系の大学を卒業し、いったん商社に就職し、その後医学部受検を試み、医学部に合格したのは27歳のときですから、どうしても経歴を言うとこの質問を受けることが多いのです。
実は私は、医学部入学当時は、まだ医師になることを考えていませんでした。医学部入学前は母校の関西学院大学社会学部の大学院に進学することを考えていて、医学部に進路変更したのは、医学の観点から社会学で取り上げるようなテーマを考えてみたいという思いがあったからです。要するに、私の医学部受験の動機は、「医師ではなく医学者を目指したいから」というものでした。
それが、医学部在籍中にいろいろな出来事があり(すべては書けませんが、病気に関することで医療機関を受診してイヤな思いをした、という話を何人もの人から訴えられた経験が大きいと言えます)、それで、こういう医師を目指したい、という”想い”が芽生えたのです。
その”想い”は”愛”か、と問われれば、そんな崇高なものではありません。そんな立派なものではなく、「このような医療を実践する医者がいないのだとすれば、そしてそういう問題に自分自身が気づいたのだとすれば、それは自分自身がやるしかないではないか・・・」、そういう類の”想い”なのです。
登山家であるジョージ・マロリーは、マスコミからのインタビューで「なぜエベレストに登るのか」という質問に、「そこに山があるから」(原文では”Because it is there.”)と答えたというエピソードがありますが、医師が医師を目指す理由もこれに近いものがあるのかもしれません。
医師を目指すこととエベレストに登ることを一緒にしてしまうのは、登山家の方に失礼かもしれませんが、もっと身近なところでも、この「そこに山があるから」と同じ動機で行動するケースはいくらでもあります。私は以前このコラムで「気づいたモン負けのルール」というものを紹介しましたが(下記コラム参照)、おそらく多くの人は、無意識的にこのルールに従って行動しているのではないかと私は考えています。人間は損得勘定のみで行動するわけではないのです。
話を『ディア・ドクター』に戻したいと思います。
主人公のニセ医者は、地域の人に慕われているというよりもむしろ神や仏のような扱いを受けています。困っている人から連絡が入ると、スクーターに乗りどこにでもかけつけます。また、毎晩医学書を見ながらひとりで遅くまで勉強をしています。このような姿を目の当たりにした研修医は、「一通りの研修を終えた後、再びこの村にやってきて(このニセ医者と)一緒に働きたい」、と言いだします。
しかし、その地域で、たったひとりで医療をおこなうには、”愛”ではない医師を志す”想い”があったとしても、それだけでは務まりません。ときには交通事故の重症の被害者や妊婦や乳幼児も診なければならないわけです。ありとあらゆる患者さんに対して、最終的には隣町の高次医療機関に搬送するとしても、初期診察というのはひとりでおこなわなければなりません。
映画の中では、破水がおこった妊婦を救急車の中で診察しながら、医学書をめくっているシーンがあったり、緊張性気胸といって早急に胸に針を刺さなければ命を失いかねない状態の患者を診たりするシーンがあります。緊張性気胸の場面では、ベテランの看護師の助言に従いながら処置をおこない、なんとか事なきを得るわけですが、これは見ている方もヒヤヒヤします。おそらく、重症患者を目の前にして何もできないニセ医者をみていた看護師は、このニセ医者がニセモノであることに気づいていたのではないかと思われます。
映画では、”愛”ではない別の”想い”でニセ医者が活躍している姿を描きながら、同時に、そんな”想い”だけでは医療はできない、という現実も訴えられているのです。
私は映画館を出るとき、この映画はもしかすると現役の医師に対するメッセージがこめられているのではないかと感じました。
つまり、「あなたたち(本物の)医師とこの映画のニセ医師の違いは、医師免許を持っているかどうか以外に何があるのでしょう。たしかに(本物の)医師であるあなたには、このニセ医師が持っていない知識や技術をいくつも持っているでしょう。しかし、そんな(本物の)あなたは、すべての病人や怪我人に対して何の迷いもなく最も適切な治療ができるのですか。それができないから、あなたは毎日のように勉強を続けているのではないですか。それではそんな勉強熱心なあなたと、このニセ医師の本質的な違いは何なのですか・・・」、このような問いかけをされているように感じたのです。
もしも、このニセ医師が金儲けや興味本位から僻地で医療をしていたなら、このようには感じなかったに違いありません。
”愛”ではない医師を志す”想い”が見事に描かれているが故に、それが我々医師に対する辛辣なメッセージとなっているように私は感じたのです。
最近のブログ記事
- 第186回(2018年7月) 裏口入学と患者連続殺人の共通点
- 第185回(2018年6月) ウイルス感染への抗菌薬処方をやめさせる方法
- 第184回(2018年5月) 英語ができなければ本当にマズイことに
- 第183回(2018年4月) 「誤解」が招いた海外留学時の悲劇
- 第182回(2018年3月) 時代に逆行する診療報酬制度
- 第181回(2018年2月) 英語勉強法・続編~有益医療情報の無料入手法~
- 第180回(2018年1月) 私の英語勉強法(2018年版)
- 第179回(2017年12月) これから普及する次世代検査
- 第178回(2017年11月) 論文を持参すると医師に嫌われるのはなぜか
- 第177回(2017年10月) 日本人が障がい者に冷たいのはなぜか
月別アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (125)