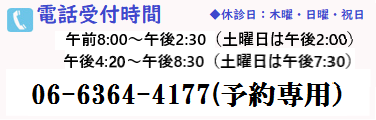2013年6月21日 金曜日
第69回(2008年10月) 「抗体」っていいもの?悪いもの?
医学用語には難解なものが多く、我々医療者側からみれば大変便利な言葉でも、患者さん側からすれば、「???」となるものが少なくありません。
例えば、「屯服(とんぷく)」「潰瘍(かいよう)」「耐性(たいせい)」などです。
これらに対しては、患者さんにとって分かりやすい言葉で表現する必要があり、そのため私は、屯服は「(痛いときなど)必要な場合のみ飲んでください」、潰瘍は「皮膚や粘膜が深いところまでただれている状態です」、耐性は「抗菌薬が効かなくなってしまった細菌です」、のように説明しています。
今挙げた3つの言葉は、比較的簡単に他の平易な言葉に置き換えることができるので、説明にはそれほど苦労しません。
しかし、なかには単純に他の言葉に置き換えるのが大変で、ときにかなりの時間を費やして説明しなければならない医学用語もあります。私がそのことを日々感じている代表的な医学用語が「抗体(こうたい)」と「炎症(えんしょう)」です。
今回は、その「抗体」についてお話したいと思います。(「炎症」については機会を改めて述べるつもりです)
まず、物事を理解するとき、とくに医学用語を理解するときにはその言葉のイメージをつかむことが大切です(と私は考えています)。
先にあげた例で言えば、「屯服」なら、「身体がしんどいときに助けてもらえる薬」ですから我々にとっての「味方」といういいイメージが沸きます。「潰瘍」は「深いところまで進行しているただれ」ですから「やっかいな病気」という悪いイメージ、「耐性」はせっかく飲んだ抗菌薬が効かなくなるわけですから悪いイメージとなります。
このように、「いいもの」「悪いもの」とする二元法は、物事をさっと理解して頭の中で整理するのに大変有用だと思われます。(頭のいい人は複雑な説明のまま理解するのかもしれませんが・・・)
話を戻しましょう。「抗体」が理解しにくいのは、抗体というものは人間にとっていいものか悪いものかという区別がつきにくいことが原因です。
「抗体」とは、「細菌やウイルスなどの病原体が身体に侵入してきたときに身体が反応してできるタンパク質」のことです。これだけでは、「それがどうしたの?」となるだけです。問題はここからです。例を挙げて考えてみましょう。
Aさんは公園に落ちていた針を踏んでしまい、感染症が心配で病院にやってきました。
この場合、我々医師は、いつその事故が起こったかを確認し、必要に応じて、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVなどの検査をおこないます(これに梅毒やHTLV-1を加えることもあります)。
どのような検査をするかはケースバイケースですが、Aさんに対しては次のような結果がでたとしましょう。
・ B型肝炎ウイルス: 抗原陰性(*1) 抗体陽性(*2)
・ C型肝炎ウイルス: 抗体陽性
・ HIV: 抗体陰性
(陽性とはその抗原や抗体をもっていること、陰性とはもっていないことです)
この場合、Aさんにとって、HIV抗体陰性は「いいこと」、C型肝炎ウイルス抗体陽性は「悪いこと」、B型肝炎ウイルス抗体陽性は「いいこと」となります。
つまり、この場合、同じ「抗体」でも、HIVとC型肝炎ウイルスは「ないのがいいこと」で、B型肝炎ウイルスは「あるいのがいいこと」となります。
これを理解するには「中和抗体」という概念を用いるのが便利です。抗体とは病原体が体内に侵入してきたときに、その病原体と戦うために体がつくる「武器」と考えることができます。そして、その武器(=抗体)が病原体を完全にやっつけることができる場合とできない場合があります。病原体を完全にやっつけることのできる武器(=抗体)を「中和抗体」と呼びます。そして、「中和抗体」ができるか、あるいは病原体をやっつけることのできない、役立たずの武器(=抗体)しかできないかはその病原体によります。
「中和抗体」ができる病原体で有名なのは、麻疹(はしか)、風疹、ポリオでしょう。これらは、ワクチンを(複数回)うつか、一度罹患すれば、それ以降はかかることがありません。そして、B型肝炎ウイルスの抗体も一度できれば一生B型肝炎ウイルスにかかることはありません(*3)。
「中和抗体」ができない病原体は、もしも体内にその病原体の抗体があれば、その病原体が体内に棲息していることになります。こういう抗体は、病原体を退治できないわけですから「役立たずの抗体」としか言いようがありません。しかし、検査をして抗体があることが分かれば、その病原体をもっていることが確認できます。そして中和抗体ができない病原体の代表が、HIVとC型肝炎ウイルスです。
ですから、HIV抗体あるいはC型肝炎ウイルスの抗体が陽性というのは、それら病原体が体内に棲息していることを示しているのです。
Aさんの例に戻れば、C型肝炎ウイルスの抗体が陽性だったので、C型肝炎ウイルスが体内に棲息していることになります(すなわちAさんにとっては悪いことです)。
そして、B型肝炎ウイルスの抗体が陽性だったので、B型肝炎ウイルスには感染したけれども現在は抗体(中和抗体)ができて完全に治癒した(もしくはワクチンをうっていて初めから抗体があった)、ということになります(すなわちAさんにとってはいいことです)。
ここまで読まれてある程度はお分かりいただけましたでしょうか。日々の診察では、例えば麻疹(はしか)の抗体検査に来た人に「抗体があってよかったですね」と検査結果を伝えて、その次の患者さんにはHIV抗体陽性(つまりHIVにかかっている)を告げなければならないというようなことがあるわけです。
何らかの機会で、医師から「抗体が・・・」という説明を聞いたときは、「それっていい抗体ですか、役立たずの抗体ですか?」と尋ねるようにすれば理解しやすいかもしれません。
************
注1 「抗原」とは、病原体の表面を構成するタンパク質のことですが、「病原体そのもの」と考えれば理解しやすいと思われます。つまり抗原陰性ということは、その病原体が体内にいない、ということです。
注2 針を踏んでしまった、などの場合、実際にはB型肝炎ウイルスの抗原(HBs抗原)だけを調べて、抗体は調べないことが多いのですが、ここでは便宜上抗体(HBs抗体)も調べたことにしています。
注3 B型肝炎ウイルスの抗体は実際には3種類(分類の仕方によってはそれ以上)あります。一生かからないかどうかはどの抗体ができているかによります。また、B型肝炎ウイルスの抗体は数年後に消えることがあるので改めてワクチンをうつべきだとする説もありますが、最近では、一度抗体ができれば数年後に抗体陰性となったとしても実際には抗体があると考えられる(ワクチン追加接種は不要)とする説が有力です。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第68回(2008年9月) 「医療はサービス業」という誤解
医療はサービス業と捉えている人がいますし、なかには医療従事者のなかにもこのような発言をする人がいるようですが、私自身は、医療はサービス業ではないと思っています。
日頃の診察で、患者さんの希望に応えられないときにこのことを感じることがあります。今日はそのあたりを考えてみたいと思います。
診察室で患者さんから言われる言葉に次のようなものがあります。
Aさん「これだけ待たされたんだから、○○(薬の名前)を処方してください」
Bさん「点滴をしてほしくて長時間待ったのに、なぜしてもらえないんですか」
Cさん「友達はここで血液検査を受けることができたのに、どうして私には検査をしてくれないんですか」
これらを詳しくみていきましょう。
まずはAさんの事例です。Aさんはある症状が気になって忙しい合間をみつけて受診しました。Aさんはその症状には○○という抗菌薬(患者さんは「抗生物質」「抗生剤」などと言います)が効くと信じています。ところが、医師が診察をするとAさんの症状は細菌感染を示唆するものではなく、抗菌薬が不要な状態です。しかし、それを医師がいくら説明してもAさんは納得しません。そして最後に出たのが「これだけ待たされたんだから・・・」という言葉です。
たしかにレストランなどのサービス業では、長時間お客さんを待たせてしまった場合、料金を安くする、サービス券を贈呈する、料理を一品無料で出す、などの”サービス”をおこなうことがあるでしょう。
しかし、医療機関では「待たされたんだから希望の薬をだしてほしい」という理屈は通用しません。たしかにお待たせすることは我々医療従事者も申し訳ないと感じていますが、待ち時間の長さと処方する薬の内容や量とはまったく関係がありません。
次にBさんの事例をみてみましょう。点滴を希望する患者さんは少なくありません。日本人には”点滴神話”というものがあり、「点滴をすればすぐに元気になる」と信じている人もいます。また医師の側も、海外に比べるとすぐに点滴をおこなう傾向にあると指摘されることがあります。(私がタイのエイズホスピスで医療活動をおこなっているとき、欧米の医師はよほどのことがない限り点滴をしませんでした。エイズ末期で食事を摂れないような患者さんにさえ「一度点滴をおこなうと癖になってしまうから・・・」という理由で点滴を許さないのです。日本人医師の私がタイ人の看護師に点滴の指示を出しても翌日には欧米の別の医師が点滴中止の指示を出すということがよくありました。タイ人の看護師にしてみればさぞかし困惑したものと思います・・・)
さてBさんの事例に戻りましょう。原則的に、「緊急的に薬剤を体内に入れる必要があるとき」、「ひどい脱水がある場合」、「吐き気や下痢がひどく放置すれば脱水になるような場合」、「絶飲しなければならないような場合」などを除けば、点滴が医学的に必要になることはありません。
東京には「点滴バー」などというものがあって、栄養剤の入った点滴をおこなうサービス機関があるそうですが、これは保険診療ではありません。こういう機関は「サービス業」をしているわけですから待ち時間に関係なく希望すればお好みの点滴をしてくれるでしょう。(私なら栄養剤が必要と感じればドリンク剤を買いますが・・・)
保険診療をおこなっている医療者からみれば、いくら待ち時間が長くなろうが「医学的に適用のない症例に点滴はできない」のです。
次にCさんの事例をみてみましょう。健康診断や人間ドックなどを除けば、血液検査を保険診療でできる場合は、何らかの症状があったり、それなりに病気を疑ったりする場合に限ります。ですから、「友達が血液検査を受けた」のは、その検査が医学的に必要だったからであり、誰もが受けることができるわけではありません。(自費での検査なら可能です。また比較的頻度の高い疾患で自覚症状が出にくいようなものであれば場合によっては無症状でもできることがあります)
Cさんの事例を一般のサービス業で考えてみましょう。例えば、Cさんの友達が先週末新しくできたホテルに泊まったとします。友達が良かったと言っているのを聞いて、Cさんもそのホテルに泊まろうとやってきました。ところが、満室でもないのにホテル側がCさんの宿泊を断ったとします。この場合、Cさんが激怒するのは当然です。「お金を払わないと言っているわけでもないのになんで友達は泊まれて自分は泊まれないんだ!」、となり、場合によっては訴えることを考えるかもしれません。
基本的に、社会常識を逸脱した言動をとらない限りは、「支払うお金に対等するサービスを提供する」のがサービス業の役割です。
一方、医療機関では「いくらお金を積まれても医学的に適用のない検査や薬の処方は(少なくとも保険診療の範囲では)できない」のです。
では、医療機関はサービス業でないなら何なんだ、という疑問が出てきますが、私自身は、医療機関は「公共の資源」と考えています。公共の資源だからこそ、国民ひとりひとりが毎月払っている保険代を使って、病気や怪我の人の治療をおこなうことができるのです。
ただ、確かに医療機関を受診すれば通常は3割の自己負担代金を徴収されますし、もしも医療従事者の態度が悪かったり、待合室が汚かったりすれば腹立たしい気持ちになるでしょうから、「医療機関はサービス業じゃないんだから患者はおとなしくしていればいいんだ」などと思っているわけではありません。
それに、公共の資源といっても、会計上は「利益」を出して「税金」を払えなければ医療機関はつぶれてしまいます。(このあたりが、「医療=サービス業」と思われる所以かもしれません)
そろそろまとめに入りましょう。
我々医療者は、できるだけ患者さんの待ち時間を減らし、要望に応えたいと考えています。当院では、待ち時間をできるだけ少なくするために予約制度を何度も見直し、待合室の快適さを追求しています。またご要望をできるだけお聞きするために「診察室では気になることをなんでもお話ください」という方針を開院以来貫いています。
もちろんまだまだ未熟な点が多々ありますが、常に患者さんの立場にたって・・・というのはミッションステイトメントにもある通りです。
ただ、「これだけ待ったんだから・・・」「お金を払うんだから・・・」という理論はちょっと違うのでは・・・ということをご理解いただきたいのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
67 医療の限界 2008/8/25
福島県立大野病院で2004年、帝王切開で出産した女性(当時29歳)が手術中に死亡した事件で、業務上過失致死などの罪に問われた産婦人科医に対し、福島地裁は8月20日、「標準的な医療措置で過失はなかった」として無罪判決(求刑は禁固1年、罰金10万円)を言い渡しました。
この事件は各マスコミで大きく取り上げられ、医療関係者の間でも注目されていました。故意に死亡させたわけでもなく、また明らかなミスとも言えない医療行為で医師が「逮捕」されたと考えられており、医療界の反発も招いていました。
一方、遺族に対する取材をみてみると、遺族は”納得していない”と報じられています。例えば、8月20日の共同通信は下記のように報道しています。
「言い訳しないでミスを受け止めて」と傍聴を続けてきた遺族。女性の父は肩を落とし、ハンカチで何度か目元をぬぐった。女性の夫は鋭い視線を前方に向けた。
こういうかたちで報道がおこなわれると、あたかも今回の裁判の焦点が「医師vs患者」のように聞こえてしまいますが、実際にはそうではありません。
我々医師が今回の事故に違和感を覚えるのは、患者側が医師や病院を訴えたのではなく、悪意のない医師が「逮捕」されたからです。つまり、この事故が刑事事件になっているところに疑問を感じるのです。それも「書類送検」ではなく「逮捕」なのです。さらに、この医師を逮捕した刑事が福島県警で表彰されたとの”噂”もあり、ますます医療従事者からみれば不可解な出来事にうつるのです。
刑事事件というのは、原告は患者側ではなく検察です。もしも、今回の裁判が民事によるもので、原告が患者側で示談金の有無、あるいは金額が争点になるというのなら、まだ理解しやすいのですが、我々医療者からみると「なんで警察や検察が・・・」という気持ちになるのです。
今回の事件で検察(=原告)が争点にしているのは、「異状死届出義務違反」と「業務上過失致死」です。
「異状死届出義務違反」は、以前にも述べましたが、「異状死」の定義自体が曖昧ではっきりとしたものはありません。もしも、今回亡くなられた女性が「異状死」なら、「まったく予見できなかった突然の死」であるわけで、それならば「出血多量で危険な状態になることがあらかじめ分かっていたのにもかかわらず、執刀医が漠然と胎盤をはがして大量出血の事態を招いた」という検察の主張に矛盾するのではないでしょうか。「異状死届出義務違反」では「予見できなかった死」としておきながら、「業務上過失致死」では「予見できたはず」としていますから、この2つの違反行為を同時に主張している検察は私には奇異に見えます。
実際の裁判では、「異状死届出義務違反」については「死亡は避けられない結果で報告義務はない」とされたと報道されており、これは我々医療者にとっても納得がいくものではあります。では、「業務上過失致死」についてはどうでしょう。
結果から言えば、
妊婦の命を救えず死亡させてしまった。 → 手術の仕方に問題があった。なぜなら、手術の目的は妊婦の命を失くすことではないはずだから。 → その病院で手術できないならあらかじめ高次病院に搬送すべきだった。 → それをしていない執刀医は「過失」に問われる。
ということになるかもしれません。しかし、これは結果をみて後から言えるわけであり、実際の医療現場はこのようにクリアカットな判断ができるわけではありません。例えば、現在では多くの疾患に「治療ガイドライン」というものがあり、医師はそのガイドラインに従って治療をおこなう、ということになっていますが、実際には、すべての症例をガイドラインに当てはめてうまくいくわけではありません。ある程度は、(疾患によってはかなりの領域が)、ガイドラインは参考にならず、医師の裁量で治療をしていくことになるのです。
ですから、医療の現場を知っている者からすれば、実際の現場にいなかった上に、後から理屈をつなぎ合わせて「過失」と責め立てる検察には同意できない、のです。今回の裁判で医師の行為は「過失」ではないとされたことは、我々医療者にとってほっとする判決でした。
では、遺族の立場からはどうでしょうか。遺族の立場にたてば、元気だったひとりの女性が突然亡くなったわけですからやりきれない気持ちになられると思います。手術に問題はなかったのかを検証したいという気持ちになられるのは当然でしょう。執刀医の充分な説明があって然るべきですし、ひとりの女性が手術で亡くなったのは事実なわけですから「謝罪」があるべきとも言えます。(この点については、被告医師は、記者会見で、「最悪の結果になり、(女性には)申し訳なく思っています」と述べています。(報道は8月20日の共同通信))
また、お金で解決するような問題ではありませんが、示談金の話にもなると思われます。(この点は、医師は医療事故の保険に入っていますから、通常は保険会社が中心になって遺族または遺族の代理人が話し合いをおこなうことになります) 報道をみる限り、遺族に対する示談金の話があるのかどうかは分かりませんが、いずれこのような話し合いがもたれるものと思われます。
ところで、現在「医療安全調査委員会」というものを設立しようという動きがあります。医療事故が起こったときには、いきなり警察が医師を「逮捕」したり、検察が「起訴」したりするのではなく、専門家から構成される医療安全調査委員会が専門的な観点から協議をおこなうことになるというものです。そして、この委員会の必要性が検討されだしたのは、今回の福島県の医療事故がきっかけだと言われています。
私の知る限り、ほとんどの医師がこの医療安全調査委員会の発足に賛成しています。いくら注意を重ねても事故を100%防ぐことはできません。医療事故がおこったときに、専門的な見地から公正に状況を審査する第三者は必要なのです。
医療事故はあってはならないことだということは、我々医療従事者は充分承知しています。しかしながら、医療行為は人間がおこなう行為である以上、いくら注意をしても完全には防ぎきれないのです。「事故は起こりうるものです」と開きなおるつもりはありませんが、「医療の限界」があるということを患者さんにも知っていただきたいと思います・・・。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
66 医師倍増は実現するか その2 2008/7/18
前回は、舛添大臣が6月17日に発表した「勤務医倍増」について述べ、さらに開業医も勤務時間が長すぎるために、勤務医だけでなく開業医も倍増させる必要があるのではないか、という話をしました。
医師数を倍にすれば、それに伴う人件費の増加をどうするのか、という問題が出てきます。今回は「医師の人件費」について考えてみたいと思います。
私は、拙書『偏差値40からの医学部再受験』で、「医師数を倍にするかわりに医師の収入を半分にすればいい」という自説を述べました。
まず、年収半減に医師たちが同意するか、という問題があります。「年収半減」などと聞くと「とんでもない!」ということになりますが、同時に「勤務時間も半分」となればどうでしょう。おそらく研修医を除く勤務医の平均年収は、当直代を入れれば1千万円を越えると思われます。例えば、年収1,200万円、週あたりの勤務時間が90時間の勤務医がいたとして、年収600万円となる代わりに勤務時間が週45時間となれば、そう悪い話ではないのではないでしょうか。さらに、1週間の夏休みと労働基準法が定める有給休暇が取得できるようになるとすればどうでしょう。かなり魅力的な労働条件ではないでしょうか。
では開業医の場合はどうでしょう。この場合、少し計算が複雑になるのですが、その理由は主に2つあります。ひとつは「借入金」という問題です。通常クリニックを開業するときには銀行などから借り入れをおこないます。ですから、開業医の収入を考えるときには借入金の返済の分を考慮しなくてはなりません。
もうひとつ計算が複雑になる理由は、通常開業医は会計的には「個人事業主」になるということです。一方で、勤務医は「従業員」であり、会計的には「給与所得者」です。「給与所得者」(=勤務医)は、「給与所得控除」というものがあり税金が大幅に安くなります。
世間では、「開業医は勤務医よりも高収入である」と思われているようですが、「借入金」と「給与所得控除を受けられない」という2つの点を考えると実際にはそうでもありません。
例えば、ある開業医の年収を2千万円とすると(実際には2千万円もないことの方が多いのですが・・・)、給与所得控除が受けられないため、税金(所得税+住民税)で約半分が持っていかれます。ここから借入金の返済をおこなうわけですが、例えば4千万円の借入金があったとすると、おそらく年の返済額は500万円程度になると思われます。(参考までに、借入金の利子は経費とみなされますが、元本は経費にはならず控除されません。消費税と事業税は経費の扱いとなります)
すると、2千万円の収入から1千万円の税金をひかれ、借入金の返済で500万円が消えますから、実際の手取りは約500万円ということになります。「手取り500万円」というと決して悪くはないのですが、世間の考えている開業医の年収からは差があるのではないでしょうか。
すてらめいとクリニックも、この試算に近からず遠からずといったところなのですが、受診したことのある患者さんはこれを意外に思われるかもしれません。なぜなら、いつも混雑していて予約がなければ長時間待たされることが少なくないからです。これだけ待たされるんだからここのクリニックは儲かっているに違いない、と思われる人もいるでしょう。
少し話がそれますが、すてらめいとクリニックがなぜそれほど儲かるクリニックでないかというと、それは患者さんひとりあたりの診察時間が長いからです。一日の患者数がだいたい50人から70人くらいですが、これでも予約がなければ2~3時間待ちなんてことも珍しくありません。(ですから、みなさん、できるだけ予約を入れてくださいね)
1日の患者数が100人を越えるクリニックも多く、先日点滴で死亡事故を起こした三重県のクリニックでは、医師ひとりで1日300人を診ていたといいますから、すてらめいとクリニックとは診察の仕方が全然違うのでしょう。ちなみに、私が大学の総合診療科で外来をしていた頃は、3時間で10人前後の患者さんを診察していました。これくらいが最も適していると私は考えています。(それでは経営が成り立ちませんが・・・)
さて、話を戻すと、すてらめいとクリニックを受診される患者さんの側からすれば、医師を増やすなどして待ち時間を減らしてほしい、という気持ちになられると思います。けれども、クリニックに医師を増やすというのはそう簡単にできることではありません。
その理由のひとつは、前回述べたように「どんな疾患にも対応できる医師」は簡単には見つからないことですが、もうひとつの理由は、医師を雇うと「経営的に成り立たない」のです。外来を担当する医師を雇おうと思えば、時給8千円から1万円くらいの人件費が必要になります。もちろん人件費は経費として計上できますが、借入金が残っている段階で高い人件費を支払うには経営上のリスクが発生します。
では、借入金がなければ、つまり無借金経営であればどうなるかですが、この場合は、開業医の年収はかなり高額であると言えるでしょう。2千万円のうち半分をもっていかれたとしても1千万円が残ります。これをまるまる自分の収入にできるわけですから充分すぎる年収となります。さらに、借入金がなければ、高い人件費を払って医師を雇うことのリスクも軽減できます。
さて、開業医が別の医師1人を雇い、自らは、勤務時間半分・年収半分になったとします。その場合、額面上の年収は半分の1千万円になりますが、実際の手取りは半分にはなりません。なぜなら、税金は累進課税になっていますから、1千万円の年収では半分も税金に取られないからです。(おそらく手取りは600万円くらいになると思われます)
さらに手取りを増やす方法があります。それはクリニックを医療法人にするという方法です。そうすれば、院長自らが「給与所得者」となりますから、「給与所得控除」が受けられるようになります。(1千万円の年収の場合、これで手取りはおそらく700万円くらいになると思われます)
長々と説明してきましたが、私が思うのは、「借入金のないクリニックであれば、勤務医の試算と同じように、年収半分・勤務時間半分という勤務が可能になるかもしれない」、ということです。
借入金なしでクリニックを開業するのは、よほどの資産がない限りはむつかしいと思われます。では、上に試算したような「勤務時間半分・年収半分」というのは無理かというと、私が提唱する方法を採用すれば実現することが可能です。
それは、以前にもこのコーナーで何度か触れたことがありますが、「開業医を含めて医師をすべて公務員にする」という方法です。開業医の場合は、その医師が物件を探してきて行政に申請すると、行政が内装や器械の購入に伴う初期費用を負担してくれるというようにするのです。そして、医師はあらかじめ決められた給与を行政からもらいます。一般の企業は営利を追求しなければなりませんから、こんなことをすると従業員の士気が下がるでしょうが(社会主義の衰退を思い出せば自明です)、営利を追求すべきでない医療機関であればこの方法が最も適切ではないかと私は考えています。
今のところ、舛添大臣は勤務医倍増と言っているだけで開業医を増やすことには言及していませんが、いずれ真剣に検討してもらいたいものです。
診察の待ち時間が長いのは何も大病院に限ったことではないのですから・・・
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
65 医師倍増は実現するか その1 2008/6/24
2008年6月17日、福田康夫首相と舛添要一厚生労働相が首相官邸で会談し、医師の増員を検討していく方針で一致したことを各マスコミが大きく取り上げました。
実際に医師の増員(=医学部定員の増加)がおこなわれるようになるかどうかは別にして、首相と厚生労働相が一致して「医師増員を検討」としたことには大きな意味があります。
それは、1997年の閣議決定では、「医師数抑制のため大学医学部の定員削減」が盛り込まれていたからです。今回の厚生労働相の見解は、この1997年の決定を根本からくつがえすことになります。
私が医学部に入学したのは1996年ですが、この1997年の行政の見解が発表されたこともあり、この頃には「医師数を抑制しなければならない」という空気が医療界に芽生えていたように思います。
しかし、私は医学部5回生の臨床実習の頃には、「医師数抑制なんてとんでもない。医師はもっと増やさなければならない」と感じるようになっていました。なぜそう感じるようになったかと言うと、単純に「患者さんの病院での待ち時間が長すぎる」からです。長時間待たされたあげくに診察は数分間などということが日常化しており、一方では、医師は外来と病棟の業務をかかえ、研究発表の準備をおこない、その上大量の勉強をしなければならないのです。緊急手術や入院患者さんの急変で夜中に病院から呼び出されることもあります。
私には、そんな日本の医療事情が異常に思えてなりませんでした。一方で、医師の給与は高すぎるという世論があったために、それならば「医師数を倍にして給料を半分にすればいいのでは」という自説を持つようになり、これは拙書『偏差値40からの医学部再受験』にも書いたとおりです。
給与を半分にすべきかどうかは後で述べるとして、まずは医師数を倍にすべきかどうかを検討していきたいと思います。
舛添大臣は、今回の発表で、「週80から90時間の医師の勤務を普通の労働時間に戻すだけで、勤務医は倍必要だ」とコメントしています。政府は従来、「小児科医や産婦人科医など一部の医師が少ないのと僻地の医師が足りないなどの”偏在”が問題であって、医師数総数は不足しているわけではない」との立場にいましたから、今回の舛添大臣のコメントはそれを否定することになります。
この舛添大臣の意見に反対する声もあるようですが、常識的に考えても「週80から90時間の勤務時間」は異常ではないでしょうか。もちろん、日本のビジネスパーソンのなかにはもっと長い時間勤務している人が大勢いることは私も知っています。しかしながら、医師はこの勤務時間以外にも研究発表の準備や日々の勉強もしなければならないのです。(一般企業で働くビジネスパーソンも勉強しなければならないことは同じかもしれませんが・・・)
今回の舛添大臣の発表では述べられていませんが、実は開業医の勤務時間も相当長いのが現実です。
例えば私の1週間を振り返ってみると、月・火・水・金・土は遅くとも午前9時から業務が始まり(診察時間は10時から)、診察が終わるのは早くて午後8時半、遅ければ10時頃になります。しかし、診察が終わったからといって帰れるわけではありません。その日に撮影したレントゲンや血液検査の見直し、その日に撮影した症例写真の整理、カルテ記載(診察中は必要最低限のことしか記載しないため診察終了後に不足している部分を追加で記入していきます)などをおこないます。さらに仕事に関連したメールや手紙のチェック、経理やその他の業務もあり、これらがすべて終了する頃には日付が変わっていることも珍しくありません。
木・日・祝は、クリニックは休診ですが、医師会や大学関連の仕事、他院での勤務もありますから、実質休日はゼロです。1週間の勤務時間は、多いときは90時間を越えます。もちろん、勉強は勤務時間以外にしなければなりません。
それで、私がその勤務時間に満足しているかというと、もっと働いている医師をたくさん知っていますからあまり自分勝手なことは言えませんが、本音を言えばもう少し勤務時間を減らしたいという気持ちがあります。
すてらめいとクリニックは一応2診制で診察できるように(医師2人で診察できるように)設計してありますし、もしも可能であれば、例えば私は午後の診察(午後4時から8時)だけをおこない、午前の診察(午前10時から午後2時)は他の医師に代わってもらいたいと思うこともあります。
そのため、実はすてらめいとクリニックでは、オープンしたときから医師を派遣する会社に医師の紹介を頼んでいます。しかしながら、すてらめいとクリニックで働いてくれる医師はまだ見つかっていませんし、当分の間見つかりそうにありません。
その理由のひとつは、すてらめいとクリニックの医療コンセプトに合致した医師がなかなか見つからないというものです。私は、医師になった頃から「どんな疾患にも対応できる医師」を目指していました。ですから、二年間の研修期間ではできるだけ多くの疾患の勉強をすることに努めましたし、その後は大学の「総合診療センター」という医局に籍を置いて総合診療の習得につとめ、さらに大学に集まる患者さんだけでは不充分と考えたために、合計6箇所のクリニックに(もちろん無給で)勉強に行っていました。
私の目標である「どんな疾患にも対応できる医師」にはまだまだ程遠く、これからも多くの勉強をしなければならないことは自負していますが、それでも「とりあえず初期の診察をおこない、自分で診られない疾患や症状に対しては然るべき医療機関や医師を紹介する」という方針の医療はできるようになったと考えたために開業する道を選んだのです。
けれども、私のような考えを持っている医師はそれほど多くありません。実際、ほとんどの医師はいわゆる「専門医」を目指しています。それに、私がたどってきた道は後輩医師に自信をもってすすめられるものではないという問題もあります。なぜなら、私がおこなったように、「大学での仕事は週に1~2度にして、あとは無給で勉強に行く」といった方法では身分が不安定ですし、経済的にも大変です。
では、なぜ私がそのような社会的にも経済的にも不安定な立場をあえて選択したかというと、既存の医師教育システムでは私のニーズに合致するものがないからです。
今回、舛添大臣が発表した対策のなかに「総合的な診療能力を持つ医師の育成 」というものがあります。私は個人的には、この対策を早急に実現化してもらいたいと考えています。もしも、総合的な診療能力を持つ医師の育成システムが充実化すれば、「専門医」ではなく、私が実践している(つもりの)「どんな疾患にも対応できる医師」を目指す若い医師が増えるかもしれないからです。
そうすれば、私の勤務時間を減らすことができるようになるかもしれません。(なんだか自分勝手な意見になってしまいました・・・)
さて、勤務医を倍増させるには、(あるいは開業医やクリニックで働く医師を倍増させるには)、医師の人件費の問題がでてきます。次回はそのあたりを考えてみたいと思います。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第64回(2008年5月) 職業人としての”掟”
2006年6月20日に奈良で起こった、有名進学高校の1年生が自宅に火をつけ母子3人が死亡した事件を取材し『僕はパパを殺すことに決めた』を出版した草薙厚子氏に対し、供述調書を頼まれて見せたことで、鑑定医の精神科医が秘密漏示罪で逮捕されました。
まずは、マスコミの報道からこの事件を簡単に振り返っておきます。
鑑定医は、奈良地裁から2006年8月4日にこの事件の鑑定人に任命されています。著者の草薙氏は、この鑑定医に会えるよう知人の大学教授に依頼し、9月8日、京都市内の料理店で会っています。そしてその後も何度か会い、「情報源は分からないようにする、コピーは取らない、原稿も最終チェックさせる」などと執拗に頼んで、鑑定医が奈良地裁から預かっている供述調書をコピーやカメラ撮影などで入手した、とされています(2008年5月2日の読売新聞)。
今回、鑑定医が逮捕されたのは、少年と少年の父親が鑑定医を秘密漏示罪で訴えたことから始まっています。そして奈良地検と(なぜか)大阪地検が捜査を開始し、鑑定医と草薙氏、さらに鑑定医を草薙氏に紹介した大学教授までが自宅を強制捜査され、鑑定医が逮捕されるに至りました。(著者の草薙氏と大学教授は不起訴)
ところが、一連の捜査には不可解な点が多く、草薙氏は”不当な”検察の捜査を告発すべく、最近『いったい誰を幸せにする捜査なのですか。』という本を出版しています。
草薙氏によると、今回の事件に対するマスコミの報道は、検察が虚偽の情報をリークしたことによるものが多く、真実が語られていないとし、「草薙氏と(鑑定医を紹介した)大学教授が不倫関係にある」とのブラックメールが捜査の発端になっている可能性があると指摘しています。
また、草薙氏は、供述調書を入手するに際し、「私は神に誓って宣言する。私と取材相手との間には金銭の授受は無く、情で繋がっている関係も断じてない」と述べています。一方、読売新聞の報道では、「(鑑定医が)謝礼として(草薙氏から)10万円余りを受け取った」となっています。
マスコミの報道と草薙氏の主張のどちらが正しいのかは分かりませんが、客観的にみて捜査に幾分かの”不透明さ”があるのは間違いないと思われます。
そもそも少年と少年の父親が共同で、鑑定医を(名誉毀損などではなく)「秘密漏示罪」で訴えるということに不自然さがあります。少年が少年院内で『僕はパパを殺すことに決めた』を読んだとは到底思えませんし、たとえ読んでいたとしても、供述調書が著者の草薙氏に渡ったのは鑑定医が草薙氏に渡したからと断定することはどう考えても不可能です。なぜなら、草薙氏が『いったい誰を・・・』で述べているように、供述調書は、鑑定医以外にも、捜査機関(検察や警察)、家庭裁判所、弁護士なども入手しているからです(このあたりについては、『いったい誰を・・・』の最後に弁護士の清水勉氏が詳しく述べています)。
草薙氏は、『いったい誰を・・・』のなかで、自分自身が記者会見で発表したコメントとして次のように述べています。
「取材源の秘匿は私が取り調べを受ける中で、ずっと守ってきたことです。(中略)私は(取材源を)『命を差し出しても言えません』と捜査当局にも言っております」
しかし、結果的には、供述調書を草薙氏に漏示したのは鑑定医であることが捜査で明らかとなりました。たしかに草薙氏は、検察官に対しては「取材源の秘匿」を守っていたかもしれませんが、鑑定医の方が、「調書を見せたのは間違いない」と事実を認めています。
今回この鑑定医が逮捕されたのは、「秘密漏示罪」ですが、これは刑法134条に定められている、いわゆる「医師の守秘義務」のことです。
鑑定医は今回の件で、ある医学雑誌にコメントを寄せています。そのコメントは、タイトルを「供述調書を見せたことは後悔していない」としており、「自分は少年と医師と患者の関係ではないのだから、供述調書を他人に見せることは守秘義務違反には相当しない」というような内容を述べています。
鑑定医が裁判所から入手した供述調書を第三者に見せるのが守秘義務違反に当たるかどうかというのはむつかしい問題で、これから審議がおこなわれることになりますが、この鑑定医は実際に10万円以上の謝礼を受け取ったことを認めている以上、守秘義務違反に当たらないという主張には説得力が欠けるように思えます。
さて、私が今回の事件で最も問題だと思うのは、草薙氏が書いた『僕はパパを殺すことに決めた』がきっかけで、結果としてひとりの鑑定医が逮捕されたということです。
草薙氏は、記者会見で「命を差し出しても(取材源を)言えません」と述べましたが、鑑定医が逮捕されたのは事実であり、これは草薙氏に責任があります。
ジャーナリストであれば、「通常の」取材で得ることのできる情報以上のものを追求したくなるでしょうし、場合によってはその追求が社会的責務という言い方ができるかもしれません。そのため、例えば、危険な場所や人物に近づいたり、知ってはいけないような情報を入手してしまったり、といったことも場合によってはあるでしょう。取材でお金を渡すのは、倫理上よくないことなのかもしれませんが、私自身は個人的にはそれほど悪いこととは思えません。端的に言ってしまえば、誰にも迷惑がかからなければ、どのような方法で取材をしてもかまわないというのが私の考えです。
しかしながら、取材源が露呈されるというのは、ジャーナリストとして「失格」であり、許されることではないと思うのです。私はジャーナリストではありませんし、ひとつの事件を念入りに調べた経験もありませんが、NPO法人GINA(ジーナ)の関連では、違法薬物や売春に深く関わっている人の取材をすることがあります。そのなかには現在も違法行為をやめていない人もいます。私は彼(女)らから話を聞いて文章を書くときには、情報源が漏れないことを約束します。また、医学の学会や研究会で症例について発表をおこなうときには、その症例が誰であるかについてわからないようにします。医師どうしの間でさえ、守秘義務は存在するのです。
今回、鑑定医が逮捕され、草薙氏が不起訴となったのは、ジャーナリストという草薙氏の職業が「秘密漏示罪」に適用されないからではないかと思われます。要するに現行の日本の法律では、医師に対しては秘密漏示罪が適用されるけれども、ジャーナリストに対しては適用する法律がないということです。
私が最も言いたいことは、(以前にもこのサイトで何度か言っていますが)、「法律よりも大切なことがある!」ということです。そもそも法律が必要なのは、それがなければ社会が不安定になるからです。安定している社会であれば法律は不要なのです。もっと言えば文字さえ不要です。実際に無文字社会が大変安定した社会であることは文化人類学的には常識です。なぜ法律や文字が不要かというと、それは、そんなものがなくても社会の成員が一定のルール(掟)に基づいて人間としての道を踏み外さないからです。
人間が職業人として仕事をするときには、たとえその職業が何であれ、職業人としての”掟”を守らなくてはなりません。”掟”は法律とは別のところにあり、私は”掟”は法律よりも重みのあるものだと思っています。なぜなら、法律は国会の審議で変更されることがありますが、”掟”は不変だからです。不変だからこそ、わざわざ法律のように文章にする必要もないのです。”掟”という表現が厳かであれば単純に”ルール”と言ってもいいかもしれませんし、ある意味では職業人の”矜持”とも言えるでしょう。
結果として取材源が露呈されてしまったのは、草薙氏がどのような言い訳をしたとしても、それは”掟”に背いたことになると私は考えています。つまり、「何があっても取材源を露呈させない」というのがジャーナリストの”掟”だと思うのです。
最後に述べて起きますが、『僕はパパを殺すことに決めた』はたいへん興味深い本です。鑑定医はこの本に対して、少年が罹患していた「広汎性発達障害」についての記述が不充分であると述べていますが、私はそれを差し引いても、真実の解明と社会への問題提起という意味ですぐれた本だと思っています。
私はこの本が絶版になってしまったことを残念に思います。もう遅いかもしれませんが、別のかたちになったとしてもこの事件を草薙氏に伝えてもらいたいという気持ちがあります。(私が言うのはおこがましいですが)それが、結果として職業人としての”掟”に背いたことに対する贖罪になると思うのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
63 カルテの読み方、お教えします。 2008/4/28
「カルテ開示」という言葉がすでに一般的になっているように思われます。
すてらめいとクリニックでも、「カルテのコピーがほしい」という人が少なくありませんし、他院でのカルテのコピーを持参される方もおられます。
カルテのコピーが必要な理由も人それぞれで、単に「受診した記念に持っておきたい」という人、「自分の病気が治ったことを他人に示したい」という人、進学や転勤で遠くに行くため「新しいクリニックで見せるためにほしい」という人もいます。
患者さんからの要望にすぐに応えられるように、私はできるだけ分かりやすく日本語で書いているつもりですが、それでも患者さんにとってみれば分かりづらい表現や略語があると思われます。
今回は、日頃患者さんからよく聞かれる「カルテ用語」、さらに「カルテの読み方」について解説したいと思います。
医師にとって「カルテを書く」というのは重要な仕事のひとつで、手をぬくわけにはいきません。カルテは「公文書」の扱いとなり、ときに裁判に使われることもあります。したがって、いい加減なことや虚偽は絶対に書けないのです。「カルテの読み方」に入る前に、まずは「カルテは大変重要な公文書である」ということを確認しておきたいと思います。
カルテは大変重要なものですから、当然、医学部を卒業するまでにカルテの記載の仕方についても学びます。ただ、正しいとされる「カルテの書き方」は私が学生の頃から比べると随分変わってきているように思えます。
特に顕著なのが、「カルテは日本語で書かなければならない」というルールです。私がまだ学生の頃は、「カルテは英語で書く方がよい」などと言われており、さらに「英語は医学の世界共通語」などとも言われていました。その言葉を真に受けていた私は、医師になってからしばらくの間は英語でカルテを書いていました。
ところが、です。医師2年目のときに病棟の看護師長に、「英語でカルテを書くと患者さんに見せるときに分かりづらいから日本語で書き直すように」と言われました。私としては、「これまで英語で書くように言われ、突然英語はダメと言われるなんて、話が違う・・・」という思いもありましたが、ちょうど「カルテ開示」が一般的になりだした時期ということもあり、その看護師長の指示に従うことにしました。それ以降は、私は原則としてカルテは日本語で記載するようにしています。
「カルテは日本語で書くべきものなんですよ」と患者さんに言うと、「カルテは英語かドイツ語だと思っていました」と言われることがあります。たしかに、以前は英語だけでなくドイツ語でカルテを記載していた時代もあったそうです。
実際、その名残は今でも残っており、カルテ用語の一部はドイツ語由来のものもあります。私はドイツ語が苦手ということもあり、そういうカルテを読むと私自身が理解できないこともあります。
カルテに記載しなければならないことは非常にたくさんあります。患者さんの訴え、診察して得られる所見、血液検査や画像検査の結果、これまでにどんな病気をしていてどんな薬を飲んでいるか、薬にアレルギーはないか、妊娠していないか・・・、など非常にたくさんの事項を記録に残さなければなりません。もちろん、病名や処方する薬などについても記載が必要です。
これらを系統だてて記載するために、現在最も一般的な記載方式は、「SOAP」と呼ばれるものです。Sはsubjective symptom(自覚症状=患者さんの訴え)、Oはobjective symptom(他覚症状=診察で得られる所見)、AはAssessment(評価、病名など)、Pはplan(治療計画)です。
例えば、胃の痛みを訴えて受診したケースで、診察の結果、胃十二指腸潰瘍の疑いがあった場合、
S) 数ヶ月前から胃が痛い。痛みは食前に顕著で食後ましになる。
O) 腹部触診で心窩部(胃と十二指腸あたりの部位)に圧痛。眼瞼結膜に貧血の所見はない。
A) 胃・十二指腸潰瘍の疑い
P) 胃カメラを予約。同時に胃粘膜保護剤と胃酸分泌抑制薬を処方。
といった具合です。実際は、もっとたくさんの情報を記載しますし、血圧や体温のデータや、これまでにかかった病気などの情報もあわせて書きます。
患者さんがカルテをみたときに分からないと思われるものにカルテ独特の略語があります。できるだけ日本語でカルテを書くことをこころがけている私も、略語についてはアルファベット表記を使っています。本当はすべて日本語で書くべきだとは思うのですが、記載にとられる時間を短縮するために現実的にはある程度は略語を使わざるを得ないのです。よく使われる略語を少し紹介すると、
BP=血圧(blood pressure)、PR=脈拍数(pulse rate)、CBC=血算(count of blood cell, 赤血球や白血球の値)、div=点滴(dripping intravenous injection)、im=筋肉注射(intramuscular injection)、Rp=処方(recipe)、などです。
医学英語はラテン語由来のものが多く、上に紹介したdivやim、Rpなどもそうです。
ドイツ語の好きな医療従事者がよく使う略語にKTというのがあります。これはKörpertemperatuの略で「体温」の意味です。私は英語でBT(blood temperature)と書きますが、ドイツ語の好きな医療従事者はKTを使います。また、HrというのはHarunの略で尿のことですが、これも私は「尿」と書くか、英語で「urine」もしくは「Ur」とする方が好きですが、ドイツ語の好きな人は「Hr」と書きます。
血圧はドイツ語でBlutdruckといい、略語は「BD」になりますが、医療従事者のなかには、血圧を「BP」と英語で書き、尿を「Hr」とドイツ語で書く人もいて、こうなると、英語・ドイツ語・日本語のちゃんぽんとなり大変奇妙なものになってしまいます。これでは患者さんが分からないのも無理もないでしょう。
カルテ記載で最も頻繁に使われる略語のひとつに「do」というものがあります。
「do」というのは英語の「ditto」の略で、意味は「(前回と)同じ」です。前回と同じ点滴をおこなうときには、「div: do」と書きます。「ditto」のような短い単語をわざわざ略す必要もないのでは、と感じられますし、私自身は個人的に英語の書類(申込書など)で「ditto」とすべきところを「do」と書いたことはないので、「do」より「ditto」と書くことが多いのですが、不思議なもので「ditto」と書いている私以外の医療従事者をみたことがありません。(さらに、ほとんどの医療従事者は、これを「ドゥー」と発音します。書いたときはdittoよりdoの方が短いのは理解できるとしても、発音するときは「ditto」でいいじゃないか!、と私はいまだにこれに違和感を覚えますが、私以外の医療従事者は抵抗がないようなので私が変わり者なのかもしれません・・・)
今回紹介した略語は、日頃頻繁に使われるもののなかのごく一部です。おそらくほとんどの人は医療従事者の書くカルテのすべては理解できないでしょう。自分のカルテのコピーをもらって分からない略語があれば遠慮なく質問するようにしましょう。
注:多くの医療機関ではカルテを診察室で開示するのは無料ですが、コピーをお渡しするときは有料になります。すてらめいとクリニックではカルテのコピーをお渡しする場合630円をいただいています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
62 不合理な医療業界の流通システム 2008/3/21
4月からの保険点数改正で、「病院やクリニックの経営が危機的になる」とか「医師は仕事量に見合う報酬が得られていないのにさらに給与が下がる」、などと言われていますが、全体では0.43%の増加となっています。この数字はもちろん全体での数字であって、多くのクリニックでは収益が下がると見込まれています。
国自体が巨額の赤字を抱えているわけであり、収益が悪化している会社や給料が下がっている会社員も少なくないでしょうから、医療従事者だけが「仕事を正当に評価してほしい」というのはスジが通らないかもしれません。
私自身は、自分の本にも書いたように「医師の給与を半分にして数を倍にすべき」という考えをもっていて、さらに「医師は開業医も含めて給与の決まった公務員的な職種にすべき」という意見をもっています。医師の給与が固定であれば、レセプト請求に伴う社会全体での業務時間と人件費が大幅に削減できるからです。(レセプト請求業務の不合理さについては、マンスリーレポート2007年7月号 -私の一番キライな仕事- を参照ください)
今回は、それ以外に見直すべきと私が考えている医療業界の”不合理”についてお話したいと思います。
それは、医薬品の流通システムに伴う不合理です。
病院やクリニックが必要な薬剤を仕入れるとき、直接メーカーから仕入れることは現在の日本ではできません。例をあげて説明しましょう。
例えば、製薬会社であるX社がYという新しい薬剤を発売したとしましょう。クリニックがYを仕入れたいときに、直接X社に見積もり依頼をすることはできません。
クリニックは、まずX社と取引のある卸業者に見積もり依頼をします。通常どこのクリニックも3~5社程度の卸業者と取引をしています。例えば、卸業者のA社、B社、C社の3社にYの見積もり依頼を出します。すると、A、B、Cの3社はクリニックに対するYの価格を提示してきます。クリニックでは、これらから最も条件のよい卸業者に対してYを発注します。
この作業がどれだけ手間がかかるかお分かりでしょうか。
まず、A,B、Cの3社が見積もり価格を出すまで待たないといけません。さらに、他のビジネスと同じように、いったん提示された見積もり価格を参照して、必要に応じて値引き交渉をしなければなりません。ほとんどの薬剤は粗利額が数パーセント未満ですから、在庫リスクや仕入れに伴う手間を考えるとすでに赤字です。値引き交渉はいかに赤字を減らすかがポイントになります。
このような手続きを経てようやく薬剤の処方がおこなえるようになります。新たに処方を開始した薬の場合、どの程度効果があるか、副作用がでないかについて充分に注意していく必要があります。そして、充分に効果が期待でき、使いやすい薬であると判断すれば、さらに仕入れ量を増やすことになります。しかし、大量に仕入れるとそれだけ在庫リスクが増えますから、「これだけ購入するからもう少し値引きをしてほしい」といった交渉を卸業者に対しておこなわなければなりません。これも大変な手間になります。
手間はまだあります。だいたいどの薬も発売開始から10年程度経過すれば、後発薬品(ジェネリック薬品)が発売されます。薬にもよりますが、だいたい後発薬品は10社以上から発売されます。すると、今度は、その後発薬品の会社を調査して、信頼できる後発薬品メーカーの見積もりをとります。この場合も、直接後発薬品メーカーに対して見積もり依頼をするのではなく、やはり卸業者のA、B、C社に対して依頼をすることになります。
しかし、後発薬品メーカーM社の薬は、A社では取り扱っているが、B社では取り扱いがないといった場合がよくあります。B社としては、後発薬品メーカーはM社ではなく、N社のものなら扱っているとします。すると、クリニックでは、M社とN社を比較検討して、いったんサンプルを入手して、さらに値引き交渉などをおこなうことになります。
これらの業務にどれだけ手間がかかるかお分かりいただけるでしょうか。上の例では、卸業者をA、B,Cの3社、後発薬品メーカーをM、Nの2社として話をすすめていますが、実際には卸業者の数も後発薬品メーカーの数もこれよりも多く、見積もりから仕入れにはもっともっと複雑な手間がかかります。
もしもこれらの手間を省けるとしたらどうなるでしょうか。要するに、卸業者の存在をなくせばどうなるでしょう。
クリニックでは、必要な薬剤を直接製薬会社に見積もり依頼をすることになります。見積もりを依頼するのが1社だけになるわけですから、上に述べた手間は数分の1になります。さらに、「たくさん買うから値引きしてください」といった交渉も直接おこなうことができますから話が早くなります。現在のシステムでは、値引き交渉も、クリニック→卸業者→製薬会社→卸業者→クリニックという流れで連絡していかなければなりません。
もしもこのようにクリニックが製薬会社と直接交渉できるようになると手間が大幅に削減できて、クリニックでの仕入れ担当者の負担が一気に減ります。その結果、スタッフの勤務時間が減り人件費を削減できることになるでしょう。
もちろん、クリニックが直接製薬会社から購入することによって薬の仕入れ価格も下がるはずです。現在の流通システムでは、なぜか必ず卸業者の担当者が直接薬をクリニックに持ってきますが、クリニックとしては製薬会社から直接宅配便で送ってもらっても何ら問題はないわけです。
もしもクリニックがFAXもしくはインターネットを通じて医薬品を直接メーカーから仕入れることができるようになり、さらに宅配便を利用すれば、かなり効率的な仕入れができるはずです。
そして、ここからが重要なことですが、これが実施できるとクリニックの医薬品での利益がでるはずです。しかし、私は「クリニックに儲けさせて!」と言っているわけではありません。こうすることによって捻出される利益を医療費の削減にあてればいいのではないかと思うのです。
クリニックとしては仕入れ業務に伴う作業が大きく減りますから、人件費の削減ができて、さらに薬の価格を下げることによって医療費が削減できて、そして患者さんの薬代が大きく減少するのです!
これほどの名案もないと思うのですがいかがでしょう。私がここで言っているのは極めて単純なことなので、おそらく多くの人が日々感じているに違いありません。
にもかかわらず、誰も発言しないのは、既存の卸業者を守らなければならない何らかの理由があるからなのでしょうか・・・。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
61 救急搬送拒否とクリニックの待ち時間 後編 2008/2/27
前回は、救急搬送が病院から拒否される理由として、「少ない医師が大勢の入院患者を診ている」現状をお伝えしました。
今回は、クリニック(診療所)での待ち時間の長さを、やはり「少ない医師(開業医)が大勢の外来患者を診ている」という観点からお話したいと思います。
すてらめいとクリニックに限らず、多くのクリニックでは「待ち時間の長さ」が問題になっています。ですから、どこのクリニックもあの手この手で待ち時間対策をおこなっています。
一方、患者さんの側からみれば、この待ち時間の長さが理解できないことがあります。他の業種であれば2~3時間もの間待たされるといったことは通常はないわけで、「こんなに長時間待たせるなんてここのクリニックは常識がないのか!」といった憤りにもつながります。
では、なぜ医療機関ではこんなに待ち時間が長くなるのでしょう。
たしかに、美容院やエステティックサロン、マッサージ店などでは、こんなに待たされることはないでしょう。特に、予約を入れておけば、決まった時間にサービスを受けることができるはずです。
ところが、医療機関の場合、予約があったとしても30分以上も待たされることがあります。
これはなぜでしょう。
最大の理由は、「ひとりの患者さんにかかる時間が予測できない」ということです。
あらかじめ、ひとりの患者さんにかかる時間が分かっていれば、それを考慮して予約のスケジュールを組むことができます。例えば、「糖尿病でかかっているAさんは最近安定しているから次の予約は5分でいいだろう。昨日、電話で初診の予約が入ったBさんは長引く咳があるとのことなので問診だけで10分以上、レントゲン撮影も入りそうだから診察にかかる時間の合計は20分以上になるだろう」、といった予想をするとします。
ところが、実際にAさんを診察してみると、「最近、倦怠感と頭痛がひどくなってきていて日常生活ができなくなってきている」といった相談をされることもあるわけです。そうなれば、ふだんみている糖尿病以外にも様々な病気のことを考え、検査と治療をおこなっていくことになります。こうなれば予想できなかった時間がとられることになります。
また、長引く咳で来院予定のBさんは、当日になって連絡もなしに来ないということもあります。とすれば、Bさんのためにあけてあった20分がまるまる無駄になってしまいます。これは、一応は利益を出さなければならない医療機関としては死活問題につながります。
この問題を避けるために、「再診はOKだけど初診予約は受け付けていない」という医療機関もあります。こうすれば、当日の連絡なしのキャンセルといったリスクを幾分かは防げるでしょう。しかし、この方法にも問題があります。すてらめいとクリニックでは、「初診でも予約を入れてください」と案内していますが、これは、予約なしだと、日によっては2~3時間待たなければならないことがあるからです。
医療機関での待ち時間が長いふたつめの理由は、「突然重症の患者さんがやってくることがある」というものです。
医療機関には様々な訴えをもった方が来ます。美容院のお客さんであればほぼ全員が髪のカットやセットに来るはずですが、医療機関を受診する理由は実に様々です。例えば、健康診断目的で来る人は、特に体調不良がないのが普通です。一方、突然40度を超える熱と激しい下痢に襲われてやってくる人がいます。こういった場合、健康診断の人(Cさんとします)は予約を入れてあり、発熱と下痢の人(Dさんとします)は、突然症状が現れたわけですから予約がないのが普通です。
この場合、医療機関はどちらの患者さんを優先すべきでしょうか。
目の前で苦しんでいる人を後回しにするわけにはいきません。この場合は予約がなくても、発熱と下痢で苦しんでいるDさんを先にみます。そして、Dさんのような症状の場合、診察にはある程度の時間がかかります。診断をつけるには詳細にわたる問診が必要な場合もあります。採血や点滴も必要になるでしょう。診察時間の合計は30分以上となるかもしれません。
一方、Cさんは健康診断が目的ですから、予定通りにすすめば15分程度で終わるはずです。もしかすると仕事の合間に健康診断を受けに来られたのかもしれません。ところが、クリニックに来てみると、予約のない別の患者さんに医師も看護師もつきっきりになっていてCさんに時間がとれなくなってしまう、ということもあり得るわけです。
さて、待ち時間を短くして予約どおりの診察をするために、「1時間に2~3人程度しか予約をとらない」といった方式にすればどうでしょうか。
実は、すてらめいとクリニックで、試験的にこのようなことをしたことがあります。症状や初診・再診の違いにもよりますが、「1時間で最少4人の予約」のシステムを取り入れてみたのです。
しかし、結果は芳しいものではありませんでした。たしかに予約のある患者さんには満足いただいたと思うのですが、その一方で、予約がすぐにいっぱいになってしまったため、多くの患者さんをお断りしなければなりませんでした。せっかく来てもらったのに「予約がいっぱいで・・・」と言って大勢の方に帰ってもらうこととなってしまったのです。実際は、結果としては診察できる時間がある場合もあったのに、です。
もうひとつの問題は「クリニックの採算がとれない」ということです。これではクリニックが存続できなくなるのです。別のところでも述べましたが、医療機関はそれほど利益のでる業種ではありません。例えば、ある医療関係者向けのウェブサイトに掲載されていた情報によりますと、「某放送局のテレビマンは時給7582円、某銀行の行員は時給5582円、これらに比べ医師(開業医)は4000円台」となるそうです。さらに医師(開業医)はここからある程度の経費を捻出しなければなりません。これだけ患者さんを待たせて、プライベートな時間を削って仕事をしても、余裕のある生活からは程遠いのが日本の開業医の現実なのです。
さて、現在のすてらめいとクリニックでは、試行錯誤を繰り返し、以前よりはかなり待ち時間の問題が解消されています。(といっても重症の人が立て続けに来られれば状況は変わりますが・・・) ただし、これは予約がある場合です。予約がなくて軽症の人には2~3時間待ってもらうことがあります。
医療機関を受診する際はできるだけ予約を入れるようにするのが賢明です。たとえ当日であっても、電話で予約状況を確認すれば、待ち時間の長さが短縮されるはずです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
60 救急搬送拒否とクリニックの待ち時間 前編 2008/1/31
昨年末に大阪府富田林市で、30もの病院から救急搬送を拒否されて89歳の女性が死亡したという事件は一般の方からは不可解にうつるかもしれません。
”30もの病院から拒否”などと聞くと、「いったい日本の病院は何をやっているんだ!」と憤りを感じる方もいるでしょう。
しかし、現場で仕事をしていると、30というのはさすがに多いような気もしますが、このようなことは”ないことはないだろうな・・・”と感じられます。
私は、現在は救急の仕事から離れていますが、少し前までは月に数回は救急車を受け入れ入る病院で夜間の勤務をしていましたし、以前は大病院の救急部で働いていたこともあります。
救急車受け入れ要請の電話は救急隊から入ります。比較的小さな病院で働いているときは、救急隊の話から判断して、「その症例はこの病院で受け入れるには重症すぎる。もっと大きな病院に行ってもらうべきだ」と判断して断ることがあります。
これは、無理して受け入れて、その結果、「やはりこの病院では人員も設備もこの症例をみるには不充分だった」などということは避けなければならないからです。初めから大病院に搬送されていれば助かったのに、無理して小さな病院で受け入れたために救える命が救えなかった、などということは絶対にあってはならないことです。
ただ、この判断がいつも正しいとは限りません。
例えば、私が以前ある中規模病院で夜間勤務をしていたとき、30代男性の交通事故の患者さんが運ばれてきました。事前の救急隊の情報によれば、「意識も清明で、頭をうっているかもしれないが両手両足は動く。あるとしても軽度の骨折程度だろう」ということでした。それならば、受け入れ可能です。私は、「頭蓋内出血や胸部・腹部の損傷を確認して、あとは骨折の治療をおこなえばいいだろう・・・」、そのように考えていました。
ところがです。実際に運ばれてきた患者は、意識は比較的保たれているものの、四肢に力が入らないといいます。これは脊髄損傷の可能性があります。もしも、脊髄損傷なら初めからそれなりの対応のできる高次病院に行かなければなりません。私は初期診察をすませ、やはり脊髄損傷の可能性のあることを確認し、それから大阪府中の高次病院に連絡をとりました。
そのときはたしか7件目くらいの病院で受け入れてもらえることになりました。その病院まではかなり距離がありましたが、私も救急車に同乗しておよそ1時間後に搬送することができました。
逆に、高度な救急をあつかっている大病院で勤務しているときは、救急隊や中規模病院からの救急搬送依頼が頻繁にあります。
もちろん、大病院としては、重症の症例を積極的に受け入れたいという気持ちはあるのですが、すべての依頼に対応するわけにはいきません。生死をさまよっているような患者さんの治療には、かなりの人員と時間がとられます。生命の危機がある患者さんをひとり受け入れれば、その後数時間は救急要請に応えることはできないのです。
また、救急外来があいているときでも、ベッドが万床であれば受け入れられないということもあります。重症の症例は、原則として入院することが前提です。空きベッドがなければ人員に余裕があったとしても救急要請を受け入れることはできないのです。
では、日本の医療現場では、なぜこのような問題が起こるのでしょうか。
最大の原因は「医師不足」でしょう。
もしも医師の数が大幅に増えれば、それだけで救急要請を断ることはかなり少なくなるはずです。夜間の当直医が1から2人しかいない病院であれば、少し時間のかかる中等度の症例が搬送されてくればそれで手がいっぱいになってしまいます。救急医療をおこなう医師が(それが交代性であったとしても)増加すれば、なかなか搬送先が見つからないという問題は大きく減少するはずです。
ちなみに、日本の人口あたりの医師数は、先進国30ヶ国中27位(2005年9月の財団法人社会経済生産性本部によるデータ)です。
そして、もうひとつの大きな問題は、「空きベッドの少なさ」です。
医師数と同時に財団法人社会経済生産性本部が発表した、人口あたりの病院ベッド数は、先進国30ヶ国中なんと第2位です。
これは一見奇妙にうつります。ベッドの数は多いのに万床で救急搬送が受け入れられないとはどういうことでしょうか。
この原因は、日本では入院を希望する患者さんが他国に比べ多くて、さらに入院期間が長いという特徴があるからです。
これが日本の医療費を圧迫しているのは事実で、そのため厚生労働省はあの手この手で入院患者数を減らして、入院期間を短くする政策を常に検討しています。
現在の日本の医療現場は、「少ない医師が大勢の入院患者を診ている」というのが現状なのです。
では、入院機能をもたないクリニック(診療所)ではどうなのでしょうか。
病院の搬送拒否とある意味で同じ問題を孕んでいるのが、「クリニックの待ち時間の長さ」です。
現在のすてらめいとクリニックの最大の問題点のひとつが、この「待ち時間の長さ」です。
特に1月は待ち時間の長さが顕著でした。正月明けで患者さんが一気に増えたこともあり、予約があっても2時間待ち、予約がなければ4時間待ち、などという事態にもなってしまいました。
現在は予約システムを大幅に見直し、待ち時間の短縮がある程度実現化し、少なくとも予約のある患者さんの待ち時間は最長でも30分程度になっています。
しかし、一方では新たな問題も出現しています。次回はそのあたりを述べたいと思います。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 2026年2月28日 樹木は心血管疾患を防ぎ、草や花はリスクを上げる
- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン
- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?
- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる
- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性
- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
月別アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (125)