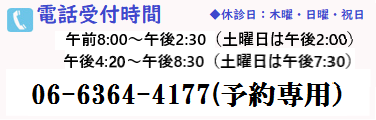2019年2月24日 日曜日
第186回(2019年2月)子供を襲う重症感染症エンテロウイルスD68の謎
前回の「はやりの病気」ではWHOが「2019年の世界の10の脅威」(Ten threats to global health in 2019)を発表したという話をしました。その10項目を簡単に振り返っておくと次のようになります。
#1 大気汚染と地球温暖化
#2 非感染性疾患(主に生活習慣病)
#3 インフルエンザ
#4 脆弱な環境(干ばつ、食糧不足など)
#5 薬剤耐性
#6 エボラウイルスなど高致死性の感染症
#7 脆弱な公衆衛生
#8 ワクチンへの抵抗
#9 デング熱
#10 HIV
今回は、まずCDC(米国疾病対策センター)が発表した「2018年の健康上の脅威」について紹介したいと思います。
#1 麻薬などの薬物過剰摂取
#2 食中毒(2018年、米国ではロメインレタスの大腸菌感染が注目されました)
#3 AFM(急性弛緩性脊髄炎)
#4 エボラ出血熱
#5 C型肝炎ウイルス
#6 性感染症
#7 自殺
#8 生活習慣病
#9 他国の公衆衛生
#10 薬剤耐性
#11 結核
WHO、CDCの両者を比べると、まず感染症の多さが目立ちます。WHOでは10項目のうち6項目が、CDCでは11項目のうち7項目が感染症です。興味深いことに、両者に共通して挙げられているのはエボラウイルスと薬剤耐性の2つだけです。
そろそろ本題に入りましょう。今回お話するのはCDCが3番目に挙げているAFM(急性弛緩性脊髄炎)です(ここからは単に「AFM」とします)。
この疾患、メディアではあまり取り上げられませんし、頻度としてはさほど多いわけでもないのですが、いまだに原因もはっきりとわかっておらず治療法もないために非状に厄介な疾患です。そして、これについては過去の「はやりの病気」第150回(2016年2月)「エンテロウイルスの脅威」で一度紹介しています。
まず、簡単にこの疾患をまとめておきます。
2014年夏、米国で突然エンテロウイルスD68(以下「EV-D68」)による重症呼吸器疾患の報告が相次ぎました。その後手足が動かなくなるような神経症状が生じる例が多く、これらはAFM、または急性弛緩性麻痺(AFP、以下「AFP」とします)と診断されました。2015年1月15日までに、呼吸器疾患を発症してEV-D68が検出された患者は49州で1,153人(AFM/AFPを発症していない患者も含めて)となり、うち14人が死亡しました。
米国での流行開始からおよそ1年後の2015年8月、日本でも麻痺症状(手足が動かなくなるなどの神経症状)を有するEV-D68の報告が突然急増しだしました。厚生労働省は、2015年10月21日、「急性弛緩性麻痺(AFP)を認める症例の実態把握について(協力依頼)」という事務連絡を発令し、全国の小児科医療機関に依頼をおこないました。
日米とも突然患者数が増えだし、しかも治療法がない重症化する疾患です。これ以上増加するようなことがあれば両国とも国中がパニックになることが予想されました。ところが、その後感染者の報告は減少していきました。
ところが、です。いったんおさまりかけていたEV-D68によるAMFが2018年に日米両国で再び増加しだしたのです。
ここでいったん言葉を整理しておきます。AFMのMは「脊髄炎(myelitis)」で脊髄の炎症を指しますが、麻痺症状も呈します。つまりAFMはAFPの一部(AFM<AFP)です。AFMはEV-D68によるものだけでなくポリオウイルスやD68でないエンテロウイルス(例えばエンテロウイルスA71)なども含みます。AFPに含まれるがAFMでない疾患にはボツリヌス症やギラン・バレー症候群があります。この時点ですでにかなりややこしいですが、さらに話は複雑になります。一応診断基準はあるのですが、「脊髄の炎症」を証明するのは簡単ではなく、AFMに入れていいかどうか判断に困るAFPもあります。それから、これは私の印象ですが、米国の方が日本よりも積極的にAFMの診断をつけているように思えます。もっとややこしい話をすると、EV-D68による麻痺症状は通常の麻痺のように左右対称とならないケースが多いことが報告されています。片側の麻痺だと乳幼児の場合は診断が困難になり、重症例もありますが軽症もありますから、診断がついていないケースも日米ともそれなりにあるのではないかと私はみています。そして、症状と状況からEV-D68感染が疑われるのに、いくら調べてもこのウイルスが検出されないケースもそれなりにあります。
複雑すぎて書いている私が混乱しそうになるほどです……。こういうときは思い切って簡略化しましょう。重要なのは、1)EV-D68が原因の可能性のある麻痺症状を呈する重篤な感染症が小児の間で3~4年ぶりに流行した、2)治療法はなく重症化する例がある、という2つです。
どれくらい増えているかを確認しておきましょう。CDCのサイトによると、2018年1年間で215例のAFMが確定されています。症状から疑われた例は合計371例あったようです。それまでのAFM確定例は、2014年120例、2015年17例、2016年39例、2016年16例です。つまり、大きく話題になった2014年の3倍以上のケースが2018年に報告されているのです。
日本はどうでしょうか。日本では届出がAFMではなくAFPとなっているために、単純に米国とは比較できないのですが、流行が始まった2015年が115例で、2018年はそれを上回る136例(12月16日まで)が報告されています。
では、CDCが2018年の健康上の「脅威」として取り上げたこの疾患を防ぐ方法はないのでしょうか。すべての症例でEV-D68が検出されたわけではありませんから、依然原因も”不明”と言わざるをえません。ということは、当然ワクチンはありません。ではどうすればいいのでしょうか。
CDCが公表している一般向けの案内から抜粋してポイントを紹介しておきます。
まず、AMFを発症した患者の90%は麻痺症状が起こる前に風邪の症状を呈しています。ということは、一般的な「風邪の予防」が大切ということになります。実際CDCは、通常の風邪と同様、手洗い、不潔な手で顔を触らない、風邪症状を有している他人に近づかない、といった一般の対処法を推薦しています。
次に神経症状が出現すれば直ちに医療機関を受診することが必要です。具体的には、手足を動かしにくい(片側でも)、眼球が動かない、まぶたが落ちてくる、飲み込みにくい、声を出しにくい、などです。治療のガイドラインはなく画一した治療法はありませんが、(小児)神経内科専門医により個別に対応した治療をおこなうことになります。理学療法や作業療法といったリハビリが有効なこともあります。
日米ともAMFが流行りだすのは夏です。インフルエンザの流行が去った後も、手洗いが重症なことは変わりません。
************
参考:毎日新聞「医療プレミア」実践!感染症講義 -命を救う5分の知識-
手足口病のウイルスが世界の脅威へ エンテロウイルスの謎【前編】(2016年2月28日)
日本でも次第に増大するリスク エンテロウイルスの謎【後編】(2016年3月6日)
投稿者 | 記事URL
2019年2月24日 日曜日
2019年2月23日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスク
ベンゾジアゼピン系(以下BZ)は認知症のリスクになるのかならないのか。これは以前から繰り返し検討されているテーマです。「はやりの病気」第151回(2016年3月)「認知症のリスクになると言われる3種の薬」では、ひとつの大規模調査を紹介し、その結論は「BZは必ずしも認知症のリスクとなるわけではない」でした。
ですが、今回発表されたメタ分析(これまで発表された研究をまとめなおして総合的に検討する分析)では、この結論がくつがえされています。
医学誌『Journal of clinical neurology』2019年1月号に掲載された論文「ベンゾジアゼピン長期使用の認知症のリスク~メタ分析による~(Risk of Dementia in Long-Term Benzodiazepine Users: Evidence from a Meta-Analysis of Observational Studies)」によると、BZを用いることにより認知症のリスクが1.51倍となります。さらに、当然といえば当然ですが、作用時間の長いタイプのBZ使用者、長期使用者で認知症のリスクが高くなっています。
************
このサイトで繰り返し述べているようにBZには強い依存性があります。たった1錠飲んだだけで人生が変わるとまでは言いませんが、使用には慎重にならなければなりません。過去に紹介した記憶のないままわが子を殺めた東京の主婦が飲んでいたのは「マイスリー」で、これもBZと同系統の薬剤です。
医療機関で簡単に処方することはありませんが、ときに患者さんは「前のクリニックでは簡単に処方してくれたのに……」と不満を言います。しかし、依存性が強く、記憶がなくなったり認知症のリスクが上がったりする薬剤を簡単に考えてはいけないのです。
参考:
はやりの病気
第164回(2017年4月)「本当に危険なベンゾジアゼピン依存症」
第151回(2016年3月)「認知症のリスクになると言われる3種の薬」
GINAと共に第152回(2019年2月)「アダム・リッポンも飲むベンゾジアゼピンの恐怖」
投稿者 | 記事URL
2019年2月24日 日曜日
2019年2月23日 乳児期に動物に接するとアレルギーを起こしにくい?!
意外な結果と言えるかもしれません。
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)の患者さんのなかにも少なくない犬アレルギーや猫アレルギー。谷口医院ではほとんどの患者さんが犬や猫が好きな人たちです。なかにはペットショップで働く人や、トリマーの人もいます。仕事を替えるわけにもいきませんし、そもそも犬や猫が好きな人たちですからプライベートでも一緒に過ごしていることが多いのです。
なぜ犬や猫が好きな人たちがそれらのアレルギーを起こすのか。それは犬や猫に触れる時間が長いからです。このメカニズムは花粉症と同じように考えればわかりやすいと思います。つまり、同じ抗原に何年もさらされていると、あるときを境にそれまでは何ともなかったものがその人にとって”敵”となるのです。以降は一種の「拒絶反応」が起こる。これがアレルギーのメカニズムです。
ということは、花粉症を防ぐには発症していない時点から花粉に触れないようにするのが最適であり、同様に動物アレルギーを防ぐには動物に触れる時間を短くするのがいい、ということになります。
ところが、です。医学誌『PLOS ONE』2018年12月19日号に掲載された論文「早い段階でペットと触れていれば動物アレルギーのリスクが低下する(Pet-keeping in early life reduces the risk of allergy in a dose-dependent fashion)」によれば、このタイトル通り、小さい頃にペットに触れているとアレルギーのリスクが下がるというのです。
この研究はスウェーデンのものです。対象は7~8歳の小児(1,029例)と8~9歳の小児(249例)です。結果は、生まれてから1年以内に(つまり乳児期に)家庭内に猫や犬を飼っていれば、喘息や鼻炎、湿疹といったアレルギー症状が少なくなるというのです。しかも、ペットの数が多いほどその傾向は顕著になり、ペットのいない子供の49%がアレルギーがあるのに対し、5匹以上のペットを飼っている家の子供ではアレルギー発症はなんと0(ゼロ)だというのです。
************
この論文によると「幼少期のペットとの接触がアレルギーのリスクを低下させる」とする研究は他にもあるそうです。ですが、そのメカニズムははっきりしません。食物アレルギーについては、以前は避けるべきだと考えられていたのが、現在はむしろ積極的に摂取すべきだ(注意点はいくつかありますが)と変わってきています(参考:「はやりの病気」第167回(2017年7月)「卵アレルギーを防ぐためのコペルニクス的転回」)。
動物アレルギーも同じメカニズムかもしれません。食物を乳児期に食べさせるときの最大の注意点はアトピー性皮膚炎などの湿疹をきっちりと治しておくということでした。ということは、乳幼児期にペットを飼うときにも湿疹の治療と予防はきっちりとおこなっておくべきでしょう。
投稿者 | 記事URL
2019年2月14日 木曜日
2019年2月 身体の底から湧き出てくる抑えがたい感情
医学部入学時には医師になるつもりのなかった私が、少しずつ医師への道を考え出したきっかけのひとつが病気で困っている人たちからの声を聞き始めたことでした。
「医師になる気はない」と事あるごとに言っていても、世間はそうはみなしません。そして世間の人からは医師も医学生も変わりがないと思われるのでしょう。医学部入学当初から、知り合いの知り合いといった人たちから「病気の相談に乗ってほしい」という依頼がよく来ました。
まだ医学を学び始めたばかりの者にそんな相談をされてもまともな答えができるはずがありません。まして私は「医師になる気はない」と言っているのです。「知り合いの知り合い」ですから会ったこともない人たちであり、無責任なことは言えませんからやんわりと断るようにしていました。ですが、知り合い(必ずしも親しいわけではない)から「話だけでも聞いてやってほしい」としつこく言われ、渋々と話を聞くという機会が何度かありました。
彼(女)らは口をそろえて「医者はまともに話を聞いてくれない」と言います。医学部で実習が始まるのは5回生からで、このとき私はまだ臨床の現場をほとんど知りません。初めて会う人たちから医師の悪口を聞かされてもどうしていいか分かりません。そもそも他人を悪くいう話を聞くときは、できるだけ客観的な立場に立ち、相手(この場合は医療者)からも話を聞くべきです。ですが、そういったことを差し引いたとしても私には彼(女)らの気持ちが分かるような気がしました。もう少し正確に言うと「医者側にも言い分があるだろうが、受診してこのような絶望的な気持ちになってしまっている人がいることをきちんと受け止めなければならない」と感じたのです。
仏語の勉強で挫折し、実験にセンスがないことを認めざるを得なくなり、入学時に考えていた研究の道を諦めかけていたところに、こういった話を頻繁に聞くようになり、私の心は次第に臨床へと傾いていきました(参考:マンスリーレポート2017年8月「やりたい仕事」よりも重要なこと~後編~)。自分が医師になったなら患者さんにこういう気持ちを持たせたくない、と考えるようになったのです。
そのうち私はあることに気づきました。私に「医者はまともに話を聞いてくれない」と言うとき、本当に言いたいことは医師の傲慢さや非人間性についてではなく、「医療者から見放されればどうしていいか分からない…」という”絶望感”だということに。そして、「いかなる人にもこの”絶望感”を持たせてはいけない」と思ったのです。
その後私は医療者や医療機関に不満をもつ多くの人と話す機会を持ちました。いわゆる「たらい回し」をされた人、セクシャルマイノリティであることを知られて差別的な言葉を言われたという人、セックスワークをしていることを思い切って医師に話すとひどいことを言われたという人、民間療法の話をすると医師にキレられたという人…。医師になってからはHIV陽性の人から話を聞く機会も増えてきました。医療者や医療機関に不満をもつ彼(女)らはたしかに軽症例も多いのですが、受診が必要、少なくとも医療者からの適切な助言が必要な人たちです。
こういった人たちのことを考えると、身体の奥から「抑えられない感情」が湧き出てきます。この感情は奥底からジワジワと湧き出てくるもので、私の身体を支配し、ときに思考を停止させます。病気の人を放っておいてはいけないというのは正しいことですが、正しいから実践するのではなく、私にとってはこの感情が文字通り「抑えられない」が故に行動せざるを得ないのです。初めてタイのエイズ施設を訪問し、他の医療機関で門前払いをされたという患者さんの話を聞いたときには抑制できない”怒り”がこみ上げてきました。
太融寺町谷口医院(以下「谷口医院」)には「他の医療機関で診てもらえなかった」といって何軒も渡り歩いてようやくたどり着いた、という患者さんが少なくありません。そういった症例は軽症である場合も多く、そもそも医療機関受診が客観的には不要というケースも多いのですが、そうでない場合もときにあります。
そのような「他院で診てもらえなかった」という症例で、数年前から増加しているのが「外国人」です。
外国人の患者さんの多くは、たとえ日本語か英語ができたとしてもそれなりに時間がかかります。また、英語は医師なら少なくとも読み書きはできますが、受付スタッフや看護師となるとコミュニケーションをとるのが困難という場合も少なくありません。これは大きな病院でも(というより、大きな病院の方が)融通が利かず、患者さんが電話しても話が通じず切られ、直接受診しても追い返され、ということがしばしばあります。
谷口医院を受診するまでにすでに5、6軒の医療機関を受診したという外国人も珍しくありません。こういう話を聞くと身体の奥から湧き出てくる感情が抑えられなくなってくるのです。医療は平等、とかそういったきれいごとを言いたいわけではありません。理屈の上で正しいからといった正論を述べたいわけでもありません。そのような理想を語りたいのではなく、もっと根源的で個人的な「感情」に抗うことができないのです。
海外で困った事態となったときや、突然の病気や怪我が起こったときに、現地の人たちに優しくしてもらった経験がある人は少なくないでしょう。キリスト教では聖書の「ヘブル人への手紙」のなかで「旅人をもてなすことを忘れてはならない」と書かれています(参考:「ヘブル人への手紙」)。イスラム教ではコーランの中に「旅人を助けよ」という教えがあると聞きます。仏教では私の知る限り「旅人」という言葉は見当たりませんが「利他」が基本的な教えであることは言うまでもありません(注1)。
日本に興味がありはるばる異国の地からやってきて、そこで予期せぬ病気に罹患してしまった。こんなとき、我々日本人はその外国人を助ける義務があると言えば言い過ぎでしょうか。谷口医院のミッション・ステイトメント第3条は「年齢・性別(sex,gender)・国籍・宗教・職業などに関わらず全ての受診者に対し平等に接する」です。逆差別もしないことを原則としていますが、複数の医療機関でイヤな思いをしてきたという外国人には少々優先的に働きかけるべきではないかとさえ最近は思っています。
ですから、メールでの問い合わせがあったとき、(内容にもよりますが)英語での外国人からの問い合わせを優先して返答するようにしています(もちろん日本人の患者さんからのメールもルール通り翌朝には返信しています)。谷口医院は総合診療のクリニックですから小児から高齢者までたいていの疾患は治療しており外国人の場合も95%は谷口医院で完結させるか、または帰国直後に母国の医療機関を受診できるように紹介状を作成します。ですが、残りの5%は日本国内での入院や専門医の治療が必要となり、このときに紹介先が見つからずに苦労することが多々あります。
そのようないきさつから、昨年(2018年)7月に「関西の外国人医療を考える会」という任意団体を立ち上げました。先日(2019年1月27日)は第2回の集会を開いて外国人医療に関心のある医療者と意見交換をおこないました。来阪する外国人は増加し続けているのにもかかわらず英語で対応してくれる医療者や医療機関が今もとても少ないのです。
残された医師としての時間のなかで、外国人が医療を受けるのに苦労しない社会を必ずつくる! これが現在の私が最も力をいれているミッションのひとつです。
************
注1:『大乗起信論』(岩波文庫)によれば、「五門」の第一の布施門のなかに次のような記載があります。
「もし人が厄難に遭い、恐怖し、また、危険が切迫しているのを見た場合には、己れに可能な(堪任)度合に応じて、その人に無畏を与えよ」
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン
- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?
- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる
- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性
- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
- 2025年12月14日 胃薬PPIは高血圧のリスクにもなる
月別アーカイブ
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (2)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (119)