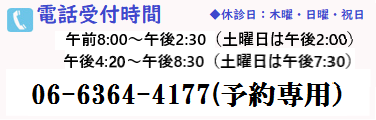2013年6月21日 金曜日
89 日本は「ワクチン後進国」の汚名を返上できるか 2010/6/20
最近、子宮頚ガンの原因であるHPV(ヒトパピローマウイルス)のワクチン接種の費用を自治体が負担することになった、というニュースをよく耳にします。
以前このウェブサイトの「はやりの病気」(下記参照)でも述べたように、私はこのワクチンが日本でも普及すべきことを切望しますが、行政が費用を負担するということは現実的でない、と感じていました。その理由は、「はやりの病気」で述べましたのでここでは繰り返しませんが、「ワクチン後進国」と呼ばれているこの国で、歴史が新しく性交渉で感染する病原体のワクチンが急速に普及するとは到底思えなかったのです。
しかし、実際には私の予想とは逆に、行政が費用を負担して積極的にワクチン接種を推奨する地域は急速に増加しています。2009年12月に全額公費負担を発表した新潟県魚沼市を皮切りに、兵庫県明石市、栃木県大田原市、東京都杉並区などがまずは続きました。その後多くの自治体が助成を決定し、2010年6月4日現在で、全国68箇所の自治体でHPVワクチンの全額(一部)助成が決定もしくは積極的に検討されています。(2010年6月9日、日本産婦人科医会の記者懇談会で同医会の理事が発表しています)
6月4日以降も、新聞報道をみるだけでも、茨城県境町、大分県九重町、熊本県美里町、福井県坂井市、山形県大蔵村、三重県伊勢市などで、全額もしくは半額の助成が決定されています。山梨県にいたっては全市町村で全額助成が決定されたそうです。
ここまでくれば加速度的に広がることもありえそうで、この流れは確かに歓迎すべきことではありますが、私は少し違和感を覚えています。誤解を恐れずに言うならば、HPVワクチンのみがこれだけ注目されるのは予防医学全般でみたときには奇妙であり、これだけ急速に広がるのは何か目に見えない”力”が働いているのではないか、という気がするのです。
HPVは性交渉で感染します。いわゆる性感染症のひとつと言えなくもありません。実際、医療者の間でも保守派の人のなかには、「性感染症のワクチンを公費でおこなうことには抵抗がある・・・」と感じている人もいます。私自身は、性行為というのは誰もがおこなうものであり、特に危険な性交渉をした人にのみ罹患する感染症ではありませんから(このあたりの詳細については下記コラムを参照ください)、HPVが性交渉で感染するからといって公費負担をしないという考えには反対です。
しかし、私に言わせれば、HPVのワクチンがこれだけ急速に広がっている現状はバランスに欠けているのです。
例えば、場合によっては致死的な病となり後遺症を残すことも少なくない子供のインフルエンザ菌ワクチン(HIBワクチン)はどうでしょう。性交渉という主体的な行為の結果感染するHPVとは異なり、インフルエンザ菌は1歳未満の赤ちゃんを襲うこともあります。インフルエンザ菌による細菌性髄膜炎をおこすと5%は死に至り、15~20%は発達障害などの後遺症を残すと言われています。インフルエンザ菌にはすぐれたワクチンがあり、アメリカでは1987年から定期接種の1つとされていますが、日本では公費負担がおこなわれているところはほとんどありません。ワクチンの費用は4回接種で3万円程度はするのに、です。(インフルエンザ菌については下記コラムを参照ください)
肺炎球菌についてはどうでしょう。子供に肺炎球菌が感染すると、インフルエンザ菌と同様、細菌性髄膜炎をきたすこともありますし、重症の中耳炎や肺炎を起こすこともあります。また、肺炎球菌は高齢者の致死的な肺炎の原因になることがあります。昔はこの細菌に罹患したとしても、適切な抗生物質の投与で治癒する病気でしたが、ペニシリンを多用した結果、人類は「ペニシリン耐性肺炎球菌」を生み出すことになり、さらに最近では、ペニシリンだけではなく、テトラサイクリン、マクロライド、ニューキノロンといった強力な抗生物質にも耐性を獲得した「多剤耐性肺炎球菌」が地球規模で増加しています。
しかし、肺炎球菌にはすぐれたワクチンがあります。このワクチンを事前に接種して抗体をつくっておけば、「多剤耐性肺炎球菌」が体の中に侵入してきたとしても免疫力でやっつけることができるのです。繰り返しますが、「多剤耐性肺炎球菌」が子供や高齢者に感染すると致死的な状態になりかねないのです。
肺炎球菌のワクチンは子供用と大人用では少し種類が違います。子供用はだいたい4回接種で合計4万円ほど、大人用は1回接種で7~8千円程度です(5年毎に追加接種がおこなわれるのが現在では一般的になっています)
今、この国では少子化が大変な問題となっています。そして大切な子供たちがワクチンを接種していれば防げたと考えられるインフルエンザ菌や肺炎球菌に罹患して命を落としているのです。もちろん、子宮頚ガンで命を落とす若い女性の方が圧倒的に数では多いのは事実です。しかし、なぜHPVワクチンのみが公費となり、他のワクチンは費用負担がないのでしょうか。
と、このような疑問を私は抱いていたわけですが、千葉県浦安市は2010年5月28日、HPV、インフルエンザ菌、肺炎球菌の3種類のワクチンについて、費用を全額助成する方針を発表したそうです。(報道は6月1日の読売新聞)
報道では、3種のワクチンを全額助成するのは<県内初>とされていましたから、千葉県以外の都道府県では、(私の知らないだけで)同じように3種のワクチンを無料で接種できる自治体があるのかもしれませんが、決して多くはないはずです。
では、HPV、インフルエンザ菌(HIB)、肺炎球菌の3つだけでいいのかといえば、まだまだ不十分です。古くから私のコラムやエッセイを読んでくれている方には、もう聞き飽きた、と言われるかもしれませんが、B型肝炎ウイルス(以下HBV)のワクチンがそれほど普及していないということは大変嘆かわしいことです。
最近は、少しずつマスコミでもHBVのことが取り上げられるようになり、例えば日経新聞は2010年6月17日、「慢性化しやすい「欧米型」、B型肝炎の4割超に」というタイトルでHBVが国内で蔓延していることに注意を促し、「すべての人にワクチンを打つなどの対策が必要」と述べています。
また、今年(2010年)の春に流行し、死者までだしているA型肝炎ウイルス(以下HAV)は食べ物から感染する、ときに致死的となる感染症であるのにもかかわらず、ワクチン接種をしよう、という声が聞こえてこないのは不思議です。(市民団体まで結成され啓蒙活動がおこなわれているHPVワクチンとは対照的です)
さらに、安全性の高い不活化ポリオワクチンや、ときに小児の重症化する下痢の原因となるロタウイルスのワクチンは日本では入手することすら困難です。これらはアメリカでは、6歳までに接種するよう政府から推奨されているワクチンなのに、です。水痘(みずぼうそう)にも大変すぐれたワクチンがあり、これは日本で開発されたのにもかかわらず、アメリカを含む諸外国では打つのが当たり前ですが、日本では定期接種に入っていませんから接種率は高くありません。(ただし一部の自治体では公費負担があります)
このように、それぞれの感染症をよくみると日本はどのように贔屓目にみても「ワクチン後進国」と言わざるを得ないのが現状です。HPVワクチンが普及することによって、予防医学への関心が社会全体で高まり、この国が「ワクチン後進国」を卒業する日は来るのでしょうか。
参考:
はやりの病気第77回(2010年1月)「子宮頚ガンのワクチンはどこまで普及するか」
はやりの病気第76回(2009年12月)「インフルエンザ菌とそのワクチン」
トップページ「肝炎ワクチンの接種をしよう!」
GINAコラム「本当に怖いB型肝炎」
GINAコラム「子宮頚ガンとHPVワクチン」
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第88回(2010年5月) 素敵な老後の過ごし方
社会学者上野千鶴子さんの『おひとりさまの老後』がロングセラーになっています。
「おひとりさま」という言葉はちょっとした流行語にもなっているようで、老後の独り者に付随する孤独や不安といった従来のネガティブなイメージが、この言葉のおかげで変わりつつあるようにも思われます。『おひとりさま・・・』は女性向けに書かれていますが、昨年(2009年)秋には『男おひとりさま道』という、男性向けの単行本も出版されました。
私はフェミニストというわけではありませんが、医学の前には社会学を学んでいましたから、上野千鶴子さんの本はこれまでに何冊か読んでいます。社会学者が「老後」の問題を取り上げており尚且つよく売れている本ですから「当然読むべきだろう」と考えて『おひとりさま・・・』『男おひとり・・』の双方を買って読んでみました。
上野千鶴子さんは、独り身でも(むしろ独り身の方が)楽しくやっていけると主張します。しかし、誰もがこの本を読めば幸せな老後が待っているかというと、そういうわけではないでしょう。「おひとりさま」を楽しく過ごす前提として、そこそこのお金があることと、そこそこの人脈、そしてある程度の健康が必要になります。健康問題については、かなり多角的に考察されており、医学的な見地からも検討されているため、なるほど・・・、と思いましたが、それでも上野氏の主張が庶民の立場に立ったものかと言われれば、少し疑問に感じます。
ひねくれた見方をすれば、「そりゃあ、上野先生はお金もあるし、上野先生を崇拝するファンが全国にいくらでもいるから、特定のパートナーとひっそりと暮らすよりも、陽気にいろんなところにでかける老後の生活は楽しいでしょうけど、お金もない、友達も少ない、特に高齢になってからは異性の友達がゼロ、なんていう庶民はどうすればいいの……」となります。
また、上野氏は、「男性も高齢になれば特定のパートナーを持つのではなく大勢の女性の友達をつくってセックスや結婚(再婚)のことは考えるな」と主張しますが、「ハーイ。上野先生の言うとおり、性欲は封印してセックスのことは考えませんし、恋愛をしたいなどと二度と申し上げません」、などと本気で言える男性がどれだけいるでしょうか。
前置きが大変長くなってしまいました。今回のコラムでは「老後をどのように過ごすべきか」について最近の医学的見解を紹介するのが目的なのですが、そのイントロダクションとして上野千鶴子さんの書籍を紹介しました(ここでは否定的な意見を中心に述べましたが一読に値する良書です。念のため……)。
さて、老後にパートナーを持つべきか否かについては『おひとりさま・・・』に譲るとして、パートナー以外には誰と過ごすべきかについて考えてみたいと思います。
一般に、高齢になると子供は巣立ち孫ができていることが多いと言えます。昔も今もほとんどの人は(子供との関係はそれほど上手くいってなくても)孫のことはかわいいと思うでしょう。孫にお小遣いをあげたり、プレゼントを買ってあげたりすることが生きがいになっている高齢者も少なくありません。
では、高齢者は孫が入れば幸せなのでしょうか。
最近興味深い学術研究が発表されました。「Health Day News」2010年4月15日の記事「孫ではなく友達が幸せなリタイヤ生活の鍵(Friends, Not Grandkids, Key to Happy Retirement)」によると、英国心理学会の年次集会で「高齢者の生活の楽しさに大きな差をもたらすのは子や孫たちではなく、活動的な社会生活の存在である」という報告がありました。
この研究は、ウェブサイトやオンラインニュースレターで募集した定年退職者279人を対象とし、家族、友人および退職後の生活に関するアンケートをおこない、生活の満足度を測定する検査を実施しています。
その結果、子や孫たちのいる人といない人との間に生活の満足度の差は認められませんでした。一方で、<強い社会的ネットワーク>の存在が生活の楽しさに大きなプラスの影響を及ぼす傾向があり、「一緒に楽しむ活発な社会集団がある」という項目に強く同意した人では生活の満足度が高く、反対に生活を楽しんでいない人は「仕事をしていたときの人付き合いがなくて寂しい」という項目に強く同意していました。
研究者はこれらをまとめて、「(仕事ではなく)趣味などを共有できる社会集団の存在は、結束感、目的意識、熟達(技能を必要とするケース)など、数々の基本的な心理的要求を満たすものである」と述べています。
Healthy Day Newsのこの記事は、米国の学者の意見も紹介しています。その学者もまた、米国の定年退職者について、今回の英国の研究結果と同様の意見を示しています。「高齢者は自分の孫に極めて強い関心があり、孫の成功を願っているが、幸せや心理的満足感をもたらしてくれるのは実は友人であると私は考えている。老後に限らず、人生のさまざまな段階で人は同年代の友人が自分の経験を理解し、社会的に支えてくれると感じている」とその学者は述べています。
英国の研究では、<強い社会的ネットワーク>だけでなくパートナーについても調査されています。結果は、「死別、離婚した人や未婚の高齢者(おひとりさま)は、パートナーとの関係を長く続けている人に比べて生活の満足度が低い」、というものだったようです。
さらに、パートナーのいる人たちに対する調査では「パートナーも退職している人に比べ、パートナーがまだ仕事をしている退職者は生活の満足度が低い」という結果がでています。
これらをまとめて、研究者は、「パートナーが退職するまでは長期休暇の計画を立てたり、生活を大きく変えたりすることができないが、ともに退職していれば一緒に計画を立て互いの生活に合わせることができる」、としています。
ところで、年を取ると頭脳も衰えるのでしょうか。身体が老いるのは仕方がないにしても、老後を楽しく過ごすにはできるだけ頭脳はしっかりと保ちたいものです。物忘れが気になるようになったり、記憶力が低下したりするということは多くの人が体感することでしょうが、すべての能力が低下してしまうのでしょうか。
実は最近、そうではなく、むしろ年を取るにつれて能力が向上する分野があるという研究結果が発表されています。医学誌『Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)』オンライン版2010年4月5日号に掲載された論文(下記注1参照)で、「高齢者は若者に比べて社会的対立を解決する能力に優れている」という研究結果が報告されています。
研究内容の詳細は割愛しますが、この「高齢者がすぐれている」という結果は、脳の画像検査(MRIやPET)とも一致します。高齢者は若年者に比べて記憶課題に前頭葉を多く使っていることが判ってきています。前頭葉は、理論的推理、問題解決、概論形成、複数の事案の同時処理、などをおこなうときに活動する部分です。「高齢者は他の認知能力を補うために前頭葉を多く使うようになり、それによって社会的対立についてよく理解できるようになると考えることができる」と研究者は述べています。
高齢になってから新しいことを始めたり、周囲が驚くほどの能力を発揮したりする人がいます(56歳から測量を開始し日本地図を完成させた伊能忠敬はその代表と言えるでしょう)。では、いわゆる「脳トレ」はどうなのでしょうか。「脳トレ」をおこなうことにより、脳力がアップして、社会的対立を解決する能力だけでなく他の領域でも頭脳明晰となるのでしょうか。
残念ながらそうはならないようです。科学誌『Nature』2010年4月20日号(下記注2参照)で発表された英国の研究結果では、11,430人にコンピューターゲームをおこなってもらい「脳トレ(brain training)」の効果を検証した結果、ゲームの成績は向上したものの論理的思考力や短期記憶を調べた認知テストの成績はほとんど向上しませんでした。
どのような境遇の人も、老後にパートナーと過ごすかどうか(過ごせるかどうか)は分かりませんから「おひとりさま」になる可能性もあるでしょう。「おひとりさま」になったとしてもならなかったとしても、「<強い社会的ネットワーク>を持ち「脳トレ」でない方法で脳をできるだけ使うようにして社会的対立を解決することで社会に貢献する」というのが最も素敵な老後の過ごし方、と言えるかもしれません。
参考までに、私は医師という職業を引退した後は、語学の勉強に本格的に取り組み(英語、タイ語以外に中国語かスペイン語を学ぼうと考えています)、NPO法人GINA(ジーナ)の活動を広げ、社会貢献に時間を費やしたい、と考えています。
************
注1 この論文のタイトルは、「Reasoning about social conflicts improves into old age」で、下記のURLで概要を読むことができます。
http://www.pnas.org/content/107/16/7246.abstract?sid
注2 記事のタイトルは「No gain from brain training」で下記のURLで内容を読むことができます。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
87 医学部新設はなぜ反対されるのか 2010/4/20
最近の与党(民主党)の支持率低下は一向に止まらないようですが、その民主党が大勝した2009年8月31日の選挙で掲げたマニフェストには「医師の数を1.5倍にします」とはっきりと明記されています。
「医師不足」については、今さら詳しく説明するまでもなく多くの人が実感していると思います。大病院だけでなく大半の診療所・クリニックでも、長時間待ったあげくの3分診療は当たり前になっており、これでは患者満足度が高くなるはずがありません。
私自身は、「どのような症状でもお話ください」というスタイルを崩したくないために、少なくとも初診時においてはできるだけ時間をとって患者さんの話を聞くように努めているつもりです。「待ち時間が長い」と患者さんからお叱りを受けながらも、1日の予約の枠を他のクリニックよりも少なくしているのは、やはり1人あたりの診察にある程度の時間をかけたいからです。しかしながら、目の前の画面の受付表に目をやって10人以上の患者さんが待っていることが分かると、1人の患者さんにそう長い時間を取るわけにもいきません。
今の日本で、いつ行っても待ち時間が少なくて診察時間には充分な時間をとってもらえる医療機関など、おそらくほとんど存在しないでしょう。(完全予約制にすればこれが実現可能になりますが、そうすると今度は突然症状が現れすぐに診てもらいたいときに「予約が入らない」という問題が起こります)
一方、医師側からみても「医師不足」は歴然としており、長時間労働はもちろん、体力の限界を超えた当直勤務(そして翌朝からは通常勤務)、家に帰れたとしても夜中の呼び出しがあり、休日はほとんどなし、などが日常化してしまっています。私の知り合いの医師をみてみても、仕事が忙しすぎることが原因で家庭崩壊・・・、というケースは珍しくありません。
このように患者側からだけでなく医師側からみてみても「医師不足」は明らかなのです。民主党がマニフェストに「医師数を1.5倍」を掲げるのも当然だと言えるでしょう。そして、このマニフェストを受けてなのか、最近国内の3つの大学が医学部新設を計画していることを発表しました。報道は各マスコミが2010年2月中旬におこなっています。
当初の私の予想は、この発表をみて多くの医師がこれを歓迎する、というものでした。ところが、実際には反対意見がかなり多く、ある調査によれば医師の7割が医学部新設に反対しているというのです。
マニフェストがいつも世論の最大公約数の希望を表しているとは言いきれないかもしれませんが、おそらく患者もしくは将来患者になるかもしれない人の立場(要するに医師以外の立場)からみたときには、医師数が多く医療機関も多い社会が望ましいでしょう。また、医学部受験を考えている人は、一部の絶対合格の自信がある受験生を除けば、医学部新設のニュースを「朗報」と捉えたに違いありません。
では、なぜ7割もの医師が医学部新設に反対するのでしょうか。
新設に反対する、または医師数を増やすことに反対する立場の意見としてよくあるのが、「医学部の定員を増やすと医師の質が保てなくなる」「医学部の学生を増やせば教育者も増やさなければならないことになり(臨床医が教育に時間をとられるため)かえって医師不足が加速する」「長期的にみれば今医師数を増やせばいずれ医師過剰となる」といったものです。
しかし、よく考えてみると、これらの理由はどれも的をはずしている、もしくは対策を考えることで解決できるようなものです。
1つずつみていきましょう。まずは、「医学部の定員を増やすと医師の質が保てなくなる」という理屈ですが、これはむしろ逆でしょう。医師の数が少ないままであれば、いったん医師になってしまえば何の努力をしなくても医師であり続けることができるわけです。いえ、もっと言えば、医師になってしまえば、ではなく、医学部に入学させしてしまえば・・・、という方が正しいでしょう。
医学部に入学さえすれば・・・、という考えは「医師の質が保てなくなる」どころか、医学部受験が絶対的なものになる危険性を孕んでいます。(というより、すでにこの危険は存在していると言った方がいいでしょう)
次に「医学部の学生を増やせば教育者も増やさなければならない」という考えですが、これは比較的簡単に解決できます。インターネットを用いてe-learningをおこなえばいいのです。基礎医学も臨床医学も全国統一の学習ツールをつくるのです。担当する教員が講義をおこないそれを撮影し、インターネットを通じて全国の医学生が聴講できるようにするのです。こうすれば、教育者が実際に医学生に接して教育をおこなうのは実習の時間だけとなります。
「長期的にみれば今医師数を増やせばいずれ医師過剰となる」という意見については、たしかに医師数が増えすぎるのは問題です。現在のように、医療を他の産業と同じ様に市場主義経済のもとにおいていれば、医師が増えすぎたとき、利益確保のために無駄な検査や投薬が増える可能性が否定できません。ほとんどの医師はそのようなことは考えませんが、「今この患者に検査をしなければクリニックが倒産する・・・」となったときに、「それでも私には医師としての矜持がありますから倒産をとります!」とすべての医師が言えるかどうか・・・、という問題があります。(私個人的には、医療機関を現在のように市場主義経済下に置くことには異論があるのですが、ここではこれ以上の議論には立ち入らないでおきます)
けれども、医師が少なすぎるのもまた問題で、私個人としては「医師はこれ以上増えれば少し多いかもしれないくらい」がちょうどいいのではないかと考えています。ただし、私のこの考えにはある前提があります。それは、「医師免許を持っている者が他の職業につきやすい社会にする」というものです。さらに、現在のように、医学部に入学してしまえばほぼ全員が医師になる、という慣行を変更すべきだと考えています。
よく言われるように、そもそも18歳で将来の職業を決めろという方に無理があり、「医学部に入ってみたけど自分には向いていないことが分かった・・・」ということも実際にはあるわけです。しかし、今の社会では「せっかく医学部に入ったんだから・・・」という周囲のプレッシャーのために、本当はやりたくないのに(あるいは他にやりたいことがあるのに)医師という道を選ばざるを得ない人もいるのです。
「医学部はつぶしがきかない」と言われることがありますが、これは誤りです。そもそも「つぶしのきく学部」とはいったい何学部のことなのでしょうか。医学部を卒業していれば、少なくとも、テストで高得点をとる能力、努力を継続することができる能力、生命科学に対する深い知識、少なくとも読み書きに関しては高い英語力(学生の間から論文やテキストを英語で読まなければならない医学生は、おしなべて言えば他の学部生より語学力があります)、などがあるはずです。
他の学部卒業生と比べても、例えば、製薬会社、化粧品会社、スポーツ製品の会社などの就職には有利になるでしょう。また、マスコミに就職し医療関係の記事を担当するというのもいいでしょう。医薬品・医療機器専門のフリーの翻訳者になるとか、医療専門のジャーナリストというのもおもしろいかもしれません。
結局のところ、<高偏差値→医学部→医師>という道のりが、他の生き方とあまりにも隔たりがあるために、様々な弊害がでているわけです。医学部を卒業し医師以外の職種を選択、医師から他の業種に転職、そして(私が実際におこなったように)他学部卒業や他の職種に従事した後に医学部再受験などがスムースにおこなえるような社会になれば、医学部新設に対する反対意見は大きく減少するでしょう。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第86回(2010年3月) 動機善なりや、私心なかりしか
奈良県大和郡山市の病院(以下Y病院)でとんでもない不正請求の事件があり院長が起訴されたことについて以前コラムを書きました(下記参照)。
このような不正請求事件が実際にあったということが信じがたく、事実ならY病院はとても病院とはとても呼べず”猟奇の館”と命名した方がいいでしょう。
すでに各マスコミに詳しく報じられていますが、簡単に経緯を振り返ってみたいと思います。
Y病院の院長であるY医師は2010年2月6日に奈良県警に逮捕されました。逮捕事由は業務上過失致死となっていますが、実際は「殺人」と言った方が適切でしょう。
Y医師(及び執刀に加わったT医師)は肝臓の手術の経験がなんと一度もない!のにもかかわらず、2009年6月に51歳男性の肝臓の手術をおこなったのです。しかもこの患者さんには初めからがんなどく、Y医師が勝手にがんと決め付けていたというのですから驚きます。
肝臓の手術は(当たり前ですが)簡単ではありません。血流が豊富ですし、重要な血管がいくつもありますから、ベテランの肝臓外科医でも予期せぬ出血を招くことがあります。案の定、Y医師は肝静脈を誤って損傷させ、大量出血を起こし、この患者さんは2時間後に死亡しました。
これはある週刊誌の報道ですが、Y医師は、大量出血を自ら招いた後に「酒を飲みに行く」と言い残して手術室を出て行ったそうです。これが事実だとしたら、Y医師は医師ではなく「猟奇殺人犯」と呼ばねばなりません。
もっとも、各メディアの報道をみてみると、Y医師は日頃から行動が相当おかしかったらしく、病院関係者がY医師から医療の真面目な話を聞いたことはなかったそうです。
口をついて出てくるのは、風俗、女、酒など下世話な話題ばかり。病院の近くに構えた豪奢な自宅の敷地内には、ここ数年で購入したハーレーダビッドソンやBMWといった高級大型バイク、新型のフェアレディZやGT-Rなど高級国産車が常時止められていた。(『週刊新潮』2010年3月4日号)
報道では、近所の人は「以前からY病院は異様だった」と証言している、と伝えられていますが、患者さんからはY病院が「猟奇の館」でY医師が「猟奇犯」だとは分かりづらかったのではないでしょうか。
患者さんは数少ない情報からできるだけいい病院を探そうとします。Y病院は数年前の『週刊朝日』の「いい病院・心臓病編」という記事で紹介されたことがあるそうです。(これはおそらく必要のない患者さんに手術をしたことにより手術件数が多かったからだと思われます) また、Y医師は阪大の第1外科の出身だそうです。阪大第1外科と言えば、あの『白い巨塔』のモデルになった医局です。
『週刊朝日』が絶賛する病院で、院長は阪大第1外科出身・・・、となれば患者さんが騙されるのも無理もありません。
さて、話は変わりますが、私は医学部入学前には在阪の企業で会社員をしていました。その前は関西学院大学で社会学を学んでいました。私の卒論のテーマは「職場におけるリーダーシップ」で、卒業してからもリーダーシップについて書かれた本をよく読んでいます。実際の企業のリーダーたちが書いた本を読むのが好きで、松下幸之助、本田宗一郎、デール・カーネギーの本などは何度も読みました。
そんな私が久しぶりに読みたくなったのは京セラの創業者である稲盛和夫さんの本です。なぜ読みたくなったかというと、稲盛さんは2010年2月1日に経営破綻した日本航空の会長となられたことが報道され、稲盛さんの本に夢中になっていた昔の自分がなつかしくなったからです。
稲盛さんはいつも「世のため人のために」と話されています。日本航空の会長職も「世のためになるのなら・・・」という思いから無給で引き受けられました。当初は週に3回の出勤の予定でしたが、現在はほぼ毎日出社されているそうです。
稲盛さんは1984年にDDI(現在のKDDI)を設立されました。当時通信業界はNTTの独占状態でしたが、通信自由化を転機と考え、その頃はまだ京セラはベンチャー企業と呼ばれる規模でしたがDDIを設立しNTTに挑んだのです。
そのDDIを設立する際、稲盛さんは何度も自問自答したそうです。その心境を稲盛さんの自伝から紹介します。
私は自分の本心を確かめるため、毎晩ベッドに入る前に、「動機善なりや、私心なかりしか」と心の中で問いかけることにした。「世間に自分をよく見せたいというスタンドプレーではないか」「国民の利益のためにという動機に一点の曇りもないか」。六ヶ月の間、たとえ、酒を飲んで帰ろうと、毎日自問自答を繰り返した結果、世のため人のために尽くしたいという純粋な志が微動だにしないことを確かめた私は、この事業に乗り出す決心をした。(『稲盛和夫のガキの自叙伝』日経ビジネス人文庫)
一般企業というのは利益を出すことが大きなミッションです。利益を出さなければ企業が存続できず従業員は路頭に迷うことになります。利益がなければ株主は納得しません。しかし、利益追求のみが目的となってはいけません。
これは一般企業の話です。医療機関の場合、一般企業とは異なるレベルで「世のため人のために・・・」という志がなくてはなりません。もとより、日本医師会が作成している『医の倫理綱領』の第6条には「医師は医業にあたって営利を目的としない」という規定があります。
もちろん医師も人間ですから、自分と家族を守らなくてはなりませんし、医療機関をつくる(開業する)のであれば従業員に対しても責任がでてきます。ですから、すべての患者さんを無料で診察します、というわけにはいきません。
しかしながら、医師の矜持があれば「世のため人のために・・・」という気持ちは自然に出てくるものであり、間違っても、必要のない検査や投薬をおこなうようなことはあり得ません。まして、必要のない手術をする、などということは考えもつかないことです。さらに、患者さんに大量出血させておいて酒を飲みに行き死亡させる、などといったことは医師という職業人の”掟”に背いただけでなく、精神に破綻をきたしていると言うべきでしょう。
動機善なりや、私心なかりしか
Y医師が稲盛さんのこの言葉を聞けば何を感じるのでしょうか・・・。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
85 製薬会社の使命と医師の使命 2010/2/20
2010年1月初旬、欧州議会議員会議(PACE, Parliamentary Assembly of the Council of Europe)が、WHO(世界保健機関)が2009年に宣言したインフルエンザのパンデミック(世界流行)宣言は、「偽りのパンデミック(fake pandemics)」の可能性が強い、と主張し調査をおこないました。
私は、このニュースを読んで大変驚きました。新型インフルエンザは、昨年4月頃からメキシコをかわきりに、米国、カナダ、日本、英国、オーストラリアなどで流行し、当初からメキシコでは高い死亡率が報告され、各国で従来の季節型インフルエンザよりも重症化することが多く死亡率も高いという調査が相次いでいるのです。
最近になって罹患者は減少しつつありますが、それでも終息したわけではなく、依然猛威をふるっています。WHOが迅速に「パンデミック宣言」をおこない、予防の重要性を訴え、ワクチン接種の勧奨をおこなったことは評価に値するのではないでしょうか。
なぜ、欧州議会議員会議(以下PACE)がWHOのパンデミック宣言を”偽り”としているかというと、PACEはワクチン製造企業とWHOの間に癒着のような関係があると考えているようです。
PACEは1月25~29日に開催された冬季会議のメインテーマを「Faked pandemics, a threat to health(偽りのパンデミック、健康への脅威)」と決定し,本部(仏ストラスブール)で緊急討議を行い、さらにWHOとワクチン製造企業の関係者に対する公聴会も実施しています。
WHO、ワクチン製造企業の関係者を招集して公聴会を開くというのですから、PACEはWHOのパンデミック宣言に対して相当嫌悪感を抱いているような印象を受けます。
これはなぜなのでしょうか。考えられる理由のひとつに、議員も世論も日頃から製薬会社に対してネガティブなイメージを抱いている、というものがあるのかもしれません。要するに、製薬会社は儲けすぎている、もっと言えば、「病気にかかるかもしれないという人の弱みにつけこんで利益を得ようとしている」といったイメージがあるのかもしれません。
映画『ミッション・インポシブル2(M:I-2)』では、殺人ウイルス「キメラ」と解毒剤「ベレロフォン」を奪還するのが、トム・クルーズ演じるイーサン・ハントの”ミッション”になっていましたが、この殺人ウイルスを開発したのは巨大製薬会社「バイサイト」という設定になっています。
また、新型インフルエンザが登場したとき、誰かが人為的にウイルスを製造したのではないか、という噂、(例えば、製薬会社がウイルスを作成し、ワクチンと特効薬を同時に売り出そうとしたのではないか、という噂)が一部でありました。
実際には自らの金儲けのために人為的にウイルスを製造するといったことはないでしょうが、病気の不安を煽って儲けようとする製薬会社があるのではないかと考える人はいるようです。
例えば、高血圧の診断基準は、以前は収縮期血圧(上の血圧)が160mmHg以上とされていました。これは1978年のWHO(世界保健機関)が定めた基準です。それが、1999年の新しい基準では、140mmHg以上と診断基準が厳しくなっています。さらに、2009年のJSH(日本高血圧学会)では、140mmHg以下であっても肥満やメタボリックシンドロームなどがあれば治療を検討すべき、ということになっています。
つまり、次第に高血圧という診断がつきやすくなり薬開始へのハードルが下がっているわけで、ここから、製薬会社が病気の人を増やして薬を売りたいからではないか、という噂がでてくるのです。(もちろん、高血圧の診断基準は公正な大規模調査により裏付けられていますから、製薬会社の思惑で基準が変更になったわけではありません)
さて、では製薬会社は儲けようとしていないかと言われれば、「不当に儲けようとはしていない」とは思いますが、製薬会社自体はほとんどが株式会社の形態をとっていますから利益を出さないと存続できないのは事実ですし、利益を出さなければ株主から厳しい追求をされることになります。それに、ある程度の利益を捻出し、それを新薬の開発費に投資しなければ、薬学の進歩は望めないことになります。製薬会社に勤める人も、ある程度の収入がなければ困るでしょう。
つまり、利益を出さなければ組織が存続できず、薬学の発展も望めないという側面があるものの、利益至上主義になってしまうことが許されないのが製薬会社の立場というわけです。
これは一般の製造業者とは似ているようで似ていません。例えば、自動車でも家電製品でもコンピュータでもいいのですが、一般の製造業者は、今の生活よりも便利になるものを開発することが使命です。つまり需要を掘り起こすことで企業の存続意義がでてきます。一方、製薬会社の場合は、今ある病気に対する薬を製造することがミッションなわけで、新たに病気を生み出したり病気に対する不安を煽ったりしてはならないのです。これを別の言葉で言えば、一般の製造会社はゼロからプラスを創造することが、製薬会社はマイナスをゼロに近づけるのがミッションであるということになります。
マイナスをゼロに近づける、という言い方をすると我々医師も同じなのですが、製薬会社のミッションと医師のミッションは、少し異なります。
私は、以前、ある後発品中心の製薬会社に「支援をするから開業しないか」という話を持ちかけられたことがあります。物件はすでに確保してあり家賃や内装費まですべて会社が負担するからクリニックの院長として診療をしてもらえないか、という提案です。
これは、普通の(医療以外の)会社や店舗ならありがたい話だと思います。何しろ開業資金がゼロとなり、その後もコンビニなどのフランチャイズとは異なり、毎月の売上から何パーセントを払わなければならないという制約もないのです。上手くいかなかったときのリスクがほぼゼロで、かつ利益をそのまま受け取ることができるのです。
しかし、私はこの申し入れを断りました。その理由は、以下のようなものです。
製薬会社のミッションは、薬を販売し利益を上げることである。一方、医師のミッションは、いかに薬を処方しないか、である。薬をできるだけ使わずに、また使ったとしても最小限に努めるのが医師の使命なのである。このようにミッションの方向が異なっているのだから、製薬会社と医師のタイアップは上手くいくはずがない。
製薬会社にはライバル会社が多く、利益追求をしなければ会社が存続できません。しかし、医療機関は利益追求を考えてはならず薬の処方は最小限にしなければなりません。このあたりの微妙な違いを日々感じながら、我々医師は薬の処方をおこなっているのです。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第84回(2010年1月) 本能としての正義感
先日、高校のミニ同窓会でのこと・・・。
高校卒業後、警察官になったK君と席が隣り合わせになった私は、興味本位で警察の内部のことを尋ねてみました。というのも、週刊誌やテレビドラマで警察内部の実情が紹介されるとき、警察の不祥事や暴力団との癒着などが浮き彫りにされることがあるからです。私は、正義を貫くことをミッションとしている警察官が、そのミッションとは逆に反社会的な行動をするようなことがあるのかどうか、本当のところを知りたかったのです。同級生のK君なら本当のことを話してくれるに違いありません。
K君によると、「すべてを知っているわけではないが、そんなこと(不祥事など)はありえない。警察官は常に自身の正義感に基づいて任務を遂行している」と言います。「正義感をなくせば人間はおしまいだ」と強く訴えるK君に私は共感を覚えました。
なぜ共感したかというと、私は年を追うごとに「正義」というものを意識するようになってきているからです。私のいう「正義」とは、警察官が日々考えているような「悪を社会から失くす正義」といった大きなものではなく、日常生活の中で、ちょっとした不公平が許せなかったり、ずるいことをする人間を非難したくなったりするような正義です。
飲み会の席で「正義」について熱く語ったのは私にとっては初めてで、K君との会話は大いに盛り上がりました。
そして、あることに気づきました。
K君と私は高校生のとき、一度クラスが一緒になったことがあるのですが、お互いテストになると憂鬱な気分になり、よく愚痴をこぼしていました。テストのときは名簿順に座りますから、K君と私はいつも席が隣で、「なんとかカンニングをする方法がないか」ということを半ば冗談半ば本気でよく話し合っていたのです。
そんなK君と私が、それから20年以上の月日を経て「正義」について熱く語り合っているのです! このことに気づいたK君と私は高校生時代を思い出して笑ってしまいました。
さて、K君が言うように「正義感をなくせば人間はおしまいだ」ということに賛同する人はどれくらいいるでしょうか。
私自身のことを言えば、おそらく20代半ばくらいまでは、「ふん! 何が正義だ。正義なんて言葉を口にする人間は偽善者に決まっている!」と考えていました。ところが、その後次第に正義を当然のことと感じるようになったというか、正義でないこと、例えば不公平や不正に対して強い嫌悪感を抱くようになってきたのです。これは、私が医師という職業を選んだことと無関係ではないでしょうが、それだけではないように思います。
たしかに私は医学部に入学し、知人から医療現場での不満を聞くにつれて、医療現場ではどのような患者さんであれ平等に医療を受けられなければならない、と考えるようになりましたし、タイのエイズの実情を目の当たりにし、エイズという病が原因で、社会から家族から、そして医療機関からも差別を受けている人を救わなければならないと考えました。そして、それらが太融寺町谷口医院やNPO法人GINA(ジーナ)のミッション・ステイトメントの原点になっています。
しかし、私が「正義」にこだわるのは、このような個人的体験だけでなく、もっと本質的なものがあるように感じていました。というのも、正義を貫くことには、何か”感動”のようなものがあるからです。例えば、身近なところに何らかの不公平があり、それを自分自身で指摘し改善するような行動をとったときに”感動”のような感覚がありますが、これは自己満足と言われるかもしれません。けれども、例えば、映画やテレビドラマで、主人公が様々な嫌がらせや脅迫を乗り越えて正義感を貫く姿にはほとんどの人が感動するのではないでしょうか。
つまるところ、「正義」とは本来は誰もが持っている言わば”本能”のようなものではないか、と感じることが私にはあったのです。そして、最近この私の感覚を裏付けるような研究が発表されました。
玉川大学脳科学研究所の春野雅彦研究員が、脳の中に不公平を嫌がるときに盛んに活動する部位があることを突き止めたのです。これは科学誌『Nature Neuroscience』のオンライン版2009年12月20日号で発表されています。(注)
この研究では、まず男女64人に報酬金の分け方について好みを調べています。自分と相手がもらう金額の差が小さくなるのを好む25人と、そうでない14人を選抜しています。そしてこの39人に自分と相手の報酬金の差を36パターン示し、その際の脳の活動をfMRI(
機能的磁気共鳴画像装置)で観察しています。
その結果、自分と相手がもらう金額の差が小さくなるのを好む人は、金額の差が大きいほど扁桃体と呼ばれる情動に関連する脳の部分が活発に活動することが分かりました。また扁桃体の活動の様子に応じて、不公平をどの程度嫌がるかも予測できたそうです。
扁桃体は、脳の大脳辺縁系と呼ばれる部分の一部にあたります。一般的には、「原始的な脳」と言われ、基本的な怒りや恐怖など、生物にとって原始的な情動に関連していると言われています。「原始的な脳」に対して、ヒトに発達している理性などをつかさどる「高次な脳」は大脳皮質に存在します。大脳皮質が高度な思考や理性を司っているというわけです。
一見すると、「正義」「公正」「平等」などは、高次な理性によって処理されている、すなわち大脳皮質に関係していると思われがちです。ところが、この研究では、こういったものは扁桃体に関係している、要するに原始的な情動のひとつである可能性を指摘しているわけです。
何らかの不正を発見したとき、ずるいことをしている輩をみたときに、我々は瞬時に「許せない」という感覚を覚えます。これは自分自身が得をするか損をするかといったものとは別の次元での感覚です。そして、自分自身の損得とは関係なく、平等、公平、正義などが感じられるときに我々は安堵感を覚えるのではないでしょうか。
私は、こういった平等、公平、正義などを絶対正しいと思う感覚は、人間の本能であると感じています。こういった感覚が本能であり、上に述べた研究が示すように原始的な脳が司っているとすれば、人間以外の動物にも認められることになりますが、最近の動物行動学の研究でも動物の様々な「利他的な行動」が報告されています。
よく「良心の呵責に耐えられなくて・・・」と言って罪を告白したり懺悔を考えたりする人がいますが、これも本能に逆らえないからではないでしょうか。
よく「本能」というと、食欲、性欲、自己顕示欲などが取り上げられますが、正義、公平、平等などを求める欲求も本能のひとつと捉えるべきではないか、と私は考えています。そして、こういった欲求に逆らうような、要するに正義、公平、平等などに反するような行動をとれば、本能に逆らうこととなりいずれ精神の破綻をきたすのではないかとも感じています。
そう考えると、私のように年をとってから正義を強く意識するようになった人間というのは、これまでの人生でさんざん正義に反する行動をとっていたために、それを埋め合わせたいという欲求が強いということなのかもしれません。
注:上記論文のタイトルは「Activity in the amygdala elicited by unfair divisions predicts social value orientation」です。
(http://www.nature.com/neuro/journal/v13/n2/full/nn.2468.html)
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
83 投薬ミスはいかにして防ぐべきか 2009/12/21
医療事故のなかで最も多いミスのひとつが「投薬ミス」です。似たような名前の薬を誤って処方・投薬することにより、患者さんに害のある薬を与えることとなり、結果として患者さんに不利益となることがあり、最悪の場合は死につながることもあります。
喘息が悪化したときなどによく使うステロイドの点滴に「サクシゾン」というものがあります。これと似た名前の薬剤に「サクシン」というものがあり、こちらは強力な筋弛緩剤で、全身の筋肉に作用するため呼吸筋も動かなくなり呼吸停止となります。
2000年11月、北陸地方のある病院で事故は起きました。40代の男性患者にサクシゾンを投与すべきところを誤ってサクシンが投与されその患者は死亡しました。これを受けたサクシンの製造会社は、製品ラベルを分かりやすいものに変更するなどで再発防止に努めましたが、悲劇は再び起こりました。
不幸な事故から8年後の2008年11月、今度は四国のある病院で、70代の男性患者に解熱目的で医師がサクシゾンを指示しようとしたところ、実際に投薬されたのはサクシンで、そのおよそ2時間後、この患者は呼吸停止による死亡が確認されました。
この事故は夜間に起こっています。宿直していた医師がなかなか解熱しない患者さんに対して、コンピュータを用いて投薬の指示をおこないました。端末に「さくし」と打ち込んで自動的に表示された「サクシン」を選択したのです。
この事故の後、製造会社は、「薬の名前を変更する以外に再発を防ぐ方法はない」、と考え、「スキサメトニウム」という名称に変更しました。サクシンは15年ほど前から使われている筋弛緩剤で、「サクシン」という名称に慣れ親しんでいる医療者の間で混乱を招くのではないかという声も一部にはあったようですが、二度の死亡事故を踏まえて名称変更に踏み切ったのです。
薬の名前なんてきちんと確認していれば間違うはずがないんじゃないの?、と思われる方も多いと思いますが、時間が勝負の臨床の現場では似たような名前には神経がすり減らされる思いがする、というのが我々医療者のホンネであります。
似たような名前の薬剤は他にも多数あり、例えば、「ノイロビタン」と「ノイロトロピン」、「アレロック」と「アロテック」、「ノルバスク」と「ノルバデックスD」などが有名です。
さて、今回は私自身がしてしまった投薬ミスについてお話したいと思います。
週末の混雑している夕方の外来に受診されたある患者さんに対し、ある薬を処方したのですが、その薬は少し胃に負担がかかることがあるために、患者さんが胃がそれほど強くないと話されたこともあり、私は胃薬を同時に処方しました。しかしこの胃薬の投薬が結果的に投薬ミスとなってしまったのです。
その胃薬は、ムコスタという胃粘膜保護剤の後発品(ジェネリック薬品)で、名前を「レバミピド」と言います。私は、電子カルテに「れ」と打ち込んで表示されたレバミピドを選択したつもりでした。
ところが、その日の診察終了後、カルテをチェックしていると、実際に処方したのは「レバミピド」ではなく「レボフロキサシン」という抗生物質であることが判りました。
それに気づいた私はその場で患者さんに電話をしました。幸い、その患者さんはまだ薬を飲んでおらずなんとか事なきを得ました。謝罪をおこない、状況を説明し誤って処方した「レボフロキサシン」は内服しないように伝えました。
今回は、その日のカルテチェックで気づきましたが、同じミスを二度と起こさないという自信はありません。以前から「レバミピド」と「レボフロキサシン」は名前が似ているから注意が必要ですね、という声は院内から上がっていましたが、私は「レ」が同じだけで間違えるなんてことはないだろう、と考えていたのです。
そう考えていたのにもかかわらずミスをしてしまったわけですから、同じことを再度してしまわない保障はありません。私は翌日の朝のミーティングでこの問題を取り上げ、取り扱う薬の変更を提案しました。
「レボフロキサシン」は「クラビット」という抗生物質の後発品です。「クラビット」は非常に優れた抗生物質ですが、値段が高いという短所があります。1錠あたり173.7円もするのです。例えば、この薬を1回1錠1日3回で5日間処方すると、3割負担でも800円近くかかることになります。これを後発品の「レボフロキサシン」にすると、患者負担額が500円ちょっとにまで下がります(それでもまだ高いように思えますが・・・)。
抗生物質のクラビットに比べると、胃粘膜保護剤「レバミピド」の先発品であるムコスタは1錠あたり22.1円とそれほど高くありません。後発品のレバミピドが15.5円で、ムコスタとの1錠あたりの差は(3割負担の)患者負担で1.98円です。院内で検討した結果、この程度の差なら、値段の高い先発品を使っても似たような名前から生じる投薬ミスのリスクを考えれば許容されるのではないかという結論に達しました。(胃薬は抗生物質に比べると長期の処方になることが多いという違いはありますが・・・)
それにしても、今回の投薬ミスは、自分の能力の限界というか、注意力のなさというか、ともかく自分自身の無能さを自覚することになり大いに反省しました。
「人間だから誰でもミスをする」とか「ミスは完全に防げない」とか言われることがあり、私は「そうかもしれないが医療者はあってはならない」と考えていました。しかし、今回のこの自分のミスで少し考えが変わりました。
「医療者は絶対にミスをしてはいけない」ではなく、「ミスを最小限にするために最大限の努力をしなければならない」と考えるべきではないかと今は思います。
今回の私の投薬ミスによって、直ちに取り扱う薬を変更するという決定をしました。しかし、今後太融寺町谷口医院で投薬ミスが二度と起こらないという保障はありません。現在もおこなっている薬のダブルチェック(実際に薬を患者さんに渡す前に最低2人のスタッフがチェックすること)を丁寧におこなうこと、どれだけ忙しくても患者さんが飲み方をきちんと理解してくれているかどうかを薬を渡すスタッフが確認すること、そして、今回のように似たような名前の薬が他にないかをいつも考えること、などを徹底したいと考えています。
そして、私にしかできないカルテのチェックにも念を入れたいと思います。たとえ長時間に及ぼうとも、その日の診察のカルテは何度も読み直すという習慣を大切にしたいと考えています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
82 肥満患者が医師に丁寧に扱われていないというのは本当か 2009/11/20
医師はすべての患者に平等に接する、というのは我々医師にとっては、言わば当たり前のことであるはずで、わざわざ言葉にする必要もないようなことです。しかしながら、この当たり前のことも守られなくなる可能性がないわけではなく、そのため、様々な医師の倫理要綱には、例えば、「貧富の差に関わりなく医師は患者を平等に診察しなければならない」といった内容のものが記載されています。
では、実際はどうなのでしょうか。実は、私が臨床医を目指そうと思った理由のひとつが、この「患者間の不平等をなくしたい」というものでした。そもそも私は医学部入学当初は臨床医をする気持ちはありませんでした。元々社会学部の大学院を目指していた私は、いったん医学部で医学を学んだ後に医学的なアプローチで社会学を研究したいという希望を持っていたのです。
ところが、医学部に入学してみると、患者さん、というか知人や、あるいは知人の知人が、まだ医師になっていない医学部生の私に対して、医療機関に対する不満を話すことが多かったのです。
「医者はちゃんと話を聞いてくれない・・・」「長時間待たされて診察時間は1分で終わった・・・」、こういう不満が多いのですが、この手のクレームは想像できることです。患者さんが結果として不満をもつのはもちろん良くないことですが、少ない医師が多くの患者さんを診察しなければならない日本の医療の現状を考えるとある程度は止むを得ないという側面もあります。
しかしながら、次のような不満は学生の私でさえも多いに問題があると感じました。
「外国人だからという理由できちんと診てもらえなかった」(30代の南米出身の男性。日本語はほぼ完璧なのにです)
「信用していたから自分の過去も話した。すると医者の態度が突然かわり、診察に行くとイヤな顔をされるようになった」(過去に違法薬物の経験があるという20代男性)
「言う必要があると思ったから本当は隠しておきたかった同性愛者であることを告げた。すると看護婦や他のスタッフも含めてジロジロ見られるようになって明らかに他の患者とは対応が違うようになった」(30代の男性同性愛者)
「言いたくなかったけど過去に自分がウリ(売春)をしていたことを医者に話した。過去のことなのに医者と看護婦に説教をされた」(20代女性)
外国人であろうが、違法薬物を使用していようが、売買春をしていようが、患者は患者です。このような理由で、医療機関で不快な思いをし、その結果病院を受診しなくなれば、病気が悪化することだってあるはずです。
私は、普段は他人に言えないようなことでも包み隠さず話すことができる、そしてそのことを自身の個人的価値感ではなく病気を治すという観点から話を聞くのが患者と医師の関係だと考えています。
医療の現場で、国籍や職業、犯罪歴などで差別されることがあってはならないのではないか・・・。私はそのように強く感じ、ならば自分自身がこういった患者さんも平等に診る医者になろうと考えました。研究者志向から臨床医を目指そうと思ったのは他にも理由がありますが、こういった人たちとの会話が私を臨床医に駆り立てたのは事実です。
また、タイのエイズ施設でボランティアをしていた頃、HIV陽性という理由で病院からさえも差別的な扱いを受けた患者さんを何人も診ることになり、これがNPO法人GINA(ジーナ)を設立するきっかけとなりました。
太融寺町谷口医院のミッション・ステイトメントに「患者さんの年齢、性別(sex, gender)、国籍、宗教、職業などに関わらず、全ての患者さんに平等に接する」とあるのは、私の個人的なこういった経験があるからです。
さて、今回お話したいのは、「肥満患者は医師に丁寧に扱われていない」という大変ショッキングな研究結果が発表されたということです。
この研究は米国ジョンズ・ホプキンス大学によっておこなわれ、医学誌『Journal of General Internal Medicine』2009年11月号に掲載されています(注1)。研究者らは医師40人に、肥満患者に対する態度について質問表を用いて質問した結果、238人の患者についてBMI(注2)が10増加するごとに、医師の患者に対する敬意が14%減少することが判明したといいます。
研究者らは「このような医師の態度が、医師と患者の関係にどのような影響をもたらすかは不明」としていますが、「患者が再診を受けることを拒絶したり、否定的態度で扱われたと感じたりすることが示されている」と述べています。さらに、「(丁寧に扱わないことによる)情報伝達の減少は患者の健康転帰に有害性をもたらす可能性がある」と指摘しています。
BMIが10増加するごとに、医師の患者に対する敬意が14%減少する、というのはにわかには信じがたいことです。
米国の現状はよく分かりませんが、日本の医療の現場でもこのようなことがありうるのでしょうか。肥満があるからといって、コミュニケーションが取りにくいということはありませんし、医師に対して反抗的というわけでもありません。私には、この研究結果が事実を反映しているとは到底思えないのですが、実際はどうなのでしょうか。
この研究では、医師の同様な態度は、アルコール中毒、麻薬使用者、HIV感染者などに対しても当てはまることが指摘されています。肥満というだけで丁寧に扱われないのなら、社会的に問題のあるアルコール中毒者や麻薬使用者などがもっとぞんざいにされていることは想像に難くありません。また、HIV陽性者が丁寧に扱われないのは、残念ながら現在の日本でもあり得ることです。
私自身はクリニックのミッション・ステイトメントにも掲げているように「全ての患者さんに平等に接する」ということを医師としてのミッションと考えています。しかしながら、今回この論文を読んで感じたことは、「たとえ私が平等に接しているつもりでいても、患者さんの側からみたときには丁寧に扱われていないと感じているかもしれない」ということです。
特に、患者数が多くひとりあたりに時間をあまりかけることができないときに、説明が早口になったりあまり大事でない部分は省略したりすることがあります。すると、結果的に患者さんは「ぞんざいに扱われた」と感じ、その結果再診に来なくなるかもしれません。すると場合によってはその病気がさらに悪化する可能性もあります。
「全ての患者さんに平等に・・・」というミッションは、常に心の片隅に置いておかねばならない・・・。この論文を読んでそれを再認識するようになりました。
注1:論文のタイトルは「Physician Respect for Patients with Obesity」です。
要約はhttp://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11606-009-1104-8で読むことができます。
注2:BMIとはボディ・マス・インデックスの略で、体重(キログラム)を身長(メートル)の2乗で割った数字です。体重88キログラム、身長2メートルの人なら、88÷2の2乗=88÷4=22となります。一般的には22~25くらいが標準とされています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
第81回(2009年10月) 医学部受験はなぜ再受験生に有利か
拙書『偏差値40からの医学部再受験』などでも述べましたが、医学部受験は現役生よりも再受験生の方が有利なのではないか、と私は思っています。
これには反論も多いと思います。例えば、いくつかの大学医学部では現役生の割合がやたらと高く、これには現役生は点数に「ゲタをはかせてもらっている」、あるいは再受験生には「ハンディが課せられている」などの噂もあります。また、2005年には群馬大学医学部で合格者の平均点(最低点ではない!)を上回る得点をとった55歳の女性が、実際に年齢が理由で不合格とされました。
このような噂や事実があるのにもかかわらず、私が医学部受験は再受験生に有利と考える最大の理由は、「勉強を楽しむことができる」というものです。
もちろん、勉強、特にテストが伴う勉強というのは楽しいだけではありません。かなりの苦痛も伴いますし、焦燥感、不安感、抑うつ感、ときには絶望感にさえ襲われることがあります。
しかし、会社を辞め収入源を断たれても再受験生として受験勉強をしたいと考えるのは、学問に対する強い思い入れがあるからに他なりません。拙書でも述べたように、受験勉強に伴う苦痛など社会人として体験する様々な苦労に比べれば微々たるものです。
少し考えてみればすぐに分かることですが、入試というのは、あらかじめ与えられた履修範囲(高校で習うこと)から問題が出題され、すべての受験生が同じ時間を与えられて採点は客観的におこなわれ点数が高ければ合格となるのです。
一方、社会で体験する多くの苦労は実に理不尽なものです。例えば、客観的にはライバル社の製品の方が優れていると感じていても自社製品を売らなければならないとか、どう考えても期日までにできそうにない仕事をプライベートを犠牲にしてまで仕上げたとたん会社の方針が変更され努力が無駄になった、などといったことは日常茶飯事です。
そんな理不尽で筋の通らない社会人の苦労に比べれば、勉強のスランプなど実に些細なことです。
このことに気づいているだけで再受験生の方が受験には有利なわけですが、それ以上に、「再受験生は勉強の楽しさをすでに知っている」ということを強調したいと思います。
私が医学部受験を本格的に開始したのは1995年の1月で26歳のときでした。この頃の勉強は苦労もありましたが、振り返ってみれば大変楽しく勉強に専念できたと思います。苦手の数学では解けない問題もありましたが、それを考えながら眠ると夢のなかで解けていた、といった経験を何度かしましたし、生まれて初めて取り組んだ古文は最初はさっぱり分かりませんでしたが、そのうち好きになり、半年後には源氏物語や徒然草の原書を読むようになりました。友達や家族とも連絡をほとんどとらなくなり、私は文字通り「寝食を惜しんで」勉強に没頭していたのです。
ところで、先日皮膚科関連のある学会で、ある有名な医師が講演しており、そのなかでハッとする内容がありました。
26から33歳の頃がもっとも研究に専念できる・・・
その有名な医師は講演のなかでそのような意見を述べたのです。そして、この26から33歳が研究にふさわしいという考えは、その医師だけでなく「多くの医師や研究者が感じていることである」ということを主張していました。
私が、なぜハッとしたかというと、これが自分にもあてはまったからです。私は26歳のときに本格的に医学部受験の勉強を開始し、1年後には医学部に入学し、その後の6年間は多少のスランプはあったものの、総じて言えば勉強に専念することができたのです。
講演していた有名な医師がおこなった立派な研究と比べれば、私がしたことは単なる勉強ですから比較するのは大変失礼なのですが、私は「そうだったのか・・・。自分が勉強に専念できたのは”勉強適齢期”だったからなのか・・・」というふうに感じ、この26から33歳という説に納得させられました。
さて、この「26から33歳説」に共感した私は、さっそくこのコラムで取り上げようと考え、頭の中で整理することにしました。
ところが、です。頭の中でこの説を反芻すればするほど、26から33歳という年齢を重視するのはちょっと違うかもしれない・・・、と思えてきたのです。
私が勉強に没頭したいと考えるようになったのは、社会人を経験してからです。以前に通っていた大学生活や社会人の生活を通して、次第に勉強の魅力に惹かれるようになっていったのです。
そして、もしかするとこの著明な医師も同じような転機をたどったのではないか・・・。そのような考えが頭をよぎりました。この医師は、おそらく中学高校と一生懸命に勉強をし、医学部入学後も過酷な勉強を強いられ医師国家試験に合格し、2年間の研修医を経て、大学院に入学し研究に専念するようになったそうです。ということは、大学と病院で様々な経験を通して勉強や研究の魅力を感じるようになったのではないでしょうか。
私はこのように考えています。既存の教育システムでは、小中高及び医学部などの大学では勉強は能動的にではなく、テストを中心に与えられたカリキュラムをマスターするように強いられます。しかし、本来勉強の面白さは、与えられたことを覚えるのではなく、自ら問題を発見することにあります。私の場合も、医学部受験を決意したのは、人間の身体や精神の神秘性に興味を持ったからです。そして、学問や勉強そのものに真剣に取り組みたいと思うのは、試験に合格しなければならないから、ではなく、もっと純粋な目的ができたときではないかと思うのです。そして、もちろん個人差はありますが、その純粋な目的意識を自覚できるようになるのは、様々な人生経験を経てからではないだろうか、と感じているのです。
であるならば、何も勉強や研究に真剣に取り組みたくなるのは26から33歳に限ったことではありません。いくつになっても勉強を開始することはできるのです。少し例をあげると、伊能忠敬が測量に興味を持ったのは50歳を超えてからですし、少しジャンルが異なるかもしれませんが画家の丸木スマさんが初めて美術に取り組んだのは74歳のときです。
結局のところ、学問の面白さに気づいた人間が研究や勉強に有利になるのです。勉強が好きで好きでたまらない、寝食を惜しんで勉強するのが楽しくて当然・・・、そのように感じる者が成果を上げることができるのです。
医学部受験も例外ではありません。いくつになっても、勉強の面白さに気づきさえすれば医学部合格も時間の問題ではないか・・・。私はそのように考えています。
投稿者 | 記事URL
2013年6月21日 金曜日
80 それって愛ではないけれど 2009/9/20
今月のある日曜日の夜、たまたま時間ができた私は、映画『ディア・ドクター』を近くの映画館に見に行きました。
『ディア・ドクター』は西川美和監督の作品で、笑福亭鶴瓶が演じるニセ医者の動揺する心境を描いたものです。(ここで「ニセ医者」と言ってしまうと、いわゆる”ネタバレ”になってしまうかもしれませんが、他の多くのサイトですでにニセ医者であることが書かれていることと、公開してすでに3ヶ月近くがたっているということを考慮して許されるのではないかと考えました)
作品の良し悪しは別にして(いくつかの映画評論サイトを見てみましたが、のきなみ高得点がつけられています)、私がこの映画で最も印象に残った場面を紹介したいと思います。
僻地で働いていた主人公のニセ医者は、ある理由から突然失踪します。警察の調べでニセ医者であることが分かり、刑事が関係者から証言を集めるのですが、香川照之が演じる薬会社の営業マンに対して、刑事が、「なぜ(失踪したニセ医者は)医者をやろうと思ったのか」と、この営業マンに尋ねます。この営業マンは日頃からニセ医者の診療所に出入りしていて仲良くやっていました。
黙っている営業マンに対して、刑事は「(ニセ医者が僻地で医療をやろうと思ったのは)”愛”なのか」とイヤミっぽく質問します。つまり、金儲け以外に免許がないのに医師をしていた理由は、病人に対する愛情なのか、と皮肉をこめて聞いているのです。
ここで、この営業マンは<ある行動>に出ます。(<ある行動>は映画を見ていない人のために伏せておきます) この営業マンが言いたかったのは、無医村の僻地で医者をやろうと免許のないニセ医者が志したのは”愛”と呼べるようなものではなくて、もっと別のものだ、ということです。
このシーンを見たときに、私は、「そうそう!」と心の中で叫びました。
私も医師ですから「どうして医師になろうと思ったのですか」と聞かれることがしばしばあります。特に私は、文科系の大学を卒業し、いったん商社に就職し、その後医学部受検を試み、医学部に合格したのは27歳のときですから、どうしても経歴を言うとこの質問を受けることが多いのです。
実は私は、医学部入学当時は、まだ医師になることを考えていませんでした。医学部入学前は母校の関西学院大学社会学部の大学院に進学することを考えていて、医学部に進路変更したのは、医学の観点から社会学で取り上げるようなテーマを考えてみたいという思いがあったからです。要するに、私の医学部受験の動機は、「医師ではなく医学者を目指したいから」というものでした。
それが、医学部在籍中にいろいろな出来事があり(すべては書けませんが、病気に関することで医療機関を受診してイヤな思いをした、という話を何人もの人から訴えられた経験が大きいと言えます)、それで、こういう医師を目指したい、という”想い”が芽生えたのです。
その”想い”は”愛”か、と問われれば、そんな崇高なものではありません。そんな立派なものではなく、「このような医療を実践する医者がいないのだとすれば、そしてそういう問題に自分自身が気づいたのだとすれば、それは自分自身がやるしかないではないか・・・」、そういう類の”想い”なのです。
登山家であるジョージ・マロリーは、マスコミからのインタビューで「なぜエベレストに登るのか」という質問に、「そこに山があるから」(原文では”Because it is there.”)と答えたというエピソードがありますが、医師が医師を目指す理由もこれに近いものがあるのかもしれません。
医師を目指すこととエベレストに登ることを一緒にしてしまうのは、登山家の方に失礼かもしれませんが、もっと身近なところでも、この「そこに山があるから」と同じ動機で行動するケースはいくらでもあります。私は以前このコラムで「気づいたモン負けのルール」というものを紹介しましたが(下記コラム参照)、おそらく多くの人は、無意識的にこのルールに従って行動しているのではないかと私は考えています。人間は損得勘定のみで行動するわけではないのです。
話を『ディア・ドクター』に戻したいと思います。
主人公のニセ医者は、地域の人に慕われているというよりもむしろ神や仏のような扱いを受けています。困っている人から連絡が入ると、スクーターに乗りどこにでもかけつけます。また、毎晩医学書を見ながらひとりで遅くまで勉強をしています。このような姿を目の当たりにした研修医は、「一通りの研修を終えた後、再びこの村にやってきて(このニセ医者と)一緒に働きたい」、と言いだします。
しかし、その地域で、たったひとりで医療をおこなうには、”愛”ではない医師を志す”想い”があったとしても、それだけでは務まりません。ときには交通事故の重症の被害者や妊婦や乳幼児も診なければならないわけです。ありとあらゆる患者さんに対して、最終的には隣町の高次医療機関に搬送するとしても、初期診察というのはひとりでおこなわなければなりません。
映画の中では、破水がおこった妊婦を救急車の中で診察しながら、医学書をめくっているシーンがあったり、緊張性気胸といって早急に胸に針を刺さなければ命を失いかねない状態の患者を診たりするシーンがあります。緊張性気胸の場面では、ベテランの看護師の助言に従いながら処置をおこない、なんとか事なきを得るわけですが、これは見ている方もヒヤヒヤします。おそらく、重症患者を目の前にして何もできないニセ医者をみていた看護師は、このニセ医者がニセモノであることに気づいていたのではないかと思われます。
映画では、”愛”ではない別の”想い”でニセ医者が活躍している姿を描きながら、同時に、そんな”想い”だけでは医療はできない、という現実も訴えられているのです。
私は映画館を出るとき、この映画はもしかすると現役の医師に対するメッセージがこめられているのではないかと感じました。
つまり、「あなたたち(本物の)医師とこの映画のニセ医師の違いは、医師免許を持っているかどうか以外に何があるのでしょう。たしかに(本物の)医師であるあなたには、このニセ医師が持っていない知識や技術をいくつも持っているでしょう。しかし、そんな(本物の)あなたは、すべての病人や怪我人に対して何の迷いもなく最も適切な治療ができるのですか。それができないから、あなたは毎日のように勉強を続けているのではないですか。それではそんな勉強熱心なあなたと、このニセ医師の本質的な違いは何なのですか・・・」、このような問いかけをされているように感じたのです。
もしも、このニセ医師が金儲けや興味本位から僻地で医療をしていたなら、このようには感じなかったに違いありません。
”愛”ではない医師を志す”想い”が見事に描かれているが故に、それが我々医師に対する辛辣なメッセージとなっているように私は感じたのです。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 2026年2月28日 樹木は心血管疾患を防ぎ、草や花はリスクを上げる
- 第270回(2026年2月) 嘘だらけの食事ガイドライン
- 2026年2月15日 レッドライトセラピーで慢性外傷性脳症が防げる!?
- 2026年2月 「最期の晩餐」への違和感と本当の幸せ
- 2026年1月31日 頭部の外傷が自殺のリスクとなる
- 2026年1月25日 SNSをまったくやらない10代は不幸
- 第269回(2026年1月) GLP-1ダイエット、中止すれば元の木阿弥
- 2026年1月 「ドイツ型安楽死」がこれから広がる可能性
- 2025年12月28日 やはりベンゾジアゼピンは認知症のリスクを上げる
- 第268回(2025年12月) 「イライラ」のメカニズムと特効薬
月別アーカイブ
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年4月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年10月 (1)
- 2014年9月 (1)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (1)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (1)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (1)
- 2013年6月 (125)